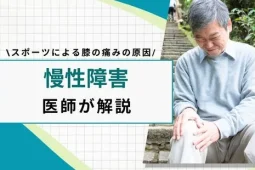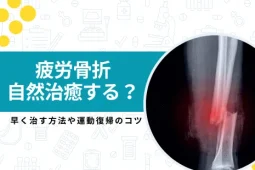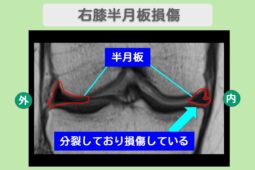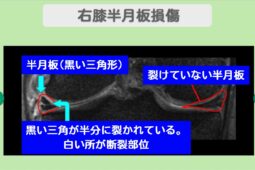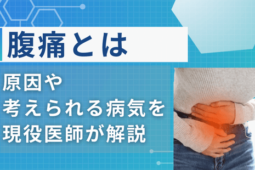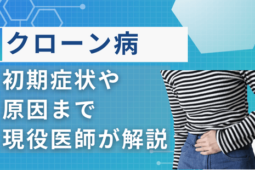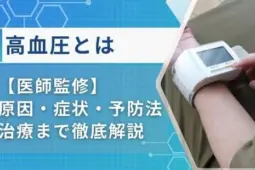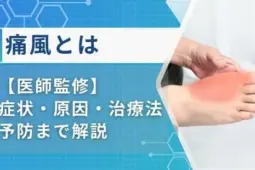- 内科疾患
- 内科疾患、その他
- スポーツ外傷
オーバートレーニング症候群とは|チェックリストや症状・治し方まで医師が解説
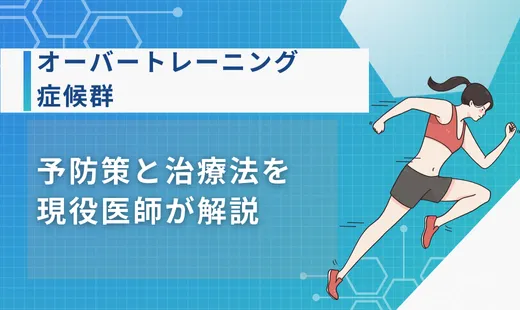
- 思うように力が出ない
- 休んでも疲れが取れない
トレーニング量を増やしたものの、思ったような結果につながらず不安に感じる方もいるでしょう。
オーバートレーニング症候群とは、過剰なトレーニングによって心身に不調が生じ、パフォーマンスが低下してしまう状態を指します。
症状は軽度の疲労感から精神的な不調まで多岐にわたり、対処が遅れると回復に長期間を要するため注意が必要です。
今回は、オーバートレーニング症候群の重症度別の症状や原因、治し方について詳しく解説します。症状のチェックリストも紹介するので、オーバートレーニング症候群が疑われる方は、ぜひ参考にしてください。
当院「リペアセルクリニック」の公式LINEでは、再生医療の情報提供と簡易オンライン診断を実施しております。
オーバートレーニング症候群について気になる症状がある方は、ぜひ一度公式LINEにご登録ください。
目次
オーバートレーニング症候群の症状【重症度別】
オーバートレーニング症候群とは、過剰なトレーニングによる疲労が十分に回復しないまま蓄積し、慢性的なパフォーマンス低下や体調不良を引き起こす状態です。
単なる「疲れ」や一時的な「スランプ」とは異なり、自律神経のバランスまで乱れてしまうのが特徴です。
オーバートレーニング症候群の症状は、進行度に応じて異なります。ここでは、症状を3段階に分けて詳しく解説します。
軽症|パフォーマンスの低下
軽症の場合、オーバートレーニング症候群によって運動時のパフォーマンスは下がりますが、明らかな体調不良は感じません。運動後の回復に時間がかかり、翌日まで疲れが残るケースもみられます。
症状の具体例は以下のとおりです。
- 以前は問題がなかったランニング距離で息が上がる
- 記録が伸びない
- 運動時の集中力が続かない
この時期は「練習不足かもしれない」と誤解しがちですが、実際には疲労の蓄積が原因である可能性が高いです。全力で取り組もうとしても身体がついてこず、以前よりすぐに息が上がる場面も増えてしまいます。
軽症の段階で十分な休養を取れば比較的早く回復できるため、無理に続けず身体の変化に気づくことが大切です。「最近、調子が戻らない」と感じた時点で、トレーニング量を見直しましょう。
中等症|疲労症状
中等症に進行すると、体が慢性的に疲れた状態となり、運動中だけでなく日常生活にも明らかな支障が出始めます。
症状の具体例は以下を参考にしてください。
- 十分な睡眠をとっても疲れが抜けない
- 朝起きた瞬間から身体が鉛のように重く感じる
- 軽いジョギングでも息切れする
- 立ちくらみや動悸が起こる回数が増える
中等症では、運動だけでなく生活全体の質が低下しやすくなります。自律神経のバランスが乱れ、回復力そのものが低下しているため、トレーニングを続けると悪化しやすい点が特徴です。
「体調がいつもと違う」と感じる程度ではなく、「治りにくい疲れ」に変化している場合は早急な休養が必要です。中等症はそのまま放置すると重症化する可能性が高いため、症状が現れている方は、迷わず休養を確保しましょう。
重症|精神・心理症状
オーバートレーニング症候群が重症化すると、身体だけでなく心にも負担が積み重なり、精神的な不調が強く現れます。
具体的な症状は、以下のとおりです。
- 気分の落ち込み
- 不眠
- 食欲不振
- 集中力の低下
- 運動へのモチベーション低下
日常生活にも影響が及ぶため、仕事や学業などに対する意欲や集中力が低下し、人間関係に支障をきたすケースも珍しくありません。
オーバートレーニング症候群が重症化した場合、無理に運動を続けると回復に長い時間がかかるため注意が必要です。重症の症状を放置せず、医師や専門家による適切なアプローチによって回復に努めるのが大切です。
オーバートレーニング症候群の原因
オーバートレーニング症候群の原因は、単に「運動量が多い」だけではありません。
原因は単一ではなく、トレーニング内容の急激な変化や生活習慣、精神状態などが複雑に絡み合い発症します。ここでは、発症の引き金となる主な4つの原因を解説するので、参考にしてください。
トレーニングによる負荷の増加
オーバートレーニング症候群の主な原因は、身体の適応能力を超えたトレーニングによる負荷の増加です。
「大会が近いから」と練習量を急激に増やしたり、十分な準備期間を経ずに高強度のメニューを取り入れたりすることが引き金となります。
トレーニングの強度や量、頻度が同時に高まる状況はとくに危険です。身体は徐々に負荷へ適応するため、急激な変化には対応しきれません。
結果として、筋肉や関節、神経系へのダメージが修復不能なレベルまで疲労が蓄積し、パフォーマンス低下を招いてしまいます。
休養・睡眠不足
運動と同じくらい重要である「回復」がおろそかになるのも、オーバートレーニング症候群の原因です。
休養日を設けずに連日トレーニングを行ったり、睡眠時間が不足したりすると、身体は修復の機会を失います。とくに、睡眠中は傷ついた組織を修復する成長ホルモンが分泌される貴重な時間です。
睡眠不足は肉体的な疲労回復を遅らせるだけでなく、自律神経の乱れにも直結します。
「休養もトレーニングの一部」である意識が欠如し、焦りから休息を犠牲にする行為は、オーバートレーニング症候群を招きます。
栄養不足
消費エネルギーに対して摂取エネルギーが不足している状態は、発症リスクを高める原因の1つです。運動で大量のエネルギーを消費しているにもかかわらず、食事量が足りていなければ、身体の回復は追いつきません。
とくに、筋肉の修復に必要なタンパク質や、エネルギー源である糖質が不足すると不調を感じやすくなります。タンパク質や糖質が不足すると、身体は自らの筋肉を分解してエネルギーを産生します。
また、極端なダイエットや偏った食事制限も、回復に必要なビタミンやミネラルの欠乏を招き、疲労を蓄積させます。
精神的ストレス
オーバートレーニング症候群の原因として見落とされがちなのが、精神的なストレスです。脳が感じるストレスは、自律神経系や内分泌系を通じて身体機能に悪影響を及ぼします。
「絶対に記録を出さなければならない」というプレッシャーや、職場・人間関係でのトラブルなどが重なると、身体的な負荷がそれほど高くなくても発症するケースがあります。
真面目で責任感が強い性格の方ほど、精神的な不調を我慢して運動で発散しようとしますが、かえって心身の許容量を超え、症状を悪化させる場合も珍しくありません。
オーバートレーニング症候群の治し方
オーバートレーニング症候群を治すには、体と心の回復を優先する必要があります。具体的には、無理な運動を控えて十分な休養を確保するのが大切です。
ここでは、オーバートレーニング症候群の回復に欠かせない3つの方法について具体的に解説するので、参考にしてください。
当院では、公式LINEにて簡易カウンセリングを実施しておりますので、お気軽にご相談ください。
\無料オンライン診断実施中!/
休養の確保
休養は、オーバートレーニング症候群の改善において最も重要な要素です。身体は運動後に回復しながら強くなるため、休みを十分に取らなければ疲労が蓄積し、症状が長引きます。
軽い不調を感じた段階で強度を下げるか、一時的にトレーニングを休む判断が必要です。実際に、数カ月間競技活動から離れて休養を確保するだけで、回復が得られる場合もあります。(文献1)
ただし、症状によっては、まったく身体を動かさないと逆効果になるケースも考えられるため「どの程度の休養が必要か」「軽度のトレーニングであれば続けても問題がないか」など、医師やトレーナーと相談しながら治療しましょう。
また、睡眠の質を高める工夫も欠かせません。就寝前のスマートフォン操作を控えたり、ぬるめのお湯に浸かったりして、副交感神経を優位にする環境を整えてください。身体が修復モードに入る夜間に、深く質の高い眠りを確保するのが重要です。
ストレス管理
オーバートレーニング症候群を治すには、身体的な疲労だけでなく、精神的なストレスを取り除くのも重要です。背景に心理的要因や環境適応などの問題があると、休養だけでは回復しにくいといわれています。(文献1)
真面目な性格の方ほど「早く治さなきゃ」「仲間に置いていかれる」と自分を追い込みがちですが、焦りが新たなストレスとなり、回復を妨げてしまいます。まずはトレーニングの記録や数値へのこだわりを一旦捨て、心身を解放するのが大切です。
精神的ストレスはオーバートレーニング症候群の原因の1つであり、症状を悪化させる要因にもなります。気分の落ち込みが続いたり、やる気がでない状態が長引いたりする場合は、精神科医やスポーツ心理士に相談してみてください。カウンセリングのほか、必要に応じて薬物療法を受けるのもおすすめです。
早期回復のためにも、心の状態を軽視せず、症状に合わせた専門的なサポートを受けましょう。
バランスの良い食事
オーバートレーニング症候群を治すためには、バランスの良い食事が欠かせません。食事を通して必要な栄養素を補うと、疲労の回復や免疫力向上の助けになります。具体的には、以下の栄養素を意識的に摂取しましょう。
|
栄養素 |
効果 |
|---|---|
|
ビタミンB群 |
|
|
ビタミンC |
|
豚肉や大豆製品などに多く含まれるビタミンB群は、エネルギー代謝を助けて疲労回復を強力に促す働きがあります。また、レモンやグレープフルーツなどに含まれるビタミンCには、疲労の原因を除去し、疲労回復に役立つといわれています。
食欲が落ちている場合は、うどんや雑炊など消化の良いものを少量ずつ回数に分けて食べるなど、胃腸への負担を減らす工夫も大切です。無理なダイエットや偏食は避け、1日3食しっかり食べ、身体の回復機能を内側からサポートしましょう。
オーバートレーニング症候群のチェックリスト
オーバートレーニング症候群を早期に発見するには、日々の体調や気分の変化に注意するのが大切です。オーバートレーニング症候群が疑われる場合は、以下の項目に該当するかセルフチェックしてみましょう。
|
貧血や感染症などが原因ではないにもかかわらず、複数の症状が該当する場合は、オーバートレーニング症候群が疑われます。
また、身体の不調を感じたときは、心拍数や血圧をチェックしてみるのもおすすめです。
疲労症状が強まると起床時の心拍数が増加するため、起床直後の心拍数をチェックすることで疲労状態を把握しやすくなります。起床直後の心拍数が1分あたり10回以上増えている場合は、オーバートレーニング症候群を疑いましょう。
上記の症状が2週間以上続く場合は、単なる疲れではない可能性があります。自己判断で放置せず、専門医へ相談してください。
オーバートレーニング症候群かもと感じたら早めに受診しよう
オーバートレーニング症候群は運動熱心な方ほど陥りやすく、トレーニング量と回復のバランスが崩れると発症します。放置すると重症化する可能性があるので注意が必要です。
「疲れ方がいつもと違う」「運動していなくても疲労感が続いている」と感じたら、休養したりトレーニングを軽くしたりして対応しましょう。
オーバートレーニング症候群は、軽症であれば比較的早く回復できますが、重症化すると復帰に時間がかかります。早期発見するには、セルフチェックリストを活用しながら、身体と心のサインを見逃さないのが大切です。
自己判断で放置せず、症状に応じて早めに医療機関を受診しましょう。
\無料オンライン診断実施中!/
オーバートレーニング症候群に関するよくある質問
オーバートレーニング症候群の診断方法は?
オーバートレーニング症候群は、一般的には以下の指標を総合的に判断して診断されます。
- 安静時心拍数の増加
- 安静時血圧の上昇
- 運動後血圧の回復の遅れ
- 競技成績の低下
オーバートレーニング症候群には明確な検査法が確立されていません。医師による問診や身体所見、血液検査などを用いて総合的に診断されます。
オーバートレーニング症候群は一般人でも発症する?
オーバートレーニング症候群は、プロのアスリートだけでなく、健康維持を目的に運動している一般の方や学生でも発症します。
オーバートレーニング症候群を発症するのは、スポーツ選手や部活動をしている学生だけではありません。
とくに、急に運動強度を上げた方や、仕事や家庭のストレスが多い中でトレーニングを続けている方は、発症しやすくなるため注意が必要です。
運動は健康の維持に欠かせない習慣ですが、過剰なトレーニングは逆効果になる可能性があるため注意しましょう。
オーバートレーニング症候群はどのくらいで治る?
オーバートレーニング症候群は、軽症・中等症であれば1〜3カ月程度での回復が期待できます。しかし、重症化すると半年〜1年かかるケースもあり、長期にわたる休養と治療が必要です。
治癒にかかる期間は、症状の重症度や発症からの期間、休養への取り組み方によって大きく異なります。
重症化を防ぐためにも、自己判断で無理を重ねず、医師や専門家のアドバイスを受けましょう。
オーバートレーニング症候群は何科を受診すれば良い?
オーバートレーニング症候群が疑われる場合は、スポーツ内科の受診がおすすめです。
ただし、地域によってはスポーツ内科の専門外来がないケースも考えられます。スポーツ内科が近くにない場合、症状に応じて整形外科や一般内科、婦人科などを受診しましょう。
目安として、2週間程度運動を控えても症状が改善されない場合は、早めに医療機関を受診してください。
オーバートレーニング症候群とうつ(鬱)の関係性は?
オーバートレーニング症候群は、身体的な疲労だけでなく精神面にも強い影響を及ぼす点が特徴で、うつ症状と似た状態が現れることがあります。
慢性的な疲労が続くと自律神経のバランスが崩れ、気分が落ち込みやすく、意欲低下や集中力の低下が目立つようになります。症状が進むと、運動への興味が失われたり、日常生活に支障が出るケースもあるため注意が必要です。
ただし、うつ病と完全に同じ病態ではないため、適切な診断とケアを受けるのが重要です。
参考文献
Vol. 31 No. 3, 2023.「オーバートレーニング症候群:理解と対応」|日本臨床スポーツ医学会誌