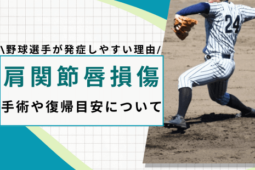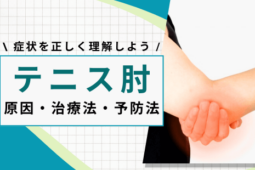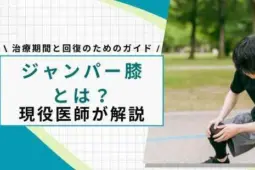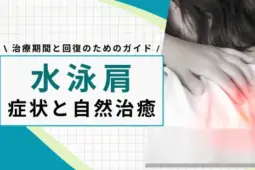- 上肢(腕の障害)
- 下肢(足の障害)
- スポーツ外傷
疲労骨折は自然治癒する?早く治す方法や運動復帰のコツを医師が解説【ランナー向け】
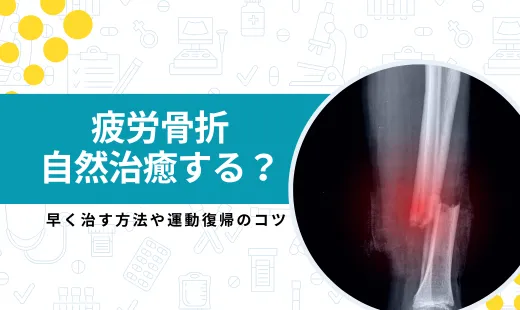
「疲労骨折は自然治癒する?」「どのくらい休めば治るの?」といった、悩みを抱えるランナーは少なくありません。
疲労骨折について、自然治癒するのか、病院に行くべきか悩む方もいるのではないでしょうか。
結論から言えば、疲労骨折は安静にすることで自然治癒が目指せるケガです。
しかし、自己判断で放置してしまうと、以下のようなリスクもあるため注意が必要です。
|
疲労骨折から早期に回復し、再びランニングを楽しむためには、正しい知識と適切なケアが欠かせません。
この記事では、疲労骨折の原因や症状、自然治癒のプロセス、そして復帰目安と予防策について詳しく解説します。
「まだ病院に行くほどではないけれど、痛みがあって、少し不安が残る」という方は、ご自身の状態が自然治癒で済むものか確かめるためにも、ぜひ一度、当院(リペアセル)の無料電話相談をご利用ください。
専門スタッフが、現在の症状や状況を丁寧に伺い、必要な対応をアドバイスいたします。
▼まずは無料で電話相談
>>こちらをクリック!今すぐ相談してみる
目次
疲労骨折は自然治癒できる!早く治すには「安静にすること」が大切
結論からいえば、疲労骨折は自然治癒するケガです。しかし、なにも対策せずに放置していても早く治るわけではありません。
疲労骨折を早く自然治癒させるには、疲労骨折がどうして発症するのか、どのような状態なのかを理解する必要があります。本章をしっかりと確認し、疲労骨折についての理解を深めてください。
疲労骨折の原因と典型的な症状
疲労骨折は、以下のような要因が重なると発生しやすくなります。
- 急激なトレーニング量の増加
- 不適切なランニングフォーム
- 硬いランニングサーフェス
- 足に合わない靴の使用
- 骨密度の低下
疲労骨折の症状は、以下のようなものがあります。
| 症状 | 説明 |
|---|---|
| 運動時の痛み | 特定の部位の痛み |
| 安静時の痛みの持続 | 休んでいても痛みが続く |
| 腫れや圧痛 | 患部が腫れたり、押すと痛みを感じる |
| 皮膚の発赤や熱感 | 患部の皮膚が赤くなったり、熱を持つ |
これらの症状が継続する場合は、疲労骨折の可能性が高いと考えられます。
疲労骨折は足をはじめ、膝や腰などにも発症しやすいケガです。以下の記事では、ランナーに多い「膝」と「足の甲」の疲労骨折について解説しています。気になる方はぜひ一度ご覧ください。
疲労骨折は通常の骨折と違い使いすぎによるもの
疲労骨折は運動などで体を使いすぎたことによって生じるケガです。病名には「骨折」とありますが、通常の骨折とは発症のメカニズムが異なります。
通常の骨折は転倒などの衝撃によって骨が折れるのに対し、疲労骨折は走った際の衝撃や筋肉が引っ張る力が繰り返し同じカ所に加わることで生じるケガです。
そのため、疲労骨折を治すためにはケガした箇所への負担を減らし、安静にすることが大切といえます。もし疲労骨折と診断されたら、治るまでは運動を中止しましょう。
ちなみに以下の記事では脛(すね)の使いすぎによって生じるシンスプリントについて解説しています。疲労骨折でお悩みの方はぜひご覧ください。
【自然治癒】疲労骨折を早く治す3つの方法!
疲労骨折を早く治す方法として、以下3つが挙げられます。
- 6〜8週間は安静にし、休息時間を取る
- 自然治癒を促進する栄養を摂取する
- 整形外科を受診し、運動療法や物理療法などのリハビリを受ける
疲労骨折で早く自然治癒させるためには、一旦運動せずに体を休めて安静期間を作りましょう。安静が必要な期間は疲労骨折の重症度によって変わり、症状が重たい場合にはより長く安静にする必要があります。
ここからは、自然治癒を早めるために大切な方法を3つご紹介します。本章を参考に、正しい疲労骨折のセルフケアを実施しましょう。
6〜8週間は安静にし、休息時間を取る
疲労骨折には6〜8週間の安静と休息時間が必要といわれています。ただし、骨折の部位や重症度によって、治癒に必要な期間は異なるので、まずは整形外科で検査を受けることをおすすめします。医師に疲労骨折の程度を確認してもらい、適切な指示を受けましょう。
疲労骨折のタイプと治癒の目安期間は以下のとおりです。
| 骨折のタイプ | 治療期間の目安 |
|---|---|
| 脛骨(シンスプリント) | 4~8週間 |
| 中足骨 | 6~8週間 |
| 大腿骨頸部 | 8~12週間 |
| 腰椎 | 6~12週間 |
ただし、これらは一般的な目安であり、治癒期間には個人差があるので注意してください。
また、疲労骨折の自然治癒には、以下の条件が必要といわれています。
- 十分な安静と休息
- 患部への負荷の回避
- 適切な栄養摂取
これらの条件を守れば、疲労骨折の自然治癒を早められる可能性があります。疲労骨折で悩んでいる方は、ぜひ実践してみてください。
自然治癒を促進する栄養を摂取する
自然治癒を促進するためには、適切な栄養摂取が重要です。以下の栄養素は、疲労骨折の自然治癒を早めてくれる可能性がある、おすすめの食材です。
| 栄養素 | 食べ物 |
|---|---|
| カルシウム |
|
| ビタミンD |
|
| タンパク質 |
|
上記の食材を食事にバランス良く取り入れ、疲労骨折の回復効果を高めましょう。
整形外科を受診し、運動療法や物理療法などのリハビリを受ける
疲労骨折の回復を早めるためには、整形外科を受診し、運動療法や物理療法など適切なリハビリを受けることをおすすめします。リハビリは自己判断で行わず、必ず医師の許可を得てから開始し、理学療法士の指導のもとで段階的に進めましょう。
疲労骨折時のリハビリの種類は以下のとおりです。
| 種類 | 目的 | 具体的な方法(例) | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 段階的な運動負荷 | 徐々に運動量を増やしていく |
|
骨折部位に過度な負荷をかけないよう、医師の指示に従う |
| 全身的な筋力トレーニング | 骨折部位周辺および全身の筋力維持・強化 |
|
骨折部位の筋力トレーニングは、完全に治癒するまで控える |
| 関節可動域訓練 | 関節の柔軟性維持 |
|
骨折部位の関節は、医師の許可があるまで動かさない |
| バランス訓練 | 再発予防とパフォーマンス向上に有用 |
|
骨折部位に体重をかけない方法から始める |
| 代償動作の修正 | 不適切な動作パターンの改善 |
|
骨折部位を保護しながら行う |
このアプローチにより、骨折部位を適切に保護しつつ、全身のコンディショニングと再発予防に焦点を当てたリハビリが可能となります。常に無理のない範囲で、徐々に活動レベルを上げていくことが大切です。痛みがある場合は必ず中止し、医師に相談してください。
また、リハビリには上記のような運動療法だけでなく電気や超音波を利用した物理療法もおこないます。物理療法では骨への血流促進効果や炎症を抑える作用があり、疲労骨折の治療として有効です。物理療法には以下のようなものがあります。
| 種類 | 効果 |
|---|---|
| アイシング | 痛みと腫れの緩和に効果的 |
| 電気刺激療法 | 痛みの軽減と筋肉の緊張緩和 |
| 超音波療法 | 骨の治癒を促進する可能性あり |
物理療法は疲労骨折による痛みの軽減や骨の自然治癒促進に働く可能性があります。効果には個人差がありますが、疲労骨折を早く自然治癒したい方は積極的に取り入れてみてください。
【再発に注意】疲労骨折後に運動復帰する2つの目安
疲労骨折から運動を再開するときに注意すべきなのは疲労骨折の再発です。
疲労骨折の治療中、安静にしていた体は想像以上に筋力・体力が衰えている可能性があります。そのため、運動復帰時の強度に注意が必要です。
これからご紹介する2つの目安を参考に運動を再開し無理をしないように心がけてください。それでも判断に迷う場合には、必ず医師の判断を仰いでから運動を再開しましょう。
なお、当院リペアセルクリニックでおこなっている再生医療は疲労骨折にも効果が期待できます。興味がある方はメール相談もしくはオンラインカウンセリングでお気軽にご相談ください。
骨折部位を押したり叩いたりして痛みがない
骨折部位を押したり叩いたりして痛みがない場合、運動を再開できる目安といえます。
疲労骨折時は、骨折部位を押したり叩いたりすると痛みを感じることが多くあります。
痛みがなければ疲労骨折が治癒している可能性があるため、少しずつ運動を再開しても良いでしょう。
逆に押したり叩いたりしたときに少しでも痛みを感じるようであれば、無理せず安静にすることをおすすめします。
運動動作をしてみて痛みがない
ジョギングなどの軽い運動動作をしてみて痛みがない場合も、運動再開の目安です。
運動再開時は疲労骨折する前と同じ運動量ではなく、負荷をかけすぎないように注意してください。走るときもまずはジョギング程度から開始し、時間・距離を短くして軽く走ると良いでしょう。
安静期間が長いほど体は衰えている可能性が高いため、急に激しく動かすと疲労骨折の再発の原因になりかねません。
軽めのジョギング程度から開始し、徐々に時間・距離を伸ばして体を運動に慣らしましょう。
また、疲労骨折の再発を予防するためのポイントは次項で詳しく紹介しています。疲労骨折後に運動復帰する上で大切なことなので、ぜひチェックしてみてください。
疲労骨折を予防する2つのポイント
疲労骨折を予防するためにはトレーニング方法の見直しとライフスタイルの調整が重要です。ここから疲労骨折を予防するためのポイントを2つご紹介しますので、ぜひ実践してみてください。
トレーニングは自分に合った方法と負荷で行う
疲労骨折を予防するためには、自分に合った方法・負荷で行うことが大切です。トレーニングでは、以下4つのポイントを抑えておきましょう。
| トレーニングのポイント | 詳細 |
|---|---|
| 段階的にトレーニング量を増やす |
|
| 十分なウォームアップとクールダウンを行う |
|
| 適切な休養日を設ける |
|
| クロストレーニングを取り入れる | 全身を使う水泳などのクロストレーニングは一部位への負担を軽減し、疲労骨折の予防につながる |
急激に大きな負荷をかけたり、休まず動かし続けたりすると、疲労骨折のリスクが高くなります。
トレーニングの負荷は段階的に増やすよう意識し、週1回以上は身体を休めるようにしましょう。
規則正しいライフスタイルで骨を休ませる
疲労骨折を予防するには、十分な休息で骨を休ませる規則正しいライフスタイルが重要です。以下のようなライフスタイルの調整が役立ちます。
| ライフスタイルの調整 | 具体的な方法 |
|---|---|
| バランスの取れた食事 |
|
| 適度な日光浴 | 1日15~30分程度、日中の太陽光を浴びる |
| 禁煙 |
|
| 過度なアルコール摂取の制限 |
|
疲労骨折の予防には、適切な栄養摂取が欠かせません。
また、意識的に太陽の光を浴びたり、喫煙や過度な飲酒を避けたりすることも、疲労骨折の予防につながります。
定期的な骨密度検査を受け、骨の健康状態をチェックすることも大切です。疲労骨折の予防や早期発見のためにも、整形外科にて定期的な骨密度検査や診察を受けておくと安心です。
まとめ|疲労骨折を早く自然治癒させるためには安静が重要!
疲労骨折は身体の使い過ぎによって起こるケガであり、自然治癒するケースが多くあります。疲労骨折を早く自然治癒させるためには、しっかりと安静にすることが大切です。
また、自然治癒を早めてくれる栄養の摂取や、運動復帰後のトレーニングの進め方も大切です。この記事で紹介したことを実践し、疲労骨折の予防や再発防止に努めましょう。
ちなみに当院リペアセルクリニックでおこなっている再生医療は、疲労骨折をはじめとするスポーツ障害の治療にも有効です。
自然治癒を目指している方でも、『このまま安静にしていて本当に治るのか?』と不安に感じたら、まずは無料の電話相談をご利用ください。
専門スタッフがあなたの状態に合わせて、適切なアドバイスをいたします
▼まずは無料で電話相談
>>こちらをクリック!今すぐ相談してみる
疲労骨折についてよくある質問
疲労骨折は自然治癒しますか?
疲労骨折は自然治癒するケガです。安静にし、骨折部位に負担をかけなければ自然治癒していくでしょう。しっかりと栄養を摂り、運動療法や物理療法を併用すればより早く自然治癒する可能性もあります。
疲労骨折で多い部位はどこですか?
足の中足骨や膝・肋骨・腰椎・脛に多く発症します。
これらの部位はあらゆるスポーツでよく使われる骨です。とくに長い距離を走ったり、体を捻ったりするスポーツ選手は注意が必要なため、疲労がたまらないようケアを心がけてください。