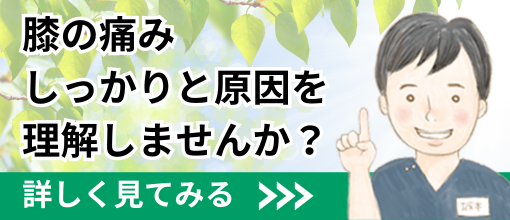-
- ひざ関節
- 膝の慢性障害
膝の皿に痛みを感じる場合、膝関節の軟骨の摩耗や靭帯損傷といった疾患の可能性があります。 原因によって適切な対処法や治療法が異なります。症状を放置して悪化させると、歩行に支障をきたす恐れもあり、早期回復のためにも早めに医療機関を受診することが重要です。 当院リペアセルクリニックでは、膝の皿の痛みだけでなく「膝のちょっとした違和感」など些細なことでも無料でご相談を承っています。 なお、膝の皿の痛みに対しては、再生医療も治療選択肢の一つです。 膝の皿の痛みに関するお悩みを今すぐ解消したい、再生医療に興味がある方は、当院「リペアセルクリニック」までお問い合わせください。 【今すぐできる】膝の皿が痛いときの対処法 膝の皿が痛いとき、病院を受診するまでの間に自分でできる対処法は、主に以下のとおりです。 安静の確保 患部の冷却 ストレッチ・トレーニング テーピング ただし、誤った方法でセルフケアをすると悪化する恐れもあるため、あくまで一時的な応急処置に留め、痛みが続く場合は早めに整形外科を受診してください。 安静の確保 膝の皿に痛みが現れた直後は、患部の安静が大切です。とくにランニングやジャンプ動作を伴うスポーツ中に痛みを感じた場合は、直ちに運動を中止してください。 痛みを我慢して動かし続けると、炎症が長引く可能性があります。 階段の使用を控えてエスカレーターを使う、正座を避けるなど、日常生活において膝への負荷を抑える工夫が必要です。 患部の冷却 痛みが出始めた直後や、腫れ・熱感を伴う場合は、患部を冷やすアイシングが有効です。冷却することで血管を収縮させ、腫れや炎症を抑えやすくなります。 保冷剤や氷嚢をタオルで包み、患部に当てます。冷やし過ぎると皮膚や血流に悪影響を及ぼす恐れがあるため、注意が必要です。 ストレッチ・トレーニング 膝の皿の痛みは、膝の皿の上にある「大腿四頭筋」や、太もも裏の「ハムストリングス」、お尻の「殿筋」の柔軟性や筋力の低下が関与しているケースがあります。これらの筋肉を無理のない範囲で伸ばし、膝関節周囲のバランスを整えることが大切です。 また、膝の皿の痛みは、大腿四頭筋の筋力低下によって起こっているケースもあります。そのため、ストレッチだけでなく適度なトレーニングをおこなうのも良いでしょう。 それぞれの部位ごとのストレッチ・トレーニング方法は以下のとおりです。 対象部位 やり方 大腿四頭筋 (太ももの前) <ストレッチ> 1.壁や椅子に手を添えて立ちます。 2.片足ずつ膝を曲げ、足首を持って後ろに引き前ももを伸ばします。 <トレーニング> 1.仰向けに寝て、両膝を立てた状態にします。 2.片方の膝を伸ばし、床から10センチほど浮かせた位置でキープします。 3.ゆっくりと下ろします。これを左右10回ずつ行います。 ハムストリングス (太ももの裏) <ストレッチ> 1.片方の膝を伸ばして床に座り、もう片方の膝は曲げます。 2.背筋を伸ばしたまま、上半身をゆっくり前に倒します。 3.太ももの裏が伸びる位置で止め、深呼吸をしながらキープします。 殿筋 (お尻) <ストレッチ> 1.床に体育座りの状態で座り、両手を後ろにつきます。 2.片方の足首を、反対側の膝の上に乗せます(数字の4のような形)。 3.両手で床を押し、胸を脛(すね)に近づけるように上体を起こします。 4.お尻の筋肉が伸びていることを確認し、15秒程度キープします(反対も実施)。 ストレッチは、反動をつけず痛気持ち良い程度で、無理なくおこないましょう。 膝の皿が痛む場合のストレッチやトレーニングについては、以下の記事も参考にしてください。 テーピング 膝の皿の痛みを和らげる手段として、テーピングも有効です。膝関節や周辺の筋肉の動きを安定させ、運動時の膝の痛みを軽減します。 テーピングの際は、血流を阻害しないよう過度な圧迫を避けながら、皮膚にシワが寄らないように巻きましょう。 正しい巻き方がわからない場合は、整形外科や理学療法士の指導を受けると安心です。 膝をサポートするテーピング方法は以下の記事で紹介しています。気になる方はチェックしてみてください。 膝の皿が痛い3つの原因 膝の皿が痛む背景には、いくつかの原因があります。 とくに多いのが、次の3つです。 太ももの筋力や柔軟性の低下 膝への過度な負荷 加齢による関節の変化 これらの要因が単独、あるいは重なることで、膝の皿まわりに痛みが生じやすくなります。 膝の皿の痛みにお悩みの方は、まずご自身に当てはまる原因がないかを確認し、今後の予防や対処につなげましょう。 太ももの筋力・柔軟性の低下 膝の皿(膝蓋骨)は、太ももの前側にある「大腿四頭筋」という筋肉と腱によって支えられています。 運動不足や加齢によってこの筋力が低下すると、膝蓋骨を正しい位置に引き上げる力が弱まり、膝の曲げ伸ばしに伴う動きにズレが生じやすくなります。 さらに、筋肉の柔軟性が低下して硬くなると、膝蓋骨が大腿骨に過度に押し付けられ、関節への負担が増加します。その結果、軟骨周辺に炎症が起こり、膝の皿の周囲に痛みを感じやすくなります。 膝への負荷増大 膝関節は、歩行や階段昇降といった日常動作のたびに体重を支える重要な部位です。膝への負荷は、平地歩行時で体重の約3倍、階段の上り下りでは約4倍にも達するとされています。(文献1) 体重の増加や長時間の立ち仕事、ランニングやスクワットなどのスポーツ動作が重なると、膝の皿やその周囲にかかる負担はさらに増大します。こうした過度な負荷が繰り返されることで、膝蓋骨と大腿骨の接触面や膝蓋腱に小さなダメージや炎症が蓄積し、膝の皿まわりに痛みとして自覚されるようになります。 加齢 年齢を重ねると、膝関節のクッションである軟骨が徐々にすり減り、弾力性が失われていきます。 軟骨の摩耗が進むと、膝の皿と骨との間で衝撃を吸収しにくくなり、骨同士が直接擦れ合う頻度が増えます。これが動作時の違和感や痛みにつながります。加齢そのものだけでなく、年齢に伴う筋力の低下や関節液の減少が重なることで、膝の皿周辺の痛みが生じやすい環境が作られてしまいます。 膝の皿が痛いときの受診目安 膝の皿の痛みで病院に行くべきか迷った場合は、以下の項目を参考にセルフチェックしてみましょう。 動作の始まり(歩き始めや立ち上がり)に膝の皿が痛む 起床時に膝の皿がこわばる感じがする 階段を上り下りすると膝の皿が痛む 膝蓋腱を指で押すと痛む うつ伏せの状態で膝を曲げると股関節まわりが床から浮く これらに1つでも当てはまる場合、変形性膝関節症などの初期症状の可能性があります。 膝の皿の痛みが続くときは放置せず、早めに整形外科を受診し、専門医による診察・検査を受けましょう。 【原因別】膝の皿が痛いときの治療法 膝の皿が痛む場合は、主に以下3つの原因が考えられます。 膝蓋大腿関節症 変形性膝関節症 膝蓋腱炎(ジャンパー膝) 膝の皿の痛みにお悩みの方は、本章で紹介する症状や治療内容を参考に、ご自身の状態を確認してください。 膝蓋大腿関節症 加齢や筋力低下、膝への負担の蓄積などによって膝蓋大腿関節にズレや炎症が起きると、軟骨がすり減って痛みが生じやすくなります。この状態を「膝蓋大腿関節症(しつがいだいたいかんせつしょう)」といいます。 膝の皿の骨である膝蓋骨と大腿骨との間で障害が起こる病気で、膝を伸ばす動作や階段の上り下りで痛みを感じやすいのが特徴です。膝の皿だけでなく、膝の皿の周囲が痛むケースもあります。 【主な治療法】 整形外科での診察や画像診断を行った上で、まずは保存療法が選択されます。保存療法には、運動療法や薬物療法があります。 症状が重い場合は、手術療法が検討されることもあります。 膝蓋大腿関節症は、とくに中高年の女性に多く見られる疾患です。女性で膝の皿の痛みに悩んでいる方は、一度医療機関の受診を検討してください。 変形性膝関節症 変形性膝関節症は、関節の軟骨が徐々にすり減り、関節が変形してしまう病気です。 主な原因は、以下が挙げられます。 加齢 肥満 遺伝 骨折などの外傷 初期段階では、膝の皿周辺の違和感や、動作の開始時に痛みが見られます。膝に水が溜まるなどの症状が現れることもあります。治療せずに放置すると、安静時にも痛むようになり、膝を伸ばせなくなることもあります。 【主な治療法】 保存療法 薬物療法:湿布や内服の痛み止め 注射療法:関節内へのヒアルロン酸注射 理学療法:リハビリテーション 装具療法:装具の装着 手術:人工関節術 また、変形性膝関節症の治療には再生医療(幹細胞治療・PRP療法)も効果的であることがわかっています。 変形性膝関節症について詳しく知りたい方はこちらもどうぞ。 再生医療について、詳しくは以下の記事をご覧ください。 変形性膝関節症の再生治療(PRP療法)の体験談|効果・費用も紹介 複数の関節痛が順調に軽減! 左変形性股関節症・左変形性膝関節症 60代女性 膝蓋腱炎(ジャンパー膝) 膝蓋腱炎(ジャンパー膝)とは、膝の皿の下にある「膝蓋腱」に繰り返し負担がかかることで炎症や損傷を生じ、痛みを起こす病気です。 発症初期は、動作の始めや運動時に膝の皿の違和感を覚える程度ですが、進行すると日常生活でも痛みを感じるようになります。 膝蓋腱は、ジャンプや着地、ランニングなど、膝の屈伸動作で引っ張られる部位です。そのため、膝蓋腱に負担がかかりやすいサッカーやバレーボール、バスケットボールなどのスポーツをしている人に多くみられます。 【主な治療法】 保存療法 薬物療法:痛み止めの内服 注射療法:ヒアルロン酸、PRP療法(多血小板血漿療法) 運動療法:ストレッチ 手術 再生医療 重症の場合は「難治性膝蓋腱炎」の可能性があり、手術を検討するケースもあります。 日常的に跳躍動作の多いスポーツをしていて、膝の皿の痛みにお悩みの方は、整形外科などの受診がおすすめです。 膝蓋腱炎(ジャンパー膝)については、以下の記事も参考にしてください。 膝の皿が痛い原因を把握し悪化する前に受診しよう 本記事では、膝の皿が痛む主な原因と、日常生活ですぐに取り入れられる対処法について解説しました。 膝の皿が痛い場合、筋力低下や負荷の蓄積といった要因だけでなく、膝蓋大腿関節症や変形性膝関節症などの疾患が背景にある可能性も考えられます。 ストレッチやトレーニング、テーピングなどは一時的な負担軽減につながることもありますが、痛みが続く場合や日常生活に支障が出ている場合は、早めに整形外科を受診しましょう。 当院「リペアセルクリニック」では、自己の幹細胞を用いた再生医療による治療をおこなっています。膝の皿の痛みに対しては、再生医療も治療選択肢の一つです。 関節部分に幹細胞を投与し、すり減った軟骨を再生させることで、手術なしで症状を改善できる可能性が高くなります。 膝の皿の痛みのお悩みを今すぐ解消したい、再生医療に興味がある方は、当院「リペアセルクリニック」の電話相談までお問い合わせください。 膝の皿が痛いときによくある質問 急に膝の皿が痛くなるのはなぜですか? 急に膝の皿が痛む場合、太ももの筋力低下や姿勢の悪さによって膝蓋骨の動きが不安定になることが原因の可能性があります。 また、大腿四頭筋腱炎など、膝周囲の腱に炎症が起きている可能性も考えられるため、痛みが続く場合や日常生活に支障が出る場合は早めに整形外科で診察・検査を受けましょう。 曲げると膝の皿が痛いときはどうすれば良いですか? 膝を曲げたときに痛みが出る場合は、膝への負担を減らし、できる限り安静にすることが第一です。 腫れや熱を持っている場合は、炎症が引くまで冷やすと症状が和らぐことがあります。 40歳以上の方では、変形性膝関節症の可能性もあるため、自己判断で放置せず、不安がある場合は整形外科での受診を検討してください。 膝の痛みは自然に治りますか? 一時的な負荷による痛みであれば、安静にすることで自然に軽快するケースもあります。 一方で、軟骨のすり減りや関節・腱の炎症が原因の場合、自然に治癒することは難しいと考えられます。 痛みが繰り返し出る、徐々に強くなる、動作に制限が出ているといった場合は、放置せず医療機関で原因を確認することが重要です。早期に対応することで、症状の進行を抑えられる可能性があります。 参考文献 (文献1) Loading of the knee joint during activities of daily living measured in vivo in five subjects|Journal of Biomechanics
2023.09.14 -
- ひざ関節
- 膝の外側の痛み
- 膝の慢性障害
- スポーツ外傷
腸脛靭帯炎(ちょうけいじんたいえん)は、有酸素運動に取り組む場合によく見られる炎症です。 とくに習慣的にランニングを楽しむ方の間で頻発することから、ランナー膝とも呼ばれます。 しかし腸脛靭帯炎の症状や治療法、予防法などはあまり知られていません。しかし発症しやすい炎症であるため、事前に知識を知って対処するのが重要です。 本記事では腸脛靭帯炎の症状や治療法、効果的なストレッチやテーピングなどを解説します。 腸脛靭帯炎(ランナー膝)の基礎知識 まず、腸脛靭帯炎がどのような炎症か解説します。 そのあと、発生の原因やメカニズム、診断方法などを解説します。 事前に腸脛靭帯炎に関して理解し、発症した際、冷静に対処できるようにしておきましょう。 「腸脛靭帯(ちょうけいじんたい)」とは? この病気がどのようなものか説明するには腸脛靭帯に関して知る必要があり、簡単にお伝えします。 腸脛靭帯とは、骨盤の外側に出っ張っている腸骨(ちょうこつ)から、膝下にある脛骨(けいこつ)につながっていて太ももの外側部分に長く伸びるように位置しています。 また、腸脛靭帯は大臀筋と大腿筋膜腸筋(だいたいきんまくちょうきん)という、これまた長くて難しい名前の筋肉とつながることで身体をぐらつかせることなく、さらに身体を安定して保つ大切な役目を担っています。 膝上の太もも部分の外側を押すと、硬いスジ状のものに触れることができますが、これが腸脛靭帯です。 とくに大きな動きに対して大臀筋と呼ばれる大きな筋肉と大腿筋膜張筋とにつながることで、それらの力を脚に伝える役割があります。 腸脛靭帯の働きのおかげで骨盤や膝が安定し、歩くことは勿論、スムーズなランニングを助けてくれます。 そんな腸脛靭帯が炎症を起こした状態が「腸脛靭帯炎」です。 メール相談 オンラインカウンセリング 「腸脛靭帯炎(ちょうけいじんたいえん:ランナー膝)」とは 腸脛靭帯炎は、別名「ランナー膝」と呼ばれるくらい、「ランニングの愛好家にとって多いケガ」の一つです。ここでは腸脛靭帯炎の症状、原因、診断に関して簡単に説明します。 自分に当てはまる点はないか、チェックしてみましょう。 腸脛靭帯炎の症状 腸脛靭帯炎の初期症状は、運動後に膝の外側に痛みが出ることです。痛みが出る場所は、外側上顆(がいそくじょうか)と言われる膝外側の出っ張り部分です。 痛みは安静にすれば徐々に収まります。 しかし、炎症がひどい場合や、痛みを我慢して無理を続けた場合、歩いたり、膝を曲げ伸ばしをしただけでも痛みが出ることがあります。 久しぶりにランニングやジョギング、ウォーキングを頑張った人によくみられる症状です。 「さぁ、健康のために頑張って走ろう!!」という矢先につまずいてしまうと、やる気も削がれかねません。 腸脛靭帯炎の発生メカニズム 腸脛靭帯炎は、繰り返される『摩擦』によって生じます。 摩擦が起こる場所は、大腿骨の外側上顆という場所です。 そこは骨が隆起しており、膝を曲げ伸ばしすることで腸脛靭帯が外側上顆を乗り越えてしまいます。 とくに膝を軽く曲げた状態(屈曲30°くらい)でちょうど乗り越えるため、ランニングのように、0〜30°くらいの曲げ伸ばしを繰り返すことで摩擦がかかりやすくなってしまいます。 発症の主な原因 腸脛靭帯炎の原因の大半はランニングやサイクリングなどの反復的な運動、もしくは運動に対する筋力不足です。 ただし以下の原因で発症する可能性があります。 O足 扁平足 股関節周囲の筋肉の老化 O足や扁平足などは、股関節の機能低下や骨同士の位置関係を乱します。これが原因で腸脛靭帯炎を発症するケースもあります。 また股関節周囲の老化が原因になるかもしれません。 したがってランナー以外の方でも腸脛靭帯炎が発症しうると言えます。 腸脛靭帯炎の初期対応 原因がランニングなどの運動なら、症状が落ち着くまで休養します。 場合によっては、患部にアイシングや湿布を貼付すれば症状の緩和が得られます。 とくに急性期では患部の安静と炎症を抑えることを最優先させましょう。 また症状がごく軽微な場合をのぞき、医療機関で診察を受けることをおすすめします。 その理由として、腸脛靭帯炎でなく、半月板損傷などの重篤な障害が生じている可能性があるからです。 また医療機関で診察を受ければ、症状の緩和や、周辺にある滑液包での炎症の予防に効果的な、投薬や注射が受けられるでしょう。 メール相談 オンラインカウンセリング 腸脛靭帯炎の診断 腸脛靭帯炎は、問診や触診である程度は鑑別できます。 ただ、炎症の状態や他の疾患と見分けるためにレントゲンやMRI、エコー検査が必要なことがあります。 また、腸脛靭帯炎には、特有のテストがあります。 それが「Grasping Test(グラスピングテスト)」です。 やり方は、難しくありませんので、もしかしたら腸脛靭帯炎かもしれない、と思われた方は、試してみましょう。 【Grasping Testの方法】 ①患者さんの膝を90°ほど曲げる。 ②痛みが出ている場所の少し上を親指で強く押さえる。 ③その状態で膝をゆっくり伸ばしていく。 ④その時に痛みが出るのであれば、腸脛靭帯炎が疑われる。 腸脛靭帯炎にならないためのトレーニング ここまで、股関節機能の低下や骨の位置関係の乱れにより、腸脛靭帯炎を発症しうると解説してきました。 股関節の筋力の低下や足元のぐらつきにより、ランニング時に膝が内外にぐらつくと腸脛靭帯への摩擦が増加してしまいます。 安静期間により症状が落ち着いても、同じような状態だとまた腸脛靭帯炎を繰り返してしまうでしょう。 そのため、ランニングなどのスポーツに復帰するにあたり、腸脛靭帯への負荷を減らすためのトレーニングを推奨しています。 ここでは以下の3つの方法を紹介します。 各トレーニングは、やみくもに動かすのではなく、いずれも体を安定させ、姿勢を意識して行うことがポイントです。 1,股関節の外側の筋肉:大臀筋、中臀筋 上になっているほうの足を持ち上げる→下ろす を繰り返す 2,股関節の内側の筋肉:内転筋 下になっている方の足を持ち上げる→下ろす を繰り返す 3,ふくらはぎの筋肉:下腿三頭筋(ヒラメ筋、腓腹筋) つま先立ち→かかとを降ろす を繰り返す 腸脛靭帯炎(ランナー膝)の治療や予防に役立つストレッチ・セルフケア 腸脛靭帯は、足首や他の膝の靭帯と違い、断裂など重症化するケースはほとんどありません。 そのため、基本的には普段と同じような生活を送っていただいて結構です。 ①腸脛靭帯炎に有効なストレッチ 腸脛靭帯炎による痛みが落ち着いたら、徐々にストレッチを開始します。 腸脛靭帯炎を発症する人の特徴として、身体のケア不足により筋肉の伸び縮みの動きが悪くなっていることがあります。 ここでは、腸脛靭帯と連結している大腿筋膜張筋と股関節および大腿部前面の筋肉の3つのストレッチ方法をお伝えします。 1.大腿筋膜張筋のストレッチ 各ストレッチは、無理をせず、痛くなりすぎない範囲で行いましょう。 2.股関節前面の筋肉のストレッチ 3.大腿部前面の筋肉のストレッチ ②腸脛靭帯炎(ランナー膝)に有効なマッサージとセルフケア またマッサージによっても、腸脛靭帯炎の症状を緩和できます。 たとえば膝蓋骨(膝のお皿)をマッサージする方法は簡単に取り組めるのでおすすめです。 左右の親指と人差し指で、膝蓋骨を軽くつかむ 内側の方向に軽く押し込む 内側から外側に軽く押し込む 2と3を繰り返す また膝蓋骨を手のひらで包み、円を描くように回すのも効果的です。 セルフケアとして、運動後や風呂上がりにアイシングをおこなうのも良いでしょう。 熱を取り除くことで、腸脛靭帯炎を予防できます。 ③重度の場合は外科手術も検討 腸脛靭帯炎の症状が顕著な場合は、外科手術が有効です。 腸脛靭帯炎の治療では以下の手術が用いられます。 腸脛靭帯炎の切開|腸脛靭帯炎の患部周辺を解放し摩擦を減らす 滑液包の除去|腸脛靭帯炎と大腿骨の隙間にある滑液包の一部または全部を取り除く 腸炎靭帯延長手術|腸脛靭帯を伸ばすなどして、症状の改善や再発防止を図る 手術と保存療法どちらが適切か、専門家でなければ判断できません。 自身で判断せず、医療機関で受診して医師の判断を仰ぎましょう。 近年では、自己脂肪由来幹細胞などを用いた、再生医療による腸脛靭帯炎の治療の研究も進められています。 再生医療を用いれば、従来よりも効果的な治療が受けられるかもしれません。 再生医療については、以下の記事を参考にしてください。 関連記事:再生医療とは|リペアセルクリニック メール相談 オンラインカウンセリング 腸脛靭帯炎(ランナー膝)とスポーツとの関係 腸脛靭帯炎のテーピングで大事なことは、腸脛靭帯の負担を減らしてあげることです。 そのため、腸脛靭帯自体をサポートするテーピングと、膝の動きをサポートするテーピングの2種類を用いて行います。 腸脛靭帯炎(ランナー膝)のテーピング あくまでテーピングは補助的な役割にしか過ぎません。また、その人によってテーピングの効果が十分に発揮できない場合もあります。 可能な限り、専門の医療機関にご相談の上、「テーピング」を施行するようにしましょう。 このようなテーピング以外にも「サポーター等の装具」を用いて腸脛靭帯を支え、安定を図る方法もあります。 腸脛靭帯炎と靴(シューズ)選び 腸脛靱帯炎の対策のなかでは靴選びも大切です。 足が左右にぐらつくと腸脛靱帯につながる大腿筋膜張筋が頑張ってぐらつきを止めようとします。 そうすると、筋肉が過剰に働き、ピンと張った状態になります。 その状態で走り続けると、腸脛靭帯への摩擦が助長されて腸脛靭帯炎を引き起こしかねません。シューズ選びの際は以下の3つのポイントを意識してみましょう。 靴は使用に伴い消耗します。 定期的、あるいは、いま一度自身の靴をチェックして自分に合った最適な靴を選びましょう。 1.シューズの後ろ、カップの部分がしっかりしているか 2.指の付け根で曲がるのか 3.シューズが過度に捻じれやすくなっていないか まとめ・腸脛靭帯炎(ランナー膝)の治療では医師の指示を受けるのが重要 今回は、腸脛靭帯炎に関して、病態や、ストレッチ、テーピング、靴選びなどの角度から、その対策をお話しました。 腸脛靭帯炎(ランナー膝)は、ランニングやスポーツをする人に多い症状ですが、正しい対処法を知っていれば予防や治療が可能です。 まずは症状や原因を理解し、痛みが出た場合には早めの対処が重要です。 また症状が軽微な場合をのぞき、医療機関を受診し、適切な指示を得るようにしましょう。 初期の対応としては、炎症を抑えるための安静やストレッチ、適切なテーピングが有効です。 また、腸脛靭帯炎を予防するためには、股関節やふくらはぎの筋力を鍛えるトレーニングや、適切な靴選びも重要です。 日常生活での意識や対策を行い、ランニングやスポーツを安全に楽しむために、ストレッチをはじめ、適切なケアを心がけましょう。 腸脛靭帯炎は誰にでも起こりうるケガです。 これから運動を始める人も、ランニング愛好家の皆さんも運動前の準備運動、そして運動後のカラダのケアをしっかり行いながら、自分に合ったペースで頑張りましょう。 メール相談 オンラインカウンセリング
2022.11.04 -
- 変形性膝関節症
- 半月板損傷
- 靭帯損傷
- ひざ関節
- 膝の慢性障害
膝の病気や痛みをかかえている方のなかには、定期的に膝へヒアルロン酸注射している方が多くいます。 しかし「最初は注射をすれば膝の痛みがひいたのに最近は効かなくなってきた」「効かないのは失敗が原因?」と感じた経験もあるでしょう。 そこで今回はヒアルロン酸注射をしていて、効かないと感じたり失敗を疑っている方に向けて、ヒアルロン酸の効果を解説します。 膝のヒアルロン酸注射が効かなくなる原因と、効果が乏しいときの対処法も紹介するので、最後までご覧ください。 膝にヒアルロン酸注射をしても効かないのは失敗が原因なの? 膝のヒアルロン酸注射が効かず、失敗を心配する方もいるかも知れませんが、病気の進行や膝の変形が重度になると効果が薄くなります。 ヒアルロン酸注射自体の問題や治療の失敗などではなく、膝自体に炎症がある場合、ヒアルロン酸注射が、効かないケースも多くあります。 膝に感染があるときは、ヒアルロン酸注射自体が余計に症状を悪化させてしまう症例もあるので注意が必要です。 変形性膝関節症は、年齢を重ねると進行する病気なので、誰でも変形が強くなっていく可能性はあります。 しかし体重が重かったり、もともと運動習慣がなかったりする方は、変形が進行する原因になるとも言われているので注意しましょう。 膝の変形性関節症における重症度や膝の組織を評価するために、レントゲン検査やMRI検査など、画像検査が行われます。 MRI検査では、膝の軟骨や靭帯、半月板が傷ついていないかも診断できるため、治療方法の選択をするためにも重要な検査です。 MRI検査が重要な理由は、以下の記事で詳しくまとめました。 そもそもヒアルロン酸注射とは 「膝のヒアルロン酸注射が効かないのは失敗が原因なの?」と不安に感じる方に向けて、ヒアルロン酸注射の概要を解説していきます。 ヒアルロン酸注射の効き目を感じず失敗と捉える前に、まずは注射として期待できる効果の概要を見ていきましょう。 ヒアルロン酸注射は初期症状におすすめ ヒアルロン酸は、膝の変形性関節症における初期症状におすすめの治療方法です。 ・ヒアルロン酸注射のみで完結する軽度な治療 ・軟骨保護のような炎症緩和 など 上記のような治療目的で使用されるのがヒアルロン酸注射です。 そもそもヒアルロン酸は水分をたくさん含む物質で、主に関節の内部を満たしている液体成分を補充する目的で注射します。 膝にヒアルロン酸を注射すれば、動きをよくする潤滑油のような役割になるのです。 膝以外にも眼の乾燥としてヒアルロン酸の目薬を行います。 目に潤いを与えるためヒアルロン酸が用いられるように、短時間で効果を得たい場合に提供される治療方法としてヒアルロン酸が活用されているのです。 ヒアルロン酸注射は根本的な治療にはならない いろいろな用途に用いられるヒアルロン酸ですが「変形性膝関節症」で、膝関節の動きを滑らかにするため注射している方もいるでしょう。 注射治療になるので手術のような日常生活の支障を気にする必要もありません。 しかしヒアルロン酸注射は、液体成分なので体内に吸収されてしまいます。 持続期間は約1〜2週間程度と言われているため、時間経過とともに「注射の効果がない」「失敗した」と感じてしまうでしょう。 膝の関節にはヒアルロン酸をたくさん含んでいる滑液で満たされています。 滑液が膝の滑らかな動きを保つのに重要な役割を担っています。 しかし、年齢を重ねたり外傷や他の疾患があったりすると、滑液の中のヒアルロン酸の量が減ってしまうのです。 ヒアルロン酸の量が減ってくると、膝を滑らかに動かすのが難しくなり、結果として膝にある骨や軟骨がこすれて痛みを感じてしまいます。 ヒアルロン酸注射をしただけでは一時的な治療になり「痛みを感じにくい状態」である持続期間が切れた際「効果がない」と捉えてしまいがちなのです。 以下の記事では、ヒアルロン酸注射の有効性と限界について詳しくまとめているので、あわせてご覧ください。 膝のヒアルロン酸注射が効かなくなった場合の対処法 ヒアルロン酸注射は、はじめは効いても徐々に効かなくなるケースがあります。 ヒアルロン酸注射以外の治療法を併用していくことも大切です。 ここからは膝のヒアルロン酸注射が効かなくなった場合の対処法として挙げられる治療法などを解説します。 適度な運動 膝のヒアルロン酸注射を必要とする代表的な症例である「膝変形性関節症」には、病院に受診しなくても自分自身で行える治療があります。 たとえば体重が重い方は、体重を減量するための運動も治療として重要な方法です。 専門的な治療を施すのであれば、運動療法を実施するのをおすすめします。 規則正しい有酸素運動や筋力トレーニング、関節可動域運動を実施して継続していくのが大事です。 膝をサポーターで保護し、テーピングを実施するのも推奨されています。 膝の負担を減らしながらできる運動については、以下の記事に詳しくまとめているので、ぜひ役立ててください。 ステロイド薬の投与 膝に炎症がある場合、ヒアルロン酸の注射ではなくステロイド薬を膝に注射する治療法もあります。 ステロイド薬の投与だけでなく、炎症を抑えるための薬を飲む治療法をしつつ、数カ月のリハビリなど保存療法を進めていく治療法も挙げられます。 人工関節を用いた手術 重症になった場合や注射が効かない状態が続くと手術が必要なケースもあります。 手術では関節の代用部品である「人工関節」を関節の代わりに埋め込む治療を実施します。 皮膚を切って開く必要があるため、全身麻酔で手術が行われます。 手術は傷口が感染しないか、麻酔によるアレルギーなどがないかを診るためにも入院が必須です。 入院自体は数日〜数週間ですが、もともとの歩行状態に戻るためには数カ月膝のリハビリが必要です。 人工関節を使った手術で知っておくべき項目については、以下の記事でまとめているので、あわせてご覧ください。 手術(人工関節)を避ける再生医療の選択肢 最近では手術の代わりに「PRP療法」や、「幹細胞治療」と呼ばれる新しい先端治療を選択できるようになってきました。 PRP療法は、患者様の血液から抽出した「血小板血漿(PRP)」を傷んでいる部位に注射する治療法です。 一方で「幹細胞治療」は、少しの脂肪を採取し、幹細胞を抽出して数千から億の単位まで培養し、増やした細胞を患部に注射で投与します。 どちらも患者様の自然治癒力を高めて治療するもので手術や入院の必要はありません。どちらも副作用はほとんどなく、患者様の身体にかかる負担が少ない治療法です。 詳しくは、お問い合わせください。 まとめ・膝のヒアルロン酸注射が効かなくて失敗を疑う前に診療を! 膝へのヒアルロン酸注射は膝の動きを滑らかにするために有用な治療法です。 最初効果があっても、治療の過程で「効かなくなった」「失敗した」と感じる可能性があります。 治療の失敗やヒアルロン酸注射自体の問題ではなく、膝の状態が良くない恐れも考えられます。 効果が乏しいのにもかかわらず、漫然と注射を重ねるのは良くないでしょう。 現在では再生医療(幹細胞治療、PRP療法)といった先端医療も考慮できます。 ヒアルロン酸の注射の効果が以前に比して減ったように感じている場合、専門家に相談し、適切な治療に切り替えを検討してはいかがでしょうか。 再生医療は、先端医療であるため厚生労働省から認められている限られたクリニックでしか受けられない治療法です。 手術も入院も避けられる身体にやさしい治療法なので、気になった方は気軽にお問い合わせください。 膝のヒアルロン酸注射でよくある質問 Q.ヒアルロン酸注射に副作用はないの? A.ヒアルロン酸注射による副作用は「まったくない」とは断言できません。 ヒアルロン酸注射をしたあと、起こる可能性がある副作用は以下の通りです。 ・内出血 ・むくみや腫れ ・かゆみ ・チンダル現象 ・血管閉塞 など 上記のような副作用が起こっても、時間経過とともに回復するケースが大半です。 ただし、副作用は放置せずヒアルロン酸注射をした医療機関で専門的なケアをしてもらうのをおすすめします。 Q.何度も打ち続けるとどうなるの? A.ヒアルロン酸注射を何度も打ち続けると、ヒアルロン酸の吸収力が低下する可能性があります。 ヒアルロン酸は膝を含めた関節部分の潤滑油として働いているので、補充する目的で注射治療を施します。 しかし、初めてヒアルロン酸注射をした方は、複数回注射をしている方より吸収が早い傾向にあるので、次第に「失敗した」と捉えてしまうでしょう。 あくまで一時的な治療になるので、膝の痛みが続く方は別の治療法を検討しましょう。 Q.痛みを感じる場合失敗を疑うべき? A.ヒアルロン酸注射は、膝に注射を刺す痛みになりますが、血管注射とは異なります。 注射針を刺した後にヒアルロン酸を注入するので、人によっては痛いと感じる方もいます。 ヒアルロン酸注射をする前に麻酔テープやクリームを塗る方法もあるので、少しでも心配な方は事前に相談しておきましょう。 とくに変形性膝関節症が重度な方は、関節に注射針を刺すのが困難なケースもあります。 副作用として痛みを感じる可能性もあるので、我慢せず医師に相談するのをおすすめします。 ▼以下もご参照ください
2022.06.30 -
- ひざ関節
- 変形性膝関節症
- 半月板損傷
- 靭帯損傷
- 関節リウマチ
- 膝の慢性障害
膝の水が溜まって痛みがある。 溜まっている膝の水を、できるなら自分で抜きたい。 膝に溜まった水が気になり、抜く方法を知りたいと考えていませんか。しかし、膝の水を抜くのは癖になってしまうという話を聞いて、不安になっている方もいるかもしれません。 膝の水を抜く方法は「病院」と「セルフケア」で2種類ありますが、自分でできるストレッチやマッサージは負担軽減の側面が大きいため、根本的な改善に至らないこともある点には注意が必要です。 この記事では【医師監修】のもと、病院で行われる膝の水を抜く処置の具体的な流れや注意点、そしてご自身でできるストレッチ・マッサージといったセルフケア方法を詳しく解説します。 「癖になるって本当?」「自分でできることはないの?」といった疑問にもお答えしていきますので、あなたの膝の悩みを解消するための一歩として、ぜひ最後までお読みください。 また、リペアセルクリニック公式YouTubeでも「膝の水を抜く方法」について詳しく解説していますので、あわせてご参考ください。 病院で膝の水を抜く方法 膝の水を抜く方法のひとつとして、病院での処置をイメージする方も多いでしょう。 本章では、病院での処置や注意点について解説します。本章を参考に膝の水を抜くかどうかを検討してください。 処置には注射器を使う 病院では主に整形外科にて、注射針を関節に刺して膝の水を抜く「関節穿刺」を行う場合があります。(文献1) 膝の水の正体は「滑液(かつえき)」です。滑液が膝に溜まることで関節を圧迫し、膝の痛みを悪化させる可能性があります。そのため、膝の水を抜くと症状の緩和が期待できます。 膝の水を抜く際、注射針を刺した直後以外に激しい痛みを伴うケースは稀です。ただし人によっては痛みが気になる方もいるため、処置後に違和感がある場合は、担当の医師に相談しましょう。 症状に応じてヒアルロン酸を注入する 膝の水を抜いた後や変形性膝関節症では、症状を和らげる目的でヒアルロン酸を注入することがあります。通常、週に1度あるいは数週間に1度の頻度でヒアルロン酸を注入し、効果がみられれば継続します。 病院でのヒアルロン酸の注入は保険適応になるケースが多いため、治療費を抑えられるメリットも期待できるでしょう。 ヒアルロン酸の注入は一時的に痛みや炎症を抑える効果がありますが、持続的ではないため定期的な通院が必要です。 また、根本的な原因疾患の治療でないため、医師の指示に従いリハビリや運動療法など根本的な原因を改善する治療と並行しましょう。 病院で膝の水を抜いた直後は安静にする 病院で膝の水を抜いた直後は、安静にして過ごすように指導されます。処置を行った当日は、以下の2点は行わないように注意しましょう。 激しい運動 入浴 また、処置の後には以下の合併症のリスクがあります。 合併症 症状 感染症 注射部位の腫れや熱感、痛みが長時間続く、または症状の悪化 出血 注射部位を圧迫しても止血しない 上記のような症状があらわれたら、早めに受診するようにしましょう。 膝の水を抜いた後の注意点について詳しく知りたい方は、下記の記事も参考にしてください。 自分で膝の水を抜く方法は?ストレッチやマッサージ方法を紹介 病院で処置してもらう以外にも、自分でストレッチやマッサージを行って膝の水を抜くことも可能です。 本章では、セルフケアで膝の水を抜く方法と注意点を解説します。 「できるなら自分で膝の水を抜きたい」という方は、本章を参考に、ストレッチやマッサージを行ってみましょう。 ①パテラセッティング:膝のお皿周りの筋肉を刺激する パテラセッティングは、膝を支える重要な筋肉である太もも前側(大腿四頭筋)を、比較的膝関節に負担をかけず安全に鍛えることができる基本的な運動です。 この運動は、膝関節自体を大きく動かさずに大腿四頭筋を刺激できるため、膝に痛みがある場合でも比較的行いやすいトレーニングです。 膝のお皿(膝蓋骨)が少し上に動くのを確認しながら行うと効果的です。 ② 太もも前側(大腿四頭筋)のストレッチ:膝を支える筋肉の柔軟性を高める 膝の曲げ伸ばしに大きく関わる太もも前側の筋肉(大腿四頭筋)を伸ばし、柔軟性を高めることで膝への負担を軽減するストレッチです。 膝自体に痛みがある場合は、曲げる角度を調整するか、このストレッチを控えてください。 筋肉が温まっているお風呂上りなどに行うとより効果的です。 ③ お尻周りのストレッチ:股関節から膝への負担を軽減する お尻周りの筋肉(殿筋群)の柔軟性を高めることで股関節の動きをスムーズにし、結果的に膝への負担を軽減する効果が期待できるストレッチです。 股関節や膝に痛みがある場合は、無理のない範囲で行いましょう。 デスクワークの合間などにも手軽に取り入れやすいストレッチです。 ④ 膝周り・太もものマッサージ:血行を促進し筋肉をほぐす 膝周りや太ももの筋肉の緊張を和らげ、血行を促進することで、膝の不快感の軽減や動きの改善をサポートするマッサージです。 マッサージは、筋肉がリラックスしている入浴中や入浴後に行うのが効果的です。 オイルやクリームを使うと滑りが良くなり、肌への負担も軽減できます。 注意点:痛みや違和感がある場合は無理に動かさない 痛みや違和感があるときは、炎症が起こっているサインです。 むやみに触ると悪化する可能性があるため、ストレッチやマッサージなどのセルフケアはおすすめできません。無理に動かさず、早めに医療機関へ行きましょう。 マッサージやストレッチは血の巡りをよくする効果が期待できますが、誤った方法で無理に行うと、症状が悪化する恐れもあります。 また、痛みを感じるときは、膝に負担をかけないよう歩行や荷物の持ち運びなどの動作にも注意しましょう。 膝の水が溜まる原因は「炎症による関節液の過剰分泌」 膝の水が溜まる原因は、炎症反応によって「関節液」が余分に分泌されるためです。 関節液は、関節がスムーズに動くための潤滑油のような役割をしています。関節液は常につくられながら吸収され、一定量になるよう調整されています。 しかし、なんらかの疾患によって炎症が起こると、いつもより早いペースで関節液がつくられ、膝の水が溜まります。(文献2) 膝に水が溜まる原因の病気は、以下のとおりです。 半月板損傷 変形性関節症 靭帯損傷 痛風、偽痛風 関節リウマチ 骨折 感染や外傷 これらの病気になると膝に水が溜まりやすくなります。膝の水を根本的に改善するには、水を抜く処置をして痛みを緩和しつつ、原因となる病気を治療することが大切です。 膝に水が溜まる原因についてもっと詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。 まとめ|膝の水を抜くなら医療機関に相談しよう 今回の記事では膝の水を抜く方法やセルフケアを中心に解説しました。 症状が出現した際に、自己判断で放置したり誤ったセルフケアを行ったりすると、悪化する可能性があります。膝の水を適切な方法で抜きたい場合は、医療機関に相談しましょう。 また、当院「リペアセルクリニック」では、人体に元々ある幹細胞を活用した「再生医療」による膝の痛みや変形性膝関節症の治療が可能です。 「メール相談」や「オンラインカウンセリング」も実施しているので、気になる方はぜひ当院までご連絡ください。 膝の水に関してよくある質問 膝の水を抜くと癖になりませんか? 膝の水を何度も抜くのが原因で、癖になるわけではありません。 膝の水を抜いても再び溜まってしまうのは、関節に炎症が起こっている根本的な原因の病気が改善されていないためです。 原因の病気として、半月板損傷や変形性関節症などが知られています。痛みを和らげるためには、原因の病気の治療をしながら膝の水を抜くことも大切です。 膝の水は自然に抜けますか? 稀に自然治癒する場合もあります。長期期間放置しても、必ず自然治癒するわけではありません。 放置すると関節が固まって動きにくくなった「拘縮状態」に陥るリスクもあります。 拘縮状態になると膝の曲げ伸ばしが辛くなり、日常生活に支障をきたす可能性もあります。そのため、1カ月以上膝の水の溜まりを放置するのはおすすめできません。 膝の水を自然に抜けるまで長期間待たずに、早めに受診するようにしましょう。 参考文献一覧 文献1 水原寛康. 関節穿刺. 医学書院 医療情報サービス. 2024年10月18日. 文献2 斉藤 聖二,関節痛(炎):診断と治療の進歩1.関節の構造と関節痛(炎)の原因, 日本内科学会雑誌, 1994年, 第83巻, 第11号, p1871-1875
2022.06.29 -
- ひざ関節
- 膝に赤みや腫れ
- 膝の慢性障害
「階段を上るたびに膝が痛む」「しゃがむ動作がつらい」そんな症状で悩んでいませんか? 膝の上部に痛みを感じる大腿四頭筋腱付着部炎は、ジャンパー膝とも呼ばれ、スポーツ選手だけでなく一般の方にも多く見られる症状です。 大腿四頭筋腱付着部炎は、運動時の膝への負担が原因で起こることが多く、放置していると日常生活にも影響を及ぼします。 本記事では大腿四頭筋腱付着部炎の症状や原因、さらに大腿四頭筋腱炎との違いを詳しく解説します。 適切な対処法を見つけて、一日も早くスポーツを楽しめるようにしましょう。 また、当院「リペアセルクリニック」では大腿四頭筋腱付着部炎(ジャンパー膝)の治療も行っております。 辛い症状にお悩みの方は「メール相談」もしくは「オンラインカウンセリング」にてお気軽にご相談ください。 大腿四頭筋腱付着部炎(ジャンパー膝)の主な3つの症状 大腿四頭筋腱付着部炎(ジャンパー膝)は、膝の痛みが主な症状として現れます。 日常生活や運動時に現れる主な症状は以下の3点です。 膝の上部に激しい痛み 階段の上り下りで増す痛み しゃがむ動作で感じる鋭い痛み 本書ではそれぞれの特徴について詳しく解説いたします。 膝の上部に激しい痛みがでる 大腿四頭筋腱付着部炎の最もわかりやすい症状は、膝の上部に現れる痛みです。 痛みの特徴は、膝蓋骨(お皿)の上端部分に集中して起こります。 始めは運動時にのみ痛みを感じる程度ですが、症状が進行すると安静時でも痛みが出るようになってしまいます。 さらに、膝を曲げ伸ばしする際には痛みが強くなり、歩行困難になるケースも少なくありません。 そのため、痛みが続く場合は早めに医療機関を受診しましょう。 階段の上り下りで痛みが増す 階段の上り下りで、膝の上部に強い痛みを感じるのも、大腿四頭筋腱付着部炎の特徴的な症状です。 階段を上るときは、膝を大きく曲げる必要があるため、膝蓋骨の上部に強い負担がかかります。 最初は違和感程度でも、徐々に痛みが強くなり階段の昇降が困難になる場合も多いのです。 また、下りの際も膝を支える必要があるため、痛みを感じやすくなります。 日常生活で階段の使用が避けられない場合は、手すりを使うなど膝への負担を軽減するように心がけましょう。 しゃがむ動作で鋭い痛みを感じる 床に座る際など、しゃがむ動作で膝に鋭い痛みを感じるのも大腿四頭筋腱付着部炎の特徴です。 とくに、しゃがんだ状態から立ち上がる際に強い痛みが出やすく、重症化すると「しゃがむ動作自体」が困難になることもあります。 また、長時間のしゃがみ姿勢後には、膝の痛みや違和感を強く感じる傾向にあります。 そのため、痛みや違和感を感じた場合は無理にしゃがまず、椅子を使用するなど工夫しましょう。 大腿四頭筋腱付着部炎が発症する3つの原因 大腿四頭筋腱付着部炎の主な原因は、スポーツや運動習慣によって繰り返し膝へ負担をかけているためです。 代表的な原因として以下3つが挙げられます。 バレーやバスケなどのジャンプ競技によるオーバーユース 運動不足から急に運動を始めた 筋力の弱さや体の硬さによって膝に負担をかけた 早期発見と治療には原因を理解する必要があります。 それぞれ詳しく解説しているので、自分の生活習慣と照らし合わせながら確認してみましょう。 バレーやバスケなどのジャンプ競技によるオーバーユース バレーボールやバスケットボールなど、ジャンプ動作を頻繁に行うスポーツは、大腿四頭筋腱付着部炎のリスクが高まります。 ジャンプ競技で発症しやすい理由は、着地時に体重の何倍もの負荷が膝にかかるためです。 さらに負荷が繰り返し加わると、腱と骨の付着部に炎症が生じて痛みを引き起こします。 また、バレーやバスケのように「ダッシュやストップ」など急激な動作も、大腿四頭筋腱付着部炎が発症する原因となります。 スポーツによる膝の痛みについては、こちらの記事も参考にしてください。 運動不足から急に運動を始めた 普段から運動習慣がない状態から、突然激しい運動を始めるのも大腿四頭筋腱付着部炎の原因となります。 運動不足の状態では、筋肉や腱が十分な負荷に耐えられる状態になっていないため、急な負荷によって炎症を引き起こしやすくなります。 そのため、ランニングやジョギングを始める際は、徐々に距離や時間を増やしていくことが大切です。 まずは、軽い運動から始めて段階的に強度を上げていく意識を持ちましょう。 筋力の弱さや体の硬さによって膝に負担をかけた 大腿四頭筋の筋力不足や体が硬くなっていたりすると、膝への負担が増加して炎症を引き起こす可能性があります。 また、普段の姿勢の悪さや足の形態異常なども原因の1つとなります。 予防するには、適切なストレッチや筋力トレーニングを継続的に行うのが良いでしょう。 ジャンパー膝の治し方や症状のチェック方法については以下の記事でも詳しく解説していますので、参考にしていただけると幸いです。 大腿四頭筋腱付着部炎の診断方法 大腿四頭筋腱付着部炎の診断は、医師による問診と触診から始まります。 また、症状の程度によっては画像検査なども組み合わせながら総合的に判断するのが一般的です。 本章では、大腿四頭筋腱付着部炎における2つの診断方法について解説します。 医師による問診と触診で判断 医師による問診では、患者の症状や運動歴、日常生活の様子などを詳しく聞き取ります。 具体的には「いつから痛み始めたのか」「どのようなときに痛みを感じるのか」「他に症状はあるか」などの質問です。 また、触診にて膝蓋骨(膝のお皿)の上部を押して痛みがあるか、膝の曲げ伸ばしで痛みが増強するかなどを確認します。 問診と触診では他の膝疾患との区別も行いますので、大腿四頭筋腱付着部炎と診断された際には、適切な治療計画が立てられるでしょう。 必要に応じて超音波検査やMRI検査を行う 問診や触診だけでは症状の程度が判断しづらい場合、画像検査を行います。 代表的な検査方法が、超音波検査とMRI検査です。 超音波検査では、腱の損傷具合や炎症の状態をリアルタイムで確認できます。一方、MRI検査はより詳細な画像診断が可能です。 腱の状態や周辺組織の様子まで細かく確認できるため、的確な治療方針を立てられます。 必要に応じて検査方法も異なりますが、症状や原因を明確にできれば適切な治療へとつながります。 ジャンパー膝の診断方法については以下の記事でも紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。 大腿四頭筋腱付着部炎の治療法とは? 大腿四頭筋腱付着部炎の治療には、症状の程度や原因によってさまざまです。主な治療法は以下の3つです。 安静・冷却の保存療法 手術療法 PRP療法など再生医療 本章を参考に、大腿四頭筋腱付着部炎における治療法の選択肢を把握しておきましょう。 安静・冷却の保存療法 大腿四頭筋腱付着部炎の初期治療では、保存療法から開始するのが一般的です。痛みを感じる部分を休ませ、患部を冷やすことで、炎症を抑える効果が期待できます。 具体的には、1日3回程度の冷却と、ジャンプや走るなどの激しい運動を控えることがポイントです。 また、医師の指導のもと消炎鎮痛剤の服用や湿布の使用も効果的でしょう。 症状が落ち着いてきたら、ストレッチや軽い運動から徐々に活動量を増やしていきます。 手術療法 保存療法で改善が見られない場合や、重症度が高い場合には手術を検討することもあります。 腱組織の縫合や骨からの剥離、再固定などの処置を行い、損傷した腱組織の修復や付着部の状態改善を目指します。 手術を受ける場合は、重症度や術後の経過、リハビリの進行度によって変わるものの、1〜2週間ほどの入院が必要になるでしょう。 また、退院後も医師の指示に従ってリハビリを行い、スポーツの復帰までには3〜6カ月かかる可能性もあります。 PRP療法など再生医療 近年注目を集めているPRP療法は、患者さん自身の血液から作った血小板濃縮液を患部に注入する治療法です。 従来の治療で改善が見られない場合の新たな選択肢として期待されています。 血小板には成長因子が含まれており、組織の修復や再生を促進する効果があります。 そのため、腱の損傷部位に直接注入すると、自然治癒力を高める働きが期待できるのです。 ただし、PRPの治療効果については、まだ研究段階の部分も多く、保険適用外の治療となります。 費用面や治療回数など、医師とよく相談しながら検討してみてください。 また、当院でも行っている再生医療については以下の記事でも詳しく紹介しています。 まとめ|大腿四頭筋腱付着部炎は正しいケアで早期回復を目指そう 大腿四頭筋腱付着部炎(ジャンパー膝)はバレーボールやバスケットボールなど、ジャンプの多いスポーツで起こりやすい症状です。 膝上部の痛みや階段での違和感、しゃがむ動作での痛みなど特徴的な症状が多く見られます。 主な原因は、スポーツでのオーバーユースや急な運動開始、筋力不足などさまざまです。 早期発見と適切な治療が回復への近道となりますので、痛みを我慢せずに早めに医療機関を受診しましょう。 また、当院「リペアセルクリニック」では再生医療治療も行っております。ジャンパー膝の症状でお悩みの方は「メール相談」もしくは「オンラインカウンセリング」にてお気軽にご相談ください。 大腿四頭筋腱付着部炎に関してよくある質問 大腿四頭筋腱付着部炎と大腿四頭筋腱炎の違いはなんですか? 大腿四頭筋腱付着部炎は、膝蓋骨上部の付着部に炎症が生じる症状です。 一方、大腿四頭筋腱炎は、太もも前面にある腱全体に炎症が起こる状態を指します。 膝蓋骨上部に痛みが出る大腿四頭筋腱付着部炎に対し、大腿四頭筋腱炎は、太もも全体に広がる痛みや違和感が特徴です。 治療方法は似ていますが、それぞれの症状に合わせた適切なケアが必要になるでしょう。 大腿四頭筋腱付着部炎の全治期間はどれくらいですか? 症状の程度や生活スタイル、治療方法によって回復期間は大きく異なります。 一般的な目安として、軽症であれば数週間、手術が必要な重度の場合は3〜6カ月程度の治療期間が必要です。 ただし、完全に無理なく運動できるまでには、さらに時間がかかる場合もあります。 焦って早期復帰すると再発のリスクが高まるため、医師の指示に従い段階的なリハビリを行いましょう。 大腿四頭筋腱付着炎の場合、サポーターはどのように選べばいいですか? サポーターは、膝蓋骨上部をしっかり固定できるタイプで、素材は通気性が良く長時間の使用でもムレにくいものがおすすめです。 サイズは膝周りをメジャーで測り、適切なものを選択します。きつすぎると血行不良の原因になり、緩すぎると効果が期待できません。 また、活動内容に応じて固定力の異なるタイプを使い分けることで、より効果的なサポートが可能になるでしょう。 また、以下の記事でもサポーターの選び方や注意点を解説していますので、ぜひ参考にしてください。 当院では大腿四頭筋腱付着部炎の治療を行っておりますので、辛い症状でお悩みの方は「メール相談」もしくは「オンラインカウンセリング」にてお気軽にご相談ください。
2022.06.20 -
- ひざ関節
- 変形性膝関節症
- 膝の内側の痛み
- 膝の慢性障害
鵞足炎と変形性膝関節症は、膝の似たような部位に痛みを引き起こしますが、発症の原因や症状の進行度が異なります。 鵞足炎は主に筋肉の炎症によるもので、変形性膝関節症は軟骨がすり減ることで発症する疾患です。 適切な治療を進めていくためには、それぞれの違いを理解しておくことが大切です。 本記事では、鵞足炎と変形性膝関節症の違いをわかりやすく解説します。セルフチェック方法や具体的な治療法も紹介しているので、参考にしてみてください。 鵞足炎と変形性膝関節症の違い まずは、「鵞足炎」と「変形性膝関節症」がどのような疾患なのかを確認しましょう。それぞれの特徴を理解した上で、両者の違いを詳しく見ていきます。 鵞足炎とは|膝付近の鵞足部で起こる炎症 膝の内側にある鵞足部で発生する炎症が、鵞足炎です。 過度のスポーツ活動や運動をすると、膝の負担が増え、炎症が生じやすくなります。 この炎症は主に、鵞足部にある「滑液包」もしくは筋肉で起きており、膝を酷使することで発症しやすくなります。 主な症状は以下のとおりです。 膝関節の少し下に圧痛がある 関節部分の腫れを伴うことがある 骨の変形は基本的には認められない のちほど解説する治療法を進めれば、症状の軽減や再発予防が可能です。 変形性膝関節症とは|膝軟骨のすり減りによって発症する疾患 膝の軟骨がすり減ることで発症する疾患が、変形性膝関節症です。 加齢や肥満が影響しやすく、関節に強い痛みを引き起こす病気です。 症状が進むと膝の動きに支障をきたし、日常生活にも影響を与えます。 主な症状は以下のとおりです。 階段の昇り降りで膝に痛みがある 膝関節が強ばり違和感が増す 関節が変形し硬くなって曲げ伸ばしに支障をきたす 発症の原因は加齢や肥満以外に、靱帯損傷や半月板損傷、骨折などの外傷による影響も考えられます。 進行すると平地での歩行にも痛みを伴うほか、化膿性関節炎の後遺症として発症する場合もあるため、早期治療が大切です。 なお、変形性膝関節症の治療法には「再生医療」の選択肢が挙げられます。損傷を起こしている膝関節に幹細胞を注入するだけで、傷ついた組織の再生に導きます。 再生医療について詳しく知りたいという方は、無料のメール相談、オンラインカウンセリング も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。 【関連記事】 変形性膝関節症の初期症状とは?原因や治療方法もわかりやすく解説 変形性膝関節症の原因、スポーツから発症するリスクについて 鵞足炎と変形性膝関節症の違いを表で比較 鵞足炎と変形性膝関節症は、どちらも似たような部位に痛みを生じるため、混同されやすい疾患ですが、発症の原因や症状、治療方法には違いがあります。 以下の表に鵞足炎と変形性膝関節症の違いをまとめました。 鵞足炎 変形性膝関節症 原因 筋肉の炎症 ・軟骨のすり減り ・加齢 ・肥満 など 発症部位 膝関節の内側付近(鵞足部) 膝関節 主な症状 ・膝関節の少し下に圧痛・関節部分の腫れ ・骨の変形は基本的に認められない ・膝関節の違和感や強ばり ・階段の昇り降りでの痛み ・関節の変形による可動域の狭まり 主な治療 ・運動制限(膝のオーバーユースを避ける) ・足のねじれ調整 ・体重管理 ・筋力トレーニング ・鎮痛剤、湿布 ・関節内の水を抜く 予防法 過度な運動を避け、膝の負担を軽減する ・体重を増やしすぎない ・膝周囲の筋力を維持する 膝の痛みを感じた際は、それぞれの特徴を理解し、適切な対処を心がけましょう。 鵞足炎と変形性膝関節症のセルフチェック表 ここでは「鵞足炎」と「変形性膝関節症」それぞれのセルフチェック表を紹介します。 当てはまる項目が多い場合は、各疾患を発症している可能性を視野に入れましょう。 【鵞足炎のセルフチェック表】 階段の上り下りで膝の内側に痛みを感じる 正座やあぐらをかいたときに痛みが強くなる 安静時よりも運動後に痛みが増すことが多い 膝を90度以上曲げたり、完全に伸ばしたりした際に痛みが出る 膝関節そのものに腫れはないが膝の内側が腫れぼったく感じる 膝の内側を押すと痛みを感じる(とくに膝の内側5~7cmほど下の部分) 膝を曲げる動作(踵をお尻に近づける)を行った際に膝の内側が痛む 【変形性膝関節症のセルフチェック表】 膝が不安定に感じることがある 膝の周囲が腫れているように感じる 膝の形が変わってきたように見える 階段の昇り降りで膝に強い痛みを感じる 正座やしゃがむ動作が難しくなっている 朝起きたときに膝がこわばることがある 歩き始めや椅子から立ち上がる際に膝が痛む 膝を動かしたときに痛みや軋むような感覚がある 長時間座った後に立ち上がると膝に痛みを感じる 体重が増加して膝への負担が大きくなっていると感じる 膝の痛みは放置すると悪化する可能性があります。 セルフチェックの結果を参考にし、症状が続く場合は医療機関の受診を検討しましょう。 鵞足炎と変形性膝関節症の治療法 ここでは、鵞足炎と変形性膝関節症の治療法について解説します。 鵞足炎の治療法 変形性膝関節症の治療法 膝の痛みに対する治療の選択肢「再生医療」について 近年注目されている新しい治療法「再生医療」も紹介しているので、治療法を選ぶ際の参考にしてみてください。 鵞足炎の治療法 鵞足炎の治療には、症状の程度に応じた適切なアプローチが必要です。 初期の治療として、安静が大切です。膝に過度な負担をかけないよう、激しい運動や長時間の正座、しゃがみ込みなどの姿勢は避けましょう。痛みがあるときはアイシング(冷却)すると、炎症の軽減が期待できます。 痛みが強い場合には、抗炎症薬の服用や湿布の使用による薬物療法を取り入れます。 理学療法によるリハビリも治療の一環です。ストレッチや筋力トレーニングをすれば、膝の機能回復や再発予防につながります。 変形性膝関節症の治療法 変形性膝関節症の治療は、症状の進行度に応じて段階的に進められます。 痛みが軽く、日常生活への影響が少ない場合は、内服薬や湿布薬、消炎鎮痛剤などの服用・服薬による薬物療法が用いられます。炎症を軽減するほかの治療法には、ヒアルロン酸の注入があります。関節の滑りを良くするため、炎症が起こりにくいです。 痛みが続き、膝の動きに違和感が出始めた場合は、リハビリや装具(サポーター・インソール)を活用して膝の負担を減らします。 痛みが強く、日常生活に支障をきたす場合は、手術が検討されます。 以下は、変形性膝関節症における代表的な手術です。 骨切り手術:骨を切って膝の形を整える方法 人工関節置換術:人工の関節を置き換える方法 早期発見により、手術を回避できる可能性もあります。症状が悪化する前に治療を進めていくことが大切です。 【関連記事】 変形性膝関節症の治療は早期発見が鍵!初期症状を見逃さないために 変形性膝関節症|高齢者も知っておくべき手術の種類とそのリスク 膝の痛みに対する治療選択肢「再生医療」について 膝の治療には「再生医療」の選択肢もあります。 変形性膝関節症や半月板の損傷などに対し、手術を伴わない治療法の1つです。 再生医療における「幹細胞治療」は、自身の幹細胞を使い、損傷した組織や細胞を再生に導く方法です。 「PRP療法」も再生医療の1つで、自身の血液から血小板を取り出し、損傷部位に注入する方法です。 血小板に含まれる成長因子が炎症を抑える働きをします。 どちらも注射を打つだけなので体への負担が少なく、手術せずに治療できる可能性があります。 当院「リペアセルクリニック」では「幹細胞治療」「PRP療法」の両方の治療が選択可能です。 再生医療について詳しく知りたいという方は、当院「リペアセルクリニック」へお気軽にお問い合わせください。 まとめ|鵞足炎と変形性膝関節症の違いを知って今後の治療方針を考えよう 鵞足炎と変形性膝関節症は、どちらも膝に痛みを引き起こす疾患ですが、その原因や治療法には違いがあります。 本記事の違いを示す表やセルフチェックを参考に、疑われる疾患があれば医療機関を受診してください。 症状が軽度の場合は、安静や炎症を抑える薬の服用などの保存療法で様子を見ます。 症状が悪化し、痛みに耐えられなかったり、動きに制限が出て日常生活に支障をきたしたりすれば、手術も検討されます。 変形性膝関節症や関節リウマチなどの治療法には「再生医療」の選択肢が挙げられます。 当院「リペアセルクリニック」では、脂肪由来の幹細胞を用いた治療を行っております。患者様自身から採取した幹細胞を用いるため、副作用のリスクが少ないのが特徴です。 人工関節や手術を避けたいとお考えの方は、ぜひ再生医療もご検討ください。
2022.04.13 -
- ひざ関節
- 膝の内側の痛み
- 膝の慢性障害
鵞足炎(がそくえん)とは「鵞足(がそく)」と呼ばれる膝関節の内側より下方に位置する脛骨付近で起こる炎症です。 鵞足炎は、ランニングや坂道の上り下りなどで膝を酷使すると発症しやすくなります。 ある日突然、膝の内側が痛み出した場合、鵞足炎の可能性も視野に入れていきましょう。 本記事では、鵞足炎の症状や原因を詳しく解説します。治療法も紹介しているので、鵞足炎の疑いがある方は参考にしてみてください。 鵞足炎とは? 鵞足炎(がそくえん)とは、膝の内側下部に位置する「鵞足」に炎症が起こる疾患です。 鵞足は「縫工筋」「半腱様筋」「薄筋」という三種類の筋肉に付着している腱が脛骨にくっついている場所を指しています。 鵞足炎を発症していると膝の屈曲や股関節を内転する動きで膝に痛みを覚えます。 膝を酷使するスポーツ選手が発症しやすいといわれており、膝への大きな負荷だけでなく打撲などの外傷を原因として発症する可能性もあります。 鵞足炎の主な原因や症状 鵞足炎になってしまう主な原因や症状を解説します。 鵞足炎の原因 鵞足炎の症状 鵞足炎は、長時間のランニングや膝に負担がかかることで発症する可能性が高くなります。 初期段階では安静にしていると痛みが落ち着くこともありますが、悪化すると歩行が困難になるほどの痛みを感じるケースも。 以下では、鵞足炎の原因と症状について、それぞれ詳しく解説していきます。 主な原因 鵞足炎を引き起こす主な原因を以下にまとめました。 長距離を走ったりダッシュしたりする 不適切なトレーニングをする 運動前にストレッチを怠る 急な坂道を急激に長時間走る 肥満体形で膝に負担がかかっている このように鵞足炎という病気は、スポーツにかかわる障害として代表的な疾患のひとつです。 主な症状 鵞足炎を発症すると、初期では膝関節の内側部より5㎝ほど下方の部位が痛くなり、その部位を押すとさらに強い痛みをともないます。 また、運動時や階段昇降時に疼痛症状が悪化しやすく、さらに病状が進行すると安静時にも同部位が疼くように痛みを感じる場合もあります。 鵞足炎と似ている症状に「変形性膝関節症」という外傷があります。 以下の記事では、鵞足炎と変形性膝関節症の違いを詳しく解説しているので、ほかの外傷の可能性を視野に入れている方は、参考にしてみてください。 鵞足炎の治療期間について 鵞足炎が治るまでにかかる期間は、一般的には2週間前後です。 適切な治療とリハビリによって改善できる疾患のため、痛みがある時は安静にし、治療に専念することが重要です。 また、早期に回復させるためにも膝に痛みを感じたら早めに医療機関を受診しましょう。 以下の記事では、病院に行くべき症状やタイミングについて詳しく解説しているので合わせてご覧ください。 鵞足炎の主な治療法3つ 鵞足炎に有効な3つの治療法を紹介します。 理学療法 ステロイドによる注射治療 テーピング・サポーター 1つずつ順番に見ていきましょう。 理学療法 鵞足炎の治療で多いのは理学療法です。 理学療法ではストレッチによるケアを重点的におこなう場合があります。なぜなら、鵞足炎は太ももの筋肉が硬くなると膝の症状が悪化しやすく、ストレッチで筋肉部の緊張を和らげるのが有効だからです。 注意点としては、炎症が強くて痛み症状が顕著な時期にストレッチ運動を過剰に実践してしまうと、逆に膝の痛みが悪化する原因になりかねないとの指摘もあります。 したがって、症状がひどい際には軽めのストレッチに留めておき、十分な安静を保持して、患部のアイシングや消炎鎮痛剤の服薬などの対処策を検討していきます。 ステロイドによる注射治療 鵞足炎の治療では、滑液包の内部に少量ステロイド薬を直接的に注射する方法もあります。 ステロイドによる注射治療は、すぐに症状が軽快するケースが多く認められます。しかし、数か月経過すると膝の痛みが再燃する可能性もあります。 テーピング・サポーター テーピングやサポーターには、動きを制限させる働きがあります。安静が必要な時期に活用すれば、膝周りの動きを制限して炎症の沈静化を早められるでしょう。 テーピング・サポーターの利用は早期回復を促進する上で、有効なアイテムといえます。 スポーツや仕事をしているときに膝の内側に痛みを感じたら、弊社『リペアセルクリニックのドクター』にご相談ください。 スポーツ外傷や加齢による腱や靭帯の損傷・炎症の治療に詳しいドクターが、患者さまに合った治療法を一緒に考えていきます。 鵞足炎を早く治す方法として先端医療の再生医療を検討しよう 鵞足炎による膝下の痛みを早く治したい方は、再生医療による治療も選択肢の一つです。 再生医療とは、患者さま自身の細胞を活用して損傷した鵞足の再生・修復を図る医療技術のことです。 患者さま自身の細胞のみを使用することで、拒絶反応やアレルギーなどの副作用リスクが少ない治療法として近年注目されています。 また、手術や入院不要で治療できるため、手術を避けたい方や早く日常生活に復帰したい方にも推奨されます。 当院リペアセルクリニックの公式LINEでは、鵞足炎に対する再生医療の治療法や症例を配信しているので、ぜひご参考ください。 鵞足炎に関するよくある質問 鵞足炎に関するよくある質問と回答をまとめて紹介します。 鵞足炎を早く治す方法はありますか? 鵞足炎を早く治すためには、運動を控えて安静に過ごすのがもっとも効果的です。 炎症を起こしている状態で無理に動けば、患部に負担がかかり回復を遅らせます。 ストレッチは鵞足炎の予防や改善に効果がありますか? ストレッチは鵞足炎に有効です。 先述のとおり、鵞足炎は太ももの筋肉が硬くなると症状が悪化しやすくなります。そのため、太ももの筋肉をほぐすストレッチが 予防と改善に効果的です。 太もものストレッチには「長座体前屈」がおすすめです。 太ももの裏側が伸び、筋肉の緊張がほぐれます。 鵞足炎になってもスポーツはできる? 鵞足炎を発症している最中は、運動を控えて安静に過ごしましょう。炎症が悪化して、痛みや腫れといった症状が強く現れる可能性があります。 炎症が沈静化して、症状が落ち着いたらスポーツを再開して問題ありません。ただし、急に動くと膝に負担がかかり再発リスクを伴うので、様子を見ながら少しずつ運動量を調整していきましょう。 【まとめ】鵞足炎の原因となる膝への負担を避けて日頃からケアすることが重要 鵞足炎は、マラソンや坂道の上り下りといった膝を酷使する運動で発症しやすい疾患です。 身体を動かしていて膝の内側が痛み出したら、鵞足炎の可能性を視野に入れ早めに医療機関を受診しましょう。 鵞足炎は再発しやすい疾患ともいわれているため、担当医師や理学療法士の指導や助言のもと、焦らず治療を進めていく姿勢が大切です。 「膝の内側が痛み出したけど、どの医療機関を受診すればいいのかわからない…」という方は当院『リペアセルクリニック』にご相談ください。 スポーツ外傷に詳しいドクターが、患者さまの状態や症状に合った治療法を一緒に考えていきます。
2022.02.16 -
- ひざ関節
- 下肢(足の障害)
- 膝の外側の痛み
- 膝の慢性障害
- スポーツ外傷
スポーツや運動をする際に、走ったりジャンプをしたりする動きは膝に大きな負担をかけます。膝への負荷が長く続くと、靭帯や腱の組織が損傷して炎症を起こし、痛みを引き起こす可能性が高まります。 このような膝の痛みは、いわゆるスポーツ障害の一種で「膝の慢性障害」です。運動による膝の使い過ぎが原因となるため、スポーツによる「使い過ぎ症候群」とも呼ばれています。 今回は、膝の使い過ぎによって発症する慢性障害の症状と対処法について詳しく解説します。スポーツによる膝の痛みを抱えている方は、ぜひ参考にしてください。 スポーツによる膝の痛みを引き起こす3つの要因 スポーツによる膝の痛みは、軽度であれば、通常通りトレーニングやプレーできるため、大きな影響はないでしょう。しかし、症状が進行すると常に膝が痛むようになり、プレーに支障をきたすようになります。 さらに重症化してくると、運動が出来なくなったり、靭帯や腱が断裂をしたりするなど、スポーツによる膝の慢性障害につながるため注意が必要です。 スポーツによる膝の痛みは、主に3つの要因があります。 身体要因 環境要因 トレーニング要因 以下で、それぞれ詳しく見ていきましょう。 1.身体要因 スポーツによる膝の痛みを引き起こす要因の一つが、身体要因です。 太ももやふくらはぎなど、膝を支える筋力が不足していると、膝にかかる負担が大きくなり、痛みを引き起こしやすくなります。また、筋肉のバランスが悪い場合や身体の柔軟性が不足している場合にも、膝に不均衡な力がかかったり、動きを制限したりする原因になります。 2.環境要因 スポーツによる膝の痛みは、環境要因によって引き起こされるケースも少なくありません。主な環境要因として考えられるのが、足に合わない靴や地面の硬さなどです。 たとえば、不適切な靴を履いていると足の動きが不自然になり、膝への負担が増加します。また、外でジョギングやランニングをする際、地面が硬すぎると膝への衝撃が大きくなり、柔らかすぎると足が沈んで膝に過度な負担がかかってしまいます。 3.トレーニング要因 トレーニング要因も膝の痛みを引き起こす原因の一つです。運動やトレーニングにおける過度な負荷や不適切な練習方法などによって、膝に痛みが生じるケースです。 たとえば、トレーニング量が多すぎたり、体力や技術に合わない運動をしたりすると、膝にかかる負担が蓄積されやすくなります。適切な休養を設けずに連続して運動すると、膝の筋力の回復を妨げ、慢性障害を引き起こすリスクを高めます。 なお、膝の痛みは、それぞれの要因が複合的に影響して引き起こされるケースがほとんどです。そのため、スポーツや運動をする際は、適切な休養を取りながら、膝に負担がかかりすぎないための配慮が必要です。 スポーツによる膝の痛み|代表的な4つの慢性疾患 前述の要因により引き起こされる、スポーツによる膝の慢性障害の代表的な症状として、以下の4つが挙げられます。 鵞足炎 大腿四頭筋腱付着部炎 膝蓋腱炎 腸脛靭帯炎 それぞれの症状は、ひざ関節の外側や内部で生じるもので、特定の動きにより発症しやすくなります。 1.鵞足炎 鵞足(がそく)とは、ひざを曲げる筋肉や腱が付着する骨の部位のことです。とくに、ランニングや急な方向転換、足を後ろに蹴り出す動作などを繰り返すことで、鷲足がすれて炎症を引き起こします。 主な症状は、内側膝部の痛みや曲げるときの違和感などです。長時間または高頻度で膝に負担をかけるような動作を続けていると、鷲足炎を発症するリスクが高まります。 ▼ 鵞足炎の治療法を詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。 2.大腿四頭筋腱付着部炎 大腿四頭筋腱とは、膝の前面から膝蓋骨(膝の皿)を通って、膝の下部に付着する筋肉の腱です。大腿四頭筋腱付着部炎は、膝関節の外側の炎症によって症状が現れます。膝の前面に痛みを感じるほか、膝を屈伸する際に痛みが強くなる傾向です。 大腿四頭筋腱付着部炎は、バレーボールやバスケットボールなどのジャンプ動作やジョギングなど、膝に衝撃が加わる動作を繰り返すことで発症しやすくなります。 ▼ 大腿四頭筋腱付着部炎の治療法については、以下の記事で詳しく解説しています。 3.膝蓋腱炎 膝蓋腱炎は、膝蓋骨(膝の皿)の下部からすぐ下の靭帯にかけて炎症が生じる疾患です。バレーボールやバスケットボールなど、ジャンプ動作の繰り返しが多いスポーツで発症しやすいとされています。 主な症状は膝蓋骨の下部の痛みで、とくにジャンプをした後やランニング後に痛みが強くなることが特徴です。また、膝を屈伸する動作でも痛みを感じることがあります。 ▼ 膝蓋腱炎について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。 4.腸脛靭帯炎 腸脛靭帯は、膝の外側を通る大きな靭帯で、太ももの筋肉と膝をつなぐ役割を担っています。腸脛靭帯炎は、長距離のランニングや長時間の膝の屈伸運動などによって、腸脛靭帯が外側の骨と擦れ合って炎症を起こし、発症する疾患です。 膝の外側に痛みを感じ、ランニング後や歩行後には痛みが強くなることもあります。また、症状が進行すると歩行に支障をきたす場合があるため注意が必要です。 ▼ 腸脛靭帯炎を早く治す方法を詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。 スポーツによる膝の痛みに対する再生医療の可能性 スポーツによる膝の痛みの治療法は、疾患の種類や程度によって異なります。膝の痛みに対する治療法として、主に以下のような選択肢があります。 手術療法 物理療法 リハビリテーション 再生医療 物理療法で効果が得られない場合に、手術に代わる治療法として注目されているのが再生医療です。再生医療とは、自然治癒力を最大限に引き出すための医療技術です。自己脂肪由来幹細胞の投与によって、膝の痛みに対する治療効果が期待できます。 リペアセルクリニックでは、再生医療による膝の痛みの治療が可能です。メール相談やオンラインカウンセリングも実施しているので、治療法でお悩みの方はぜひ気軽にご連絡ください。 スポーツによる膝の慢性障害への対処法 スポーツによる膝の慢性障害への対処法としては、症状が出るのを予防したり、発症してしまった症状を改善したりすることが重要となります。そして、膝の痛みを予防するためには、自己対処も必要です。 以下で、スポーツによる膝の慢性障害への代表的な対処法をまとめているので、ぜひ参考にしてください。 ストレッチ 体の柔軟性を高めるために、運動開始前には十分なストレッチを行うことが大切です。運動前に体の筋を十分伸縮させて筋肉の緊張をほぐすことで、運動による膝への衝撃を和らげられます。また、ストレッチによって関節の可動域を広げることで、ケガのリスクを減らせます。 なお、膝に痛みを感じているときは、できるだけ足を伸ばしたり、痛みが強くなる前にストレッチを終えたりするなど、無理なく行うことが大切です。 アイシング 運動後に膝の痛みや違和感を感じたときは、アイシングが効果的です。氷や水などで膝を局所的に冷やすことで、急性炎症を抑えられます。冷却効果によって血流が制限されると、炎症が鎮まって痛みの軽減につながります。アイシングは15分程度、痛みが強い場合には数回に分けて行うと良いでしょう。 なお、膝を冷やすときは直接肌に氷を当てないよう、タオルに包んだり専用のアイシングバッグを使用したりしてください。また、過度に冷やしすぎないように注意しましょう。 筋トレやリハビリテーション スポーツによる膝の痛みに対して、筋力トレーニングやリハビリテーションが必要になるケースもあります。膝周りの筋力を強化すると、効率的に回復を目指せるほか、再発防止にもつながります。 膝の慢性障害を発症してしまったら、適度に休憩を取ったり、強度の低いトレーニングに変更したりして、調整することが大切です。また、症状が重い場合には、リハビリテーション専門のトレーナーや理学療法士と連携しながら、トレーニングに取り組む必要があります。 まとめ・スポーツによる膝の痛みを感じたら早めに医療機関を受診しよう 健康意識の高まりとともに、趣味で競技スポーツをする方が年々増加傾向にあります。 体に過度な負担がかからない範囲で運動するのは良いでしょう。しかし、無理な運動をしたり足に合わない靴を履いて膝に負荷をかけ続けたりしていると、スポーツによる膝の慢性障害を発症する確率が高くなるため注意が必要です。 また、我慢できる程度の痛みだからといって、ストレッチや運動後のケアを怠らないよう気をつけてください。場合によっては、症状が悪化して日常生活に支障が出る可能性も考えられます。 スポーツによる膝の慢性障害は症状が進行すると、自然治癒が難しくなり、手術が必要になるケースも珍しくありません。そのため、スポーツによる膝の痛みを感じたら、できるだけ早めに医療機関に相談しましょう。 リペアセルクリニックでは、メール相談やオンラインカウンセリングを実施しています。スポーツによる膝の痛みでお困りの方は、ぜひ気軽にご相談ください。 ▼ 症状別に考えられる膝の病気について詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。
2022.02.10 -
- ひざ関節
- 変形性膝関節症
- 膝の慢性障害
変形性膝関節症を罹患している患者様は、大きく分けて「保存療法」と「手術療法」の2つが選択肢になります。 保存療法にはリハビリテーション、装具療法、薬物療法などを組み合わせて行います。 手術療法は保存療法では効果が得られない場合に検討する選択肢です。 中でも「高位脛骨骨切り術」が手術療法の選択肢に挙げられます。 しかし高位脛骨骨切り術を受ける患者様の中には「術後の後悔は避けたい」と考える方もいるでしょう。 そこで今回は、現役医師の立場から高位脛骨骨切り術が適応になる症例やリハビリ内容などを詳しく解説していきます。 術後の後悔を減らすためにも、手術自体のメリット・デメリット、入院期間などもまとめました。 高位脛骨骨切り術とは 高位脛骨骨切り術とは、O脚変形のために内側部(内側大腿から脛骨関節)に偏った過重なストレスを、自分の骨を切って少し角度を変える処置が施される手術です。 「HTO手術」とも呼ばれており、内反変形されたO脚からX脚にするのを目的にしています。 膝の内側部に過度の負担となっていた外力のベクトルを比較的きれいな軟骨の存在する外側部(外側大腿から脛骨関節)に移動できる手術です。 高位脛骨骨切り術により、患者様の膝関節が温存できるため、スポーツや、農業などの仕事へ復帰できる方が多くいます。 仕事復帰できるメリットがある一方で、ある程度の入院期間や継続的な痛みを感じ「後悔した」と感じる患者様がいるのも実情です。 高位脛骨骨切り術の対象になる「変形性膝関節症」は、早期の発見と治療が大切です。 以下の記事では、初期症状を見逃さないためのポイントをまとめています。 高位脛骨骨切り術が適応になる症例や手術方法 高位脛骨骨切り術が適応になるのは、主に「変形性膝関節症」を罹患している患者様です。 過度なスポーツ活動により関節に対して大きな負担がかかる「膝内反モーメント(ひねり)」が増大した結果発症します。 「運動の前後には入念なストレッチを」と言われる要因でもあり、股関節から足の甲までを一直線に結んだ「荷重線」が影響しています。 荷重線が膝の内側を通っているので、膝の内側に荷重がかかり過ぎて膝に障害が起こり、変形性膝関節症が発症するのです。 ここからは変形性膝関節症の患者様を含め、具体的に高位脛骨骨切り術が適応な患者様と適応外のケースを紹介します。 手術を受ける対象者 高位脛骨骨切り術が対象になる方は、主に以下のケースです。 50歳〜75歳の方 変形性膝関節症を認める症例の中でも中程度の変形を呈する方まで 若年者でも症状が強ければ高位脛骨骨切り術を行って、下肢機能軸や脛骨近位の内反角を正常化する手術になる可能性もあります。 また、人工膝関節置換術を行う患者様もいます。 骨と人工の異物を接合する都合上、ゆるみなど再手術が必要になる場合があり、初回の手術よりも再手術は、手技的に難しくなります。 再手術のリスクを避けるためにも、65歳よりも若い方には高位脛骨骨切り術が推奨されているのです。 変形性膝関節症の症状が中程度までで、運動や肉体を使う仕事を続ける方は、本手術治療を受けるのがおすすめです。 以下の記事では変形性膝関節症で行う手術内容や費用をまとめました。 高位脛骨骨切り術以外の手術法や費用が気になる方は、あわせてご覧ください。 手術が適応外の方 高位脛骨骨切り術が適応外になる方は、以下のケースが挙げられます。 適応外の方 理由 変形性膝関節症の程度が末期の方 高位脛骨骨切り術の効果が出にくいため 関節の外側に痛みがあるX脚の方 「遠位大腿骨骨切り術」が適応になるため 靭帯を損傷している方 膝が不安定な状態で症状が改善されにくくなるため 骨粗しょう症の方 高位脛骨骨切り術を行っても、骨の「癒合」しない、または遅れる可能性があるため 75歳以上の方 変形性膝関節症の進行が早いため ※早期発見の場合適応する可能性あり 当院では症状にあわせた適切な治療ができるよう、メール相談やオンラインカウンセリングも実施しています。 高位脛骨骨切り術のメリットとデメリット ここからは高位脛骨骨切り術を受ける上で後悔したくない方に向け、手術自体のメリット・デメリットを解説していきます。 入院期間や術後の注意点も触れているので、ぜひ参考にしてください。 高位脛骨骨切り術のメリット 高位脛骨骨切り術のメリットは、最終手段の人工関節を使わずに「自分の関節を残したまま」で症状の改善が期待できる点です。 高位脛骨骨切り術は、O脚に変形した脚を、X脚ぎみに矯正して変形性膝関節症の進行を遅らせる唯一の術式と考えられています。 体への負担が少ない手術でもあり、手術後の日常生活に対する制限も少ないのも特徴です。 新しい手術法が開発された結果、術後早期からの歩行も可能になっています。 入院期間も従来の人工膝関節置換術と変わらず、約4~6週間が入院期間の平均です。 高位脛骨骨切り術のデメリット 従来の高位脛骨骨切り術は、骨癒合までの数カ月間、手術した足に十分な体重をかけられず、入院が長期にわたるのがデメリットでした。 仕事をしている方にとって、復帰に時間が必要な点は大きな欠点になるでしょう。 高位脛骨骨切り術の処置に伴って腓骨短縮などの合併症や有痛性偽関節(骨がくっつかず、痛みも出る)が引き起こされる点も問題視されていました。 骨が癒合するまで多少なりとも膝部の痛みが続くと言われています。 実際に術後の痛みが軽快して骨癒合が完了するまでに個人差はあるものの、約半年以上は時間がかかります。 膝機能がある程度満足が得られるレベルまで回復するためには、気苦労の多いリハビリをコツコツ、しっかり行う必要があるでしょう。 高位脛骨骨切り手術後におすすめのリハビリ法 高位脛骨骨切り術の対象な方に向け、術後のリハビリや入院期間について深掘りしていきます。 「こんなつもりじゃなかった……」と後悔したくない方は、ぜひ参考にしてください。 リハビリ内容 高位脛骨骨切り術を受けたあとのリハビリ内容は、関節の曲げ伸ばしや適度な運動など、自宅でもできる内容です。 高位脛骨骨切り術の術後1週間位から徐々に膝へ体重をかけ始めて、3週間以内には全体重をかけて歩行訓練を施行します。 術後は膝に負担をかけられないため、最初は関節の曲げ伸ばしや立ち座りから始めます。 徐々に膝の可動域や立った際のバランスを整えるため、理学療法士によるサポートを受けるのがおすすめです。 4~5週間程度で安定した歩行、階段の昇降、日常生活動作などをクリアすれば軽快退院の運びとなります。(文献1) 手術後の入院期間 高位脛骨骨切り術の入院期間は、5〜6週間程度です。 手術自体は1時間30分程度で終了し、手術当日は血栓塞栓症を予防するために「フットポンプ」を用います。 フットポンプとは、寝たままの患者様を対象に下肢静脈の血流を手助けするために用いる医療器具です。 多くの場合術後2日目でフットポンプを外し、車椅子での移動になり、徐々に松葉杖を使った歩行へ切り替えます。 術後3週目から松葉杖をつきながらの歩行が始まり、5週目を目安に松葉杖なしでの歩行練習になる流れです。 以下の記事では、高位脛骨骨切り術の入院期間やリハビリについて、より詳しく解説しています。 高位脛骨骨切り術で後悔しないためにも、手術の全体像を把握しておきましょう。 まとめ・高位脛骨骨切り術で後悔したくないなら術後のリハビリを! 変形性膝関節症は慢性疾患であり、骨肉腫などのように、命に関わる疾患ではありません。 つまり、どのような治療法を選択するかは、患者様一人ひとりが望むゴールによって変わってくるのです。 術後に多少疼痛は伴うデメリットが挙げられるため「手術をしたけれど後悔した」と感じる患者様がいるのも実情です。 一方で、自分の関節を温存して機能を維持できるため、術後の日常生活でほとんど制限がない点がメリットと言えます。 高位脛骨骨切り術で後悔しないためにも、術後のリハビリは気を抜かず適切な方法で受けるのが大切です。 高位脛骨骨切り術で後悔したくない方からのよくある質問 高位脛骨骨切り術で後悔したくないと考える患者様からよくいただく質問を3つ紹介します。 術後の痛みはいつまで続くの? 仕事復帰や運転はいつからできる? リハビリ以外で後悔しない方法はないの? 気になる点がある方は、以下でそれぞれ回答しているので、ぜひ参考にしてください。 術後の痛みはいつまで続くの? 高位脛骨骨切り術を受けたあとの痛みは、段階によって異なりますが、約3カ月ずつかかる傾向にあります。 術後最初の3カ月で高位脛骨骨切り術を施した患部が痛み、4〜6カ月はリハビリで使った筋肉が痛む可能性があります。 患者様によっては7カ月目以降で太ももやお尻などの周辺が筋肉痛を感じるでしょう。 手術で切った患部の痛みが落ち着くまでの期間は、3〜4週間程度ですが痛みの経過を見ながらリハビリを実施するのがおすすめです。 理学療法士から適切なリハビリを受け、術後の後悔を減らしていきましょう。 仕事復帰や運転はいつからできる? 高位脛骨骨切り術を受けて、仕事復帰や運転ができる目安は以下の通りです。 デスクワーク:退院後すぐ 立ち仕事:2〜3カ月 運転:松葉杖を外してから(術後2カ月程度) 患者様の体重やリハビリの進行度にもよるため、上記はあくまで目安になります。 また、高位脛骨骨切り術は術後3年目を目安にプレートを外すための手術が必要です。 「歩けるようになったから大丈夫」と捉え、負担をかけてしまう膝の回復が遅れ、後悔してしまうでしょう。 高位脛骨骨切り術で後悔しないためにも、術後の経過観察が大切です。 リハビリ以外で後悔しない方法はないの? 高位脛骨骨切り術で後悔したくない方は「再生医療」との併用をおすすめします。 そもそも高位脛骨骨切り術は、人工関節による治療を必要とするまでの期間を遅らせるのが目的です。 高位脛骨骨切り術を受けた患者様の半数以上が、15年以上も人工関節による治療をせずに済んだ結果が出ています。(文献2) しかし高位脛骨骨切り術だけでは、膝関節の環境は変えられないのが欠点でした。 再生医療を併用すれば、膝関節の環境を整えられる効果が期待できます。 治療の選択肢が増えている昨今「高位脛骨骨切り術とリハビリで改善するしかないのか……」と考える前に、整形外科でカウンセリングを受けましょう。 少しでも後悔しそうな要因を減らしたい方は、ぜひ当院へご相談ください。 参考文献 (文献1) 佐野明日香, 辻修嗣.「高位脛骨骨切り術後の理学療法-歩行時痛の改善に着目した1症例-」『第48回近畿理学療法学術大会』セッションID: 102, 2008年 https://doi.org/10.14902/kinkipt.2008.0.102.0(最終アクセス:2025年4月27日) (文献2) Michaela G, et al. (2008). Long-term outcome after high tibial osteotomy. Arch Orthop Trauma Surg, 128, pp.111–115. https://doi.org/10.1007/s00402-007-0438-0(最終アクセス:2025年4月27日)
2021.10.09