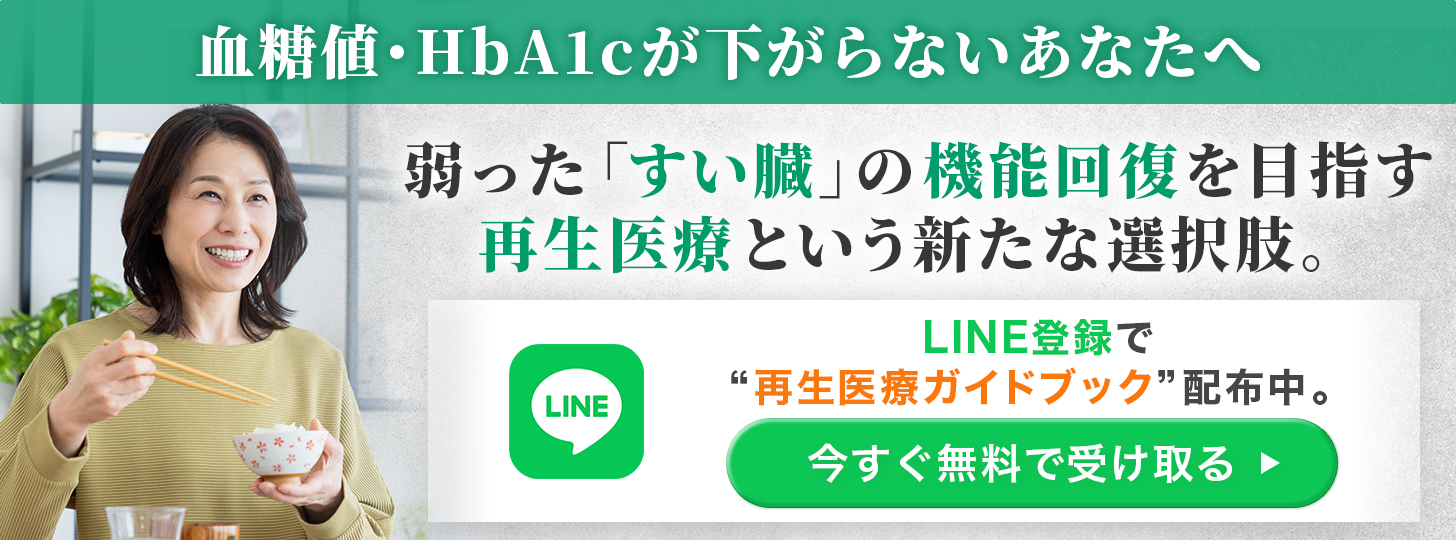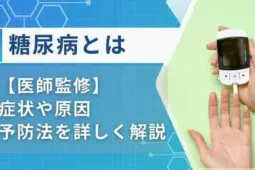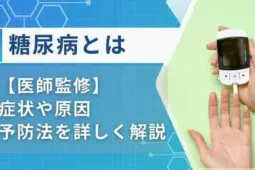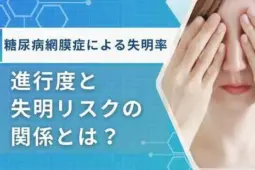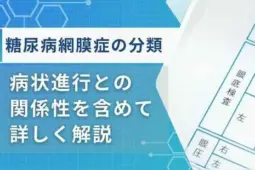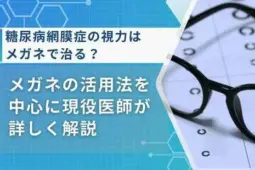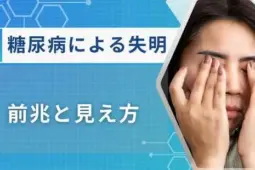- 糖尿病
- 内科疾患
糖尿病は筋トレで完治は難しくても改善する!運動療法で糖尿病を改善するには

2024年11月に発表された「国民健康・栄養調査」によれば、糖尿病の疑いが強い人は成人男性の16.8パーセント、女性は8.9パーセントにものぼります。(文献1)
糖尿病は完治しない病気であるといわれていますが、筋トレやウォーキングなどの運動を日常に取り入れることで、薬のみに頼らずとも症状を改善していくことは可能です。
この記事では、筋トレをはじめとする運動療法が糖尿病の改善につながる理由、糖尿病の方におすすめな運動方法を紹介しています。
目次
糖尿病の完治は難しいが筋トレで改善が目指せる
まず重要なポイントとして、糖尿病は完治する病気ではありません。
これは、血糖値が上昇しやすい代謝特性や加齢による生理的変化を根本的に変えることができないためです。
しかし、血糖値が上がらないよう生活習慣の見直しを続けることで、薬に頼らずに血糖値を下げ「寛解(一時的に症状が軽減・消失した状態)」を目指すことはできます。
薬に頼らない治療法には、筋トレやウォーキングなどの「運動療法」、食生活を見直す「食事療法」が主に挙げられます。
糖尿病の改善に筋トレが有効な理由
運動療法は、2型糖尿病を患っている人にとって重要な治療のひとつです。
日本糖尿病学会が発表しているガイドラインによると、運動療法を取り入れることで、以下の症状が改善するとされています。(文献2)
- 血糖コントロールの改善
- 肥満
- 内臓脂肪の蓄積
- インスリン抵抗性
- 脂質異常症
- 高血圧症
- 慢性炎症
- うつ状態
- 認知機能障害
上記は有酸素運動、筋トレ(無酸素運動)どちらを行っても得られる効果です。どちらか一方を行うより、有酸素運動と筋トレ(無酸素運動)を組み合わせることでさらに効果が上がることが報告されています。
さらに、高齢者の糖尿病患者の人は非糖尿病患者と比べて筋肉量の低下が著しいことが指摘されています。
有酸素運動の実施が困難な高齢者の人にとって筋トレ(無酸素運動)は有効な手段のひとつだといえるでしょう。
糖尿病は筋力の低下を引き起こす
糖尿病の改善に筋トレが有効な理由として、糖尿病を患っている人は非糖尿病患者と比べ筋肉量が減りやすいという点が挙げられます。
糖尿病は血糖値を下げるインスリンというホルモンの働きが弱くなることで発生します。
インスリンは血糖値のコントロールだけでなく、細胞の成長を促す特性も備えています。インスリンの働きが弱くなることによって、細胞の成長も低下し、筋肉にも影響を与えてしまうのです。
さらに、神戸大学の研究では、血糖値の上昇によって発生するKLF15というタンパク質によって筋肉の成長が抑制され、筋肉量の減少を起こしていることが明らかになりました。
健康な人は、KLF15を分解し量を減少させるWWP1というタンパクの一種が発生することで筋肉量の低下を防いでいます。しかし、糖尿病の人は血糖値の上昇によりWWP1が減少してしまうため、筋肉量が落ちてしまうのです。(文献3)
上記の理由からも、能動的に筋トレを行うことが重要であるとわかります。
体重のコントロールの必要性!肥満の悪循環を知る
糖尿病の寛解を目指す臨床試験「DiRECT」がイギリスで行われ、食事療法と運動療法をしっかり行い、体重をコントロールすることで2型糖尿病患者の半数近くは「寛解(症状が軽減・消失した状態)」を維持できることがわかりました。
では、なぜ食事療法と運動療法と体重コントロールだけで、薬物を使わず「寛解」を達成できたのかを解説します。
暴飲暴食や運動不足が続くと、全身に脂肪がたまり、肝臓にも脂肪がたまります。脂肪がたまった肝臓は働きが低下します。肝臓の働きが低下するとインスリンへの体の反応が鈍くなることがわかっています。これを「インスリン抵抗性」といいます。インスリン抵抗性が強まると、体は大量のインスリンを必要とするようになります。
すると、すい臓は「フル稼働」でインスリンをつくろうとするので、次第に疲弊してインスリンの分泌に支障をきたすようになります。インスリンの分泌が減ると、さらに肝臓に脂肪がたまるので、インスリン抵抗性がさらに強まってしまうのです。
この悪循環を断ち切るには、食生活と運動不足を改善し、脂肪がたまらないように肥満を解消する必要があります。
糖尿病の悪循環(断ち切ること)
暴飲暴食、運動不足で全身に脂肪がたまる
肝臓に脂肪がたまり、肝臓の働きが低下
インスリン抵抗性が発生:インスリンへの体の反応が鈍くなる
インスリン抵抗性が強まる:大量のインスリンが必要となる
すい臓が最大限に働いてインスリンをつくる
疲弊し、インスリンの分泌に支障をきたす
インスリンの分泌が減ると、さらに肝臓に脂肪がたまる
インスリン抵抗性がさらに強まる>ますます悪化
糖尿病の悪循環を断ち切るには肥満の解消が必要
2型糖尿病の改善には、上記の悪循環を断ち切ることが必要です。悪循環のメカニズムを知れば、「体重コントロール(脂肪を減らす)」によって症状を緩和できることが理解できると思います。
体重コントロールとは、標準体重(身長(m)×身長(m)×22)に近づけることです。
糖尿病の場合、標準体重と比べてやせている人より、太っている人のほうが問題になります。
食事量のコントロールも効果的ですが、脂肪を燃焼させるための筋肉がなければ長期的な改善は難しいといえるでしょう。
糖尿病を改善するおすすめの筋トレ方法を紹介
糖尿病の改善のために推奨されている筋トレ方法について、厚生労働省が推進している「2型糖尿病の人を対象にした運動プログラム」から抜粋して紹介します。
運動療法は主治医と相談の上で行ってください。代謝のコントロール状態や心疾患などの合併症、整形外科的疾患による運動の制限が必要な場合があります。
有酸素運動
有酸素運動はインスリンの働きを強め、糖の流れを改善してくれます。
- ウォーキング
- トレッドミル
- エアロバイク
- エアロビクス
- ヨガ
- 水中歩行
などが推奨されています。運動の頻度は週に150分以上の中等度~高強度の運動がガイドラインでは推奨されていますが、週30分~100分程度の運動でも血糖改善効果が出ていることがわかっています。(文献2)
無理のない範囲で取り入れてみてください。
有酸素運動に併せて筋トレ(無酸素運動)を行う
有酸素運動と併せて筋トレ(無酸素運動)を行うことで、糖尿病の改善効果をさらに高めることができます。
糖尿病患者の方におすすめしたいのは、大きな筋肉を鍛えるトレーニングです。
大きな筋肉として挙げられるのは「胸」「背中」「下半身」の3カ所です。ダンベルなどの重りを使用し、適切なフォームで行いましょう。
動作中に重りをあげる際は息を吐き、重りを下げる際は息を吸うと筋肉の成長に効果的です。
各部位のトレーニングでは以下の種目がおすすめです。
胸筋
- ダンベルフライ:仰向けに寝て、両手のダンベルを胸の上で開閉させる運動
- チェストプレス:仰向けで両手のダンベルを胸から上へ押し上げる運動
- 水中で腕を開閉する運動
背筋
- ダンベルローイング:前かがみになり、ダンベルを腰の高さまで引き上げる運動
- ラットプルダウン:上部のバーを肩の高さまで引き下げる運動
- バックエクステンション:うつ伏せで上半身を持ち上げる運動
下半身
- ダンベルスクワット:両手にダンベルを持ち、膝を曲げ伸ばしする運動
- レッグプレス:足で重りを押し出す運動
ダンベルを使用する運動と考えるとハードルは高いですが、自重のトレーニングでも十分効果は得られます。
ジムに行くことが困難だったり、ダンベルを持っていないという人は、ダンベルの応用として水を入れたペットボトルを使うこともおすすめです。
医師と相談し、自分に合った筋トレを選ぶ
糖尿病の改善のため運動療法に取り組みたくても、体調面の制約や時間的な余裕がない方もいるでしょう。
ある研究では短い運動時間でも血糖値の抑制は可能であるという報告が上がっています。まずは散歩や軽いストレッチなど、負担の少ない運動から始め、徐々に強度や時間を増やしていきましょう。
いきなりの高負荷な運動はけがのリスクを高めてしまうため注意が必要です。
運動を始める前には必ず主治医に相談し、ご自身の状態に適した運動の種類や強度、頻度について指導を受けることが重要です。
筋トレ以外の治療法
ここまで運動療法を中心に紹介しましたが、運動療法以外にも糖尿病の改善に効果的な治療法として食事療法があります。
また、近年は「再生医療」の注目も高まっています。それぞれの治療法についても理解を深めていきましょう。
糖尿病には筋トレだけでなく食事療法も効果的
糖尿病の改善には体重コントロールが必要ですが、運動療法だけでは十分とは言えません。適切な筋トレや有酸素運動を行っていても、食生活の改善がなければ摂取カロリーが過剰なままとなり、十分な効果が得られないことがあります。運動療法と食事管理を組み合わせることで、より効果的に糖尿病の症状を改善できます。
糖尿病患者の理想の食生活ポイント
- 糖質やカロリーの低い食事を摂る
- 1日3食、規則正しい時間に摂る
- 1日の活動量に合わせた適正なエネルギー量の食事をする
- 栄養バランスの取れた食事をする
食事量が多い人は、食事量を適正エネルギー量に調整しましょう。
1日の適正エネルギー量は、人によって異なり、「標準体重×身体活動量」で算出できます。
標準体重と身体活動量
標準体重=身長(m)×身長(m)×22
身体活動量
- 軽い労作(デスクワークが多い)25~30kcal/kg
- 普通の労作(立ち仕事が多い)30~35kcal/kg
- 重い労作(力仕事が多い)35~kcal/kg
近年糖尿病の治療として注目されている「再生医療」
再生医療とは、患者様自身の細胞から採取・培養した幹細胞を投与する先進的な医療法です。
糖尿病治療においては、自身の脂肪から培養した幹細胞をすい臓に投与することで、弱っていたすい臓の機能の改善を図ります。
すい臓が回復することによりインスリン分泌の増加、血管内の糖の吸収を促進することが可能になります。
一般的な内服治療やインスリン治療では糖尿病の進行を遅らせる効果はあるものの、根本的な回復を目指す治療ではありませんでした。
再生医療は自分自身が持つ「回復力」にアプローチする治療であるため、薬物療法とは異なった治療法だといえます。
まとめ|糖尿病は筋トレや運動療法、再生医療で改善を目指そう
「糖尿病は、一度発症すると完治しない」と、よく言われています。しかし、筋トレなどの運動療法や食事療法を通じて症状を改善することは可能です。特に2型糖尿病では、肥満や不健康な生活習慣が悪循環を生み出し、症状を悪化させることがあります。
この悪循環を断ち切るためには、食事のタイミングや、量をコントロールして、更に運動を行うことで脂肪を減少させることに取り組むことが重要です。
実行にあたっては医師の指導を受けながら、病状の管理に取り組みましょう。
また、糖尿病に対しては、運動療法の他にも「再生医療」という治療法もあります。
糖尿病に対する再生医療について詳しくは、以下のページをご覧ください。

糖尿病のお悩みに対する新しい治療法があります。
参考文献
(文献1)
厚生労働省「令和5年 国民健康・栄養調査結果の概要」 2024年
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45540.html(最終アクセス:2025年3月25日)
(文献2)
日本糖尿病学会. 糖尿病診療ガイドライン2024「第4章 運動療法」pp.67-68.日本糖尿病学会, 2024年.
https://www.jds.or.jp/uploads/files/publications/gl2024/04_1.pdf(最終アクセス:2025年3月25日)
(文献3)
Hirata Y, et al. (2019). Hyperglycemia induces skeletal muscle atrophy via a WWP1/KLF15 axis. JCI Insight, 4(4), e124952.
https://doi.org/10.1172/jci.insight.124952(最終アクセス:2025年3月25日)