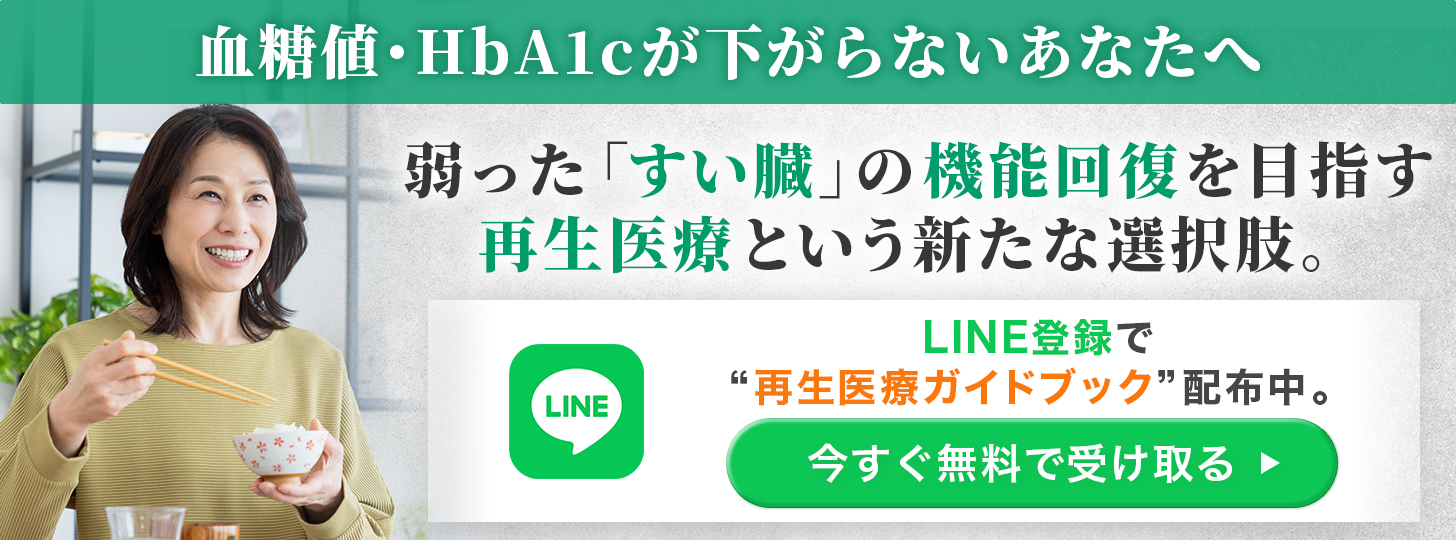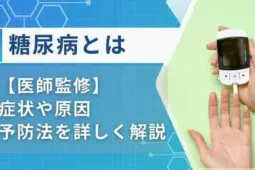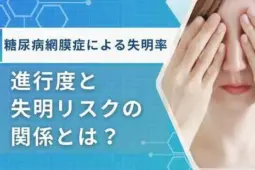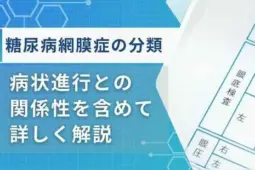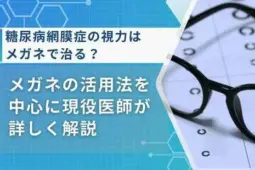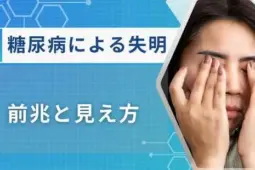- 糖尿病
- 内科疾患
【医師監修】糖尿病予防に効果的な運動3選|続けるコツや注意点も紹介
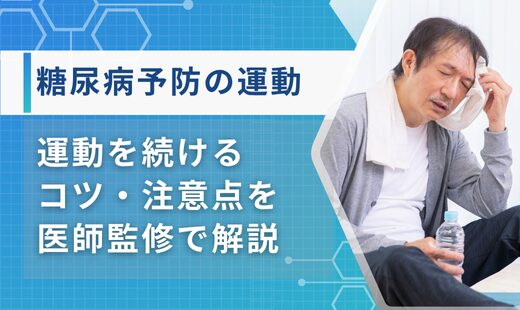
「糖尿病予防のため運動したいけれど、どのような運動をしたら良いのかわからない。」
「運動は長続きしないので、継続する方法を知りたい。」
このようにお悩みの方もいるのではないでしょうか。
糖尿病には、その発症状況から、いくつかのタイプがあることが判明しています。ただ、その中でも自己免疫の異常によって引き起こされる「1型糖尿病」は、完全に予防できる方法が発見されていません。
その一方で、日頃の生活習慣が関与している「2型糖尿病」、あるいは妊娠を契機に発症する「妊娠糖尿病」は、生活習慣やライフスタイルを見直すことで、それらの発症自体や、症状悪化を一定の割合で回避または改善できます。
そこで本稿では、この2型糖尿病について、その改善方法を記してまいります(以下に記す「糖尿病」の表記は、2型糖尿病を指すものとします)。
当院「リペアセルクリニック」の公式LINEでは、再生医療の情報提供と簡易オンライン診断を実施しております。
糖尿病について気になる症状がある方は、ぜひ一度公式LINEにご登録ください。
目次
運動が糖尿病予防に欠かせない理由
糖尿病は、規則正しい食生活はもちろんのこと、日常から意識して身体を動かすなどの運動を実践することが大切です。運動することで血液中のブドウ糖が筋肉にとり込まれやすくなり、ブドウ糖などの利用が促される結果、血糖値が下がる現象が認められます。
とくに2型糖尿病では低下したインスリン機能が改善すると言われています。
さらに運動は、加齢に伴う筋肉の衰弱を改善できるばかりか、心肺機能の向上、ストレス解消効果も期待できます。
|
運動療法の効果
|
運動を行うことで、改善はもちろん、予防にも効果的です。
|
1型糖尿病 |
治療、予防が難しい |
|---|---|
|
2型糖尿病 |
|
実施にあたっては、適宜体調に合わせて、無理をしないように継続できる運動の種類を選択するように心がけましょう。
以下、糖尿病を改善し、予防に有効な「運動に関する情報」を詳細に紹介してまいります。
【関連記事】
糖尿病は筋トレで完治は難しくても改善する!運動療法で糖尿病を改善するには
妊娠糖尿病で運動してもいい?妊婦さんが安心して取り組める運動
糖尿病予防に効果的な運動3選
2型糖尿病の血糖コントロールには、有酸素運動や筋肉トレーニング(レジスタンス運動)が推奨されています。(文献1)
運動を継続して実践すると、インスリンの働きがよくなり、血糖値を上手く調整しやすくなると考えられています。
糖尿病における運動療法は、とくに問題がなければ有酸素運動とレジスタンス運動、両方行うことが勧められていますが、まずは運動不足改善のために有酸素運動から始めると良いでしょう。
余裕が出てくれば次のステップとして、身体に負荷をかけるレジスタンス運動を検討すれば良いと思われます。
一方で、有酸素運動が難しい方は、レジスタンス運動を検討しましょう。
ここでは、糖尿病予防に効果的な運動を3つ紹介します。
①有酸素運動(ウォーキング・ジョギング・水泳等)
具体的な有酸素運動(ウォーキングやジョギング、水泳等)について、糖尿病診療ガイドライン2024では、「週に150分以上の中等以上の強度の有酸素運動を、3日以上に分けて行うこと」がすすめられています。(文献1)
さらに、「運動しない日が2日以上続かないようにする」ことも大切です。
これは通常、「糖の代謝が改善する期間」が運動してから、24~48時間程度持続することから導かれたもので、血糖値を上手く制御するためには、運動を1週間のなかで3日間は実践することが理想的だからです。
週末だけまとめて運動するのではなく、できるだけ間を空けずに週の中でこまめに体を動かすのが、糖尿病予防のコツです。
②レジスタンス運動(筋肉トレーニング)
レジスタンス運動は、以下の効果により血糖コントロールを改善します。
- 骨格筋の量や筋力を増加
- インスリン抵抗性(インスリンの効きが悪くなる)の改善
運動の頻度は週に2〜3日、できれば日をあけながら行うのがおすすめです。
腕・脚・お腹・背中など、体の大きな筋肉をまんべんなく使う運動を、5種類以上取り入れましょう(例:スクワット、腕立てふせ、腹筋など)。
最初は軽めの負荷や1セット(1回分)から始めて、慣れてきたら少しずつ回数や負荷を増やしていくと効果的です。
レジスタンス運動は、有酸素運動と同じくらい血糖値(HbA1c)を下げる効果があるという研究結果も出ています。高齢者など有酸素運動が難しい人にはおすすめできる運動です。(文献1)
さらに、レジスタンス運動には筋肉量の減少(サルコペニア)を防ぐ目的でも効果的です。
③ストレッチ(ヨガ・太極拳)
ヨガや太極拳は、激しい動きや瞬発的な運動がほとんどないため、高齢者でも取り入れやすい運動です。
研究では、これらの運動が糖尿病にも良い影響を与えることが報告されています。
ヨガは、空腹時血糖値やHbA1cを改善させるだけでなく、筋力や心肺機能を高める効果もあるとされています。
また太極拳には、血糖値の改善やバランス能力の向上がみられた研究結果もあります。
ただし、まだ研究の数は多くないため、今後さらに詳しい検証が期待されています。(文献1)
糖尿病予防の運動を続けるコツ
運動を長く続けるコツは、「最初から完璧を目指さない」ことです。
現在、運動不足だからと言って一念発起し、一気にやり始めると、疲労やケガにつながる恐れがあります。
通勤や買い物ついでに歩く「ながら運動」や、家事の合間のストレッチなど、日常生活に運動を取り入れるのもおすすめです。
まずは軽いウォーキングや筋トレを週3回など、無理のないペースで行うことを目指しましょう。
無理のない範囲でコツコツと継続することで、糖尿病予防の大きな力になります。
1型糖尿病は、インスリンを分泌する膵臓細胞が壊れてしまうことで発症するため、運動によりインスリン機能そのものの回復を期待できるような治療効果は期待できません。
しかし、運動することで心身の健全な発達やストレス解消に貢献するため、決して無駄ではありません。
糖尿病予防の運動を実施する際の注意点
糖尿病予防には、運動だけではなく、食事とのバランスも重要です。
運動と食事は、血糖値をコントロールする「両輪」です。
治療効果は、どちらか一方が欠けても十分に発揮できません。
また、運動のタイミングも重要です。
食後すぐの運動は、胃に負担がかかるため控えましょう。
食後1時間ほど経過してから行うと、食事から取り込まれたブドウ糖や脂質を効率的に利用でき、血糖値の上昇を抑える効果が期待できます。
「毎日運動しているから食事は気にしない」「食事療法をしているから運動はしなくても良い」と、どちらか片方だけを頑張るのではなく、運動・食事の両方をバランスよく取り入れて、糖尿病の予防・改善を目指しましょう。
|
運動 + 食事 = 予防、改善(どちらかに偏らないバランスが大切) |
運動だけでは防げない?糖尿病に再生医療という新しい選択肢
これまで運動や食事管理を続けてきても、どうしても血糖値が安定しないケースがあります。
そうしたときは、再生医療という選択肢があります。
糖尿病は、膵臓のβ細胞機能やインスリン分泌能の低下が関係しており、生活習慣の改善だけでは十分にコントロールできない状況もあるためです。
再生医療では、ご自身の脂肪から培養した幹細胞を投与することで、すい臓や血管の再生および修復を目指します。
糖尿病に対する当院「リペアセルクリニック」の再生医療については、以下の症例をご覧ください。
再生医療を提供する当院では、メール相談、オンラインカウンセリングを承っております。糖尿病に対する再生医療について詳しく知りたい方は、お気軽にお問い合わせください。

糖尿病のお悩みに対する新しい治療法があります。
運動で糖尿病を予防しつつ健康的な体を手に入れよう
今回は糖尿病の予防・改善に役立つ運動について詳しく紹介しました。
とくにウォーキングなどの有酸素運動は、続けやすくお勧めです。
1日8,000歩程度を目標にして、1週間に3日間以上の頻度で行うと良いでしょう。
|
運動の開始時間 |
食事後1時間程度経過してから |
|---|---|
|
効果的にするために |
運動だけに偏らない、食事療法も一体で行う |
|
運動内容 |
ウォーキング、ジョギング等の有酸素運動 |
|
回数 |
週3回を目途、間隔を3日空けない |
|
時間 |
一回当たり30分~60分程度 |
歩行運動は、時間や場所を選ばずに一人で実践できるため、忙しい方でも通勤や買い物中などに行えます。
どこまで運動強度を上げて良いか不安に感じる患者さんは、かかりつけ医ともよく相談してみましょう。
糖尿病は食事や運動、生活習慣の改善や薬物による治療のほか、再生医療の選択肢もあります。
再生医療について、さらに詳しく知りたい方は以下のページをご覧ください。メール相談やオンラインカウンセリングも承っておりますのでご利用ください。
今回の記事の情報が少しでも参考になれば幸いです。
糖尿病に効果的な運動に関するよくある質問
糖尿病予防に効果的な運動に関するよくある質問をまとめました。
糖尿病で運動しないとどうなりますか?
糖尿病で運動をしないと、血糖値を下げるインスリンの働きが弱まり、血糖コントロール不良による血糖が高い状態が続きやすくなります。
その結果、動脈硬化が進み、心筋梗塞や脳梗塞、腎臓・神経・目の合併症などを引き起こすおそれがあります。運動は血糖コントロールを助け、合併症を防ぐ上でも重要です。
糖尿病予防の運動は食前と食後どちらが良いですか?
糖尿病予防のための有酸素運動は、食後に行うのが効果的とされています。
食後すぐは消化に負担がかかるため避け、血糖値が上がり始めるタイミングで軽いウォーキングなどを行うと、血糖の上昇を緩やかにする効果が期待できます。
参考文献