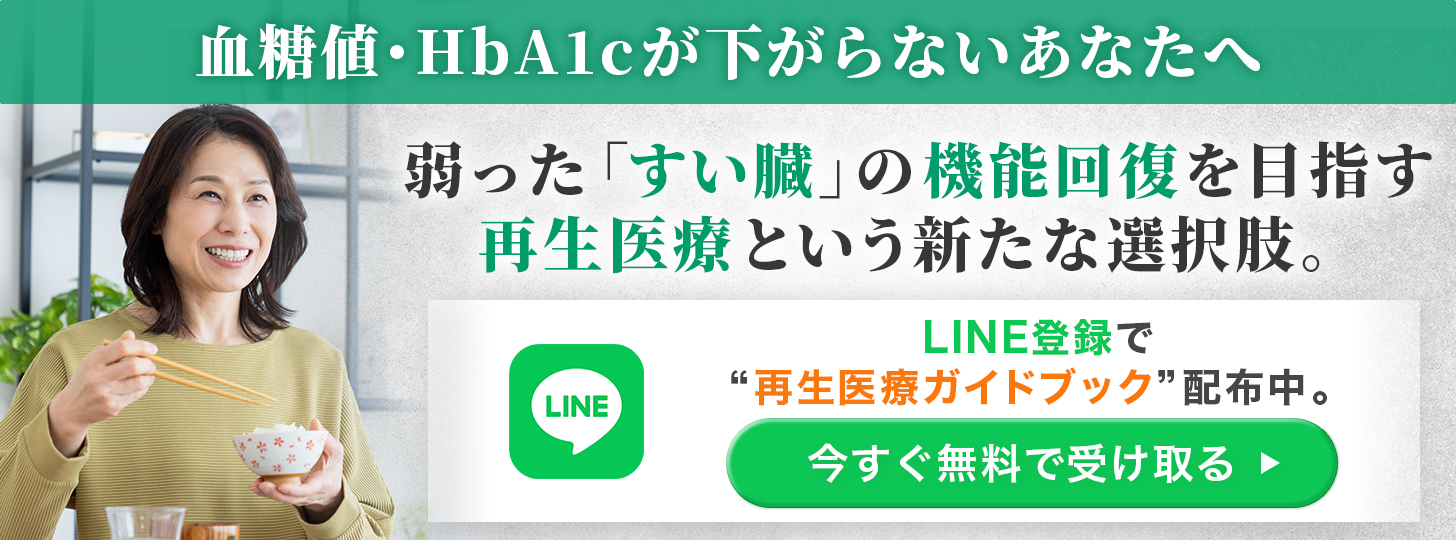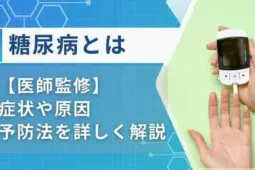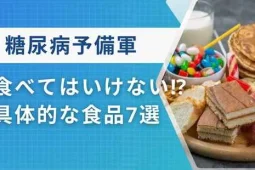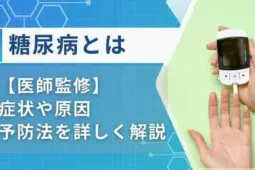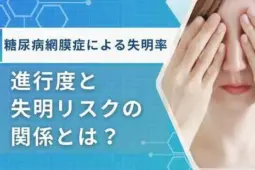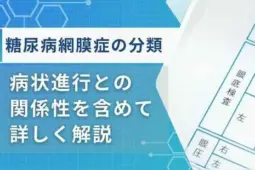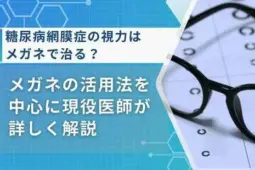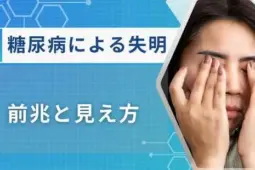- 糖尿病
- 内科疾患
糖尿病の運動療法における禁忌とは?中止すべき基準や注意点を解説

「糖尿病だけど、運動しても大丈夫なのか不安…」
「運動をしてはいけない人もいるって聞いたけど本当?」
このように悩んでいる方もいるのではないでしょうか?
糖尿病の人にとって、適度な運動は血糖値を安定させる上で大切です。
しかし、すべての運動が良いわけではありません。間違った方法で運動すると、血糖値のバランスが崩れたり、合併症を悪化させたりして体に悪影響を及ぼすリスクがあります。
本記事では、糖尿病で運動療法をやめるべき基準や運動が許可された場合の注意点を解説します。運動療法の方針を考えていく際の参考にしてください。
目次
【禁忌】糖尿病で運動療法をやめるべき基準
糖尿病の治療において運動療法は効果的な治療法の一つですが、患者様の状態によっては運動が逆に症状を悪化させる場合があります。
以下の条件は禁忌(実施すると危険性がある行為)に該当するため、運動療法をやめるべき基準となります。
- 増殖網膜症・増殖前網膜症を発症している
- レーザー光凝固後3〜6カ月以内の網膜症を発症している
- 第3B期(顕性腎症後期)以降の腎症(血清クレアチニン:男性2.5mg/dl以上、女性2.0mg/dl以上)
- 心筋梗塞など重篤な心血管系障害がある
- 高度の糖尿病自律神経障害がある
- 1型糖尿病でケトーシスがある
- 代謝コントロールが極端に悪い(空腹時血糖値≧250mg/dlまたは尿ケトン体中等度以上陽性)
- 急性感染症を発症している
自身がこれらの状態に該当するかどうかは、医師の診断や判断が必要です。糖尿病の方は運動療法をはじめる前に、必ず医師に相談してください。
糖尿病の基本的な治療は「運動療法」と「食事療法」
糖尿病の基本治療は、本来「運動療法」と「食事療法」です。それぞれの治療効果を詳しく見ていきましょう。
運動療法|運動しないとどうなるかのリスク管理も大切
運動療法は糖尿病の基本治療の1つです。
運動は血糖値を下げ、インスリン(血糖値を下げるホルモン)の働きを助ける効果があります。
糖尿病の人が運動をしないと、血糖値が上がりやすくなるほか、インスリンの働きも弱まるため、症状が悪化する可能性があります。
糖尿病の方に適した運動のタイミングは血糖値が上昇する食後です。食後の急激な血糖値上昇を運動によって抑えることが大切です。
毎日の生活の中に取り入れ、無理のない範囲で運動を続けましょう。
食事療法|食材選びや食べ方の工夫が症状を安定させるコツ
食事療法では、食べるものや食べ方を工夫して血糖値をコントロールしたり、適切な体重を維持したりするのが目標です。
血糖値の上昇を引き起こしやすい栄養素は、糖質です。糖質は、パンやご飯、甘いお菓子などに多く含まれます。一方で、食物繊維は血糖値の上昇を緩やかにする働きがある栄養素です。食物繊維は、野菜や海藻、いも類などに多く含まれています。
栄養バランスを考えた食事選びが、糖尿病管理の基本となります。
なお、糖尿病の治療においては再生医療も選択肢として挙げられます。体内の脂肪細胞を活用して、すい臓・血管の機能回復を図り糖尿病治療を進めます。
再生医療について詳しく知りたいという方は、メール相談、オンラインカウンセリング も承っておりますので、ぜひご活用ください。
【関連記事】
糖尿病!運動療法なら改善はもとより予防にも効果を発揮
効果が上がる!糖尿病の予防に最適な運動!その効果と注意点
運動療法の制限が必要な糖尿病の人|7つの特徴
糖尿病の方の中には、完全に運動を禁止するのではなく、医師の指導のもとで制限付きの運動療法が可能な場合があります。
以下は、注意深く運動を行う必要がある人の7つの特徴です。
- インスリン治療中の人
- 単純網膜症の人
- 増殖前網膜症・増殖網膜症を患っている人
- 糖尿病神経障害の人
- 重篤な心血管障害や肺の病気を患っている人
- 腎症を患っている人
- ケトーシス状態の人
それぞれの特徴を詳しく解説します。
インスリン治療中の人
インスリンを使った治療を受けている人は、運動のタイミングに注意が必要です。
適切な運動は血糖値を安定させるのに役立ちますが、誤ったタイミングで行うと低血糖を引き起こす危険があります。
とくに、寝起きや食事前は血糖値が低くなりやすいため、この時間帯の運動は避けたほうが良いでしょう。
運動中に血糖値が急激に下がると、めまいやふらつきが起こり、意識を失う可能性もあります。そのため、血糖値が上がりやすい食後に運動を取り入れるのが理想的です。
薬を使いながら運動をする場合は、主治医に相談し、自分に合った運動方法を確認してください。
単純網膜症の人
糖尿病の合併症の1つに「糖尿病網膜症」があります。
これは、目の奥にある網膜(光を感じる部分)の血管が傷つき、視力に影響を与える病気です。
糖尿病網膜症は進行の度合いによって「単純糖尿病網膜症」「増殖前網膜症」「増殖網膜症」の3段階に分かれます。
糖尿病網膜症は血圧の変動によって出血する可能性があります。また、低血糖になれば眼底出血が引き起こされる場合があるので、運動のタイミングや強度には注意が必要です。
病状によっては、運動が制限される場合や禁止されるケースもあります。
増殖前網膜症・増殖網膜症を患っている人
増殖前網膜症の場合は血圧におよぼす影響の少ない軽度の運動にとどめます。
頭を強く振る、頭を下げる、力むといったことは血圧を上げ、頭部への血流を増やすため、眼底出血などを起こす可能性があります。
また、増殖網膜症の方は、運動以外にも、力んだり、息をこらえたり、重量物を持ち上げたりするような行為は身体に負担がかかるので避けましょう。
糖尿病神経障害の人
糖尿病神経障害には、「感覚神経障害」と「自律神経障害」があります。
感覚神経障害では、足の感覚が鈍くなり、痛みに気づきにくくなるため、足に負担の少ない運動が適しています。たとえば、自転車エルゴメーターや水泳などです。
一方、自律神経障害では、血圧や心拍の調整が難しくなるため、運動療法が禁止される可能性があります。
重篤な心血管障害や肺の病気を患っている人
心臓や肺に病気がある人が運動を始める際は、事前に体への負担を確認する取り組みが大切です。
とくに、心臓の病気がある場合は、運動中の心拍の変化を調べる「負荷心電図」(運動中に心臓の働きを記録する検査)の実施が推奨されます。
運動の強さによっては、心臓に負担をかける可能性があるため、どの程度の運動が安全かを医師と相談しましょう。
腎症を患っている人
糖尿病による腎臓の病気「糖尿病性腎症」は、進行度によって5段階に分かれます。
- 第1期:腎症前期(尿中アルブミンが正常範囲)
- 第2期:早期腎症期(微量アルブミン尿)
- 第3期:顕性腎症期(顕性アルブミン尿or持続性タンパク尿)
- 第4期:腎不全期(腎機能の著しい低下)
- 第5期:透析療法期(透析療法中)
第1期から第3期までは、病状に応じた適切な運動が推奨されています。
第3期の顕性腎症期まで進行すると、腎臓の負担を減らすために運動を制限する可能性があります。
以前は腎症患者には運動を控えるよう一律に指導されていましたが、現在の医学的見解では、適度な運動による持久力向上や血中脂質代謝改善の効果が認められています。
ケトーシス状態の人
血糖値が250mg/dl以上(高血糖)やケトーシス状態の場合は運動が制限されます。
ケトーシスとは血中のケトン体が増加し、尿中のケトン体が中等度以上の状態です。
高血糖のときに運動をすると、糖の代謝がうまくいかず、症状が悪化する可能性があります。そのため、まずは食事や薬の治療で血糖値を安定させてから運動を取り入れましょう。

糖尿病のお悩みに対する新しい治療法があります。
糖尿病の人が運動するときの注意点
運動が許可されている糖尿病の方は、以下の点に注意して安全に運動をする必要があります。
|
運動時の状況 |
起こりうるリスク |
|---|---|
|
低血糖を引き起こしている |
めまいや意識障害を引き起こし、転倒・事故のリスクを高める |
|
運動の強度や頻度が高すぎる |
関節や筋肉を損傷する可能性がある |
|
インスリン調整剤や飲み薬を服用している |
低血糖になりやすいため、体調の変化に注意する必要がある |
運動療法は継続が何より大切です。運動を長続きさせるためにも、安全を第一に心がけましょう。
糖尿病を発症したら運動療法の前に医師によるメディカルチェックが必要
糖尿病患者の方が運動療法を行う際、やり方を間違えると事故や症状を悪化させるリスクがあります。
そのため、運動療法を始める前には医師によるメディカルチェックを受けて、安全性を確認することが大切です。
以下は、糖尿病患者の運動療法を行う際のメディカルチェックにおける基本項目です。
|
項目 |
検査内容 |
|---|---|
|
問診 |
・糖尿病以外で治療中の病気や服薬中の薬 ・家族の既往歴 ・現在の生活状態や運動習慣 |
|
血液検査 |
・空腹時血糖 ・HbA1c(ヘモグロビン量の測定) |
|
診察 |
・血圧 ・脈拍数 ・身体計測(身長、体重、腹囲) ・肥満度 |
|
尿検査 |
たんぱく、ケトン体の測定 |
|
心電図 |
安静時心電図 |
運動療法を開始後も、少なくとも年に一回は医師によるメディカルチェックを受けましょう。
まとめ|糖尿病の運動療法における禁忌を知って正しい治療を進めよう
禁忌とは、単なる禁止という意味ではなく、それを行うことで症状を悪化させたり、予期せぬ副作用が起きたりするなどのリスクがあるという意味で用いられています。
よって、自分の状態が運動療法の禁忌に該当するかどうかを医師に確認し、安全な範囲で糖尿病の治療を進めていく姿勢が大切です。
糖尿病はこれまで「治らない病気」と言われてきました。しかし、近年「再生医療」という新しい医療分野が発達し、血糖値が大幅に改善した事例が数多く報告されています。糖尿病の再生医療に興味がある方は、当院リペアセルクリニックにお気軽にお問い合わせください。
\無料オンライン診断実施中!/
【関連記事】
糖尿病が改善!肝機能も良くなる 幹細胞治療 60代女性
糖尿病に対する幹細胞治療でHbA1Cは正常値に戻る!70代男性