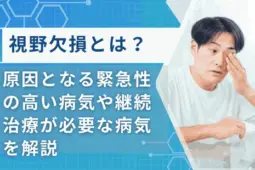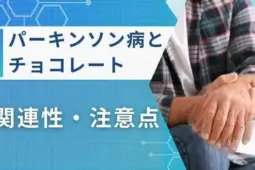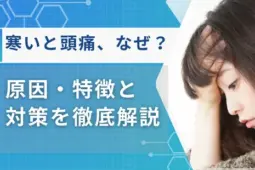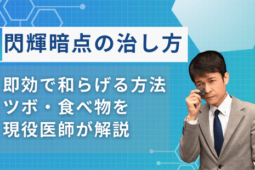- 頭部
- 頭部、その他疾患
もやもや病(ウィリス動脈輪閉塞症)は遺伝する?家族への影響と遺伝の関係

もやもや病(ウィリス動脈輪閉塞症)は、脳血管に異常が生じることで脳卒中などを引き起こす可能性がある、原因不明の難病です。
近年、家族内で複数の患者様が見られるケースも報告されており、「もやもや病は遺伝するのでは?」と心配する方も増えています。
この記事では、もやもや病と遺伝の関係性について、最新の研究や専門的な見解をわかりやすく解説します。
なお、当院「リペアセルクリニック」の公式LINEでは、再生医療の情報提供と簡易オンライン診断を実施しております。
もやもや病が引き起こす可能性がある脳卒中の予防や、再生医療について詳しく知りたい方は、ぜひ一度公式LINEにご登録ください。
目次
もやもや病と遺伝の関係|どこまで明らかになっているのか
もやもや病は長らく原因不明の病気とされてきましたが、近年の研究により、遺伝との関連が少しずつ解明されつつあります。
家族内での発症例や、特定の遺伝子との関連が指摘されており、遺伝的な背景を考慮した研究が進められています。
もやもや病は「遺伝病」ではないが遺伝的要因が関与する可能性がある
もやもや病は、いわゆる「遺伝病」ではありません。
つまり、親から子へ必ず受け継がれるような仕組みは確認されていません。
しかし、これまでの研究では、家族内に複数の患者様がいるケースが一定の割合で報告されており、遺伝的な要因が関係している可能性があると考えられています。
また、特定の人種や地域に患者様が集中していることからも、環境要因に加えて、体質的な背景も影響しているのではないかと指摘されています。
現在のところ、もやもや病の発症には、遺伝だけでなく複数の要因が複雑に関わっていると考えられており、まだ解明されていない部分も多いのが現状です。
家族内発症の傾向と報告例について
もやもや病は、日本において10〜20%の患者様に家族内での発症が確認されていると報告されています。
つまり、兄弟や親子などの近い家族の間では、10人に1〜2人の割合で罹患していることになります。(文献1)
このような「家族性もやもや病」は、特定の遺伝的背景を持つ人に起こりやすい可能性があると考えられています。
また、家族性のケースでは、次の世代になるほど発症年齢が早くなったり、症状が重くなるといった傾向(表現促進現象)が見られることもあります。
子どもへの遺伝確率や兄弟リスクは?
家族にもやもや病の患者様がいると、「子どもや兄弟にも遺伝するのでは」と不安に感じる方が多いかもしれません。
とくに親が患者様である場合、将来の子どもの健康に影響があるかを心配されるケースもあります。
現在のところ、もやもや病は単純な遺伝形式で受け継がれる病気ではないとされています。
たとえば、親が発症しても子どもには症状が現れない場合も多く、反対に親に症状がなくても子どもが発症することもあります。
また、兄弟間で発症する確率が何%といった明確な数値は示されていません。
これは、遺伝的な素因に加えて、環境や個人の体質など、さまざまな要因が発症に関わっているためです。
当院「リペアセルクリニック」の公式LINEでは、簡易オンライン診断が受けられます。
もやもや病による脳卒中に関してお悩みの方は、公式LINEに登録してぜひ一度お試しください。
\無料オンライン診断実施中!/
もやもや病と関連した遺伝子とは?
もやもや病は、家族内に複数の患者様がいるケースや、東アジアに多いという特徴から、以前から遺伝的な要因が関係しているのではないかと考えられてきました。
近年では、ある特定の遺伝子と病気の関連性も報告されており、研究が進んでいます。
遺伝子多型
私たちの体は、細胞の中にあるDNA(遺伝情報)によってつくられています。
DNAは、アデニン(A)・チミン(T)・グアニン(G)・シトシン(C)の4種類の「塩基」が並んでできており、この配列によって体のさまざまな情報が決まります。
人間同士のDNAは、約99.9%が同じですが、ごくわずかに異なる部分があります。
この違いを「遺伝子多型(いでんしたけい)」と呼びます。
たとえば、肌や髪の色の違い、病気へのなりやすさの個人差などが、この多型によって現れることがあります。
ただし、遺伝子多型があるからといって、必ず症状が出るわけではありません。
体質の違いや傾向を示す個性のようなものと考えると、イメージしやすいでしょう。
RNF213遺伝子多型p.R4810K
もやもや病と関わりの深い遺伝子として、「RNF213(アールエヌエフ213)」があります。
これはヒトの染色体のうち17番目に存在する遺伝子です。
日本人の患者様のRNF213遺伝子を調べると、80〜90%もの人が「p.R4810K」という遺伝子多型があることがわかりました。
一方で、このp.R4810K多型は、健康な日本人でも約1〜2%の人に見られることがわかっています。
つまり、この多型を持っているからといって、必ずもやもや病を発症するわけではありません。
これは、RNF213のp.R4810Kが「発症しやすい体質を示す素因」であり、発症には他の遺伝的要因や環境要素も関係していることを意味します。
発症の背景は複雑で、一つの要因だけで決まるものではないと考えられているのです。
遺伝子検査はできる?費用や対象について
現在のところ、RNF213遺伝子の多型(p.R4810K)を調べる遺伝子検査は、一般的な医療機関では実施されていません。
保険診療の対象にもなっておらず、通常の診療では行われていないのが現状です。
また、この遺伝子多型を持っていても、必ず発症するわけではないため、検査で結果が出ても予防や治療に直結するわけではありません。
そのため、現時点では、診断目的の検査は画像検査(MRAや脳血管造影など)が中心となっています。
研究機関や一部の専門施設では、研究協力の一環として遺伝子検査が行われる場合がありますが、その際も倫理審査を経て同意が必要となります。
費用や受けられる条件も施設によって異なるため、希望がある場合は専門医に相談することをおすすめします。
\無料相談受付中/
もやもや病と診断されたら|家族の健康管理でできること
もやもや病と診断されたとき、本人だけでなく家族も「ほかの家族にリスクはないのか」と不安を感じることがあります。
この章では、家族として意識しておきたい健康管理のポイントや、子ども・兄弟への対応についてご紹介します。
子どもや兄弟の定期的なチェックは必要?
家族にもやもや病の方がいると、発症リスクがやや高まるとされているため、気になる症状があれば早めに受診しておくことをおすすめします。
もやもや病は、5〜10歳ごろの小児期に発症のピークがあることが知られています。
また、成人期では40歳前後に発症するケースが多く、子どもから大人までどの年代でも注意が必要な病気です。(文献2)
とくに、小児では過呼吸や運動後の脱力、てんかん発作のような症状が現れることがあり、成人では脳出血で発症する例もあります。
症状がなくても、気になる背景がある場合は画像検査(MRAなど)で早期に確認するという選択もあります。

脳卒中のお悩みに対する新しい治療法があります。
不安なときの相談先や検査のすすめ方
家族に患者様がいる場合、「自分や子どもも発症するのでは」と心配になる方は少なくありません。
そんなときは、一人で悩まずに医療機関で相談することが大切です。
もやもや病の診療を行っているのは、主に脳神経外科や神経内科です。
とくに、もやもや病に詳しい専門医のいる病院や、脳卒中センターを併設している大きな医療機関での相談が安心です。
症状がある場合はもちろんですが、「家族に患者がいるので心配」「子どもの頭痛が気になる」といった理由でも、相談して問題ありません。
必要に応じてMRA(磁気共鳴血管撮影)などの画像検査が行われます。
また、小さなお子さんの場合は、検査中に動かずにいられるかどうかがポイントになります。
状況によっては鎮静剤を使って検査を受けることもあるため、不安があれば事前に医師に相談しましょう。
まとめ|もやもや病は遺伝だけではないが家族で知っておきたい病気
もやもや病は、一部で家族内での発症が見られる病気であり、関連する遺伝子も報告されています。
ただし、「遺伝=必ず発症する」わけではなく、さまざまな要因が重なって起こる複雑な病気です。
遺伝的な背景があることを知っておくことは大切ですが、過剰に心配し過ぎる必要はありません。
大切なのは、必要に応じて早めに相談・検査を行い、家族で健康を守っていくことです。
参考文献
(文献1)
もやもや病(指定難病22)|難病情報センター