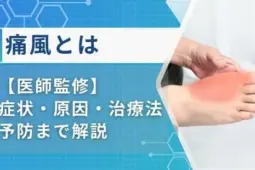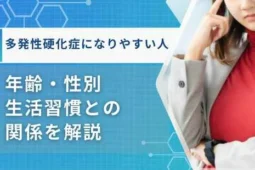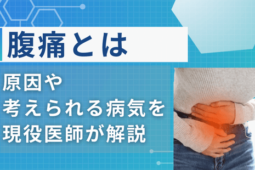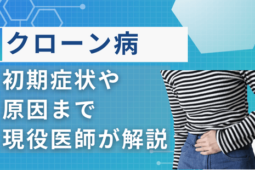- 内科疾患
- 内科疾患、その他
痛風の初期症状は?早期発見につなげて重症化を防ごう【医師監修】

「痛風の初期症状を知りたい」
「足の親指が突然激痛に襲われたけど、痛風の初期症状?」
足の指における激痛などの症状は、痛風の初期症状かもしれません。
痛風は放置すると関節の変形や機能障害を引き起こす可能性があり、早期発見と適切な対処が大切です。
今回は痛風の初期症状の見分け方と、症状が出たときの対処法を詳しく解説します。本記事を読むと痛風の初期症状を見逃さず、重症化を防げるはずです。
先に「痛風の初期症状」における詳細を知りたい方は、リンクをクリックいただくと該当ページに飛べます。
目次
痛風の初期症状と基本知識
痛風と聞くと、中高年男性の病気をイメージされませんか。しかし、最近では30代以下の発症も増えており、女性も決して無縁ではありません。
以下で、痛風の基本的な知識を解説します。
痛風とは何か?
痛風は、体内で作られた尿酸が関節内に蓄積し、激しい炎症と痛みを引き起こす病気です。
尿酸とは「プリン体」と呼ばれる物質が分解されてできる老廃物の一種で、通常は血液中から腎臓を介して尿に溶けて排出されます。
しかし、尿酸値が高くなりすぎると、血液中で尿酸が結晶化し、関節内に蓄積します。
主に足の親指の付け根(第一中足趾節関節)に発症しますが、足首や膝などの関節にも生じます。関節の変形や機能障害につながる恐れがあるため、初期症状を見逃さないようにしましょう。
|
痛風が起こる生物学的メカニズム
体内の尿酸濃度は、尿酸の「産生」と「排泄」のバランスで決まります。痛風は、以下のような原因で尿酸の産生過剰や排泄低下が起こりやすく、血中尿酸濃度が上昇すると発症します。
| 原因 | 説明 |
| プリン体の過剰摂取 | 肉類、魚類、ビールなどに多く含まれるプリン体を過剰に摂取すると、尿酸の産生が増加する |
| 尿酸の排泄低下 | 体内で尿酸が過剰に生成される または腎臓からの尿酸排泄が低下する |
| 遺伝的要因 | 尿酸の産生や排泄に関連する酵素の遺伝的な異常により、尿酸が上昇しやすくなる |
高濃度の尿酸は針状結晶となって関節内に蓄積し、激しい炎症反応を引き起こすのです。炎症は発赤、腫脹、熱感、痛みなどの症状を引き起こします。
|
上記のように、痛風は尿酸値の上昇を引き起こす病気であり、生活習慣や遺伝的要因が関与しているといわれています。初期症状を見逃さず、適切な治療を行うのが大切です。
痛風の初期症状【激しい関節痛・違和感がある】
痛風の初期症状は、主に突然の激しい関節痛です。しかし、痛風発作が起こる前に、軽い痛みや違和感などの前兆が現れるときもあります。
初期症状を見逃さず、適切な対処を行うためにも、以下で痛風の初期症状と前兆を見ていきましょう。
痛風が起きたときの症状
痛風の代表的な初期症状は、以下のとおりです。
| 症状 | 説明 |
| 足の親指の付け根の激痛 |
|
| 関節の腫れと発赤 |
|
| 関節の熱感 |
|
| 歩行困難 |
|
痛風発作は非常に強い痛みを特徴とし、安静時でも痛みが持続します。さらに、関節を動かすと痛みが増強します。発作が起こると日常生活に大きな支障をきたすでしょう。
発作は数日から長くて2週間ほど続きますが、炎症が治まると痛みや腫れは徐々に引いていきます。
しかし、適切な治療を行わないと発作を繰り返すようになり、関節の変形や機能障害につながる場合があります。
初期症状を見逃さず、早期に治療を開始するのが大切です。症状が軽度でも痛風が疑われる場合は、放置せずに医療機関を受診しましょう。
痛風の前兆に起こる症状
痛風の発作が起こる前兆の症状は、以下のようなものがあります。
| 前兆 | 説明 |
| 関節の違和感やこわばり |
|
| 軽い痛みや熱感 |
|
| 倦怠感や微熱 |
|
前兆を感じたら、安静にし、患部を冷やし、十分な水分を摂取するなどの対処を行いましょう。
痛風は発作を繰り返すと関節の変形や機能障害につながる恐れがある疾患です。初期症状を見逃さず、適切な治療を行うのが重要です。
痛風の症状が強いときや発作が起こった場合を始め、症状が気になるときは、早めに医療機関を受診して専門医の診断を受けましょう。
痛風になるリスクが高い人の傾向は?
痛風は特定の人に起こりやすい病気です。以下で痛風のリスクが高いかどうか、セルフチェックしましょう。
5つのセルフチェックリスト
以下の項目に当てはまる人は、痛風のリスクが高い傾向にあります。
| リスク因子 | 説明 |
| 肥満または過体重 |
|
| 生活習慣病 |
|
| 多量のアルコール摂取 |
|
| 高プリン食の嗜好 |
|
| 家族歴 |
|
参照:日本痛風・核酸代謝学会高尿酸血症・痛風の治療ガイドライン
当てはまる項目が多いほど、痛風のリスクは高くなります。しかし、これらの項目に当てはまらない方でも痛風を発症する可能性はあります。
リスクが高いと感じた方は、生活習慣の改善に取り組むのが大切です。食事、飲酒、運動などの生活習慣を見直して、尿酸値の上昇を防ぐのが重要です。
ただし、すでに痛風の症状がある場合や、生活習慣の改善だけでは尿酸値が下がらない場合は、医療機関で専門医に相談しましょう。
痛風になる確率を高めるリスク要因
痛風の発症には、遺伝的要因と生活習慣の両方が関与しているといわれています。主な痛風のリスク要因とメカニズムは以下のとおりです。
| リスク要因 | メカニズム |
| 肥満 | 体重増加により尿酸値が上昇 |
| 多量飲酒 | アルコールによる尿酸の産生促進と排泄阻害 |
| 高プリン食の過剰摂取 | プリン体の摂取過剰による尿酸産生増加 |
| 遺伝的要因 | 尿酸代謝関連酵素の遺伝子変異 |
| 家族歴 | 遺伝的素因による発症リスクの上昇 |
| 加齢 | 加齢に伴う腎機能低下と尿酸排泄機能の減少 |
| 性別 | 男性に多く、女性は閉経後にリスク上昇 |
痛風の発症は複数の要因が絡み合って起こるため、リスク要因を理解して、ご自身に当てはまるリスクを把握しておくのが重要です。
痛風が疑われるときの対応法【家庭でできる対策】
痛風の発作が疑われる場合、以下のような対応を取りましょう。
| 対応方法 | 説明 |
| 安静 | 痛みのある関節を動かさないようにし、安静にすると炎症の拡大を防ぐ |
| 冷却 | 痛みと腫れのある関節を冷やし、炎症を抑える。氷のうやアイスパックを20分程度当てる |
| 水分補給 | 体内の尿酸を排出するために、十分な水分補給を行う。1日2リットル以上の水分摂取を心がける |
ただし、上記は応急処置で根本的な治療にはなりません。
痛風の治療は早ければ早いほど効果的です。症状が改善しない場合や、発作が頻繁に起こる場合は、速やかに医療機関を受診してみてください。
医師の診断を受けるタイミング【早期発見が大切】
痛風の症状が疑われる場合、早めに医師の診断を受けるのが大切です。以下で、医療機関を受診すべきタイミングをまとめています。
| 受診すべきタイミング | 詳細 |
| 突然の激しい関節痛がある |
|
| 関節が腫れて赤く変色している |
|
| 痛みが引かず、日常生活に支障をきたす |
|
| 発熱や倦怠感などの全身症状を伴う |
|
上記の症状がある場合、痛風の可能性が高いと考えられます。早めに医療機関を受診し、適切な診断を受けるのが重要です。
医師は患者の症状や病歴、身体診察から痛風を疑い、以下のような検査を行って診断します。
| 医師が行う主な検査 | 目的 |
| 血液検査 | 血中尿酸値の測定。痛風発作時は正常値でも、症状が治っている期間には高値を示す |
| 関節液検査 | 関節から液体を採取し、尿酸結晶の有無を顕微鏡で確認。痛風に特異的な所見 |
| 画像検査 | X線やCTスキャン、超音波検査で、関節の損傷や尿酸結晶の沈着を評価 |
上記の検査結果を総合的に判断し、痛風の確定診断が行われます。
軽い痛みでも繰り返し出る場合は、長期化のサインかもしれません。早めに専門医(リウマチ科、整形外科、内科など)に相談し、適切な診断と治療方針を検討するのが賢明です。
痛風は早期発見・早期治療が重要な疾患です。症状が軽度であっても、痛風が疑われる場合は、自己判断せずに医療機関を受診してみてください。
適切な治療と生活指導を受けると、痛風の症状をコントロールしながら、病状の進行や合併症を防げるでしょう。
また、痛風以外にも、体の症状でなにかお悩みを抱えておられる方は、当院のメールや電話からお気軽にご相談ください。
生活習慣における痛風の予防法
痛風を予防するには、日頃の生活習慣を改善するのが大切です。とくに食生活の見直しと運動の習慣を作るのがポイントになるので、以下で詳細を解説します。
食生活の改善
痛風を予防する食事療法のポイントは以下のとおりです。
| 食生活の改善ポイント | 内容 |
| プリン体の摂取制限 |
|
| 低脂肪・低エネルギー食 |
|
| 野菜・果物の積極的摂取 |
|
| 水分摂取の励行 |
|
| アルコールの制限 |
|
運動と健康管理
運動は痛風の予防に欠かせません。有酸素運動を中心に、無理のない範囲で定期的に体を動かすのが大切です。
| 運動の種類 | 具体例 | 強度(目安) | 時間(目安) | 頻度(目安) |
| 有酸素運動 | ウォーキング、ジョギング、 水泳、サイクリング など |
会話ができる 程度の強度 |
30分以上 | 週5日以上 |
| 筋力トレーニング | 自重トレーニング、 ダンベル体操など |
ややきつい 程度の強度 |
20分以上 | 週2日以上 |
| ストレッチ | 静的ストレッチ、 動的ストレッチなど |
伸びる程度の強度 | 10分以上 | 毎日 |
運動するときは、関節に負担をかけすぎないよう注意しましょう。痛みを感じる運動は避けて、徐々に強度と時間を増やすのが大切です。
また、定期的な健康診断で尿酸値のチェックを忘れずに行います。尿酸値が高めの場合は、あわせて生活習慣の改善に取り組みましょう。
痛風の予防には、バランスの取れた食事と適度な運動が欠かせません。一度に大きな変化を求めるのではなく、自分のペースで少しずつ生活習慣を改善するのが重要です。
医師や管理栄養士など専門家のアドバイスを参考に、ご自身に合った予防法を見つけましょう。痛風と上手に付き合い、健康的な生活を送るためのサポートを積極的に活用するのをおすすめします。
まとめ|痛風の初期症状があるときは早めに医療機関を受診しよう
痛風の初期症状を見逃さず、適切に対処するのが肝心です。また、尿酸値に注意して痛風を予防する生活習慣を日頃から意識するのも大切になります。
もう一度、痛風の初期症状を以下でおさらいしましょう。
【以下に当てはまるときは医療機関へ受診を】
|
定期的な健康チェックを怠らず、痛風知らずの健康な生活を送りましょう。症状が気になる場合は早めに医療機関を受診し、医師のアドバイスをもとに治療を行ってみてください。
また、痛風以外の症状でも、なにかしらの不調が出てしまう場合もあります。体のお悩みを抱えておられるときは、ぜひ当院「リペアセルクリニック」にご相談ください。
| 【リペアセルクリニックへのご相談方法】 |
痛風の初期症状についてよくあるQ&A
痛風の初期症状でよくある質問と答えをまとめています。
Q.女性でも痛風になりますか?
A.痛風患者の約95%は男性ですが、約5%は女性です。
女性の痛風発症年齢は60歳以降が多く、閉経後に増加します。これは、閉経後にエストロゲンの低下により尿酸値が上昇しやすくなるためです。
Q.サプリメントで痛風は予防できますか?
A.痛風の予防はサプリメントに頼るよりも、バランスの取れた食事と運動が基本です。
サプリメントの使用を検討するときは、必ず医師に相談し、適切な助言を受けるのが大切です。
Q.痛風の合併症にはどのようなものがありますか?
A.痛風は、放置すると関節の変形や腎臓の機能低下など、重大な合併症を引き起こします。
たとえば、痛風結節は関節や軟骨に尿酸の結晶が蓄積し、こぶのようにできものができる状態で、関節の変形や機能障害の原因となります。
また、尿路結石は尿酸が尿路で結晶化し、腎臓や尿管に結石ができる合併症です。激しい腹痛や血尿を引き起こします。
ほかにも、長年の高尿酸血症により、腎臓の尿酸排泄機能が低下して腎不全に至るケースもあります。
痛風と腎機能の関係は、以下の記事で詳細を解説しているので参考にしてみてください。
Q.痛風の発作を予防するための生活習慣は?
A.痛風の発作を予防するには、日常生活での工夫が欠かせません。1日2リットル以上の水分摂取を心がけて、体内の尿酸を排出しやすくしましょう。
また、肥満は痛風のリスクを高めるため、標準体重(BMI 22)の維持を目指すべきです。アルコールについては、尿酸の排泄を妨げるので飲酒は1日純アルコール20g以下に抑えましょう。
食事では高プリン食品を控えて、バランスの良い食事を心がけるのが大切です。
さらに、有酸素運動を中心に無理のない範囲で定期的に体を動かすと、尿酸値の低下と全身の健康維持につながります。
痛風と生活習慣における内容については、以下の記事も参考になります。
Q.痛風の発作は一日で治りますか?
A.痛風の発作は一日では治りません。適切な治療を行わないと、数日から長くて2週間ほど続く場合もあります。
関連する内容は、以下の記事で詳細を解説しているので参考にしてみてください。