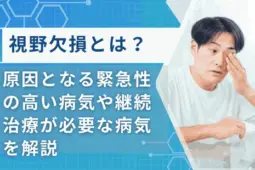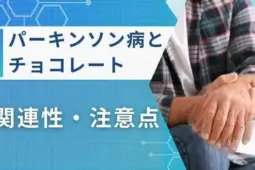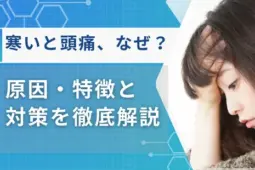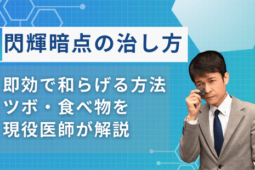- 頭部
- 頭部、その他疾患
高次脳機能障害患者の家族が抱えるストレスは?対処法や支援制度を現役医師が解説
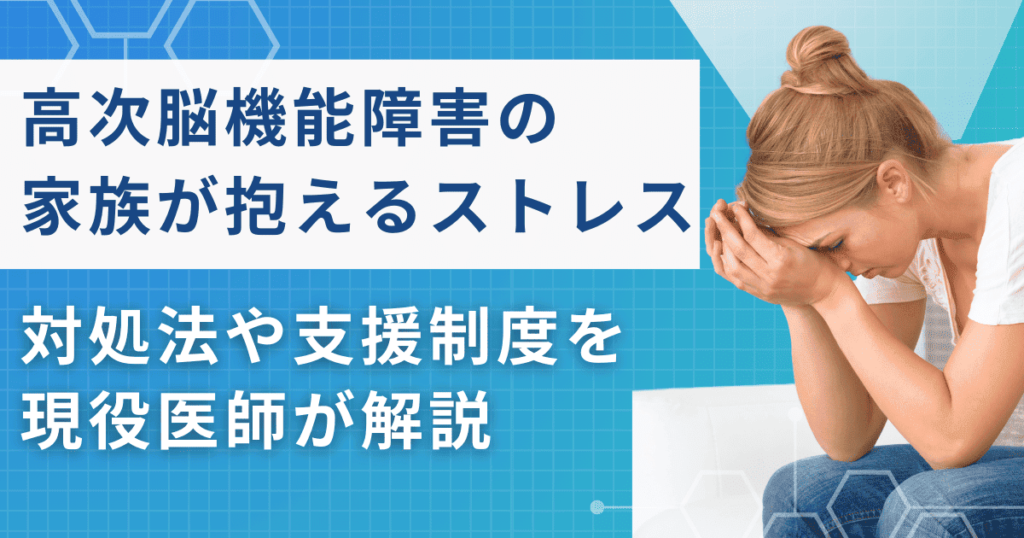
高次脳機能障害患者への対応において、ストレスを抱える家族は少なくありません。
高次脳機能障害では、感情のコントロールや日常生活の維持が難しくなる場合があります。そのため、高次脳機能障害患者を側で支える家族の負担は大きくなりがちです。
今回は、高次脳機能障害患者の家族が抱えるストレスについて解説します。ストレスの対処法や利用できる支援制度もまとめているので、ぜひ参考にしてください。
目次
高次脳機能障害患者の家族が抱える主なストレス
高次脳機能障害患者の家族は、日常生活や求められる役割の変化などを理由に、ストレスを感じやすくなります。
この章で、高次脳機能障害患者の家族が抱える主なストレスについて詳しく解説します。
高次脳機能障害の種類や原因など、包括的な解説を見たい方は「【医師監修】高次脳機能障害とは|種類・原因・治療法を解説」をご覧ください。
高次脳機能障害の症状について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
日常生活に対するストレス
高次脳機能障害患者がいる家庭では、日常生活においてさまざまな変化が生じます。たとえば、患者が自立して身の回りのことをできなくなると、家族は常にサポートにまわる必要があります。また、患者が社会生活を維持できなくなるにつれて、家族も外出する機会が限られるでしょう。
高次脳機能障害による日常生活の変化が大きいと、家族は社会からの孤立感を感じるようになり、次第にストレスが増加します。
求められる役割に対するストレス
高次脳機能障害患者の家族は、本人に代わってさまざまな手続きを担います。通院スケジュールの管理や医療費の支払いのほか、各種制度に関する手続きなど、慣れないうちはストレスを感じる場面も多いでしょう。
また、高次脳機能障害患者が高齢の場合や症状が重い場合には、介護も必要です。とくに、介護者にあたる家族が仕事や子育てで忙しいケースでは、求められる役割の多さにストレスを感じやすくなります。
当事者に対するストレス
高次脳機能障害患者の家族が抱えるストレスのなかには、当事者に対する感情もあります。高次脳機能障害の症状の一つに、感情や行動のコントロールが難しくなることが挙げられます。
そのため、患者が感情的になって過剰に反応したり、急に暴力的な行動を取ったりするケースも珍しくありません。
患者の不安定な言動は、家族が精神的な負担を感じるきっかけになります。日常生活において、患者の言動に振り回されていると、気づかないうちにストレスが蓄積されてしまうため注意が必要です。
今後の不安に対するストレス
高次脳機能障害患者の家族に多いのが、今後の不安に対するストレスです。
高次脳機能障害は、治療やリハビリテーションによって症状の改善が期待できます。しかし、必ずしもすべての方に治療の効果があるとは限りません。
そのため、多くの家族が、将来自分が介護できなくなったときのことを考えて不安を感じてしまいます。
高次脳機能障害は進行性の障害ではないものの、根本的な治療が見込めないことに不安を覚える方も少なくありません。障害に対する不安は、患者だけではなく、家族にとって大きなストレスになります。
高次脳機能障害患者の家族が抱えるストレスの対処法
高次脳機能障害患者の家族は、日常生活においてさまざまなストレスを抱えています。ただし、家族の精神的・身体的な負担は、いずれ介護疲れにつながるため注意が必要です。
以下で、高次脳機能障害患者の家族が抱えるストレスの対処法について解説するので、ぜひ参考にしてください。
症状にあわせて対応の仕方を工夫する
高次脳機能患者の家族が抱えるストレスを減らすためには、症状にあわせて対応の仕方を工夫する必要があります。高次脳機能障害は症状が多岐にわたるほか、どのような症状がどの程度現れるかも個人差が大きい障害です。
症状別の対応のポイントは、以下の通りです。
|
症状 |
対応のポイント |
|---|---|
|
注意障害 |
|
|
記憶障害 |
|
|
遂行機能障害 |
|
|
社会的行動障害 |
|
|
失語症 |
|
症状にあわせて対応の仕方を工夫すると、患者だけではなく、家族のストレス軽減にもつながります。
▼ 高次脳機能障害への対応の仕方について詳しく知りたい方は、以下の記事もチェックしてみてください。
第三者の協力を得る
高次脳機能障害患者の家族が抱えるストレスを軽減するためには、専門家や支援機関からの協力が重要です。
患者の家族だけですべてを背負い込むと、精神的にも身体的にも負担が大きくなり、介護を継続することが困難になる場合があります。
高次脳機能障害の治療では、長期にわたって治療やリハビリテーションに取り組む必要があります。そのため、医療機関と連携しながら、適切なサポートを受けることが大切です。定期的に症状の進行や回復をモニタリングしてもらうと、家族の不安を軽減できます。
なお、介護の負担が大きいときは、各自治体に設置されている地域包括支援センターや福祉窓口への相談がおすすめです。
リペアセルクリニックでは、メール相談やオンラインカウンセリングを実施しています。高次脳機能障害の症状や治療法でお悩みの方は、ぜひ気軽にご相談ください。
\無料オンライン診断実施中!/
家族会に参加する
家族会への参加も、高次脳機能障害患者の家族が抱えるストレスの軽減につながります。
家族会とは、高次脳機能障害患者の家族が集まって悩みを共有したり、情報交換したりできる場です。
家族会は、自治体や国立障害者リハビリテーションセンターなどの支援を受けて各地域で活動しており、高次脳機能障害患者の家族であれば参加できます。
高次脳機能障害患者の家族同士で、日常生活におけるストレスや悩みなどを共有できると、孤独感の軽減につながります。また、交流を通して、対応の仕方を工夫するためのヒントも得られるでしょう。
なかには、専門家による相談会や勉強会を開催している家族会も少なくありません。勉強会は、介護の方法や支援制度の活用法などについて理解を深められる貴重な機会になるため、参加を検討しましょう。
高次脳機能障害患者と家族が利用できる支援制度
高次脳機能障害患者と家族が利用できるサービスとして、以下のような支援制度があります。
- 障害福祉サービス
- 介護保険サービス
- 就労支援サービス
以下で、それぞれの支援制度について詳しく解説するので、ぜひ参考にしてください。
障害福祉サービス
高次脳機能障害患者が障害者手帳を取得すると、さまざまな障害福祉支援を受けられます。障害者手帳の申請には、医師の診断書が必要です。
代表的な障害福祉サービスは、以下の通りです。
|
居宅介護(ホームヘルプ) |
居宅訪問による介護を行う |
|---|---|
|
自立生活援助 |
定期的な訪問や随時の対応による日常生活支援を行う |
|
共同生活援助(グループホーム) |
施設で共同生活を送る障がい者を対象に日常生活支援を行う |
なお、障害福祉サービスの内容は自治体によって異なります。障害福祉サービスの手続きと利用に関しては、自治体の障害福祉担当課に相談してみてください。(文献1)
介護保険サービス
介護保険制度に基づく要介護認定を受けると、高次脳機能障害患者も介護保険サービスを利用できます。
介護保険制度は、65歳以上の方と40歳以上で脳血管疾患による高次脳機能障害と診断された方が、要支援・介護状態になった場合に利用できる制度です。
代表的な介護保険サービスは、以下の通りです。(文献2)
|
施設サービス |
老人ホームや介護施設に入所する人を対象に介護を行う |
|
訪問型サービス |
居宅訪問による介護を行う |
|
通所型サービス |
老人ホームや介護施設に通所する人を対象に介護や運動機能訓練、日常生活支援を行う |
なお、各サービスにはそれぞれ利用条件があります。介護保険サービスを利用する際は、地域包括支援センターやケアマネージャーに相談しましょう。
就労支援サービス
高次脳機能障害患者の方は、就労支援の各種制度を利用できます。就労支援サービスを利用するためには、全国に設置されている公共職業安定所(ハローワーク)や自治体の障害福祉担当課へ問い合わせしてみてください。
高次脳機能障害患者が利用できる主な就労支援は、以下の通りです。(文献3)
|
公共職業安定所(ハローワーク) |
障がい者専用の職業窓口を設置し、職業紹介を行う |
|
障害者職業能力開発校 |
障がい者向けに職業訓練を行う |
|
障害者職業センター |
就業や復職に向けた職場順応のための支援を行う |
症状に合わせて適切な支援を受けられるよう、まずは相談するところから始めましょう。
高次脳機能障害に対する再生医療の可能性
高次脳機能障害の治療法として、最近では再生医療や幹細胞治療が注目を集めています。再生医療とは、自然治癒力を最大限に引き出すための医療技術で、幹細胞や血小板の投与によって症状改善を目指す治療法の一つです。
再生医療は、従来の薬物療法やリハビリテーションといった治療法で、十分な改善が得られない場合に選択肢となる治療法です。
再生医療を取り入れることで、高次脳機能障害の症状改善の一助となる場合があります。
リペアセルクリニックでは、高次脳機能障害の原因の一つである脳卒中の再生医療・幹細胞治療を行っています。
以下の動画では、当院で再生医療を受けた方の声を紹介しているので、参考までにご覧ください。
当院では、メール相談やオンラインカウンセリングも承っております。
再生医療について詳しく知りたい方は、お気軽にご相談ください。
まとめ・高次脳機能障害患者の家族は公的制度を利用してストレスを軽減しよう
高次脳機能障害患者の家族は、日常生活においてさまざまなストレスを抱えています。高次脳機能障害は長期にわたって付き合っていかなければならない障害です。
そのため、ストレスを溜め込みすぎると、当事者と家族が共倒れしてしまう可能性があります。
そのため、家族だけで悩みを抱え込まず、障害福祉サービスや介護保険などの公的制度を活用しましょう。また、医療機関と連携しながら、適切なサポートを受けることも重要です。
支援を上手に利用することで、家族の負担を軽減し、高次脳機能障害と向き合う日々を前向きに過ごせる環境を整えましょう。

脳卒中のお悩みに対する新しい治療法があります。
参考文献
(文献1)
厚生労働省「障害福祉サービスについて」
(文献2)
厚生労働省「介護保険制度の概要」