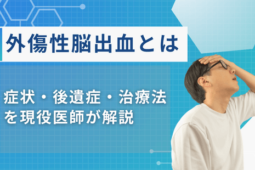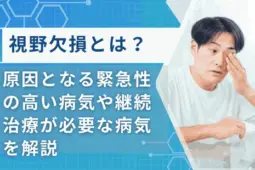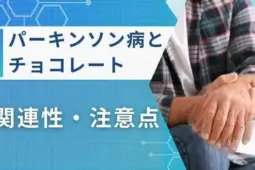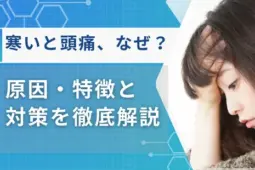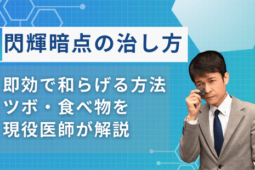- 頭部
- 頭部、その他疾患
【医師監修】高次脳機能障害とは|種類・原因・治療法を解説
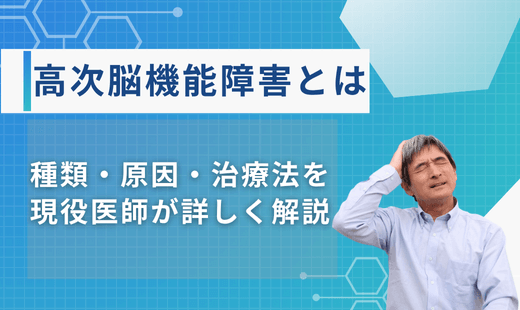
「最近、物覚えが悪くなった」
「言葉が上手く話せないと感じる」
高次脳機能障害は、脳卒中や交通事故などで脳が損傷し、記憶・言語・注意・思考・感情の調整など高度な脳機能に障害が生じる状態です。
本記事では、高次脳機能障害について現役医師が詳しく解説します。
- 高次脳機能障害の症状
- 高次脳機能障害の原因
- 高次脳機能障害の治療法
- 高次脳機能障害と似た症状
記事の最後には、高次脳機能障害についてよくある質問をまとめていますので、ぜひ最後までご覧ください。
当院「リペアセルクリニック」の公式LINEでは、再生医療の情報提供と簡易オンライン診断を実施しております。
高次脳機能障害について気になる症状がある方は、ぜひ一度公式LINEにご登録ください。
目次
高次脳機能障害とは
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 高次脳機能障害とは | 脳の病気や外傷で記憶・注意・判断・言葉の働きが低下する状態 |
| 主な症状の例 | 記憶低下、言葉が出にくい、計画困難、感情制御の難しさ |
| 特徴 | 身体ではなく認知機能や感情の働きに障害が出て外見からはわかりにくく |
| 主な原因 | 脳梗塞や脳出血、交通事故による頭部外傷 |
| 経過と改善 | 個人差があり、リハビリや支援で改善の可能性がある |
高次脳機能障害は、脳梗塞や脳出血、外傷などにより脳の一部が損傷し、記憶力・注意力・判断力・言語機能・感情の調整など、高度な脳の働きに障害が生じる状態です。
主な症状には、新しいことを覚えにくい、会話中に言葉が出にくい、計画的に行動することが難しい、感情のコントロールがしにくいなどが挙げられます。これらは手足の麻痺や感覚異常といった身体症状とは異なり、認知機能や感情の働きに影響が出る点が特徴です。
そのため、外見上は健康に見えても、本人や家族は日常生活で大きな困難を抱えることがあります。症状の現れ方や程度は個人差があり、リハビリテーションで徐々に改善する可能性があります。障害の特性を理解し、適切な対応を行うことが、生活の質の向上につながります。
高次脳機能障害の症状
| 症状 | 詳細 |
|---|---|
| 記憶障害(覚えられない・思い出せない) | 新しい出来事を覚えられない状態や過去の記憶が抜け落ちる状態 |
| 言語障害(言葉が上手く話せない) | 自分の思いや言葉を適切に表現できない状態 |
| 注意障害(集中できない・気が散りやすい) | 作業や会話に集中し続けられない状態 |
| 遂行機能障害(計画を立てて行動できない) | 物事の手順を考えて実行できない状態 |
| 社会的行動障害(感情コントロール・対人関係の変化) | 感情の起伏や対人関係の維持が難しい状態 |
高次脳機能障害では、脳の損傷により記憶力・注意力・判断力・言語機能・感情の調整など、日常生活に欠かせない高度な脳機能にさまざまな影響が生じます。
新しい情報を覚えられない、言葉が思うように出てこない、作業に集中し続けられない、計画を立てて実行できない、感情や対人関係のコントロールが難しくなるなど、症状は多岐にわたります。
これらは外見からはわかりにくい場合も多く、本人や家族の生活に大きな負担となります。適切な理解と支援が、症状の改善や生活の質の向上に重要です。
以下の記事では、高次脳機能障害の症状と診断方法や対応の仕方について詳しく解説しています。
記憶障害(覚えられない・思い出せない)
新しい出来事を記憶するためには、情報を注意深く受け取り、脳内で整理し、必要時に呼び出すという一連の過程が必要です。この過程には、主に内側側頭葉の海馬と前頭葉が関与します。
海馬は、情報を覚える・整理する役割を担い、この部位が脳卒中や頭部外傷で損傷すると、新しい情報が正しく整理されず、記憶として定着しにくくなります。
前頭葉は覚える対象を意識し、整理された情報を呼び出す指令を出す働きを持ち、損傷すると注意力の低下や記憶の呼び出し困難を招きます。さらに、びまん性軸索損傷(DAI)などで脳内の神経回路が損なわれると、海馬や前頭葉が保たれていても情報伝達が障害され、記憶形成のネットワークが機能しなくなります。
これらの障害は単独または複合して生じ、覚えようとしても記憶に残らない、思い出そうとしても想起できないといった記憶障害を引き起こします。
言語障害(言葉が上手く話せない)
| 困りごと | 詳細 |
|---|---|
| 言いたい単語が頭に浮かぶのに思い出せない(喚語困難) | 言葉が口まで出かかっているのに言えない状態 |
| 発話がゆっくり・断続的で流暢さに欠ける(非流暢型) | 話のテンポが遅く途切れがちな状態 |
| 何か言おうとするが違う単語が出てしまう(音韻性錯語) | 意図とは異なる単語や音が出てしまう状態 |
| 相手の言葉を聞いても意味がつかみにくい(理解障害) | 会話内容の理解が難しい状態 |
| 失語症に分類される症状 | 聞く・話す・読む・書くのすべてで障害がある状態 |
高次脳機能障害による言語障害は、ブローカ野やウェルニッケ野、またそれらをつなぐ神経回路の損傷で起こります。ブローカ野の損傷では言葉が出にくい非流暢型失語、ウェルニッケ野の損傷では意味が理解できない受容性失語、弓状束の損傷では言い間違いが続く伝導性失語が生じます。
これらは構音障害や声帯障害とは異なり、脳の情報処理機能の障害によるもので、多くは記憶や注意、思考の障害を伴うため、適切なリハビリと支援が改善に必要です。
注意障害(集中できない・気が散りやすい)
| 種類 | 特徴 |
|---|---|
| 容量性注意障害 | 一度に意識できる情報量が少なくなる状態 |
| 選択性注意障害 | 必要な情報に集中できず周囲の刺激に気を取られる状態 |
| 転換性注意障害 | ひとつのことに固執して注意を切り替えられない状態 |
| 持続性注意障害 | 集中を長時間保てずすぐに途切れる状態 |
| 配分性注意障害 | 複数作業に注意を分けられずミスや抜けが出る状態 |
注意障害は高次脳機能障害のひとつで、集中力の維持や必要な情報への注意が難しくなる状態です。前頭葉やその神経回路の損傷が原因となり、情報の選択・切り替え・持続といった機能が低下します。
脳梗塞や頭部外傷でこの部位が損傷すると、集中力が低下し注意が逸れやすくなり、容量性・選択性・転換性・持続性・配分性の各注意障害が単独または複合して現れます。
仕事や学習、日常生活に大きく影響を及ぼしますが、適切なリハビリや生活環境の調整により改善が期待できます。
遂行機能障害(計画を立てて行動できない)
遂行機能障害は、高次脳機能障害のひとつで、目標の設定や計画の立案、行動の順序立てが困難になる状態です。主に前頭葉が関与し、この部位は思考、判断、計画などの機能を担います。
脳卒中や交通事故で前頭葉が損傷すると、段取りが立てられない、作業を途中でやめてしまう、優先順位を決められないといった症状が現れます。
注意力や記憶力の低下、神経伝達物質のバランス異常も影響します。日常生活では、仕事や家事の進行が滞る、約束や期限を守れない、やるべきことを忘れるといった例が見られます。
遂行機能障害は外見からわかりにくいため、適切な理解と周囲の支援、専門的なリハビリテーションが生活の質を保つ上で重要です。
社会的行動障害(感情コントロール・対人関係の変化)
社会的行動障害は、脳損傷によって感情や行動の調整が難しくなり、普段とは異なる言動が現れる状態です。
前頭葉の損傷や、記憶障害・注意障害・遂行機能障害などの影響により、衝動的な行動、場にそぐわない発言、相手の気持ちを理解しにくいなどの症状が生じ、対人関係に誤解やトラブルを招きます。
外見からはわかりにくく、周囲の理解が得られにくい点が特徴です。これは性格や意志の問題ではなく脳の損傷によるもので、周囲の理解と支援、専門的なリハビリが改善に重要です。
高次脳機能障害の原因
| 原因 | 詳細 |
|---|---|
| 脳梗塞や脳出血などの脳血管障害 | 脳の血管が詰まったり破れたりして脳組織が損傷を受ける状態 |
| 交通事故などによる外傷性脳損傷 | 頭部への強い衝撃による脳の損傷で、見た目ではわかりにくい損傷も含む |
| 低酸素脳症や感染症などその他の要因 | 脳への酸素不足や脳炎などの感染症による損傷や影響 |
高次脳機能障害は、脳の損傷によって記憶・言語・注意・行動などの高度な脳機能に障害が生じる状態で、原因は多岐にわたります。
主な原因には、脳梗塞や脳出血などの脳血管障害、交通事故による外傷性脳損傷、低酸素脳症や脳炎などの感染症があります。これらは脳の組織や神経回路に影響を与える可能性があります。
発症時には早期に医療機関を受診し、適切な診断・治療・リハビリテーションを受けることが、症状の軽減や回復に重要です。
脳梗塞や脳出血などの脳血管障害
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 高次脳機能の働き | 記憶、言語、注意力、計画、判断をつかさどる脳の働き |
| 高次脳機能障害が起こる仕組み | 脳血管障害で脳の特定部位が損傷し、その働きが低下または消失する状態 |
| 脳血管障害の主な症状 | 記憶障害、言語障害、注意障害、遂行機能障害、感情コントロールの低下 |
| 脳梗塞の特徴 | 脳の血管が詰まり、詰まった先の組織が血液不足となり細胞が死ぬ状態 |
| 脳出血の特徴 | 脳の血管が破れて脳内に血が広がり、損傷部位や範囲によって症状が異なる状態 |
| 原因と結果 | 損傷部位が酸素と栄養を受けられず、高次脳機能に障害が生じる状態 |
脳は、記憶や言語、注意力、計画、判断、感情の制御など、日常生活に欠かせない高次脳機能を担っています。脳血管障害で脳の一部が損傷すると、その部位の機能が低下または失われ、高次脳機能障害が生じます。
脳血管障害による症状は多岐にわたり、損傷部位や範囲によって重症度が異なります。脳梗塞は血管の詰まり、脳出血は血管破裂で発生し、いずれも早期診断・治療と適切なリハビリが回復に重要です。
以下の記事では、脳梗塞と脳出血の症状について詳しく解説しています。
【関連記事】
交通事故などによる外傷性脳損傷
外傷性脳損傷は、交通事故や転倒、スポーツ中の衝撃などで頭部に強い外力が加わり、脳に損傷が生じる状態です。衝撃によって脳組織が傷ついたり、脳内で出血が起きたりし、その結果、脳の機能に障害が生じます。
脳の損傷部位や範囲によって多様な高次脳機能障害が現れ、とくに交通事故では前頭葉を含む広範囲が損傷しやすく重い障害を招くことがあります。
脳挫傷・脳内出血・びまん性軸索損傷はいずれも高次脳機能を低下させるため、早期診断と適切な治療・リハビリが重要です。
以下の記事では、外傷性脳出血の症状について詳しく解説しています。
低酸素脳症や感染症などその他の要因
| 状態・要因 | 詳細 |
|---|---|
| 低酸素脳症 | 脳への酸素供給が不十分となり、脳細胞がダメージを受ける状態(溺水、窒息、心停止、一酸化炭素中毒などが原因) |
| 低酸素脳症で高次脳機能障害が起こる理由 | 酸素不足により、記憶・注意・判断を担う脳細胞が損傷される状態 |
| 症状の特徴 | 記憶障害、注意障害、感情コントロールの障害などが現れやすい傾向 |
| 脳炎や感染症が高次脳機能障害を引き起こす理由 | 感染による脳の炎症で正常な脳機能が妨げられる状態(ヘルペス脳炎などでは認知や情緒面の障害が特徴) |
| その他の要因 | 髄膜炎、脳腫瘍、てんかんなどによる脳細胞の損傷と高次脳機能障害発症の可能性 |
低酸素脳症は、溺水、窒息、心停止、一酸化炭素中毒などにより脳への酸素供給が不足し、脳細胞が損傷する病態です。
高次脳機能を担う部位が障害されると、記憶障害、注意障害、判断力低下、感情コントロールの困難など多様な症状が現れます。とくに記憶障害や注意障害が出やすい傾向があります。
脳炎や髄膜炎などの脳感染症も、脳組織に炎症や損傷を与え、認知機能や情緒面に影響を及ぼします。さらに、脳腫瘍やてんかん発作なども高次脳機能障害の原因となります。これらの障害は損傷部位や範囲によって症状が異なるため、適切なリハビリテーションが回復に不可欠です。
高次脳機能障害の治療法
| 治療法 | 詳細 |
|---|---|
| リハビリテーション | 記憶や言語、注意力、計画力など低下した機能の改善を目指す訓練や作業療法 |
| 薬物療法 | 集中力や意欲、感情の安定など症状に応じた薬剤を用いた治療 |
| 再生医療 | 幹細胞などを利用し損傷した脳組織の修復や機能回復を促す治療 |
高次脳機能障害の治療は、症状や原因、重症度に応じて複数の方法を組み合わせて行います。中心は記憶や言語、注意力などの回復を目指すリハビリテーションで、作業療法士や言語聴覚士が訓練を行います。
薬物療法は注意力や意欲低下、感情の不安定さに対して補助的に使用されます。再生医療は幹細胞や成長因子を用いて損傷した脳組織の修復や機能回復を促す新しい治療法です。
しかし、取り扱う医療機関が限られているため、実施には事前の問い合わせと医師による診察が不可欠です。再生医療は単独でなくリハビリなどと組み合わせて行われ、早期かつ継続的な介入により生活の質向上が重要視されます。
リハビリテーション
| リハビリ内容 | 有用性 |
|---|---|
| 言語療法(ST) | 言葉の理解・表現力の改善、会話能力の向上、コミュニケーションの円滑化 |
| 作業療法(OT) | 日常生活動作(食事、着替え、家事)の能力向上、手先の動作や計画力の改善 |
| 認知機能訓練 | 記憶力、注意力、判断力、遂行機能の強化による生活自立度の向上 |
| 理学療法(PT) | 基本的な身体の動きやバランスの安定化による活動範囲の拡大 |
| 心理的支援・カウンセリング | 自信回復、抑うつ・不安の軽減、社会参加意欲の向上 |
リハビリテーションは、高次脳機能障害の中心的な治療法です。記憶力、注意力、遂行機能、言語能力などを回復させ、日常生活の自立を支援します。
脳には損傷後に新しい神経回路を形成する可塑性があり、リハビリはこの能力を最大限に活用する治療法です。医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理士、ソーシャルワーカーなど多職種が連携し、症状や生活状況に応じたプログラムを提供します。
効果を高めるには発症早期から開始し、6カ月から1年程度継続することが推奨され、継続的な評価と調整によって機能改善、自信回復、抑うつや不安の軽減、社会復帰の促進が期待できます。
以下の記事では、高次脳機能障害のリハビリ効果について詳しく解説しています。
【関連記事】
高次脳機能障害は回復する?事例やリハビリの重要性を現役医師が解説
薬物療法
| 理由・特徴 | 詳細 |
|---|---|
| 症状の軽減と生活の質向上 | 記憶障害・注意障害・感情や行動の問題を和らげる補助療法 |
| 神経伝達物質のバランス調整 | セロトニン・ドーパミン・ノルアドレナリンなどを整え脳機能をサポートする治療 |
| 行動・感情コントロールの支援 | 衝動性や攻撃性、うつ症状、不安を鎮め落ち着いた状態を保つ治療 |
| リハビリの効果向上 | 薬物の作用で集中力や安定性を高め、リハビリ訓練への取り組みを後押しする効果 |
| 継続的な治療の重要性 | 症状や状態に合わせ、医師が薬剤を調整しながら数カ月以上継続する治療 |
薬物療法は、高次脳機能障害に対し脳損傷そのものを治すのではなく、症状を軽減し日常生活の質を高める補助的治療法です。記憶障害、注意障害、衝動性や攻撃性などの感情・行動の問題を緩和し、リハビリテーション効果を向上させます。
治療ではセロトニン、ドーパミン、ノルアドレナリンといった神経伝達物質のバランスを調整し、注意力や意欲の改善、感情の安定を図ります。たとえば、注意障害にはメチルフェニデートが用いられ、集中力や覚醒度を高めます。抗うつ薬や抗精神病薬は衝動性、不安、うつ症状の緩和に有効です。
薬物療法は認知リハビリや作業療法と併用することで効果が高まり、数カ月以上の継続が推奨されます。薬物療法では、必ず医師の指導のもと実施することが重要です。
以下の記事では、高次脳機能障害の薬物療法とリハビリでの治療法について詳しく解説しています。
再生医療
再生医療は、患者自身の幹細胞を用いて損傷した脳組織の修復や再生を促し、失われた機能の回復を目指す治療法です。
幹細胞は損傷部位で新しい神経細胞を作り、修復を支援します。これにより脳の自己治癒力が高まり、リハビリ効果も向上します。従来より短期間で症状改善が報告される例があり、幹細胞が分泌する物質は血管修復や保護にも働き、脳卒中再発予防の可能性があります。
ただし、再生医療は実施できる医療機関が限られているため、事前に対応可能かを確認し、適応の有無を診察で判断することが必要です。
脳卒中の後遺症である高次脳機能障害や再発予防に関してお悩みの方は、再生医療も治療の選択肢としてご検討ください。
当院「リペアセルクリニック」では、脳卒中に対する再生医療の症例を紹介しています。治療内容の参考にご覧ください。
高次脳機能障害と似た症状
| 似た症状 | 詳細 |
|---|---|
| 認知症(アルツハイマー型・血管性など) | 進行性の認知機能低下と記憶障害が中心の状態 |
| うつ病や統合失調症などの精神疾患 | 気分の落ち込みや思考・行動の障害を伴う精神状態 |
| 発達障害(自閉スペクトラム症・ADHDなど) | 社会的コミュニケーションや注意集中の困難が持続する状態 |
| 脳腫瘍・正常圧水頭症などの脳疾患 | 脳の腫瘍や脳室の異常による認知や運動機能の障害 |
| てんかん(とくに側頭葉てんかん) | 発作やそれに伴う意識障害、記憶・行動の異常 |
高次脳機能障害と似た症状は、認知症、精神疾患、発達障害、脳疾患、てんかんなど多岐にわたります。認知症では記憶障害や判断力低下が進行し、うつ病や統合失調症などの精神疾患では意欲低下や感情の不安定さがみられます。
自閉スペクトラム症やADHDなどの発達障害では、社会的コミュニケーションや注意・行動の調整が困難です。脳腫瘍や正常圧水頭症では脳の構造変化や圧迫により記憶・歩行・判断力が障害されます。
側頭葉てんかんなどのてんかんでは、発作に伴い記憶や感情の変化、一時的な意識障害が生じます。これらは症状が似ていても原因や治療法が異なるため、正確な診断が不可欠です。
認知症(アルツハイマー型・血管性など)
| 項目 | 高次脳機能障害 | 認知症 |
|---|---|---|
| 主な原因 | 交通事故・脳卒中・外傷などによる急性の脳損傷 | アルツハイマー病・血管性認知症などによる脳の変性や萎縮 |
| 発症の仕方 | 急に症状が現れる発症 | 徐々に症状が進行する発症 |
| 症状の進行 | 基本的に進行しにくい状態 | 時間とともに進行し悪化する状態 |
| 主な経過 | リハビリによって改善が期待できる経過 | 根本的な治療は難しく進行を遅らせる支援が中心の経過 |
| 主な共通症状 | 記憶障害、遂行機能障害、注意障害、人格変化などの症状 | |
高次脳機能障害と認知症は、どちらも記憶障害や注意障害、計画力の低下、人格変化など似た症状を伴いますが、原因と経過が異なります。高次脳機能障害は、交通事故や脳卒中などによる急な脳損傷が原因で、症状は突然現れます。基本的に進行せず、リハビリによって改善が見込めます。
一方、認知症はアルツハイマー病や血管性認知症などが原因で脳が徐々に変性・萎縮し、症状が進行していきます。根本的な治療は難しく、薬剤や生活支援で進行を遅らせることが治療の中心となります。
以下の記事では、高次脳機能障害と認知症の違いを詳しく解説しています。
うつ病や統合失調症などの精神疾患
| 項目 | 高次脳機能障害 | うつ病や統合失調症などの精神疾患 |
|---|---|---|
| 主な原因 | 交通事故・脳卒中などによる器質的な脳損傷 | 心理的・社会的ストレス、神経伝達物質バランスの乱れ遺伝的素因など |
| 発症の仕方 | 脳損傷後に突然症状が現れる発症 | 徐々に進行する場合や急性に悪化する場合がある発症 |
| 背景メカニズム | 損傷部位の神経ネットワーク障害による症状発現 | 器質的損傷を伴わない脳機能異常や心理社会的要因による症状発現 |
| 治療の方向性 | 原因疾患の治療とリハビリによる機能回復支援 | 薬物療法や心理社会的支援による症状の安定化と再発予防 |
| 主な共通症状 | 注意障害、意欲低下、感情コントロールの不全、社会的行動の変化 | |
高次脳機能障害は、交通事故や脳卒中などによる明確な脳損傷を原因として、認知機能や感情の制御が低下する病態です。これに対し、うつ病や統合失調症などの精神疾患は脳の構造的損傷を伴わず、心理社会的ストレス、神経伝達物質の異常、遺伝的要因などが主な背景と考えられます。
いずれも注意力や意欲の低下、感情の不安定さ、対人関係の変化といった共通症状を示し、日常生活や社会生活に大きな支障をきたしますが、その発症機序は異なります。高次脳機能障害は脳の器質的障害による直接的な機能低下であり、精神疾患は脳機能の異常や心理社会的要因による変化が中心です。
症状が類似するため誤診の恐れもあり、正確な診断には医師による詳細な問診、神経心理検査、画像検査が不可欠です。
発達障害(自閉スペクトラム症・ADHDなど)
| 項目 | 高次脳機能障害 | 発達障害(自閉スペクトラム症・ADHDなど) |
|---|---|---|
| 主な原因 | 脳梗塞・交通事故・外傷などによる後天的な脳損傷 | 生まれつきの脳機能の特徴や発達の仕方の違い |
| 発症の時期 | 成人期・小児期を問わず、脳損傷後に突然発症 | 幼少期から症状がみられる発達期発症 |
| 背景メカニズム | 損傷部位の神経ネットワーク障害による情報処理の低下 | 先天的な脳情報処理の特性による行動や認知の違い |
| 治療・支援 | リハビリテーションや薬物療法で機能回復支援 | 療育・環境調整・必要に応じた薬物療法による適応支援 |
| 共通する症状 | 注意の持続困難、遂行機能障害、社会的行動の変化 | |
高次脳機能障害と発達障害(自閉スペクトラム症、ADHDなど)は、注意が続かない、計画や段取りが苦手、感情や対人関係の調整が難しいといった共通の症状があります。これらは脳の情報処理や行動調整機能の障害で起こります。
発達障害は先天的で幼少期から症状があり、高次脳機能障害は脳梗塞や事故など後天的損傷が原因です。症状の時期や経過が診断の鍵であり、正確な鑑別には医師の評価が必要になります。
以下の記事では、ブレインフォッグとADHDについて詳しく解説しています。
脳腫瘍・正常圧水頭症などの脳疾患
| 項目 | 高次脳機能障害 | 脳腫瘍・正常圧水頭症 |
|---|---|---|
| 主な原因 | 交通事故・脳卒中・外傷などによる脳の損傷 | 脳内の腫瘍形成や脳脊髄液循環障害による脳圧迫 |
| 発症の仕方 | 脳損傷後に突然症状が現れる発症 | 腫瘍や液体貯留が進行して症状が徐々に出現する発症 |
| 症状発現の仕組み | 損傷部位の神経細胞や神経回路の破壊による直接的障害 | 脳の圧迫や循環障害による二次的な機能障害 |
| 主な治療 | リハビリテーションを中心とした機能回復支援 | 外科的治療(腫瘍摘出・シャント手術)による圧迫解除と症状改善 |
| 共通する症状 | 記憶障害、注意障害、感情のコントロール不全 | |
脳腫瘍は脳内に発生する異常な腫瘤であり、正常圧水頭症は脳脊髄液の流れが障害されて脳室に液が過剰にたまる疾患です。いずれも脳を物理的に圧迫し、血液や脳脊髄液の循環を妨げることで、記憶障害、注意力低下、感情の不安定化など、高次脳機能障害に似た症状を引き起こします。
原因は脳細胞の直接的な損傷ではなく、圧迫や循環障害による二次的な機能低下です。治療は腫瘍摘出術やシャント手術などの外科的手段が中心で、圧迫を解除することで症状が改善する可能性があります。高次脳機能障害とは症状や原因が異なるため、医師の診断が不可欠です。
【関連記事】
【くも膜下出血の後遺症】水頭症は寿命がある?症状から治療法まで医師が解説
水頭症による高齢者の認知症は手術で治る?手術しないリスクとは【医師監修】
てんかん(とくに側頭葉てんかん)
| 項目 | 高次脳機能障害 | てんかん(とくに側頭葉てんかん) |
|---|---|---|
| 主な原因 | 脳梗塞・交通事故・外傷などによる器質的な脳損傷 | 脳内の異常な電気活動(発作)や潜在的なてんかん性放電 |
| 発症の仕方 | 脳損傷後に突然症状が現れる発症 | 発作の繰り返しに伴い徐々に症状が現れる場合もある発症 |
| 症状発現の仕組み | 損傷部位の神経細胞や神経ネットワークの破壊による直接的障害 | 異常な電気活動やネットワークの乱れによる機能障害 |
| 主な治療 | リハビリテーション中心の機能回復支援 | 抗てんかん薬や外科手術による発作コントロール |
| 共通する症状 | 記憶障害、注意障害、感情のコントロール不全 | |
てんかん、とくに側頭葉てんかんは、高次脳機能障害と同様に記憶障害・注意障害・感情変化を示します。記憶障害は発作時だけでなく非発作時にも現れ、新しい情報を覚えにくい、過去の出来事を忘れやすいなどの症状があります。
注意障害は集中力低下や気の散りやすさ、感情変化は怒りやすさや感情コントロール困難として表れます。これらは異常な電気活動や潜在的なてんかん性放電による脳ネットワークの乱れが原因です。
一方、脳腫瘍や正常圧水頭症では脳の圧迫や循環障害による二次的症状であり、外科手術で改善を図ります。てんかんは抗てんかん薬や手術で発作を抑えるなど治療法が異なるため、正確な鑑別診断が重要です。
以下の記事では、側頭葉てんかんの手術後に起こりうる後遺症について詳しく解説しています。
改善しない高次脳機能障害は当院へご相談ください
高次脳機能障害は、記憶力の低下や注意力の欠如などが現れ、日常生活に支障をきたします。早期発見と治療の継続で改善が見込めます。しかし、症状が進行している状態の場合、改善が困難になることがあります。
改善が見られない高次脳機能障害でお悩みの方は、当院「リペアセルクリニック」へご相談ください。当院は、損傷部位の修復にアプローチする再生医療を積極的に提案し、患者様の症状に合う治療方針を策定します。
ご質問やご相談は、「メール」もしくは「オンラインカウンセリング」で受け付けておりますので、お気軽にお申し付けください。
\無料オンライン診断実施中!/
高次脳機能障害に関するよくある質問
高次脳機能障害の家族の向き合い方を教えてください
高次脳機能障害の患者さんは、日常生活や介護の多くを家族が担いますが、症状は外見からわかりにくく、性格や行動の変化も伴うため、家族の心理的負担は大きくなります。介護を続けるためには、病気の正しい理解が重要です。
症状や経過を知ることで患者さんの行動を病気の一部として受け入れやすくなり、家族会やセミナーの参加も有効です。また、家族自身の心身の健康維持も必要で、心理カウンセリングや相談窓口の活用、同じ立場の家族との交流がストレス軽減に役立ちます。
また、行政や福祉サービス、レスパイトケアを利用して介護負担を分散させることが、患者さんの生活の質向上にもつながります。
以下の記事では、高次脳機能障害の家族の向き合い方について詳しく解説しています。
【関連記事】
高次脳機能障害への対応の仕方は?介護疲れを軽減するコツを解説
高次脳機能障害患者の家族が抱えるストレスは?対処法や支援制度を現役医師が解説
高次脳機能障害の平均余命はどのくらいですか?
高次脳機能障害の平均余命は、発症年齢や性別によって異なりますが、健常者より短くなる傾向があります。男性では、20歳発症の場合は平均余命が42.61年で、健常男性の61.45年より約18.8年短くなります。
年齢が上がるにつれて差は縮まり、50歳発症では約12.4年、80歳発症では約6.5年の差です。女性も同様で、20歳発症では約17.3年、50歳発症では約11.9年、80歳発症では約8.5年短くなります。
この余命短縮は、脳損傷による高次脳機能障害と、それに伴う身体機能低下や合併症リスクの増加が影響していると考えられます。ただし、適切な医療管理やリハビリテーション、生活習慣の改善によって健康状態を保ち、余命や生活の質(QOL)を高めることは可能です。
平均余命は統計上の目安であり、個々の生活環境や支援体制によって変わるため、医療機関と連携し、長期的な健康管理と社会参加を継続することが重要です。
以下の記事では、高次脳機能障害の平均余命について詳しく解説しています。