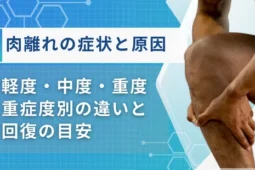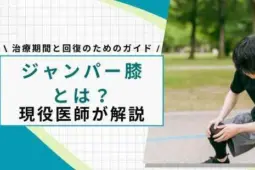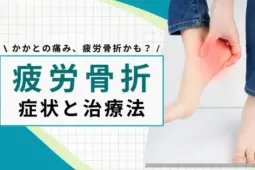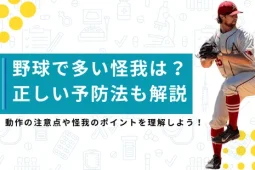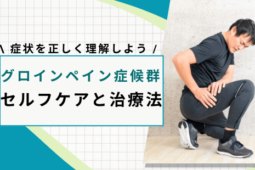- 下肢(足の障害)
- スポーツ外傷
ふくらはぎの肉離れについて|症状や前兆を紹介【歩ける場合も油断は禁物!】

ふくらはぎに違和感を感じる
ふくらはぎが赤く腫れ上がっている
運動中に突然、肉離れを起こしたかもと不安に感じているかもしれません。
ふくらはぎの違和感や、腫れ上がりを放置すると重症化する恐れがあります。
突然の肉離れにどうすれば良いのか焦りを感じている方もいれば、違和感はあるものの、歩けるから問題ないと思っている方もいることでしょう。
この記事では、ふくらはぎの肉離れについて解説します。
歩けるからといって油断は禁物です。
正しい知識を身につけて、ふくらはぎの肉離れに対し、適切な治療を行いましょう。
また肉離れからの早期復帰を目指す・手術を避けたいという方は、再生医療もご検討ください。
ふくらはぎの肉離れに対する
再生医療とは
再生医療はご自身の血液に含まれる成分を活用し、損傷した筋肉の修復をサポートする治療法です。
【こんな方は再生医療をご検討ください】
- できるだけ早い競技復帰・仕事復帰を目指したい
- 長期間の安静による筋力低下を避けたい
- 肉離れを繰り返しており、再発予防に向けたアプローチを検討したい
>>再生医療専門の「リペアセルクリニック」に無料相談する
一般的な肉離れの治療では、痛みが引いて組織が回復するまでに通常3〜4週間ほどの安静期間が必要です。
しかし、その期間に筋肉を使わないことで筋力低下や競技パフォーマンスの低下につながる可能性もあります。
また肉離れはただの怪我と放置したり、治りきらないうちに無理をしたりすると、患部が硬くなるなどして再発を繰り返すリスクがあります。
根本的な治療を行うためにも、当院(リペアセルクリニック)の無料カウンセリングにて、お気軽にご相談ください。
まずは肉離れの治療について無料相談!
目次
肉離れ(ふくらはぎ)の症状
| 分類 | 症状 |
|---|---|
| Ⅰ度(軽度) | アキレス腱ストレッチで若干の違和感がある |
| Ⅱ度(中度) | アキレス腱ストレッチで強い違和感があるものの、膝を曲げた状態で行うと違和感は弱まり、つま先立ちができる |
| Ⅲ度(重度) |
アキレス腱ストレッチで、膝を曲げた状態でも軽く伸ばしただけで強い違和感があり、つま先立ちが困難 |
肉離れは筋肉が急激に引き伸ばされることで、筋繊維が切れて起こる症状です。症状としては熱感、炎症性の違和感、腫脹、皮下出血が起こります。
また、肉離れ(ふくらはぎ)を引き起こした瞬間に「プチッ」といった音が聞こえるのも特徴です。
肉離れ(ふくらはぎ)の症状は表のⅠ度(軽度)〜Ⅲ度(重度)で分類されます。
症状がもっとも軽いⅠ度(軽度)であれば、自力で歩行でき、若干の違和感がありつつもアキレス腱ストレッチも行えます。
しかし、Ⅲ度(重度)になると、アキレス腱ストレッチが難しい状態になり、自力での歩行が難しい状態です。
以下の記事では、肉離れについて現役医師が詳しく解説しています。
ふくらはぎの肉離れの原因
ふくらはぎの肉離れの原因としては、急激な筋肉の収縮や準備運動不足など、運動中に引き起こされることが多いです。
運動以外では、加齢や筋肉疲労などで引き起こされるケースも存在します。
ふくらはぎの肉離れの原因を詳しく解説します。
急激な筋肉の収縮と伸張
急激な筋肉の収縮と伸張でふくらはぎに負担がかかることで、肉離れが起こります。
原因としては、運動中に急なダッシュやジャンプ、方向転換など脚の筋肉に急激な負荷がかかるためです。
とくに運動前に十分なウォーミングアップを怠ると、筋肉が柔軟になっていない状態で筋肉の収縮と伸張が起こるため、肉離れを引き起こしやすくなります。
筋肉の疲労
| 筋肉疲労による影響 | 肉離れのリスク |
|---|---|
| 筋肉の柔軟性低下 | 筋肉が硬くなり、急な動きに耐えられず損傷しやすい |
| 筋力低下 | 筋肉が正常な動作を維持できず、損傷しやすい |
| 運動制御の乱れ | 筋肉の協調性低下、不自然な動作やバランスの乱れで損傷しやすい |
筋肉疲労はさまざまな要因で引き起こされます。疲労を抱えたまま、筋肉に負担を与え続けるのは危険です。
ふくらはぎの筋肉に対して、オーバーユース(使いすぎ)や十分な休息を与えていないことが重なることで筋繊維が切れ、肉離れが起こります。
筋肉疲労を引き起こさないためには、運動後に軽いストレッチや、クールダウンを習慣化するのが大切です。
また、脚に少しでも違和感を感じた場合は運動を中断し、アイシングなどで対策しましょう。
準備運動不足
| 準備運動の役割 | 効果 |
|---|---|
| 筋肉の温度上昇 | 筋肉の柔軟性が高まり、収縮と伸張がスムーズになり、急激な動作への耐性が向上し、肉離れのリスクが低下 |
| 関節の可動域拡大 | 関節の可動域が広がり、動作範囲が広がることで筋肉への負担が分散され、肉離れのリスクを軽減 |
| 神経の活性化 | 神経系が活性化し、筋肉の協調性が高まることで動作がスムーズになり、筋肉への負担が軽減 |
準備運動を十分に行わず、急な走り込みや脚の使い込みも肉離れを引き起こす原因になります。
準備運動は筋肉や関節を温め、柔軟性を向上させてくれますが、準備運動が十分に行われていない場合、筋肉に過度な負担がかかりやすくなり、肉離れを起こすリスクが高くなります。
普段運動が習慣化されていない人は、筋肉が硬直しやすいので、入念な準備運動を心がけることが大切です。
加齢
加齢によって筋肉の力が弱まり、柔軟性が失われることで、肉離れ(ふくらはぎ)を引き起こす原因になります。
また、加齢によって血管が硬くなり、筋肉への血液を流す力も減少し、筋肉への酸素や栄養の供給が滞り、修復機能が低下します。
加齢による筋肉量の減少を予防するには、無理のないトレーニングや軽い運動の習慣化が大切です。
症状の再発
肉離れ(ふくらはぎ)は過去に経験歴があると、再発しやすい症状です。
再発の理由としては、損傷した筋繊維は瘢痕組織(はんこんそしき)と呼ばれる硬い組織に置き変わります。
硬い組織に置き換えることで、柔軟性や伸縮性が低くなり、再発しやすくなります。
再発を防ぐために正しいフォームなどを意識し、負担が偏らないようにしましょう。
肉離れ(ふくらはぎ)の前兆
肉離れ(ふくらはぎ)には前兆があります。
- 筋肉の違和感や張り感
- 筋肉の疲労感
- 筋肉の痙攣
肉離れの前兆を解説します。
筋肉の違和感や張り感
ふくらはぎの肉離れは運動中に負荷がかかり、発症するケースが多いです。しかし、前兆として普段とは違うふくらはぎに違和感や張りを感じることがあります。
筋肉に普段感じない違和感や張り感が現れた場合は運動を中止し、安静やアイシングを行います。
また、症状が改善せずに悪化するようであれば、医療機関を受診しましょう。
筋肉の疲労感
ふくらはぎの肉離れの前兆として、筋肉の疲労感が挙げられます。筋肉疲労は筋肉が悲鳴を挙げており、柔軟性や強度が低下してる状態です。
筋肉の疲労感を無視して運動を行うと、肉離れを起こすリスクがあります。
いつもより筋肉にだるさを感じる場合は、無理な運動はせずに安静や軽いストレッチを行いましょう。
また、筋肉を温められる入浴なども有効です。筋肉の疲労感が数日続くようであれば、医療機関の受診をおすすめします。
筋肉の痙攣
痙攣は筋肉が異常な収縮を起こしている状態です。筋肉の痙攣が起きている状態は、ミネラルバランスの乱れや筋肉疲労を起こしているサインです。
筋肉の痙攣が起きた場合は、すぐに運動を中止し、適切な休息や水分補給などを行い、筋肉の状態を正常に戻すことが最優先です。
痙攣の症状が頻繁に起こる場合は、医療機関を受診しましょう。
ふくらはぎの肉離れは歩ける場合でも油断は禁物です!
ふくらはぎの肉離れの症状が軽度であれば、歩ける場合があります。しかし歩けるからといって油断は禁物です。
ふくらはぎの肉離れは、適切な治療を怠ると以下のリスクがあります。
- 放置すると重症化するリスク
- 症状が良くなるまでに時間がかかる
- 内出血や腫れが遅れて現れることがある
起こりうるリスクについて解説します。
放置すると重症化するリスク
ふくらはぎの肉離れは、歩行可能な状態でも放置すると重症化するリスクがあります。
適切な処置や治療が遅れると後遺症として、筋肉の修復が不完全になり、慢性的な違和感や機能障害が残る可能性が高いです。
また不完全な修復は、筋肉の微弱性を高めるため、再発のリスクがあります。
軽度でも自己判断はせず、応急処置を行い、医療機関を受診しましょう。
症状が良くなるまでに時間がかかる
ふくらはぎの肉離れは、軽度の症状でも初期段階で適切な対応を怠れば、症状がよくなるまでに時間がかかります。
損傷した筋繊維は、瘢痕組織(はんこんそしき)と呼ばれる硬い組織に置き変わるため、伸展性や収縮性が低下します。
そのため、負荷のかかる動きには耐えにくい組織に切り替わるので、再発しないよう注意が必要です。
自己判断はせず、医師の指示に従い適切な治療を受けることで、早期回復につながります。
内出血や腫れが遅れて現れることがある
肉離れの症状は個人差も大きく、内出血や腫れが出るタイミングも人それぞれであり、遅れて症状が現れた場合でも、自己判断は禁物です。
内出血や腫れが遅れて出る理由は、組織損傷後の炎症反応が時間をかけて進行するためです。
進行のスピードは人それぞれであり、肉離れを起こした時点で内出血や腫れが現れる人もいれば、遅れて症状が出る人もいます。
歩けるからといって無理すると、後から内出血や腫れの症状がでる可能性があるため、早い段階での適切な対応が大切です。
ふくらはぎの肉離れを起こしたときの対策
ふくらはぎの肉離れを起こしたときは、焦らずに対策しましょう。
- 安静にする
- 応急処置を行う
- 適切なリハビリを行う
- 症状の再発を防止する
- 再生医療(PRP療法)
ふくらはぎの肉離れを起こしたときの対策を解説します。
安静にする
ふくらはぎの肉離れを起こした場合は、安静にしましょう。肉離れを起こしたときはすぐに運動を中止し、必要に応じて冷却などを行います。
RICE処置(安静(Rest)・冷却(Ice)・圧迫(Compression)・患部を心臓より上に上げる(Elevation))の流れの1つであり、一時的な処置として効果的な手法です。
発症してから数日間は受傷部を保護する必要があるので、おおよそ3〜5日は安静にする必要があります。
安静期間は症状の程度によって異なるため、自己判断はせず医師の指示に従いましょう。
応急処置を行う
| 処置 | 詳細 | 目的 |
|---|---|---|
| 安静 (Rest) | 患部を動かさない | 症状の悪化を防ぐ |
| 冷却 (Ice) | 保冷剤をタオルで包み15~20分冷やす(1日数回) | 腫れと炎症を抑える |
| 圧迫(Compression) | 包帯などで患部を圧迫 | 内出血と腫れを抑える |
| 挙上(Elevation) | 患部を心臓より高い位置に | 腫れを軽減する |
ふくらはぎの肉離れが起きたときに有効なのが、RICE処置:安静(Rest)・冷却(Ice)・圧迫(Compression)・挙上(Elevation)です。
肉離れを起こした初期の段階ではRICE処置が有効であり、とくに安静(Rest)と冷却 (Ice)が大切です。
冷却 (Ice)を行う際は、冷やしすぎると凍傷になる可能性があります。保冷剤をタオルなどで包み、数秒に一回は肌から離すなど工夫しましょう。
また、圧迫 (Compression)も力任せではなく、加減を調整しながら行います。圧迫時にしびれや変色を起こした際はすぐに緩めることが大切です。
あくまでも応急処置のため、症状が改善しない場合は医療機関への受診が必要です。
適切なリハビリを行う
| 内容 | 目的 | 効果 |
|---|---|---|
| 瘢痕組織の改善 | 柔軟性向上 | 正常な筋肉に近づける |
| 筋力と柔軟性の回復 | 機能回復 | 日常生活・運動への復帰 |
| 筋力バランスの調整 | バランス改善 | 再発リスク軽減 |
| 再発防止 | 筋肉の状態回復 | 運動再開を目指す |
安静にすると同時に適切なリハビリが大切です。リハビリでは、瘢痕組織の改善や筋力バランスの調整を行い、症状の改善を目指していきます。
リハビリは自己判断ではなく医師指導のもと、無理のない範囲で行うのが大切です。
症状の再発を防止する
ふくらはぎの肉離れは再発の可能性が高いので、再発を防止する必要があります。
再発を防ぐには適切なリハビリや休息、食生活のバランスが大切です。
筋肉の修復を考え、無理な運動は控え、食事はタンパク質(鶏肉・魚・卵・豆類・ナッツ・乳製品など)や、ビタミンC、ビタミンE、オメガ3脂肪酸などを含む食事を中心に行いましょう。
肉離れはクセになりやすい症状なので、油断は禁物です。
再生医療(PRP療法)
ふくらはぎの肉離れに対して、PRP療法(多血小板血漿療法)は有効な手段です。
PRP療法(多血小板血漿療法)は、患者様自身から採取した血液から、多血小板血漿(Platelet-Rich Plasma:PRP)を抽出します。
抽出した多血小板血漿(Platelet-Rich Plasma:PRP)を肉離れで起きた損傷部位に注射し、症状改善を目指します。
手術を必要としない上に副作用のリスクもほとんどありません。最短30分で施術が完了します。
短い時間で対応かつ通院だけで行えるため、スポーツ選手にも効果的な療法です。
以下の記事では再生医療(PRP療法)について、詳しく解説しています。
ふくらはぎに肉離れの疑いを感じたら医療機関を受診しよう
ふくらはぎに肉離れの疑いを感じたら、自己判断はせず医療機関を受診しましょう。
症状が軽いと歩ける場合もありますが、放置してしまうと症状が悪化し、後遺症が出る可能性があります。
ふくらはぎの肉離れを重症化させないためにも応急処置は適切に行い、軽度だったとしても、医療機関で診察を受けることが大切です。
肉離れの症状が辛い方は当院「リペアセルクリニック」にご相談ください。再生医療で組織の修復をサポートします。
ふくらはぎの肉離れでお悩みの方は、「メール」もしくは「オンラインカウンセリング」にてお気軽にお問い合わせください。