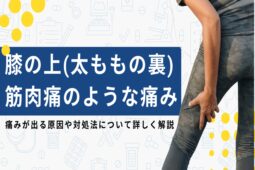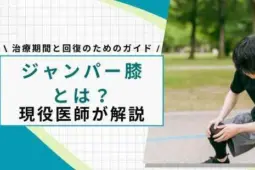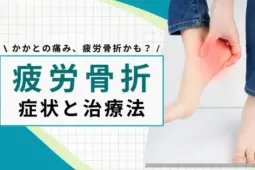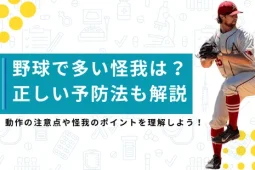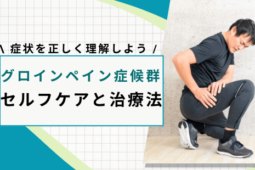- 下肢(足の障害)
- スポーツ外傷
肉離れの原因とは?具体的な症状と対処法を解説【医師監修】
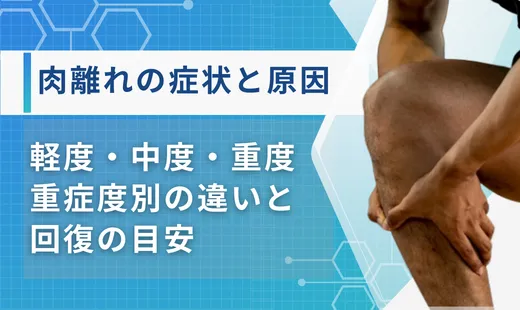
スポーツ中や日常生活の何気ない動作で、急に筋肉に痛みが走ったことはありませんか。
その痛みは、筋肉に強い負担がかかったことで起こる「肉離れ」かもしれません。
肉離れは、筋肉が部分的に損傷することで発生するケガです。
症状の程度には軽いものから重いものまで幅があり、無理をすると回復の遅れや再発を繰り返すおそれもあります。
この記事では医師監修のもと、肉離れの状態や重症度ごとの症状、回復までの流れについて解説します。
肉離れの症状の見方や、判断の目安を知るための参考にしてください。
当院「リペアセルクリニック」の公式LINEでは、再生医療に関する情報提供や簡易オンライン診断を行っています。
肉離れについて気になる症状がある方は、ぜひ一度公式LINEにご登録ください。
目次
肉離れとは?症状と損傷の仕組み
肉離れとは、筋肉に強い負担がかかることで筋肉の繊維が部分的に損傷してしまうケガで、主にスポーツ中の急な動きや、日常生活での無理な動作をきっかけに起こる場合があります。
正式には「筋挫傷(きんざしょう)」と呼ばれ、損傷の程度が大きい場合には「筋断裂」と表現されることもあります。
肉離れが起こると、動かした瞬間に鋭い痛みを感じるほか、筋肉を伸ばす動作や力を入れるときに痛みが強くなるのが特徴です。
症状の出方には個人差があり、軽い違和感で済む場合もあれば、腫れや内出血が現れ、歩くのがつらくなるケースもみられます。
なかには、痛みが出た瞬間に「プチッ」といった断裂音が聞こえることもあります。
とくに太ももやふくらはぎなど、日常的に大きな力がかかりやすい部位は負担を受けやすく、肉離れが起こりやすいとされています。
気になる症状が続く場合は、無理をせず、整形外科で専門医の診察を受けることを検討しましょう。
肉離れが起こる主な3つの原因
肉離れは、偶然起こるケガではなく、筋肉の状態や運動時の環境が重なることで発生しやすくなります。
肉離れが起こりやすくなる主な原因は、次の3つです。
- 疲労の蓄積や筋力バランスの乱れによる筋肉への過負荷
- ウォーミングアップ不足・柔軟性の低下
- 水分不足による筋肉の柔軟性低下
ここでは、それぞれの原因について詳しく解説します。
疲労の蓄積や筋力バランスの乱れによる筋肉への過負荷
激しい運動や筋力トレーニングを続けて行うと、筋肉の中では目に見えない細かな損傷が少しずつ蓄積していきます。
本来、筋肉は十分な休養によって修復・強化されますが、回復が追いつかないまま負荷の高い運動を続けると、耐久性が低下し、損傷しやすい状態になります。
そのため、肉離れのリスクを減らすには、運動と休養のバランスを意識することが大切です。
疲労がたまると筋肉の伸縮性や反応性が低下し、普段であれば問題のない動作でも、筋繊維が耐えきれずに損傷して肉離れにつながる場合があります。
また、筋力バランスが崩れると特定の筋肉に負荷が集中し、急な動作が加わった際に肉離れを起こしやすくなります。
十分な睡眠や休養に加えて、筋肉の回復を助ける栄養管理やこまめな水分補給を意識することも大切です。
ウォーミングアップ不足・柔軟性の低下
運動前にウォーミングアップを行わずに激しい運動を始めると、冷えた筋肉に急激な伸縮が加わり、筋繊維が耐えきれずに傷ついてしまう可能性があります。
柔軟性が低下している筋肉は、引き伸ばされた際に損傷しやすく、肉離れのリスクが高まります。
効果的なウォーミングアップとしては、軽いジョギングやスキップなど、徐々に負荷を高めていく動的なストレッチがおすすめです。
とくに、寒い時期や久しぶりに運動を再開する場合は、入念な準備運動が大切です。
水分不足による筋肉の柔軟性低下
体内の水分が不足すると、筋肉の働きにも大きな影響が出ます。
とくに暑い時期や長時間の運動では発汗量が増え、自覚がないまま水分不足に陥りやすいため注意が必要です。
水分不足になると血流が悪くなり、筋肉に必要な酸素や栄養が十分に届かなくなることで、疲労物質がたまりやすくなり、筋肉の柔軟性も低下します。
筋肉が硬くなると、伸び縮みがスムーズに行えなくなり、肉離れを起こすリスクが高まります。
肉離れを防ぐためには、運動前・運動中・運動後にこまめな水分補給を心がけることが大切です。
長時間の運動を行う場合は、ナトリウムや糖質を含むスポーツドリンクを活用すると、水分とともに失われやすい成分を補うことができます。
日頃からの水分管理は、筋肉のコンディションを保ち、肉離れを防ぐ基本です。
\無料オンライン診断実施中!/
肉離れの重症度の違い
肉離れは、主に太もも(大腿部)やふくらはぎ(腓腹筋)などの大きな筋肉に発生しやすく、筋肉の損傷の程度によって症状の現れ方や日常生活への影響が大きく異なります。
また、肉離れは症状の程度によって、軽度(Ⅰ度)・中度(Ⅱ度)・重度(Ⅲ度)の3段階に分けられ、それぞれ特徴や注意点が異なります。
筋肉別の肉離れの判別方法は以下のとおりです。
| 大腿四頭筋 | ハムストリングス | 腓腹筋 | |
|---|---|---|---|
| 軽度(Ⅰ度) | うつ伏せで膝を90度以上曲げられる | 仰向けで膝をまっすぐ伸ばし脚を70度位まで上げられる | アキレス腱を伸ばすと若干の痛みがある |
| 中度(Ⅱ度) | うつ伏せで膝を45度~90度曲げられる | 仰向けに寝て膝をまっすぐ伸ばし脚を30度~70度位まで上げられる |
アキレス腱を伸ばすと強い痛みがあり、膝を曲げた状態で行うと痛みが弱くなる |
| 重度(Ⅲ度) | うつ伏せで膝を45度位まで曲げられる | 仰向けに寝て膝をまっすぐ伸ばし脚を30度位まで上げられる | 膝を曲げた状態でもアキレス腱を軽く伸ばしただけで強い痛みがある つま先立ちができない |
ここでは、肉離れの重症度ごとの特徴や症状の違いについて、解説します。
軽度(Ⅰ度)の特徴
軽度(Ⅰ度)の肉離れは、筋肉の一部に小さな損傷が起きている状態です。
動かしたときに痛みや違和感を覚えることはありますが、安静にしている間は痛みが落ち着く場合も多く見られます。
上記表にもあるように、関節の動きはある程度保たれていることが特徴です。
腫れや内出血は目立たないか、出ても軽度である場合が多く、日常生活への影響も比較的少ない傾向があります。
ただし、痛みがある状態で無理に運動を続けると悪化する可能性があるため、軽症であっても注意が必要です。
中度(Ⅱ度)の特徴
中度(Ⅱ度)の肉離れは、筋肉の一部がはっきりと損傷している状態です。
動かした際に強い痛みが出やすく、関節の可動域が制限され、腫れや内出血が現れる場合もあります。
運動や強い負荷をかける動作は行いにくく、無理をすると症状が長引いたり、再発につながるおそれがあります。
痛みの程度や動かしにくさが続く場合は、早めに医療機関での診察を検討することが大切です。
重度(Ⅲ度)の特徴
重度(Ⅲ度)の肉離れでは、筋肉が大きく損傷している、もしくは完全に断裂している状態が考えられます。
安静にしていても強い痛みが続くことがあり、関節を動かすこと自体が難しくなるケースも少なくありません。
また、明らかな腫れや内出血が見られる場合もあります。
症状が疑われる場合は自己判断せず、整形外科医の診察を受けてください。
\無料オンライン診断実施中!/
肉離れになった時の対処法は?
肉離れが疑われる場合は、受傷直後の対応によって、その後の回復スピードや再発リスクが大きく変わります。
誤った対処をすると、痛みが長引いたり再発を招くおそれがあります。
ここでは、肉離れを起こした際の対処法について解説します。
肉離れになったら「RICE処置」で応急対応
肉離れを起こした直後の応急的な対応として、一般的に知られているのが「RICE処置」と呼ばれる方法です。
RICE処置は、Rest(安静)・Icing(冷却)・Compression(圧迫)・Elevation(挙上)の4つの処置の頭文字から名付けられており、受傷後できるだけ早い段階で行うことで、内出血や腫れ、痛みを抑え、回復を助ける効果が期待できます。
具体的なRICE処置の内容は、以下のとおりです。
【RICE処置】
- Rest(安静):損傷した部位への負担を最小限に抑え、炎症の広がりを防ぎます
- Icing(冷却):患部を水や氷で冷やし、腫れや内出血を抑えます
- Compression(圧迫):弾性包帯やテーピングで適度に圧迫し、腫れを抑えます
- Elevation(挙上):損傷部位を心臓より高い位置に保ち、腫れの軽減を図ります
ただし、RICE処置はあくまで受傷直後の応急対応です。
急性期を過ぎた受傷後数日以降は、回復状況を確認しながら、専門家の指導のもとで段階的にリハビリへ移行することが重要です。
痛みの再発がないことを確認しつつ、慎重に活動量を調整していきましょう。
肉離れになった時にやってはいけない行動
肉離れを起こした直後に無理な動作を行うと、炎症が強まり、症状の悪化や回復の遅れにつながるおそれがあります。
痛みがある状態で無理に動かしたり、我慢して運動を続けるなどの行為は避けましょう。
また、自己判断によるマッサージや、十分に回復しないまま運動を再開する行為は注意が必要です。
損傷した筋肉に刺激を与えると、炎症が強まり、再発のリスクが高まる可能性があります。
違和感や痛みが残っている場合は、無理をせず慎重に対応しましょう。
医療機関を受診した方がよいケース
肉離れが疑われる場合でも、症状の程度によっては医療機関での診察が必要になります。
とくに、強い痛みで歩行や日常動作が難しい場合や、腫れや内出血がはっきりと現れている場合は、早めの受診を検討しましょう。
また、数日経っても痛みが改善しない、あるいは悪化した場合や、肉離れを何度も繰り返している場合も注意が必要です。
重症度の判断に迷う場合は、整形外科を受診し、専門医の診察を受けましょう。
肉離れの検査と診断
肉離れの状態を正確に把握するためには、複数の検査を組み合わせた診断が行われます。
なかでも、筋肉の損傷状態を詳しく確認できるのがMRI検査です。
MRI検査では、損傷した筋繊維や周囲の組織の状態を画像で確認できるため、断裂の程度や範囲を正確に評価できます。
また、超音波検査(エコー)は、リアルタイムで筋繊維の断裂や血のかたまり(血腫)の有無を確認できる検査です。
短時間で行えるうえ、身体への負担が少ない検査として広く活用されています。
必要に応じて、骨の異常がないかを確認するためにレントゲン検査が行われることもあります。
画像検査に加え、医師による触診も重要な判断材料です。
痛みの部位や腫れの範囲、筋肉の状態などを総合的に評価し、検査結果をもとに適切な治療方針や回復までの見通しが立てられます。
\無料オンライン診断実施中!/
肉離れの治療|回復までの流れと期間の目安
肉離れの治療や回復までにかかる期間は、筋肉の損傷の程度によって大きく異なります。
初期対応とリハビリを適切に行えば、回復を早め、再発を防ぎやすくなります。
ここでは、肉離れの回復の流れと期間の目安を重症度別に解説します。
軽度(Ⅰ度)の回復までの流れ
軽度の肉離れは筋肉の損傷が小さいため、適切な対応を行えば数日から数週間で症状が改善します。
痛みが軽減すれば、日常生活への影響も比較的少なく、早期に通常の生活へ戻れる場合があります。
治療の基本は患部の安静を保ち、必要に応じて冷却やテーピングなどで負担を軽減することです。
痛みが和らいできた段階で、軽いストレッチなどから少しずつ体を動かしていくと、回復を進めやすくなります。
中度(Ⅱ度)の回復までの流れ
中度の肉離れでは、筋肉に明らかな損傷があり、回復までに数週間から1カ月以上かかる場合があります。
この段階では、一定期間の安静と計画的なリハビリが必要になります。
痛みが落ち着いた後も、いきなり運動を再開するのではなく、ストレッチや軽い運動から段階的に負荷を上げていくことが大切です。
無理をすると再発しやすいため、症状の様子を見ながら慎重に進めましょう。
重度(Ⅲ度)の回復までの流れ
重度の肉離れは、筋肉の損傷範囲が大きく、日常生活にも支障が出やすい状態です。
安静にしていても痛みが強く、回復までに2〜3カ月以上かかるケースもあります。
この場合の治療は、安静や薬の使用などの保存的治療に加え、運動機能の回復を目的として手術が検討される場合もあります。
治療後は専門医の判断のもとでリハビリを進め、筋力や柔軟性を少しずつ取り戻していくことが重要です。
重度の肉離れが起こった際は、自己判断を避け、医療機関での継続的なフォローを受けながら回復を目指しましょう。
\無料オンライン診断実施中!/
肉離れを防ぐために日常で意識したいこと
肉離れは、特別な対策だけでなく、日常の習慣を見直す意識が予防につながります。
肉離れを防ぐために、普段の日常に以下の方法を組み合わせてみましょう。
- 運動前のウォームアップ
- 筋肉のバランスを整える
- 栄養摂取と休息
- 十分な水分補給
まず、運動前にはウォームアップを行い、筋肉を十分に温めてください。
筋肉の柔軟性が高まると、急な動きや強い負荷にも対応しやすくなります。
運動後には軽いクールダウンを取り入れると、筋肉の緊張が和らぎ、疲労の蓄積を防ぎやすくなります。
こうした運動後のケアに加えて、日常的なトレーニングやストレッチで筋肉の柔軟性や筋力バランスを整える意識も重要です。
特定の筋肉に負荷が集中しない体づくりを心がけると、突発的な動作による肉離れのリスクを抑えやすくなります。
また、筋肉の回復と強化には、適切な栄養摂取と十分な休息が欠かせません。
タンパク質やビタミンなどを意識した食事と、しっかりとした睡眠を心がけると、筋組織の修復がスムーズに進みます。
あわせて意識したいのが、日頃からの水分補給です。
体内の水分が不足すると筋肉の柔軟性が低下し、疲労もたまりやすくなります。
運動時だけでなく、普段の生活でもこまめに水分を補給し、筋肉のコンディションを整えることを意識しましょう。
【FAQ】肉離れに関するよくある質問
肉離れとこむら返りの違いは何ですか?
肉離れは運動中や急激な動作時に痛みが発生しますが、こむら返りは、筋肉が一時的に強く収縮することで起こる症状です。
肉離れでは、内出血や腫れが見られる場合がありますが、こむら返りには通常目に見える変化はありません。
肉離れは何科を受診するべきですか?
肉離れは通常、整形外科の受診をおすすめします。
症状が重い場合やスポーツ中の急な痛みを伴う場合は、とくに受診が必要です。
スポーツ医学を専門とする整形外科医がいる病院を選ぶとより専門的な治療が受けられます。
寝てる時でも肉離れは発症しますか?
一般的に、肉離れは急激な動作や過度な負荷がかかることによって発生しますが、寝ている間に発症する場合もあります。
身近なものでは、起床時に首から肩にかけて痛みが出る寝違えです。
睡眠中、頭部が中央からずれることで、前後左右どちらかの筋肉の血流が止まり、強い凝りが発生します。
起床時に急に動くことで、凝った筋肉に刺激が加わり、症状が発症する場合があります。
寝違えなどの症状が発生し強い痛みを感じた場合は、自己対処せずに専門家に相談しましょう。
\無料オンライン診断実施中!/
まとめ|肉離れは症状に合わせた対応が大切
肉離れは、筋肉に強い負荷がかかることで起こり、損傷の程度によって症状や回復までの期間が異なります。
軽い痛みで済む場合もあれば、腫れや内出血を伴い、日常生活に影響をきたす場合もあります。
受傷直後はRICE処置などの応急対応を行い、痛みが強い場合や判断に迷う場合は医療機関の受診を検討してください。
無理に動かすと回復が遅れ、再発につながるおそれがあるため、症状の経過を確認しながら対応することが大切です。
また、日頃からウォーミングアップや水分補給、休養を意識し、筋肉の状態を整えておくことも予防につながります。
痛みや違和感が続く場合は、無理をせず専門医に相談しましょう。