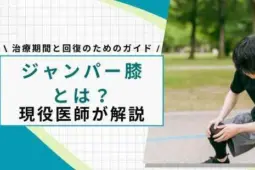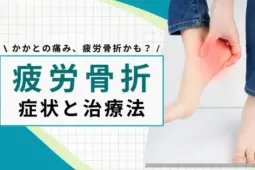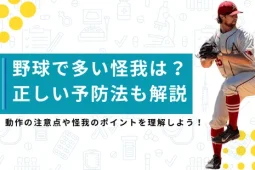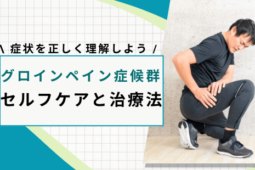- 下肢(足の障害)
- スポーツ外傷
肉離れの応急処置を医師が解説|RICEの手順と受診目安・再発予防を解説
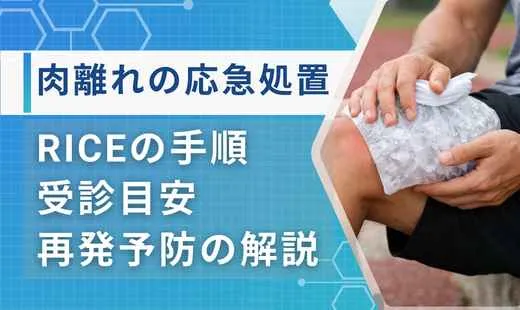
「運動中に突然、太ももやふくらはぎに強い痛みが走った」
「これって肉離れ?まず何をすれば良いのかわからない」
このような不安を感じていませんか。
肉離れは、スポーツ中だけでなく、日常の動作や準備不足の状態でも起こることがあります。
発症直後の対応を誤ると、痛みや腫れが長引いたり、治ったと思っても再発しやすくなったりするため、初期の応急処置がとても重要です。
本記事では、肉離れが疑われるときにまず行うべき応急処置(RICEの基本)から、受診の目安、回復までの流れ、再発を防ぐためのポイントまでを、医師の視点でわかりやすく解説します。
「正しい対処法を知って、できるだけ早く回復したい」という方は、ぜひ参考にしてください。
また、当院「リペアセルクリニック」の公式LINEでは、再生医療に関する情報提供と簡易オンライン診断を実施しております。
肉離れについて気になる症状がある方は、ぜひ一度公式LINEにご登録ください。
目次
肉離れの応急処置は「まず悪化を防ぐ」のが目的
肉離れは筋肉が強い力で伸ばされたり、部分的に断裂したりした状態で、急な痛みと腫れ、内出血を伴います。
とくに発症直後は組織が不安定なため、不用意に動かしたり刺激を与えたりすると損傷が広がり、回復が遅くなってしまうリスクがあります。
そのため、応急処置ではまず「悪化を防ぐこと」が重要です。
痛みを感じる部分を無理に動かしたり、熱を加えたりする行為は、腫れや炎症を増大させ、回復を妨げるおそれがあります。
まずは炎症が強い時期(ケガをしてから24~72時間程度)に症状を落ち着かせることを優先し、適切な処置につなげることが大切です。
肉離れ直後にやってはいけないこと
肉離れ直後は、以下のような対応を避けてください。
- 無理に動かす・動かし続ける
- 強いストレッチやマッサージをする
- 熱を加える行為(入浴、温熱パックなど)
- 過度な飲酒や激しい運動
痛みがある場所を使い続けると、損傷した筋繊維がさらに引き伸ばされ、状態が悪化する可能性があります。
また、炎症が起きている時期に過度なストレッチや圧力をかけると、損傷部位に強い負担がかかり、回復が遅れるおそれがあります。
発症直後に熱を加えたり飲酒をしたりすると血流が増え、腫れや内出血が悪化する可能性があるため注意しましょう。
応急処置の基本「RICE処置」
応急処置で広く用いられてきたのがRICE処置です。
これは、筋肉や靭帯の急性損傷に対する初期対応として世界的に知られている方法で、次の4つの手順の頭文字から名付けられています。
- Rest(安静)
- Icing(冷却)
- Compression(圧迫)
- Elevation(挙上)
スポーツ現場や医療現場でも広く用いられており、肉離れの応急対応として基本となる考え方です。
【RICE】肉離れの応急処置4ステップ
RICE処置は肉離れの初期対応として基本とされています。
これはRest(安静)、Icing(冷却)、Compression(圧迫)、Elevation(挙上)の頭文字を取った言葉です。(文献1)
ケガをした直後にRICE処置を適切にすれば、症状の悪化を防ぎ、回復を促す効果が期待できます。
医療機関を受診する前に、まずはこの基本的な処置をしましょう。
ここからはRICEの4つの処置について、詳しく説明していきます。
Rest(安静)
肉離れを起こした際、重要な処置の一つが安静です。
安静とは、損傷した筋肉を無理に動かさずに十分に休ませることを意味します。
肉離れは筋繊維の部分的な断裂や損傷が起こっている状態です。
さらに筋肉を使い続けると、断裂箇所が大きくなり、より深刻な損傷へと進行する恐れがあります。(文献1)
つまり、軽度の肉離れが中度や重度へと悪化する可能性が高まるのです。
安静を保つことで、傷ついた筋繊維が自然治癒するための準備を整えられます。
受傷直後の数日間は、痛みのある動作を避け、患部への負担を最小限に抑えることで回復へ近づきます。
医師の指示に従いながら、適切な安静期間を設けましょう。
Icing(冷却)
肉離れが発生すると、筋繊維の断裂によって組織が炎症を起こし、腫れや内出血が生じます。
このとき冷却をすると、症状を効果的に抑えられます。
冷却には血管を収縮させる作用があり、出血量の軽減、腫れの抑制、痛みの緩和に効果的です。
受傷後できるだけ早く冷却を始めましょう。
具体的な冷却方法としては、氷や保冷剤をビニール袋に入れ、薄いタオルで包んでから患部に当てます。
直接皮膚に氷を当てると凍傷のリスクがあるため、必ず布などを間に挟みましょう。
1回のアイシングは15~20分程度が目安で、その後は再び痛くなったら冷却を数回繰り返します。(文献2)
長時間の連続冷却は避け、適度な間隔を空けることが大切です。
受傷後24〜48時間は冷却がとくに効果的ですが、その後も痛みや腫れが続く場合は継続してみましょう。(文献3)
Compression(圧迫)
肉離れを起こした筋肉には、適切な圧迫処置が効果的です。
テーピングや弾性包帯を使って患部に適度な圧力をかけると、内出血や腫れの進行を抑制できます。
圧迫は毛細血管からの出血を最小限に抑え、過剰な浮腫(むくみ)を防ぐ働きがあります。
あくまで一例ですが、太ももの肉離れの場合、具体的な圧迫方法としてはまず弾性包帯とパットが必要です。
包帯を巻く前に、患部が清潔で乾いていることを確認してください。
パッドを患部に当て、弾性包帯でらせん状に巻いていきます。
圧迫は強すぎず弱すぎない適度な強さで行います。
血行不良の兆候(しびれ、皮膚の色の変化、冷感など)が現れた場合は、すぐに緩めましょう。(文献3)
Elevation(挙上)
肉離れが発生した場合、患部を心臓より高い位置に保つ挙上をしましょう。
挙上すると、心臓に向かって血液が流れるため、腫れや炎症を効果的に抑制できます。
具体的な挙上方法としては、太ももの肉離れの場合、仰向けに寝た状態で患部の下に枕やクッションを何個か重ねて配置し、脚全体が心臓より高くなるようにします。
ソファや椅子に座る場合は、別の椅子やスツールを使って脚を高く上げるようにしましょう。(文献3)
挙上は腫れが続く限り、可能な限りの継続が望ましいです。
就寝時も枕を使って患部を少し高くすると、夜間の腫れを軽減できます。
他のRICE処置(安静・冷却・圧迫)と組み合わせると、肉離れの回復には効果的です。
ただし、痛みを伴う無理な姿勢での挙上は避けましょう。
湿布・テーピングは肉離れの応急処置として有効か?
肉離れを起こしたとき、「とりあえず湿布を貼る」「テーピングで固定すれば良い」と考える方は少なくありません。
しかし、湿布やテーピングは正しく使わなければ、応急処置として十分な効果が得られないこともあります。
ここでは、湿布とテーピングの役割や注意点、RICE処置との違いについて解説します。
湿布は「冷却」ではない
肉離れの応急処置として「冷湿布を貼れば冷やしたことになる」と思われがちですが、湿布はRICE処置における「Icing(冷却)」の代わりにはなりません。
湿布の主な役割は以下のとおりです。
- 痛みや炎症を和らげる「消炎鎮痛」
- ひんやりした感覚による「冷感刺激」
つまり、湿布は皮膚表面に冷たく感じさせる作用はありますが、筋肉の深部までしっかり冷却して血流を抑える効果は、ほぼありません。
そのため、
1.受傷直後は、まず氷や保冷剤でしっかり冷却(アイシング)を行う
2.その後の痛みや炎症のケアとして湿布を使う
という順番が望ましいといえます。
湿布だけで応急処置を済ませてしまうと、腫れや内出血の抑制が不十分になる可能性があるため注意しましょう。
テーピング・包帯固定の考え方
テーピングや包帯固定は、肉離れの応急処置において「圧迫」と「安定」の補助として有効です。
ただし、目的を理解して使うことが大切です。
テーピング・包帯の主な役割は以下のとおりです。
- 患部を適度に圧迫し、腫れや内出血を抑える
- 筋肉の動きを制限し、再損傷を防ぐ
- 不安定感を軽減し、安心して安静を保てるようにする
一方で、次のような使い方には注意が必要です。
- 強く巻きすぎて血流を妨げる
- 固定したまま無理に動いてしまう
- テーピングをしているから大丈夫と運動を続ける
テーピングや包帯は、「治すため」ではなく「悪化させないための補助」と考えるのが基本です。
あくまでRICE処置の「Compression(圧迫)」と「Rest(安静)」を支える手段として使いましょう。
圧迫はいつまで必要?外すタイミングの目安
圧迫は、肉離れ直後の腫れや内出血を抑えるために重要ですが、ずっと続ければ良いわけではありません。
一般的な目安は以下のとおりです。
圧迫が必要な時期
- 受傷直後〜腫れや熱感が強い間(目安として24〜48時間程度)
- 動かすとズキズキ痛む時期
- 明らかな腫れや内出血が広がっている間
圧迫を緩める・外す目安
- 腫れや熱感が落ち着いてきた
- 安静時の痛みが軽くなってきた
- 圧迫しなくても不安定感がなくなった
また、圧迫中に次のような症状が出た場合は、すぐに緩めるか中止してください。
- しびれや強い違和感
- 皮膚の色が紫や白っぽくなる
- 冷感が強くなる
圧迫は「腫れを抑えるための一時的な処置」であり、回復段階に入ったら、必要以上に続けず、動かしながら治すことへ移行するのも重要です。
不安がある場合は、自己判断せず医療機関で相談しましょう。
病院に行くべき肉離れのサイン
肉離れは軽度であれば自宅での安静や応急処置で回復するケースもあります。
しかし、すべての肉離れが自己対応で済むわけではありません。
中には、重症化していたり、他のケガが隠れていたりするケースもあるため、「病院に行くべきかどうか」を見極めることが非常に重要です。
ここでは、医療機関を受診すべき症状と、受診する診療科の目安について解説します。
受診が必要な症状
次のような症状がある場合は、自己判断せず、早めに医療機関を受診しましょう。
重症の可能性が高い症状
以下のような場合は、中等度〜重度の肉離れや筋断裂が疑われるため、できるだけ早い受診が必要です。
- 痛みが非常に強く、歩行が困難、またはまったく動かせない
- 受傷直後から腫れや内出血が急激に広がっている
- 筋肉が「へこんでいる」「割れている」ように見える
- 力を入れようとしてもまったく入らない
- 受傷時に「ブチッ」「パチン」といった断裂音を感じた
- 安静にしていても痛みが改善しない、むしろ悪化している
これらは、筋繊維の大きな損傷や断裂が起きている可能性があるサインです。
放置すると回復が遅れるだけでなく、後遺症や再発につながるおそれもあります。
放置すると長引く・再発する可能性が高いケース
以下のような場合も、「軽い肉離れだから大丈夫」と自己判断せず、早めの受診が望ましいケースです。
- 数日経っても痛みや腫れがほとんど引かない
- 軽いと思っていたが、動かすたびに強い痛みが出る
- スポーツや仕事に復帰する必要があり、正確な診断が必要な場合
- 同じ部位を何度も肉離れしている(再発を繰り返している)
とくに再発を繰り返している場合は、
「筋肉に瘢痕(はんこん)と呼ばれる硬い組織が残っている」
「回復が不十分なまま復帰している」
といった可能性も考えられ、専門的な評価やリハビリが必要になることがあります。
歩けるから大丈夫と自己判断せず、違和感が長引く・不安がある場合は早めの受診が安心です。
肉離れは何科を受診する?
肉離れが疑われる場合、基本的には「整形外科」の受診がおすすめです。
整形外科
- 肉離れ・捻挫・打撲など運動器のケガ全般に対応
- エコー(超音波)やMRIで筋肉の損傷度を確認できる
- 重症度に応じた治療・リハビリ指導が受けられる
まず迷ったら整形外科が第一選択です。
スポーツ整形外科・スポーツクリニック
- アスリートや運動習慣のある方にとくにおすすめ
- 競技復帰を見据えたリハビリ・再発予防まで対応可能
肉離れは「筋肉・腱・靭帯」といった運動器の損傷であるため、内科や一般外科ではなく、運動器専門の整形外科が適切な診療科となります。
肉離れの応急処置後に必要な治療と回復の流れ
肉離れの早期回復・再発防止のためには、応急処置を行ったあとも適切な治療と回復過程を踏むことが大切です。
肉離れの治療の基本は、安静と患部への負担軽減です。
痛みを感じる動作は避け、損傷した筋肉が自然に修復される環境を整えます。
痛みや炎症が強い場合には、医師の判断のもとで
- 消炎鎮痛作用のある湿布や塗り薬
- 内服薬(鎮痛薬・消炎薬)
などが用いられることがあります。
これらは痛みや炎症を和らげるための補助的な治療であり、筋肉そのものを治す治療ではない点も理解しておきましょう。
痛みや腫れが落ち着いてきたら、徐々にストレッチやリハビリを開始します。
この段階で適切な運動療法を行わず、いきなり元の運動に戻ると再発しやすくなるため注意が必要です。
筋肉の柔軟性と筋力を回復させながら、段階的に運動強度を上げていくことが大切です。
また、肉離れの回復期間は、重症度によって異なります。
- 軽度:1〜2週間程度
- 中等度:3〜6週間程度
- 重度:2カ月以上かかることもある
とくに中等度以上の場合は、4週間前後を目安に治療とリハビリが必要になるケースが多いとされています。(文献4)
また、近年では、通常の治療で改善が乏しい場合や、早期復帰を目指すアスリートを中心に、幹細胞治療やPRP療法(多血小板血漿療法)などの再生医療が注目されています。
再生医療とは、損傷した組織や細胞に対して、自分自身の幹細胞や血液を用いる治療法です。
幹細胞治療では、幹細胞がさまざまな種類の細胞に変化する「分化能」という能力を活かし、PRP療法は血小板に含まれる成長因子などが損傷した組織の修復を促進する働きを活用します。
当院「リペアセルクリニック」の公式LINEでは、再生医療の情報提供と簡易オンライン診断を実施しております。
肉離れについて気になる症状がある方は、ぜひ一度公式LINEにご登録ください。
\無料オンライン診断実施中!/
肉離れの再発予防
肉離れは一度起こすと、同じ部位で繰り返しやすいケガとして知られています。
とくに、回復が不十分なまま運動を再開した場合や、筋肉の柔軟性・筋力が十分に戻っていない場合には、再発リスクが高まるのです。
しかし、日常生活や運動前後の意識を少し変えることで、肉離れは予防・再発防止が可能なケガでもあります。
ここからは、肉離れを防ぐために心がけたいポイントを、具体的に解説していきます。
身体を温める
肉離れを予防するには、筋肉の冷えを防ぐことが重要です。
体温が低下すると筋肉も冷えてしまい、柔軟性や弾力性が失われて伸縮性が低下します。
このような状態で急に強い力をかけたり、無理な動きをしたりすると、筋繊維が断裂して肉離れを起こしやすくなります。
冬場や冷房の効いた室内、運動前の体が十分に温まっていない状態では注意が必要です。
予防のためには、運動前の十分なウォームアップが欠かせません。
具体的には、軽いジョギングやその日使う筋肉を意識した動的ストレッチが効果的です。
また、日常的に適切な服装で体を冷やさないよう心がけ、入浴での全身の血行促進も効果的です。
運動時には保温性のある適切なウェアを着用し、屋外での活動時には天候や気温に合わせた服装を心がけましょう。
体を温めると筋肉の柔軟性が保て、肉離れのリスクを軽減できます。
十分にストレッチをする
肉離れの主な原因の一つに、運動前の準備不足が挙げられます。
日頃から運動習慣がない方は筋肉が硬くなっており、急に激しい動きをすると筋繊維が断裂しやすくなります。
運動不足の状態から突然激しい運動をすると、肉離れのリスクを大幅に高めることになるでしょう。
肉離れのリスクを軽減するには、運動前に適切なストレッチをして、筋肉を十分にほぐすことが重要です。
ストレッチにより筋肉の柔軟性が向上し、急な動きや負荷にも対応できるようになります。
普段使わない筋肉を使う運動をする場合は、その部位を重点的にストレッチすると、肉離れの予防効果が期待できます。
肉離れの起きやすいふくらはぎやハムストリングス、太ももを中心にストレッチしましょう。
無理な動作をしない
スポーツ活動中に肉離れを起こす主な原因の一つは、無理な動きや急激な負荷です。
競技中の勝負へのこだわりや、自分の限界を超えた無理な動きは筋肉に過度の負担をかけ、肉離れのリスクを高めます。
自分の体力や筋力の限界を理解し、段階的に運動強度を上げていきましょう。
また、疲労が蓄積している状態では、筋肉が適切に機能せず、負荷に耐えられなくなるため注意が必要です。
指導者がいる環境では、正しい技術や体の使い方を学ぶと肉離れ予防に効果的です。
専門知識を持った指導者からフォームの指導を受けると、筋肉への不必要な負担を軽減できます。
初心者や若年層のアスリートは、基本的な動作を丁寧に学ぶと、将来的な肉離れのリスクを減らせます。
無理をせず、適切に体を動かし、安全にスポーツを楽しみましょう。
しっかりと休息を取る
十分な休息は肉離れ予防において非常に重要です。
過度なトレーニングや連続した運動により休息時間が不足すると、筋肉が常に緊張状態となり硬くなってしまいます。
緊張状態では筋肉の弾力性が低下し、わずかな負荷でも肉離れを起こすリスクが高まります。
また、精神的なストレスも筋肉の緊張を引き起こす要因です。
ストレスを感じると身体は自然に緊張し、筋肉も硬くなりやすい状態になります。
メンタル面のケアも肉離れ予防には欠かせません。
適切な休息日を設けると、筋肉は本来の柔軟性を取り戻しリラックスした状態になります。
次の運動時に筋肉が適切に伸縮できるようになり、肉離れのリスクを軽減できます。
日常から身体を動かしておく
運動不足が続くと筋肉が徐々に硬くなり、柔軟性が失われていきます。
このような状態では、特別な運動をしなくても、日常生活の何気ない動作で突然肉離れを起こすリスクが高まります。
肉離れを予防するためには、定期的な軽い運動が効果的です。
ウォーキングや軽いジョギングは、筋肉に過度な負担をかけることなく血流を促進し、筋肉の柔軟性を維持するのに適しています。
軽い有酸素運動を日常に取り入れれば、筋肉が硬くなるのを防ぎ、健康的な身体機能を維持できます。
まとめ|肉離れは正しい応急処置が早期回復と再発防止につながる
肉離れは、起こった直後の対応によって、その後の回復スピードや再発リスクが大きく変わります。
とくに発症直後に行うRICE処置は、症状の悪化を防ぎ、治癒をスムーズに進めるための重要な第一歩です。
初期対応を怠ると、痛みや腫れが長引いたり、再発しやすくなったりする可能性があります。
一方で、正しい応急処置と適切なケアを行えば、回復までの期間を短縮し、安心して日常生活やスポーツに復帰しやすくなるでしょう。
当院「リペアセルクリニック」の公式LINEでは、再生医療の情報提供と簡易オンライン診断を実施しております。
肉離れについて気になる症状がある方は、ぜひ一度公式LINEにご登録ください。
\無料オンライン診断実施中!/
肉離れの応急処置に関するよくある質問
ここからは、肉離れの応急処置に関するよくある質問を紹介します。
肉離れの応急処置にテーピングは効果的ですか?
肉離れの応急処置において、テーピングは補助的に有効な方法です。
適切にテーピングすると患部を安定させ、圧迫によって内出血の広がりを防ぎ、炎症の拡大を抑える効果が期待できます。
ただし、テーピングだけで治療が完結するわけではなく、RICE処置と併用することが重要です。
肉離れの応急処置に湿布は効果的ですか?
肉離れの応急処置として、冷湿布は補助的に効果が期待できます。
湿布には炎症や痛みを和らげる作用があり、アイシング後のケアや補助的な手段として活用できます。
ただし、湿布はRICE処置の「冷却」を完全に代替するものではありません。
氷や保冷剤によるアイシングと併用し、あくまでサポートとして使うことが大切です。
また、湿布には「冷湿布」と「温湿布」がありますが、肉離れ直後の急性期に適しているのは冷湿布です。
肉離れは筋肉に炎症が起きている状態のため、冷湿布で炎症や痛みを抑えることが目的となります。
一方で、痛みや腫れが落ち着いてきた回復期には、温湿布で血流を促すことが役立つ場合もあります。
ただし、受傷直後に温湿布を使うと炎症を悪化させるおそれがあるため注意しましょう。
湿布を使用する際は、症状や時期に応じた使い分けを意識することが重要です。
肉離れの応急処置はどのくらい冷やしたら良いですか?
肉離れを起こした直後はアイシングが効果的ですが、冷やしすぎないようにしましょう。
過剰なアイシングは筋肉を必要以上に硬くさせ、回復に必要な血行を阻害してしまうリスクがあります。
一度のアイシングは15~20分程度を目安とし、それ以上長時間続けないようにしましょう。
適切な時間でのアイシングは、炎症を抑えつつも回復に必要な血流を維持できるため、回復へとつながります。
(文献1)
社会福祉法人 恩賜財団 済生会「筋挫傷(きんざしょう)」済生会ホームページ
(文献2)
一般社団法人 日本スポーツ整形外科学会「スポーツ外傷の応急処置(RICE処置)」日本スポーツ整形外科学会ホームページ
(文献3)
ニチバン株式会社「RICE(ライス)処置」battlewinホームページ
(文献4)
大正大学「保健室だより」2016年