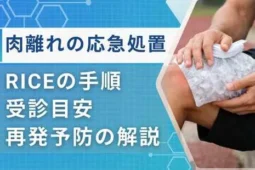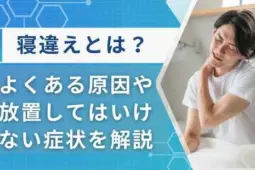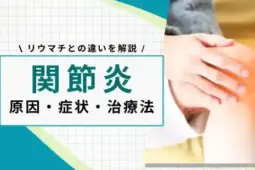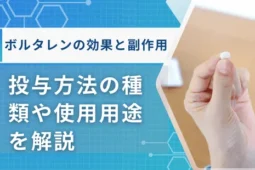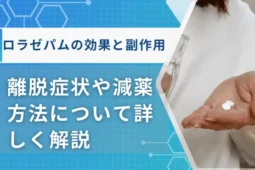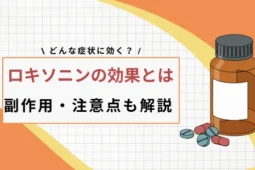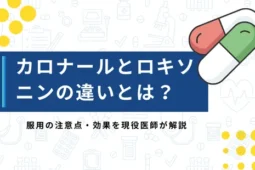- その他、整形外科疾患
肉離れ直後はストレッチNG!正しい実施時期と早期回復を目指す治療法

「スポーツ中に太ももが痛んで動けなくなった」「肉離れかもしれないけど、ストレッチをしてもよいのか」と不安を感じていませんか。
結論からお伝えすると、肉離れ受傷直後はストレッチをしてはいけません。筋肉が断裂している状態でストレッチを行うと、損傷を悪化させ、回復期間を大幅に延ばしてしまう恐れがあります。
本記事では、受傷直後にストレッチが不適切な理由や、経過別のストレッチ方法、部位別の予防ストレッチなどを紹介します。
肉離れを正しく理解し、適切なタイミングでリハビリを進めれば、安心してスポーツ復帰を目指せます。焦らず、段階的な回復を心がけましょう。
当院「リペアセルクリニック」の公式LINEでは、再生医療の情報提供と簡易オンライン診断を実施しております。
肉離れについて気になることがある方は、ぜひ一度公式LINEにご登録ください。
目次
肉離れ受傷直後のストレッチはNG!まずはRICE処置で応急対応
肉離れ受傷直後は、筋肉が断裂している状態です。この時期に無理にストレッチを行うと、以下のようなリスクがあります。
- 損傷部位がさらに広がる
- 内出血や炎症が悪化する
- 二次的な損傷につながり、回復期間が長引く
受傷直後は、ストレッチだけでなく、マッサージや患部を温める行為も避けるべきです。場合によっては、症状を悪化させ、治療期間を数週間〜数カ月延ばしてしまう可能性があります。(文献1)
肉離れの部位や重症度を問わず、受傷後48時間以内はRICE処置が基本的な応急対応です。
RICEとは、以下4つの処置の頭文字を取ったものです。
| RICE | 目的・手順 |
|---|---|
| Rest(安静) | ・患部の腫れや血管・神経の損傷を防ぐのが目的 ・固定具やテーピングで患部を固定し、不要な動きを制限する |
| Ice(冷却) | ・患部の腫れや細胞の損傷を抑えるのが目的 ・アイスバックや氷のうで患部を15〜20分冷やす(凍傷予防のため、直接肌に当てず、タオル等で包む) ・痛みがあれば繰り返し実施 |
| Compression(圧迫) | ・患部の内出血や腫れを防ぐのが目的 ・テーピングパッドやスポンジを腫れが予想される部位に当て、テーピングなどで軽く圧迫して固定する |
| Elevation(挙上) | ・腫れの抑制および軽減が目的 ・台などを用いて患部を心臓よりも高い位置に保つ |
(文献2)
RICE処置を適切に行った後は、速やかに医療機関を受診し、重症度の診断を受けてください。
以下の記事では、肉離れ受傷時の応急処置を解説しています。ぜひ、参考にしてください。
肉離れ後のストレッチ方法【経過別】
受傷後48時間はストレッチ厳禁です。この期間を過ぎてから、段階的に以下のリハビリを進めていきます。
ただし、ここで解説する経過はあくまで一例です。重症度によってストレッチを含めたリハビリの開始時期と内容は異なります。
なお、受傷割合の多いハムストリングスの肉離れを例に解説しています。
亜急性期|3日〜1週間は痛みの確認から
受傷して3日〜1週間は、基本的に安静を保ちながら患部の状態を観察します。ストレッチによる痛みが伴わなければ、リハビリを開始する目安となります。(文献3)
なお、肉離れ受傷による患部の固定は、最小限の期間にとどめることが推奨されています。長期間の固定は筋力低下や関節の硬さを招き、かえって回復を遅らせる原因となるためです。
損傷部位にもよりますが、2週間以内にはストレッチを開始するのが望ましいとされています。(文献4)
回復期|2週間以降は本格的なストレッチ
2週目以降は、以下のように「経過に応じた本格的なストレッチ」を始めます。
| 経過 | ストレッチ内容 | 詳細 |
|---|---|---|
| 2週目頃 | 静的ストレッチ(スタティックストレッチング) | 反動や弾みをつけずにゆっくりと筋肉を伸ばすストレッチ 筋肉への負担が少なく、柔軟性の回復に効果的 |
| 3週目頃 | 動的ストレッチ(ダイナミックストレッチング) | 体を動かしながら筋肉をほぐすストレッチ 関節の可動域を広げ、スポーツ動作への適応を促す |
(文献3)
ストレッチを含めたリハビリの開始時期と内容は、肉離れの重症度によって大きく異なります。必ず医師やリハビリスタッフの指示を守りながら進めてください。
自己判断で無理に進めると、再発のリスクが高まります。
肉離れを予防するストレッチ方法【部位別に紹介】
肉離れが発生する原因として、柔軟性の低下が挙げられます。(文献5)
ここでは、筋肉の柔軟性を高める部位別のストレッチを解説します。
なお、共通するストレッチのポイントは、息を止めないで深呼吸をしながら行うことです。
ハムストリングスのストレッチ
ハムストリングス(太ももの裏側)は、短距離走やサッカー、テニスなど、急なダッシュやストップ動作が多い競技で肉離れが発生しやすい部位です。
ハムストリングスのストレッチの一例は以下の通りです。
- 仰向けになる
- 片方の膝関節と股関節を曲げる
- 胸に引き寄せてももの裏を両手で保持する
- 曲げた股関節の角度は保ちながら膝関節を延ばす
- ももの裏が伸びているのを感じる角度で6〜8秒保つ
- 反対の足も同様に行う
左右それぞれ1セット3〜5回を目安にしてください。
大腿四頭筋のストレッチ
大腿四頭筋(太ももの表側)は、サッカーやバスケットボールなど、ジャンプ動作や急激なキック動作が多い競技で肉離れが発生しやすい部位です。
大腿四頭筋ストレッチの一例は以下の通りです。
- 横向きに寝そべり下側の膝関節を曲げて前に持ってくる
- 上側の足首を持って、かかとをお尻に近づける
- そのまま足を後ろに引き、太ももの前の筋肉を10秒間伸ばす
- 反対の足も同様に行う
1セット10回を目安にしてください。
体が反りすぎないように注意しましょう。
内転筋群のストレッチ
内転筋群(太ももの内側)は、サッカーやラグビーなど横方向の動きが多い競技で肉離れが発生しやすい部位です。
内転筋群のストレッチの一例は以下の通りです。
- 座った状態で両足の裏を合わせる
- 両手で足先を持ち、かかとを体に引き寄せる
- 背筋を伸ばしたまま、上体をゆっくり前に倒す
- 太ももの内側が伸びているのを感じる位置で20〜30秒保つ
膝を無理に床に押し付けず、気持ちよく伸びる範囲で行いましょう。
下腿三頭筋のストレッチ
下腿三頭筋(ふくらはぎ)ストレッチは、腓腹筋(ひふくきん:ふくらはぎの表層の筋肉)とヒラメ筋(深層の筋肉)の2つの筋肉それぞれ行うことがポイントです。(文献6)
ストレッチの方法は以下の通りです。
| 部位 | 手順 |
|---|---|
| 腓腹筋のストレッチ | ・壁に手をつき、膝を伸ばした状態で片足を後ろに一歩引く ・体重を前にかけてふくらはぎの表面の筋肉を伸ばす |
| ヒラメ筋のストレッチ | ・壁に手をつき、膝を曲げた状態で片足を後ろに一歩引く ・体重を前にかけてふくらはぎの内側の筋肉を伸ばす |
1回20〜30秒ほど伸ばし、両足とも行いましょう。
肉離れを早く治したい方へ「再生医療」という治療法
肉離れの保存療法では、松葉杖での生活が3〜4週間必要となり、その間は筋肉のトレーニングができません。とくにアスリートの方にとって、筋肉量の低下は大きな課題となります。
そこで肉離れの新たな治療の選択肢の一つとして「再生医療」があります。
再生医療は、自己の幹細胞や血液の働きを活用する治療法です。代表的なものに幹細胞治療やPRP療法があります。肉離れに対しては、主にPRP療法が用いられます。
PRP療法では、まず患者様の血液を採取し、遠心分離機にかけて成長因子を多く含むPRP(多血小板血漿)を抽出します。その後、エコー(超音波画像)で患部を確認しながら、抽出したPRPを肉離れを起こした部位に注入する治療法です。
再生医療について詳しく知りたい方は、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひご覧ください。

スポーツ外傷は⼿術しなくても治療できる時代です。
まとめ|肉離れは焦らず正しいタイミングでストレッチをしよう
肉離れ受傷直後はストレッチをしてはいけません。無理なストレッチは損傷部位を悪化させて、回復を遅らせる恐れがあります。
受傷直後はRICEを実施し、医療機関を受診してください。受診後は必要に応じてMRI検査などを行い、重症度の診断を受けます。その後は、医師やリハビリスタッフの指示に従い、経過に応じたストレッチを進めていきましょう。
なお、近年肉離れの治療において、再生医療のPRP療法が活用されています。焦らず正しいタイミングでリハビリを進めれば、スポーツ復帰を目指せます。
当院「リペアセルクリニック」の公式LINEでは、再生医療に関する情報の提供や簡易オンライン診断を行っております。肉離れによる痛みでお悩みの方は、ぜひご登録ください。
\無料オンライン診断実施中!/
肉離れのストレッチに関するよくある質問
ストレッチをすると痛いけど、どこまでが許容範囲?
ストレッチ中の痛みの許容範囲は、以下を目安に判断してください。
| 痛みの種類 | OK(許容範囲内) | NG(中止すべき) |
|---|---|---|
| 張り感・伸び感 | ・筋肉が伸びている心地よい張り感 ・じんわりとした温かさを感じる程度の伸び |
・鋭い痛みやズキッとした痛み ・刺すような痛み |
| 痛みの強さ | 気持ち良さを感じる程度 | 前回より強い鈍い痛み(炎症が再燃している可能性があるため、すぐに中止) |
静的ストレッチを中心に行い、反動や無理な力を避けるのが基本です。動的ストレッチや反動をつけたストレッチは、筋肉の再断裂リスクを高めるため、回復期の適切なタイミングまで控えましょう。
なお、痛みの感じ方には個人差があるため、少しでも不安がある場合は医師やリハビリスタッフに相談してください。
肉離れを早く治すストレッチはある?
肉離れを早く治すためのストレッチはありません。
以下のように経過に応じたストレッチを行い、運動機能を回復させていくことが大切です。
| 経過 | ストレッチ内容 |
|---|---|
| 受傷から1週目〜 | 安静 |
| 2週目〜 | 静的ストレッチ |
| 3週目〜 | 動的ストレッチ |
(文献3)
受傷状態によって、ストレッチ内容や開始タイミングは異なります。医師と相談しながらリハビリを進めていきましょう。
オーバーストレッチで肉離れになることはある?
オーバーストレッチとは、必要以上に筋肉を伸ばしてしまうことです。肉離れに限らず、過度なストレッチはケガにつながる恐れがあります。
ストレッチは気持ちが良い程度が効果的です。苦痛を感じるほどのストレッチは行わないでください。また、基本的にストレッチは体が温まっている状態のときに行います。体が冷えている際のストレッチは、細心の注意を払ってください。
参考文献
(文献1)
スポーツでケガをしたら?|日本臨床整形外科学会
(文献2)
3.スポーツ外傷の応急処置(RICE処置)|日本整形外科スポーツ医学会広報委員会
(文献3)
ハムストリング肉離れからのスポーツ復帰時の身体機能―損傷型による比較―|日本臨床スポーツ医学会
(文献4)
No.Ⅴ 肉離れに関する最新の指針|日本体育協会
(文献5)
肉離れって何??|医療法人社団めぐみ会
(文献6)
TVコンディショニングレター|テニスユニバース