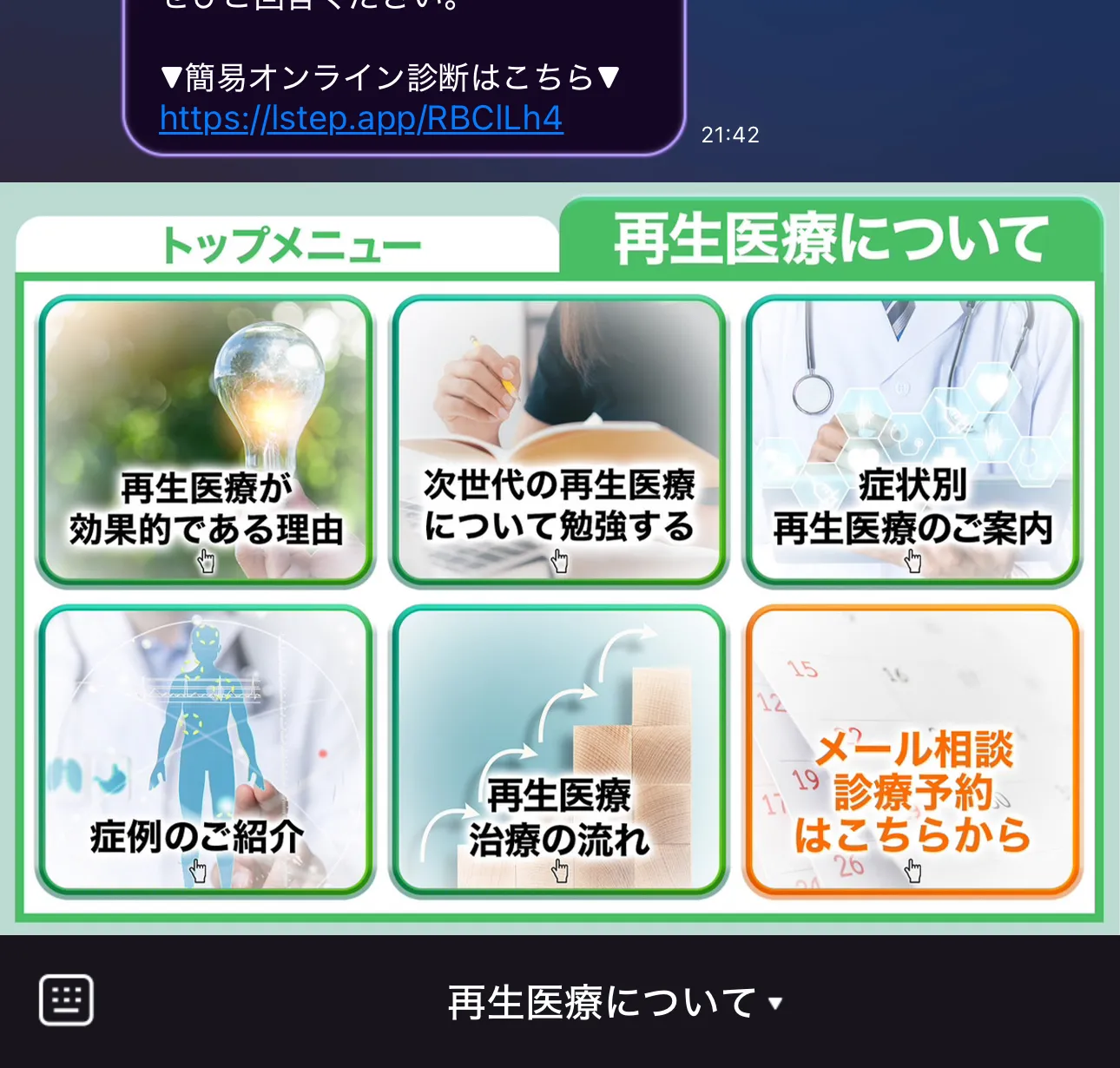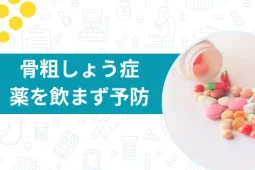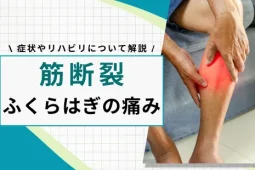- スポーツ外傷
- その他、整形外科疾患
鎖骨骨折の過ごし方と安静期間は?少しでも早く治す方法

鎖骨骨折があった際には、すみやかに医療機関を受診し、患部を正しく固定するのが重要です。
鎖骨骨折はスポーツや事故などで起こりやすい骨折の一つのため、 適切な処置や過ごし方をしないと完治が遅れたり、後遺症が残ったりする可能性もあります。
鎖骨骨折が起きた際に「どう過ごすか」「どんな治療法があるのか」を事前に知っておくことは、後遺症の予防や早期回復に大きな差を生むことでしょう。
本記事では、鎖骨骨折の症状、応急処置、その後の適切な過ごし方、安静期間などについて詳しく解説。
加えて「早く治したい」「後遺症が心配」という方のために、新たな治療の選択肢である「再生医療」についてもご紹介します。
また上記に当てはまる方は本記事だけでなく、ぜひ当院の公式LINEもご参考ください。
鎖骨骨折の治療に関する情報や、再生医療の詳細についての情報など、様々なお役立ち情報をお届けしています。
▼無料で最先端治療の「再生医療」がわかるガイドもプレゼント!
目次
鎖骨骨折の症状と安静期間について

まずは鎖骨骨折の症状を解説します。
また、骨折時の適切な対応や必要な安静期間などに触れていきます。
正しい知識を知っていれば、より早く鎖骨骨折を完治させられるでしょう。
鎖骨骨折の症状
鎖骨骨折の症状で特徴的なものは、骨折部の痛みと腫れ、腕を上に挙げられないなどの運動制限です。
さらに、鎖骨周囲には血管や神経が通っているため、骨折の程度によりそれらの組織を傷つけ、手指がしびれたり動かせなくなる場合もあります。
また、鎖骨は皮膚の上から触れるほど体表にあるため、骨折している場合は簡単に観察できます。
肌を露出させられるようであれば、骨折があるかどうか目視で確認してみましょう。
鎖骨骨折した際の安静期間
続いて鎖骨を骨折した、もしくは疑われる場合の対処法と安静期間を解説します。
鎖骨骨折はすぐに受診
鎖骨骨折が疑われる場合は、できるだけ早く医療機関を受診しましょう。
鎖骨の骨辺が重要な神経を傷つけている可能性があるからです。対応が遅れると、生命に関わるかもしれません。
また折れた鎖骨が動いて血管を傷つけ、新たな出血が生じるおそれもあります。
したがって鎖骨骨折は、他の部位を骨折した場合よりも、すみやかに医療機関で受診するのが重要です。
三角巾を使った鎖骨骨折の固定
鎖骨骨折があった場合、早急に患部を固定します。固定しないと、転移(骨の位置のずれ)が起こる可能性が出てきます。
転移があると、完治が遅れたり、異常な形で癒合したりするかもしれません。
転移を解消するための手術が必要になるケースもあります。
したがって正しく患部を固定し、転移を防がなければいけません。
以下では医療機関をただちに訪問できない場合の応急処置として、三角巾を用いた患部の固定方法を解説します。
|
①怪我した方の手を反対の手で固定してもらいます。(この姿勢が楽だと感じる人が多い)
②三角巾の頂点を骨折側の肘の下に挟み込むようにセットし、一方の端を反対の肩に回します。
③他方の端を骨折側の脇の下を通すように背中側に回します。そうすると骨折側の腕を包み込むように固定できます。 ④首のところで両端を結び固定します。 ⑤頂点は肘の位置がズレないように結びます。 ⑥もう一つ三角巾を用意し、肘を体幹で固定するように巻くとぶれずに固定できます。 |
鎖骨骨折には3〜8週間の安静期間が必要
鎖骨骨折があった場合、4〜6週間ほどの安静期間が必要です。期間中、患部は鎖骨バンドなどで固定します。
安静期間がなければ、鎖骨の癒合がうまく進みません。癒合を促進するためにも、この期間が必要です。
また後述する禁忌動作を避ける、定期的に鎖骨バンドを締めるなどの取り組みも必要です。
鎖骨を骨折している際の過ごし方と少しでも早く治す方法
鎖骨を骨折している際に、少しでも早く治すための過ごし方とポイントは大きく分けて3つあります。
- なるべく腕を上げないようにする
- 基本的に横向きに寝る
- 1日2回ほど固定具を締める
それぞれ以下で詳しく解説します。
なるべく腕を上げないようにする(禁忌動作を避ける)
鎖骨は腕(上肢)を動かすための、重要な部分です。鎖骨が動かせなければ、腕はほんの少ししか上がりません。
腕を大きく挙げようとすれば鎖骨も連動します。つまり、鎖骨が折れている状態で腕を大きく動かせば、鎖骨は自ずと動き、ズレようとする力が働くため、強い痛みが出てしまい、さらには骨の癒合を邪魔してしまいます。
そうなると、治りが遅くなり肩の動きが悪くなる後遺症が出る可能性もあります。
また、偽関節ができてしまい、力が入りづらくなることも考えられます。
そのため、鎖骨骨折後の早期は手術の有無に関わらず、腕を挙げる行動を控えることが重要です。
基本的に横向きに寝る
鎖骨骨折後の早期は、寝る姿勢にも注意しなければなりません。
基本的に仰向けか患部を上にした横向きで寝ることが推奨されています。その際、骨折した側の腕が動かないようにバンドや三角巾などで固定しておくと良いでしょう。
仰向けで寝る場合は、肘が下に落ち過ぎて肩に負担がかかる場合もあります。
したがってバスタオルを折り畳んだものを骨折側の肘の下に敷いておくと安定感が得られます。
1日2回ほど固定具を締める
鎖骨骨折がある際は、1日2回ほど、鎖骨バンドなどの固定具を締め直しましょう。
前章では、鎖骨の癒合を進めるためには患部を固定するのが重要と述べました。
しかし鎖骨バンドの固定部が緩むと、鎖骨が動くようになり、完治が遅れます。
患部が固定されるよう、1日2回ほど固定具を締めるようにしましょう。
鎖骨骨折後の治療
ここまで、鎖骨骨折の発生要因や症状、鎖骨骨折後の対処をお話ししてきました。
それでは実際にどのような治療方法があり、どのような経過をたどるのでしょうか?
治療の方法は大きく2つに分けられます。一つは、体にメスを入れない保存療法、そしてもう一つは折れた骨同士を癒合させる手術療法です。
今回は、保存療法を中心にご説明します。保存療法が選択されるケースは以下です。
保存療法が必要となるケース
|
骨のずれが少ない場合は、鎖骨バンド(クラビクルバンド)と呼ばれるサポーターで固定をし、骨が繋がるのを待ちます。

鎖骨骨折の特徴として、胸の中心に近い方の骨片が上に移動し、外側の肩に近い方の骨片が相対的に下に位置するケースがあります。
そのため、バンドで胸の中心の方の骨片を上から抑えこむことで、そのズレを少なくし、骨をつながりやすくします。
通常であれば、2~3カ月もすれば、ある程度骨癒合(ひっつく)します。
ただ、鎖骨バンドを早期に外してしまったり、つけ方が甘かったり、早くから腕を動かし過ぎたりすると、骨が癒合するのが遅れ、遷延治癒(※)となることもあるので注意が必要です。
(※遷延治癒・・・一定期間が経過しても治らない状態)
鎖骨骨折の治療には保存療法や手術療法といったように様々な選択肢がありますが、当院「リペアセルクリニック」が提供している、再生医療という新しい選択肢もあります。
より詳しく、手術を必要としない治療法として注目されている再生医療について知りたい方は、以下からぜひご確認ください。
▼セルフケアに関する情報についても配信中!
>>公式LINEはこちら
鎖骨骨折の完治までの期間は?痛みのピークはどれくらい?
鎖骨骨折の完治までは3カ月ほどかかるでしょう。しかし、ズレが大きい、手術が必要などの事情があれば、3カ月より長くかかるかもしれません。
幹部の痛みは、安静にした期間が伸びるにつれ軽減されます。
骨折直後の2、3日に痛みはピークに到達します。、以後少しずつ痛みが引いていくでしょう。
2カ月後にはほとんど痛みを感じなくなります。
車の運転はいつからいいの?
よく聞かれる質問の一つに、「車の運転はいつからしていいのか?」というものがあります。
一人ひとり骨のつながり具合や手術の有無によって差があるので一概にはいえませんが、腕をしっかり挙げてOKと医師から許可が出た頃から練習をし始めるのが良いでしょう。
運転では、やむを得ず急ハンドルを切る場面が出てくるかもしれませんし、大きいカーブでは腕が上がる動作も加わります。
予測できないハンドル操作が出てくることも考えると、少なくとも1カ月半〜2カ月程度は我慢した方が良さそうです。
とにかく、鎖骨骨折をしてしまったら、自分で判断せずに専門の医療機関に診てもらい、骨折後や手術後すぐに肩を大きく動かす動作は避けましょう。
骨のつながりは、レントゲンなどによって判断されるので、医師の指示のもと、段階的に動かすよう心がけましょう。
まとめ・鎖骨骨折した際の正しい過ごし方を理解しよう
今回は、鎖骨骨折の発生要因や症状、治療方法、過ごし方などを紹介しました。
骨折のなかでは頻度が高い鎖骨骨折ですが、その予後は良く、医療機関の指示を守って生活すると大部分は前と同じように動かせるようになるでしょう。
鎖骨の骨片で大事な神経や血管を傷つけている可能性もあるため、骨のつながり状況を確認しながら段階的に治療に取り組むことが完治への一番の近道、早く治すために有効です。
鎖骨骨折が疑われる場合は手術をせざるを得ない状況も考えられるため、「大丈夫だろう」と自分の判断で無理されることなく、早めに医療機関を受診してください。
また、骨が癒合した後も痛みや後遺症が残り、リハビリを続けたものの完治しなかったという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
考えられる後遺症としては以下が挙げられます。
- 神経障害(痛みやしびれ)
- 変形障害
- 機能障害
もし上記にお困りであれば、再生医療でより早期の回復を目指せる可能性があります。
最先端の再生医療を提供しているリペアセルクリニックでは、自己脂肪由来幹細胞を用いた再生医療を提供しており、骨癒合の促進や後遺症の改善が期待できます。
無料相談も実施しておりますのでお気軽にご相談ください。
▼再生医療のさらに詳しい情報も配信中
>>公式LINEはこちら