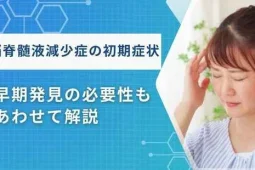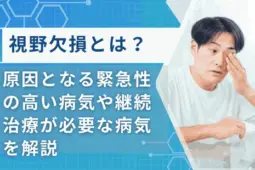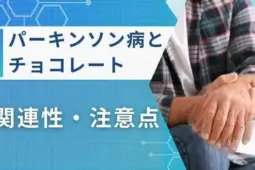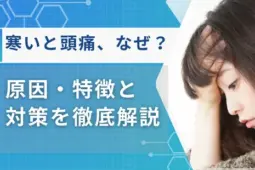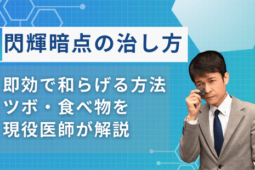- 頭部
- 頭部、その他疾患
低髄液圧症候群の原因は大きく分けると2つ|診断基準や治療法なども解説
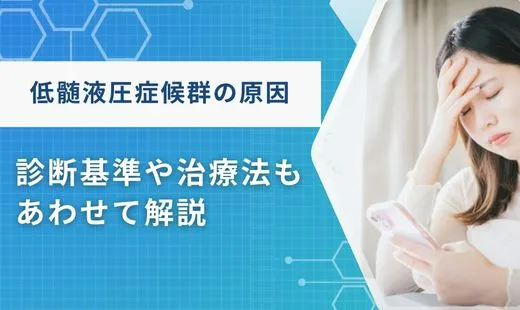
「交通事故でけがをしてから、頭痛が続いている」
「首や目の奥が痛んだり、めまいを起こしたりしている」
このような症状でお悩みではありませんか?
けがをしていないのにもかかわらず頭痛やめまいが急に現れて、辛い思いをされている方も多いでしょう。これらの症状は、低髄液圧症候群が原因の可能性があります。
本記事では低髄液圧症候群を発症する原因や診断基準、検査方法、治療方法などについて紹介します。
低髄液圧症候群を初めて知った方に役立つ内容ですので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
低髄液圧症候群の原因は大きく2つに分けられる
低髄液圧症候群の原因は、大きく分けると以下の2つです。
- 外傷性の原因
- 外傷性以外の原因
外傷性の原因
文字どおり、なんらかの外傷により引き起こされるものです。主なものを以下に示しました。
- 交通事故による頭部打撲やむち打ち症
- 仕事中の事故
- スポーツ時の外傷
- 階段昇降時の転倒
- 自転車運転中の転倒
低髄液圧症候群の大半は外傷によるものとされており、軽くしりもちをついただけで発症するケースもあります。
外傷性以外の原因
外傷性以外の原因としては、腰椎穿刺検査や腰椎麻酔、脳神経外科手術といった、医療行為によるものが考えられます。(文献1)
医療行為以外に原因としてあげられるものは、主に以下のとおりです。
- 整体治療
- 出産
- 発熱による脱水症状
外傷性、外傷性以外にかかわらず、原因が特定できないケースもあります。
低髄液圧症候群とは
低髄液圧症候群とは、脳脊髄液の漏れにより髄液の圧力が低下して、頭痛やめまい、首や背中の痛みなどを引き起こす疾患です。しかし実際には、髄液の圧力低下が測定できないケースも存在するため、脳脊髄液減少症と呼ばれることもあります。
低髄液圧症候群と脳脊髄液減少症の違いは、診断方法確立の有無です。低髄液圧症候群はMRI画像や腰椎穿刺検査などで診断されますが、脳脊髄液減少症は明確な診断方法が確立されていません。
国際的には、低髄液圧症候群が病名として主に使用されています。
脳脊髄液減少症について詳しく知りたい方は、以下の記事をあわせてご覧ください。
低髄液圧症候群の特徴的な症状は起立性頭痛です。(文献1)起立性頭痛の場合、立ったり座ったりすると痛みが強くなります。
その他の症状としては、以下のようなものがあげられます。
- 体のだるさ
- 不眠
- 食欲の低下
- 集中力の低下
- 記憶力の低下
低髄液圧症候群は、頭痛やめまいなどに加えて、精神・心理的症状が見られるため、片頭痛や緊張性頭痛、うつ病などと誤解されやすい疾患です。
低髄液圧症候群の診断基準
低髄液圧症候群の診断基準は、前提基準と大基準の2種類です。(文献2)
前提基準は2項目、大基準は3項目存在しており、「前提基準1項目+大基準1項目以上」に該当した場合に低髄液圧症候群と診断されます。
前提基準
前提基準の1つ目は起立性頭痛、2つ目は体位による症状の変化です。両者を表で示しました。
| 前提条件 | 詳細 |
|---|---|
| 起立性頭痛 |
頭部全体が鈍く痛む 立ったり座ったりすると、痛みが強くなる |
| 体位による症状の変化 |
|
項部硬直とは、首から後ろにかけての筋肉のこわばりを指します。光過敏とは、少しの光でもまぶしさや不快感を覚える症状です。
大基準
大基準は、以下に示した3点です。
- 造影MRIでびまん性の硬膜肥厚増強
- 腰椎穿刺にて髄液圧の低値(60mmH2O以下)の所見
- 髄液漏れを認める画像所見
びまん性の硬膜肥厚増強とは、脳内の硬膜が広い範囲で厚くなっている状態で、MRI検査で確認できます。
髄液圧の正常値は、健康な成人の場合70~200mmH2Oとされています。(文献2)
髄液漏れを認めるための画像検査については、確立された方法がありません。CTミエログラフィーやMRミエログラフィー、RI脳槽シンチグラムなどを組み合わせて行います。
低髄液圧症候群の検査方法
低髄液圧症候群の検査としては、MRI検査や腰椎穿刺検査、RI脳槽シンチグラムなどです。これらの検査で、髄液圧や髄液漏れについて詳しく調べます。患者からの病歴聴き取りも必要な情報です。
検査方法について詳しく知りたい方は、以下の記事をあわせてご覧ください。
低髄液圧症候群の治療法
低髄液圧症候群の治療法は、主に以下の2種類です。
- 保存療法
- ブラッドパッチ療法
保存療法
保存療法の基本は、安静と十分な水分補給です。
自宅での水分摂取とは別に、必要に応じて、生理食塩水の点滴を1~2週間程度行う場合もあります。点滴の量は、1日1,000~2000ml程度です。
髄液は1日につき約500ml作られます。脳や脊髄を守るために必要な髄液を作るには、十分な水分補給が欠かせません。
ブラッドパッチ療法
ブラッドパッチ療法は、自分の血液を硬膜外に注入して、髄液の漏れを塞ぐ治療法です。硬膜とは、脊髄を覆っている一番外側の膜です。硬膜外から注入された血液中の成分が、のりの役割を果たします。必要に応じて、X線により注入部の様子を観察しながら行う場合もあります。
ブラッドパッチ療法は、平成28年4月から保険適用されました。(文献3)
低髄液圧症候群の原因を把握し医療機関の受診を検討しよう
低髄液圧症候群の原因は、外傷性と非外傷性の2つに分けられます。非外傷性には、原因不明(特発性)のものも含まれます。
いずれの原因においても症状は共通しており、特徴的な症状は起立性頭痛です。それ以外にも、耳鳴りや吐き気、光過敏などの症状があれば、速やかに医療機関を受診しましょう。主な診療科は、脳神経外科です。
多くの都道府県ホームページでは、検査・治療ができる医療機関を紹介しています。医療機関の受診を検討している方は、検索してみると良いでしょう。
リペアセルクリニックでは、メール相談やオンラインカウンセリングを実施しています。低髄液圧症候群と思われる症状でお悩みの方は、お気軽にお問い合わせください。
低髄液圧症候群の原因に関するよくある質問
低髄液圧症候群を発症した芸能人は誰ですか?
俳優の米倉涼子さんが、低髄液圧症候群を発症しました。まっすぐに歩くことや立ち上がることが困難になり、一時は芸能界引退も覚悟したとテレビ番組で話しています。
脳脊髄液減少症を発症した芸能人については、以下の記事で紹介しています。あわせてご覧ください。
低髄液圧症候群は慢性疲労症候群と関連していますか?
低髄液圧症候群と慢性疲労症候群との関連は不明です。
慢性疲労症候群とは、検査や診察で異常が認められないものの、日常生活を送ることが難しいほどの重度の疲労感が続く疾患です。症状としては、強い疲労感や頭痛、集中力低下、抑うつなどがみられます。低髄液圧症候群と似ている症状も少なくありません。
慢性疲労症候群は感染性疾患や免疫の異常、遺伝や環境要因に関連していると考えられますが、はっきりとした原因は解明されていません。
ベルギーの研究者によって執筆された論文では、脳脊髄液圧の上昇と慢性疲労症候群が関与している可能性が示されています。(文献4)
参考文献
(文献1)
戸田茂樹ほか.「低髄液圧症候群(脳脊髄液減少症)」『日本医科大学医学会雑誌』3(1), pp.44-45, 2007年
https://www.nms.ac.jp/sh/jmanms/pdf/003010044.pdf(最終アクセス:2025年4月23日)
(文献2)
松本英之,宇川 義一.「脳脊髄液減少症」『日本内科学会雑誌』100(4), pp.1076-1083, 2011年
https://www.jstage.jst.go.jp/article/naika/100/4/100_1076/_pdf(最終アクセス:2025年4月23日)
(文献3)
一般社団法人日本脳脊髄液漏出症学会「日本脳脊髄液漏出症学会公式診療マニュアル」一般社団法人日本脳脊髄液漏出症学会ホームページ
https://js-csfl.main.jp/guideline.html(最終アクセス:2025年4月23日)
(文献4)
Mieke Hulens, et al.(2023).The Link Between Empty Sella Syndrome,Fibromyalgia, and Chronic Fatigue Syndrome: TheRole of Increased Cerebrospinal Fluid Pressure.Journal of Pain Research, 2023(16), pp.205-219.
https://www.dovepress.com/article/download/81240(最終アクセス:2025年4月23日)