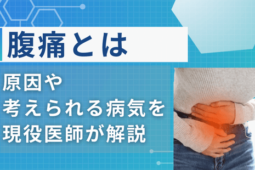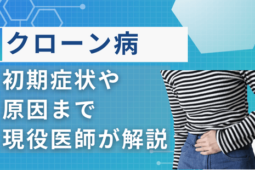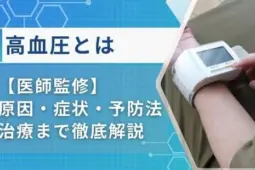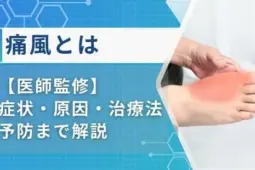- 内科疾患
- 内科疾患、その他
大腸がんステージ3でもあきらめない|最善の治療選択と再発予防のポイント

大腸がんのステージ3と告げられると、リンパ節への転移があるのではないか、どんな痛みや便通異常が起こるのか、手術でどこまで治せるのかといった不安が一気に押し寄せるかもしれません。
実際のところ、大腸がんの進行度合いは腸壁への浸潤度(T因子)、リンパ節転移(N因子)、遠隔転移(M因子)の3つを組み合わせて判断します。その中でステージ3は、腸壁の深さに関わらずリンパ節に転移が認められる段階です。ここに該当する場合は治療計画や再発リスクの面で注意が必要となり、自覚症状もさまざまな形で現れる可能性があります。
本記事では、ステージ3の大腸がんにおける代表的な症状や治療選択、再発予防のポイントをわかりやすく整理します。がんがリンパ節に到達しているとはいえ、決してあきらめる必要はありません。治療技術の進歩や新しい薬の登場により、ステージ3であっても長期生存や再発予防に大いに期待が持てることがわかっています。
この記事を通して、症状を把握し早めに行動するメリットを理解し、前向きな気持ちで治療に取り組むきっかけになれば幸いです。
目次
大腸がんにおけるステージ3とは
大腸がんは0期から4期までの5段階にわかれ、ステージ3はリンパ節転移があるかどうかが重要なポイントです。腫瘍の大きさや腸壁への深達度が比較的浅くても、リンパ節にまでがん細胞が入り込んだ時点でステージ3と判断されます。
この段階になると手術だけでなく、術後の補助化学療法や放射線治療などを組み合わせた治療戦略が必要になるケースが多くなります。再発率を左右する重要な段階でもあるため、医師の説明や検査内容を十分に理解し、自分に合った治療を検討しましょう。(文献1)
リンパ節は全身をめぐるリンパ液の通り道なので、がん細胞がここに入ると体の別の場所へ転移するリスクが高まります。
腸壁の深達度を示すT因子や、他臓器に転移しているかどうかのM因子と組み合わせて総合的にステージが決まりますが、リンパ節転移が確認された場合はステージ3として扱われ、さらに転移の個数や位置によってIIIa、IIIb、IIIcなどに細分化されます。
腸壁の浸潤が浅い場合でもリンパ節転移が明らかであれば、比較的早期の状態から積極的な治療を考えることになります。(文献2)(文献4)
リンパ節転移があるからといって、すぐに悲観する必要はありません。手術や抗がん剤、放射線治療を適切に組み合わせることで、5年生存率がかなり高まることが多くのデータから示されています。
昔はリンパ節転移がある段階だと治癒が難しいイメージもありましたが、近年は治療法の進歩により、ステージ3であっても長期的に元気に過ごしている方が増えています。さらに、手術前後の治療をどのように組み合わせるかによって、再発を防ぐ道筋が見えやすくなってきました。
まずは自分がなぜステージ3と判断されたのか、リンパ節転移の範囲はどの程度なのかを把握し、それに基づいてより効果的な治療法を検討していくことが大切です。
大腸がんのステージ3を判断する基準
治療計画を立てる上で欠かせないのが N因子(リンパ節転移数)です。転移したリンパ節の数によってステージ3は三つのサブカテゴリーに細分化され、それぞれで推奨される治療の強さが変わります(文献2)(文献3)。
| サブカテゴリー | 病理検査で確認された転移リンパ節数 | 再発リスクの目安 | 術後補助化学療法の位置づけ |
|---|---|---|---|
| Ⅲa | 1〜3個 | 中リスク | 単剤経口薬+点滴薬の標準コース。副作用による中断も比較的少ない |
| Ⅲb | 4〜6個 | 高リスク | 二剤併用または三剤併用を基本とし、治療期間は6カ月以上を推奨 |
| Ⅲc | 7個以上、または主リンパ節転移 | 超高リスク | 強力な併用療法に加え、臨床試験や免疫チェックポイント阻害薬の適応を検討 |
病院ではまず造影CTやMRIで腫れたリンパ節の数を推定し、手術で切除した組織を顕微鏡で詳細に調べて最終的な個数を確定させます。この二段階の確認によって見落としを最小限に抑えられるため、過不足のない治療強度を選びやすくなります(文献5)。
たとえばⅢaであれば、補助化学療法を行ってもしびれや白血球減少などの副作用が軽度で済むケースが多く、仕事を続けながら外来通院で治療できる方もめずらしくありません。
Ⅲcの方では強力な薬剤を用いるぶん副作用が強く出やすいため、主治医やがん専門薬剤師と相談しながら段階的に薬を調整したり、臨床試験で新しい治療オプションを探る選択肢も加わってきます。
このようにリンパ節転移数は治療の強さと再発リスクをはかる重要な物差しとなります。
ステージ3大腸がんの生存率・余命
大腸がんのステージ3と聞くと、治癒率や生存率がどれくらいなのかが気になる方が多いでしょう。一般的なデータでは、ステージ3全体の5年生存率はおよそ60〜80%程度と報告されています。(文献5)(文献6)
数字に幅があるのは、先述のリンパ節転移の数や部位によって細分化されるIIIa、IIIb、IIIcなどの病期によって再発リスクが変わるためです。
N1相当の小規模転移であればより高い生存率が見込まれ、N2やN3のように転移数が多ければ再発のリスクが上がるため、平均値としてはやや低めに見えることがあります。
手術だけでなく、補助化学療法や放射線治療を適切に組み合わせることで、この生存率をさらに押し上げられます。術後に抗がん剤を投与して再発リスクを抑える方法が一般的にとられるのは、リンパ節転移のあるステージ3で微少ながん細胞が体内に残る可能性が高いためです。
あくまで生存率の数値は統計的な平均で、個々の体質や腫瘍の性質によって大きく変動する可能性があります。
最近は免疫チェックポイント阻害薬などの新しい薬も選択肢として出てきたため、従来よりもさらに生存率が向上するケースが増えています。とくに術後5年を無事に乗り越えれば、その後10年、20年と元気に過ごす例も珍しくありません。
ステージ3大腸がんの治療方法
ステージ3の治療の中心となるのは、やはり外科的手術です。がんがリンパ節まで広がっている以上、腫瘍を切除しないかぎり根治をめざすのは難しくなります。
ただし、ステージ3は手術のほかにも補助的な抗がん剤治療や放射線治療、近年注目されている免疫療法や再生医療などを組み合わせて、トータルで対策していくことが一般的です。(文献3)
腫瘍の部位や大きさ、リンパ節転移の数によって治療プランは異なるため、主治医との相談の上で自分に合った方法を見極めてください。
手術(外科治療)
ステージ3大腸がんの根治をめざす場合、まず優先されるのが手術です。結腸がんではがんの部分とその周囲のリンパ節を含めて切除し、残った腸管を縫合して機能を保ちます。
腹腔鏡やロボット支援手術などの低侵襲手術が活用されるケースも増えていますが、腫瘍が大きい場合や多数のリンパ節転移が疑われる場合は開腹手術が選択されることもあります。(文献3)
直腸がんの場合は肛門に近い場所にがんがある場合など、切除範囲によっては肛門を温存できずに人工肛門(ストーマ)の造設が必要となるケースがあります。(文献1)
人工肛門が必要になったときは日常生活がどう変化するか不安に感じる方も多いのですが、ストーマ装具の性能が進化し、専門スタッフによる指導などのサポート体制が整っているので、慣れれば仕事や外出も十分に可能になります。(文献1)
術後は切除した組織を病理検査し、リンパ節転移の詳しい数や腫瘍の性質を確認して、再発予防のための補助化学療法などを検討します。ステージ3の段階では、手術に加えて抗がん剤治療を組み合わせることで再発リスクを大幅に下げることが一般的とされるため、医師から「術後の追加治療」を勧められるケースが多いのが特徴です。(文献3)
\まずは当院にお問い合わせください/
抗がん剤治療
抗がん剤治療は、手術後の再発予防や、切除が難しいがんに対する進行抑制を主な目的として行われます。
ステージ3の大腸がんに関しては、手術後に微小ながん細胞が体内に残っている可能性が高いため、再発を防ぐ目的で抗がん剤が投与されるのが通例です。抗がん剤の種類は、患者さんごとの体力や副作用の出方を考慮して決定されますが、気になる副作用については吐き気や倦怠感、下痢やしびれなどが典型例です。
ただし、制吐剤や補助薬が進歩しているので、以前と比べてコントロールしやすくなりました。
治療を続けている間も仕事を続けられる人がいる一方で、副作用が強く出て体力的につらい方もいます。主治医や看護師、薬剤師などの医療チームと相談しながら、生活環境や費用面も含めて治療計画を調整しましょう。
抗がん剤による再発率低減の効果はエビデンスが多く、術後の再発リスクを抑えるためには欠かせない選択肢として位置付けられています。(文献3)
放射線治療
放射線治療は、大腸がんのうちとくに直腸がんの治療でよく併用されます。大きくわけて補助放射線治療と緩和的放射線治療があり、補助放射線治療では、骨盤内の再発を抑えるために手術前または手術後に行われます。
術前放射線では腫瘍を小さくして手術の成功率を上げたり、局所再発率を下げたりする効果が期待でき、術後放射線は、切除では取りきれなかった可能性のある微小ながん細胞に対処する狙いで実施されることがあります。
ただし、大腸がんは放射線感受性がさほど高くないとされ、単独で根治をめざす効果は限定的です。そのため、手術や化学療法との組み合わせが非常に重要になります。緩和的放射線治療は、切除不能で痛みや出血を緩和したい段階で行うことで症状の軽減をはかります。
照射範囲によっては放射線性腸炎や放射線性膀胱炎といった副作用が起こることもありますが、照射技術が進歩しており、正常組織へのダメージを最小限にとどめる工夫が年々進んでいるのが現状です。(文献3)
免疫療法・再生医療
免疫療法は、患者自身の免疫力を高めてがん細胞を攻撃する治療法ですが、大腸がんに効果が認められた療法は免疫チェックポイント阻害薬のみです。(文献7)
近年話題になっている再生医療は幹細胞などを用いて臓器や組織を修復・再構築する手法を指し、がん治療分野ではまだ研究段階にあるものの、今後の発展が期待されています。
大腸がん治療と直接結び付くものは現状では多くありませんが、一部の施設では細胞培養技術などを活用して免疫機能を補う取り組みを行っています。
標準治療の補助として利用できるかどうかは症例や研究段階によりますが、興味がある場合は詳しい医療機関へ相談するのも一つの方法です。免疫療法や再生医療が標準治療に完全に組み込まれるには時間がかかるかもしれませんが、新しい選択肢を探したい方にとってはチェックしておきたい領域です。再生医療に興味がある方はぜひ当院にお問い合わせください。
\まずは当院にお問い合わせください/
ステージ3大腸がんにおける術後の生活と再発予防
ステージ3大腸がんの治療を終えても、術後の生活や再発予防への取り組みは引き続き重要になります。食事や運動、定期検診をどう続ければ良いのか悩む方は多いでしょう。
大腸がんならではの便通管理や生活習慣の見直しなど、日常的に気をつけることは数多くあります。
手術によって便の通り道が変わると、排便回数の増加や下痢の傾向が続く場合もあるため、体に合わせて少しずつ慣らしていく必要があります。
ここで焦って無理を重ねると、体力がなかなか回復せず、日常生活に支障を来すこともあるので、段階的にできることを増やしましょう。
リハビリとメンタルサポート
術後のリハビリでは、まず体力や筋力を回復させることが基本となります。ウォーキングや軽い体操から始めて、徐々に体を動かす時間や内容を増やすのが効果的です。
食事面でも、腸の機能が安定するまで、消化に良いものや腸内環境を整えやすい食材を意識的に摂るようにすると、便通トラブルの緩和が期待できます。
手術前は運動習慣がなかった人でも、リハビリをきっかけに体の動かし方を学ぶことで、思った以上に筋力がつき、回復が早まることがあります。
さらに、メンタル面のサポートも欠かせません。がん治療による精神的ストレスや再発への不安などで落ち込む場合は、患者会やカウンセリングなどを活用して、同じような体験をした人の話を聞いたり、専門家から気持ちの整理に関するアドバイスをもらうことが大いに助けになります。
緩和ケアは終末期だけでなく、治療中から受けられるものです。心のケアに取り組むことで、治療のモチベーションを保つ効果も期待できるため、遠慮せず医師や看護師に相談してみると良いでしょう。(文献8)
経過観察
大腸がんの術後は、ある程度長い期間にわたって経過観察が必要になります。とくに術後3年以内は再発リスクが高い時期であり、血液検査や腫瘍マーカーの測定、CTやMRIによる画像検査を定期的に受けることが推奨されます。なぜなら、肝臓や肺などへの転移が起きやすい性質があるため、症状がなくても画像上で変化が見つかる場合があるからです。
大腸内視鏡検査も定期的に実施して、新たなポリープやがんの発生がないかを確認します。もし再発が見つかったとしても、転移が限局していれば再切除や薬物療法で対処できる可能性があります。自己判断で検査を中断せず、主治医の指示に従って定期的な観察を受けましょう。(文献3)
大腸がんステージ3と宣告されて辛いあなたへ
ステージ3と宣告されると、リンパ節転移があることで「完治は難しいのではないか」「再発が怖い」と落ち込む方が少なくありません。しかし、リンパ節転移があったとしても、手術や化学療法、放射線治療、免疫療法などを上手に組み合わせることで完治や長期生存をめざす道が開けるのも事実です。
再生医療などの新しい選択肢も研究が進んでおり、特定の患者さんに有望な可能性を示す報告もあります。
治療法によっては保険適用外の場合もあるため、費用や効果の面で十分に検討は必要ですが、セカンドオピニオンを通じて情報を集める価値は大いにあります。
大腸がんは他のがんと比べて手術と薬物療法でコントロールしやすい側面もあるため、適切なタイミングで行動に移せば未来を変えられるかもしれません。不安を一人で抱えず、まずは担当医を頼ってください。
生活面のサポートや経済的な補助制度も充実しているので、社会福祉士や医療ソーシャルワーカーに相談してみると具体的なアドバイスが得られるでしょう。つらい状況が続きますが、少しでも行動を起こし、未来を見つめ直しましょう。
参考文献
(文献1)国立がん研究センター がん情報サービス. 大腸がん 治療 1.ステージと治療の選択. 2025年03月24日更新. https://ganjoho.jp/public/cancer/colon/treatment.html(最終アクセス:2025年04月20日)
(文献2)ざいつ内科クリニック. 大腸がんのステージについて. 2023年.http://www.zaitsu-naika.com/%E7%99%8C/p3826.html(最終アクセス:2025年04月20日)
(文献3)国立がん研究センター がん情報サービス.大腸がん(結腸がん・直腸がん)について.https://ganjoho.jp/public/cancer/colon/print.html(最終アクセス:2025年04月20日)
(文献4)国立がん研究センター中央病院. 大腸がんのステージ(病期)について. https://www.ncc.go.jp/jp/ncch/clinic/colorectal_surgery/160/index.html.(最終アクセス:2025年04月20日)
(文献5)国立消化器内視鏡クリニック. 「大腸がん」の 5 年生存率は?早期治療のメリット&知っておきたい病気の要点. 2023‑01‑31. https://kunitachi-clinic.com/column/%E3%80%8C%E5%A4%A7%E8%85%B8%E3%81%8C%E3%82%93%E3%80%8D%E3%81%AE%EF%BC%95%E5%B9%B4%E7%94%9F%E5%AD%98%E7%8E%87%E3%81%AF%EF%BC%9F%E6%97%A9%E6%9C%9F%E6%B2%BB%E7%99%82%E3%81%AE%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%83%83/(最終アクセス:2025年04月20日)
(文献6)国立がん研究センター がん情報サービス. 院内がん登録生存率集計結果閲覧システム. 2015年.https://hbcr-survival.ganjoho.jp/graph?year=2014-2015&elapsed=5&type=c02(最終アクセス:2025年04月20日)
(文献7)国立がん研究センター がん情報サービス.免疫療法 もっと詳しく. 2015年.https://ganjoho.jp/public/dia_tre/treatment/immunotherapy/immu02.html#003(最終アクセス:2025年04月20日)
(文献8)国立がん研究センター がん情報サービス.がんのリハビリテーション医療. 2015年.https://ganjoho.jp/public/dia_tre/treatment/rehabilitation/index.html(最終アクセス:2025年04月20日)