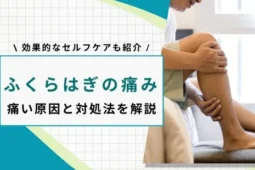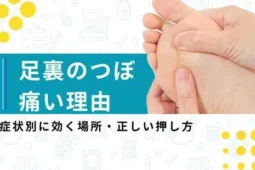- 足部、その他疾患
- 足部
下肢閉塞性動脈硬化症(ASO)に対するマッサージが禁忌となる3つのケースとは?
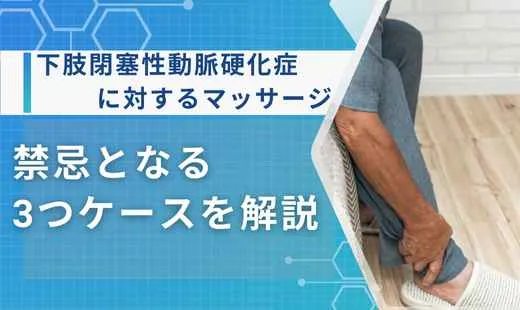
「下肢閉塞性動脈硬化症に対してマッサージはしても良いの?」
「マッサージをしてはならないケースは?」
下肢閉塞性動脈硬化症(ASO)に対する自己流のマッサージは危険です。病状によってはASOを悪化させる恐れもあるためです。ASOを改善するのであれば、適切な運動療法やフットケアが効果的です。
本記事では下肢閉塞性動脈硬化症(ASO)に関して、以下の内容を解説します。
- マッサージが禁忌となる3つのケース
- 効果的な運動療法
- セルフケアにおける5つのポイント
マッサージが推奨されてないケースを具体的に解説しています。ASOの適切な管理方法を身につけるために役立ててください。
目次
下肢閉塞性動脈硬化症に対するマッサージが禁忌となる3つのケース
前提として、下肢閉塞性動脈硬化症(ASO)に対して自己流のマッサージは危険です。マッサージにより血流が阻害されてASOを悪化させる恐れがあるためです。
とくに以下のような状況では、運動療法やマッサージは禁忌(きんき:実施してはならないこと)となります。ASOに対するマッサージ方法は医師に相談してください。
- 深部静脈血栓(しんぶじょうみゃくけっせん)が疑われる
- 潰瘍(かいよう)や炎症が起きている
- 安静時に痛みがある
それぞれの詳細を解説します。
1.深部静脈血栓が疑われる
太ももから下側に腫れや赤み、痛みが現れているときは、深部静脈血栓が疑われるためマッサージは禁忌です。(文献1)深部静脈血栓とは、長時間足を動かさないで同一姿勢でいると、足の静脈に血栓(けっせん:血の塊)ができてしまうことです。
血栓が血流に乗ってしまうと、肺の血管を詰まらせて肺塞栓症(はいそくせんしょう)という危険な病気を引き起こす恐れがあります。深部静脈血栓が疑われる際にマッサージをすると、圧迫により血栓が剥がれて肺塞栓症に進展する危険性があります。(文献2)
ASOにおいても血栓ができることがあるため注意が必要です。深部静脈血栓が疑われる症状が現れている場合は、速やかに医療機関を受診してください。
2.潰瘍(かいよう)や炎症が起きている
下肢閉塞性動脈硬化症(ASO)のFontaine(フォンテイン)分類におけるⅣ度に該当する場合は、原則運動療法は禁忌です。(文献3)Fontaine分類とは、ASOの重症度をⅠ〜Ⅳ度で評価するための分類です。
このような重症例では皮膚や組織への血流が著しく低下しているため、マッサージによる組織への物理的な圧迫や摩擦が潰瘍や壊死部に対して悪影響を及ぼす可能性があります。そのため、マッサージの実施も推奨できません。
Ⅳ度は、皮膚や筋肉への血流が不足している最も重い状態です。小さな傷や低温やけどをきっかけに以下のような症状が現れています。
| 症状 | 詳細 |
|---|---|
| 潰瘍(かいよう) | 皮膚や粘膜が深く傷ついている状態 |
| 壊死(えし) | 細胞の一部が壊れている状態 |
赤く炎症が起きている場合は、なんらかの感染症が発生している恐れもあります。これらの症状が現れている場合は、マッサージは行わず速やかに医療機関を受診してください。
3.安静時に痛みがある
安静時に痛みがある場合は、Fontaine分類におけるⅢ度に該当します。Ⅲ度も原則運動療法は禁忌です。(文献3)そのため、マッサージの実施も推奨できません。
ASOにおいて、II度とⅢ度の症状を間違えないように注意が必要です。症状の違いは以下の通りです。
| 分類 | 症状 |
|---|---|
| II度 | 一定の距離を歩くと、ふくらはぎが締め付けられるような痛みが現れ歩けなくなる。休むと痛みがなくなり歩けるようになる。この状態を間欠性跛行(かんけつせいはこう)と呼ぶ。 |
| Ⅲ度 | 歩く距離が徐々に短くなり、安静にしていても痛みが持続する。 |
(文献4)
Ⅲ度の症状が現れている場合は、狭窄や閉塞が悪化している状態です。こちらも医療機関を受診して医師の指示に従ってください。
その他の下肢閉塞性動脈硬化症に対する禁忌
下肢閉塞性動脈硬化症(ASO)の患者様は、弾性ストッキングを原則着用してはいけません。ASOの患者様が装着すると、圧迫により血行障害が悪化する恐れがあるためです。弾性ストッキングとはストッキングの圧力により、下肢の筋肉のポンプ作用を高めて血流を促す製品です。
ASOの患者様に対して弾性ストッキングの着用が必要になった際は、医師が慎重に検討します。医療現場では、2011年から2016年の間にASOの患者様に対して、弾性ストッキングを着用させてしまった事例が4件発生しています。(文献5)
万が一のために患者様本人と家族の間でも、ASOを患っている場合は原則弾性ストッキングを着用してはならないことを理解しておきましょう。
下肢閉塞性動脈硬化症に効果的な運動療法
下肢閉塞性動脈硬化症(ASO)に対する運動療法は、Fontaine分類におけるⅠ度(冷寒やしびれ感がある)、Ⅱ度の方に推奨されています。有効な運動療法は歩行です。間欠性跛行の改善や歩行距離の向上を期待できます。歩行は以下のような流れで実施します。
- がまんできる痛みが生じる強度で歩く
- 強い痛みが出る手前で休む
- この繰り返しを1回30〜60分行う
歩行は週3回を少なくとも3カ月間の実施が推奨されています。運動療法は「病院で行う監督下運動療法」と「自宅で行う在宅運動療法」があります。
監督下運動療法のほうが間欠性跛行の改善効果が高く、推奨されています。(文献6)自宅で運動療法を行う場合は、医師の指導を受けてからにしましょう。
下肢閉塞性動脈硬化症のセルフケアにおける5つのポイント
ASOを管理するには、以下のようなポイントを抑えておくことが大切です。
- フットケアを行う
- 高血圧を改善する
- 脂質異常症を改善する
- 血糖値をコントロールする
- 禁煙をする
それぞれの詳細を解説します。
1.フットケアを行う
ASOを管理するためには、以下のようなフットケアの実施が大切です。
| フットケアの種類 | 詳細 |
|---|---|
| 足を冷やさない |
足が冷えると血管が収縮してしまい血流が悪くなるため、以下のような方法で保温する。
靴下は締め付けがきつすぎないものにする。 |
| 傷を作らない |
小さな傷から感染症を引き起こすリスクがあるため、以下のことに注意する
|
| 低温やけどに注意する | 低温やけどから感染症を引き起こすリスクがある。電気あんかや湯たんぽ、カイロは直接肌に当てると低温やけどを起こすリスクがあるため、使用する際は間接的に保温する。 |
(文献4)
巻き爪は傷ができるリスクがあります。巻き爪がある方は形成外科などで治療してもらいましょう。
2.高血圧を改善する
高血圧は、動脈硬化(どうみゃくこうか:血管が弾力性を失っている状態)を引き起こすためASOを悪化させる原因です。ASOの方は以下の血圧値を目標として改善を目指しましょう。
| 年齢 | 降圧目標 |
|---|---|
| 75歳未満 | 130/80mmHg未満 |
| 75歳以上 | 140/90mmHg未満 |
(文献6)
高血圧の管理において減塩はとくに大切です。以下を参考にして減塩をしましょう。
- 麺類の汁は飲まない
- 外食や加工食品は避ける
- 薄味に味付けをする
- 香辛料や香草野菜、酸味などで味付けをする
- 調味料は酢やケチャップ、マヨネーズなど塩分が少ないものを上手に利用する
- 味噌汁などの汁物は具だくさんにして塩分量を減らす
- 漬物は自家製の浅漬けにして少量にする
3.脂質異常症を改善する
脂質異常症は下肢閉塞性動脈硬化症(ASO)の悪化に関係しています。悪玉コレステロール値や中性脂肪値が高いと動脈硬化を進行させるためです。一般的にASOと脂質異常症を合併している方は、薬物療法が検討されます。(文献6)
薬物療法だけでなく以下のことに注意して、脂質異常症の改善を目指しましょう。
- 禁煙をする(受動喫煙も避ける)
- 標準体重を目指す
- 過食をしない
- アルコールの過剰摂取をしない
- 肉類や乳製品、卵黄の摂取を控える
- 魚類や大豆製品をおかずにする
- 野菜類や果物類、海藻類、穀類(精製されていない物)の摂取を増やす
脂質異常症を改善するための運動療法に関しては、医師と相談しながら進めましょう。
4.血糖値をコントロールする
糖尿病患者様は血糖値のコントロールが重要です。糖尿病は末梢神経障害の発症が多く、下肢閉塞性動脈硬化症(ASO)と併存すると足病変(そくびょうへん:足に起こるトラブルの総称)を生じるリスクがあります。(文献6)
血糖値をコントロールするには、以下のような食習慣の改善が重要です。
- ゆっくりとよく噛んで食べる
- 1日3食規則正しく食べる
- 食事は腹八分目にする
- 就寝前に食事や間食をしない
- 三大栄養素は炭水化物4〜6割、タンパク質2割、脂質2〜3割の割合にする
- 野菜類、海藻類、きのこ類、大豆製品、乳製品などさまざまな食品をバランス良く食べる
血糖値改善のための運動療法に関しては、医師と相談しながら進めましょう。
関連記事:糖尿病|食事で予防する、食生活を整えて病気の悪化や合併症を防ぐ
関連記事:糖尿病!運動療法なら改善はもとより予防にも効果を発揮
5.禁煙をする
たばこは下肢閉塞性動脈硬化症(ASO)を悪化させるだけではありません。ASOの治療方法である血行再建術(けっこうさいけんじゅつ:閉塞や狭窄した血管の血流を改善する治療)を実施した患者様の症状を再発させる恐れがあります。(文献4)
これは、ニコチンに血管を収縮させる作用があるためです。他にも中性脂肪値を増加させるため、高血圧や脂質異常症、動脈硬化などを悪化させる原因にもなります。一人で禁煙できそうにない場合は、禁煙外来で医師に相談しましょう。
まとめ|下肢閉塞性動脈硬化症のマッサージ方法は医師に相談しよう
前提として下肢閉塞性動脈硬化症(ASO)に対するマッサージは、自己流で行わず医師に相談しましょう。
深部静脈血栓が疑われる場合や重症度Ⅲ度とⅣ度のASOに対しては、マッサージを実施しないでください。
マッサージよりも、足を「保温する」「清潔にする」「傷を作らない」などのフットケアが大切です。また、高血圧や脂質異常症、糖尿病を合併している方は、それぞれの治療を進めて、食生活や運動習慣を見直してください。
ただし、運動療法の歩行は、病院で医療者の監督の下で実施するのが推奨されています。自宅で行う場合は医師の指導を受けてからにしましょう。
参考文献
(文献1)
冨岡 正雄,佐浦 隆一.「下肢DVT下でのリハビリテーション治療―整形外科疾患―」『Jpn J Rehabil Med』58(7), pp.724-730, 2021年
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjrmc/58/7/58_58.724/_pdf(最終アクセス:2025年5月20日)
(文献2)
厚生労働省「深部静脈血栓症/肺塞栓症(いわゆるエコノミークラス症候群)について」厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10600000-Daijinkanboukouseikagakuka/0000121801.pdf(最終アクセス:2025年5月20日)
(文献3)
林 富貴雄.「III. 治療と管理の実際 1.内科的治療(薬物療法運動療法)」『日本内科学会雑誌』97(2), pp.66-72, 2008年
https://www.jstage.jst.go.jp/article/naika/97/2/97_332/_pdf(最終アクセス:2025年5月20日)
(文献4)
国立循環器病研究センター「閉塞性動脈硬化症」国立循環器病研究センターホームページ
https://www.ncvc.go.jp/hospital/section/cvs/vascular/vascular-tr-03/(最終アクセス:2025年5月20日)
(文献5)
日本医療機能評価機構「【3】下肢閉塞性動脈硬化症の患者への弾性ストッキング装着に関連した事例」日本医療機能評価機構ホームページ
https://www.med-safe.jp/pdf/report_2016_4_T003.pdf(最終アクセス:2025年5月20日)
(文献6)
日本循環器学会「2022年改訂版 末梢動脈疾患ガイドライン」日本循環器学会ホームページ
https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2022/03/JCS2022_Azuma.pdf(最終アクセス:2025年5月20日)