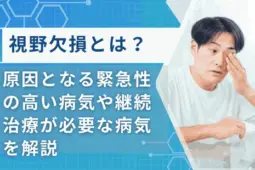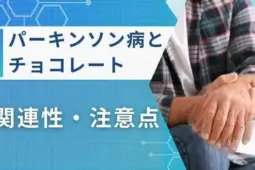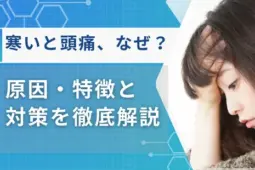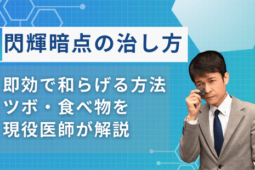- 頭部
- 頭部、その他疾患
パーキンソン病の初期症状とは?セルフチェック法や進行度別の症状も解説
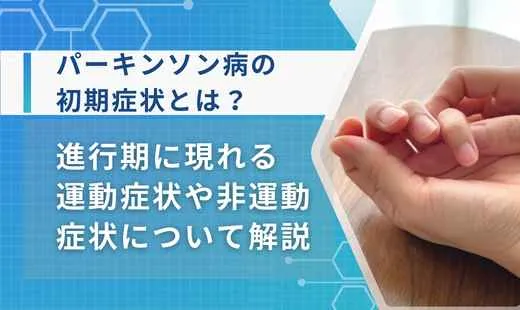
「パーキンソン病の初期症状を具体的に知りたい」
「進行するとどのような症状が現れる?」
「発症した際に気を付けることは?」
パーキンソン病の初期症状として頻繁に現れるのは、静止時の手指のふるえです。とくに50歳を超えてから現れている方は注意が必要です。
本記事では、パーキンソン病の初期症状をはじめとして以下を解説します。
セルフチェックするために初期症状の一覧も記載しています。気になる症状が現れている方は、本記事を参考にしてください。
当院「リペアセルクリニック」の公式LINEでは、再生医療の情報提供と簡易オンライン診断を実施しております。
パーキンソン病について気になる症状がある方は、ぜひ一度公式LINEにご登録ください。
目次
パーキンソン病の初期症状【セルフチェック法】
パーキンソン病の初期症状には以下のようなものが挙げられます。
- 今までなかった手指のふるえが静止時に現れる
- 周囲と比較して歩行が遅い
- 起き上がりの動作が遅く、上手にできない
- 歩行時に手の振りが上手にできていないと指摘された
- ゴルフなど緻密さが必要なスポーツが以前よりも下手になった
以上のいずれかが現れている場合は、パーキンソン病を発症している恐れがあります。とくに50歳以降に現れている場合は注意が必要です。ここからは、それぞれの初期症状の詳細を解説します。
パーキンソン病の症状以外の原因や治療法について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
静止時に手指がふるえる
パーキンソン病の初期症状として最も多いと言われているのが振戦(しんせん)です。振戦とは、静止時に現れる手指のふるえのことです。振戦は約60%の割合で初期症状として現れると報告があります。
(文献1)
振戦の特徴は以下の通りです。
- いつの間にか手や指がふるえる
- 自分で意識を向けたり、他人に指摘されるとふるえは消える
- ふるえは1秒に5回前後で規則的である
- 下顎にふるえが現れることもある
今までなかった手のふるえが続く場合は、医療機関の受診を検討してください。
歩行しづらくなる
以下のような歩行障害が現れている場合は、パーキンソン病の初期症状の恐れがあります。
- 周囲の人よりも歩行が遅い
- 段差でつまずく
- 前傾姿勢(前かがみになること)で歩くようになった
歩行障害は、約24%の割合で初期症状として現れると報告があります。(文献1)基本的には、前傾姿勢は初期段階では目立たない場合が多いです。
動きが遅くなる
以下のような症状は、パーキンソン病の初期症状の恐れがあります。
- 起き上がりの動作が遅く、上手にできない
- 手を内側や外側に回すことは早くなり、動作範囲が狭くなった
動きの遅さは約21%の割合で初期症状として現れると報告があります。(文献1)すべての動作が遅くなるというわけではありません。主に大きな動きが遅くなり上手にできなくなる傾向です。
体が硬くなる
体の硬さは、パーキンソン病の初期症状として現れることがあります。とくに表情が硬くなる仮面様顔貌(かめんようがんぼう)が現れる傾向です。(文献1)
しかし、仮面様顔貌は医療者以外の方では、見分けることが困難である場合が多いです。体の硬さとしてわかりやすい症状には、以下のようなものが挙げられます。
- 歩行時に手の振りが上手にできない
- ゴルフなど緻密さが必要なスポーツが以前よりも下手になった
ただし、これらの症状は本人では気付けないことが多いです。
パーキンソン病の進行期症状(運動症状)
パーキンソン病の進行期には、以下のような運動症状が現れます。
| 運動症状 | 詳細 |
|---|---|
| 無動(むどう) | 運動の減少や動作の遅れ |
| 筋強剛(きんきょうごう) | 筋肉が硬くなりこわばる |
| 姿勢保持障害 | 安定した姿勢を保つことが困難になる |
| 姿勢異常 | 姿勢が前屈してしまう |
| すくみ現象 | すくみ足や歩行の加速が見られる |
それぞれの詳細を解説します。
無動|運動の減少や動作の遅れ
無動とは、運動の減少や動作の遅れなどの症状です。
具体的な症状は以下のようなものです。
- 字が上手に書けない
- 箸が使いにくくなる
- 歩行障害が現れる
- 寝返り、着替えなどの大きな動作が障害される
- 声量が小さくなる
- 仮面様顔貌が現れる
- 流涎(りゅうぜん:よだれが流れること)が見られる
無動が進行すると、患者様の日常生活の動作に支障をきたします。
筋強剛|筋肉が硬くなりこわばる
筋強剛とは、筋肉がこわばって、関節の曲げ伸ばしが制限される症状です。
筋強剛は以下の2つの種類に分けられます。
| 筋強剛の種類 | 詳細 |
|---|---|
| 鉛管様強剛(えんかんようきょうごう) | 関節の抵抗がほぼ一定である |
| 歯車現象 | カクカクと小刻みに引っかかるような抵抗である |
筋強剛は、手や足だけでなく、首や胴体にも現れます。関節の動きが制限されるため、進行すると日常生活に支障をきたし始めます。
姿勢保持障害|安定した姿勢を保つことが困難になる
姿勢保持障害とは、安定した姿勢を保てなくなる症状です。パーキンソン病を発症してから、数年後に現れる症状であり、初期段階で見られることはほとんどありません。
姿勢保持障害が現れ始めると、立位の体制を立て直すことが困難になり、外力を加えると簡単に倒れてしまうようになります。立ち上がり時や歩行時、方向転換時に転倒しやすくなるため注意が必要です。
姿勢異常|姿勢が前屈してしまう
姿勢異常とは、立位時または歩行時に前屈姿勢が現れる症状です。
前屈姿勢は以下のようなパーキンソン病特有のものが見られます。
- 上体は前屈しているが首は後屈して顎を突き出している
- 手首と肘の関節は曲がった状態になる
腰付近で大きく前屈する場合や側方で屈曲する姿勢異常が現れることもあります。これらは、パーキンソン病の進行に伴って悪化していきます。
すくみ現象|すくみ足や歩行の加速が見られる
すくみ現象とは、以下のような症状のことです。
| すくみ現象 | 詳細 |
|---|---|
| 加速歩行 | 歩き出すと足早になり止まることが難しくなる |
| すくみ足 |
歩行時に足が前になかなか出ないまたは止まってしまう |
加速歩行やすくみ足と姿勢保持障害が合わせて現れると、転倒リスクが高まってしまいます。すくみ足は「等間隔に引いた線をまたいで歩く」「メトロノームを活用する」など、視覚や聴覚に訴えるリハビリを行うと改善する場合があります。
パーキンソン病の非運動症状
パーキンソン病は運動症状だけでなく、以下のような非運動症状も現れます。
- 睡眠障害
- 精神・認知・行動障害
- 自律神経障害
- 感覚障害
それぞれの詳細を解説します。
睡眠障害
パーキンソン病の睡眠障害には、以下のようなものがあります。
| 睡眠障害 | 症状 |
|---|---|
| 日中過眠 | 日中に過度な眠気が現れる |
| 突発的な睡眠 | 眠気の有無にかかわらず食事や会話、運転などの活動中に突然眠り込んでしまう |
| 夜間不眠 | 寝付きが悪い、夜間目が覚める、朝早く起きてしまうなどの症状が現れる |
| レム睡眠行動障害 | 入眠中に夢の内容と一致した行動が現れる |
| 下肢静止不能症候群 |
入眠時に下肢の不快感や下肢を動かしたい欲求などが現れる |
これらの睡眠障害は、パーキンソン病の進行とともに現れやすくなります。とくに「突発的な睡眠」は運転中などに起こると危険なため、症状がある場合は医師に相談し、運転については慎重に判断することが大切です。
精神・認知・行動障害
パーキンソン病の精神・認知・行動障害には以下のようなものがあります。
| 精神・認知・行動障害 | 症状 |
|---|---|
| 気分障害 | うつ気分、無感情、意欲の低下、快感の消失、興味の減少、不安などが現れる |
| 幻覚・妄想 | 「あるはずのないものが見える」「真実ではないことを真実だと思って想像する」などの症状が現れる |
| 行動障害 | 病的な賭博、性欲の亢進、買いあさり、むちゃ食いなどの症状が現れる |
| 認知機能障害 |
作業をやり通す能力の低下や注意力の低下、物の形や位置を正確に把握できないなどの症状が現れる |
これらはパーキンソン病の症状だけでなく、治療薬の副作用として現れることもあります。治療を開始してから普段と異なる行動が見られたら、すぐ医師に相談してください。
自律神経障害
パーキンソン病の自律神経障害には以下のようなものがあります。
| 自律神経障害 | 症状 |
|---|---|
| 起立性低血圧 | 急に立ち上がった際に血圧が低下してふらつきやめまいが現れる |
| 排尿障害 | 排尿の回数が多くなる、強い尿意が生じるなどの症状が現れる |
| 消化管運動障害 |
主に便秘 |
| 性機能障害 | 男性では勃起障害が現れる |
| 発汗障害 | 発汗が多くなる、または発汗が少なくなる |
| 流涎 | よだれが口から流れ出ること 飲み込みの減少や姿勢異常、無動などが原因である |
| 嚥下障害 | 飲み込みが悪くなりむせやすくなる |
自律神経障害は日常生活に大きく影響します。これらの症状は適切な治療や生活習慣の改善で軽減できる場合が多いため、我慢せずに医師や理学療法士に相談しましょう。
感覚障害
パーキンソン病の感覚障害には以下のようなものがあります。
| 感覚障害 | 症状 |
|---|---|
| 嗅覚障害 | 匂いを感じにくくなる |
| 痛み |
肩や背中などに痛みが現れる |
嗅覚障害は、パーキンソン病の初期から現れることが多く、運動症状よりも早期に出現する場合があります。痛みについては、筋肉のこわばりが原因の場合、適切なリハビリや薬物治療で改善が期待できます。
パーキンソン病の進行度別の症状
パーキンソン病には、進行度を評価するHoehn-Yahr(ホーン・ヤール)重症度分類があります。
Hoehn-Yahr重症度分類を参考にした進行度別の症状は以下の通りです。
| Hoehn-Yahr重症度分類 | 進行度別の症状 |
|---|---|
| Ⅰ度 | 片側の手足だけにふるえや筋肉のこわばりが現れる |
| Ⅱ度 | 両側の手足にふるえや筋肉のこわばりが現れる |
| Ⅲ度 | 手足のふるえや筋肉のこわばりが強くなり、姿勢保持障害も現れる |
| Ⅳ度 |
症状が重度となり立ち上がりや歩行など日常生活の動作が困難になる |
| Ⅴ度 |
重度の症状により自力での日常生活が困難な状態になる |
パーキンソン病にかかりやすい人の特徴
以下に該当する方は、パーキンソン病を発症しやすい人と言われています。
- 年齢が50歳を超えている
- 家族にパーキンソン病を発症した方がいる
- 便秘をよく起こしている
- 気分障害や頭部への外傷の既往歴がある
パーキンソン病は基本的に50歳を超えると発症しやすい傾向にあります。とくに65歳を超えると罹患率は約10倍にまで増えると報告があります。(文献2)
パーキンソン病は、ほとんどの場合に遺伝は関係ありません。しかし、家族に既往歴があると、50歳以下の若年性パーキンソン病になりやすいと考えられています。
その他にも、便秘や気分障害、頭部外傷の既往歴などの環境因子もパーキンソン病の発症リスクに関連すると考えられています。
パーキンソン病になったら気を付けることとは
パーキンソン病を発症した場合は、適切な薬物療法とリハビリを受けてください。適切に薬物療法を進めないと、症状の悪化や悪性症候群を引き起こすリスクがあるためです。
悪性症候群とは、パーキンソン病の薬の投与後や減薬後、中止後などに現れる発熱、急激な血圧の変化、意識障害などのことです。場合によっては生命が危険な状態になることもあります。悪性症候群を防ぐためにも、自己判断による薬の減薬や中断は行わないことが大切です。
パーキンソン病におけるリハビリは、症状や進行度に沿って適切に実施すれば、症状の改善または進行の抑制を期待できます。医師やリハビリスタッフと相談しながら適切に取り入れてください。
パーキンソン病における再生医療
近年パーキンソン病における再生医療の研究が多く行われています。再生医療とは、人が本来持っている「再生する力」を活用した治療方法です。
パーキンソン病に対する再生医療では、iPS細胞(あらゆる細胞に変化できる能力をもつ細胞)を用いた治療や遺伝子治療などの先進的なアプローチによる、問題の解決の研究が行われています。(文献3)例えば、体の外でドパミン細胞を作り、脳内に移植する治療方法などの研究です。
再生医療を含むパーキンソン病に対する先進医療について、詳しくは以下の記事をご覧ください。
また、当院の公式LINEでは、再生医療の情報提供や症例紹介、簡易オンライン診断を実施しております。
パーキンソン病について気になる症状がある方は、ぜひチェックしてみてください。
\無料オンライン診断実施中!/
まとめ|パーキンソン病の初期症状が疑われたら受診しよう
パーキンソン病の初期症状で多いのは手指のふるえや歩行障害、動きの遅さ、体の硬さなどです。進行すると、無動や筋強剛、姿勢保持障害、姿勢異常、すくみ現象などの症状が現れ始めます。その他にも、睡眠障害や自律神経障害、精神・認知・行動障害などの非運動症状も現れます。
パーキンソン病は進行性であり完治する病気ではありません。しかし、早期に適切な診断や薬物療法、リハビリを実施すれば、進行を遅らせることができます。疑われる症状が現れている場合は、医療機関を受診してください。
治療の選択肢として再生医療をご検討の場合は、当院「リペアセルクリニック」へお気軽にご相談ください。患者様の状態にあわせて治療方針を提案いたします。
(文献1)
1.パーキンソン病の初期症状と診断|日本内科学会雑誌