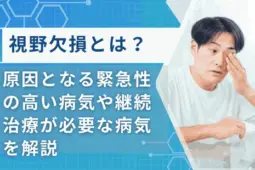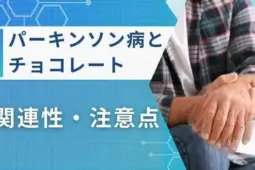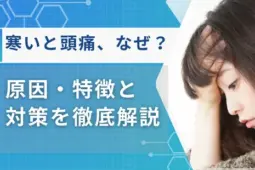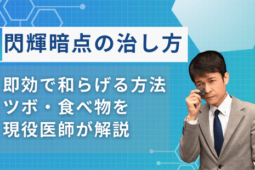- 頭部
- 頭部、その他疾患
閃輝暗点の原因はコーヒーかも?カフェインの影響と飲み方のコツを解説
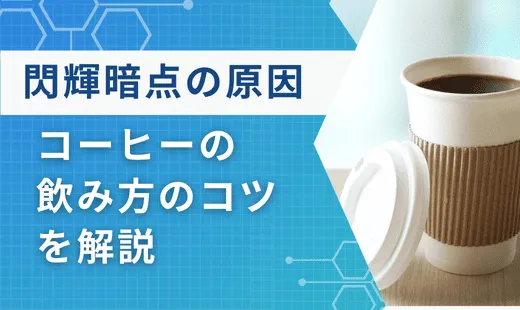
閃輝暗点は視界の一部にキラキラ・ギザギザした光や模様があらわれ、徐々に拡大して視野の欠損を引き起こす症状です。
片頭痛の前兆としてよく知られる閃輝暗点ですが、必ずしも頭痛を伴うわけではありません。(文献1)
閃輝暗点を起こす有力な説としては後頭葉の血流低下が挙げられており、コーヒーの過剰摂取が発症リスクを高めるのではないかと考えられています。
閃輝暗点は眼科系疾患ではなく、脳の機能の一時的変化により引き起こされるため、発症すると脳の病気を心配する方もいるでしょう。
本記事では閃輝暗点とコーヒーの関係について解説するとともに、1日当たりの摂取目安を紹介します。閃輝暗点にお悩みのコーヒー好きの方は参考にしてください。
目次
コーヒーが原因で閃輝暗点を引き起こすことがある
コーヒーに含まれるカフェインには血管を収縮させる作用があり、過剰摂取により閃輝暗点のリスクを高める可能性があります。
一方で、カフェインには抗酸化作用があり、血管機能の改善が見込めるためデメリットばかりではないのも事実です。
はじめに、コーヒーと閃輝暗点および血管機能との関係について詳しく解説します。
閃輝暗点の見え方や初期症状や治療法などについては、以下の記事もご覧ください。
【関連記事】
【医師監修】閃輝暗点の見え方について解説|片目だけ・初めての症状は危険?
【医師監修】閃輝暗点とは|放置によるリスクから初期症状・治療法まで詳しく解説
カフェインが脳血管収縮を助長することで起こる
コーヒーが原因で閃輝暗点を起こす理由は、カフェインの過剰摂取により脳の血管収縮が助長されるためです。
コーヒーに含まれるカフェインには血管を収縮させ、血液の循環を阻害する作用があります。
閃輝暗点は後頭葉に送られる血流量の減少により発症リスクが増加すると考えられており、カフェインの過剰な摂取は脳の血管を収縮させ、閃輝暗点のリスクを高める可能性があります。
カフェインは神経を鎮静させるアデノシンと似た構造を持つのも特徴です。
カフェインを過剰摂取すると、本来であればアデノシンが結合するはずの受容体にカフェインが結合し、神経の鎮静作用が阻害されます。(文献2)
コーヒーを飲み過ぎると睡眠の質が低下すると言われるのは、カフェインの過剰摂取により神経が興奮状態に陥るためです。
睡眠不足も自律神経のバランスを乱して血管の収縮を起こすため、閃輝暗点の発症リスクを高める一因となります。(文献3)
クロロゲン酸の抗酸化作用で血管機能の改善が見込める
コーヒーにはカフェイン以外にも多くの成分が含まれていますが、なかでもクロロゲン酸には高い抗酸化作用があり、血管機能の改善が見込める点がメリットです。
クロロゲン酸はポリフェノールの一種で、LDLコレステロールの酸化を抑制し、動脈硬化の予防に役立つことで知られています。
クロロゲン酸による血管機能の改善効果は、FMD値(血流依存性血管拡張反応)を調べることで明らかになります。
FMD値に関して462名の高血圧患者を対象に、コーヒー摂取量と血管機能についての評価が行われました。
その結果、コーヒーを摂取した群では非摂取群に比べ、FMD値に有意な増加が見られました。(文献4)
カフェインの過剰摂取は血管収縮のリスクを高めますが、1日あたりコーヒー2杯(400ml)程度であれば、むしろ血管拡張作用が得られるとわかります。
閃輝暗点はコーヒー以外のカフェインにも起因する
閃輝暗点はコーヒーだけでなく、カフェインを含むその他の飲料にも起因するため注意が必要です。
カフェインが含まれる主な飲料および含有量の目安は以下のとおりです。(文献5)
| 飲料 | カフェイン含有量(100mlあたり) |
|---|---|
| コーヒー | 60mg |
| ほうじ茶 | 20mg |
| ココア | 14mg |
| ウーロン茶 | 20mg |
| 紅茶 | 30mg |
| 抹茶 | 48mg |
| コカ・コーラ | 9.5mg |
| エナジードリンク | 32~300mg |
エナジードリンクのなかにはカフェイン含有量が多い商品もあるため、閃輝暗点を起こしやすい方は注意が必要です。(文献6)
眠気覚ましにエナジードリンクを気軽に飲む方もいますが、1本飲むだけでコーヒー2〜3杯分のカフェインを摂取するケースもあるため、何本も飲まないようにしましょう。
エナジードリンクの過剰摂取は閃輝暗点のリスクを高めるだけでなく、糖尿病の発症リスクも増加するため注意する必要があります。(文献7)
コーヒーが原因で起こる閃輝暗点のリスクを下げるコツ
コーヒーが原因で起こる閃輝暗点のリスクを下げるコツは以下の2つです。
- 1日に摂取するコーヒーは2杯(400ml)ほどに留める
- コーヒーの合間に水分を意識的に補給する
それぞれについて解説します。
1日に摂取するコーヒーは2杯(400ml)ほどに留める
コーヒーが原因で起こる閃輝暗点のリスクを下げるためには、1日の摂取量を400ml(カップ2杯分)程度にとどめるのがポイントです。
1日400ml程度のコーヒーであれば、クロロゲン酸の作用によりFMD値が増加し、血管機能の改善が見込めるとわかっています。
一方、カフェインの過剰摂取は心拍数や血圧を増加させ、心血管疾患のリスクを高めることも示唆されています。
ACCアジアで発表された研究では、1日に400ml以上のコーヒーの摂取が自律神経に重大な影響を与え、心拍数と血圧を徐々に増加させるとわかりました。(文献8)
適量のコーヒーは心身に良い影響をもたらしますが、過剰摂取は健康被害のリスクを高めると覚えておきましょう。
コーヒーの合間に水分を意識的に補給する
コーヒーが原因で起こる閃輝暗点のリスクを下げるためには、水分を意識的に補給するよう意識しましょう。
コーヒーに含まれるカフェインは腎臓で行われる水分の吸収を妨げる作用があるため、摂取量が増えると排尿の回数が増加しがちです。(文献9)
排尿の回数が増えると血液中に含まれるカフェインの濃度が相対的に上昇するため、閃輝暗点のリスクを高めやすくなります。
コーヒーを常飲する方は合間に意識的に水分を補給し、血中カフェイン濃度が上がり過ぎないよう注意してください。
コーヒーの利尿作用に悩まされる方には、カフェインを取り除いたデカフェがおすすめです。
コーヒーの飲み方を改善しても閃輝暗点を繰り返すなら脳の病気の疑いあり
上記の対策を講じても閃輝暗点を繰り返す方は、脳の病気の疑いもあると覚えておいてください。
閃輝暗点は片頭痛の前兆としてよく知られていますが、脳梗塞などが原因で発現する例も見られるためです。
閃輝暗点の後に片頭痛の発作が見られない場合、脳梗塞や脳腫瘍、一過性脳虚血発作(TIA:transient ischemic attack)の疑いがあると考えられています。(文献10)
一過性脳虚血発作(TIA)を発症すると突然の言語障害や感覚障害など脳梗塞と似た症状があらわれますが、通常は24時間以内に消失します。しかし、症状が消失したからといって安心はできません。一過性脳虚血発作(TIA)は脳梗塞に移行する可能性が高いため注意が必要です。
なお、閃輝暗点が脳梗塞の前兆である可能性は低いと考えられているため、過度に心配する必要はありません。
脳の病気が疑われる閃輝暗点が気になるなら早急に受診しましょう
脳の病気が疑われる閃輝暗点をたびたび繰り返す方は、早急に専門の医療機関を受診しましょう。
閃輝暗点の原因の一つである脳梗塞を発症すると、身体の片側のしびれや麻痺、ろれつが回らない、手にしたコップを取り落とすなどの症状があらわれます。
閃輝暗点だけでなく上記の症状が見られる方は、脳神経外科や脳神経内科、神経内科などを受診してください。
脳梗塞の発症から時間が経過するほど脳細胞が破壊され続けるため、一刻も早く専門医による治療を受けることが大切です。(文献11)
まとめ|閃輝暗点が落ち着くようにコーヒーの飲み方を調整しよう
閃輝暗点を発症すると視界の一部にキラキラ・ギザギザした光や模様があらわれ、徐々に拡大して視野の欠損を引き起こします。
片頭痛の前兆としてよく知られる現象の一つですが、閃輝暗点の後に頭痛の発作が起きないケースでは、脳梗塞や脳腫瘍、一過性脳虚血発作(TIA)の可能性も疑われます。
コーヒーに含まれるカフェインには血管を収縮させる作用があるため、頻繁に閃輝暗点を起こす方は摂取量の調整が必要です。
健康な成人であれば1日に400mgのカフェインを摂取しても問題ないとされますが、妊婦や妊娠の可能性がある女性、授乳中の女性は300mgまでにとどめてください。
閃輝暗点の原因でもある脳梗塞の治療法として、近年になり再生医療への関心が高まっています。
リペアセルクリニックでは脳梗塞の後遺症治療・再発予防に再生医療(幹細胞治療)をご提案しております。ご質問やご相談がございましたら、気軽に無料カウンセリングまでお越しください。
\無料オンライン診断実施中!/
(文献1)
徳島県医師会「閃輝暗点」
https://www.tokushima.med.or.jp/kenmin/doctorcolumn/hc/1663-2018-11-22-00-41-33(最終アクセス:2025年6月18日)
(文献2)
農林水産省「カフェインの過剰摂取について」
https://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/risk_analysis/priority/hazard_chem/caffeine.html(最終アクセス:2025年6月18日)
(文献3)
溜池山王伊藤眼科「急に視界の一部が見えない:閃輝暗点の原因・症状・対処法」
https://ts-itoeyeclinic.com/diary/scintillating_scotoma/(最終アクセス:2025年6月18日)
(文献4)血管 Vol47 No.2「高血圧患者におけるコーヒー摂取:血管機能に与える影響について」
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjcircres/47/2/47_1/_pdf/-char/ja(最終アクセス:2025年6月18日)
(文献5)
農林水産省「カフェインの過剰摂取について」
https://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/risk_analysis/priority/hazard_chem/caffeine.html(最終アクセス:2025年6月18日)
(文献6)ニューロテックメディカル「コーヒー摂取と閃輝暗点発症の関係性とは」
https://neurotech.jp/medical-information/coffee-intake-and-the-development-of-scintillating-scotoma/#1link(最終アクセス:2025年6月18日)
(文献7)NHK「「エナジードリンク」 飲みすぎの危険性とは」
https://www.nhk.jp/p/nhkjournal/rs/L6ZQ2NX1NL/episode/re/YX4128VJRR/(最終アクセス:2025年10月09日)
(文献8)AMERICAN COLLEGE of CARDIOLOGY「慢性的なカフェイン摂取は活動後の心拍数や血圧に影響を与え、CVDのリスクを高める」(英文による解説)」
https://www.acc.org/Latest-in-Cardiology/Articles/2024/08/14/16/39/Chronic-High-Caffeine-Consumption-Impacts-Heart-Rate-BP(最終アクセス:2025年6月18日)
(文献9)
ウィスパー「【医師監修】コーヒーと頻尿の関係」
https://www.whisper.jp/article-top/learn-urinary-incontinence/coffee/(最終アクセス:2025年6月18日)
(文献10)
横濱もえぎ野クリニック「閃輝暗点」
https://www.ymc3838.com/scintillating-scotoma/(最終アクセス:2025年6月18日)
(文献11)
名古屋徳洲会総合病院「脳梗塞」
https://www.nagoya.tokushukai.or.jp/wp/depts/neurosurgery-2/disease-3/cerebral-infarction(最終アクセス:2025年6月18日)