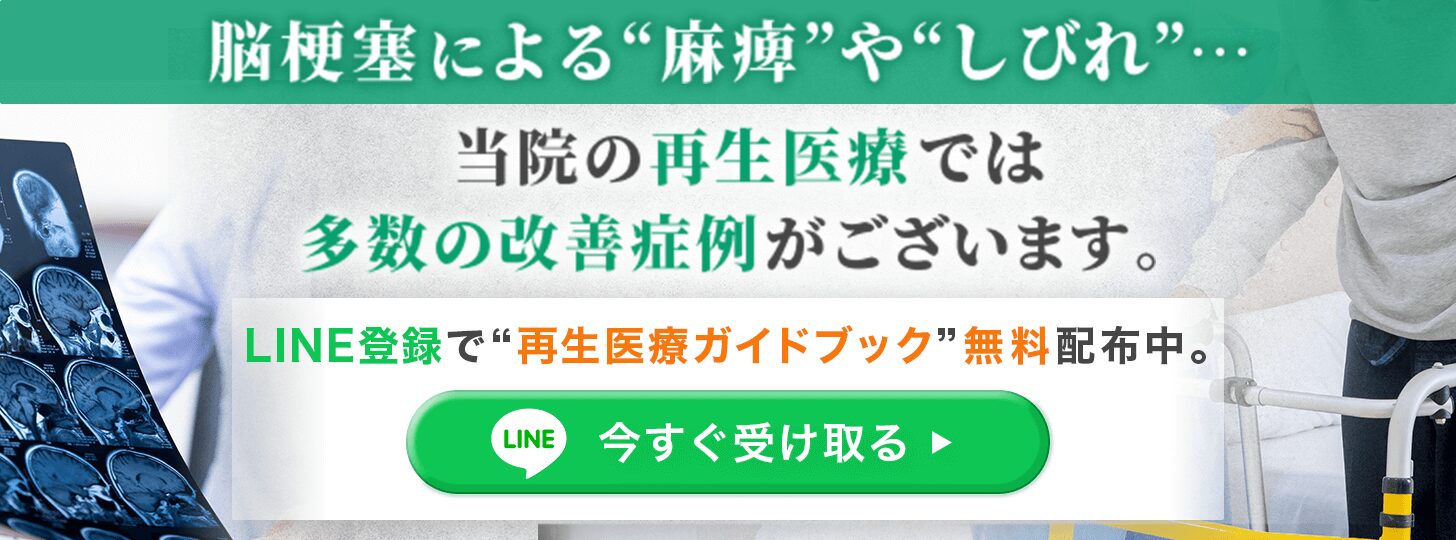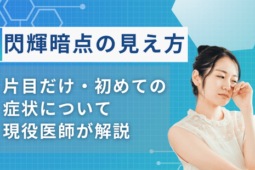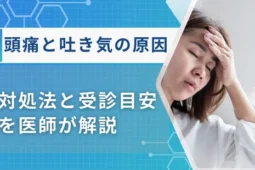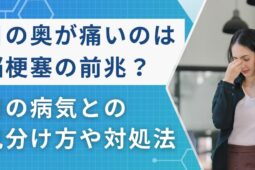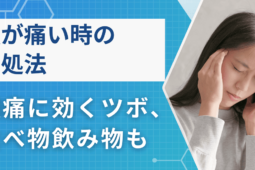- 脳梗塞
- 脳卒中
- 頭部
閃輝暗点が脳梗塞の前兆になる確率は?症状やサインを現役医師が解説
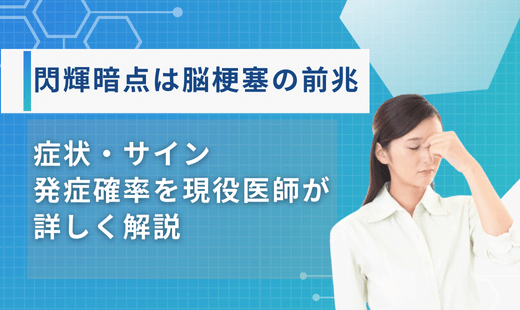
「閃輝暗点から脳梗塞に進展する確率を知りたい。」
「閃輝暗点が出たらどうしたら良いのだろう?」
この記事を読んでいるあなたは、「閃輝暗点」と脳梗塞の関係について、不安に思っているのではないでしょうか。
「受診の目安や受診先を知りたい」と思っているかもしれません。
結論として、閃輝暗点が脳梗塞の前兆となる可能性はあります。過度に恐れる必要はありませんが、脳梗塞であった場合のリスクを考えて受診をおすすめします。
本記事では、閃輝暗点が脳梗塞の前兆である確率や、脳梗塞の場合の症状やサインなどを現役医師が詳しく解説しています。記事を最後までご覧いただくことで閃輝暗点と脳梗塞の関係を理解し、適切な対処ができるようになるでしょう。
当院「リペアセルクリニック」の公式LINEでは、再生医療の情報提供と簡易オンライン診断を実施しております。
閃輝暗点と脳梗塞について気になる症状がある方は、ぜひ一度公式LINEにご登録ください。
目次
閃輝暗点とは?脳梗塞との関係性
| 項目 | 閃輝暗点とは | 脳梗塞との関係性 |
|---|---|---|
| 症状の特徴 | ジグザグ・キラキラした光や模様が視界に現れ、一時的に見えにくくなる | 脳の視覚野の血流低下や血管攣縮で似た症状が現れることがある |
| 持続時間 | 数十分以内で自然に消失 | 持続する場合や他症状を伴う場合は脳梗塞やTIAの可能性 |
| よくみられる原因 | 片頭痛の前兆 | 脳血管の障害や一時的な脳の血流障害 |
| 注意すべきサイン | 中高年で頭痛を伴わず初発・繰り返すケース | 麻痺や言語障害、視覚異常など他の神経症状が同時に出現 |
| リスクが高まる条件 | 前兆を伴う片頭痛がある45歳未満女性 | 片頭痛に喫煙・経口避妊薬を併用すると脳梗塞リスクが7〜9倍に上昇 |
| おすすめの対応 | 症状や経過の記録、心配な場合は脳神経外科受診 | 初発や異常を感じた場合はMRIやCTによる早期精密検査 |
閃輝暗点とは、視界にギザギザした光やチカチカした模様が現れ、数分から30分程度続く一過性の視覚異常です。多くの場合は片頭痛の前兆として生じますが、脳の血流障害が原因となることもあり注意が必要です。
閃輝暗点の初期症状や治療法など、包括的な解説を見たい方は「【医師監修】閃輝暗点とは|放置によるリスクから初期症状・治療法まで詳しく解説」をご覧ください。
脳梗塞では、血流が障害されることで視覚異常が起こることがあります。片頭痛に伴う閃輝暗点と、脳梗塞に関連する視覚症状は、症状の経過や見え方に違いがあるため、区別することが大切です。
とくに初めて経験した場合や、これまでと異なる症状が出た場合には、速やかに医療機関を受診し、必要に応じて検査を受けることが推奨されます。
閃輝暗点の見え方については「【医師監修】閃輝暗点の見え方について解説|片目だけ・初めての症状は危険?」をご覧ください。
閃輝暗点が脳梗塞の前兆である確率は低い
閃輝暗点が脳梗塞の前兆である確率は高くありません。
多くの場合は片頭痛に関連した現象であり、直接脳梗塞に結びつくことは少ないとされています。しかし、これまでの研究では脳梗塞の前兆として閃輝暗点が出現した例も報告されています。
とくに40歳以上の方や、高血圧・糖尿病・不整脈といった生活習慣病を有する場合には注意が必要です。症状の頻度が急に増えたり、見え方がこれまでと異なったりする場合は、一過性脳虚血発作(TIA)など脳血管障害のサインである可能性も考えられます。
脳梗塞は早期に発見し適切な治療を受けることで、進行や悪化を防げるケースもあります。不安を感じた際には、速やかに脳神経外科などを受診しましょう。
以下の記事では、脳梗塞の前兆について詳しく解説しています。
【症状例】閃輝暗点から脳梗塞を発症した2つのケース
| 発症ケース | 詳細 |
|---|---|
| ケース1. 閃輝暗点から片頭痛になり脳梗塞を発症する | 閃輝暗点が片頭痛の前兆として発生し、通常は数十分で消失。片頭痛の後に手足のしびれや脱力感が加わり、脳の後頭葉で脳梗塞が診断された例。片頭痛による血管の収縮が血栓を作り脳梗塞へ進展する可能性 |
| ケース2. 頭痛のない閃輝暗点から脳梗塞を発症する | 頭痛を伴わない閃輝暗点が突然起き、視野の一部欠損や見え方の異常が続く。脳の後頭葉に脳梗塞や一過性脳虚血発作(TIA)が発生し血流障害による症状。自己判断が難しく受診による画像診断が必要 |
閃輝暗点から脳梗塞になる際は、片頭痛発作の後になるパターンと頭痛なしで脳梗塞になるパターンがあり、症状や経過によって背景にある病態は異なります。
片頭痛に続いて脳梗塞が発症するケースでは、血管の収縮や血栓形成が関与すると考えられています。一方、頭痛を伴わない閃輝暗点は一過性脳虚血発作(TIA)の前兆で、見逃すと脳梗塞につながる危険があります。いずれの場合も自己判断は難しく、早期の受診と検査が重要です。
ケース1. 閃輝暗点から片頭痛になり脳梗塞を発症する
| 年齢・条件 | 脳梗塞発症リスクの増加 |
|---|---|
| 45歳未満の前兆のある片頭痛女性 | 脳梗塞リスクが2倍 |
| 50歳未満の前兆のある片頭痛女性(年12回以上の発作がある場合) | 脳梗塞リスクが2~10倍 |
閃輝暗点とは、視界にギザギザした光が現れ数十分でおさまる、片頭痛の前兆です。片頭痛は、脳梗塞のリスクを増加させる可能性があります。
また、喫煙する人や経口避妊薬を服用している人は、脳梗塞の発症リスクが7〜9倍になると報告されています。
若年者で脳梗塞は稀です。しかし、閃輝暗点を伴う片頭痛がある人ではリスクが2倍以上に高まります。
以下の記事では、片頭痛を含む頭痛の危険性について詳しく解説しています。
ケース2. 頭痛のない閃輝暗点から脳梗塞を発症する
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 頭痛を伴わない閃輝暗点 | 脳梗塞や一過性脳虚血発作(TIA)の前兆の可能性 |
| 発症の特徴 | 突然の視覚異常が数分~数十分で回復するが脳血管異常のサイン |
| 発生部位 | 視覚情報を処理する脳の後頭葉 |
| 主な症状 | 視野欠損や視界の異常 |
| 自己判断の難しさ | 脳梗塞かどうかの判断が困難 |
| 受診の推奨 | 初めての症状や異常な経過時は脳神経外科または内科での検査が必要 |
閃輝暗点は、視界にギザギザやチカチカした光が現れる一過性の視覚異常で、多くは片頭痛の前兆として起こります。
頭痛を伴わない閃輝暗点の中には脳梗塞や一過性脳虚血発作(TIA)の前兆として現れることもあります。TIAは数分から数十分で自然に回復するものの、将来的に脳梗塞へ進展するリスクが高い病気です。
脳の部位である後頭葉は、視野を司る部位であり、血流障害が生じると視野の欠損、視覚異常などが起こります。
頭痛を伴わない閃輝暗点は脳梗塞の兆候の可能性があるため、自己判断せず医療機関を受診することが重要です。
脳梗塞のサインとして現れる視覚異常の特徴
| 視覚異常の特徴 | 詳細 |
|---|---|
| 片側だけが見えにくくなる(半盲) | 脳の後頭葉や視覚路の障害による、左右どちらかの視野が欠ける状態 |
| 視界の一部が欠ける(視野欠損) | 視界の一部分が見えなくなり、日常生活に支障をきたす視覚障害 |
| 物が二重に見える(複視) | 脳神経の障害により物が二重に見える状態。両眼で見ると二重に見えることが特徴 |
| 急に視力が落ちる・かすむ | 突然の視力低下やぼやけ、ピントが合わない状態 |
| 目の奥が我慢できないほど痛む | 脳や神経の異常による強い眼球奥の痛み。頭痛や吐き気を伴うこともある |
脳梗塞のサインとして、半盲、視野欠損、複視、急な視力低下やかすみ、強い眼痛などの視覚異常が現れることがあります。
これらは脳の後頭葉や視覚に関わる神経の異常による症状であり、脳梗塞の前兆の可能性もあります。症状が突然出たり繰り返す場合は、速やかに医療機関を受診することが重要です。
片側だけが見えにくくなる(半盲)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 半盲とは | 両目の同じ側の視野が欠ける状態 |
| 発症の原因 | 脳梗塞による視放線や後頭葉の血流障害 |
| 欠損視野の左右 | 右脳障害で左視野欠損、左脳障害で右視野欠損 |
| 日常生活での影響 | 欠けた視野に気づきにくく、壁にぶつかるなど支障 |
| 注意点 | 視野欠損の多くは脳梗塞起因、中年以降はとくに注意 |
半盲は、視野の半分が突然見えなくなる視覚障害です。右側または左側の視野全体が欠け、真っ黒に見える、あるいは見えない壁があるように感じることが特徴です。
原因は、視覚情報を処理する後頭葉や視放線といった経路が、脳梗塞によって障害されることです。閃輝暗点が光のジグザグや一部の欠けとして現れるのに対し、半盲は広範囲が失われる点で異なります。
自身では気づきにくく、物にぶつかる、文字の一部が読めないなど日常生活に支障をきたします。半盲は脳梗塞の重要なサインであり、出現した際には速やかに医療機関で診察とMRIなどの検査を受けることが重要です。
視界の一部が欠ける(視野欠損)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 見え方の特徴 | 視界の片側一部が見えなくなる、文字の一部が欠ける、かすかに光が見えるが全体的に欠損感あり |
| 日常生活での気づき | 通路や道で片側から人や柱にぶつかる、読書や画面で文字の一部が突然見えなくなる |
| 原因 | 脳梗塞による後頭葉や視覚伝導路の損傷で視覚情報が脳に届かなくなること |
| 自覚症状 | 視野の一部が黒く抜けたように感じることがあり、症状が固定する場合もある |
| 注意点 | 目の問題ではなく脳の障害によるもので、早期受診が重要 |
視野欠損とは、視野の一部が欠けて見えなくなる状態で、閃輝暗点と異なり光を伴わず見えない、ぼやけるといった症状が持続するのが特徴です。
脳梗塞による後頭葉や視覚経路の障害で起こり、片側の視野が欠ける、文字が読めない、黒く抜けたように見えるなどの症状として現れます。
日常では、人や柱に片側からぶつかることで気づかれることもあり、一部は回復するものの固定して残る場合もあります。目の異常ではなく脳の障害による重要なサインであり、脳梗塞の可能性があるため、早期の受診とMRI検査などによる確認が必要です。
物が二重に見える(複視)
複視とは物が二重に見える症状で、脳幹の血流障害により眼球を動かす神経が障害され、左右の目が協調して動かなくなることで起こります。
動眼神経の障害で目の動きやまぶたに異常が生じ、複視は脳梗塞のほか脳腫瘍・動脈瘤・頭部外傷でも起こります。突然の複視は脳卒中の重要なサインのひとつであり、片目が動かしにくい、二重に見えるといった症状が現れた場合は、速やかに医療機関で検査を受けることが重要です。
急に視力が落ちる・かすむ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 原因 | 脳への血流遮断による後頭葉や視覚経路の障害 |
| 急な視力低下・かすみ | 片側眼または両眼での急激な視力低下やぼやけ |
| 一過性黒内障 | 片眼の視野がカーテンのように暗くなる、一時的な血流遮断による症状 |
| 後頭葉梗塞の影響 | 右脳後頭葉障害による両眼の左側視野欠損(同名半盲)、視界の欠損や薄暗さ |
| 閃輝暗点との違い | 閃輝暗点は光や模様の視覚異常、こちらは直接的な視力低下や視野欠損を伴う症状 |
急な視力低下やかすみは、脳梗塞による視覚野や視覚経路の血流障害で起こる重要なサインです。代表的なものに一過性黒内障があり、片目だけ突然暗くなり、カーテンが下りるように視野が遮られます。
これは頚動脈の血栓による一時的な血流遮断が原因です。また、後頭葉の梗塞では両眼の同じ側に視野欠損(半盲)が生じ、視界が欠けたり全体が薄暗く見えることがあります。
閃輝暗点が光や模様を伴う一過性の現象であるのに対し、これらは直接的な視力低下や持続する視野障害が特徴です。こうした症状が現れた場合は、脳梗塞の可能性を考慮し、速やかな受診と検査が必要です。
目の奥が我慢できないほど痛む
目の奥の激しい痛みは、多くの場合は眼精疲労やドライアイ、緑内障発作、群発頭痛など目や頭の病気が原因です。しかし、まれに脳梗塞や一過性脳虚血発作(TIA)、さらには脳動脈瘤破裂によるくも膜下出血といった脳血管障害の前兆として現れることがあります。
とくに突然の強い痛みに加えて視力低下、視野の欠損、物が二重に見えるなどの症状を伴う場合、あるいはしびれ・麻痺・言語障害が一緒に出る場合は注意が必要です。
これらは脳卒中の緊急サインであり、速やかな受診、場合によっては救急要請が推奨されます。
以下の記事では、目の奥の痛みと脳梗塞の関係性を詳しく解説しています。
【脳梗塞?】閃輝暗点が起きたときの受診の目安
| 受診の目安 | 詳細 |
|---|---|
| 身体の麻痺・しびれ、視覚異常、言語障害の有無をチェック | 手足の麻痺やしびれ、視覚の変化、言葉がうまく話せない症状の有無の確認 |
| 「初めて」「頻度・性質・持続時間が変わった」ときは要注意 | 閃輝暗点が初発の場合や、症状の頻度・強さ・持続時間に変化があった場合は早めの受診推奨 |
閃輝暗点は多くの場合、片頭痛の前兆として現れますが、稀に脳梗塞のサインの可能性もあります。そのため、ただの片頭痛と自己判断せず、受診の目安を知っておくことが大切です。
とくに手足の麻痺やしびれ、視覚異常、言葉が出にくいなどの神経症状を伴う場合、また初めて症状が出たときや頻度・性質・持続時間に変化がある場合は注意が必要です。受診の目安は示されていますが、少しでも異変を感じた場合は早めの受診が重要です。
身体の麻痺・しびれ、視覚異常、言語障害の有無をチェック
閃輝暗点は多くの場合、片頭痛の前兆として現れる一時的な視覚症状ですが、稀に脳梗塞などの脳血流障害の前兆として発症します。
脳梗塞では視覚異常に加えて片側の手足の麻痺やしびれ、言葉が出にくい、理解が難しいといった言語障害を伴うことが多く、これらは血流が途絶えた部位の機能障害を反映する重大な兆候です。そのため閃輝暗点が起きたときには、麻痺やしびれ、普段と異なる視覚障害、言葉のもつれや認知障害がないかを確認することが重要です。
こうした症状を伴う場合は脳梗塞の可能性が高いため救急受診が必要であり、視覚症状のみであっても頻度や性質が変化する際には早めに医療機関を受診することが重要です。
「初めて」「頻度・性質・持続時間が変わった」ときは要注意
閃輝暗点は多くの場合、片頭痛の前兆として一過性に現れますが、初めて症状が出た場合には脳梗塞や一過性脳虚血発作(TIA)など脳の血流障害による可能性もあります。とくに40歳以降で初発の場合は、医療機関で検査を受けることが推奨されます。
また、以前から閃輝暗点がある方でも、出現頻度が急に増えたり、見え方がこれまでと異なったり、症状が長引く場合には注意が必要です。こうした変化は単なる片頭痛の前兆ではなく、脳の血管異常を示す可能性があります。
閃輝暗点は多くが一過性ですが、脳梗塞の早期サインと重なることもあるため、自己判断せず、異変を感じた際には早急に医療機関を受診しましょう。
【脳梗塞?】閃輝暗点が起きたときの対処法
| 対処法 | 詳細 |
|---|---|
| 眼科ではなく脳神経外科を受診する | 閃輝暗点は脳が原因の症状のため、眼科ではなく脳神経外科の受診が必要 |
| 脳梗塞を見逃さないためにCTやMRI検査を受ける | 脳神経外科で問診・診察後、頭部CTやMRIで脳梗塞の有無を詳しく確認 |
| 脳梗塞と診断された場合は血栓回収療法を受ける | 脳梗塞診断後は血栓を取り除く治療(血栓回収療法)などを早期に開始することで重症化予防が可能 |
閃輝暗点は多くの場合片頭痛の前兆ですが、稀に脳梗塞のサインとして発症します。とくに手足の麻痺やしびれ、言葉のもつれなど他の神経症状を伴う場合は、自己判断せず速やかに受診することが重要です。
眼の病気と思って眼科に行く方もいますが、原因は脳にあるため脳神経外科を受診する必要があります。診察後には頭部CTやMRIで脳梗塞の有無を詳しく確認し、脳梗塞と診断された場合は血栓回収療法など早期治療を開始することで重症化を防止できます。
眼科ではなく脳神経外科を受診する
閃輝暗点は一見すると目の病気のように感じられますが、実際には脳の血流異常や神経の働きの異常が関与していることが少なくありません。
脳梗塞や一過性脳虚血発作(TIA)が背景にあり、正確な診断のためには脳を専門とする脳神経外科や神経内科の受診が必要です。眼科は緑内障や網膜剥離など目そのものの疾患を対象とする診療科であり、脳の異常を十分に評価することは困難です。
一方、脳神経外科や神経内科ではCTやMRIといった画像検査によって脳の血管や神経の状態を詳細に確認でき、脳梗塞の早期発見や適切な治療につながります。とくに初めて症状が出現した場合や経過がこれまでと異なる場合、さらに麻痺や言語障害を伴う場合には、速やかに医療機関を受診することが重要です。
脳梗塞を見逃さないためにCTやMRI検査を受ける
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 脳出血の除外 | 急な症状発症時にCTで脳出血の有無を迅速確認、治療方針決定に必須 |
| 初期脳梗塞の検出 | MRIの拡散強調画像(DWI)で小さな梗塞や見落としやすい領域も高精度で把握 |
| 血栓位置・血流状態の把握 | CTAやMRAで血栓の位置や範囲を特定し、適切な血栓回収療法やt-PA投与の判断につなげる |
| 診断精度の向上・誤診防止 | 症状だけでは片頭痛等との区別困難なため、画像検査で脳以外の原因との鑑別を可能に |
脳梗塞の診断にはCTやMRIが欠かせません。CTは脳出血の有無を迅速に確認でき、治療方針の決定に直結します。MRIは発症直後のごく小さな梗塞も捉えられ、とくに後頭葉など見落としやすい部位の診断に有用です。
CTAやMRAで血管の詰まりを把握でき、血栓回収療法など治療の適応判断に役立ちます。症状だけでは片頭痛などとの区別が難しいため、画像検査による早期評価がより正確な診断につながる可能性があります。
以下の記事では、MRI検査について詳しく解説しています。
脳梗塞と診断された場合は血栓回収療法を受ける
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 血栓回収療法の目的 | 詰まった血栓を機械的に取り除き、血流を再開させる治療 |
| 脳細胞の壊死防止 | 血流遮断による脳細胞の死滅進行を抑え、後遺症の軽減を図る |
| 高い再開通率 | カテーテル使用で約90%の再開通率 |
| 治療可能時間の拡大 | 発症から最大24時間まで治療可能な場合があり、発症から時間が経過していても治療を受けられる可能性がある |
| 後遺症リスク軽減と社会復帰支援 | 早期治療により麻痺や言語障害の後遺症を減らし、生活や社会復帰の支援を促進 |
脳梗塞は、血栓によって脳の血管が詰まり、神経細胞に酸素や栄養が届かなくなることで急速に壊死が進行し、重い後遺症や生命の危険を招く疾患です。血栓回収療法は、カテーテルを用いて血栓を直接除去し血流を再開させる治療であり、高い再開通率が報告されています。
脳梗塞では、発症から最大24時間まで適応可能な場合があり、発症時刻が不明なケースや発症から4.5時間を超えた患者にも治療の選択肢が広がっています。早期に血流を再開することで脳細胞の壊死を最小限に抑え、後遺症を軽減し社会復帰や自立につなげられるため、速やかな血栓回収療法は命と生活の質を守る上で極めて重要です。
以下の記事では、脳梗塞の治療や後遺症について詳しく解説しています。
脳梗塞の予防策
| 予防策 | 詳細 |
|---|---|
| 高血圧を防ぐ | 定期的な血圧測定と記録、減塩や適度な運動による生活習慣改善 |
| 片頭痛をコントロールする | 医師の診断と薬物療法、ストレス管理や規則正しい生活習慣の維持 |
| 定期健診を受ける | 健康状態の把握と早期発見のための血圧、血糖、脂質検査の継続 |
脳梗塞の予防には、高血圧の管理、片頭痛のコントロール、定期健診の受診が重要です。高血圧は定期的な測定と記録、減塩や運動による生活習慣改善で防ぐことができます。
片頭痛は医師の診断による薬物療法や、ストレス管理、規則正しい生活でコントロールが可能です。定期健診では血圧・血糖・脂質を継続的に確認し、生活習慣病の早期発見につなげます。閃輝暗点が直接脳梗塞を起こすことは稀ですが、脳梗塞は誰にでも起こり得るため、日頃から予防策を実践することが大切です。
なお、脳梗塞の再発予防を目的とした治療法として、再生医療という選択肢があります。脳梗塞に対する再生医療の治療例については、以下の症例記事をご覧ください。
高血圧を防ぐ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 脳卒中リスクの最重要因子 | 高血圧は脳梗塞や脳出血の主な原因であり、血圧上昇に伴いリスクも直線的に増加する |
| 血圧の持続的上昇の影響 | 収縮期・拡張期ともに高い状態が続くと血管がダメージを受け、脳卒中の発症率が上昇する |
| 血管負担軽減と動脈硬化抑制効果 | 血圧を下げることで血管への負担を軽減し、動脈硬化の進行を遅らせることで予防効果を発揮 |
| 脳卒中リスクの明確な低下 | 収縮期血圧が10mmHg下がると脳卒中リスクが約40%減少し、5mmHg低下でもリスク低下が確認されている |
| 早期管理の重要性 | 高血圧の早期発症や長期持続はリスク増大と降圧薬の必要性増加につながり、早期対応が必須 |
| 発症率抑制の可能性 | 高血圧を完全予防できれば、脳卒中の発症率を約半分に減少させる可能性がある |
高血圧は脳梗塞をはじめとする脳卒中の最大のリスク因子であり、血圧を下げることで動脈硬化の進行を抑え、脳卒中の発症率を減少させることが期待できます。
収縮期血圧を10 mmHg下げると脳卒中リスクが約40%低下することが報告されています。(文献1)
さらには日常的な降圧で発症率を半減させる可能性もあるため、生活習慣の改善や定期測定による早期管理が極めて重要です。
以下の記事では、脳梗塞の発症予防について詳しく解説しています。
片頭痛をコントロールする
| 片頭痛に関連する可能性のある要因 | 内容 |
|---|---|
| 空腹 | 食事を抜くことや長時間の空腹状態 |
| 運動 | 激しい運動や身体活動 |
| 月経周期 | ホルモン変化に伴う周期的な影響 |
| 天候の変化 | 気圧や温度の変化 |
| 光・におい・音・温度差 | 強い光、特定のにおい、大きな音、温度差 |
| 睡眠の乱れ(寝不足・寝すぎ) | 不規則な睡眠や過不足による影響 |
| 食べ物(チョコレート・ナッツ・ワインなど) | 特定の食材が誘因となる場合がある |
| ストレス(感じる・解放される) | 精神的緊張や解放後の反応 |
片頭痛の誘発要因として、空腹による血糖値の低下、急激な運動による身体的負担、月経周期に伴うホルモン変動、天候の変化や光・におい・音・温度差などの環境刺激、睡眠の乱れ(寝不足・過剰睡眠)、特定の食品(チョコレート・ナッツ・ワインなど)、ストレスの蓄積や解放といった要素が挙げられます。
さらに、閃輝暗点などの前兆のある片頭痛を持つ女性においては、脳梗塞の発症リスクが約2倍とされ、喫煙や経口避妊薬の併用、高頻度の発作(年12回以上)などが重なると、そのリスクはさらに上昇します。(文献3)
前兆のある片頭痛の場合は、頭痛としての対処だけでなく専門医に相談し、脳卒中のリスクを踏まえた全身的な管理を行うことが重要です。
以下の記事では、頭痛の対処法について詳しく解説しています。
定期健診を受ける
脳梗塞は、高血圧・糖尿病・脂質異常症・不整脈(心房細動)などの生活習慣病が主な原因です。これらは自覚症状が現れにくく、気づかないうちに進行して脳の血管に負担をかけ、脳梗塞を引き起こす可能性があります。
定期健診では血圧・血糖値・コレステロール値・心電図を確認でき、脳梗塞のリスク因子を早期に発見し、生活習慣の改善や薬でコントロールすることで将来の発症リスクを大きく下げられます。
また、健診で医師に相談することで、自分の体質や生活習慣に合わせた予防方法を取り入れられる点も大きなメリットです。
閃輝暗点から脳梗塞に進展する確率は低いが医療機関での受診が重要
閃輝暗点から脳梗塞に至る確率は低いとされていますが、その症状が問題ないものなのかを自身で判断することは困難です。
脳梗塞だった場合、治療が遅れると症状が悪化するリスクが高まるため、不安な閃輝暗点が現れた際は早めに脳神経外科を受診しましょう。
当院「リペアセルクリニック」では、脳梗塞後の治療として再生医療(幹細胞治療)を行っています。再生医療は、脳梗塞によってダメージを受けた脳細胞の修復や麻痺の改善、リハビリ効果の向上などに効果が期待できます。
再生医療へのご質問・ご相談は、「メール」もしくは「オンラインカウンセリング」で受け付けております。気になる点がありましたら、どうぞ気軽にご相談ください。
\無料オンライン診断実施中!/
閃輝暗点と脳梗塞の確率に関するよくある質問
閃輝暗点から脳梗塞になる原因はスマホですか?
閃輝暗点は脳の血流低下が原因で起こるため、スマホが直接的に閃輝暗点や脳梗塞を起こす可能性は低いと考えられます。
しかし、以下のようなパターンでは、スマホの使用が閃輝暗点や脳梗塞へ間接的に影響する可能性があります。(文献4)
- スマホの光から片頭痛発作が起こり、脳梗塞になる
- 疲れているときにスマホを操作し、片頭痛発作から脳梗塞になる
- 悪い姿勢でのスマホ操作が続き、脳を含めた全身の血流が低下する
操作姿勢やタイミング、使用時間などを見直し、適切なスマホ使用を心がけましょう。
閃輝暗点を放置するとどうなりますか?
閃輝暗点が片頭痛の前兆だった場合、その後頭痛発作が起きると考えられます。
また、閃輝暗点が脳梗塞の前兆だった場合は、しびれ、言葉が出なくなるなどの症状が出る可能性もあります。閃輝暗点が脳梗塞に移行するかどうかを自分で判断するのは困難です。不安を感じる場合には、医療機関を受診することが望まれます。
頭痛がない閃輝暗点は危険ですか?
頭痛が伴わない閃輝暗点が出現した場合、片頭痛以外の異常が起きている可能性があります。
閃輝暗点が脳梗塞の前兆である可能性は否定できません。脳梗塞は早期対応によって予後が大きく左右されます。頭痛を伴わない閃輝暗点が見られた場合は、脳梗塞の前兆を確認するために医療機関への受診が推奨されます。
脳梗塞の後遺症が出た場合はどうすれば良いでしょうか?
脳梗塞の後遺症には、早期からのリハビリと多職種による支援が重要です。理学療法での機能回復、作業療法での日常動作支援、言語療法でのコミュニケーション回復に加え、心理的なサポートも効果的です。入院後も外来や訪問でリハビリを続けることで、機能の維持・向上につながります。
また、自己管理を取り入れることで生活の質や自立性は高められますが、リハビリは自己流ではなく、医師の指導のもとで行うことが不可欠です。医師と連携し、自分に合ったプランを進めることで、より適切で効果的な回復が期待できます。
以下の記事では、脳梗塞の後遺症について詳しく解説しています。
参照文献