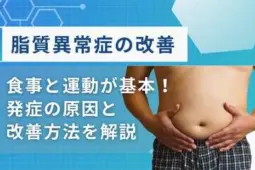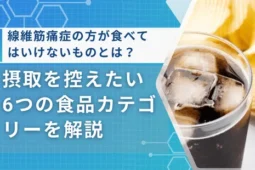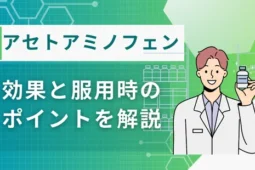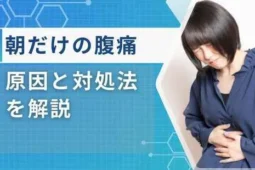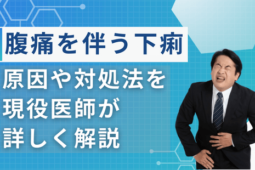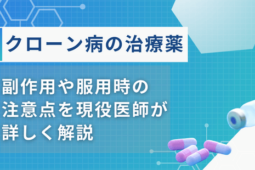- 内科疾患
- 内科疾患、その他
脂質異常症を判断する診断基準|LDL・HDL・中性脂肪の基準値と改善の目安を医師が解説
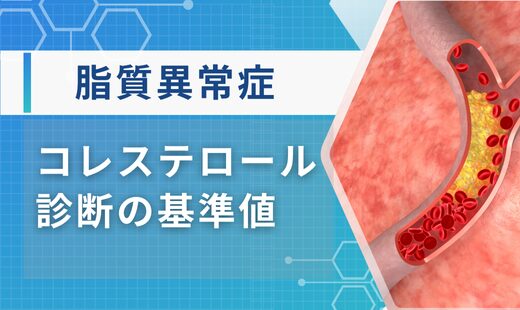
「健康診断で脂質の数値が気になると言われた」
「コレステロールが高めだけど、どこまでが問題なのかわからない」
このような不安を抱えていませんか?
脂質異常症は自覚症状がほとんどないまま進行することが多く、診断基準を正しく理解しておくことが早めの対策につながります。
本記事では、LDL・HDL・中性脂肪などの診断基準と再検査や治療が必要となる目安について解説します。
脂質異常症を放置すると動脈硬化が進行し、心筋梗塞や脳梗塞といった重篤な疾患のリスクが高まります。
本記事を参考に、ご自身の検査結果を確認し、必要に応じて早めの受診や生活習慣の見直しを始めましょう。
なお、当院「リペアセルクリニック」の公式LINEでは、脳梗塞後の後遺症改善や再発予防といった、脳血管疾患に対する再生医療の情報提供と簡易オンライン診断を実施しております。
将来的なリスクに備えて再生医療について知りたい方は、ぜひ一度公式LINEにご登録ください。
目次
脂質異常症を判断する診断基準【基準値一覧】
脂質異常症の診断では、LDLコレステロール・HDLコレステロール・中性脂肪(トリグリセライド)・non-HDLコレステロールといった血中脂質の数値をもとに判断します。
これらの数値が基準を超えると、動脈硬化の進行リスクが高まるため注意が必要です。
まずは各項目の基準値を確認し、自分の検査結果がどこに該当するのかを把握しておきましょう。
| 診断項目 | 基準値 |
|---|---|
| 高LDLコレステロール血症 | 140mg/dL以上 |
| 境界域高LDLコレステロール血症 | 120~139mg/dL |
| 高トリグリセライド(中性脂肪)血症(空腹時) | 150mg/dL以上 |
| 高トリグリセライド(中性脂肪)血症(随時) | 175mg/dL以上 |
| 低HDLコレステロール血症 | 40mg/dL未満 |
| 高Non-HDLコレステロール血症 | 170mg/dL以上 |
| 境界域高Non-HDLコレステロール血症 | 150~169mg/dL |
(文献1)
脂質異常症は、これらの数値が基準を超えることで診断されます。
一つでも基準値を外れると脂質異常症の可能性があり、複数項目に異常がある場合は動脈硬化のリスクがさらに高くなります。
とくにLDLコレステロールが160mg/dL以上、中性脂肪が400mg/dL以上、HDLコレステロールが30mg/dL未満のときは、動脈硬化や重症な急性膵炎などのリスクが高いため、医療機関での精密検査が必要です。(文献2)
以下の記事では、脂質異常症の異常値で起こりうる症状のひとつであるしびれについて詳しく解説しています。
LDL・HDL・中性脂肪の基準値と判断基準
脂質異常症の診断では、LDL・HDL・中性脂肪の3つがとくに重要です。
LDLコレステロール(悪玉)
増えすぎると血管の壁に蓄積し動脈硬化を進めるため、140mg/dL以上は脂質異常症と判断されます。
とくに160mg/dLを超える場合は、動脈硬化リスクが高く、早めの受診がすすめられます。
HDLコレステロール(善玉)
余分な脂質を回収する役割があるため、40mg/dL未満は要注意です。
HDLが低いほど、血管に負担がかかりやすい状態といえます。
中性脂肪(トリグリセライド)
150mg/dL以上で異常とされ、400mg/dLを超えると精密検査の対象になることがあります。
食事や生活習慣の影響を受けやすいため、食後採血か空腹時採血かも重要な判断ポイントです。
それぞれの数値は単独でも評価されますが、複数項目の異常が重なると動脈硬化のリスクがさらに高まるため、総合的な判断が必要です。
non-HDLコレステロールの評価が重視される理由
non-HDLコレステロールとは、血液中に含まれる動脈硬化の原因になりやすいコレステロールの総量を示す数値です。
LDLだけでなく、VLDL、IDL、レムナントなど、すべての悪玉系脂質をまとめて評価できる点が特徴です。
近年のガイドラインでは、このnon-HDLコレステロールがより正確にリスクを把握できる指標として重視されるようになりました。
とくに中性脂肪が高い場合は、LDLコレステロールだけでは動脈硬化のリスクを十分に評価できないため、non-HDLの数値確認が重要です。
non-HDLコレステロールは、食後でも比較的安定した値を示すため、随時採血で診断しやすい利点もあります。
LDLが正常でも、non-HDLが高ければ動脈硬化のリスクが考えられるため、健診では必ず確認しておきたい項目です。
総コレステロール「だけ」高い場合の見方
総コレステロールは、LDL・HDL・中性脂肪由来のコレステロールをすべて合計した数値です。
そのため、総コレステロールが高いからといって、すぐに脂質異常症と判断されるわけではありません。
たとえば、HDLコレステロール(善玉)が高いことで総コレステロールが上がっている場合、必ずしも危険ではなく、むしろ血管の健康状態は良好なケースもあります。
反対に、総コレステロールが正常範囲でも、LDLだけ高い場合は脂質異常症と診断されることがあります。
総コレステロールの数値を評価する際は、
- LDLコレステロールが基準値内か
- HDLコレステロールが低くないか
- 中性脂肪が高くないか
といった項目を合わせて確認する必要があります。
総コレステロール「だけ」を見ても正確な判断はできないため、血液検査の詳細項目を医師と一緒に確認し、自分の数値のどこに注意が必要なのか整理することが大切です。
健康診断の判定(A~D)と何が違う?
健康診断の判定(A〜D)は、あくまで「健康状態のスクリーニング(一次評価)」として用いられる指標です。
一方で、脂質異常症の診断基準は、医学的根拠に基づいて設定された「治療が必要かどうかを判断する数値」です。
この2つは似ているようで役割が異なります。
健康診断の判定では、総合的なリスクを簡易的に判断するため、境界値(少し高めの数値)でもC判定やD判定がつくことがあります。
これはあくまで「詳しい検査や生活改善が必要かどうか」を知らせるためのものです。
一方、脂質異常症の診断基準は、LDLコレステロール・HDLコレステロール・中性脂肪などの数値が医学的な基準値を超えているかどうかで判断されます。
同じC判定でも基準値に近い場合と、大きく超えている場合では必要な対応が異なるため、検査結果は個別に確認することが大切です。
健康診断の判定は目安として活用しつつ、基準値との比較や他の検査結果も合わせて医師の判断を受けることが、早期の対策につながります。
脂質異常症を疑うときの検査方法
脂質異常症が疑われる場合は、まず血液検査を中心に体の状態を確認します。
脂質の数値は体調や食事によって変動しやすいため、正確に判断するためには適切な検査方法を知っておくことが大切です。
ここでは、脂質異常症の診断でよく行われる検査について紹介します。
\無料オンライン診断実施中!/
血液検査でわかること
脂質異常症が疑われる場合、まず血液検査を行い、血液中の脂質バランスを調べます。
測定される主な項目とその役割は以下の通りです。
| 検査項目 | 役割・意味 |
|---|---|
| LDLコレステロール(悪玉) | 増えすぎると血管壁に蓄積し、動脈硬化を進行させる |
| HDLコレステロール(善玉) | 余分なコレステロールを回収し、血管を守る |
| 中性脂肪(トリグリセライド) | エネルギー源だが、増えすぎると脂質バランスが崩れ、動脈硬化や急性膵炎のリスクを高める |
| non-HDLコレステロール (総コレステロール−HDL) |
LDLだけでなく、動脈硬化の原因となるすべての悪玉系脂質をまとめて評価でき、総合的なリスク判断に有効 |
これらの数値は、現在の動脈硬化のリスクを客観的に評価し、生活習慣の見直しや治療の開始タイミングを判断するための大切な手がかりとなります。
再検査が必要な数値の目安
血液検査で脂質の異常が見られた際、軽度の変動は生活習慣による一時的な可能性もありますが、数値が明らかに基準値を大きく外れている場合は注意が必要です。
動脈硬化の進行や重篤な合併症リスクを考慮し、速やかに再検査や医師の診察を受けてください。
とくに下記の範囲に該当する場合は、精密検査を検討する目安とされています。
- LDLコレステロール:160mg/dL以上
- 中性脂肪:400mg/dL以上(空腹時)
- HDLコレステロール:30mg/dL未満
また、「前回より急に悪化している」「複数の項目が同時に異常値」という場合も、早めの医療機関受診が安心です。
生活習慣の見直しをしても改善しないときは、他の病気が関係している可能性もあるため、自己判断せずに相談しましょう。
家族性脂質異常症(FH)の可能性
家族性脂質異常症(FH)は、生まれつきLDLコレステロールが非常に高くなりやすい遺伝性の疾患です。
一般的な生活習慣による脂質異常とは異なり、健康的な食事や運動をしていても数値が高くなることが特徴です。
LDLコレステロールが180mg/dL以上、あるいは200mg/dLを超える状態が続く場合は、FHの可能性を考える必要があります。
また、家族に「若い頃からコレステロールが高かった」「心筋梗塞を早期に発症した」方がいる場合も注意が必要です。
FHは遺伝的な背景が関係するため、家族歴は非常に重要な手がかりになります。
FHは放置すると動脈硬化が早期に進行し、心筋梗塞や狭心症のリスクが高まります。
疑いがある場合は、早めに医療機関での検査や専門的な治療の相談を行いましょう。
適切に管理することで、健康リスクを大きく減らせます。
脂質異常症の原因
脂質異常症は、食生活や運動習慣だけでなく、体質・基礎疾患・薬剤など、さまざまな要因が複雑に関わって起こります。
原因を正しく理解することで、改善方法や医療的な対応が明確になります。
| 原因 | 詳細 |
|---|---|
| 食生活の乱れと栄養バランスの偏り | 飽和脂肪酸やコレステロールの過剰摂取、野菜や食物繊維の不足、糖質やアルコールの多量摂取 |
| 運動不足・喫煙・ストレスなどの生活習慣の乱れ | 運動不足による代謝低下、喫煙によるHDLコレステロール(善玉)低下、ストレスや肥満による脂質代謝の悪化 |
| 遺伝や体質による要因 | 家族性高コレステロール血症(FH)などの遺伝的素因、体質による脂質代謝異常 |
| 基礎疾患や薬剤の影響による脂質異常症 | 糖尿病や甲状腺機能低下症などの基礎疾患、一部薬剤の副作用による脂質バランスの変化 |
脂質異常症の原因としては、脂っこい食事や野菜不足、糖質・アルコールの過剰摂取など食生活の乱れが挙げられます。
また、運動不足や喫煙、ストレスなどの生活習慣も脂質異常症に影響しやすく、とくにHDLコレステロールが減る原因となります。
さらに、遺伝や体質により脂質代謝が乱れやすい人もいます。
糖尿病や甲状腺の病気、一部の薬剤の影響でも脂質異常症を発症するおそれがあるため、原因を把握し、早急に対策することが大切です。
以下の記事では、脂質異常症と高脂血症の違いについて詳しく解説しています。
脂質異常症の治療法
脂質異常症の治療は、まず生活習慣の改善から始めます。
食事の見直しや運動習慣の定着によって、血中脂質は着実に改善しやすくなります。
これらを続けても数値が十分に下がらない場合や、リスクが高い場合には薬物療法が検討されます。
| 治療法 | 詳細 | 注意点 |
|---|---|---|
| 食事療法 | 摂取エネルギー量の調整、脂質・糖質の制限、食物繊維や魚・大豆製品の積極的摂取、バランスの良い食事 | 飽和脂肪酸やトランス脂肪酸、コレステロールの多い食品、過度な糖質やアルコールの摂取に注意 |
| 運動療法 | 有酸素運動や筋力トレーニングの定期的実施、適正体重の維持、基礎代謝の向上、脂質代謝の改善 | 急激な運動や無理な運動は避け、体力や持病に合わせて無理なく継続することが重要 |
| 薬物療法 | スタチンやフィブラートなどの脂質低下薬の使用、医師の指導による継続的な投薬管理 | 副作用や他の薬剤との相互作用に注意し、自己判断で中止せず定期的な検査と診察を受けること |
いずれの治療法も自己判断で行うのではなく、医師の助言に従い適切に取り組むことが重要です。
生活習慣の改善と治療の継続が、動脈硬化や心疾患の予防につながります。
\無料オンライン診断実施中!/
以下の記事では、脂質異常症の改善について詳しく解説しています。
食事療法
| 取り組み内容 | 期待できる効果 | ポイント・目安 |
|---|---|---|
| 飽和脂肪酸・コレステロールの摂取を減らす | LDLコレステロール(悪玉)の低下 | 肉の脂身・バター・卵・レバーなどを控える |
| 食物繊維・野菜をしっかり摂る | コレステロール吸収の抑制、LDL低下 | 食物繊維20~25g/日、野菜350g/日が目安 |
| 砂糖や精製炭水化物の摂取を控える | 中性脂肪(TG)の上昇抑制 | 菓子・ジュース・白米・パンなどを控えめに |
| 青魚(DHA・EPA)を積極的に摂る | 中性脂肪(TG)の低下 | サバ・イワシ・サンマなどを週2回以上 |
| 適正体重・エネルギーバランスを保つ | 内臓脂肪減少・インスリン感受性向上、LDL・TGの正常化 | 標準体重×25~30kcal/日を目安 |
| 飽和脂肪酸の摂取を控え、不飽和脂肪酸を積極的に摂る | LDL増加の抑制、HDLや非HDLのバランス改善、動脈硬化予防 | オリーブ油・しそ油・青魚油などを活用 |
脂質異常症の治療で最も基本となるのが食事療法です。
飽和脂肪酸(肉の脂身やバター)やコレステロール(卵・レバーなど)の摂取を控え、青魚やオリーブオイル、ナッツ類など不飽和脂肪酸を積極的に取り入れることが重要です。
また、食物繊維を多く含む野菜や全粒穀物、海藻類を摂ることで、腸でのコレステロール吸収を抑え、血中LDLコレステロールの低下が期待できます。
食物繊維20〜25g/日、野菜を1日約350g摂ることが推奨されます。
中性脂肪(TG)を下げるためには、砂糖や精製炭水化物、甘い飲料の摂取を控え、青魚に含まれるDHA・EPAを意識して摂ることも効果的です。
適正体重の維持(標準体重×25〜30kcal/日)により、内臓脂肪の減少やインスリン感受性の改善とともに、LDL・TGの正常化が期待されます。
食事療法は薬を使わずに始められる基本の治療であり、生活習慣病全般の予防にもつながります。
運動療法
定期的な有酸素運動は脂質異常症治療に有効です。
中等度〜高強度の運動でHDLが6.6〜11.6%増加し、LDLが低下することが報告されています。(文献5)
ウォーキングなどの継続的な運動は中性脂肪(TG)値を下げ、筋肉内のリポプロテインリパーゼ(LPL)活性を高めることで、効率的に中性脂肪を減少させます。
体脂肪・内臓脂肪が減るとインスリン感受性が改善し、LDL・TGの正常化を促します。
また、週150分以上の中等度運動は心筋梗塞や脳卒中などの心血管リスクを低減し、他の生活習慣病予防にも役立ちます。(文献6)
食事と並び、無理なく続けられる運動習慣を構築することが、血管を守る上で重要です。
薬物療法
LDLコレステロール(悪玉)は動脈硬化を進め、心筋梗塞や脳梗塞の原因となります。
まずは食事や運動での改善が基本ですが、効果が不十分な場合は薬物療法が有効です。
代表的な治療薬には、肝臓でのコレステロール合成を抑えるスタチン、腸での吸収を抑えるエゼチミブ、中性脂肪を下げるフィブラート系薬、注射でLDLを大幅に下げるPCSK9阻害薬などがあります。
糖尿病や腎疾患のある方、過去に心筋梗塞を経験した方にはとくに重要な治療法です。(文献7)
薬の効果や副作用は血液検査で定期的に確認し、医師が患者様一人ひとりに合わせて治療内容を調整します。
生活習慣の見直しと薬を組み合わせることで、将来のリスクを減らすことができます。
脂質異常症は治療前から予防が重要
脂質異常症は、気づかないうちに進行することが多い病気です。
数値が基準値をわずかに超えている段階でも、生活習慣を見直すことで改善が期待でき、将来的な動脈硬化のリスクを下げることにつながります。
そのため、治療が必要になる前から、日々の暮らしの中で予防を意識することが大切です。
| 予防法 | 詳細 |
|---|---|
| 食生活と適正体重の管理 | 脂肪分の多い食品を控え、野菜や魚、果物を中心としたバランスの良い食事、適正体重の維持 |
| 運動習慣を身につける | 有酸素運動や筋力トレーニングの継続、基礎代謝の向上と脂質代謝の改善 |
| 禁煙と生活習慣の見直し | 喫煙の中止、ストレス管理、十分な睡眠と適切な飲酒量の維持 |
| 定期的に健康状態をチェックする | 健康診断や血液検査で脂質の状態を把握し、異常があれば早期対応 |
食生活と適正体重の管理
脂質異常症予防には、日々の食事と体重管理が重要です。
摂取エネルギーを消費に近づけることで、肝臓での中性脂肪・コレステロール合成を抑制できます。
また、体重の5〜10%減少により、LDL値や中性脂肪が改善し、HDLも増加するため、心血管リスクが低減されます。(文献8)
バランスの取れた食事、つまり飽和脂肪・トランス脂肪酸の制限と食物繊維、オメガ-3脂肪酸の豊富な食品の摂取は、LDL低下とHDL増加に効果的です。
さらに、健康的な体重維持と良い食習慣は、血圧や血糖、内臓脂肪、炎症マーカーにも好影響を与え、総合的に動脈硬化リスクを下げます。
肉の脂身を控えて青魚や大豆製品、野菜・果物・海藻・きのこを意識的に取り入れ、間食やアルコール、甘い飲料を控えることが重要です。
そしてBMI25以上を目安に、急激ではなく無理のないペースで少しずつ減量を続けることが、継続的な改善と予防につながります。
運動習慣を身につける
脂質異常症を予防するためには、日常的に体を動かす習慣をつけることがとても大切です。
ウォーキングやサイクリングなどの有酸素運動を続けると、中性脂肪やLDLコレステロールが下がり、HDLコレステロールが増えやすくなります。
その結果、動脈硬化の予防にもつながります。
また、軽い筋力トレーニングで筋肉量が増えると基礎代謝が上がり、脂質や糖の代謝がスムーズになります。
運動が苦手な方でも、階段を使う、通勤で一駅分歩くなど、日常の中でできることを取り入れるだけで十分効果があります。
| 効果 | 詳細 |
|---|---|
| 中性脂肪・LDL低下 | 有酸素運動を続けることで、中性脂肪(トリグリセライド)やLDLコレステロール(悪玉)が減りやすくなる |
| HDL増加・リスク低下 | 運動でHDLコレステロール(善玉)が増え、動脈硬化や心血管疾患リスク低下 |
| 体脂肪・内臓脂肪減少 | 継続的な運動により内臓脂肪や体脂肪が減少し、肥満・メタボ予防につながる |
| 基礎代謝上昇 | 筋肉量が増えると基礎代謝が上がり、脂質や糖の代謝が整いやすくなる |
| 生活習慣病全般の予防 | 運動が血圧・血糖も整え、生活習慣病全体の改善・予防につながる |
無理のない範囲で継続することが、脂質異常症の効果的な予防法です。
禁煙と生活習慣の見直し
脂質異常症の予防には禁煙が不可欠です。
喫煙はHDL(善玉)コレステロールを低下させ、動脈硬化を進行させますが、禁煙により改善が期待できます。
さらに、運動や食事など他の健康習慣への意識も高まり、生活全体の改善に貢献します。
過度な飲酒や睡眠不足、ストレスも脂質代謝に悪影響を及ぼすため、リラックスできる時間を意識的に確保し、生活習慣の見直しが大切です。
脂質異常症は自覚症状がほとんどないまま進行するため、早めの対策が重要です。
定期的に健康状態をチェックする
脂質異常症は自覚症状がほとんどなく、気づかないうちに進行することがあります。
そのため、年1回の血液検査でHDLやLDL、中性脂肪の変化をチェックすることが予防につながります。
検査結果は、生活習慣を見直す手がかりとなるだけでなく、高血圧や糖尿病など他の病気のリスクを早期に発見する上でも役立つため、毎年欠かさず受けることが大切です。
また、薬を服用している場合には、効果や副作用を評価するためにも定期検査が欠かせません。
健康を守る第一歩として、定期的にチェックを行う習慣を身につけましょう。
脂質異常症の診断基準値が高い方は早めに医療機関へ
健康診断でLDLコレステロールや中性脂肪の値が基準より高い場合、放置せず医療機関を受診することが重要です。
脂質異常症は自覚症状がないまま進行し、動脈硬化や心筋梗塞、脳梗塞などのリスクを高めます。
とくに数値が大きく基準を超えている場合や、複数項目に異常がある場合は注意が必要です。
放置せず、医師の評価を受けて治療方針を立てましょう。
脂質異常症の診断基準が高いと指摘された方は、当院「リペアセルクリニック」へご相談ください。
当院では、脂質異常症と深く関わる糖尿病などの疾患に対して、再生医療を治療の選択肢のひとつとしてご提案します。
\無料オンライン診断実施中!/
脂質異常症の診断基準に関するよくある質問
数値が少し高いだけなら様子見で大丈夫?
健康診断で「少しだけ高い」と言われても、放置はおすすめできません。
脂質異常症は自覚症状がほとんどなく、気づかないうちに動脈硬化が進むことがあるためです。
ただし、数値がわずかに基準を超えているだけで、すぐに薬の治療が始まるわけではありません。
まずは生活習慣の見直し(食事・運動・禁煙など)が基本となり、3か月ほど経過を見て再検査するのが一般的です。
痩せていても脂質異常症になりますか?
痩せ型の人でも脂質異常症になることはあります。
体重だけでは脂質バランスは判断できず、遺伝体質・食習慣・ストレス・運動量などさまざまな要因が関わっています。
とくに、痩せていても
- LDLコレステロールが高い
- 中性脂肪が高い
- HDLコレステロールが低い
といったパターンは珍しくありません。
「太っていないから大丈夫」と思っている人ほど、血液検査で初めて異常が見つかるケースもあります。
痩せ型の人も、数値が気になるときは油断せず、定期的に検査を受けることが大切です。
家族に脂質異常症の人がいるのですが自分も検査すべき?
家族に脂質異常症の人がいる場合、自分も検査を受けることをおすすめします。
とくに家族性脂質異常症(FH)は遺伝的にLDLコレステロールが上がりやすい病気で、家族に同じ傾向が見られることが多いです。
FHは遺伝性の疾患で、親がFHの場合、子どもに遺伝する可能性は50%あります。(文献9)
また、LDLコレステロールが180mg/dL以上、または家族歴がある場合は、FHの可能性が高くなります。(文献10)
早期に発見すれば、薬による治療や生活習慣の改善により、心筋梗塞や脳卒中のリスク減少が期待できます。
また、検査は20歳前後で受け、その後も定期的なフォローが推奨されています。
ホルモンバランス(更年期)は関係ありますか?
更年期は脂質のバランスが変化しやすい時期です。
女性ホルモン(エストロゲン)の減少によって、脂質の代謝が乱れやすくなるため、
- LDLコレステロールが上がりやすい
- 中性脂肪が増えやすい
- HDLコレステロールが低下しやすい
といった変化が起こることがあります。
更年期のタイミングで数値が悪化した場合は、生活習慣の見直しと定期的な検査がとても大切です。
必要に応じて医師と相談し、無理なく続けられる改善策を選びましょう。
まとめ|脂質異常症の診断基準を知り早めの対策につなげよう
脂質異常症は自覚しにくい一方で、放置すると動脈硬化が進み、将来的に心筋梗塞や脳梗塞などの重大な病気につながる可能性があります。
そのため、LDL・HDL・中性脂肪といった診断基準を正しく理解し、数値の変化に早めに気づくことが大切です。
数値が基準を少し超えただけでも、生活習慣を見直すことで改善できる場合があります。
食事の工夫や運動習慣の追加など、自分にできる範囲から始めることが対策として重要です。
また、数値が高いまま続く場合や、家族に脂質異常症の人がいる場合は、医療機関での検査や治療を早めに検討しましょう。
診断基準を知ることは、将来の健康を守るための大切な指標になります。
日々の習慣を整えながら、無理なく続けられる改善を積み重ねていきましょう。
(文献1)
脂質異常症の診断基準|生活習慣病オンライン
(文献2)
脂質異常症の検査と治療の最前線|2020年度日本内科学会生涯教育講演会Cセッション
(文献3)
家族性高コレステロール血症(ホモ接合体)(指定難病79)|難病情報センター
(文献4)
家族性高コレステロール血症(FH)とは?|一般社団法人日本動脈硬化学会
(文献6)
疾病予防および健康に対する 身体活動・運動の効用と実効性に影響する要因|運動基準・指針の改定のための検討会資料
(文献8)
How to Lower Triglycerides & LDL Cholesterol|EatingWeII