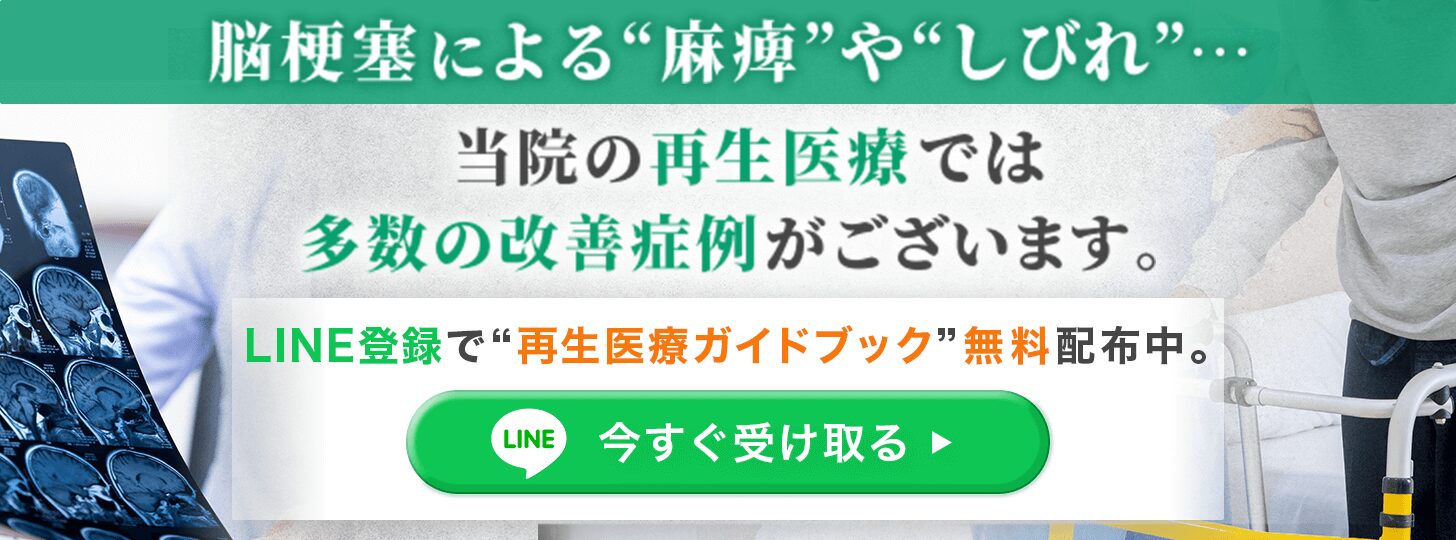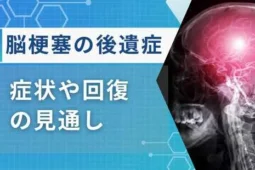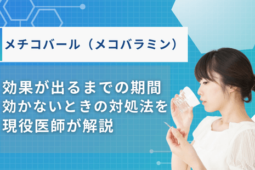- 脳梗塞
- 脳卒中
- 頭部
脳梗塞後遺症で性格が変わる?主な変化と原因を解説
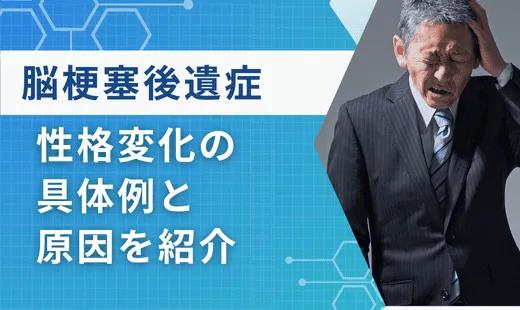
脳梗塞の後遺症で性格が変わることは、よく知られている症状の一つです。(文献1)
脳梗塞を発症をする前は穏やかで几帳面な性格だった方が、後遺症で怒りっぽくなったり、だらしなくなったりするケースが散見されます。
脳梗塞の後遺症のわかりやすい症例は麻痺です。一方、外見からは分からない症状もあります。これが高次脳機能障害です。
高次脳機能障害を発症すると性格が変わるだけでなく、記憶に問題が生じたり言語を適切に発せなくなったりとさまざまな症状があらわれます。
本記事では脳梗塞の後遺症が原因で起こる性格の変化や治療法について解説します。
なお、当院「リペアセルクリニック」の公式LINEでは、再生医療の情報提供と簡易オンライン診断を実施しております。
脳梗塞の後遺症や再発予防に関する再生医療について、詳しく知りたい方は、ぜひ一度公式LINEにご登録ください。
目次
脳梗塞の後遺症によって変化する性格の主な具体例
脳梗塞の後遺症によって変化する性格の主な具体例は以下のとおりです。
それぞれについて解説します。
脳梗塞の症状や原因など、包括的な解説は「脳梗塞とは|症状・原因・治療法を現役医師が解説」をご覧ください。
易怒性・攻撃性
脳梗塞の後遺症として多く見られる性格変化の一つが易怒性(いどせい:怒りっぽくなること)・攻撃性です。
脳梗塞により感情のコントロールを司る脳の前頭前野が損傷されると、感情の抑制が困難となり易怒性・攻撃性が見られる傾向にあります。(文献2)
発症前には気にならなかった些細な出来事が原因でイライラしたり、怒声を発したりするのが特徴です。
脳梗塞を発症した事実を知らない周囲の人からは「単に怒りっぽい人」と認識されて敬遠されるなど、社会生活が困難になるケースもあります。
易怒性・攻撃性がどのような場面で見られるのか原因を特定し、家族やパートナーなどの協力を得て対処する必要があります。
意欲低下・無関心(アパシー)
意欲低下や無関心(アパシー)も、脳梗塞の後遺症として多く見られる性格の変化の一つです。
脳梗塞が原因で脳の前頭葉や大脳辺縁系の機能が低下すると、脳内の神経伝達物質の働きが妨げられます。その結果、意欲の低下や無関心状態を引き起こすと考えられています。(文献3)
脳梗塞後に高次脳機能障害と診断された方のおよそ71%に、意欲発動性の低下・アパシーが見られるとの報告も見られます。(文献4)
意欲が低下して何事にも関心を持てなくなると、脳梗塞後のリハビリテーションにも非協力的になり、麻痺やADL(日常生活動作:食事、入浴、着替えなど基本的な生活行為)からの回復が遅延しがちです。
感情の不安定さ(感情失禁)
脳梗塞の後遺症として多く見られる性格の変化としては、感情の不安定さ(感情失禁)も挙げられます。
感情失禁は、感情の表出が適切にコントロールできない状態です。過剰に泣いたり突然笑いだしたりするケースも少なくありません。(文献5)
脳の前頭葉のなかでも眼窩面の障害により感情失禁を来すと、児戯性や多幸感により些細なことで泣いたり、面白くもないことで笑いだしたりします。
感情失禁は他者とのコミュニケーションを困難にさせるだけでなく、食事中の誤嚥や吹きこぼしのリスクも高めるため早期の対処が求められます。(文献6)
衝動性・自制の欠如
脳梗塞の後遺症として多く見られる性格の変化としては、衝動性および自制の欠如もよく知られています。
衝動性・自制の欠如も感情のコントロールが困難になる高次脳機能障害の一種で、とくに前頭葉の障害により発症しやすい傾向にあります。
もともと穏やかだった方が急に怒りっぽくなるなどの変化が見られる場合、脳梗塞の後遺症の高次脳機能障害を疑う必要があるでしょう。
衝動性や自制の欠如も他者とのコミュニケーションを阻害する原因の一つで、社会生活を営む上で重大な障壁となりかねません。
本人は自分の性格が変わったことに気付いていないケースが多いため、専門家のアドバイスを得て柔軟に対処する必要があります。
固執性・融通のなさ
固執性や融通のなさも、脳梗塞後の後遺症として多く見られる性格変化の一つです。
脳梗塞の後遺症により固執性や融通のなさを発症すると、一つのことにこだわって他に目が向かず、いつまでたっても同じことを繰り返すのが特徴です。(文献7)
行動だけでなく考え方に関しても固執が見られるようになり、多様な選択肢から適切な解を導き出せなくなります。
環境や状況の変化に対して柔軟に対処できないため、初対面の方とのコミュニケーションもうまく取れません。
固執性や融通のなさを改善していくためにはリハビリテーションはもちろん、安定した環境を整えることも重要です。
脳梗塞の後遺症における性格変化は損傷部位によって異なる
脳梗塞の後遺症によりあらわれる性格の変化や運動機能の低下、言語障害などを総称して高次脳機能障害と呼びます。
どのような変化があらわれるかは脳の損傷部位により異なります。
高次脳機能障害に伴う症状、および脳の損傷部位は以下のとおりです。(文献8)
| 損傷部位 | 主な機能 | 具体的な症状 |
|---|---|---|
| 前頭葉 | 計画立案・行動・注意力など | 注意障害・失行・遂行機能障害・社会的行動障害など |
| 頭頂葉 | 空間認知・触覚など | 半側空間無視・失認など |
| 側頭葉 | 言語理解・聴覚・記憶など | 失語症・記憶障害など |
| 後頭葉 | 視覚 | 視野狭窄・視覚失認など |
右脳と左脳のどちらに障害を起こしたかによって、あらわれる症状も異なります。
たとえば左脳に障害を起こすと失語症などの言語障害が見られ、右脳の障害を起こすと半側空間無視などの空間認知障害が見られます。
脳梗塞の後遺症に伴う高次脳機能障害において、性格の変化をもたらすのは主に前頭葉の障害です。
前頭葉のなかでも、内側の穹窿面(きゅうりゅうめん)を損傷すると無関心や無感情が見られやすく、下側の眼窩面(がんかめん)を損傷すると感情の不安定さが生じやすくなります。
脳梗塞の後遺症で家族の性格が変わったらどうすべき?
脳梗塞の後遺症で家族の性格が変わった場合、まずは原因を突き止める必要があります。
性格の変化は主に以下2つの原因によりもたらされることを理解しておいてください。
- 前頭葉の損傷により感情がコントロールできなくなって起こる
- 注意障害や遂行機能障害に伴い二次的に起こる
感情がコントロールできない方に対しては、本人の意思を尊重し感情の変化が起こりにくい環境を整える必要があります。
注意障害や遂行機能障害が見られる場合は、気が散る原因を取り除いたり、根気強くリハビリテーションに取り組んだりするのが大切なポイントです。
感情がコントロールできない社会的行動障害は、本人も無自覚なケースがほとんどのため、家族やパートナーの方は感情に任せず冷静に対処する必要があります。(文献9)
脳梗塞の後遺症に対する治療法
脳梗塞の後遺症に対する主な治療法は以下のとおりです。
それぞれ解説します。
高次脳機能障害に対するリハビリテーション
脳梗塞の後遺症として多く見られる高次脳機能障害に対しては、以下のリハビリテーションやカウンセリングが行われます。
- 認知リハビリテーション
- 認知行動療法(CBT)
- 行動変容療法
- 社会技能訓練
- 心理カウンセリング
認知リハビリテーションは、脳梗塞に伴う高次脳機能障害を改善する目的で行われます。
記憶力や判断力、注意力などの認知機能を向上させる目的で行われ、ADL(日常生活動作)の向上を目指すのが特徴です。
認知行動療法(CBT)は考え方や行動パターンを変化させる心理療法の一種で、感情のコントロールに役立ちます。
行動変容療法も心理療法の一種で、問題行動の原因となる行動を抑制し、より適切な行動を習得するのが目的です。
社会技能訓練ではコミュニケーション能力を高め、自信をもって生活を送るためのサポートを行います。
心理カウンセリングは高次脳機能障害患者を支援するだけでなく、家族へのサポートも行う点が特徴です。
症状の回復度合いを大きく左右するため、高次脳機能障害に対するリハビリテーションは発症から6カ月以内に開始することが推奨されます。
薬物療法
脳梗塞の後遺症を治療する際に行われる治療の一つが薬物療法です。
高次脳機能障害に伴う感情のコントロールや、うつ病・不安症などの精神症状を軽減し、日常生活の質を向上させる目的で行われます。
用いられる主な医薬品および期待できる効果は以下のとおりです。(文献10)
| 主な医薬品 | 期待できる効果 |
|---|---|
| メチルフェニデート・アマンタジン | 注意障害・意欲低下を改善する |
| リスぺリドン・ハロペリドール | 不安や興奮を抑制する |
| ミルナシプラン・トラゾドン | 意欲を向上させる |
| ブロマゼパム・ロラゼパム | 不安や緊張、抑うつ状態を緩和する |
| ゾピクロン・ニトラゼパム | 睡眠障害を改善する |
| カルバマゼピン・バルプロ酸 | 易怒性・攻撃性を緩和する |
高次脳機能障害に伴う症状を抑制する医薬品だけでなく、脳の神経伝達物質のバランスを整えるために抗うつ薬や抗精神病薬なども用いられます。
再生医療
脳梗塞の後遺症に対する治療法の一つが再生医療です。
再生医療では患者自身の脂肪細胞から抽出した幹細胞を分離して培養し、増殖させたうえで点滴を用いて静脈内に注入します。
患者自身の細胞を用いた治療法のため拒絶反応が起こりにくく、副作用のリスクも低い点が特徴の一つです。
日帰りでも治療が受けられるため、手術を避けたい方にとって適した選択肢となっています。
脳梗塞の後遺症や予防についてお悩みの方は、再生医療に関する以下の記事もご覧ください。

脳卒中のお悩みに対する新しい治療法があります。
脳梗塞の後遺症による性格変化が気になる方は当院へご相談ください
脳梗塞の後遺症によるご家族やパートナーの性格の変化が気になる方は、当院「リペアセルクリニック」までお気軽にご相談ください。
脳梗塞の発症に伴い前頭葉が損傷されると易怒性や攻撃性、意欲の低下、感情の不安定など社会的行動障害を起こしがちです。
社会的行動障害はご家族やパートナーの方に大きな負担となる上、患者本人が社会生活に復帰する際に障害となります。
脳梗塞の後遺症に対する治療法の一つが再生医療です。再生医療では患者の脂肪細胞から採取した幹細胞を培養・増殖させ、点滴を用いて損傷部位に注入します。
当院「リペアセルクリニック」では、再生医療に関してLINEでの簡易オンライン診断を実施しています。再生医療に興味がある方は、ぜひ一度お試しください。
\無料相談受付中/
脳梗塞の後遺症に関してよくある質問
脳梗塞になると顔つきは変わる?
脳梗塞を発症すると顔つきが変わることがあります。
たとえば写真を撮る際に笑顔を作ると片方の口角や頬しか上がらず、顔つきが左右でゆがんで見えるケースがあります。
笑顔を作った際に顔つきが左右で違って見えるのは、脳梗塞を発症する前兆の可能性もあるため注意が必要です。
脳梗塞の後遺症で片麻痺を発症すると、左右いずれかの表情筋がはたらかず、表情を作った際に顔がゆがんで見えやすくなります。
また、脳梗塞の後遺症で意欲低下や無関心(アパシー)状態に陥ると、表情の変化に乏しくなるケースがあります。
脳梗塞後の麻痺が左右どちらかで症状は変わる?
脳梗塞後の麻痺が左右いずれにあらわれるかによって、症状にも変化が見られます。
脳梗塞に伴う麻痺は、損傷した脳と反対側にあらわれます。たとえば脳梗塞に伴い左脳を損傷すれば、麻痺は右半身にあらわれやすいです。
右脳には運動だけでなく空間認知や感情を司る機能があるため、右脳を損傷すると運動機能障害や社会的行動障害(感情のコントロールが難しくなるなど)が見られます。
左脳には言語や論理的思考を司る機能があるため、左脳を損傷すると言語障害や思考能力の低下が起こります。
脳梗塞の後遺症はもやもや病とどう違う?
脳梗塞の後遺症ともやもや病はいずれも脳の血管障害が原因で起こりますが、主に以下の違いがあります。
| 疾患 | 原因 | 症状 | 治療法 |
|---|---|---|---|
| もやもや病 | 脳血管の狭窄 | 虚血症状 | バイパス手術など |
| 脳梗塞 | 脳血管の閉塞 | 言語障害・麻痺など | 血管拡張術・薬物療法など |
もやもや病はなんらかの原因により脳の血管が狭くなって(狭窄)血流不足を起こし、細い血管が煙のようなもやもやした見た目に発達する病気です。(文献11)
発症原因や症状、治療法は脳梗塞と異なりますが、脳梗塞の前兆のケースもあるため、頻繁に症状が見られる場合は速やかに医療機関を受診してください。
\無料オンライン診断実施中!/
(文献1)
作業療法士Q&A|一般社団法人日本作業療法士協会
(文献2)
感情はどこから?実は生存をかけて脳が下した判断|日本経済新聞
(文献3)
脳卒中後遺症としての意欲低下について|社会福祉法人さわらび会
(文献4)
社会的行動障害への対応と支援|国立障害者リハビリテーションセンター
(文献5)
脳卒中で笑い止まらぬ感情失禁の原因と対処法|ニューロテックメディカル
(文献6)
不安な表情の多い高齢者への介護福祉士の関わり|高田短期大学
(文献7)
よくある質問|国立障害者リハビリテーションセンター
(文献8)
高次脳機能障害のリハビリテーション|慶應義塾大学病院
(文献9)
社会的行動障害とは?行動や感情への影響とリハビリ方法|御所南リハビリテーションクリニック
(文献10)
高次脳機能障害とは|沖縄県医師会
(文献11)
もやもや病|国立循環器病研究センター