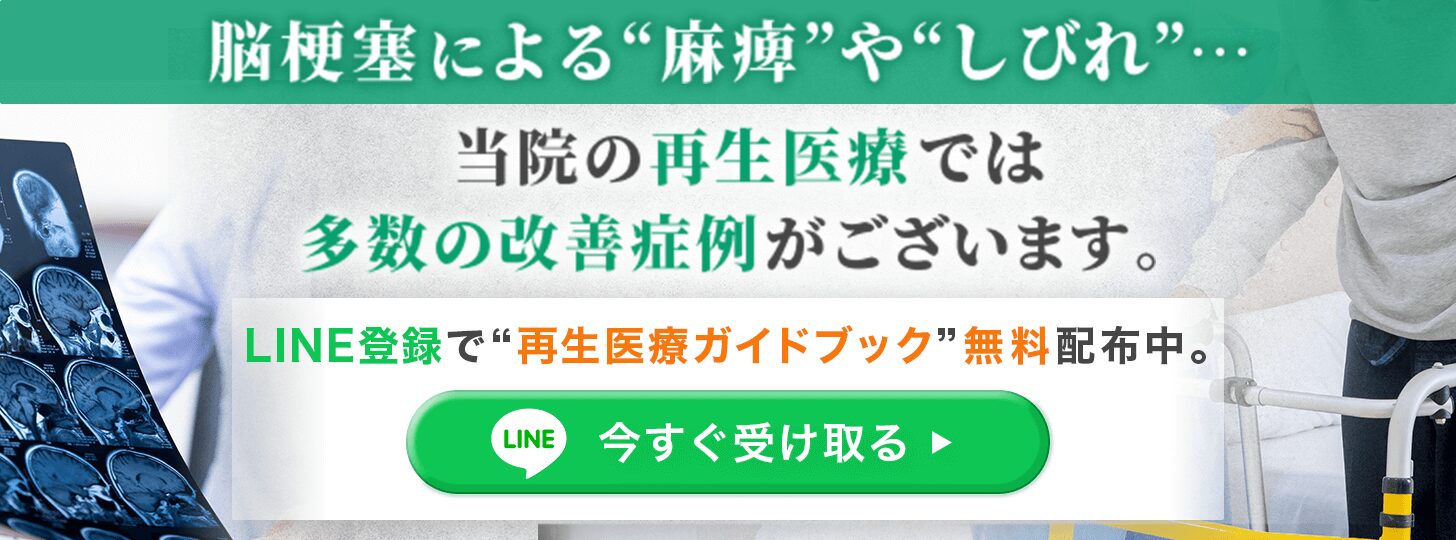- 脳梗塞
- 脳卒中
- 頭部
脳梗塞のリハビリ期間は?方法や注意点も解説【医師監修】
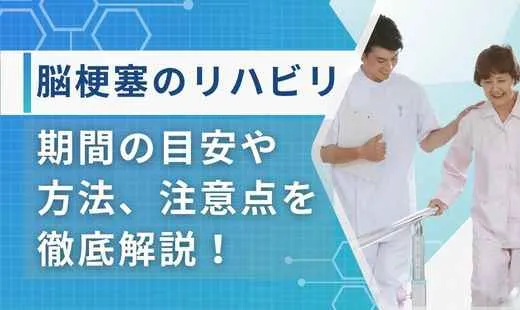
脳梗塞で入院した場合、麻痺した機能の回復を図ることは欠かせません。しかし、具体的にリハビリにどの程度の期間がかかるのかは気になる部分です。
脳梗塞のリハビリ期間は、病院に入院している間であれば最長で6カ月程度です。病状や年齢によって必要な期間が異なるため、目安を知っておくとリハビリに取り組む際に役立ちます。
本記事では、脳梗塞のリハビリ期間の目安を、訓練の方法やポイント・注意点とともに解説します。
なお、当院「リペアセルクリニック」の公式LINEでは、脳梗塞の後遺症や再発予防に対する再生医療の情報提供と簡易オンライン診断を実施しております。
脳梗塞の後遺症でお悩みの方は、ぜひ一度公式LINEにご登録ください。
目次
脳梗塞のリハビリ期間の目安
脳梗塞は、脳の血管が詰まることで血流が途絶え、脳細胞が壊死する疾患です。脳梗塞の治療でリハビリを進めていく際、病気の時期に応じたリハビリ期間の目安があります。病期別にリハビリ期間の目安を見ていきましょう。
急性期:発症後1~4週間
急性期とは、脳梗塞の症状が発生してから不安定な状況が続く期間を指します。急性期の場合、リハビリ期間は、発症後1~4週間程度です。全身状態が安定するまでの間は、ベッドの上で手足の関節を動かしたり、寝返りを打ったりといった、負担の少ないメニューから始めます。
ただし、年齢や症状の重さによって必要な期間は変わってきます。
【年齢による違い】
- 20~40代の若年層:1~2週間程度
- 70代以上の高齢者:4週間程度
【症状の重症度による違い】
- 軽度の場合:1週間程度
- 中等度の場合:2~3週間程度
- 重度の場合:3週間以上
このように、症状が重いほど急性期のリハビリ期間は長くなる傾向があります。
回復期:発症後1~6カ月
回復期は脳梗塞の症状が落ち着き、脳機能の改善が進む時期です。発症後1~6カ月程度で、この間に積極的なリハビリを進めていきます。
回復期のリハビリに必要な期間も、年齢や脳梗塞の症状の重さによってさまざまです。
【年齢・症状による期間の目安】
- 20~40代の若年層で症状が軽度の場合:1~2カ月程度
- 高齢者や症状が重度の場合:3~6カ月以上
この時期に適切なリハビリを行うことで、失われた機能の回復が促進されます。
脳梗塞リハビリの医療保険適用期間は180日まで
脳梗塞のリハビリの公的医療保険の適用期間は、発症後の入院で最大180日(6カ月程度)までです。もし、退院後もリハビリが必要な場合は、40歳以上で要介護認定されれば介護保険が適用されます。
要介護認定を受けられない場合でも、後遺症の種類によっては訓練等給付を受けられることがあります。
生活期(維持期):発症後6カ月以降
病院での脳梗塞の治療やリハビリが終わって退院した後は生活期(維持期)に入り、その時期は遅くとも発症後6カ月以降です。
入院中のリハビリで回復した機能を、日常生活の中で維持・強化していきます。日常的な動作や散歩などの軽い運動に励みつつ、定期的にリハビリに対応した病院・クリニックに通院して訓練します。
【時期別】脳梗塞のリハビリの方法
脳梗塞のリハビリの方法は、病期によってさまざまです。病期ごとのリハビリの方法や場所を一つずつご紹介します。
急性期:筋力低下を防止するリハビリ
急性期は脳梗塞発症直後の容態が安定するまで医療機関のベッドの上で過ごします。このため、リハビリも身体や認知面の機能の衰退を防ぐのが目的です。
寝た状態で過ごす日々が続くため、行われる訓練は次の通りです。
| 訓練名 | 訓練の内容 |
|---|---|
| 簡単なストレッチ | 関節を動かし、拘縮の予防・改善をおこなう |
| 離床訓練 | ベッドから起き上がる・座る・立つ・車椅子への移動 |
| ADL訓練 | 食事・着替え・トイレなど日常生活の動作を回復する訓練 |
| 摂食・嚥下(えんげ)訓練 | 食べ物を噛む・飲み込む機能を回復する訓練 |
| 機能回復訓練 | 運動麻痺や言語障害などがある場合に行う |
容態が安定する前の段階では、ベッドやその周囲で行える簡単な訓練で、少しずつ基本的な機能の回復を目指します。
回復期:運動機能や言語機能に関する訓練が中心
脳梗塞の容態が落ち着き回復期に入ると、訓練も急性期に行っていたものに日常生活の復帰を目指す内容が加わります。病室も回復期リハビリテーション病棟に移るとともに、訓練もベッドやその周辺に加えて、リハビリテーション施設で行うのが一般的です。
回復期に行うリハビリの内容は、以下のとおりです。
| 訓練名 | 訓練の内容 |
|---|---|
| ベッドやベッド周りでの訓練 | ベッドで起きる・座る・ベッドサイドで歩く など |
| 歩行訓練 | 車椅子に座る・杖や歩行器を使った歩行・歩行時のバランスの回復 など (ロボットスーツを使って行うケースも) |
| 日常動作に関する訓練 | 食事・着替え・トイレ・入浴など日常生活の動作を回復する訓練 |
| より応用的な訓練 | 手芸や工作など手や指などを使った複雑な動作の訓練 |
| 機能回復訓練 | 運動まひや言語障害などがある場合に行う |
| 口の動作に関する訓練 | 発声など口・のどが関わる動作の訓練 |
| 顔を動かす訓練 | 首の周囲や肩の筋肉・関節を動かす訓練 |
| 嚥下訓練 | 舌や喉の刺激、水分・食物を実際に飲み込む訓練 |
| 高次脳機能障害を予防・改善する訓練 | プリントや積木など物品を使った訓練や動作の反復練習など、認識や判断・実行を促す訓練 |
なお、以上の訓練をすべて行うわけではありません。実際に行う訓練は、症状の重さや回復の見込みに応じて決定されます。
生活期(維持期):自宅での継続的な訓練
医療施設を退院した後の生活期(維持期)は、リハビリも自宅やリハビリ専用施設で継続的に進めるのが一般的です。とくに自宅でリハビリを進める場合は、退院日を迎える前に手すりやスロープなどを準備して、落ち着いてリハビリできる環境を整えることが重要です。
生活期におけるリハビリの内容として、以下のものが挙げられます。
| 訓練名 | 訓練の内容 |
|---|---|
| 日常動作に関する訓練 | 食事・着替え・トイレ・入浴など日常生活の動作を回復する訓練(回復期より継続) |
| 歩行訓練 | 手すりにつかまりながら歩く訓練・杖などを活用した訓練など |
| 自宅内外での簡単な散歩・運動 | 散歩・筋力トレーニング・ストレッチなど |
なお、退院後に麻痺など新たな問題が見つかるケースもあります。新しい問題や課題が見つかったときは、担当医師やリハビリテーション施設などへの速やかな相談が大切です。
脳梗塞のリハビリのポイント・注意点
脳梗塞のリハビリを進めていく際、ポイントや注意点を踏まえておくことも大切です。主なポイントや注意点として、以下のものが挙げられます。
リハビリは急性期から始める
脳梗塞を含む脳卒中のリハビリは、急性期から始めることが重要です。具体的には、発症後24~48時間以内のリハビリ開始が推奨されます。(文献1)
リハビリは早期に始めるほど、脳機能や神経の回復が促されると考えられるためです。加えて早い時期からリハビリを始めれば、手足の筋力の衰えを防ぎつつ、基礎体力を温存した状態で回復期のリハビリに臨めます。
ただし、病状の深刻度などによっては、開始時期について慎重な判断が求められる場合があります。
残された能力も同時に鍛える
脳梗塞のリハビリでは、失われた機能だけでなく、今残されている能力を同時に鍛えることも重要です。
仮に左手が麻痺して動かせない場合でも、右手が通常通り動かせるのなら、右手を鍛えることで麻痺した左手の機能をサポートできます。麻痺した側は一般的に発症6カ月以内であれば、継続的なリハビリで回復できる見込みが十分にあります。
加えて、残された能力を鍛えることは、リハビリの継続の面でも有効です。体の一部が麻痺した事実は、想像以上に患者を落ち込ませる場合があります。前向きにリハビリに取り組んで日常生活に戻れるようにするためにも、残された能力を鍛えることは重要です。
無理のない範囲で積極的なリハビリを意識する
脳梗塞のリハビリは、無理のない範囲で継続的に取り組むことがポイントです。脳梗塞で麻痺した部位は、リハビリを始めてもすぐに効果が見込めません。
ただし、急性期から積極的にリハビリを続けることで、早期の回復が促されます。なお、リハビリ中に痛みや疲れを感じたら、無理せず休憩を取りましょう。疲労が溜まった状態で無理やりリハビリを続ければ、逆に回復の妨げになります。
退院後もリハビリを継続する
脳梗塞のリハビリは、退院した後の継続も大切です。退院後にリハビリをやめると、回復した機能が衰えて日常生活に支障が出ます。加えて、リハビリをやめたことでそれ以上の機能回復が見込めない場合さえあります。
退院後も自宅内外での散歩や日常生活にまつわる訓練のほか、パソコン操作など自分の好きなことでリハビリに取り組むのがおすすめです。
脳梗塞を含む脳卒中の治療には再生医療も一つの選択肢
脳梗塞を含む脳卒中に対しては、再生医療という治療法があります。
脳梗塞の後遺症や再発予防には、再生医療の幹細胞治療を行います。
当院「リペアセルクリニック」の幹細胞治療では、患者様から米粒2~3粒ほどの少量の脂肪組織を採取し、幹細胞を培養して増やした後に患部に点滴で投与します。幹細胞が持つ、さまざまな細胞に変化する「分化能」という能力を活用する治療法です。
脳梗塞の後遺症である、しびれや言語機能の低下、再発への不安でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
以下では、実際に当院で幹細胞治療を受けた方の症例を紹介しています。
また、脳卒中に対する再生医療について詳細は、以下のページをご覧ください。

脳卒中のお悩みに対する新しい治療法があります。
まとめ|脳梗塞のリハビリ期間を知って焦らず取り組もう
脳梗塞のリハビリに必要な期間は、急性期で発症後1~4週間程度、回復期で3~6カ月程度です。ただし、発症時の年齢や症状の重さによって前後します。
基本的に症状が落ち着くまではベッドで簡単なメニューをこなし、回復期に入ってからさまざまな内容でリハビリを進めます。なお、退院後も自宅内外での継続的なリハビリは欠かせません。
脳梗塞のリハビリはすぐに効果が表れません。しかし、無理のない範囲で積極的にリハビリを続ければ、回復が促されます。脳梗塞のリハビリ期間の目安を知っておくことは、今後のリハビリに前向きに取り組む上で重要です。
脳梗塞の後遺症や再発の不安でお悩みの方は、当院「リペアセルクリニック」へお気軽にご相談ください。
\無料相談受付中/
脳梗塞のリハビリ期間のよくある質問
脳梗塞の入院期間が2週間で済む場合はある?
発症後の症状が軽い方であれば、2週間程度での退院も可能です。
急性期病院では、脳梗塞を発症しても症状が比較的軽く、早期に状態が安定した方であれば、1~2週間程度で退院が可能です。ただし、これは症状の程度や回復の経過によって個人差があります。
脳梗塞のリハビリしないとどうなる?
脳梗塞を発症した場合、リハビリしないと失われる脳機能が増えて症状が悪化します。日常生活に大きな支障をきたす上に、寝たきりになるリスクさえあるため、早期のリハビリの開始が重要です。
脳梗塞になった高齢者が回復する見込みは?
高齢者が脳梗塞を発症した場合でも、早いうちから適度なリハビリを続けることで少しずつ回復する見込みがあります。ただし、若年層よりも時間をかけてリハビリしていく必要があるため、休みも挟みつつ理学療法士などの専門家とともに根気強く取り組みましょう。
脳梗塞で退院した後の注意点は?
脳梗塞の治療を終えて退院した後は、再発を防ぐための生活習慣の見直しが重要です。日本人に限った場合、脳梗塞を含む脳卒中の10年再発率は51.3%である研究結果が出ています。(文献2)
10年で見ても2人に1人が再発するリスクがあるため、退院後も生活習慣に気を付けることが大切です。具体的には、肥満や糖尿病、高血圧などの生活習慣病への警戒が予防可能性を高めます。栄養バランスのとれた食事や適度な運動を心掛ける一方で、過度の飲酒・喫煙のような習慣は控えるべきです。
参考文献
(文献1)
一般社団法人 日本脳卒中学会『脳卒中治療ガイドライン2021【改訂2025】』
(文献2)
J Hata, Y Tanizaki et al.(2005) J Neurol Neurosurg Psychiatry.