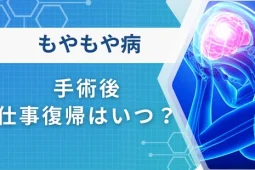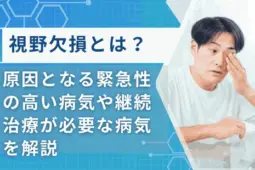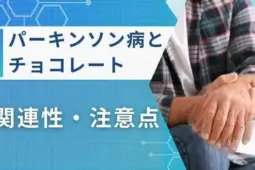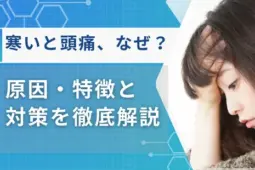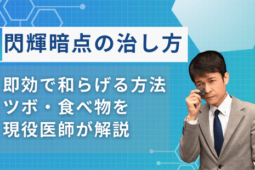- 頭部
- 頭部、その他疾患
もやもや病になると性格が変化する?メカニズムや高次機能障害について医師が解説
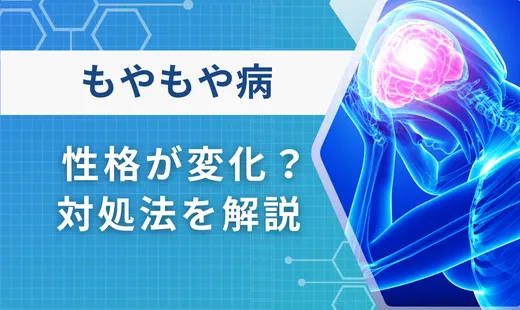
もやもや病になってから性格が変わった気がする。
もやもや病による性格変化にはどのように対処すべき?
この記事を読んでいるあなたは、自分や大切な人がもやもや病になり、性格変化が起きているのではないでしょうか。
「どのように接したら良いかわからない」と悩んでいる人もいるかもしれません。
結論、もやもや病による性格変化は、「高次脳機能障害」が関係している可能性があります。
以前とまったく同じ性格に戻すのは困難ですが、原因や対処を知れば、生活上の不便は軽減できます。
本記事では、もやもや病による性格変化のメカニズムと対処法について詳しく解説します。
記事を最後まで読めば性格変化の原因や対処法がわかり、毎日を快適に過ごしやすくなるでしょう。
目次
もやもや病の後遺症で性格が変化することがある
もやもや病は、脳の重要な動脈が狭くなった結果、通常では見られない細い血管(もやもや血管)が発達する病気です。もやもや血管は血流悪化や脳卒中のリスクが高く、脳機能の低下につながるケースも見られます。
また、脳機能の低下によって「高次脳機能障害」が生じると、性格変化が起こる可能性があります。高次脳機能障害とは「怪我や病気によって脳がダメージを受けた結果、複雑な処理ができなくなり、生活に支障が出る状態」です。
もやもや病でダメージを受けやすいのは、脳の「前頭連合野」と呼ばれる部位です。
前頭連合野には以下のようなはたらきがあります。(文献1)
|
前頭連合野の機能 |
説明 |
|---|---|
|
認知・実行機能 |
状況を深く理解したり推理したりする |
|
心の理論・社会性機能 |
人の気持ちを想像したり、周りを見て行動したりする |
|
情動・動機付け機能 |
積極的に行動したり、自己表現をしたりする |
どの機能も、人間が社会的な生活を送るのに欠かせません。
そのため、もやもや病によって前頭連合野の機能が失われると、「感情のコントロールができず自己中心的になる」「周りの状況を見て動けない」などが起こり、性格が変わったと思われやすいのです。
当院「リペアセルクリニック」では、もやもや病による脳卒中後の治療として再生医療(幹細胞治療)を提供しています。再生医療には、リハビリの効果を高めたり、後遺症を軽減したりする効果が期待できます。
もやもや病後の後遺症にお悩みの方は「メール」もしくは「オンラインカウンセリング」へ気軽にご相談ください。
\無料オンライン診断実施中!/
なお、もやもや病については、以下の記事で詳しく説明しています。
もやもや病の後遺症でみられる性格の変化
もやもや病の後遺症「高次脳機能障害」による性格の変化は、以下のとおりです。
- 記憶障害により物忘れが増える
- 注意障害により気が散りやすくなる
- 社会的行動障害により感情をコントロールできなくなる
- 遂行機能障害により段取りが悪くなる
本章の内容をもとに、気になる性格の変化が高次脳機能障害によるものなのかを考えてみましょう。
なお、性格変化以外の後遺症については、以下の記事もぜひ参考にしてください。
記憶障害により物忘れが増える
もやもや病によって脳の記憶をつかさどる部分の機能が低下すると、「作業記憶(ワーキングメモリー)」が低下することがあります。
作業記憶とは、何かを行うときに一時的に置いておく「記憶の引き出し」です。記憶障害の症状例は、以下のとおりです。
- 聞いたことをすぐ忘れて何度も聞き返す
- 買い物に出かけても、何を買えばいいか忘れる
- ものを置いた場所を思い出せない
何度も同じことを聞いたり、頼みごとができなくなったりする結果、本人や周囲の人に不便が生じ、ストレスとなるケースは珍しくありません。
注意障害により気が散りやすくなる
注意障害とは、気が散りやすく一つの物事に集中できない状態です。生活に支障をきたす注意障害の症状は、以下のとおりです。
- ぼんやりしていてミスが多い
- 2つのことを同時にできない(マルチタスクができない)
- 少しの変化に気をとられ、自分の動作が止まる
注意障害は、仕事や勉強などのパフォーマンスの低下につながりやすい症状といえるでしょう。
社会的行動障害により感情をコントロールできなくなる
社会的行動障害とは、自分の感情をうまくコントロールできない、衝動的な行動が増えるなどの状態です。以下のようなケースがあり、社会生活に問題が出る可能性も考えられます。
- 自己中心的になる
- 感情の振れ幅が大きくなる
- 思い通りにならないと大声を出す
- 興奮したり暴力をふるったりする
- 欲求を抑えられずにギャンブルや借金に走る
逆に、人や物事への興味や自発性がなくなるケースもあります。
遂行機能障害により段取りが悪くなる
遂行機能障害とは、物事を順序立てて行えなくなることです。具体的な症状は、以下のとおりです。
- 段取りが悪い
- 優先順位をつけられない
- 約束の時間に間に合わない
- 人に指示してもらわないと何もできない
- 臨機応変に行動できず、少しのトラブルにも対応できない
日常生活は、予期せぬ出来事がたくさん起こります。遂行機能障害によりその場に応じた対応ができなくなると、仕事や生活の維持に支障が出やすくなるかもしれません。
もやもや病による性格変化は検査・症状で診断する
性格変化がもやもや病による高次脳機能障害が原因なのかは、以下の内容から総合的に判断されます。(文献2)
- 何かの病気(今回はもやもや病)が原因で起きたものか
- 現在、脳機能が低下したことにより日常生活・社会生活に支障が出ているか
- MRIやCT、脳波検査などにより、認知障害の原因が脳の異常によるものと考えられるか
- 先天性疾患や発達障害、持病などが関連していないか
なお、高次脳機能障害の診断は、原因となる脳の病気や怪我の急性期が過ぎ、症状が安定してから行われます。そのため、もやもや病と診断されてすぐではなく、ある程度の期間が必要です。
当院「リペアセルクリニック」では、もやもや病による脳卒中後の治療として再生医療(幹細胞治療)を提供しています。再生医療は、もやもや病による脳卒中後の身体機能の回復や再発予防を目指した治療法の一つです。
もやもや病による脳卒中が原因の高次機能障害にお悩みの方は、「メール」もしくは「オンラインカウンセリング」へ気軽にご相談ください。
\無料オンライン診断実施中!/
もやもや病で性格が変化したときの対処法
もやもや病で性格変化や行動変化が見られても、原因を知り適切に対処すれば、日常生活への支障を軽減できます。
本章では、「自分の性格が変わった場合」「家族や友人の性格が変わった場合」の2つの事例において、おすすめの対処法を解説します。
自分の性格が変わった場合
もやもや病にかかった場合、病気による変化を理解した上で、自分に合う対応を学ぶのがおすすめです。
具体的な対処法の例は以下のとおりです。(文献3)
- 無理のない範囲で運動し、体力をつける
- バランスの取れた食事や規則正しい生活を意識する
- 人と比較せず、自分の状況や希望に合わせた生活の目標を考える
地域のリハビリ科や精神科の病院、地域の保健福祉センターなどに相談してみるのも良い方法です。焦らずに、少しずつ進んでいきましょう。
家族や友人の性格が変わった場合
性格変化が周りの人に起きた場合は、もやもや病による影響を正しく理解し、適切なサポートを検討しましょう。
たとえば、本人がどのような状況でイライラしたり不自由したりしているかをチェックし、専門家からどのような生活や手助けが適しているかのアドバイスを受けます。相談先は病院や保健福祉センターなどです。
具体的な対策の例は、以下のとおりです。
- 気が散らない環境を整え、ものごとに集中できるようにする
- こまめにメモを取り、低下した記憶力をおぎなう
- 低下した機能を助ける訓練を受ける
一度の相談ですべての課題に対応するのは難しいため、相談と検討を繰り返しながら少しずつ本人の抱える困難に対応していきます。焦らずに、寄り添う姿勢を大切にしてみてください。
まとめ|もやもや病で性格変化が起きたら医療機関へ相談しよう
本記事では、もやもや病の後遺症による性格変化について、詳しく説明しました。
もやもや病のあとに性格が変わるのは、脳のダメージによる「高次脳機能障害」が原因の可能性があります。感情の制御をつかさどる「前頭連合野」がダメージを受けた結果、記憶障害や行動障害などが起こります。
性格変化は病気の後遺症であると理解し、専門家の指導のもとに適切な対応を行いましょう。
当院「リペアセルクリニック」では、損傷した脳に対する再生医療(幹細胞治療)を実施しています。再生医療は、もやもや病による脳卒中後の身体機能の回復や再発予防を目指した治療法の一つです。
「メール」もしくは「オンラインカウンセリング」を行っております。気軽にご相談ください。
\無料オンライン診断実施中!/
もやもや病による性格変化に関するよくある質問
高次脳機能障害は完治しますか?
脳に傷がある状態のため、高次脳機能障害を完全に治すことは困難です。しかし、得意・不得意を考慮した工夫により、生活上の不便は軽減できます。根気強くリハビリをおこないましょう。
脳卒中による高次脳機能障害があるとき、入院期間はどのくらいになりますか?
脳卒中では、発症直後の急性期を過ぎたあとは「回復期リハビリテーション病棟(回復期リハ病棟)」に移ってリハビリを続ける方が多く見られます。
回復期リハ病棟では、脳血管障害における一般的な入院期間は150日とされています。ただし、高次脳機能障害の合併があると、180日まで入院可能です。
期間すべてを使っての入院が必要というわけではありません。しかし、高次脳機能障害は麻痺と違い一見してわかりづらく、周りの理解が得られにくいケースが多いです。退院後を快適に過ごすために、社会復帰のためのリハビリや環境整備にしっかりと時間をかけましょう。
もやもや病による脳梗塞については、以下の記事もぜひ参考にしてください。
参考文献
渡邊正孝「頭連合野のしくみとはたらき|高次脳機能研究( 第36巻,第1号)」https://www.jstage.jst.go.jp/article/hbfr/36/1/36_1/_pdf
厚生労働省 科学研究成果データベース「令和4年版高次脳機能障害診断基準 ガイドライン」
https://www.jstage.jst.go.jp/article/hbfr/36/1/36_1/_pdf
相模原市「もしかしたら高次脳機能障害?」
https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/025/677/r03_pamphlet.pdf