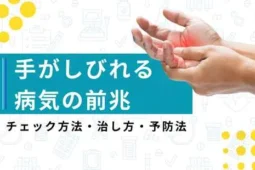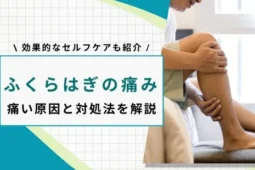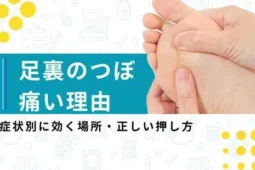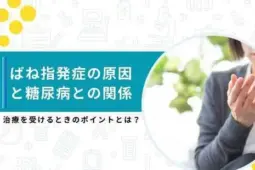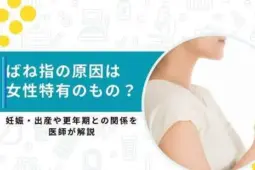- 足部、その他疾患
- 手部、その他疾患
- 手部
- 足部
手足のしびれとピリピリ感の関係は?症状の原因や治し方を解説
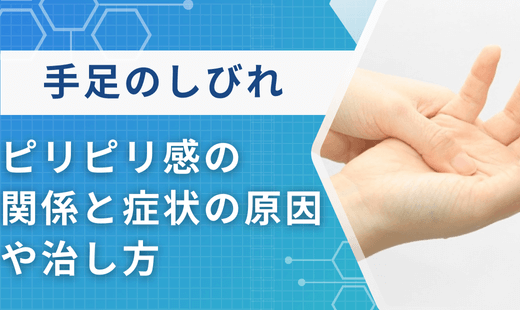
「最近、手足が妙にしびれる」
「手足にピリピリした違和感に不安を覚えている」
手足のしびれやピリピリとした感覚には、重大な病気のサインが隠れているかもしれません。
本記事では、手足のしびれとピリピリ感の関係に加え、しびれの原因や治し方について詳しく解説します。
適切な治療を受けずに放置してしまうと神経の回復力が損なわれ、手足のしびれが残ったり、指先を使った動作が困難になったりする場合があります。
症状が悪化して日常生活に影響が出る前に治すためにも、手足のしびれを根本的に治療できる「再生医療」をご検討ください。
\しびれの原因である神経を治療する「再生医療」とは/
再生医療は、患者さまの細胞や血液を用いて自然治癒力を高めることで、しびれや痛みの原因となっている損傷した神経の再生・修復を促す治療法です。
【こんな方は再生医療をご検討ください】
- 手足のしびれが1週間以上続いている
- しびれが徐々に強くなっている、または範囲が広がっている
- 日常生活に影響が出るほど悪化する前に早く治したい
>>再生医療専門の「リペアセルクリニック」に無料相談する
当院リペアセルクリニックでは、手足のしびれに対する再生医療について無料カウンセリングを実施中のため、お気軽にご相談ください。
目次
手足のしびれとピリピリ感の関係性
手足のしびれやピリピリ感は、脳神経系の疾患や糖尿病の可能性があります。
| 症状 | しびれ(感覚鈍麻・感覚消失) | ピリピリ感(異常感覚) |
|---|---|---|
| 自覚される感覚 | 感覚が鈍い、麻痺したような感覚。触れてもわかりにくい、あるいはまったく感知しない | ピリピリ・ジンジン・チクチクするような、実際には刺激がないのに感じる異常な感覚 |
| 日常例との比較 | 正座を長時間した後、足の感覚がなくなるような状態 | 正座の後、血が戻ってくるときのジンジンした感じ |
| 発生する仕組み | 神経の信号が正常に伝わらなくなり、感覚の低下や消失が起こる | 神経が過敏になり、実際には存在しない刺激をあるものとして誤認する |
| 主な原因 | 神経の圧迫・損傷・炎症・血行不良など、末梢神経の機能障害 | しびれと同様の原因で起こる(神経の異常興奮や回復途中も含む) |
| 症状が出現するタイミング | 圧迫や障害が長引いた場合に出やすい。慢性的な場合も | 圧迫の初期段階や、血流再開・回復途中で出やすい |
| 放置によるリスク | 感覚障害が進行し、神経の損傷が回復しにくくなる可能性がある | 神経の異常を知らせる初期サインであることが多い |
(文献1)
しびれやピリピリ感はいずれも神経系に異常をきたしている症状ですが、放置すると症状が進行したり重症化したりするリスクがあります。
適切な治療を受けないと、後遺症として「しびれ」が残る可能性があるため、放置せず医療機関を受診しましょう。
手足のしびれやピリピリ感を早く治したい方は、原因となっている神経損傷を根本治療できる「再生医療」をご検討ください。
当院リペアセルクリニックでは、神経損傷に対する再生医療について無料カウンセリングを実施中のため、お気軽にご相談ください。
以下の記事では、手足がしびれる病気について詳しく解説しています。
手足のしびれとピリピリ感の原因
手足のしびれとピリピリ感にはさまざまな原因が考えられます。その中には重大な病が隠されている可能性もあるため、早期発見が重要です。
手足のしびれとピリピリ感の原因は以下の5つです。
- 一時的なもの
- 整形外科的な症状
- 内科的な症状
- 脳神経系の症状
- 糖尿病の症状
しびれの原因を解説します。
以下の記事では、手足がしびれる原因について詳しく解説しています
【関連記事】
手足のしびれの原因となる病気の症状や予防法を解説!前兆も紹介
寝起きに手足のしびれが起きる原因とは?自分でできる対処法もあわせて紹介
一時的なもの
日常生活の中で、手足がしびれたりピリピリしたりする症状は誰にでも起こり得ます。一時的に神経や血管が身体の重みなどで圧迫されることで起こります。
また、血行不良のほかには、寒さや激しい運動や発汗、過労・ストレスなどが挙げられます。一時的なしびれでも症状が毎日のように出る、あるいは数時間続くような場合は、重大な病気のサインかもしれません。
症状が悪化する前に、早めに医療機関を受診しましょう。
整形外科的な症状
| 病名 | 原因となる部位 | 主な症状が出る部位 | 症状の特徴 |
|---|---|---|---|
| 椎間板ヘルニア(頚椎/腰椎) | 首・腰の椎間板が飛び出し神経を圧迫する |
頚椎:首〜腕・指 |
しびれ、動かしにくさ、 しびれのような感覚が続く |
| 脊柱管狭窄症(頚椎/腰椎) | 背骨の神経の通り道が狭くなる | 頚椎:手・腕・足 腰椎:足・腰・お尻 |
歩くとしびれや違和感が出て、休むと楽になる |
| 手根管症候群 | 手首の神経(正中神経)圧迫 | 親指〜薬指の一部 | 手のしびれ、細かい動作がしにくくなる |
| 肘部管症候群 | 肘の神経(尺骨神経)圧迫 | 小指・薬指 | 指のしびれ、手を使うと悪化することがある |
| 足根管症候群 | 足首の神経(後脛骨神経)圧迫 | 足の裏・足指 | 足裏のしびれ、熱感や冷感、ピリピリした感覚 |
| 胸郭出口症候群 | 首〜肩の神経・血管が圧迫される | 肩・腕・手 | しびれ、だるさ、冷感、力が入りにくい |
手足のしびれやピリピリ感の原因として、運動器(骨・関節・筋肉・靭帯)の異常が神経を圧迫、または刺激し、しびれや違和感が症状として現れることがあります。
ヘルニアなどの症状は、骨や関節、筋肉などの構造に問題があることが原因で起こるため、整形外科での検査が必要です。
また、近年の治療では、ヘルニアや脊柱管狭窄症などによって傷ついた神経を治療し、しびれを根本的に改善できる可能性がある「再生医療」が注目されています。
当院リペアセルクリニックでは、手足のしびれに対する再生医療について無料カウンセリングを実施中のため、お気軽にご相談ください。
内科的な症状
| 病名・原因 | 症状の原因 | 主に症状が出やすい部位 | 症状の特徴 |
|---|---|---|---|
| 糖尿病性神経障害 | 高血糖により末梢神経が損傷される | 足の裏・足指(左右対称に出やすい) | しびれ、違和感、感覚が鈍くなる。気づかずケガをすることも |
| ビタミンB12不足 | 神経の働きを保つ栄養素が不足 | 手足全体 | しびれ、感覚異常。貧血や疲れも伴うことがある |
| 甲状腺機能異常 | 代謝の低下やホルモンバランスの乱れが神経に影響 | 手足、筋肉 | しびれ、冷え、筋肉痛。機能低下・亢進どちらでも起こることがある |
| 閉塞性動脈硬化症など血管系の病気 | 動脈の血流が悪くなり、神経や組織に酸素が届かない | 手足(とくに足) | 冷え、しびれ、違和感。歩くと悪化し、休むと楽になることもある |
| 自己免疫疾患(ギラン・バレー症候群など) | 免疫が誤って神経を攻撃し、炎症・障害が起こる | 手足(左右対称に進行) | 急速なしびれ、筋力低下。重い場合は呼吸障害もある |
| その他 | 薬の副作用、腎臓病、肝臓病、膠原病など多岐にわたる | 個人差あり | 慢性的なしびれや違和感が持続し、全身疾患がある |
内臓の不調やホルモンの乱れでも、神経に異常が出て手足がしびれたりピリピリしたりする症状があります。たとえば、神経の働きに欠かせないビタミンB群などが不足すると、末梢神経の機能が低下し、しびれを感じることがあります。
ビタミンB群の不足や甲状腺ホルモンの異常は、末梢神経の働きが低下し、しびれを引き起こすことがあります。肝臓や腎臓の機能が低下すると体内に老廃物がたまり、神経に悪影響を及ぼすため、早期発見が重要です。
脳神経系の症状
| 病名・原因 | 原因のしくみ | 主に症状が出やすい部位 | 症状の特徴・例 |
|---|---|---|---|
| 脳卒中(脳梗塞・脳出血) | 脳の血管が詰まったり破れたりして脳細胞が損傷する | 片側の手足、顔、視覚、言語 | 片側のしびれ・麻痺、ろれつが回らない、急な視力低下など。突然起こる |
| 一過性脳虚血発作(TIA) | 一時的に脳への血流が低下する | 片側の手足や顔、視覚、言語 | 脳卒中と似た症状が一時的に出現。通常は24時間以内に回復 |
| 脳腫瘍 | 脳内にできた腫瘍が周囲の脳を圧迫する | 手足、視覚、言語、中枢神経機能全般 | 徐々に進行するしびれや麻痺、頭痛、吐き気、視野異常などがみられる |
| その他の脳神経系疾患 | 神経への炎症や損傷、脱髄など | 手足・感覚神経・運動神経 | 多発性硬化症、脊髄損傷、重度の末梢神経障害などでしびれや運動障害が出ることがある |
(文献2)
脳や脊髄といった中枢神経に異常がでると、手足の感覚に大きく影響します。具体的には、脳卒中や脊髄の病気では、突然のしびれや力が入らないといった症状が起こることがあります。
脳神経にかかわるしびれは、命に関わることもある重大な病気のサインです。脳神経の症状は進行がゆっくりな病もあり、違和感が徐々に広がります。
年齢を重ねるにつれてリスクが高まるため、違和感を放置せず、早めに医療機関を受診しましょう。
近年の治療では、脳梗塞をはじめとする脳卒中によって傷ついた神経を治療し、しびれを根本的に改善できる可能性がある「再生医療」が注目されています。
当院リペアセルクリニックでは、手足のしびれに対する再生医療について無料カウンセリングを実施中のため、お気軽にご相談ください。
糖尿病の症状
| 糖尿病に関する項目 | 内容 |
|---|---|
| 発症のメカニズム | 高血糖状態が長期間続くことで、神経や血管が損傷し、とくに末梢神経が障害される(糖尿病性神経障害) |
| 手足に症状が出やすい理由 | 手足は血流が届きにくいため、糖尿病の影響を受けやすい |
| 主な自覚症状 | 足の裏や指先から始まる左右対称のしびれ、ピリピリ感、感覚の鈍さが現れる |
| 症状の進行パターン | 初期は軽い違和感やしびれだが、放置すると神経障害が進行し、歩行障害や日常生活の支障につながる |
| その他にみられる影響 | 感覚が鈍くなることで、ケガや火傷に気づきにくくなる |
(文献3)
糖尿病は、血糖値が高い状態が続くことで神経が傷つきやすくなり、しびれやピリピリ感が出やすくなります。足先から始まり、徐々に広がるのが特徴です。
症状の初期段階では、軽い違和感にとどまっていても感覚が徐々に鈍くなり、ケガや感染症に気づきにくくなります。糖尿病は生活習慣病であり、発見が遅れると手足の壊死や失明を引き起こす恐れがあります。
糖尿病とすでに診断されている方は、手足のしびれに対して、とくに注意が必要です。
手足のしびれとピリピリ感の治し方(治療法)
| 治療法 | 内容 | 治療の対象となりやすい状態 | 期待される効 | 補足・注意点 |
|---|---|---|---|---|
| 薬物療法 | 薬剤(飲み薬・貼り薬など)で症状を和らげる | 初期症状、違和感、血行不良など | 違和感の軽減・しびれ軽減、血行促進 | 医師の指示に従い服用し、副作用に注意する |
| 理学療法 | 運動・温熱・電気刺激などで身体の機能を改善する | 神経圧迫、血行不良、筋肉・関節の問題 | 血行促進、緊張緩和、圧迫軽減 | 医師の指導のもと行い、自己判断はしないようにする |
| 神経ブロック | 神経の近くに注射し、痛みや興奮を抑える | 強い違和感、原因神経が特定できる場合 | 強い違和感を素早く軽減する | 効果は一時的なこともあるため、医師と要相談 |
| 手術療法 | 手術で神経圧迫の原因を取り除く | 他の治療で改善しない、原因が明らかな重症の場合 | 神経圧迫の根本的改善 | 身体への負担・リスクがあるため、医師と要相談 |
| 再生医療 | 自身の細胞などで神経の修復・再生を促す | 手術で起こりうる後遺症などを避けたい場合 | 損傷した神経機能の回復 | 再生医療を取り扱っている医療機関が限られている |
手足のしびれとピリピリ感じる症状は正しい治療法で改善できます。手足のしびれを感じた際は、早期発見と正しい治療の継続が大切です。
手足のしびれとピリピリ感の治療法は以下の5つです。
- 薬物療法
- 理学療法
- 神経ブロック
- 手術療法
- 再生医療
治療法について解説します。
薬物療法
| 薬剤の種類 | 主な目的 | 特徴・処方例 |
|---|---|---|
| 神経修復薬 | 損傷した末梢神経の修復を促進し、神経機能を改善する | 主にビタミンB群(B1、B6、B12など)が処方される。神経の栄養補給に役立つ |
| 神経痛治療薬 | 過敏になった神経の興奮を抑え、違和感やピリピリ感を緩和する | 抗けいれん薬(プレガバリンなど)や抗うつ薬(デュロキセチンなど)を使用する |
| 血流改善薬 | 血管を広げて血流を改善し、神経への酸素・栄養供給を助ける | プロスタグランジン製剤などが用いられる。とくに血行不良が原因の場合に有効 |
| 漢方薬 | 体全体のバランスを整え、血流や神経の働きを調整する | 体質や症状に応じて処方される(例:当帰芍薬散、八味地黄丸など) |
薬物療法は、しびれやピリピリ感の原因や症状に応じて、薬剤が用いられます。原因によって処方内容が異なるため、自己判断ではなく医師の指示に従いましょう。
薬剤によっては副作用が生じることもあるため、服用中は定期的な診察を行いながら処方します。
理学療法
| 療法分類 | 主な内容 | 期待される効果 |
|---|---|---|
| 運動療法 | ストレッチ、筋力トレーニング、軽い有酸素運動など | 筋肉の柔軟性向上、血行促進、筋力アップ、神経への負担軽減 |
| 物理療法 | 温める、電気をあてる、マッサージするなど | 血行改善、違和感の緩和、筋肉の緊張緩和、筋力改善 |
| 日常生活動作(ADL)指導 | 正しい体の使い方・姿勢の指導、杖や装具など福祉用具の活用 | 神経への負担軽減、日常生活動作の改善 |
理学療法では、リハビリやストレッチ、電気治療などを通じて神経や筋肉の機能を回復させる治療法です。筋肉のこわばりなどが原因で神経が圧迫されている場合に有効です。
理学療法を実施する場合は、自己判断ではなく、医師の指導のもと無理のない範囲で行いましょう。
神経ブロック
| ブロックの種類 | 注射する箇所 | 主な対象・効果 |
|---|---|---|
| 末梢神経ブロック | 手足など、原因となる神経の近く | 特定の神経の圧迫によるしびれ・違和感の軽減 |
| 硬膜外ブロック | 背骨の中、脊髄神経の周辺 | 腰のヘルニアなど、脊髄神経の圧迫によるしびれ・違和感の軽減 |
| 星状神経節ブロック | 首の付け根あたり | 血行不良が原因と考えられるしびれ・違和感の軽減 |
(文献4)
神経に局所麻酔薬などを注射し、神経の興奮を一時的に止める治療法です。強いしびれやピリピリ感が長引いている場合や、薬が効きにくいときに神経ブロック療法が選ばれます。
神経からの異常な信号の伝達を一時的に遮断し、症状を和らげるのが目的です。症状を抑えるだけでなく、血行を改善させる効果も期待できます。
注射する場所や薬の種類は、原因や症状の部位によって異なります。神経ブロック注射は注射箇所に傷や感染の症状がある場合、注射ができません。神経ブロック注射を検討する際は、該当箇所に注射が可能かどうかを医師に確認しましょう。
手術療法
| 手術の種類 | 主な目的・内容 | 対象となる状態 |
|---|---|---|
| 神経剥離術 | 神経への圧迫を取り除く | 手根管症候群、肘部管症候群など、神経が締め付けられている状態 |
| 脊椎手術 | 脊髄(神経の束)への圧迫を取り除く | 椎間板ヘルニア、脊柱管狭窄症など、背骨で神経が圧迫されている状態 |
| 神経修復術 | 損傷した神経を修復する(つなぐなど) | 事故や怪我などで神経が切れたり、傷ついたりしている場合 |
薬剤やリハビリなどの保存療法で効果が不十分な場合や、検査で神経の圧迫がはっきりしている場合、手術が選択肢になります。
たとえば椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症では、神経を圧迫している椎間板や骨を取り除く手術が必要です。
手根管症候群では、神経の通り道を広げるために、靭帯を切開する手術が行われることがあります。手術には種類ごとのメリットやリスクがあるため、医師の説明をよく聞き、検討した上で治療方針を決めることが大切です。
再生医療
再生医療は、患者さまの細胞や血液を用いて、しびれや痛みの原因となっている損傷した神経の再生・修復を促す治療法です。
患者さま自身の細胞を使うため、アレルギー反応や拒絶反応などの副作用リスクが少なく、体への負担が抑えられる点が特徴です。
ただし、現時点では、対応している医療機関が限られているため、再生医療での治療を検討される方は、取り扱いのある病院への受診が必要です。
以下のような症状やお悩みがある方は、ぜひ再生医療についてご検討ください。
- 手足のしびれが1週間以上続いている
- しびれが徐々に強くなっている、または範囲が広がっている
- 日常生活に影響が出るほど悪化する前に早く治したい
>>再生医療専門の「リペアセルクリニック」に無料相談する
当院リペアセルクリニックでは、手足のしびれに対する再生医療について無料カウンセリングを実施中のため、お気軽にご相談ください。
以下の記事では、当院「リペアセルクリニック」の再生医療について詳しく解説しています。
手足のしびれとピリピリ感は脳卒中の可能性あり!
脳卒中は進行すると、運動障害、感覚障害、言語障害、高次脳機能障害などの後遺症が出る恐れがあります。
脳卒中の危険性がある初期症状は以下の7つです。
- 片側の手足や顔にしびれ・力が入らない
- ろれつが回らない・言葉が出にくい
- 激しい頭痛を伴う
- めまい・ふらつき・歩行困難などが頻繁に起こる
- ものが二重に見える
- 意識障害を引き起こしている
- 排泄のコントロールができない
脳卒中の可能性を示す初期症状を解説します。
以下の記事では、脳卒中の前兆や見逃してはいけないサインを詳しく解説しています。
片側の手足や顔にしびれ・力が入らない
片側の手足や顔だけにしびれが出たり、力が入りにくくなったりする場合は、脳の血管に異常が起きているサインです。
突然、力の入らない症状が現れた場合、すぐに救急車を呼ぶもしくは、すぐに医療機関を受診しましょう。
脳卒中の発見が遅れるほど、後遺症のリスクが高まるため、すぐに行動に移すことが重要です。
ろれつが回らない・言葉が出にくい
話そうとしてもうまく言葉が出なかったり、ろれつが回らなくなったりするのも、脳卒中の可能性があるサインです。
本人はいつも通り話しているつもりでいるため、自身では気づきにくく、周囲が最初に異変を察知することも少なくありません。
急に会話の意味がわからなくなったり、相手とのやりとりがうまくかみ合わなくなったり変化が見られた場合は、脳や神経の異常が疑われることもあり、注意が必要です。
激しい頭痛を伴う
これまでに感じたことのないような突然の激しい頭痛がある場合も、脳内の出血や血管のトラブルが疑われます。
とくにしびれやピリピリ感と同時に起こる場合は、ただの偏頭痛では済まない可能性があります。脳卒中の中でも、くも膜下出血など重大な症状のケースもあるため、違和感があれば、すぐに医療機関を受診しましょう。
めまい・ふらつき・歩行困難などが頻繁に起こる
強いめまいや、体がふらついてまっすぐ歩けない、立っていられないといった症状も、脳卒中の可能性があります。
激しい回転性のめまいやふらつき、物が二重に見えるなどの症状が急に現れた場合は、脳卒中の可能性があります。しびれを伴うときはとくに注意が必要です。
ものが二重に見える
視界が急にぼやけたり、ものが二重に見えたりするのも、脳の機能に異常が疑われる症状です。
突然、片方の眼球が思うように動かせなくなったり、左右の目の焦点が合わなくなったりすることで、物がダブって見えることがあります。
急に物が二重に見えるようになった場合は、単なる目の疲れなどと自己判断せず、医療機関を受診する必要があります。
意識障害を引き起こしている
しびれやピリピリ感があるだけでなく、意識がもうろうとする、呼びかけに反応しにくいといった変化が見られる場合は、脳卒中の症状が疑われます。
呼びかけに対して反応がなかったり、傾眠(眠り込んでしまい、起こしてもすぐにまた眠ってしまう)だったりが頻繁に起こる場合は、非常に危険な状態です。
家族や周囲にいる方が異変に気づいた場合は、本人が平静を装っていても、迷わず救急車を呼ぶことが重要です。
排泄のコントロールができない
突然、尿意や便意を感じずに漏らしてしまう(失禁)、あるいは逆に尿や便が出せなくなるといった排泄のコントロールができない症状も脳卒中の可能性があります。
脳卒中の症状によって、排泄をコントロールする脳の機能が働かなくなり、引き起こされます。
しびれやピリピリ感と同時に現れる場合は、症状が進行しており、危険な状態です。すぐに医療機関を受診する必要があります。
手足のしびれ・ピリピリ感は放置せず医療機関へ相談を
手足のしびれ・ピリピリ感がある場合は、症状が軽度に感じられても重大な疾患が隠れている可能性があるため、放置せずに医療機関を受診しましょう。
症状が進行すると後遺症が残ったり、重症化して治療の選択肢が限られたりするケースがあります。
症状が悪化して日常生活に影響が出る前に治すためにも、手足のしびれを根本的に治療できる「再生医療」をご検討ください。
\しびれの原因である神経を治療する「再生医療」とは/
再生医療は、患者さまの細胞や血液を用いて自然治癒力を高めることで、しびれや痛みの原因となっている損傷した神経の再生・修復を促す治療法です。
【こんな方は再生医療をご検討ください】
- 手足のしびれが1週間以上続いている
- しびれが徐々に強くなっている、または範囲が広がっている
- 日常生活に影響が出るほど悪化する前に早く治したい
>>再生医療専門の「リペアセルクリニック」に無料相談する
当院リペアセルクリニックでは、手足のしびれに対する再生医療について無料カウンセリングを実施中のため、お気軽にご相談ください。
手足のしびれ・ピリピリ感についてよくある質問
最後に、手足のしびれ・ピリピリ感についてよくある質問に回答していきます。
以下でそれぞれの内容について詳しく見ていきましょう。
手足のしびれ・ピリピリ感を予防のために気をつけることはありますか?
手足のしびれ・ピリピリ感を予防するには、適度な運動やバランスの良い食事、十分な睡眠、ストレスの軽減が大切です。
姿勢に気をつけ、体を冷やさないよう心がけましょう。生活習慣病の管理や禁煙・節酒も予防に役立ちます。
手足のしびれ・ピリピリ感は何科を受診すべき?
症状によって異なりますが、まずは内科や神経内科の受診をおすすめします。
何科を受診すれば良いのか悩まれている方は、当院「リペアセルクリニック」へ「メール相談」もしくは「オンラインカウンセリング」にて、お気軽にお問い合わせください。
参考資料
Mark Freedman, et al.(2023).Numbness.MSD MANUAL Professional Version
https://www.msdmanuals.com(最終アクセス:2025年4月11日)
日本神経学会「脳神経内科の主な病気」一般社団法人 日本神経学会
https://www.neurology-jp.org/public/disease/shibire_detail.html(最終アクセス:2025年4月11日)
一般社団法人 日本臨床内科医会「手足のしびれ・痛み」日本臨床内科医会
https://www.japha.jp/general/byoki/numbness.html(最終アクセス:2025年4月11日)
「激しい両足痛を伴う糖尿病性神経障害に対し腰部持続硬膜外ブロックが著効した1症例」
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsdt1994/30/11/30_11_1315/_pdf(最終アクセス:2025年4月11日)