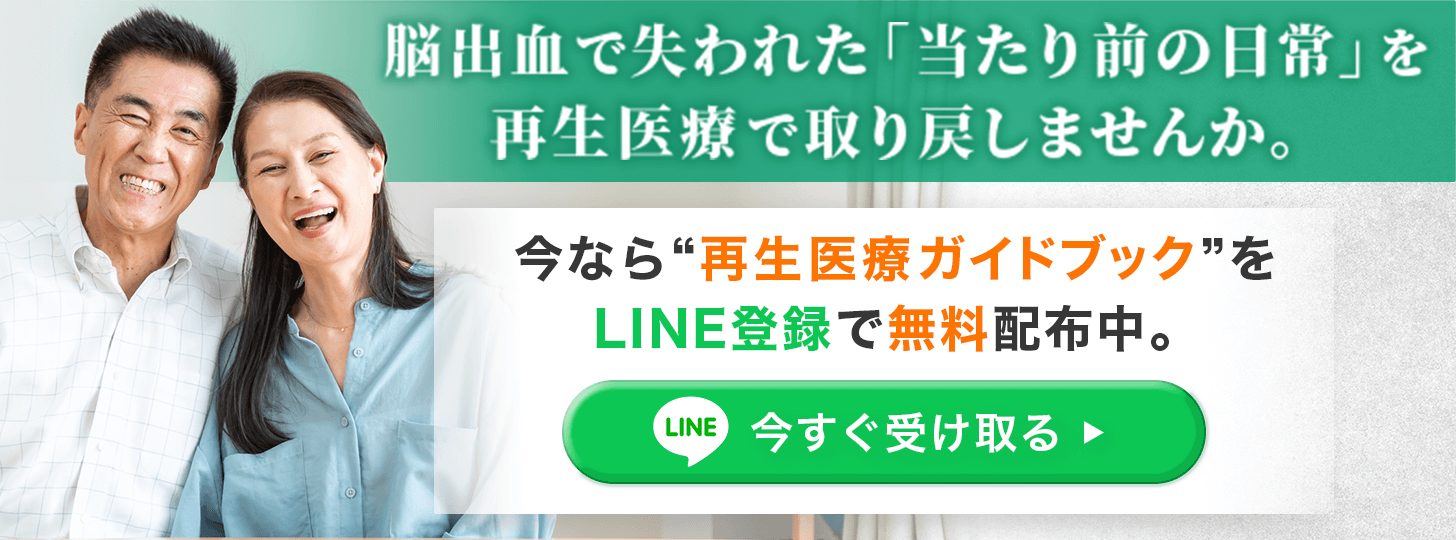- 脳卒中
- 頭部
- 脳出血
体幹失調とは?ふらつきの原因や効果的なリハビリについて解説【医師監修】
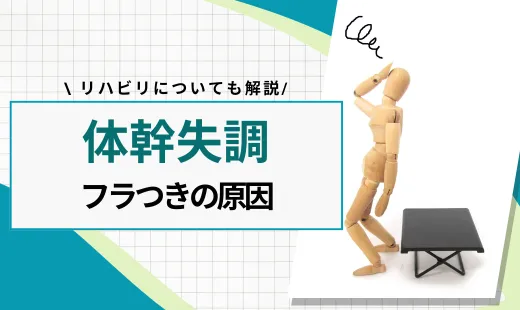
脳卒中や脳出血の後遺症でふらふらする状態が続いている方は「体幹失調」かもしれません。
体幹失調とは、脳の障害により胴体(体幹)のバランスがうまく取れない状態です。ふらつきが続くと、転倒のリスクもあるため不安ですよね。
体幹失調は適切なリハビリ・治療を行うことで体幹の筋力やバランス感覚が改善され、ふらつきの緩和が期待できます。
本記事では、体幹失調の原因や効果的なリハビリについて解説します。体幹失調でお悩みの方は、本記事を参考に、体幹失調を改善する方法を実践してみてください。
また、当院「リペアセルクリニック」では再生医療による脳卒中の後遺症治療も行っております。メールやオンラインでの無料カウンセリングも実施しておりますので、気になる方はお気軽にご連絡ください。
目次
体幹失調とは胴体のバランスが取れない状態
体幹失調は、運動失調の一種です。運動失調は「脳と筋肉の連携がうまくできていないため、体のバランスが取れずスムーズな動作が難しい状態」です。(文献1)
その中でも体幹失調は「胴体」の運動失調として知られており、胴体のバランスがうまく取れない状態です。歩き方が不自然になり、転びやすくなる可能性もあるでしょう。
体幹失調では、以下のような歩き方の特徴が見られます。
- 足を広く開いて歩く
- 手足の動きがバラバラである
- 酔っぱらっているような歩き方をする
体幹失調の症状が強いと、座っているときも胴体がぐらぐら揺れるケースもあります。
脳幹梗塞で体幹失調が起こるメカニズム
脳の病気の一つである「脳幹梗塞(のうかんこうそく)」は、体幹失調を引き起こす原因となることがあります。
脳幹梗塞とは、脳と脊髄をつなぐ「脳幹」の血流がふさがれる脳梗塞の一種です。
脳幹は以下3点の重要な役割を担っています。(文献2)
- 脳と体の信号をつなげる
- 心臓や呼吸など、生命維持に必要な活動をコントロールする
- 動作のための指令を体に送る
脳幹梗塞が起こると、体のバランス感覚をつかさどる小脳や前庭迷路との連絡通路も障害されます。その結果、体幹失調の症状があらわれてふらつきやすくなるのです。
脳幹梗塞と似たような病気で「脳幹出血」があります。脳幹出血について詳しく知りたい方は下記のコラムを参考にしてください。
体幹失調のリスクがあるそのほかの脳障害
脳幹梗塞以外には、以下の脳の部位の障害により体幹失調があらわれる可能性が考えられます。
- 小脳
- 前庭迷路
- 脊髄
- 大脳
本章が体幹失調の原因への理解が深まり、脳の病気の早期発見や適切な対応に役立てられれば幸いです。
バランスの維持に関わる「小脳」の障害
動作を行う際に必要な関節・筋肉などを調整して活動する「協調運動」を担う小脳が障害されると、体幹失調があらわれる可能性があります。
小脳は、運動のコントロールやバランスの維持をする脳の部位です。さまざまな筋肉を連携させてスムーズな動作をするためには小脳の活動が欠かせません。
そのため小脳に障害が起こると、体幹失調のようにバランスが取れなくなったり、手足の細かい動きが不自然になったりする可能性が考えられるでしょう。
バランス感覚をつかさどる「前庭迷路」の障害
前庭迷路は内耳に位置しており、バランス感覚をつかさどっています。
前庭迷路が正常に働き、平衡バランスや空間認識(物体の位置や距離・形・大きさなどを立体的に認識する能力)を保っているのです。
しかし、前庭迷路が障害されると前庭迷路やそこから情報を伝える神経にダメージを受けます。そのため、体幹失調や物体の距離感がうまくつかめなくなる症状が目立つようになります。
反射的動作に関わる「脊髄」の障害
脊髄は以下の役割を果たしています。
- 体を動かすための動作をするよう脳から筋肉に指令する
- 熱いものに触ると手を引っ込めるような「反射的動作」の指令を体に送る
脊髄に障害が起こると、筋肉の伸び縮みの具合や関節の状態についての感覚(深部感覚)が障害されます。その結果、自分の筋肉や関節の状態がうまく把握できず、体幹失調のようなふらつきが起こるのです。
運動の計画に関わる「大脳」の障害
大脳の一部である「前頭葉」は、運動の計画や運動の指令を出す働きをします。目的に向かって歩く、ご飯を食べるなど日常的に行っている動作も無意識で順番通りに行っている方が多いでしょう。これらは前頭葉で情報を正確に処理して行われています。
前頭葉が障害されると、運動の計画や実行がうまくいかないため、体幹失調のような歩行困難や手足の動きが不自然になる症状があらわれるのです。
大脳は小脳とともに協調運動に関わっているため、小脳の障害と症状が類似しています。
体幹失調の改善におすすめの運動4選【リハビリが重要】
病院による体幹失調の治療は、リハビリが重要です。実際には以下のようなリハビリ方法が行われます。
- フレンケル運動
- 運動学習
- 重り荷運動
- 弾性緊縛帯
本章を参考に、積極的にリハビリに取り組んでみてください。
当院「リペアセルクリニック」では、人体に元々ある幹細胞を活用した脳卒中・脳梗塞の後遺症の治療が可能です。詳しく知りたい方は、下記のリンクをご覧ください。
フレンケル運動
フレンケル運動とは、運動失調の方が体の動きや位置を把握する感覚や、協調運動が再びできるようになるリハビリ方法です。(文献3)たとえば、以下のようなフレンケル運動があります。
| 姿勢 | 方法 |
|---|---|
| 座った状態 |
|
| 横になった状態 |
|
フレンケル体操では、無理のない範囲での段階的な難易度調整が重要です。初めは簡単な動作から始め、徐々に複雑な運動へと移行します。
運動学習
運動学習とは、運動の動作をいくつかの工程に分けて繰り返すリハビリ方法です。運動学習は、主に以下の3段階に分けて実践されます。
1.認知段階:一連の運動を行うためにはどのような動作をどの手順で行う必要があるのかを考える
2.連合段階:認知段階で学んだ運動を試行錯誤しながら行い、自然な動作を目指す
3.自動化段階:意識しなくても一連の運動が自然とできるようになる
何度も同じ動作を繰り返し、動きが上手になる訓練をする目的があります。
重り荷運動
重り荷運動は、手足に重りをつけて負荷をかけるリハビリ方法です。手足に負荷をかけると体幹の筋肉が鍛えられて安定し、体幹失調の症状を緩和する目的があります。
最初は軽い重りから始め、個人の症状に応じて徐々に重さを上げていくと、無理をせず体幹の筋肉トレーニングができるでしょう。
また、病院によっては靴の中に重りが含まれている装具を活用している場合もあります。(文献4)
弾性緊縛帯
弾弾性緊縛帯(だんせいきんばくたい)とは、ゴムのように伸縮性がある包帯です。
体幹や手足の付け根部分に適度な圧迫感を感じる程度に弾性緊縛帯を巻いて使用します。個人差はありますが、弾性緊縛帯を用いてリハビリすると、過度な動きを抑えながら体幹の安定性の向上が期待できるでしょう。
弾性緊縛帯を用いたリハビリにより小脳性運動失調症が改善した報告もあります。(文献5)
体幹失調に効果的なトレーニング3選【自宅でできる】
体幹失調のトレーニングは、自宅で取り組めるものもあります。おすすめのトレーニング方法は、以下の3つです。
- 寝ながら行う「ブリッジ運動」
- 立ちながら行う「ひざの屈伸運動」
- 座りながら行う「ゆらゆら運動」
いずれも手軽にできるトレーニング方法です。無理のない範囲で取り組んでみてください。
寝ながら行う「ブリッジ運動」
ブリッジ運動は、名前の通り橋の形になって体幹を鍛えるトレーニング方法です。実際には、下記の手順で行います。
1.床で仰向けになる
2.ひざを曲げる
3.太ももと股関節が一直線になる程度に腰を上げる
4.そのまま数秒程度キープする
5.ゆっくり腰を床に降ろす
実際に体幹の安定性やバランス感覚が改善された報告もあります。(文献6)強引にブリッジ運動を行うと腰を痛める原因になるため、無理のない範囲で行いましょう。
立ちながら行う「ひざの屈伸運動」
ひざの屈伸運動も、体幹の安定性の向上に効果的であるとの報告があります。(文献6)実際には、以下の手順で行いましょう。
1.立った状態のまま、手すりや壁や重たい家具などに手をかける
2.上半身は背筋を伸ばした状態で保ったまま、ひざを45度くらいに曲げる
3.2.の状態を5秒前後キープする
転倒する可能性があるため、手すりのような手をつかめる場所で行うようにしましょう。また、立った状態でもふらつきを感じる場合は、ひざの屈伸運動を控えることをおすすめします。
座って行う「ゆらゆら運動」
足に障害があり、まっすぐ立つ姿勢が難しい方は座ってできる「ゆらゆら運動」がおすすめです。
「ゆらゆら運動」は以下の手順で行います。事前にタオルを用意しましょう。
1.巻いたタオルをお尻の下に敷いて座る
2.背筋は伸ばしたままお尻の重心を左右に交互に移動させ、ゆらゆらさせる
自宅にいるときの隙間時間を活用し、ゆらゆら運動を実践してみてください。
脳梗塞の後遺症を改善するリハビリ方法について詳しく知りたい方は、下記のコラムを参考にしてください。
まとめ|体幹失調を改善するために定期的なリハビリを行いましょう
体幹失調とは、脳梗塞や脳出血などの障害により、胴体(体幹)のバランスがうまく取れない状態を指します。
体幹失調は日々のリハビリやトレーニングで症状の改善が期待できます。脳の病気の後遺症でふらつきや歩き方が気になる方は、積極的に実践してみてください。
当院「リペアセルクリニック」では、再生医療による治療を行っております。メールやオンラインでの無料カウンセリングも実施しておりますので、気になる方はお気軽にご連絡ください。
\無料オンライン診断実施中!/
体幹失調についてよくある質問
体幹失調と麻痺の違いはなんですか?
麻痺とは、脳や神経のダメージにより体が自分の意志通りに動かせない状態です。筋肉がまったく動かせない、または動かすときに力が入らない症状が麻痺に該当します。
一方の体幹失調は、脳と筋肉の連携がうまくいっていない状態です。麻痺とは違い、筋肉自体は動かせます。ただし、筋肉をスムーズに動かせないため、歩くとふらつきが出たり、日常の動作がぎこちなくなったりします。
体幹が不安定だとどうなりますか?
体幹は体の中心にあり、頭や手足を除いた胴体の部分です。正しい姿勢を保ち、手足の動きを支える役割を果たしています。
体幹が不安定だと姿勢や手足の動きを支えきれず、バランスが取れなくなり歩行困難や転倒のリスクがあります。
そのため、体幹失調の場合は、体幹を鍛えるリハビリやトレーニングが重要となるのです。