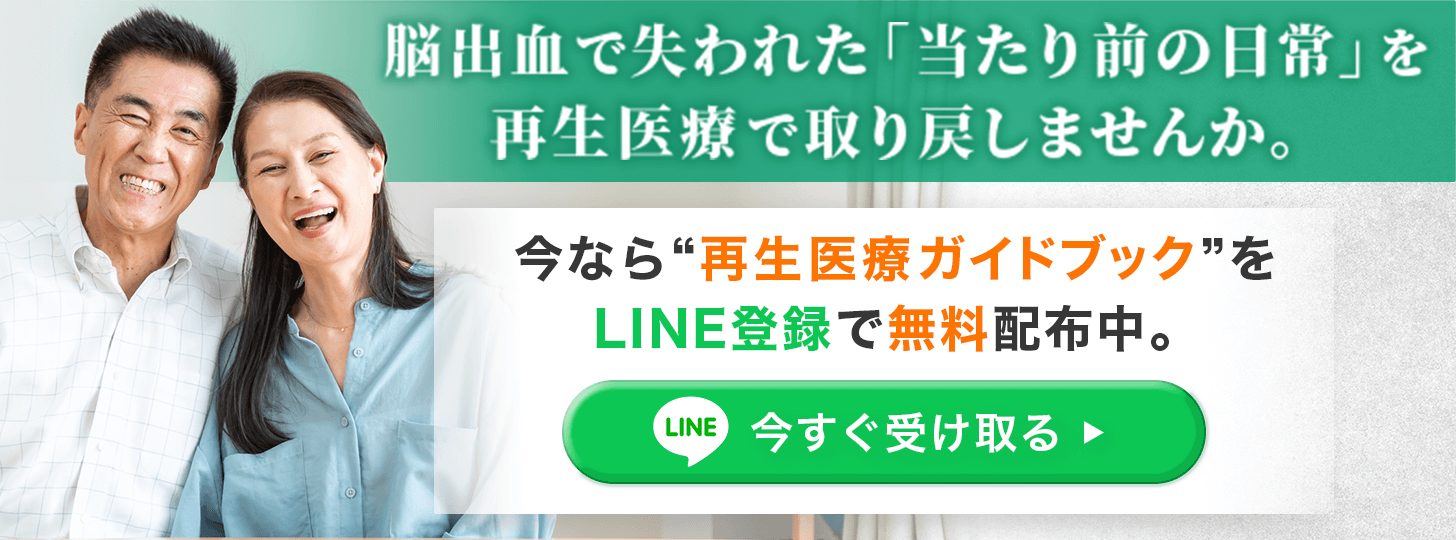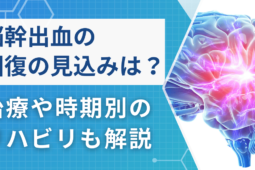- 頭部
- 脳卒中
- 脳出血
脳幹出血のリハビリプログラムを詳しく解説|早期アプローチが回復を左右する
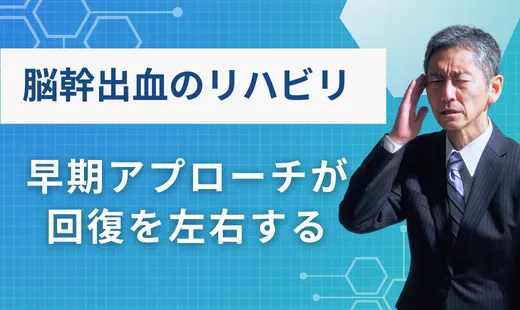
脳幹出血を発症すると、意識障害や四肢麻痺、嚥下障害など重い後遺症が残る可能性があります。
しかし、治療と併行したリハビリにより、機能回復や自立した生活への復帰が可能です。
本記事では、脳幹出血のリハビリの進め方(急性期・回復期・生活期)や、リハビリ期間の目安について紹介します。
脳幹出血後の早期リハビリアプローチが回復を左右するため、時期別のリハビリプログラムを理解し、効果的な機能回復を目指しましょう。
目次
脳幹出血とは?発症後にリハビリが必要な理由
脳幹出血とは、脳幹(脳の中心部)で起こる出血性疾患のことです。
脳幹は、呼吸や心拍、運動機能、嚥下などの生命維持に関わる重要な役割を果たしています。
脳幹出血を起こすと、重度の場合は意識障害、呼吸障害、四肢麻痺などをきたします。
軽度の出血でも、片麻痺や感覚障害、運動失調、嚥下障害や高次脳機能障害などの後遺症を残します。
看護が必要なくなっても、元の生活に戻るまでには長い時間が必要です。
少しでも後遺症を軽減し、寝たきり状態を防ぐために、発症後できるだけ早期からのリハビリテーションが重要となります。
早期リハビリは機能回復の可能性を高めます。
脳幹出血のリハビリの進め方【急性期・回復期・生活期】
脳幹出血のリハビリテーションの内容は、発症からの時期により変わってきます。
リハビリでは、
- 急性期
- 回復期
- 生活期(維持期)
という3つの時期に分けてプログラムを組みます。
脳幹出血の具体的なリハビリテーションを、3つのステージ別に見ていきましょう。
\無料オンライン診断実施中!/
急性期(発症直後〜1ヶ月)|早期リハビリが回復を左右する
急性期とは、脳幹出血が発症し、まだ状態が安定していない時期を指します。
発症から概ね2週間〜1ヶ月程度です。
急性期は、治療と並行してリハビリを進めていきます。
まず目指すのは、早い段階でベッドから離れる「早期離床」です。
脳幹出血をはじめとした脳卒中では、体の状態が安定していれば、発症後24〜48時間以内のリハビリ開始で回復が早まるとされています。
リハビリの初期段階では、
- 寝返りを打つ練習
- 体を起こして座る練習
- 立ち上がる、歩行の練習(可能であれば補助具を使用)
- 着替えや食事など日常生活動作(セルフケア)の訓練
といった基礎的な動作の回復を目指します。
また、脳幹出血の患者様は、嚥下障害(飲み込む力の低下)を伴うことが多いです。
肺炎予防のためにも、早くから嚥下機能の評価と口腔ケアを開始します。
一方で、重度の脳幹出血では、呼吸や血液循環の障害が生じる場合があります。
出血が広がり、髄液の流れに影響を及ぼす水頭症になることもあります。
このような状態では、早期離床が難しくなるため、ベッド上でできるリハビリを行います。
例えば、
- 関節が固まらないようにするための「関節可動域訓練」
- 筋肉が萎縮しないようにするための「他動運動」
などを行い、後の回復を促します。
回復期(1ヶ月〜6ヶ月)|本格的なリハビリで機能回復を目指す
急性期を脱し、体の状態が安定してくる回復期は、後遺症が完全に固定されていない時期です。
そのため、失われた機能の改善や、残っている機能を高める訓練をします。
多くの脳卒中の患者様は「回復期リハビリテーション病棟」に移ります。
リハビリを専門にしている病院や病棟です。
ここでは、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士などのリハビリ専門スタッフが多く在籍しています。
1日最大3時間のリハビリが可能で、施設によっては休日も含めて毎日リハビリを行っている病棟もあります。
脳幹出血による後遺症は人それぞれ異なるため、リハビリの内容も個別に調整されます。
急性期から徐々に始めていたリハビリを、回復期ではより本格的に実施し、患者様一人ひとりに合った詳細なリハビリプログラムを組んでいきます。
本章では一例を紹介します。
運動麻痺
筋肉や関節の動きを自分の意思通りに動かせるよう、繰り返し訓練します。
麻痺は3〜6ヶ月程で回復が止まってしまいます。
症状が固定した後でも、麻痺のない部分でカバーしたり、装具や杖などを利用したりして動く訓練も行なっていきます。
運動失調
筋肉同士の協調性が失われ、運動をスムーズに行えない状態を運動失調といいます。
運動失調のリハビリでは、例えば、目で確認しながら何度も動作の練習をします。
重りを使い、固有感覚(身体の位置や力の入れ具合を感じる感覚)を刺激して、運動のコントロールを行う訓練も行います。
一つの動作をいくつかに区切って行うことも効果的です。
嚥下障害
急性期に引き続き、嚥下障害へのリハビリも続けます。
どのくらいの固さのものが食べられるのか、一口量はどのくらいが適切かなど、詳細な評価を行います。
飲み込む力を強化する訓練をしながら、少しずつ食事の形態を調整していきます。
構音障害
呂律が回らない、声の大きさのコントロールがつかないなど、喋りづらさ(構音障害)を抱える方が多いです。
正しい発音の練習や、話すスピードを調整する訓練によって、コミュニケーションが取りやすいようにしていきます。
綿密なリハビリテーションを続けながら、自宅への退院、社会復帰に向けた支援も行なっていきます。
生活期(6ヶ月以降)|自宅でのリハビリ
生活期(維持期)とは、退院後に自宅での生活を継続しながら、リハビリを続けていく時期です。
身体機能の維持・向上を目指し、できる限り自立した生活が送れるように支援することが重要になります。
リハビリ方法の例
| 関節可動域訓練 |
関節の柔軟性を保つためのストレッチを行います。関節や筋肉の硬直を防ぎ、動きをスムーズにします。 |
| 筋力強化トレーニング | 自宅で安全に行える動作の中で筋力を強化します。立ち座りや踵上げなどが効果的です。 |
| バランストレーニング | 壁を持った状態でのスクワットや片脚立ちなど、バランス能力の改善を図るトレーニングです。転倒リスクの軽減が期待できます。 |
自宅以外にも、通所リハビリ(デイケア)や訪問リハビリなど、専門家の指導を受けることで、より効果的なリハビリが可能となります。
また、脳幹出血の最大のリスク要因は高血圧であり、血圧管理が再発予防につながります。
適度な運動習慣をつけることで、血圧を安定させ、再発リスクを減らす効果が期待できます。
脳幹出血を含む脳出血の再発予防策のひとつ「再生医療」
脳幹出血を含む脳出血は、一度発症すると再発リスクが高いとされています。
再発を防ぐためには、高血圧の管理や生活習慣の改善が基本ですが、近年では「再生医療」が新たな治療法として注目されています。
再生医療とは、患者様自身の幹細胞を活用し、損傷した神経細胞の修復や再生を促す治療法です。
脳幹出血を含む脳卒中の後遺症に対して再生医療が行われます。

脳卒中のお悩みに対する新しい治療法があります。
脳幹出血のリハビリについてよくあるQ&A
Q.脳幹出血はリハビリすれば回復見込みはある?
A.後遺症の程度によりますが、リハビリによって回復の可能性はあります。
脳幹出血のリハビリは急性期・回復期・生活期の各段階で適切に行うことで、機能回復の可能性が高くなります。
特に早期リハビリが重要とされ、症状の軽減や日常生活への復帰が期待されます。
脳幹出血の方の予後に関しては、以下のようなデータがあります。(文献)
良好な回復だった方:13人(6.1%)
中程度の障害:27人(12.7%)
重度の障害:27人(12.7%)
植物状態:23人(10.8%)
死亡:122人(57.5%)
死亡あるいは後遺症が残る方が多いですが、回復見込みもゼロではないことが分かります。
Q.どうして急性期と回復期で病院(病棟)が変わるのですか?
A.できれば同じところでリハビリを続けたいですよね。
しかし、場所が変わることにはきちんと理由があります。
発症直後に入院する「急性期病院(病棟)」の目的は、体の状態を落ち着かせることです。
リハビリのための時間や人手には制約があります。
治療がひと段落すれば、よりリハビリに特化した場所に移る方が良いのです。
次に急性期病棟に入院が必要な方にベッドをあけるためにも、状況が落ち着いてくれば行き先の調整を考え始めます。
Q.どのくらいの期間、入院が必要ですか?
A.麻痺などの回復が一定の段階に達し、日常生活に必要な動作ができるようになれば退院を検討します。
どこまでできるようになるかという目標は患者様毎に異なります。
ただし、回復期リハビリ病棟の入院は脳卒中の場合は最大で150日(高次脳機能障害がある場合は180日)までと決まっているため、これを超えることはありません。
Q.リハビリ中に気をつけるべきことは?
A.脳幹出血のリハビリでは、無理をせず、適切なペースで継続することが重要です。
リハビリの進め方には個人差があるため、焦って過度な負荷をかけないようにしましょう。
また、バランス能力の低下により転倒のリスクが高まるため、歩行補助具の活用や、リハビリ中の環境整備を行うことが大切です。
Q.家族ができるサポート方法とは?
A.リハビリの継続をサポートし、無理のない範囲で日常生活の手助けをすることが重要です。
具体的には、コミュニケーションをとりながら軽い運動を一緒にしたり、食事管理、再発予防のための健康管理などがあります。
また、患者様本人のモチベーションを維持できるよう、励ましやポジティブな声かけを意識しましょう。
リハビリは長期間に及ぶことが多いため、家族も無理をせず、介護サービスや専門家の力を借りることも大切です。
まとめ|脳幹出血のリハビリは継続と早期アプローチがカギ!
脳幹出血後の回復には、早期からのリハビリが重要です。
リハビリを継続することで、後遺症を軽減し、もとの生活に近い状態に戻ることを目指していきます。
回復には長い時間がかかることもありますが、焦らず、一歩ずつ進めることが大切です。
家族や医療チームと協力しながら、継続的にリハビリを行い、生活の質を向上させていきましょう。

脳卒中のお悩みに対する新しい治療法があります。
参考文献
日本脳卒中学会. 「日本脳卒中治療ガイドライン2021(2025年改訂版)」
https://www.jsts.gr.jp/img/guideline2021_kaitei2025_kaiteikoumoku.pdf
福岡 達之ほか. 「小脳失調を伴うdysarthriaと嚥下障害のリハビリテーション医療」 リハビリテーション医学, 2019年, 56(2), pp.105-109.
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjrmc/56/2/56_56.105/_pdf
Takeuchi Satoru ほか. 「Prognostic factors in patients with primary brainstem hemorrhage」 Clinical Neurology and Neurosurgery, 2013年, 115(6), pp.732-735.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22944466/