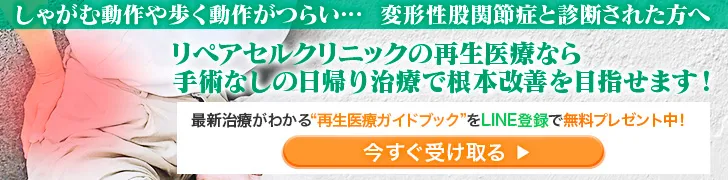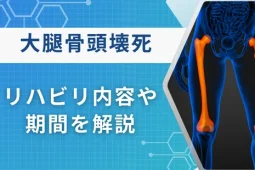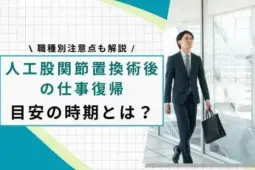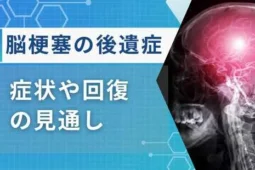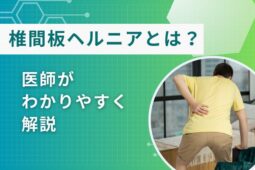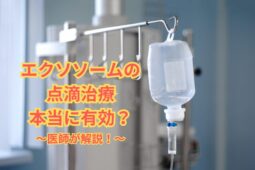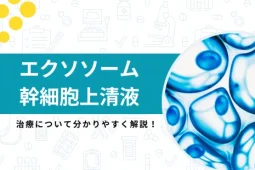- 幹細胞治療
- 大腿骨骨頭壊死
- 股関節
- 再生治療
大腿骨頭壊死の保存療法|病期分類や治療の進め方を解説

「大腿骨頭壊死(だいたいこっとうえし)」と診断され、先の見えない不安や股関節の痛みに悩んでいませんか?
とくに働き盛りの世代に多いこの病気は、今後の仕事や生活に大きな影響を与えかねません。(文献1)
「手術は避けたいけれど、何もしないで悪化するのは怖い」「保存療法とは言うけれど、具体的に何をすればいいの?」
この記事では、そんな疑問や不安に寄り添い、手術をせずに股関節の機能を温存する「保存療法」についてわかりやすく解説します。
なお、当院「リペアセルクリニック」の公式LINEでは大腿骨頭壊死の治療法の一つ、再生医療の情報提供と簡易オンライン診断を実施しております。
大腿骨頭壊死でお悩みの方は、ぜひ一度公式LINEにご登録いただき再生医療についてご確認ください。
目次
大腿骨頭壊死の保存療法とは
大腿骨頭壊死とは、股関節にある大腿骨頭が壊死してしまい潰れることで痛みを生じる疾患です。
一度壊死が起こってしまうと、壊死した骨組織そのものを元の状態に戻すことは極めて困難です。
発症原因は明確ではありませんが、大腿骨頭を栄養している血管が障害されることや、免疫を抑えるステロイドやアルコールが危険因子とされています。(文献2)
骨頭壊死の治療法は、保存療法と手術療法に大きく分けられます。
大腿骨頭壊死の保存療法とは、手術以外で股関節への負担を減らしながら、痛みや進行の様子を見ていく治療のことです。
壊死の範囲が小さい場合や、痛みなどの症状がほとんどないときには、まずこの方法が選ばれます。
日常生活では、股関節にかかる重さを減らす工夫として以下のことを意識します。
- 杖で体重を分散する
- 体重を大きく増やさない
- 長く歩き続けない、
- 重い荷物は持たない
- 痛みが強い時期は、無理に動かず休む
痛みや炎症に対しては、医師と相談のうえで鎮痛薬を使います。
ただし、これらの対処だけで骨のつぶれ(圧潰)の進行を強く止められるとは限りません。
圧潰が進みそうなタイプでは、骨頭の形を保つことを目的に、手術に切り替える時期を逃さないことが大切です。
大腿骨頭壊死の病期(ステージ)分類
保存療法の方針を決める上で重要なのが、壊死がどのくらい進行しているかを示す「病期(ステージ)」です。
国際的によく使われる「ARCO分類」では、MRIやX線(レントゲン)の画像所見から、Stage1~4までの4つのステージに分類します。
この分類は、病気の進行度や治療方針を決定するための重要な指標です。 (文献3)
ここでは、病期(ステージ)別に画像所見の特徴と主な症状について解説します。
Stage 1
|
MRIやX線(レントゲン) |
主な症状 |
|---|---|
|
|
X線ではまだ変化が見られず、MRIで初めて骨内部の壊死が確認される段階です。
痛みは軽度〜中等度で、長距離歩行や階段の上り下りなどに違和感を覚えることがあります。
Stage 2
|
MRIやX線(レントゲン) |
主な症状 |
|---|---|
|
|
骨内部の構造変化が進み、X線で骨密度の不均一や境界線が現れます。
この段階では骨頭の形はまだ保たれていますが、放置すると次の圧潰期に移行するリスクが高まります。
Stage 3A、3B
|
MRIやX線(レントゲン) |
主な症状 |
|---|---|
|
|
骨頭が部分的につぶれ(圧潰)、関節の形が少しずつ変わっていきます。
X線でも明確な扁平化が確認でき、歩行時の痛みが強くなることが多いです。
症状が続く場合や圧潰の進行が見られる場合は、骨切り術(骨頭の壊死した部分へかかる負荷を抑えるため、骨の一部を切って角度を変える手術)を専門医と検討します。
Stage 4
|
MRIやX線(レントゲン) |
主な症状 |
|---|---|
|
|
関節軟骨のすり減りや関節の変形が生じる時期とされ、骨頭のつぶれがさらに進み、股関節全体に変形が及びます。(文献4)
軟骨のすり減りによって骨同士が直接触れ合うようになり、強い痛みや可動域の制限が生じます。
【病期別】保存療法で「やるべきこと」「避けるべきこと」
大腿骨頭壊死の保存療法の目的は、骨頭の圧潰を防ぎ、痛みをコントロールすることです。
特に圧潰が起きていない、あるいは軽度なStage 1〜3Aが保存療法の主な対象となります。
Stage 1〜2 (圧潰前)
| やるべきこと |
避けるべきこと |
手術への切り替えを |
|---|---|---|
|
|
|
※免荷とは、杖などを使って患部への体重負担を減らすこと。
圧潰前は、骨頭の形が保たれており、早期の保存療法が有効とされます。
痛みや炎症がある患者様には、症状を緩和させるために、消炎鎮痛薬(内服薬や外用薬)を使用することもあります。
運動では、痛みが出ない範囲で関節可動域を維持し、股関節に体重をかけない方法で筋力維持に努めます。
股関節の負担が少ない運動として、エルゴメーター(自転車こぎ)や、横になった状態での足上げ、水中ウォーキングなどがあります。無理のない範囲で毎日運動を続けましょう。
また、アルコール摂取と喫煙にも注意が必要です。
アルコールの過剰摂取は骨の代謝や血流に悪影響を与え、骨密度の低下を招きます。喫煙は血管を収縮させ、骨への酸素・栄養供給を阻害します。
どちらも壊死の進行に関わる要因とされているため、控えましょう。
Stage 3A 〜4 (圧潰初期〜圧潰進行期)
| やるべきこと | 避けるべきこと |
手術への切り替えを |
|---|---|---|
|
|
|
この段階では、更なる圧潰を防ぐためにも体重管理を徹底します。ただし、痛みを我慢しての自己判断による運動は、かえって圧潰を進行させる危険性があるため避けてください。
骨頭の圧潰が始まっている場合や、保存療法でも症状の改善がみられない場合には、手術による治療へ移行する判断がなされます。
関節軟骨が残っており、関節の隙間が保たれている段階では、骨切り術が選択肢となります。
一方で、壊死の範囲が広い場合や圧潰が進行している場合には、人工関節置換術(股関節を人工関節に置き換える手術)が行われることがあります。
他、運動方法について詳しく知りたい方は、こちらの記事も合わせてご確認ください。
\無料相談受付中/
痛みを悪化させない日常生活のコツ
痛みを悪化させず、圧潰の進行を防ぐためには、日常生活での工夫が欠かせません。
| 日常生活の工夫 |
ポイント |
|---|---|
| 杖をつかう | 患肢と反対側で杖を持つと、痛みが軽減できます |
| 股関節を曲げる動作を避ける | 長距離を歩く、しゃがむ、階段昇降などの動作を避けます |
| 重い荷物を持つのを避ける | 患肢と反対側で荷物持つと、関節を保護できます |
| 生活様式を洋式に変更する |
床座りやふとん、和式トイレは避けます。 椅子やベッド、洋式トイレを使用しましょう。 |
| 高い椅子を使用 | 台所などでの立ち仕事では高い椅子を使用し、腰掛けることで股関節への負荷を減らすことができます |
これらの工夫を日常生活に取り入れることで、股関節への負担を軽減できます。ご自身の病期や症状に応じて、担当医と相談しながら実践してください。
再生医療という選択肢
大腿骨頭壊死の治療の選択肢の一つに、再生医療の選択肢もあります。
当院「リペアセルクリニック」では、大腿骨頭壊死に直接注射で幹細胞を届ける治療を行っております。患者様自身の幹細胞を採取・培養して用いるため、拒否反応のリスクが低い治療法です。
手術以外の治療法をお探しの方、人工関節にすることに抵抗がある方は、ぜひ当院へご相談ください。
当院では、検査結果や生活状況を踏まえ、再生医療を含む複数の選択肢を説明した上で治療計画をご提案いたします。
当院の大腿骨頭壊死に対する再生医療について詳しくは、以下の記事も合わせてご確認ください。
まとめ|痛みをコントロールしながら前向きな一歩を
大腿骨頭壊死の保存療法では、病期(Stage 1〜4)に応じた適切な対応が必要です。
圧潰前(Stage 1〜2)では、免荷や体重管理、股関節に負担をかけない運動により、圧潰の進行を防ぐことが目標となります。
圧潰初期以降(Stage 3A〜4)では、より厳格な免荷と体重管理を徹底し、保存療法で改善が見られない場合は、骨切り術や人工関節置換術などの手術療法への移行を検討します。
日常生活では、杖の使用、股関節を深く曲げる動作の回避、生活様式の洋式化などの工夫により、股関節への負担を軽減できます。また、アルコールと喫煙は壊死の進行に関わる要因とされているため、控えることが推奨されます。
保存療法は、ご自身の体の状態を正しく理解し、痛みをコントロールしながら、今後の治療方針を考えるための重要な期間です。
一人で抱え込まず、定期的な検診を受けながら専門医と相談し、ご自身に合った治療計画を立てていきましょう。
\無料オンライン診断実施中!/
大腿骨頭壊死の保存療法に関するよくある質問
保存療法で壊死は治りますか?
一度壊死した骨組織が保存療法で元通りになることはないといえるでしょう。
保存療法の目的は、壊死した部分が潰れてしまう「圧潰」を防ぎ、痛みをコントロールして、自分の関節をできるだけ長く温存することにあります。
自転車に乗っていいですか?
自転車の利用自体は可能ですが、転倒しないこと、そして転びそうになった際に無理に踏ん張らないことが前提になります。
走行するなら、平坦で人通りが少なく、接触の危険が少ない道を選びましょう。
一方で、坂道で立ちこぎが必要な場面や、人や車が多く衝突のリスクが高い場所では自転車の使用は控えた方がいいでしょう。
食生活で気をつけることはありますか?
食べ物の規制は特にありませんが、股関節の負担を減らす上で体重管理は非常に効果的です。
栄養バランスを考えた食事を意識しながら、適正体重を心がけましょう。
また、危険因子としてアルコール飲料は骨頭壊死の進行リスクを高めるといわれており、国際的な基準も定められています。過剰な摂取は避けてください。
参考文献
(文献1)
特発性大腿骨頭壊死症(指定難病71)|難病情報センター
(文献2)
Osteonecrosis of the Femoral Head: an Updated Review of ARCO on Pathogenesis, Staging and Treatment|PMC
(文献3)
Guidelines for clinical diagnosis and treatment of osteonecrosis of the femoral head in adults (2019 version)|PMC.
(文献4)
71 特発性大腿骨頭壊死症|厚生労働省