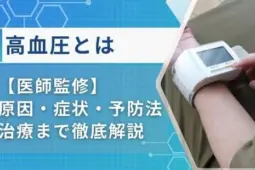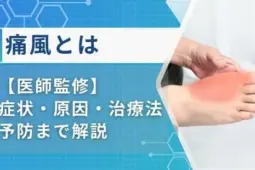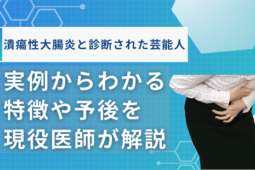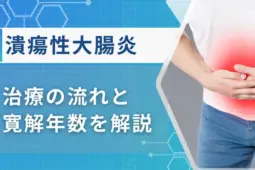- 内科疾患
- 内科疾患、その他
女性が高血圧になる原因は?更年期との関連性・対策を医師が解説!

40代、50代になってから急に血圧が高くなったのはなぜ?
血圧とホルモンバランスには関連はあるの?
このような悩みを持つ女性も多いのではないでしょうか。
高血圧は生活習慣病の一つとして広く知られていますが、女性の場合は更年期障害が原因のケースもあります。
女性ホルモンであるエストロゲンの減少により、血圧が下がりにくくなるためです。
本記事では、女性に多い高血圧の原因や、自分でできる対処法について解説します。
記事を最後まで読めば、女性由来の高血圧について正しい知識が身につくでしょう。
また、高血圧の改善について、専門科に相談したいという方はぜひ当院「リペアセルクリニック」の「メール相談」「オンラインカウンセリング」をご活用ください。
目次
40代・50代女性の高血圧は「更年期による女性ホルモン減少」が原因
更年期の変化によって生じる高血圧を「更年期高血圧」と呼びます。
高血圧を放置しておくと、心臓病や脳血管障害につながることもあります。
本章を参考に、なぜ更年期になると高血圧が起こるのかを理解し、きちんと対策をしましょう。
女性ホルモンの減少によって生じる更年期障害
女性ホルモンには、エストロゲンとプロゲステロンの2種類があります。更年期になると卵巣機能が低下し、それに伴い女性ホルモンも減少します。このうちエストロゲンの減少が、更年期障害の発症に大きく関わっていると考えられています。
更年期になると卵巣機能が低下し、それに伴い女性ホルモンも減少します。
ホルモンバランスを保てなくなったことに対して、脳がそれを補おうと必死に身体にさまざまな命令を送り、それが更年期症状として現れてしまうのです。
多岐にわたる更年期症状ですが、高血圧以外には以下のようなものが挙げられます。
- 血管運動に関わる症状(ほてり、のぼせ、発汗、動悸、息切れ、むくみなど)
- 精神症状(頭痛、不眠、不安感、イライラ、抑うつ、無気力など)
- 消化器症状(便秘、下痢、胃の不快感、胸焼け、吐き気など)
- 皮膚症状(かゆみ、湿疹など)
- 運動器に関わる症状(肩こり、腰痛、背中の痛み、関節痛など)
- そのほか(疲労感、排尿トラブル、不正出血など)
症状が軽度で済む人もいれば、日常生活に支障が出るくらい重い症状が出る人もいます。軽度の場合は更年期症状、症状が重くなると更年期障害となります。(文献1)
主にエストロゲンの減少が高血圧を招く
私たちの身体は、常に一定の血圧を保持できるよう機能しており、高くなりすぎず、低くなりすぎないように調整されています。
エストロゲンは、その調整因子の一つであり、血管を広げて血圧を下げる働きをしています。更年期による卵巣機能の低下によってエストロゲンが減少すると、血圧が下がりにくくなってしまうのです。
また、自律神経の乱れも更年期高血圧に大きく関わる因子です。
自律神経には、交感神経と副交感神経があります。活発な時や緊張状態の時には交感神経が優位となり、血管が収縮して血圧が上昇します。
逆に休んでいる時や就寝中は副交感神経が優位となり、血管は拡張して血圧が下がります。
このように血圧調整にとても大切な自律神経ですが、女性ホルモン低下に追いつけないことでパニックになった脳は、さまざまな命令を身体に送る中で、自律神経も乱してしまうのです。
自律神経の乱れは血圧変動のみならず、上記に述べたような精神症状や身体症状の原因にもなっています。
このようにエストロゲンの減少と自律神経の乱れは、本来私たちに備わっている血圧調整の歯車を狂わせ、結果的に更年期高血圧を引き起こすのです。
更年期の女性がやるべき高血圧の対策7選
今日からご自身で始められる、更年期高血圧の対策は以下の7つです。
- 血圧測定を習慣化する
- 塩分を控える
- 体重管理を行う
- 運動習慣を取り入れる
- 睡眠時間を十分に取る
- ストレスを溜めない
- イソフラボンを摂取する
本章では、各項目について解説します。
血圧測定を習慣化する
血圧は普段の状態と、高くなっているときの違いを探すことが大切です。
以下のポイントを意識して、血圧の測定を行いましょう。
- 血圧上昇が一時的なものなのか
- 血圧が高い状態がずっと続いているのか
- どのような時に高くなるのか
外出時は精神的・身体的・環境的因子が血圧に影響することも多いため、自宅での血圧測定を推奨します。
なお「高血圧治療ガイドライン2019」では、血圧測定は、手首型の機器よりも二の腕で測るタイプを勧めています。(文献2)
定期測定は起床時と就寝前の2回、そしてめまいや動悸など、上記の更年期症状が出た際にも血圧を測定し、血圧の推移とともにどのような状況で血圧が上がったのかを書き留めておくと良いでしょう。
自分の状況を把握するだけでなく、医師からの診察の際にも役立ちます。
塩分を控える
塩分過多は高血圧の原因として最も多いとされています。
塩分を多く摂ると、血液中の塩分濃度が上がるため、それを薄めようと血管内の水分が増えます。そのため、血管を押し拡げる力が強くなり、血圧が上がってしまうのです。
近年はとくに、インスタント・冷凍食品の改良化や食事のデリバリー事業などが進み、便利な時代となりました。しかし、既製品や外食は塩分量とカロリーが高くなる傾向にあります。減塩調味料の使用や野菜多めの食事を心がけるようにしましょう。
体重管理を行う
血圧の管理には、体重管理も大切です。
肥満の人は食べ過ぎによるインスリンの出過ぎから、交感神経が刺激されカテコールアミンという物質が分泌され、血圧を上げてしまいます。さらに、脂肪細胞が肥大してアンギオテンシノーゲンという物質が出ることでも血圧上昇を引き起こします。
食事や運動を組み合わせてカロリーを調整し、BMI25以下を目指すようにしましょう。
また、食べ過ぎで塩分を過剰摂取してしまい、血圧上昇につながっている可能性もあります。日頃から減塩を意識して食事を摂りましょう。
運動習慣を取り入れる
仕事や家事に追われて、なかなか運動の時間をとるのが難しい方もいらっしゃいます。
1日の中で、少し早起きしてウォーキングをしてみる、10分のエクササイズ動画を真似してみる、休日にスポーツセンターに行ってみる、一駅分歩いてみる、など小さなことで構いません。自分のできる範囲内で何か始めてみましょう。運動するとイライラした気持ちも収まり、身も心もスッキリします。
睡眠時間を十分に取る
睡眠不足は交感神経を刺激し、高血圧を引き起こします。
しかし更年期障害の一つに不眠もあり、夜なかなか寝付けない人もいるかと思います。
具体的な方法は以下の通りです。
- 就寝時間の2時間前までに食事を摂り終える
- 布団に入ったらスマートフォンはいじらない
- 夜にカフェインやお酒は控える
- リラックス効果のある香りや音楽をつける
ここまでの対策は自身でできることですが、やはり重症化予防の鍵は早期受診となります。
高血圧を適切に治療しなかった場合、心臓や脳の血管に障害を生じ、心筋梗塞や脳卒中のリスクが上がります。こうならないためにも、適切な治療を受けることが必要です。
ストレスを溜めない
体や心にかかるストレスは交感神経を興奮させ、血圧を上昇させます。
ストレスが強い、長く続いているという方は要注意です。
自分に合ったストレス解消法を見つけ、ストレスを溜めないことも血圧管理には大切です。
ストレス解消法の一例は、以下の通りです。
- 体を動かす
- 趣味に没頭する
- 日光を浴びる
- 好きな音楽を聴く
- 動物と触れあう
自分なりのストレス解消法を見つけ、高血圧を予防・改善させましょう。
イソフラボンを摂取する
イソフラボンは、更年期に減少する女性ホルモンのエストロゲンと似た働きをします。そのため、イソフラボンを摂取すると、更年期障害による心や体の症状の改善が期待できます。
イソフラボンは大豆、豆腐、納豆などのマメ類に多く含まれます。
さらに、LDLコレステロールを下げる働きもあり、動脈効果を防ぎます。そのため、動脈硬化による血圧上昇の予防にもなるのです。(文献3)
まとめ|更年期女性の高血圧はエストロゲン減少が原因!医療機関の受診も検討しよう
更年期高血圧は、更年期を迎える女性の身体の変化に伴って生じるものです。
更年期を過ぎると血圧が元に戻ることもありますが、多くの場合は加齢の変化と相まって高血圧のままとなります。命を脅かす病気に発展しないよう、血圧のコントロールを行うことが大切です。
毎日の生活習慣を改善し、早期に病院を受診しましょう。このコラムがご参考になれば幸いです。
血圧が高くなってきて悩んでいる方は、当院の「メール相談」「オンラインカウンセリング」もぜひご活用ください。
\無料オンライン診断実施中!/
また、高血圧とストレスについて、さらに詳しく知りたい方はこちらの記事も参考にしてください。
|
参考文献 |