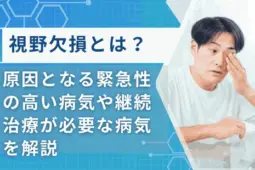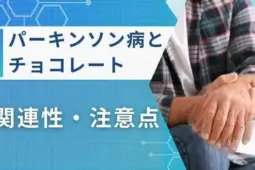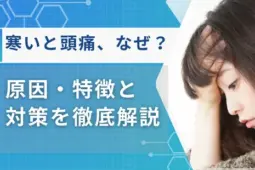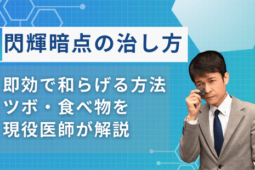- 頭部
- 頭部、その他疾患
「首こりからくるめまい」の治し方は?頭痛などにも効果的なストレッチを医師が紹介!
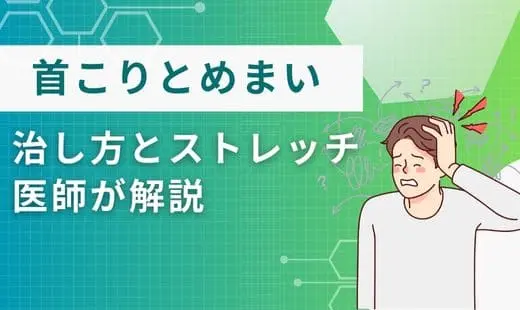
日常生活の中で、首こりを感じていませんか。
「首まわりが張っている」
「首の辺りが重く疲労感がある」
上記のような感覚は、首こりの症状である可能性が高い傾向にあります。
首こりは、頭痛やめまいを引き起こす原因となり、ひどくなると日常生活に影響をおよぼします。
今回の記事では、首こりの解消や予防、首こりに関連する症状を解決するための治し方をまとめました。
首こりに悩んでいる方や、すでに日常生活に影響が出ている方は、ぜひ最後までお読みください。
目次
首こりでめまいや頭痛になる主な原因
首こりは首まわりの頭を支える筋肉に、過度な緊張や負担がかかった場合に生じます。
首こりによるめまいや頭痛が起こる原因は、日常生活のなかにあり、考えられる要因としておもに以下の3つです。
- 不適切な姿勢
- 自律神経の乱れ
- 長時間のパソコン作業
まずは上記3つがなぜ首こりの原因になるのか、それぞれ解説します。
不適切な姿勢
長時間の不適切な姿勢は、首周囲の筋肉に負荷がかかり、首こりが起こります。
日常生活の中でスマートフォンやタブレットを操作する際、少しうつむくような姿勢で操作している方は要注意です。
成人の頭の重さは約4〜6kgあり、首周囲の筋肉や骨で頭の重さを支えていますが、頭が前に傾けば傾くほど、首にかかる負担は大きくなります。
たとえば、スマートフォンを操作するために首を約30度前に傾けると、約18㎏の負荷が首にかかるとされています。
18㎏は5歳くらいの子どもの体重とほぼ同じなので、かなりの負担が首にかかっている状態です。
もともと人間の首は、重い頭を支えるためにゆるやかなカーブをしており、その姿勢が首に負担が少ない姿勢です。
日常生活でスマートフォンの操作時間が長い方や、うつむいた姿勢で長時間作業する職業の方は、首こりになりめまいや頭痛が起きやすいでしょう。
不適切な姿勢になりやすいのは身体に合わない寝具も影響します。
合わない枕は寝ている間に首へ負荷がかかっている可能性があります。
枕は高さや柔らかさなど、自分の身体に合ったものを選びましょう。
自律神経の乱れ
ストレス状態が続くと、自律神経が乱れ、筋肉の緊張を引き起こした結果、めまいや頭痛が起きてしまいます。
そもそも自律神経とは、血圧や呼吸数などを調整し、自律的に身体の中のバランスを整える役割です。
自律神経が乱れると身体機能のバランスが崩れ、全体的に血行が悪くなります。首周囲の血行も悪くなるため、首こりの症状を引き起こす原因になるのです。
自律神経が乱れないためにもストレスはため込むまえに上手く解消できるよう、適度な運動や趣味の時間を増やすなどを実施してみましょう。
長時間のパソコン作業
長時間のパソコン作業は、首こり以外にも眼精疲労が起こる可能性があります。
新型コロナウイルスの拡大で、リモートワークの活用が進み、今までオフィスで仕事をしていた方も、自宅で仕事をする機会が増えたでしょう。
しかしリモートワークは、パソコン作業に向かない机やイスを使っている方も多く、整った環境ではない可能性があります。
パソコン作業に向かない机やイスは、姿勢が悪くなり、気づかないうちに身体に負担がかかっています。
同じ姿勢で座っている時間が長くなるため、首周囲だけでなく、肩や腰の筋肉も凝り固まるでしょう。
長時間ディスプレイを見続けると、目の筋肉が疲れるために、眼精疲労を引き起こします。
見えづらさを感じると姿勢が悪くなりがちなため、首こりの原因になるので、まずは環境を整えていきましょう。
首こりに関連する症状
首こりは、めまいや吐き気、腕の重だるさ、やる気が出ないなど、心身にさまざまな症状があらわれます。
以下の症状は、首こりがひどくなるとあらわれる主な症状です。
- 頭痛
- 目の疲れ
- ストレスからくる自律神経の不調
首こりに関連する3つの症状をそれぞれ解説していきます。
頭痛
「頭全体が締め付けられる痛みがある」
「頭痛が続いていてつらい」
上記のような頭痛を感じる方は、首こりが原因の可能性があります。
首周囲の筋肉や肩、肩甲骨周りの筋肉が緊張するため、血流が悪くなります。
頭に向かう血流にも悪影響をおよぼし、頭痛を引き起こすのです。
首こりからくる頭痛が気になる方は、以下の方法が治し方としておすすめなのでぜひ試してみてください。
- 40℃のお湯に10分程度入浴する
- 首のまわりに温めたタオルやホットパックをあてる
上記の方法は、首周囲の血流が改善する効果が期待できる治し方です。
首周囲の筋肉の緊張をほぐし、血流を改善すれば、頭痛がよくなる可能性があります。
ただし「片頭痛」の場合、血流が良くなると痛みが悪化するので注意が必要です。
目の疲れ
目の疲れは「眼精疲労」とも呼ばれ、首こりの原因や自律神経のバランスを崩します。
1日6時間以上、ディスプレイを見ている方は、目の疲れを引き起こし、首こりにつながる可能性があるので注意が必要です。
パソコンやスマートフォンの操作は同一の姿勢でおこなう場合が多く、液晶画面を見ている時間が長いと、目の疲れやめまいも感じやすいのです。
目の疲れを感じたら、以下のようなケアをおこないましょう。
- 目薬をさす
- 適度な休憩をとる
- ホットパックで目元を温める
上記の方法は、目の疲れやめまいの治し方としておすすめの方法です。
目元をホットパックで温める治し方は、ホットアイマスクやお湯で濡らしたタオルを目に2分ほどあてましょう。
目の疲れやめまいが治れば、首こりの軽減につながる可能性が高まります。
自律神経の不調
首こりがひどくなると、自律神経に影響を与え、副交感神経の働きが低下します。
自律神経には以下の2種類があり、それぞれ違う役割があります。
|
神経名 |
概要 |
|
交感神経 |
起きているときや活動するときに優位 |
|
副交感神経 |
夜間やリラックスしているときに優位 |
首こりによって自律神経が乱れると、以下のような症状が起こるので注意しましょう。
- 頭痛や頭重感
- めまい
- 不眠症 など
ひどくなると「自律神経失調症」を引き起こす可能性があります。
首こりを放置すると、さまざまな関連症状をもたらすので、放置せずできる範囲から取り組み、対処しましょう。
以下の記事では自律神経の乱れに関係するストレスと「高血圧の関係性」についてまとめています。
首こりからくるめまい以外の症状でもあるので、自己判断しないためにもぜひあわせてご覧ください。
首こりを解消させる効果的なストレッチ
日常生活のなかで、首こりからくるめまいや頭痛を解消したい方に向け、現役医師の立場から効果的なストレッチを紹介します。
ストレッチは、身体をリラックス状態にし、血行改善効果があります。
血行が良くなれば、首周りの筋肉もほぐれ、首こりによる症状が緩和するでしょう。
「時間がなくてなかなか運動の時間が確保できない」と感じる方でも取り組める方法をまとめました。
「自宅でもできる治し方が知りたい」方は、ぜひ参考にしてください。
首のストレッチ
首こりでめまいや頭痛を感じる方は、以下のストレッチを試してみてください。
- 背筋をのばし肩の力を抜く
- 首を前に倒しゆっくり右にまわす
- ぐるっと一周まわしたら今度は左にまわす
- 左右10回程度おこなう
パソコンやスマートフォンを見る時間が長い方は以下のストレッチもおすすめの治し方です。
- 両手の親指を鎖骨にかかるように胸の前に置く
- 口を閉じ、上を向いて背筋を伸ばす(顎を突き出すイメージ)
- 首の前部分が伸ばす
- 余裕があれば顎の向きを斜めになるよう左右に傾ける
- 一連の流れを2〜3回繰り返す
肩のストレッチ
首こりからくるめまいや頭痛は、肩のストレッチでも改善できる可能性があります。
肩のストレッチは、以下の手順で実施してみましょう。
- 背筋をのばしてイスに座る
- 腕の力は抜く
- 息を吸いながら両肩を持ち上げる
- 息を吐きながらストンと肩をおろす
- 一連の流れを2~3回繰り返す
肩甲骨のストレッチ
肩甲骨のストレッチも、首こりからくるめまいや頭痛を改善したい方におすすめです。
一連の流れは以下の通りです。
- 両肘を曲げて肩より上に肘をあげる
- 両手は軽くにぎり鎖骨のあたりにもってくる
- 両肘を下げないようにしながらゆっくり後ろへ引く
- 肩甲骨をギュッと寄せように意識する
- そのまま両肘を下げ力を抜く
- 5回程度繰り返す
今回紹介したストレッチは、座ったままでもできる簡単な方法です。
作業の合間や首こりや肩こりを感じたときなどにやってみましょう。
隙間時間を利用し、1日のなかで定期的にストレッチすれば、凝り固まる前に解消できるでしょう。
ただし、体調や自分の首や肩の動かせる範囲内で無理せずストレッチするのが大切です。
無理をすると、筋肉や関節を傷めてしまう可能性があるので、ゆっくり気持ち良いと感じられる力加減でストレッチするのがポイントです。
マッサージ技術の活用
マッサージをすると、凝り固まった筋肉をほぐし血行が良くなるため、首こりの解消におすすめです。
首こりで悩む方のなかには「マッサージや整体院、鍼灸院に行きたいけれど時間がない」方もいるでしょう。
ここからは自宅でできる簡単なマッサージも紹介します。
<胸鎖乳突筋マッサージ>
胸鎖乳突筋とは、首の横に耳の後ろ辺りから鎖骨辺りまでつながっている筋肉です。
場所がわからない場合、顔を横に向けると浮き出てくるためわかりやすいでしょう。
- 耳の後ろ側に人差し指・中指・薬指を縦方向に押し当てる
- 首を横に傾けながら20秒程上下にさする
- 揉みほぐすイメージで指で胸鎖乳突筋をつまむ
- つまむ位置を徐々に下へ移動する
- 反対側も同様におこなう
胸鎖乳突筋の近くには、頸動脈もあるためマッサージをおこなう際には注意しましょう。
痛みや苦しさを感じた方は、すぐにマッサージを中止してください。
自宅でできるマッサージではなく、プロによる適切な施術を希望の方はお気軽に当院へご連絡ください。
日常の運動
首こりを感じたらストレッチやマッサージをするだけでなく、適宜運動も取り入れてみましょう。
日常的に運動をしていると首こりが生じる前に解消でき、予防にもつながります。
以下のような全身運動は、身体の筋肉を動かすため血流がよくなり、首こりの解消や予防におすすめです。
- 縄跳び
- 水泳
- ヨガ など
適度な運動習慣は、首こりの解消だけでなく、健康の維持増進にもつながります。
適度に身体を動かす習慣があると、脳の活性化や疲労回復の効果もあり、仕事の効率アップも期待できます。
また、運動にはストレスホルモンを下げる働きがあるとされているのもおすすめポイントです。
イライラしやすかったり寝つきが悪かったり、ストレスがうまく発散出来ていない方は、運動で発散してみるのも良いでしょう。
ストレスが溜まった状態は自律神経の乱れが起こり、首こりの原因になるため、適度に運動し首こりの解消や予防をしていきましょう。
日常でできる首こり解消法
首こりは、日常生活の中で少し意識して行動するだけで、予防できます。
めまいや頭痛など、さまざまな症状があらわれ、不調をきたす前に、首こりを予防しましょう。首こりの予防は、一度だけではなく長期的な管理が大切です。
毎日過ごす日常生活の中で、自分ができる治し方から取り入れてみましょう。
正しい姿勢の維持
正しい姿勢の維持は、身体全体のバランスが良くなるため、首こりだけでなく肩こりや腰痛の予防にもつながります。
正しい姿勢ができているかは、以下のような確認方法があります。
- 壁に背中を向け立つ
- かかと・おしり・肩・頭を順番に壁につける
- 腰の辺りと壁の間に手のひらを差し込む
手のひら1枚分が入るかどうか隙間があるのが理想ですが、それ以上に隙間が開いている方は「反り腰」を疑いましょう。
肩が壁につかない方は巻き肩で1カ所でも壁につけられない部位があれば、姿勢が悪い可能性があります。
立ったときに、耳や肩、膝、くるぶしが一直線になる状態が、正しい立ち姿勢です。
座ったときには、イスに深く腰かけて骨盤がまっすぐ立つように座りましょう。
足の裏をしっかり床につけ、膝と股関節が90°になるよう座ると、骨盤が立ちやすい座り方になります。
日常生活の中で、正しい姿勢を意識するよう心がけてみましょう。
姿勢改善以外の治し方が気になる方は、以下の記事もあわせて参考にしてください。
職場の環境改善
オフィスでは、適切な明るさ、適切な机やイス、ディスプレイの適切な位置や明るさなど、職場環境が整えられている場合が大半です。
厚生労働省からガイドラインも出されているため、VDT作業(Visual Display Terminals)のための環境設定は重要といえます。
しかし、テレワークや在宅ワークなど、環境が整っていない場所で作業をしている方もいるでしょう。
スペースの問題でディスプレイと近くなってしまったり、机やイスが合わず姿勢が悪くなってしまったりするので、以下を試してみてください。
<VDT作業のための正しい環境設定>
|
300ルクスとは、新聞が読める程度とされており、蛍光灯を使用した少し古い事務所のようなイメージです。
できる範囲で適切な環境設定をすれば、首こりや腰痛などの身体の不調の予防につながります。
定期的な運動とストレッチのルーチン
定期的な運動やストレッチは、首こりの予防に効果的です。
しかし「忙しいから時間がとれない」や「毎日疲れて運動なんてできない」と考えている方もいるでしょう。
「毎日ストレッチを頑張ろう」と決意しても、なかなか続けるのは難しいのが実情です。
定期的な運動スケジュールを立て、ルーティン化すると、長く続けていきやすいでしょう。
運動に対するモチベーションを維持し継続する方法
定期的な運動を続けるためにも、モチベーション維持が大切です。
- 無理のない程度に運動をする日を設定する
- 設定した日に運動やストレッチができたらカレンダーに印をつける
- 慣れてきたら運動する日を増やしてみる
カレンダーに印をつければ「できた」事実が視覚的にわかります。
体調や忙しさによってできない日があっても、徐々にカレンダーにつく印が増えていくと、頑張っていると実感でき、達成感を味わえるでしょう。
モチベーションが上がらない方は「印が何個ついたらご褒美」と設定するのもおすすめです。
まずは、散歩や軽いウォーキング、軽いストレッチを週に数回程度に設定してみましょう。
忙しくても運動の習慣をつける方法
忙しくて時間がなく、まとまった運動の時間を確保するのが難しい方は、日常に変化を加えるのがおすすめです。
|
上記のような時間もとれない方は、日常生活行動の中で「ながら運動」をしてみましょう。
|
運動に対して気が進まず、始めるのにハードルが高い方もいるでしょう。
しかし、適度な運動習慣がある方は、首こりの解消や予防だけでなく、ストレスの解消や健康的な生活にもつながります。
適度な運動習慣をつけるのをおすすめします。
まとめ・首こりが気になる方は一度受診しておくのがおすすめ!
首こりからくるめまいや頭痛は、姿勢の悪さやストレス、長時間のデスクワークから生じます。
首こりを放置すると頭痛やめまいだけでなく、自律神経の乱れを引き起こし、身体全体の不調を感じる原因となります。
首こりは、ストレッチや運動で解消できるので、本記事で紹介したストレッチやマッサージを試してみてください。しかし、今回紹介した治し方を実施しても首こりが解消しない場合、別の疾患も考えられるため、一度受診をしておきましょう。
首こりの原因によって受診する診療科は異なりますが、まずは整形外科を受診するのがおすすめです。
当院では、首こりからくるめまいや頭痛だけでなく、自律神経の乱れから発症するお悩みなどを、メールやオンラインでカウンセリングを行っています。
症状にあわせた解消法やストレッチなどを、診断結果に応じてお伝えします。
「めまいしか感じないけれど治し方を聞いても良い?」と感じる方も、気軽にお問い合わせください。