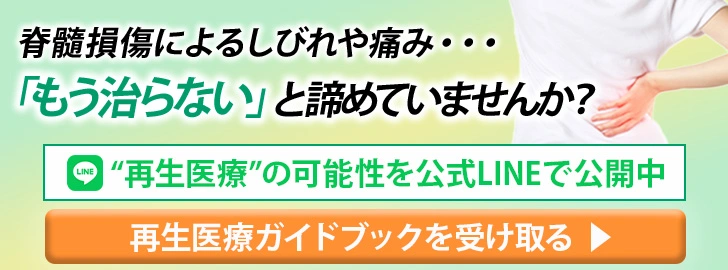- 脊髄損傷
- 脊椎
- 脊椎、その他疾患
脊髄硬膜外血腫の主な後遺症|症状レベル別の治療法や予後についても解説

「脊髄硬膜外血腫」とは、背骨の中で出血が起きる病気の一種です。(文献1)脊髄を覆う「硬膜」の外側で出血し、激しい痛みが起きるほか、溜まった血が脊髄を圧迫すれば麻痺やしびれなどを引き起こします。
脊髄硬膜外血腫の患者様の中には、後遺症が出て日常生活に不便を感じ、お悩みの方もいるのではないでしょうか。
後遺症は今までリハビリテーションなどの対症療法でのみ治療されていましたが、現在では再生医療も選択可能となり、根治的治療として注目を浴びています。
今回は脊髄硬膜外出血の後遺症や、急性期の治療法と発症後のリハビリテーション、予後についてもお伝えします。また、後遺症の治療法(再生医療)についても解説するのでぜひ参考にしてください。
目次
脊髄硬膜外血腫の主な後遺症
脊髄硬膜外血腫は、溜まった血を取り除くまでに脊髄が傷ついてしまうと、治療後に後遺症が出る可能性があります。
後遺症の症状や程度は、障害部位(頸髄や胸髄、腰髄、仙髄、馬尾)や脊髄へのダメージ具合(部分的か全体的なダメージか)によってさまざまです。
代表的な後遺症を以下にまとめました。
- 運動障害(麻痺)
- 感覚障害(温痛覚や振動感覚、位置感覚の障害など)
- 膀胱直腸障害(尿失禁、頻尿、便秘、頻便など)
- 呼吸障害
- 体温調節障害
- 起立性低血圧 など
それぞれ説明していきます。
運動障害(麻痺)
筋肉がうまく動かせなくなるのが運動障害です。具体的には以下の症状が現れます。
- 手足に力が入らない
- しびれる
- まったく動かせない など
出血が起きた部位により、運動障害の範囲は異なります。首のあたりで起きれば両手足の麻痺が、胸や腰の背骨内で起きれば両足の麻痺が出やすいです。
一方で、左右の片方だけに麻痺が起きることもあります。
日常生活での困難は歩けない、座ったり立ったりしていられない、手の細かい動作ができないなどです。
着替えや食事、入浴といった日常生活動作が難しくなり、介助が必要となる場合もあります。リハビリテーションが重要となりますが、どれくらい回復するかは個人差があります。
感覚障害(温痛覚・振動感覚・位置感覚の障害など)
感覚障害とは、以下に示す感覚が鈍くなったり消失したりする障害です。
- 熱さ・冷たさ
- 痛み
- 触覚(触られている感覚)
- 振動感覚(震えを感じとる感覚)
- 手足の位置感覚 など
感覚障害も、出血が起きた部位によって範囲が異なります。首のあたりで出血が起きれば両手足に感覚障害が出やすく、胸や腰で起きれば下半身に症状が出ることが多いです。また、左右どちらかだけに症状が出ることもあります。
日常生活では、やけど・けがに気付きにくくなります。歩くときにバランスが取りにくい、箸を使いにくいなどもよくある症状です。
運動障害と同様、リハビリテーションによって回復が見込める場合があります。
膀胱直腸障害(尿失禁・頻尿・便秘・頻便など)
膀胱直腸障害とは、排泄に関する障害です。
排尿に関する症状は以下の通りです。
- 尿意切迫感
- 頻尿
- 尿失禁
- 排尿困難
- 残尿感 など
また、排便に関する症状として以下が挙げられます。
- 便秘
- 排便困難
- 便失禁
- 頻便 など
日常生活では、突然の尿意や便意あるいは失禁により、生活に大きな支障をきたすでしょう。
逆に排尿困難や便秘があると、お腹の張りや不快感につながります。外出時のトイレの不安から、活動範囲が狭くなる方も多いです。
症状に応じて自己導尿や排便コントロールを身につけたり、薬の力を借りたりして適切に管理することが大切です。
その他(呼吸障害・体温調節障害・起立性低血圧など)
脊髄硬膜外血腫では、運動・感覚・膀胱直腸障害以外にもさまざまな後遺症の可能性があります。
呼吸障害は、頸椎の上の方で出血が起きた場合の症状です。呼吸に必要な筋肉が麻痺し、人工呼吸器が必要となる場合もあります。
自律神経が障害されれば、体温や血圧の自動調節がうまくいかず、体温調節障害や起立性低血圧などを引き起こします。自律神経への影響が大きくなるのは、胸椎より上で出血が起きた場合です。
筋肉が緊張しすぎる「痙縮」では手足が突っ張ったり、意識しないのに動いてしまったりします。ビリビリとした痛みや刺すような痛みを感じる場合は「神経障害性疼痛」かもしれません。これは神経が傷ついたことで、外傷がない部位でも痛みを感じる症状です。
脊髄硬膜外血腫の治療法
脊髄硬膜外血腫の治療法は、手術をしない保存的治療と、手術による外科的治療に分けられます。どちらを選択するかは、症状の程度や持続時間、出血が止まりにくい要因の有無を考慮して決定します。
保存的治療|症状が軽度の場合
保存的治療では安静を保ち、必要に応じて止血剤や降圧剤を投与します。保存的治療を選択する明確な基準はありません。(文献2)脊髄硬膜外血腫102例を分析した報告では、以下の両方に当てはまれば、保存的治療での回復も期待できるとされています。(文献3)
- 血をサラサラにする薬(抗凝固薬)を使っていない
- 運動機能が完全に麻痺していない
上記の片方だけに当てはまる場合も、保存的治療を選択する場合があります。抗凝固薬を使用中なら、必要に応じて効果を打ち消す薬を投与します。
保存的治療では、注意深い経過観察が重要です。症状の変化を定期的に確認し、保存的治療を続けるか手術に変更するかを判断するのです。
麻痺が出てから15時間以内に症状が回復に向かえば、出血が自然に止まって血腫の吸収が始まり、神経への圧迫がゆるんできていると考えられます。(文献3)この場合は自然に完治する可能性が高いとされます。
外科的治療|症状が重篤な場合
運動機能が完全に麻痺している場合や、神経症状の進行が見られる場合は速やかに外科的治療を検討します。少しでも麻痺が見られれば速やかに手術すべきとの考えもあります。
発症から24時間以内に手術できれば、重度の麻痺から回復できる可能性が高まるとの報告もあり、素早い判断が重要です。(文献3)
脊髄硬膜外血腫の手術では、血腫ができている部分の背骨の一部(椎弓(ついきゅう)と呼ばれる部分)を削り、奥にある血腫を取り除きます。(文献1)手術用の顕微鏡を使って血腫を除去し慎重に止血すれば、脊髄を圧迫する原因はなくなります。
脊髄硬膜外血腫に対するリハビリテーション
初期治療後に残った症状は、リハビリテーションを行いながら改善を目指します。
リハビリテーションとは、病気や怪我の後に社会復帰を目指して行う訓練の総称です。
病気や怪我以前の生活水準を目指し、日常生活を見据えた身体的訓練のほか、不安や無力感などの精神的な障害には心理的訓練、また必要に応じて職業訓練も行われます。
リハビリテーションに携わるスタッフは、医師や看護師に加えて、作業療法士や理学療法士、言語聴覚士などのスペシャリストです。
病院で行われることもあれば、リハビリ専門施設で実施されることもあります。
脊髄硬膜外血腫の急性期リハビリ
怪我や病気を患った直後の急性期は、まず全身状態を落ち着かせ、損傷や障害を最低限に抑えるためのリハビリテーションが必要となります。
具体的には、以下の訓練を実施します。(文献5)
- 頸髄や上位胸髄の損傷による呼吸機能低下に対しては呼吸訓練
- 手術後にうまく寝返りができない場合には、床ずれ予防のために体位変換訓練
- ベッド上で動けない間に関節が固まってしまわぬように関節可動域訓練
全身状態が安定後のリハビリ
全身状態が落ち着いた後は、症状に合わせて積極的にリハビリテーションを進めていくことが重要です。
脊髄硬膜外出血によって脊髄が大きなダメージを受けた場合は、神経障害などを完全に取り除くのは難しく、後遺症が出ることが多いでしょう。
そのため、早期からのリハビリテーションを通じて、残存した能力を強化し、必要な筋力や柔軟性を取り戻します。
具体的には以下を実施し、合併症を避けて自分で尿路管理できることを目指します。
- 両下肢の麻痺(対麻痺)の場合には上肢の筋力を高め、プッシュアップ動作を練習し、車椅子の訓練
- 排尿障害を患っている場合は、腹壁徒手圧迫法や反射誘発、自己導尿法などの指導
脊髄硬膜外血腫の予後
脊髄硬膜外血腫はまれな疾患で、死亡率や予後についての情報も少ないのが現状です。
最初の運動麻痺が軽度の場合や、重度であっても早く血腫を取り除ければ良好に回復する傾向がありますが、確実に回復するかどうかは一概にはいえません。
海外で脊髄硬膜外血腫の報告を1000例以上集めて検討した論文では、死亡が確認された例は7%だったと報告されています。年齢別では40歳以上が9%、40歳未満が4%で、治療法によらず40歳以上では死亡率が有意に高くなると報告されました。(文献8)
後遺症については、初めの症状が軽度であった患者群では、8.5%がわずかな障害を示すのみでした。一方で、初めの症状が重篤だった患者群では、28.3%に軽度の障害が残っています。(文献8)
また、日本国内のある病院では、自院で治療を行った16症例を分析しました。この報告では、完全治癒が10例(2回発症し2回とも完全治癒した例を含む)、軽度の運動麻痺が残ったケースが6例、死亡が1例でした。死亡例は、合併していた大動脈解離と腎不全が直接の原因とされています。(文献9)
脊髄硬膜外血腫の術後後遺症に対する再生医療
再生医療は、失われた身体の組織を再生する能力、つまり自然治癒力を利用した医療です。脊髄硬膜外血腫の手術後に残ってしまったしびれ、麻痺などの後遺症に対する治療として「幹細胞治療」が適応される可能性があります。
当院リペアセルクリニックで行う再生医療「自己脂肪由来幹細胞治療」では、患者様から採取した幹細胞を培養して増殖し、その後身体に戻します。自分自身の細胞から作り出したものを用いるため、アレルギーや免疫拒絶反応のリスクが極めて低い治療法です。
日本での一般的な幹細胞治療は、点滴によって血液中に幹細胞を注入するものです。しかし、それでは目的の神経に辿り着く幹細胞数が減ってしまいます。
そこで当院では、損傷した神経部位に直接幹細胞を注入する「脊髄腔内ダイレクト注入療法」を採用しています。注射によって脊髄のすぐ外側にある脊髄くも膜下腔に幹細胞を投与します。
幹細胞の培養には時間を要しますが、治療そのものは短時間の簡単な処置で、入院も不要です。
実際に当院では術後や外傷、脊髄梗塞、頚椎症による神経損傷に由来する麻痺やしびれ、疼痛などの後遺症に対して再生療法を施しております。
脊髄硬膜外血腫の術後後遺症にお悩みの方は、ぜひ一度リペアセルクリニックへお問い合わせください。
まとめ|脊髄硬膜外血腫の後遺症への理解を深めて正しい治療法を選択しましょう
脊髄硬膜外血腫を発症した場合、保存的治療または外科手術により治療を行います。麻痺の程度や、出血しやすい要因を考慮して治療を選択しますが、症状の変化に応じた素早い判断が重要です。
また、後遺症には運動障害や感覚障害、排尿・排便障害などがあります。回復には早期のリハビリテーションによる残存能力の強化や、合併症予防のための訓練が大切です。
さらに、多大なダメージを受けてしまった神経を元に戻す治療がなかった中で、近年になって再生医療が多くの患者様へ提供可能となりました。
当院では入院不要、外来診療のみで再生医療を受けられますので、気になる方はぜひ当院へ一度ご相談ください。

脊椎損傷のお悩みに対する新しい治療法があります。
参考文献
(文献1)
日本脊髄外科学会「特発性脊髄硬膜外血腫」日本脊髄外科学会ホームページ
https://www.neurospine.jp/original63.html(最終アクセス:2025年3月21日)
(文献2)
中村直人ほか.「特発性脊髄硬膜外血腫の臨床診断と治療方針」『脊髄外科』32(3), pp.306-310, 2018年
https://www.jstage.jst.go.jp/article/spinalsurg/32/3/32_306/_pdf(最終アクセス:2025年3月21日)
(文献3)
武者芳朗ほか.「急性脊髄硬膜外血腫に対する保存療法の適応と手術移行時期」『脊髄外科』29(3), pp.310-314, 2015年
https://www.jstage.jst.go.jp/article/spinalsurg/29/3/29_310/_pdf(最終アクセス:2025年3月21日)
(文献4)
西亮祐ほか.「特発性脊髄硬膜外血腫に対する当院での治療成績の検討」『済生会滋賀県病院医学誌』32, pp.15-20, 2023
https://www.saiseikai-shiga.jp/content/files/about/journal/2023/journal2023_4.pdf(最終アクセス:2025年3月21日)
(文献5)
日本リハビリテーション医学会「脊髄損傷のリハビリテーション治療」日本リハビリテーション医学会ホームページ
https://www.jarm.or.jp/civic/rehabilitation/rehabilitation_03.html(最終アクセス:2025年3月21日)
(文献6)
日本脊髄外科学会「脊髄損傷」日本脊髄外科学会ホームページ
https://www.neurospine.jp/original62.html(最終アクセス:2025年3月21日)
(文献7)
吉原智仁ほか.「当科で経験した脊髄硬膜外血腫の 3 例」『整形外科と災害外科』65(4), pp.845-848, 2016年
https://www.jstage.jst.go.jp/article/nishiseisai/65/4/65_845/_pdf(最終アクセス:2025年3月21日)
(文献8)
Maurizio Domenicucci, et al. (2017). Spinal epidural hematomas: personal experience and literature review of more than 1000 cases.J Neurosurg Spine, 27(2), pp.198–208.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28574329/ (Accessed: 2025-03-21)
(文献9)
原直之ほか.「特発性脊髄硬膜外血腫の 16 症例の臨床分析 ―脳卒中との類似点を中心に―」『臨床神経学』54(5), pp.395-402, 2014年
https://www.neurology-jp.org/Journal/public_pdf/054050395.pdf(最終アクセス:2025年3月21日)