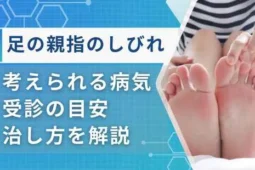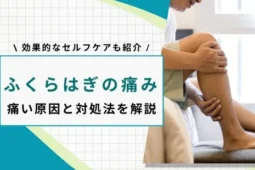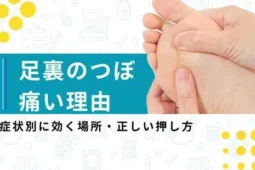- 足部、その他疾患
- 下肢(足の障害)
モートン病とは?原因や症状・治療法を解説【医師監修】

モートン病は足指の付け根が立位や歩行などで負荷がかかり痛みが生じる疾患です。
足の痛みは日常生活に大きく影響するため、できるだけ症状を減らしたいと困っている方も多いでしょう。
この記事では、モートン病の原因や初期症状、治療法などを詳しく解説しています。セルフチェックも用意していますので、足の状態を把握したい方はご活用ください。
目次
モートン病とは?
モートン病は、足指の間のしびれ、痛み、灼熱感などの神経症状が出現する疾患です。症状が出現するのは主に中指と薬指の間が多いですが、人差し指と中指、薬指と小指の間に発症する場合もあります。
モートン病の原因と初期症状について、詳しく見ていきましょう。
モートン病の原因は主に「つま先立ちのような姿勢」
モートン病の原因は、つま先立ちの姿勢を長時間続けることです。つま先立ちの姿勢は、足指につながる神経を圧迫するため神経障害を発症します。
以下はつま先立ちの姿勢を引き起こす要因です。
- ヒールの高い靴の着用
- 外反母趾や扁平足などの足の形態異常
- ダンスやバレエなど足を酷使するスポーツ
- ジョギングやランニングなど前足に繰り返し力がかかる運動
モートン病は中年以降の40代〜60代の女性に多く発症すると言われています。しかし、年代問わずつま先に負担がかかる姿勢が続くと、発症する可能性があります。
モートン病の初期症状は「つま先のしびれ、痛み」など
以下は、モートン病の初期症状です。
- 靴を脱ぐと痛みやしびれが軽減する
- 足指の付け根に違和感や軽い痛みが生じる
- 足の指で握ったり、足の指を広げたりすると痛む
最初は、足指の感覚に対する違和感や軽い痛みからはじまります。初期段階は症状が一時的で、時間が経つと症状がおさまるケースも少なくありません。
悪化してくると、強い痛みやしびれなどが長時間続いたり、突然激痛が走ったりする症状が見られます。
モートン病のセルフチェック方法
以下はモートン病のセルフチェックポイントです。当てはまるものがないか確認してみてください。
- 足の指の付け根に痛みやしびれを感じる
- 足の付け根をつまむ、押す、叩くと痛む
- 歩行時や長時間の立ち仕事で足裏に痛みが走る
- 足の指を曲げたり広げたりすると痛みが強まる
- 靴を履いていると痛みが強まり、脱ぐと和らぐ
- ヒールや先の細い靴を履くと、痛みやしびれが悪化する
モートン病を正確に診断するには整形外科の受診が必要です。当てはまる項目があれば、近くの整形外科での診察を検討してみましょう。
モートン病の治療
モートン病は放置すると症状が悪化し、歩行が困難になる場合もあります。
症状の進行を防ぐための治療法としては、主に以下5つがあります。
- 保存療法(マッサージ・ツボ押し・運動)
- 薬物療法
- 手術療法
- 再生医療
順番に解説します。
保存療法(マッサージ・ツボ押し・運動)
モートン病の治療では、マッサージやツボ押しなどの保存治療が行われます。
ツボ押し(指圧療法)は、足の血流を改善し、痛みをやわらげる方法です。とくに、以下4つのツボが症状の緩和に役立つと考えられています。
- 承山(しょうざん):ふくらはぎの裏面
- 下承山(げしょうざん):ふくらはぎの裏側
- 築賓(ちくひん):ふくらはぎの内側
- 漏谷(ろうこく):すねの内側
ただし、ツボ押しの効果には個人差があり、医学的に確立された治療法ではありません。
筋力を鍛える運動もモートン病の症状緩和につながります。
横アーチ(足の横方向のカーブ)を支えるために、足の裏の筋肉を強化しましょう。
たとえば、タオルギャザーは簡単にできる運動です。床にタオルを敷き、指を使って手前に引き寄せると、足の裏の筋肉が鍛えられます。
意識的に指を広げたり、指を上げたりする運動もモートン病に効果があります。
【関連記事】
モートン病のマッサージ方法とは?痛みに効果的なセルフケアを解説【医師監修】
モートン病に対するツボの効果とは?代替治療を取り入れて症状を改善しましょう
靴の変更・足底挿板の作成
靴の変更・足底挿板の作成も保存療法の1つです。
足に合った靴やインソール(靴の中敷き)を選ぶと、歩くときの痛みを軽減できます。
靴を選ぶ際は、足に優しいデザインを意識しましょう。以下は、モートン病で負担のかかりにくい靴の特徴です。
- 靴底が柔らかい
- かかとが低い
- つま先が広め
自分に合った靴を選べば、歩くときの負担が軽減します。
足底挿板(そくていそうばん)は、足を正しい位置に保つための特別な中敷きです。専門の技術者に依頼して、足の形や状態に合わせて作ってもらいます。
モートン病は、足のアーチ(土踏まずのようなカーブ)が低下することで神経が圧迫され、痛みやしびれを引き起こします。そのため、アーチを支える足底挿板を使うと、負担が減り、症状が楽になりやすいです。
市販のインソールも使えますが、形や厚みがさまざまなので、専門家に相談して選ぶのがおすすめです。足に合っていないものを使うと、逆に痛みが増すリスクがあります。
薬物療法
モートン病の薬物療法では、消炎鎮痛剤によって痛みや炎症を抑えます。
これは、モートン病を治すというより痛みに対処するための治療方法です。
痛みが軽減しない場合は、ステロイド注射や局所神経ブロック注射を行う場合もあります。
手術療法
手術は、運動療法や薬の治療を試しても症状が良くならない場合に選ばれます。
モートン病で代表的なのは、痛みが出ている部位周囲の組織を取り除く手術です。
神経ごと取り除くため、そこから先の感覚はなくなってしまいます。、違和感が残る場合もありますが、術後1週間から2週間で以前と同じように歩けるようになります。
再生医療
モートン病の治療法には「再生医療」の選択肢もあります。
再生医療には、幹細胞治療とPRP(多血小板血漿)療法などがあります。
幹細胞治療では、自身の幹細胞を培養して患部に注射し、損傷している組織の修復と再生を促す治療法です。
PRP療法では、自分の血液を採取して血小板を濃縮し、修復を助ける成分を含んだ液体を患部に注射します。血小板は体の傷を治す働きを持つため、損傷した組織の修復や痛みの軽減が期待できます。
どちらも注射のみの治療なので、手術のように傷跡が残る心配や術後のリハビリの必要がありません。体への負担が少ないため、再生医療は早い回復が期待できる治療法です。
\無料オンライン診断実施中!/
モートン病でやってはいけないこと
モートン病では、症状を悪化させないためにやってはいけないことがあります。
- 長時間同じ姿勢を取らない
- ハイヒールや幅の狭い靴は避ける
以下で具体的な内容を解説します。
長時間同じ姿勢を取らない
長時間立ったり歩いたりすると、足に負荷がかかり続けるため、症状が悪化する原因になります。
仕事上、そうせざるを得ないことも多いかもしれませんが、少しでも姿勢を変えて足を休められると良いです。
また、自宅で家事をしているといつの間にか立っている時間が長くなるでしょう。そのため、休憩時間を少しずつ挟んで足を休めるのが大切です。
ハイヒールや幅の狭い靴は避ける
モートン病は前足部への負荷が原因となりやすいため、ハイヒールや幅の狭い靴は避けましょう。
とくにハイヒールは、常に足趾の付け根が圧迫されている状態であり、モートン病や外反母趾など足の疾患につながります。
まとめ|モートン病の理解を深めて適切な治療を進めよう
モートン病は、放置すると痛みが強くなり、歩行が困難になる場合もあります。症状が悪化すると手術が必要になるケースもあるため、早めの対処が大切です。
本記事で紹介したセルフチェックを活用し、万が一、モートン病が疑われれば、整形外科の受診を検討しましょう。
「できるだけ身体に負担の少ない治療を進めたい…」という方に、選択肢の1つとして考えてほしいのが「再生医療」という新しい治療法です。
再生医療は、傷ついた組織の修復と再生を促し、治療期間の短縮が期待できます。
モートン病に関するよくある質問
モートン病は再発のリスクがありますか?
モートン病は保存療法や手術療法で治療しても再発する可能性があります。そのため、足へ負担がかかりにくい生活習慣やインソールや靴などをフィットしたものに変更するなど、足へのケアが大切です。
また、定期的に病院を受診すれば、再発したとしても早期発見・早期治療ができるため、症状が改善しやすくなるでしょう。
モートン病は何科を受診すればいいですか?
モートン病が疑われる場合は、整形外科を受診しましょう。整形外科では、歩行時の痛みやしびれの原因を詳しく調べ、適切な治療方法を提案します。
参考文献
長田瑞穂ほか「モートン病の足部タイプと足底挿板療法について」『骨・関節系理学療法』
https://www.jstage.jst.go.jp/article/cjpt/2005/0/2005_0_C0442/_article/-char/ja/(最終アクセス:2025年2月25日)
梅﨑泰侑ほか「足部形態の違いからとらえた足部内在筋群エクササイズの筋活動に対する即時効果」『理学療法科学』38(6)pp444-450
https://www.jstage.jst.go.jp/article/rika/38/6/38_444/_pdf/-char/ja(最終アクセス:2025年2月25日)
厚生労働省「市販の解熱鎮痛薬の選び方」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00404.html(最終アクセス:2025年2月25日)
三森 経世「関節リウマチ,抗炎症薬とステロイド薬,内科医が診るべき骨・関節疾患:治療の新展開」『日本内科学会雑誌』第97巻 第10号pp17-22 平成20年10月10日
https://www.jstage.jst.go.jp/article/naika/97/10/97_2393/_pdf(最終アクセス:2025年2月25日)