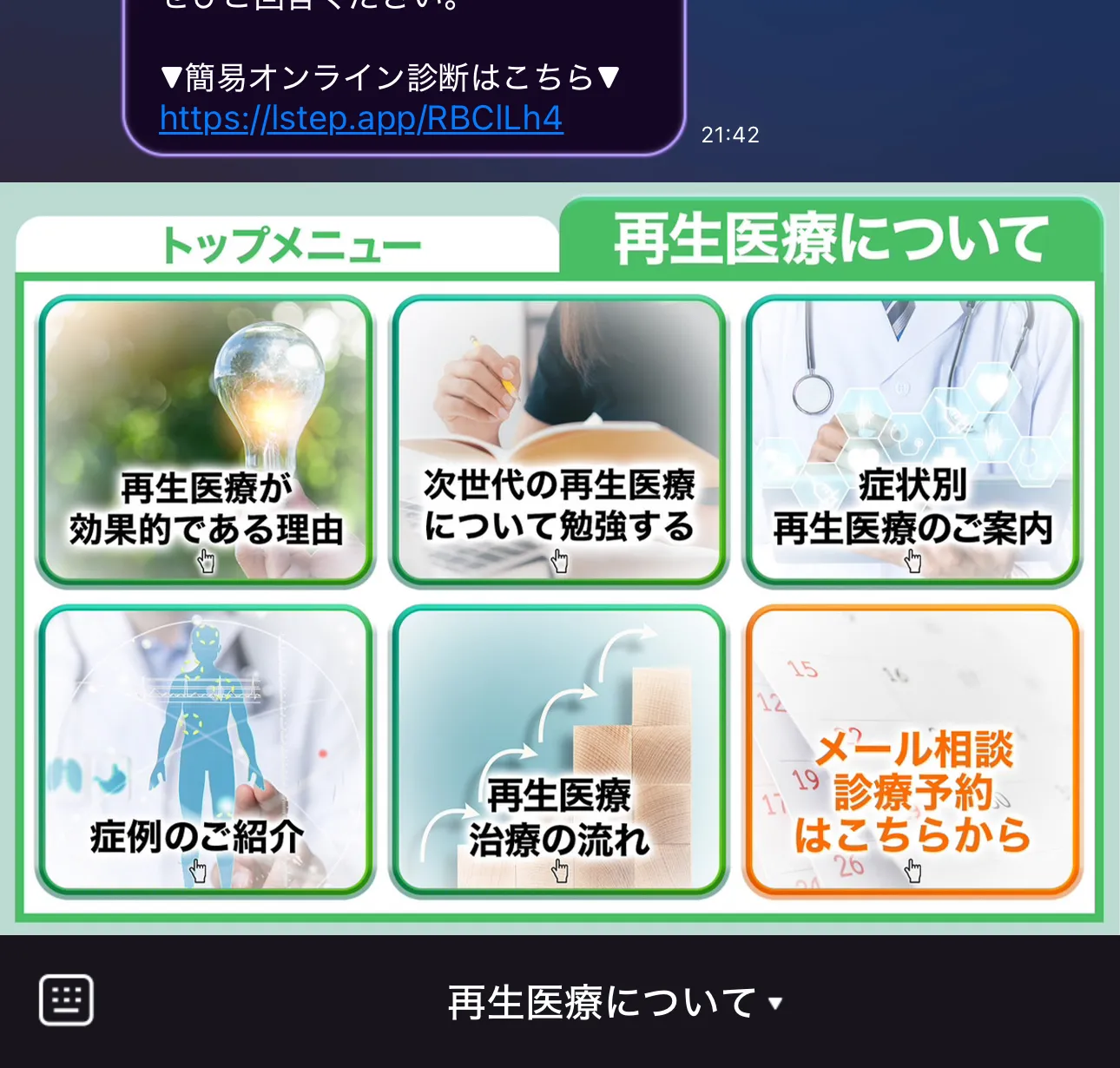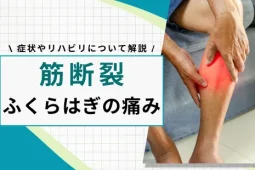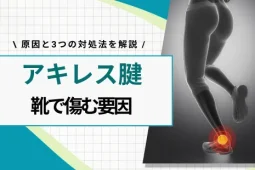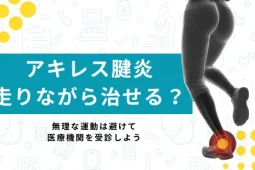- 足部、その他疾患
- 足部
アキレス腱断裂に対するリハビリメニューをご紹介!時期や治療法別に医師が解説

スポーツなどで起こりやすいとされるアキレス腱断裂は、足首を動かすことが困難になり、日常生活が大きく制限されてしまいます。
アキレス腱断裂では、保存療法と手術どちらでもリハビリが必要ですが、実際にどんなリハビリをするか気になる人もいるのではないでしょうか。
実はリハビリをすすめていく上で、必ず守らないといけない注意事項や効果的な方法があるため、実際にリハビリを進めていく際には注意が必要です。
そこで本記事では、アキレス腱断裂をした後のリハビリメニューや治療法などを詳しく解説します。アキレス腱断裂をしてその後のリハビリメニューや治療法が気になる方はぜひ最後までチェックしてください。
目次
アキレス腱断裂でのリハビリメニューは「アキレス腱以外の部位も行う」
アキレス腱断裂をした後のリハビリで重要なポイントは以下の3つです。
- 治療は手術と保存療法がある
- どちらの場合でもアキレス腱以外の部位を怪我した直後から動かす
- 患部は装具を使ってゆっくりと動かしていく
アキレス腱断裂の治療は、外科的にくっつける手術と自然治癒を待つ保存療法の2択ですがどちらもリハビリが欠かせません。
とくにアキレス腱以外の膝・股関節・足趾(足の指)といった部位は、怪我した直後から積極的に動かすようにしましょう。
手術・保存療法どちらの場合でも、アキレス腱に負担をかけないために、踵を挙げた状態で固定する装具を装着してリハビリを行います。
なお、当院リペアセルクリニックでは手術・保存療法のほか再生医療の提供も可能です。もし気になる方はお気軽にメール相談もしくはオンラインカウンセリングでご相談ください。
\無料オンライン診断実施中!/
また、アキレス腱治療における再生医療については、以下の記事でも解説していますので、ぜひチェックしましょう。
アキレス腱以外のリハビリは「足首以外を弱らせないため」に大切
アキレス腱断裂後のリハビリでは、足首以外の筋力を維持するために、アキレス腱以外の膝・股関節・足趾(足の指)などを積極的に動かします。とくに問題がなければ、怪我した直後から動かしていくメニューが一般的です。
とくにアキレス腱断裂の場合、足首以外の関節を装具で固定するケースも多くあります。関節を保護しすぎて動かす量が減ると、下肢筋力が大きく低下してしまう可能性も考えられます。
社会復帰を早めるためにも、足首以外の筋力強化は積極的におこないましょう。
足首が固まらないことを優先する
アキレス腱断裂では、アキレス腱の再生を促す目的で、足首を固定する期間を設けるケースがほとんどです。足首が固まってしまい可動域が制限されることが多いため、リハビリでは足首の可動域を維持することが大切です。
具体的には、装具を使ってアキレス腱に負担がかからないようにしながら体重をかける練習や、足首周囲のマッサージを積極的におこないます。
アキレス腱に負担がかからない範囲で足首のリハビリをおこなうことで、足首の可動域制限を最小限にとどめることが大切です。
アキレス腱断裂後におこなうリハビリメニュー4選【アキレス腱】
アキレス腱断裂後におこなうアキレス腱のリハビリメニューには、以下の4つがあります。
- 足首を反らして可動域を広げる運動
- アキレス腱にかかわる下腿三頭筋(ふくらはぎ)の筋力強化運動
- 体重を乗せる練習
- スポーツや社会復帰に向けた動作練習
これらのリハビリは、アキレス腱への負担を考慮しながら進める必要があります。痛みが出たら即中止し、無理をしないようにこころがけてください。
関節可動域運動足首を反らして可動域を広げる運動
足首の関節が固まらないように、関節可動域運動(かんせつかどういきうんどう:ROM運動)を行います。
つま先を上に持ち上げるような動き(背屈運動:はいくつうんどう)はアキレス腱が伸ばされるため、慎重に始めて再断裂を予防するのが大切です。
アキレス腱の強度が高まれば、立ってアキレス腱を伸ばすようにストレッチをして関節の動きを改善します。
Step1
- 自分でゆっくり動かす
- アキレス腱の組織が癒着しているのをはがす
Step2
- 最初はつっぱり感があり、痛みも出やすい
- 優しく行うのが重要です
Step3
- 徐々に理学療法士によるマッサージやストレッチを加えながら関節を動かす
- アキレス腱の柔軟性を改善します。
筋力トレーニングアキレス腱にかかわる下腿三頭筋(ふくらはぎ)の筋力強化運動
アキレス腱が十分修復されてくれば、日常の動作やスポーツに必要な筋力を戻すためのトレーニングを実施します。
まずはゴムバンドなどを使用して体重をかけない状態で負荷をかけましょう。筋力や痛みの有無に合わせて、体重をかけた状態でのトレーニングに移行します。最初は無理をせず、徐々に負荷を高めていくことが重要です。
トレーニング
1. 座って踵上げ(座位カーフレイズ)から始める
⇩
2. 両脚で立っての踵上げ(両脚カーフレイズ)
⇩
3. 片足で立っての踵上げ(片脚カーフレイズ)
荷重練習体重を乗せる練習
アキレス腱の修復状況に合わせて、体重をかける時期や量を調整します。体重を乗せる練習は装具を使って、アキレス腱が無理に伸ばされないようにこころがけてください。
なお、保存療法に比べ、手術療法の方が早くから体重をかけることができます。
荷重は装具を使用しながら調整します。装具については、後ほど詳しく解説します。
動作練習スポーツや社会復帰に向けた動作練習
アキレス腱の強度や筋力が十分になれば、装具を外してのウォーキングやジョギング、ランニング、ジャンプといった動作を実施していきます。
スポーツ動作は複雑な動きや強い瞬発力を必要とするため、短くても6カ月ヶ月程度の期間が必要です。
アキレス腱断裂後におこなうリハビリメニュー4選【アキレス腱以外】
アキレス腱断裂後におこなうリハビリメニューとして、以下の4つをご紹介します。
- 足趾の強化(タオルギャザー)
- 太ももの筋力強化
- 膝を伸ばす運動
- お尻の外側の筋力強化
これらの運動は、体重がかかったときにアキレス腱の働きを補助する筋肉を鍛えるメニューです。これらのリハビリを行うことで、アキレス腱の負担軽減につながります。
いずれもアキレス腱への負担がかかりにくい運動であり、アキレス腱断裂後、早期から実施可能です。
しかし、慣れないうちは足首に力を入れてしまうこともあるかもしれません。もしリハビリの実施中に痛みを感じた場合は、無理せず中止してください。
足趾の強化(タオルギャザー)
用意するもの:フェイスタオル等やや厚手のタオル
1.裸足で立位または椅子に座り、指先でタオルをたぐり寄せる。
2.たぐり寄せたタオルを指先で元の位置に広げる。
3.左右を入れ替えて繰り返し行う。
1セット10回を1日3セット程度から開始して、余裕があれば増やします。実践する際にはタオルを引き寄せるときに指を大きく動かすことが重要です。また、足首を反らしながら指を曲げてしまう人が多いため、つま先を床につけたままおこなう意識を持ってください。
太ももの筋力強化運動
用意するもの:バスタオル(またはクッション)
1.仰向けになり、まっすぐに伸ばした膝裏に丸めたタオルを挟む。
2.膝裏でタオルを力強く押すと同時に、つま先は上に持ち上げる。(5 秒ほど)
3.左右を入れ替えて繰り返し行う。
体重がかかったときに踏ん張って体を支えてくれる太もも(大腿四頭筋)の筋力強化運動です。1セット10回で1日3セット程度を目安に進めていきましょう。
ポイントはしっかりと膝を伸ばしながら足を持ち上げることで、膝を伸ばす意識を持てば太ももの筋肉に大きく刺激が入ります。また、足首に力を入れてしまう人が多いため、足首の力は抜くようにしてください。
膝を伸ばす運動
用意するもの:背もたれのある椅子か机などつかまれるもの
1.立位で椅子の背もたれなどに摑まり、片足を後ろに引き、膝を伸ばす。
2.左右を入れ替えて繰り返し行う。
後ろに引いた足の膝を伸ばして太ももの筋肉(大腿四頭筋)に刺激を入れる運動です。1セット10回で1日3セットを目安におこないます。体重をかけることで太ももの筋肉により強い刺激が入るでしょう。
この練習をするときはアキレス腱保護のため装具を必ず装着してください。体重をかけることで痛みを感じるようであれば、無理をしないように気をつけましょう。
お尻の外側の筋力強化
1.横向きになり、上側の足をゆっくりと持ち上げ、ゆっくりと下ろす。
2.左右を入れ替えて繰り返し行う。
立ったときに骨盤を横から支えてくれるお尻の筋肉(中臀筋)を鍛える運動です。1セット10回を2〜3セットを目安におこないましょう。
ポイントとして足を上げ下ろしする角度が大切です。骨盤より前で足を上げ下ろしすると太ももの筋肉に力が入りやすいので、足を骨盤と同じ角度か少し後ろに引く気持ちで上げ下ろしするとお尻への刺激が入りやすいでしょう。
日常生活やスポーツへの復帰を早めたいなら「手術」も検討する
もし早期の社会復帰・スポーツ復帰をしたいと考えているならば、手術を受けることも検討しましょう。
手術ではアキレス腱を縫合するため、再生を早められるほか、保存療法による自然治癒よりも強固に修復できるためです。
アキレス腱断裂後に早く日常生活やスポーツに復帰したい人は、主治医と相談の上、手術も視野に入れても良いかもしれません。
本章ではアキレス腱断裂後のリハビリにかかる経過を、保存療法をおこなったケースと手術をしたケースでそれぞれご紹介します。
保存療法でのリハビリスケジュール
| 受傷日からの日数 | リハビリメニューの例 |
|---|---|
| 受傷〜2週間 | ・体重はまったくかけてはいけない ・患部以外のトレーニングの実施 |
| 2週間〜6週間 | ・足首を下に向けた状態で固定 ・床に触れる程度から体重をかけ始める ・4周目以降に全体重をかけ始める ・足首をゆっくり自分で動かす |
| 6週間〜8週間 | ・足首をストレッチする |
| 8週間〜12週間 | ・徐々に筋力トレーニングを開始 ・ゴムバンドなどを使ったトレーニングを開始 ・筋力が向上すれば座位カーフレイズ開始 ・両脚カーフレイズ、片脚カーフレイズを段階的に実施 |
| 3カ月〜4カ月 | ・装具を外してウォーキングやジョギングを開始 |
| 4カ月〜6カ月 | ・ランニングやジャンプ開始 |
| 6カ月〜 | ・スポーツ復帰 |
アキレス腱断裂後、保存療法を行う場合は、受傷からアキレス腱の修復状況に合わせて、段階的にリハビリメニューを変更していきます。
アキレス腱の修復状況や痛みの程度、合併症の有無などによって、上記のメニューのようにいかない場合もあるため、都度強度の調整が重要です。
受傷直後はギプス固定をして、足首が完全に動かないようにしばらく固定をする場合もあります。あくまでもアキレス腱の修復や再断裂の予防が最優先ですので、医師や理学療法士としっかり連携をとり、リハビリを進めていくのが大切です。
手術療法でのリハビリスケジュール
| 受傷日からの日数 | リハビリメニューの例 |
|---|---|
| 受傷〜4週間 | ・体重はまったくかけない。 ・患部以外のトレーニングの実施 ・痛みに合わせて徐々に足首の運動を実施 ・徐々に体重をかける量を増やしながら荷重する |
| 4週間〜6週間 | ・つま先を下に向ける ・徐々に戻していき、全体重をかけていく |
| 6週間〜8週間 | ・立った状態 ・ストレッチや足首の筋力トレーニングを始める ・筋力がつけば両足カーフレイズを実施(両手支持から始める) |
| 8週間〜3カ月 | ・装具を外してのウォーキング開始 ・片脚カーフレイズで筋力を向上させる |
| 3カ月〜5カ月 | ・ジョギングやランニング ・ジャンプなどを段階的に実施 |
| 5カ月〜 | ・スポーツ復帰を目指す |
アキレス腱断裂後、手術を行う場合は、保存療法よりも早期に体重を乗せるリハビリをはじめます。
手術療法は比較的アキレス腱の修復が早く、体重を早くかけられるようになります。そのため、保存療法よりも早く社会復帰・スポーツ復帰が可能です。
メリットは手術でアキレス腱を強固に修復でき、スポーツ復帰が早いことです。しかし、費用や手術での感染・神経損傷リスクはデメリットといえるでしょう。
なお、当院リペアセルクリニックではアキレス腱断裂に対しても再生治療に取り組んでいます。興味がある人はお気軽にメール相談もしくはオンラインカウンセリングでご相談ください。
\無料オンライン診断実施中!/
また、アキレス腱断裂後の手術については以下の記事でも解説しています。手術を検討している人はぜひチェックしてください。
まとめ|アキレス腱断裂後のリハビリメニューは下肢全体を鍛えよう!治療法で悩んだら受診がおすすめ
アキレス腱断裂後のリハビリメニューは、断裂したアキレス腱以外の部位も含めて下肢全体を鍛えるように行う必要があります。
また、アキレス腱断裂後のリハビリ内容や経過は、保存療法か手術療法によって異なります。治療方法は医師としっかり相談して、個人個人のライフスタイルに合わせて選択してください。
いずれの治療方法でも、アキレス腱の修復を待ちながら、段階的にリハビリを進めて、日常生活やスポーツに復帰することが大切です。
ちなみに、当院リペアセルクリニックではアキレス腱断裂に対しても再生医療をおこなっています。保存療法の選択肢として検討してみたい人は、お気軽にメール相談もしくはオンラインカウンセリングでご相談ください。
本記事を参考にアキレス腱断裂後のリハビリについての理解を深めて、医師や理学療法士と連携しながら回復を目指しましょう。
\無料オンライン診断実施中!/
アキレス腱断裂についてよくある質問
アキレス腱断裂は手術が必要ですか?
A:必ず手術というわけではありません。
アキレス腱断裂では必ずしも手術が必要ではなく、保存療法という選択肢もあります。しかし手術をした方がスポーツ・社会復帰が早くできるため、ライフスタイルに合わせて治療方法を選択してください。
アキレス腱断裂後はどんなリハビリをしますか?
A:足首だけでなく、下肢全体で運動を進めていきます。
アキレス腱断裂後はアキレス腱に負担がかからないように、股関節や膝などを動かしていきます。アキレス腱の修復度をみながら、足首も徐々に負荷をかけていき、無理せず動かすことが重要です。なお、リハビリも手術をした方が経過が早く進みます。