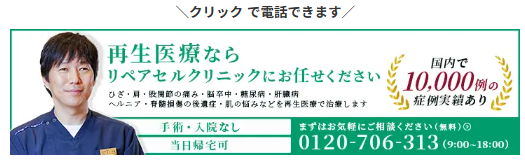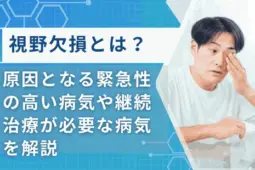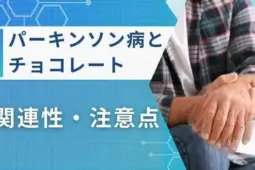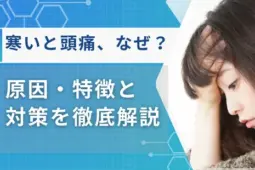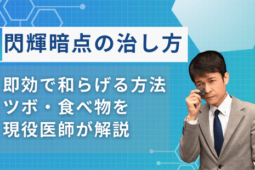- 頭部
- 頭部、その他疾患
高次脳機能障害で怒りやすくなる?家族への適切な対応を紹介
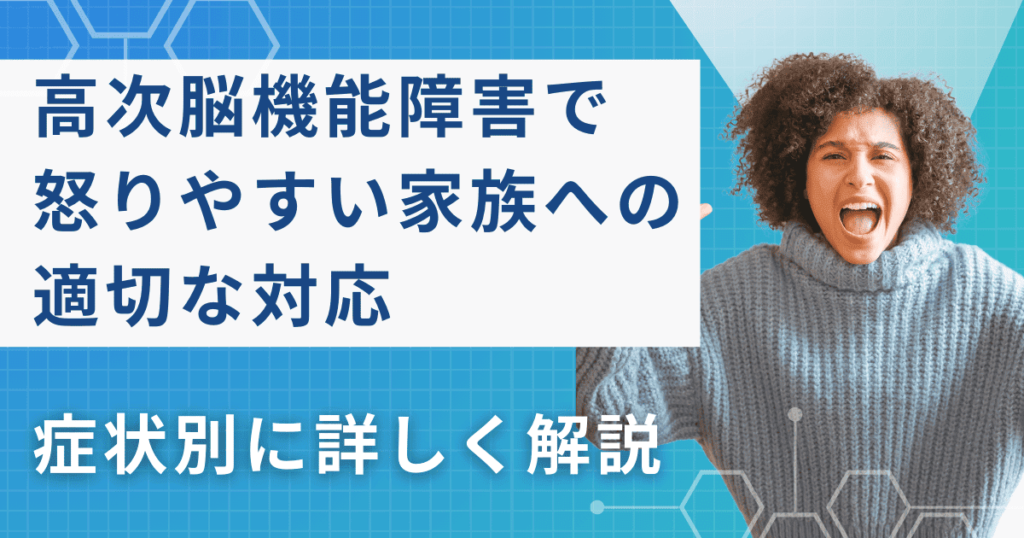
高次脳機能障害によって、「急に怒りやすくなった」「感情の起伏が激しくて対応に困っている」といったご家族さまも少なくありません。
脳血管障害によって脳細胞が損傷すると、感情を適切にコントロールする機能が低下し、怒りやすくなる症状(社会的行動障害)がみられます。
本記事では、高次脳機能障害によって怒りやすい患者様への対応や、治療法について解説します。
また、高次脳機能障害の根本治療につながる再生医療も紹介しているので、患者様との接し方にお困りの方は、ぜひ参考にしてください。
\根本治療につながる再生医療とは/
再生医療とは、機能障害や機能不全になった脳細胞に対して、体が持つ再生能力を利用して損なわれた機能を再生させる医療技術のことです。
怒りやすくなる症状をはじめとした高次脳機能障害の治療には、先端医療である再生医療をご検討ください。
【こんな方は再生医療をご検討ください】
- 高次脳機能障害の症状を治療したい
- 現在受けている治療やリハビリで期待した効果が得られていない
- 患者本人が治療やリハビリに積極的になれない
再生医療では、損傷した脳細胞に対してアプローチできる治療法で、従来の治療では元に戻らないとされている脳細胞の改善が期待できます。
「現在の治療で期待した効果がでていない」「患者様が治療やリハビリに積極的になれない」という方は、ぜひ再生医療を検討してみましょう。
詳しい治療法については、再生医療を専門とする当院「リペアセルクリニック」にお問い合わせください。
目次
高次脳機能障害の影響で怒りやすい性格になる人は多い
高次脳機能障害の影響で怒りやすい性格になる人は少なくありません。高次脳機能障害にはさまざまな症状がありますが、そのうちの一つが社会的行動障害です。
社会的行動障害とは、状況に応じた感情や言動のコントロールが難しくなる障害です。
厚生労働省の調査によると、社会的行動障害の具体的な症状として最も多いのが「感情コントロールの障害・易怒性」で、対象者の85%に現れているという結果でした。(文献1)
なお、本人が社会的行動障害に対する家族の不安や負担を理解していないケースも多く、対応の難しさを感じる方も少なくありません。
まずは怒りやすさが高次脳機能障害による影響であると理解し、対応を工夫しましょう。
高次脳機能障害の種類や原因など、包括的な解説を見たい方は「【医師監修】高次脳機能障害とは|種類・原因・治療法を解説」をご覧ください。
高次脳機能障害の症状について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
【症状別】高次脳機能障害で怒りやすい人への対応例
怒りやすいと一言でいっても、怒りの原因や具体的な症状はさまざまです。
以下で、高次脳機能障害の影響で怒りやすい人への対応例を症状別に解説します。
怒りが爆発する場合
高次脳機能障害の影響によって、患者が怒りを爆発させることがあります。高次脳機能障害患者の怒りが爆発した場面では、以下のポイントを押さえて対応しましょう。
- イライラしてきたと感じたら一時的に本人を一人にさせる
- その場で本人の行動に介入しない
- 本人の怒りにさらされる疲労やストレスを抱え込まない
- どのような場面で怒りが爆発したかを記録する
爆発した怒りにさらされることで、周囲は疲労や負担を感じます。怒りやすい人の対応においては、特定の人にこうしたストレスを集中させないための工夫も必要です。
▼再生医療に関する無料相談はこちらから
>>(こちらをクリックして)今すぐ電話で相談してみる
感情のコントロールが難しい場合
高次脳機能障害患者が怒りやすいのは、感情のコントロールが難しいためです。感情のコントロールが難しい人に対しては、以下のような対応を心がけましょう。
- 本人をイライラの原因から離す
- 気分を切り替えるためのきっかけを決めておく
- 感情を表に出しすぎるデメリットを冷静に伝える
- どのような態度が望ましいか、落ち着いているときに一緒に考える
感情のコントロールが難しくて怒りやすい場合は、本人の気持ちが落ち着いているタイミングで一緒に対応の仕方を考えておくことがポイントです。
周囲の刺激にすぐ反応してしまう場合
高次脳機能障害の影響で怒りやすい人のなかには、周囲の刺激にすぐ反応してしまうケースがあります。周囲からの刺激を減らすためには、具体的に以下のような対応が効果的です。
- 行動する前に一呼吸を置くよう伝える
- イライラしたら深呼吸をするよう伝える
- 聴覚過敏の場合は耳栓やノイズキャンセラーを使用する
- トラブルの原因になる場所や人との接点を減らす
また、本人が集中しているときは、できるだけ刺激しないよう無理のない範囲で配慮しましょう。
欲求を抑えられない場合
高次脳機能障害の影響で怒りやすい人のなかには、欲求を抑えられなくてイライラするケースもあります。この場合、単に禁止するだけではなく、ルール作りやサポートを重視した対応が効果的です。
- 本人と相談してルールを決める
- 特定の行為がなぜ問題となるのかを丁寧に説明する
- 行動を制限するだけではなく対策もあわせて伝える
- 視覚的にわかりやすいようメモや写真に残す
本人が制限されていると感じるのではなく、自己管理のための協力だと納得できるよう支援することが大切です。
高次脳機能障害患者が怒りやすい場合の4つの基本対応
高次脳機能障害患者が怒りやすい場合は、本人への接し方だけではなく、生活環境を整えたり、支援者間で情報を共有したりすることも大切です。
以下で、高次脳機能障害患者が怒りやすい場合の基本対応について解説します。
▼ 高次脳機能障害への対応の仕方について詳しく知りたい方は、以下の記事もチェックしてみてください。
1.生活環境を整える
高次脳機能障害患者にとって、生活環境の乱れや不規則な生活リズムは、怒りを引き起こす要因になりかねません。 まずは、どのような状況で怒りやすいのかを観察し、以下のポイントを押さえて少しずつ生活環境を整えましょう。
- 毎日の生活に規則性を持たせる
- 静かな環境を確保する
- リラックスできる場所をつくる など
生活環境を整えて落ち着ける空間をつくることで、本人の心理的な安定を図ります。
2.第三者に相談する
高次脳機能障害患者が怒りやすいと感じるようになったら、早めに第三者に相談しましょう。症状の改善のためには、医師や作業療法士などと連携して、適切な治療とリハビリテーションを受けることが大切です。
とくに怒りのコントロールが難しい場合には、心理的なサポートも不可欠です。心理士やカウンセラーなどは、本人が感じている怒りや不安の根本的な原因を探る手助けをしてくれます。
また、周囲がどのように接したら良いか、適切な対処法についてアドバイスしてもらうことも可能です。
3.障害福祉・介護保険サービスを利用する
高次脳機能障害と診断されたら、症状に応じて、障害福祉サービスや介護保険サービスの利用を検討しましょう。公的制度の利用は、家族の負担を軽減できるだけではなく、本人がより安定した生活を送るための基盤になります。
|
サービス |
対象者 |
主なサービス内容 |
|---|---|---|
|
障害福祉 |
|
|
|
介護保険 |
|
|
公的制度や各種サービスを利用する際は、自治体の障害福祉窓口や地域包括支援センターに相談してください。
4.支援者間で情報を共有する
高次脳機能障害患者への対応においては、支援者間で情報を共有しておくことが大切です。家族のほか、医師や看護師、理学療法士などが協力して一貫した対応が可能になると、本人の混乱や怒りのきっかけを防ぐことにつながります。
人間関係における心理的な安全は、怒りやすい症状を和らげるために不可欠です。そのため、本人に直接「周囲が協力している」と伝えることも重要です。
支援者間のスムーズな連携が、患者の「自分は周りに支えられている」という気持ちを育むことにつながります。
なお、リペアセルクリニックでは、メール相談やオンラインカウンセリングを実施しています。高次脳機能障害の症状がなかなか改善せずにお悩みの方は、ぜひ気軽にご相談ください。
\無料オンライン診断実施中!/
高次脳機能障害の治療法
ここでは、高次脳機能障害の主な治療法について解説します。
- 薬物療法
- リハビリテーション
- 再生医療
以下で、それぞれの治療法について解説するので、医師と相談しながら、症状に合わせて適切なアプローチを図ってください。
▼ 以下の記事では、高次脳機能障害の回復事例を紹介しています。
高次脳機能障害は回復する?事例やリハビリの重要性を現役医師が解説
薬物療法
薬物療法の主な目的は、症状の軽減と生活の質の向上です。
脳の神経伝達物質のバランスを整える作用がある薬のほか、抗精神病薬や認知機能を改善するための薬が用いられます。
たとえば、抗精神病薬は、イライラや興奮を落ち着ける効果が期待されます。薬物療法は、感情の起伏を穏やかにし、高次脳機能障害の影響で怒りやすい人の精神状態を安定させるために効果的です。
ただし、薬物療法はあくまで症状のコントロールを目的としているため、根本的な治療法ではない点を理解しておく必要があります。高次脳機能障害の症状を改善するためには、薬物療法だけではなく、心理的なサポートを含めて多角的にアプローチしましょう。
リハビリテーション
リハビリテーションは、高次脳機能障害の回復において重要な役割を果たします。高次脳機能障害のリハビリテーションには、主に以下のような内容が含まれます。
- 理学療法
- 作業療法
- 言語療法
- 認知行動療法
なかでも、高次脳機能障害の影響で怒りやすい人に対しては、認知行動療法が効果的です。認知行動療法とは、物事の受け取り方や考え方など、認知に働きかけて気持ちを楽にする心理療法の一種です。
認知行動療法を取り入れることで、怒りやストレスなどの感情をコントロールしやすくなる効果が期待できます。
▼ 高次脳機能障害のリハビリテーションについて詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。
再生医療
再生医療は、高次脳機能障害の治療効果が見込める点で最近注目を集めている治療法です。自然治癒力を最大限に引き出すために用いられる医療技術で、幹細胞や血小板の投与により症状改善の一助となる場合があります。
高次脳機能障害は進行性の障害ではないものの、薬物療法やリハビリテーションで思うような改善が見られないケースも珍しくありません。
近年は再生医療の研究が進み、幹細胞治療によって高次脳機能障害の原因である脳卒中の後遺症が回復した事例も数多く報告されています。
怒りやすくなる症状をはじめとした高次脳機能障害の治療には、先端医療である再生医療をご検討ください。
【こんな方は再生医療をご検討ください】
- 高次脳機能障害の症状を治療したい
- 現在受けている治療やリハビリで期待した効果が得られていない
- 患者本人が治療やリハビリに積極的になれない
再生医療では、損傷した脳細胞に対してアプローチできる治療法で、従来の治療では元に戻らないとされている脳細胞の改善が期待できます。
当院リペアセルクリニックでは、専門の医師・スタッフによる無料のカウンセリングも実施しており、再生医療による治療内容や注意点について丁寧にご説明いたします。
「高次脳機能障害を根本的に治したい」「再生医療について詳しく知りたい」という方は、ぜひ当院までご相談ください。
まとめ・高次脳機能障害患者が怒りやすい場合は第三者に相談して対応しよう
高次脳機能障害患者が怒りやすいのは、社会的行動障害の一種です。脳の損傷によって感情のコントロールが難しくなり、怒りやすくなるケースも珍しくありません。
高次脳機能患者が以前と比べて怒りやすくなったと感じたら、早めに第三者に相談しましょう。
怒りにさらされることは、本人だけではなく、周囲にとって心理的負担が大きいものです。第三者への相談や公的制度の活用を通して、周囲の負担を減らせるほか、本人が生活しやすい環境づくりも可能です。
高次脳機能障害は、適切なアプローチによって症状の改善を目指すことが可能です。怒りやすい症状への対応に悩んでいる場合は、早めに専門家に相談してサポートを受けましょう。
当院リペアセルクリニックでは、専門の医師・スタッフによる無料のカウンセリングを実施しており、再生医療についてわかりやすくご説明いたします。
「高次脳機能障害を根本的に治したい」「再生医療について詳しく知りたい」という方は、ぜひ当院までご相談ください。
参考文献
厚生労働省「社会的行動障害への対応と支援」
https://www.rehab.go.jp/application/files/9915/7559/7229/201912_.pdf