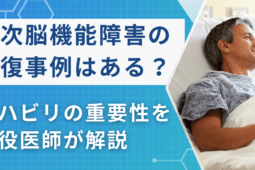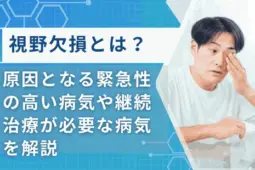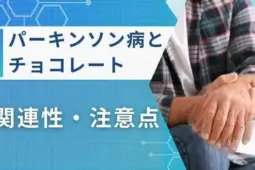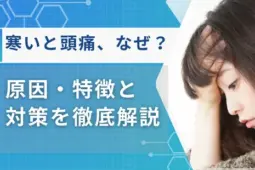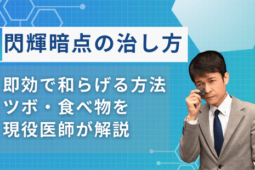- 頭部
- 頭部、その他疾患
【医師監修】高次脳機能障害のリハビリ方法とは?効果や期間を合わせて解説

「高次脳機能障害のリハビリ方法を知りたい」
「高次脳機能障害のリハビリ内容を把握しておきたい」
高次脳機能障害のリハビリがこれから始まるものの、流れやどのくらいの期間行われるのかと疑問を持つ方もいることでしょう。
高次脳機能障害のリハビリ方法や効果を事前に理解しておくことで、今後のリハビリをスムーズに進めることができます。
本記事では、現役医師が高次脳機能障害のリハビリについて詳しく解説します。記事の最後にはリハビリについてよくある質問をまとめていますので、ぜひ参考にしてみてください。
当院「リペアセルクリニック」の公式LINEでは、再生医療の情報提供と簡易オンライン診断を実施しております。
高次脳機能障害の症状にお悩みの方は、ぜひ一度公式LINEにご登録ください。
目次
高次脳機能障害におけるリハビリの目的と効果
| 目的と効果 | 詳細 |
|---|---|
| 日常生活の自立を促進する | 記憶力・注意力・判断力などの改善を通じた、食事や身支度、家事など日常動作の自立支援 |
| 社会復帰・職場復帰を支援する | 対人関係やコミュニケーション能力の向上、作業遂行力の回復を目的とした社会・職業生活への適応支援 |
| 長期的に安定した生活を維持する | 感情コントロールやストレス対処能力の向上による、精神的安定と継続的な生活基盤の確立 |
高次脳機能障害はリハビリにより、症状の改善や進行の遅延が見込めます。
「高次脳機能障害のリハビリテーション」によると、リハビリの実施により家事手伝い・何もしていない人の割合が34.2%から20.7%に減少したという結果が示されています。
また、リハビリは認知機能の改善だけでなく、日常生活の自立の促進や社会復帰、さらには長期的に安定した生活を維持するための精神的自立の支援においても欠かせません。
さらに、社会復帰した人は30.6%から43.7%に増加した結果も報告されています。(文献1)
これらの結果から、リハビリによって高次脳機能障害の症状が改善し、社会復帰につながる可能性が示唆されています。
日常生活の自立を促進する
| 理由 | 詳細 |
|---|---|
| 認知機能の低下により生活動作が難しくなるため | 記憶・注意・判断力の低下による、食事や身支度など日常動作の不安定化 |
| 家族・介護者の負担軽減につながるため | 生活動作の自立による、介護にかかる時間や労力の軽減 |
| 本人が主体的に生活できるようになるため | 自己管理力・実行力の獲得による、安定した生活の実現 |
| 自尊心や意欲の維持につながるため | 成功体験の積み重ねによる、自信や前向きな気持ちの回復 |
| 長期的な生活の質を高めるため | QOL(生活の質)の維持・向上と、安定した生活基盤の確立 |
(文献2)
高次脳機能障害のリハビリでは、日常生活の自立が重要な目標です。認知機能の低下により、これまで当たり前にできていた動作が難しくなることがあります。
しかし、生活に即した訓練を重ねることで、少しずつ自分で行える範囲を広げることが期待できます。
自立した生活は介護負担の軽減だけでなく、本人の自信や意欲を支え、長期的に安定した生活を送るための基盤といえるでしょう。
社会復帰・職場復帰を支援する
| 理由 | 詳細 |
|---|---|
| 役割・目的意識の回復 | 仕事や家事、社会活動を通じた、自分の役割や生きがいの再獲得 |
| 認知機能の維持・向上 | 注意力・判断力・記憶力などの継続的使用による、認知機能の維持と改善 |
| 経済的・生活的安定 | 就労や社会参加による、収入確保と生活リズムの安定 |
| 本人・家族の心理的負担軽減 | 社会とのつながりによる孤立感の軽減と、家族の精神的・経済的負担の緩和 |
| 生活の崩れや再発予防 | 社会活動による生活習慣の安定と、無気力・引きこもりの予防 |
(文献3)
高次脳機能障害のリハビリにおいて、社会復帰や職場復帰は生活の質を高める大切な目標です。
社会参加を通じて役割や目的意識を取り戻すことは、心の安定や意欲の回復につながります。
また、仕事や社会活動で認知機能を使い続けることは、機能の維持にも有効です。
経済面や生活リズムの安定、家族の負担軽減にも寄与するため、段階的な支援を通じた社会復帰が欠かせません。
長期的に安定した生活を維持する
| 理由 | 詳細 |
|---|---|
| 長期的な経過をとりやすい疾患特性 | 症状の慢性化による、生活不安定やトラブル発生リスクへの継続的対応 |
| 症状変化に応じた支援調整の必要性 | 定期的評価と支援内容の見直しによる、生活の混乱や再発の予防 |
| 生活習慣の安定による症状管理 | 食事・睡眠・活動量の調整による、認知機能と精神状態の安定 |
| 本人・家族の精神的負担軽減 | 生活安定による不安や疲弊の軽減と、安心感の確保 |
| 社会参加・自立の継続支援 | 就労や日常生活を続けるための、長期的フォローアップ体制 |
(文献4)
高次脳機能障害は症状が長く続くことが多く、時間の経過とともに生活上の課題が変化する場合があります。
そのため短期間のリハビリだけでなく、長期的に生活の安定を支える視点が重要です。
生活習慣を整え、必要に応じて支援内容を見直すことで、心身の負担を軽減できます。継続的な見守りと支援は、社会参加や自立した生活を無理なく続けるための基盤となります。
高次脳機能障害におけるリハビリの流れ
高次脳機能障害のリハビリでは治療に加えて、設定した目標の達成に向けた訓練を段階的に進めていきます。
医学的リハビリの流れは、以下の通りです。
| 1.リハビリ計画を立てる | 高次機能障害に関する診断や評価結果に基づいたリハビリ計画を立てる |
|---|---|
| 2.具体的な目標を設定する | 当事者がイメージしやすく、かつ短期間で実現可能な目標を決める |
| 3.リハビリを実施する | リハビリ計画と目標設定をもとにリハビリを開始。訓練は段階的に進める |
| 4.結果を判定し、目標の修正 | リハビリの評価を定期的に繰り返し、プログラムの妥当性や体制を見直 |
高次脳機能障害のリハビリは漠然と進めていくのではなく、医師の指導のもとで定期的に評価を繰り返しながら、最終的な目標の計画を立てていく流れとなります。
1.リハビリ計画を立てる
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 認知機能の評価 | 記憶・注意・判断力・遂行機能など、日常生活に必要な認知能力の把握 |
| 日常生活動作の評価 | 食事・着替え・移動・家事など、生活動作の自立度の確認 |
| 行動・情緒面の評価 | 感情コントロールや対人関係の変化、行動上の課題の把握 |
| 家族状況・生活環境の確認 | 家族の支援負担や生活環境、家庭・職場での困りごとの確認 |
| 本人・家族の目標設定 | 希望する生活の共有と、短期・中期・長期目標の明確化 |
(文献5)
リハビリ計画を立てる段階では、現在の症状や生活状況を評価し、本人に合った支援の方向性を定めます。
認知機能や日常生活動作だけでなく、行動面や家族の状況も含めて確認することで、無理のない計画が立てられます。
本人と家族が目指す生活を共有し、段階的な目標を設定することは、リハビリを継続する上で欠かせません。
2.具体的な目標を設定する
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 改善したい症状・動作の具体化 | 記憶・注意・遂行機能など、向上させたい能力と到達レベルの明確化 |
| 日常生活に即した目標設定 | 家庭生活や社会参加に必要な動作の整理と、自立度の設定 |
| 本人の希望・価値観の反映 | 本人が望む生活や大切にしたいことの尊重 |
| 家族・支援者との共有 | 目標や支援方針の共有による、支援体制と役割分担の調整 |
| 短期・長期目標の設定 | 段階的な達成を目指した短期目標と長期目標の設定 |
(文献6)
リハビリの目標設定は、回復を実感しながら取り組むための重要な工程です。改善したい症状や動作を具体的にすることで、訓練の方向性が明確になります。
また、日常生活に即した目標や本人の希望を反映することは、意欲の維持において欠かせません。
家族や支援者と目標を共有し、短期・長期の目標を段階的に設定することで、無理のないペースでリハビリを継続できます。
3.リハビリを実施する
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 認知機能への訓練 | 記憶・注意・判断力・遂行機能の改善を目的とした、課題練習や補助具活用 |
| 日常生活動作の練習 | 食事・着替え・移動・買い物など、生活動作の段階的な練習 |
| 行動面・情緒面の支援 | 感情調整や対人関係への対応力向上を目的とした行動理解とトレーニング |
| 社会生活・就労に向けた訓練 | 社会参加や復職を見据えた、生活スキルや職場適応力の訓練 |
| 家族・支援者との連携 | 支援方法や役割分担の共有による、生活維持と負担軽減 |
(文献7)
リハビリを実施する段階では、設定した目標に基づき、日常生活に直結する訓練を計画的に行います。認知機能の訓練だけでなく、生活動作や行動面、社会生活への対応力を高めることが重要です。
また、家族や支援者と連携しながら進めることで、家庭での対応が統一され、無理のない生活が実現します。
本人の状態に合わせた段階的なリハビリは、機能改善と生活の安定を支える基盤となります。
4.結果を判定し、目標の修正
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 達成状況の評価 | 設定目標に対する達成度と、認知機能・生活動作・行動面の変化の確認 |
| 改善要因の分析 | 効果がみられた訓練や支援内容の整理と有効要因の把握 |
| 課題の整理 | 改善が不十分な機能や動作の原因検討と支援方法の見直し |
| 生活変化の反映 | 生活環境や家族状況、体調変化を踏まえた支援内容の調整 |
| 目標の修正と再設定 | 現実的で取り組みやすい短期・長期目標の再設定 |
(文献2)
リハビリの結果を判定する段階では、これまでの取り組みが目標達成に寄与しているかを確認します。
高次脳機能障害は経過に個人差があるため、計画を固定せず、状況に応じて柔軟に見直すことが大切です。
達成できた点と課題を整理し、生活環境や体調の変化も反映させながら、次の目標を再設定します。この繰り返しにより、無理のないリハビリ継続と生活の安定が実現します。
高次脳機能障害におけるリハビリ期間
高次脳機能障害のリハビリ期間は、6カ月~1年ほどです。はじめの6カ月間は、症状回復を目的に医学的リハビリを受けます。
6カ月目以降は、必要に応じて生活訓練や機能訓練を実施するのが一般的な流れです。「高次脳機能障害者支援の手引き」によると、リハビリを受けた74%が6カ月、97%が1年でリハビリの成果が得られています。
高次脳機能障害の場合、症状によって異なりますがリハビリ期限となる180日を超えて訓練を受けられるため、訓練期間は6カ月〜1年が目安です。(文献8)
高次脳機能障害におけるリハビリ内容と方法
| リハビリ内容と方法 | 詳細 |
|---|---|
| 環境調整 | 生活環境や作業環境の工夫による、混乱を減らす支援 |
| 要素的訓練 | 記憶・注意・判断力など、認知機能の一部を集中的に高める訓練 |
| 代償訓練 | メモやスマートフォンなどを活用した、低下した機能を補う方法の習得 |
| 行動変容療法 | 問題行動の理解と望ましい行動への置き換えを目的とした支援 |
| 認知行動療法 | 考え方や受け止め方の調整による、不安や抑うつへの対処支援 |
| 社会技能訓練 | あいさつや会話、対人関係の練習による社会適応力の向上 |
| 調理行動 | 手順理解や配慮を含めた、調理動作を通じた生活技能の訓練 |
高次脳機能障害におけるリハビリは、認知機能や生活能力の改善を多面的に支援することが主な目的です。
環境調整では、生活上の混乱を減らす工夫を行い、要素的訓練では記憶や注意力など特定の機能を強化します。
また、代償訓練は外部ツールを活用して日常生活を支え、行動変容療法や認知行動療法では行動や心理面の安定を図ります。
さらに、社会技能訓練や調理行動を通じて、実践的な社会適応力と生活技能の向上を目指します。
環境調整
高次脳機能障害のリハビリでは、治療環境を整えることが大切です。
環境調整により、環境要因による混乱を減らすことができ、当事者が余分な負担やエネルギーを費やさずに取り組めるようになります。
環境調整における症状別の対策は、以下の通りです。
| 症状例 | 対策 |
|---|---|
| 注意障害 | 気が散りやすい環境とならないよう配慮する |
| 左半側空間無視 | ベッドの左側から降りられないよう壁につける |
| 失算 | 時計をアナログ時計にする |
| 視空間失認 | 階段に手すりをつける |
症状によって人的環境を整えるのもポイントです。たとえば、注意障害では集中力が持続しにくく、複数の相手との会話が難しい場合があります。
そのためリハビリでは、刺激を減らし、複数人ではなく1対1の会話環境を整えることが望まれます。
また、注意障害では短時間で区切った課題を用い、左半側空間無視では視線誘導を意識した動作練習の継続が欠かせません。(文献9)(文献10)
失算や視空間失認に対しては、実生活に即した反復練習を取り入れ、環境で得た効果を定着させていきます。
要素的訓練
要素的訓練は注意障害や記憶障害など、症状の改善を目的とする訓練です。高次脳機能障害における症状の回復では、症状別に作業を実践する方法が再構築に寄与すると考えられています。
たとえば、相手の話を理解できない失語症では、実物や写真などを提示し、それを基に反応してもらう方法が有効です。
また、集中力が持続しにくい注意障害に対しては、問題集を用いた課題に取り組むことで、注意機能を高める要素的訓練として効果が期待できます。
なお、要素的訓練を実践する際は、当事者の意欲や理解度を踏まえるとともに集中しやすい環境を整え、目的に合った治療方法を選択することが、目標達成において欠かせません。(文献9)
代償訓練
代償訓練とは、症状の対処法を身につけるためのリハビリです。
対処法を身につけることで、自ら障害を補いながら仕事や日常生活の質を維持できるようになります。
たとえば、注意障害には以下の対処法があります。
| 対処場面 | 具体的な方法 |
|---|---|
| 集中が途切れやすい場合 | 適宜休憩を挟む |
| 作業に時間がかかる場合 | 作業時間を長めに設定する |
| 手順がわかりにくい場合 | 工程表を提示する |
リハビリを行う際は自己判断に頼らず、医師の指導のもとで無理な負荷を避け、継続的に取り組むことが大切です。
行動変容療法
行動変容療法は、オペラント条件付け理論に基づいたリハビリです。オペラント条件付け理論とは、行動とその結果を結びつけ、望ましい行動が報酬につながると学習させる方法です。
たとえば、突然怒り出す行動を減らすため、感情を抑えられた場面で褒めたり達成感を与えたりします。
一方、怒りが出た場合は過度に反応せず、落ち着いた行動を促します。このように、望ましい行動が評価される経験を積み重ね、怒りの頻度を徐々に減らしていくのが行動変容療法です。
認知行動療法
認知行動療法とは、物事の見方や考え方、行動を調整し、心理的安定を図るリハビリです。
高次脳機能障害における怒りやすい・うつなどの症状は、感情をうまく制御できないことから、怒りや抑うつが生じる場合があります。
認知行動療法では、障害や環境、周囲の対応などに対する否定的かつ誤った解釈を修正していくことが欠かせません。
また、怒りが生じる前に冷静さを保つ訓練を行うため、トラブル回避において重要なリハビリ方法のひとつといえるでしょう。
社会技能訓練
社会技能訓練は、高次脳機能障害の方が社会に復帰できるようにするリハビリです。主なリハビリ内容は、以下の通りです。
| 主な支援 | リハビリ内容 |
|---|---|
| 就労支援 | 職業訓練の場となるハローワークや障がい者職業総合センターなどの就労支援機関と連携して、復職の可能性を検討する。万が一、復職困難と判断された場合、リハビリで職業能力を高めていく |
| 自動車運転支援 | 自動車運転に際し、視野欠損や半側空間無視、運動操作能力の有無など運動能力評価や診断、指導を実施する |
また、グループの中で自分の考えや気持ち、相手に対する要求など社会で人と関わりながら生きていくためのスキルを身につける訓練も、社会技能訓練では実施します。(文献9)(文献11)
調理行動
調理行動では、調理に伴う危険性を理解し、自身の能力を把握することを目的とします。
調理は危険を伴う行動となるため、高次脳機能障害の当事者に自身の能力を認識してもらうことが重要です。
「高次脳機能障害者の自立に向けた調理行動振り返り支援システムに基づく認知リハビリテーション」によると、リハビリとして、当事者に自身の調理体験映像を見せ、客観的に自分の行動を振り返る機会を設けました。(文献12)
客観視によりリハビリに対する意欲向上が見込まれた事例であり、調理行動は高次脳機能障害の訓練として有効である可能性が示唆されました。
高次脳機能障害におけるリハビリ以外の治療方法
| リハビリ以外の治療方法 | 詳細 |
|---|---|
| 薬物療法 | 集中力低下・抑うつ・不安・不眠などの症状を和らげるための内服治療 |
| 食事療法 | 脳の回復を支える栄養素を意識した食事内容の調整 |
| 再生医療 | 損傷した脳機能の回復を目的とした先進的医療技術の活用 |
高次脳機能障害では、リハビリに加えて、注意力低下や気分の落ち込み、不眠などの症状を和らげ、日常生活の安定を図ることを目的とした薬物療法が行われます。食事療法は、脳の働きを支える栄養を意識し、体調管理や回復を内側から支援します。
再生医療は将来的な機能回復を目指す新しい治療として研究・活用が進められていますが、適用できる症状や医療機関が限られているため、医師と相談した上で検討することが大切です。
以下の記事では、高次脳機能障害の回復事例について詳しく解説しています。
薬物療法
薬物療法では、神経伝達物質のバランスを整えることで、注意力や集中力、記憶、情緒の安定を補助し、日常生活やリハビリへの取り組みを支えます。
認知リハビリや環境調整と併用することで効果が引き出されやすく、回復の土台を整える役割を担います。
一方で効果には個人差があり万能ではないため、医師の管理のもと副作用や症状の変化を評価しながら、補助的手段として慎重に用いることが重要です。
食事療法
| 理由 | 詳細 |
|---|---|
| 脳と身体に必要な栄養の安定供給 | 神経の修復や機能維持に必要なエネルギー・栄養素の確保 |
| 神経機能を支える成分の摂取 | オメガ3脂肪酸や抗酸化物質などによる脳機能維持の補助 |
| リハビリ効率の向上 | 体力・集中力・精神状態の安定による訓練効果の向上 |
| 摂食・嚥下障害への対応 | 食形態調整や環境配慮による適切な経口摂取の維持 |
| 生活習慣の改善と健康維持 | 合併症予防や再発防止につながる食生活の見直し |
(文献13)
食事療法は、高次脳機能障害の回復を支える重要な基盤のひとつです。脳や身体に必要な栄養を安定して摂取することで、神経機能の維持やリハビリに取り組むための体力・集中力を支えます。
また、摂食・嚥下障害がある場合でも、適切な工夫により安全な食事摂取が期待できます。食事療法は単独で行うものではなく、リハビリや医療的支援と併用し、個々の状態に合わせて取り入れることが大切です。
再生医療
高次脳機能障害におけるリハビリ以外の治療法には、再生医療があります。再生医療とは、けがや病気によって、機能障害に陥った組織や細胞の機能回復を目指す治療法です。
体の自然治癒力を高め、組織や機能などの修復を行うのが再生医療です。再生医療による治療は早いほど、脳機能の回復が期待できる場合があります。また、再生医療では、体内に存在する幹細胞の修復力を活用し、損傷した細胞の補完や機能回復を図ります。
体へ戻す幹細胞は患者自身の細胞を使用するため、拒絶反応やアレルギー反応などが起こりにくい点も再生医療の特徴です。
以下の動画では、当院で再生医療を受けた方の声を紹介しています。
リペアセルクリニックでは、高次脳機能障害の原因の一つとなる脳卒中の再生医療・幹細胞治療を実施しています。
メール相談やオンラインカウンセリングも提供していますので、再生医療について詳しく知りたい方はお気軽にご相談ください。

脳卒中のお悩みに対する新しい治療法があります。
リハビリで改善しない高次脳機能障害の後遺症は当院へご相談ください
高次脳機能障害は適切なリハビリにより症状の回復効果が期待できます。リハビリでは治療に加え、目標を設定した上で訓練を進め、期間はおおよそ6カ月から1年が目安とされます。
症状に応じて訓練内容は異なるため、定期的な評価を行いながら目標達成を目指すことが大切です。
リハビリで改善しない高次脳機能障害でお悩みの方は、当院「リペアセルクリニック」へご相談ください。当院では、高次脳機能障害に対して再生医療を用いた治療をご提案しています。
再生医療は、失われた脳機能の回復を目指す新しい治療法として注目されており、主に幹細胞を用いて脳細胞の修復や再生を促し、症状の改善を図ります。従来のリハビリや薬物療法と併用されることが多く、比較的副作用のリスクが低い点も特徴です。
ご質問やご相談は、「メール」もしくは「オンラインカウンセリング」で受け付けておりますので、お気軽にお申し付けください。
\無料オンライン診断実施中!/
高次脳機能障害のリハビリに関するよくある質問
高次脳機能障害のリハビリにおいてやってはいけないことはありますか?
高次脳機能障害のリハビリにおいてやってはいけないことは以下です。
| やってはいけないこと | 詳細 |
|---|---|
| 過度な負荷をかける運動や活動 | 身体・認知機能に無理を強いることによるけがや二次障害のリスク |
| 認知的・感覚的ストレスの過剰付与 | 強い刺激や情報過多による注意障害や疲労の悪化 |
| 補助なしで高い自立を求めること | 心理的負担や挫折感によるリハビリ意欲低下の懸念 |
| 医師の指示のない治療・訓練 | 障害特性に合わない対応による回復妨害の可能性 |
| 短期間での成果を過度に期待 | 焦りや失望感による精神的負担の増大 |
(文献14)
高次脳機能障害のリハビリでは、無理や焦りが回復を妨げることがあります。医師の指導のもと、負担や刺激を調整しながら、段階的に取り組む姿勢が大切です。
高次脳機能障害で利用できる支援制度はありますか?
高次脳機能障害で利用できる支援制度は以下が該当します。
| 支援制度 | 内容 |
|---|---|
| 障害者総合支援法による福祉サービス | 介護給付や訓練等給付による日常生活支援、生活動作訓練、就労支援、相談支援 |
| 障害者手帳による支援 | 手帳交付による公共サービス利用、施設利用料や税金、交通費などの減免 |
| 経済的支援制度 | 障害年金や医療費助成による生活費や医療・リハビリ費用の負担軽減 |
| 専門相談窓口・支援拠点 | 専門職による相談対応、支援制度の案内、家族や支援者への助 |
| 就労・復職支援制度 | 就労移行支援や職業リハビリによる無理のない就労や職場復帰の支援 |
気になる症状や利用できる支援制度については、主治医や地域の相談窓口に相談し、状況に合った支援を受けましょう。
高次脳機能障害のリハビリにおいて家族が気を付けるべきことはありますか?
高次脳機能障害のリハビリにおいて家族が気を付けるべきことは以下の表にまとめています。
| 気を付ける点 | 詳細 |
|---|---|
| 以前の姿に無理に戻そうとしない | 症状特性の理解と現状に合った関わりの尊重 |
| 刺激や変化の多い環境を避ける | 注意障害や疲労に配慮した生活環境の調整 |
| できることを少しずつ支援する | 小さな成功体験の積み重ねによる意欲維持 |
| 家族自身の心身ケア | 休息確保と支援サービス活用による負担軽減 |
| 専門家・支援制度の活用 | 医療・福祉との連携による継続的支援 |
(文献15)
高次脳機能障害のリハビリでは、家族の理解と関わりが重要です。
回復を急がず本人のペースを尊重し、刺激を抑えた環境づくりや小さな成功を認める姿勢が意欲の維持につながります。
以下の記事では、高次脳機能障害への対応の仕方を詳しく解説しています。
高次脳機能障害の家族が抱えるストレスへの対処法を教えてください
高次脳機能障害の家族は、長期的な支援により心身の負担を抱えやすくなります。休息やセルフケアの時間を確保し、外部の福祉サービスや相談窓口を活用することが大切です。
また、同じ立場の家族との交流や正しい知識の共有は、孤立感や不安の軽減につながります。負担が強い場合は、医師への相談も検討しましょう。
以下の記事では、高次脳機能障害の対処法について詳しく解説しています。
【関連記事】
高次脳機能障害患者の家族が抱えるストレスは?対処法や支援制度を現役医師が解説
参考文献
高次脳機能障害支援マニュアル|平成30–31年度 厚生労働科学研究 高次脳機能障害の障害特性に応じた 支援マニュアルの開発のための研究班
高次脳機能障害のリハビリテーションと連携|リハビリテーション連携科学 26:1-11 2025
高次脳機能 障がい支援 ハンドブック|大阪府障がい者自立支援協議会
高次脳機能障害者に対する支援プログラム~利用者支援、事業主支援の視点から~|独立行政法人 高齢・障害者雇用支援機構 障害者職業総合センター職業センター
高次脳機能障害制度利用マニュアル|茨城県高次脳機能障害支援センター令和6年6月版
高次脳機能障害のリハビリテーション | KOMPAS – 慶應義塾大学病院 医療・健康情報サイト
高次脳機能障害に対するリハビリテーション治療―患者・家族会との連携―|Jpn J Rehabil Med Vol. 58 No. 4 2021
高次脳機能障害と暮らす|香川大学医学部附属病院 リハビリテーション部 作業療法士 津川 亮介
高次脳機能障害者の自立に向けた調理行動振り返り支援システムに基づく認知リハビリテーション|J-STAGE
TBI Recovery: Essential Tips & What to Avoid After a Brain Injury|NeuLife REHABILITATION