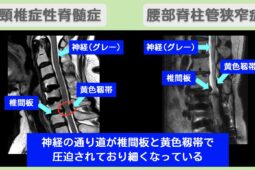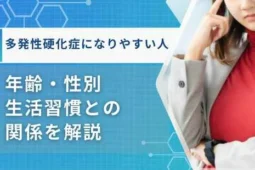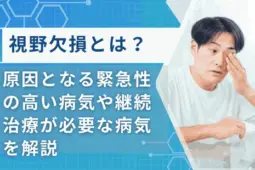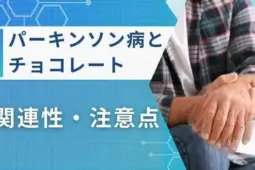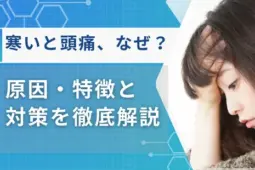- 頭部
- 頭部、その他疾患
セロトニン欠乏脳は自己チェック可能!確認方法や不足している場合の対策を解説
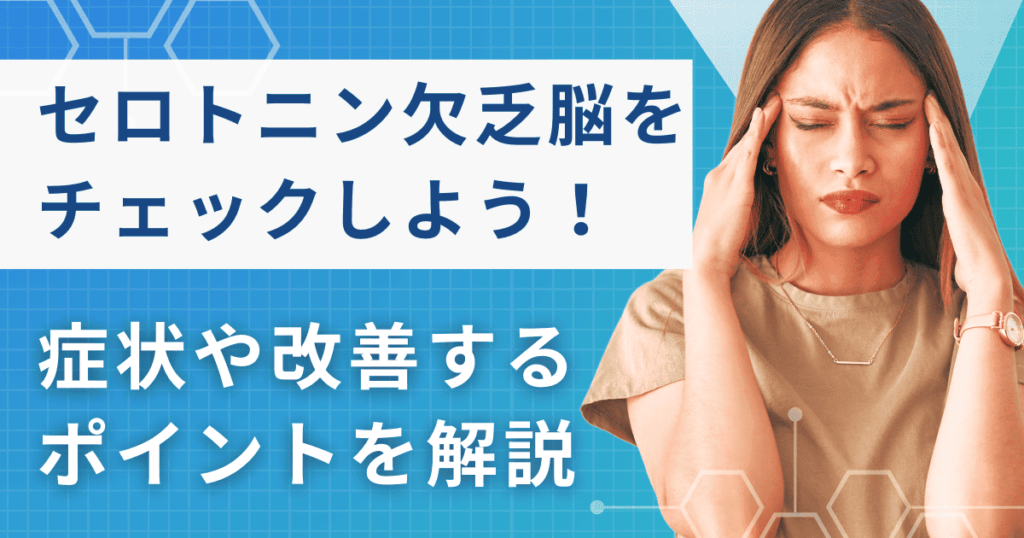
「最近イライラしたり、落ち込んだりしやすい」
「セロトニンは幸せホルモンと聞いたが、自分は不足しているのではないか」
このようなお悩みはありませんか?
日常の中で、些細なことでも強い怒りを感じる、また気持ちが沈んでしまう場合は、セロトニンが不足している可能性があります。セロトニンは別名「幸せホルモン」と呼ばれ、心を穏やかに保つためにとても大切なホルモンです。
この記事では、セロトニンが不足している際に起こる「セロトニン欠乏脳」の自己チェック方法と、対策についてご紹介します。セロトニン不足のお悩みの参考になれば幸いです。
自分の状態がセロトニン欠乏脳ではないか不安、またセロトニン欠乏脳による気分の不調を解消したいと感じたら、当院のメール相談 やオンラインカウンセリングもご活用ください。
目次
セロトニン欠乏脳チェック【当てはまったら要注意】
いつもよりキレやすい、気持ちが落ち込みやすいといった場合には「セロトニン欠乏脳」の状態かもしれません。
セロトニンは脳内で作られる神経伝達物質の1つで、喜びの感情を司るドーパミンや怒り・恐怖といった感情を司るノルアドレナリンといった神経伝達物質をコントロールする働きがあります。(文献1)
そのため、セロトニンが欠乏すると、気分が安定しにくくなります。
「もしかしたら自分もセロトニン欠乏脳ではないか」と思う方もいるでしょう。下に「セロトニン欠乏脳」になると現れる変化をチェックリストとしてまとめています。複数当てはまる方はセロトニン欠乏からの不調かもしれないので、注意が必要です。
|
1.疲れやだるさが続く 2.動悸やめまいがする 3.慢性的な頭痛がある 4.よく眠れない、すっきりと起きられない 5.食欲が湧かない 6.身支度が整わない 7.時間通りの行動が難しい 8.遅刻や早退が多い 9.いつもよりミスが多い 10.自分は無価値だと思う 11.気分が落ち込みやすい 12.理由もなく不安になる、緊張する 13.すぐにイライラしてしまう 14.他の人には聞こえない声が聞こえる |
セロトニン欠乏脳の症状6選
セロトニン欠乏脳は、脳の中でセロトニンの分泌が少なくなることで起こります。有田秀穂氏の論文によれば「セロトニン欠乏脳」の代表的な症状として以下の6つが挙げられています。(文献2)
- 朝すっきりと起きられない
- 自律神経失調症の症状がある
- 背筋や顔の筋緊張が弱い
- 痛みに弱い
- キレやすい状態
- 生活習慣が乱れている
それぞれの項目について詳しく解説します。
1.朝すっきりと起きられない
セロトニン欠乏脳になると朝すっきりと起きられなくなります。
なぜなら、朝の調子を整えるための自律神経の働きに、セロトニンが関わっているからです。
自律神経には、体を活発に動かすための交感神経と、体を休ませるための副交感神経があります。眠っている時には体をリラックスさせる副交感神経が働いていますが、目覚めてから体を動かすためには交感神経を働かせるというのが通常の働きです。セロトニンは、この切り替えを円滑にするために用いられます。
そのため、セロトニン欠乏脳の状態では、うまく自律神経が切り替わらず「朝目覚めても、なんだかすっきりしない」と感じやすくなります。
2.自律神経失調症の症状がある
セロトニンが欠乏すると、自律神経失調症の症状が出ます。
自律神経失調症とは、病気ではないのに体になんらかの不調がある状態です。自律神経失調症では、全身のだるさやめまい、頭痛、動悸などが現れます。(文献3)
こちらも、自律神経の切り替えにセロトニンが関わっているためです。自律神経は臓器とつながっているため、セロトニンの欠乏により交感神経と副交感神経の働きが乱れると、各臓器、そして全身に悪影響を及ぼします。
そのため、自律神経失調症のような症状があるときには、セロトニン欠乏脳が疑われます。
3.背筋や顔の筋緊張が弱い
背筋や顔の筋肉の収縮が弱くなることも、セロトニン欠乏脳の特徴です。
セロトニンは筋肉の収縮を司る「運動ニューロン」という神経細胞にも影響を及ぼします。とくに、姿勢を維持するための体幹や筋肉、そして顔のまぶたや頬の筋肉の収縮を司っています。そのため、セロトニンがしっかり分泌されていると、背筋がピンとして顔に締まりが出るのです。
いつもより姿勢が悪い、顔がゆるんでいるといったときには、セロトニンが上手く分泌していないかもしれません。
4.痛みに弱い
セロトニンは、脊髄から脳に痛みを伝える伝達路にも作用し、痛みを和らげる鎮痛作用も持っています。そのため、セロトニンが少なくなると、痛みが脳に伝わりやすくなり、少しの傷やけがでも痛みの感じ方が強くなってしまいます。
これはキレやすい子どもにとくに見られやすいと言われています。
5.キレやすい状態である
セロトニン欠乏脳の状態になると、ささいなことでもキレやすくなります。
原因としては「青斑核ノルアドレナリン神経」という、ストレスを他の神経に伝える道筋を抑えられなくなるからです。ストレスが他の神経にすぐ伝わってしまうと、ストレスをうまく制御できず、感情的になる、普通では考えられないような行動を取るといったことが起こります。
いつもよりキレやすい、すぐ感情が爆発してしまって手が付けられなくなってしまう、といった状態が続く場合は、セロトニンが足りていないかもしれません。
6.生活習慣が乱れている
セロトニンが少なくなると、眠りが浅く朝起きられなくなったり、食欲がコントロールできなくなったりして生活習慣が乱れてしまいます。
まず、睡眠にはレム睡眠とノンレム睡眠という2つの種類があります。レム睡眠は浅い眠りで体がよく休まっている状態、ノンレム睡眠は深い眠りで脳がよく休まっている状態のことです。セロトニンが足りなくなるとレム睡眠の時間が短くなり、体が十分に休まらなくなってしまいます。そのため、朝すっきり起きられず生活習慣の乱れにつながってしまうのです。
そして、セロトニンは食欲の調節にも重要です。ドパミンという神経伝達物質が食欲を司っていますが、この調節機能にもセロトニンが作用します。食欲をコントロールできなくなると、精神面にも体の健康にも悪影響が出てしまいます。
よく眠れているか、そして暴飲暴食はないかといった生活習慣についても確かめてみましょう。
セロトニン欠乏脳とは気持ちが揺らぎやすい状態
セロトニン欠乏脳になると、突然怒りが爆発したり、気分が落ち込んでしまったりと揺らぎやすい状態になります。この章では、そもそもセロトニンとはどのようなものか、そしてそこからどのようにセロトニン欠乏が起こるのかという部分について解説します。
セロトニンは「幸せホルモン」と呼ばれる
セロトニンは脳の「脳幹」と呼ばれる部分から分泌される神経伝達物質です。セロトニンが分泌されることで、喜びを感じる伝達物質と怒りや恐怖を感じる伝達物質の調節をし、心の安静を保ちます。分泌によって気持ちを穏やかに保ったり、幸福感を感じたりすることから「幸せホルモン」と呼ばれているのです。
また、セロトニンは腸でも作られています。ある文献によれば、腸内に細菌がいるマウスよりも、いないマウスの方がセロトニンの量が少なかったという研究があります。(文献4)
セロトニン欠乏脳は怒りやすさや気分の不安定を招く
セロトニンが欠乏すると、感情を司る神経伝達物質のバランスが崩れて、気持ちのコントロールが難しくなります。感情が不安定になると、仕事や人間関係がうまくいかなくなってしまうでしょう。有田氏の論文によれば、セロトニンの欠乏は生活習慣の乱れにより引き起こされるという結果があります。(文献2)
しかし、逆に言えば、生活習慣を整えればセロトニンの分泌を促せるということです。
次の項目でセロトニン欠乏脳を改善するときのポイントを6つ載せていますので、ぜひ今日から取り入れてみてください。
\無料オンライン診断実施中!/
セロトニン欠乏脳を改善するときのポイント
セロトニンは、食事や運動、そして日常生活の中での少しの工夫で分泌を促せます。(文献5)
すぐに実践できる内容ですので、ぜひお試しください。
1.バナナや乳製品などを積極的に摂る
2.リズム性の運動を行う
3.日光を浴びる習慣を持つ
各項目について、詳しく解説します。
1.バナナや乳製品などを積極的に摂る
セロトニンは、必須アミノ酸の1つであるトリプトファンから合成されます。必須アミノ酸とは、体の中では合成できないため、食品から摂る必要のある栄養素です。そのため、トリプトファンを多く含む食品を摂ることで、セロトニンを増やせます。
トリプトファンを含む食品としては、以下のようなものが挙げられます。
- 果物:バナナ、キウイなど
- 乳製品:牛乳、チーズなど
- 豆製品:大豆、納豆など
- 卵
- 種実類:ゴマ、アーモンドなど
日頃の生活に、プラス一品トリプトファンを含む食品を取り入れてみましょう。
2.リズム性の運動を行う
一定のリズムで行う運動もセロトニン欠乏の予防・改善に効果があるといわれています。論文によれば、運動として、歩行、咀嚼(そしゃく)、呼吸が挙げられています。
日々の生活の中で、以下のような行動を取り入れましょう。
|
歩行 |
少し息が上がるくらいのリズミカルな運動を取り入れましょう。 通勤や通学などの日々の生活のなかで、少し早足で歩いてみることも良いでしょう。また、時間のある方はウォーキングで歩く習慣を作るのもおすすめです。 |
|---|---|
|
咀嚼 |
噛む、という動きも等間隔でのリズム運動です。 そのため、よく噛むことでリズム運動の機会を増やせます。家事や仕事に追われて、ついつい早食いになっていることも多いでしょう。食事をよく噛んで食べるだけでもセロトニンが増えます。 |
|
呼吸 |
ストレッチやヨガ、座禅でゆっくりと大きな呼吸をしましょう。ストレスを感じると、呼吸は浅くなりがちです。一日のなかで、少しでも自分のために呼吸を整える習慣を作ってみましょう。 |
運動や呼吸自体のリラックス効果や食事で満足感を得られることに加え、セロトニンの分泌が促進されることで、より充実感が得られるでしょう。
3.日光を浴びる習慣を持つ
太陽光を浴びることでセロトニンの分泌が活性化します。(文献5)
電球の光だけでは分泌を促すほどの照度がないため、カーテンを開けたり、外に出たりしてしっかり日光を浴びましょう。日光を浴びると、1日の体内時計のリズムも整い、調子よく過ごせます。
まとめ|セロトニン欠乏脳だと感じたら生活習慣を見直そう
いつもよりも怒りっぽい、調子が悪いと感じたら、セロトニンが欠乏している状態かもしれません。先述のチェックリストで自分がセロトニン欠乏脳ではないかと感じたら、生活習慣の見直しからはじめましょう。それでも体調や気分が変わらない場合は、ほかの心身の病気の可能性もあります。
自分だけでは判断が難しい、もっと詳しく話を聞きたいという場合には、当院のメール相談 、オンラインカウンセリング にてお気軽にご相談ください。
\無料オンライン診断実施中!/
セロトニン欠乏脳についてよくある質問
セロトニン欠乏脳について、よくある質問をまとめました。ぜひご参考ください。
日本人はセロトニンが少ないですか?
過去の論文においては、日本人の遺伝子型としてセロトニンが少ないことも示されているようです。しかし、日本人といっても一人一人の遺伝子型は異なります。もともと落ち込みやすい性格である、不満を感じやすいといった特徴があれば、セロトニン欠乏を疑うべきでしょう。
セロトニンを増やすマッサージやストレッチはありますか?
目、顔、背中のリズミカルなマッサージがセロトニン神経を活発にする、という研究結果があります。規則的に、気持ちよいくらいの強さでトントンと指や手全体で刺激をしてみましょう。加えて、ストレッチで体を動かすことも呼吸を早く、大きくするため、セロトニンを増やす効果があります。
参考文献
(文献1)
厚生労働省「セロトニン|e-ヘルスネット」
https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/dictionary/heart/yk-074.html
(文献2)
有田秀穂「セロトニン欠乏脳 −キレる脳・鬱の脳を鍛え直す−」
https://www.jstage.jst.go.jp/article/hbs/3/2/3_123/_pdf/-char/ja
(文献3)
厚生労働省「自律神経失調症:用語解説|こころの耳:働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト」
https://kokoro.mhlw.go.jp/glossaries/word-1591/
(文献4)
尾畑佑樹氏,腸内細菌による消化管神経回路の修飾
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jim/36/1/36_21/_pdf
(文献5)
小西正良ほか「セロトニン分泌に影響を及ぼす生活習慣と環境|大阪河﨑リハビリテーション大学紀要」
https://cir.nii.ac.jp/crid/1050285299827544832