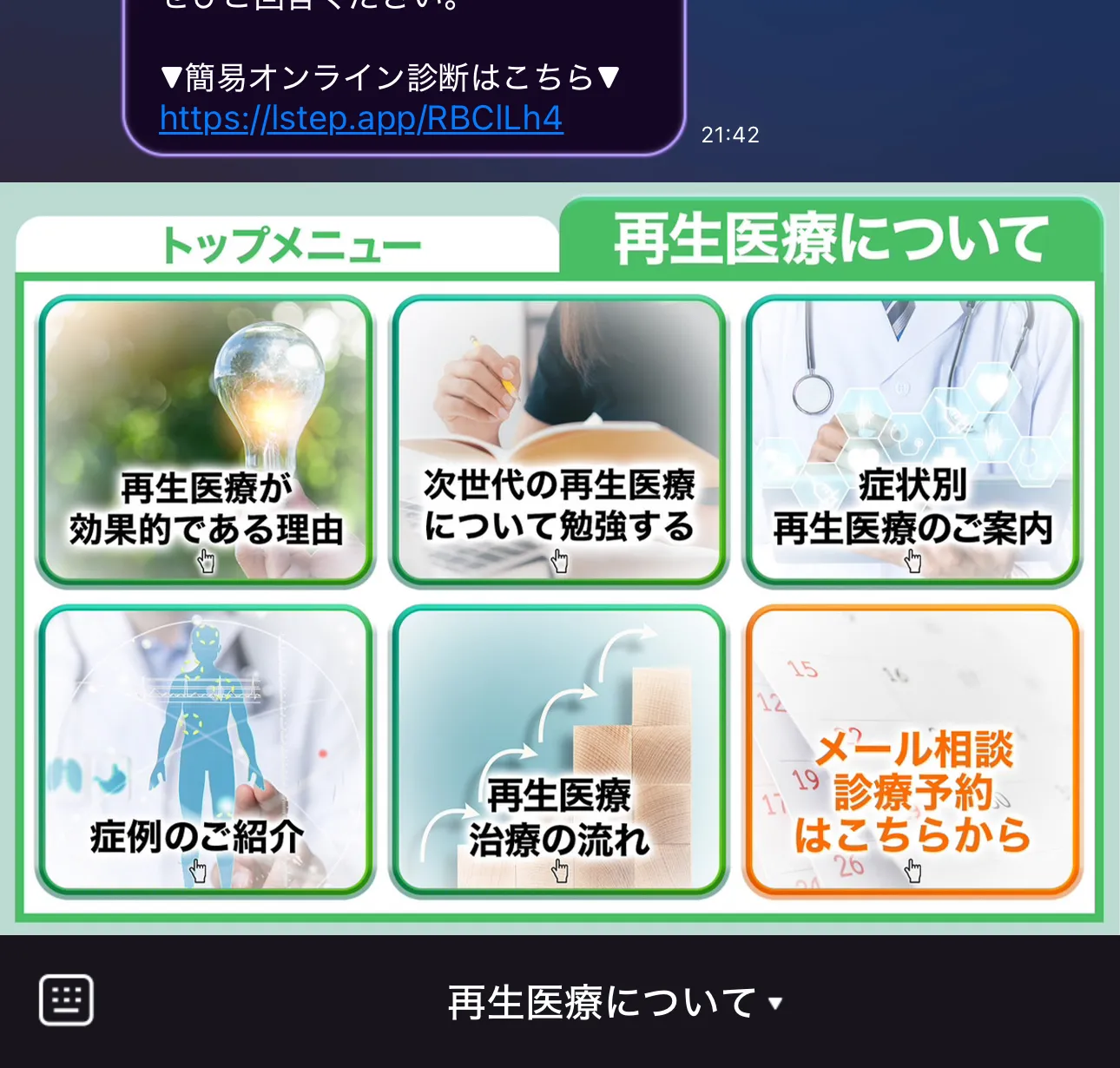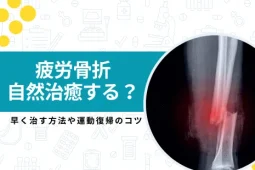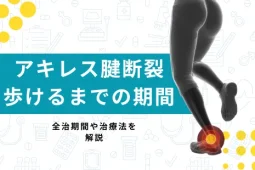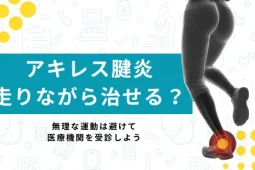- 足部、その他疾患
- 下肢(足の障害)
- 足部
- スポーツ外傷
シンスプリントを走りながら治すことはできる?マッサージやストレッチの仕方を紹介
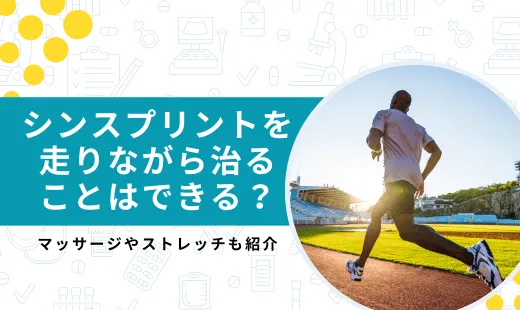
シンスプリントと診断されたが、練習を休みたくない
大事な試合が近いから走りながらでも、なんとかしたい
シンスプリントを抱えながらも、練習は継続したいと悩む方は多いです。練習をできる限り続けたい気持ち、よくわかります。
ですが、シンスプリントは走りながら治せるほど単純な症状ではありません。
無理して練習を続けると、症状の悪化を招く可能性があります。しかし、無理のないメニューや環境をしっかり整えば、練習を継続できます。
そこで本記事では、以下について解説します。
- 休息と対策方法
- 負担を軽減するマッサージ方法
- 負担を軽減するストレッチ方法
- 予防する足裏やふくらはぎのトレーニング方法
最後に、シンスプリントについてのよくある質問にお答えします。気になる疑問を解決できますので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
【結論】シンスプリントは走りながら治せない|休息と対策が必要
シンスプリントは走りながら治すことはできません。また、シンスプリント(脛骨過労性骨膜炎)は医師や専門機関により、走りながらの治療は推奨されていません。(文献1)
脚に違和感を抱えたまま走ることで、症状が悪化する可能性があります。また無理をすると、症状の回復が遅れる原因にもなります。
そのため、シンスプリントと診断された際は、走りながら治そうとしてはいけません。シンスプリントを治すには休息と対策が必要です。
テーピングを貼る
| 手順 | 内容 |
|---|---|
| 1.準備 | 足をタオルや水で洗い、乾燥させる |
| 2.テープを適切な長さにカットする | 5cm幅のキネシオロジーテープを適切な長さにカット |
| 3.貼り始め | 足の外側からスネの内側に向かって貼る |
| 4.引っ張りながら貼る | 土踏まずを持ち上げるように、膝下まで伸ばす |
| 5.重ね貼り | 1本目のテープに1/2~2/3重ねて2本目を貼る |
| 6.クロス貼り | 外くるぶしの上からスネの内側へ斜め上に貼る |
| 7.固定 | 足首を1周するようにテープを巻き、しっかり固定する |
シンスプリントの改善にはテーピングがおすすめです。テーピングを適切に貼ることで、症状の緩和や再発防止につながります。
テーピングには5cm幅のキネシオテープと7.5cm幅のバンテージを使用します。自分で貼るのは難しいため、表を参考に周りの人や、詳しい人に貼ってもらうと良いでしょう。
以下の記事では、シンスプリントのテーピングの方法を詳しく解説しています。
運動後にアイシング
| 手順 | 内容 |
|---|---|
| 1.準備 | ビニール袋に氷を入れ、空気を抜いて患部にフィットさせる |
| 2.冷却時間 | 1回のアイシングは15~20分を目安にする |
| 3.頻度 | 1時間ごとに間隔を空けて繰り返す |
| 4.注意点 | 凍傷防止のためタオルを挟む、長時間のアイシングは避ける |
シンスプリントの緩和にはアイシングが有効です。(文献2)アイシングを行うことで炎症を抑え、症状を和らげるのに役立ちます。
1回のアイシングは15~20分を目安に行い、1時間ごとに間隔を空けてを繰り返します。アイシングを行う際は凍傷を防ぐために、長時間の冷却は避け、適度な時間で行うのが大切です。
アイシングは、運動後や違和感を感じたときに効果的な手法ですが、症状が改善しない場合は医師に相談するようにしましょう。
負荷のかからない練習量と環境にする
シンスプリントの症状を悪化させないためには、練習量と環境を改善する必要があります。シンスプリントが悪化する要因としては以下が挙げられます。
- 不整地や硬い地面での運動・練習
- 足の疲労によって衝撃吸収が弱まった状態での練習
- 過度な走り込み
負担を減らすには、無理な運動や硬い地面での練習は避け、クッション性のある場所を選ぶことが大切です。またシンスプリントの症状が出た場合は、練習量を減らすなどし、負担軽減を優先しましょう。
シューズを変える
| ポイント | 解説 |
|---|---|
| クッション性だけに頼らない | クッションは分厚ければ良いものではない。シューズの形状や高さが衝撃吸収能力に影響を与えることがある。 |
| 走り方に合わせたシューズを選ぶ | 走り方に応じて、つま先と踵の高さが異なるシューズを選ぶと衝撃吸収能力が向上する。 |
| 足部の安定性を保つ | 分厚いクッションが足部の不安定さを引き起こす可能性がある。安定性を保てるシューズを選ぶこと。 |
| 普段のトレーニングに合わせる | 分厚いクッションは不要。普段のトレーニングに合わせて、クッション性や形状を選ぶこと。 |
| 自分に合ったシューズの選び方 | 足のアーチや走り方に合わせたシューズを選び、フィッティングを受けることが大切。 |
クッション性の低い靴の使用や、かかとのすり減った靴での練習は脛骨に負荷をかけます。しかし、クッション性と怪我の予防に関する明確なエビデンスはありません。そのため、クッション性だけに重点を置かないことが大切です。(文献3)(文献4)
シューズを選ぶ際は、足のアーチや走り方、負担のかかりやすい部分を考慮し、選択するようにしましょう。
自分だけで選ぶのが難しい場合は、専門店でシューズフィッティング(足に合った靴の選定、履き心地の確認)を受けることで、自分に合うシューズを見つけやすくなります。
マッサージ・ストレッチ
マッサージ・ストレッチは筋肉や筋膜の柔軟性を高めます。とくに入浴後は血行が良くなり、筋肉が柔らかくなるため、このタイミングで行うと効果的です。(文献5)(文献6)
マッサージ・ストレッチは筋肉の柔軟性強化だけでなく、血行の改善や負荷のかかる部分(とくに下肢の筋肉)の緊張をほぐせます。
無理のない範囲で行う必要はあるものの、適度な運動は怪我の予防や回復の促進が研究でも明らかになっています。(文献5)(文献6)
シンスプリントの負担を軽減するマッサージの仕方
シンスプリントの負担を軽減するために、マッサージが効果的です。筋肉をリラックスさせ、血流を促進し、症状を和らげます。ただし、無理なく優しく行うことが大切です。
以下でポイントを詳しく解説します。アイスマッサージ
| ステップ | 詳細 | 注意点 |
|---|---|---|
| 準備するもの | 小さな袋に氷を入れる、またはアイスパックを使用する。 | 直接氷を肌に当てないようにする。氷が肌に直接触れると凍傷の原因になります。 |
| アイシング部位 | スネの内側や足首周りを対象にアイスを当てる。 | アイシングを行う部位を清潔に保つこと。傷や炎症がひどい場合は無理に行わないようにしましょう。 |
| アイスを当てる方法 | 5〜10分間、円を描くようにアイスを当てながらマッサージする。 | 長時間行いすぎないように注意する。冷却しすぎると血行が逆に悪くなり、症状が悪化につながります。 |
| 休憩後の再実施 | 冷却後、少し休憩してから再度実施するとより効果的。 | 休憩時間を設けることで、肌や筋肉に過度な負担をかけずに効果的にアイスマッサージを行えます。 |
| 主な効果 | 炎症や腫れを軽減し、血流の促進に繋がります。 | 冷却後に違和感があれば、すぐに中止する。必要に応じて医師に相談しましょう。 |
氷を入れた小さな袋を患部に直接当てて、マッサージします。円を描くように10分〜15分程度行いましょう。アイスマッサージには炎症や腫れを軽減し、血流を促進する効果があります。
氷はスネの内側や足首周りに当てますが、直接肌に触れたり、同じ場所を長時間冷やしたりしないよう注意しましょう。冷却後に違和感があれば、中止して医師に相談しましょう。
足裏のマッサージ
| ステップ | 詳細 | 注意点 |
|---|---|---|
| 準備するもの | とくに準備は必要なく、手やマッサージオイルなどの使用もできます。 | マッサージを行う際には爪を切り、硬い部分で引っかからないようにしましょう。 |
| マッサージ部位 | 足の前部からかかとに向かって、親指や指の腹でマッサージする。 | 強すぎない圧力でマッサージを行いましょう。過度な圧力を加えるとマッサージを行なった箇所に負担がかかります。 |
| マッサージの方法 | 円を描くように優しく押しながらマッサージし、30秒〜1分間行う。 | アーチ部分をとくに重点的にマッサージしますが、無理に押さないようにする。少しでも違和感を感じた場合は中止します。 |
| 両足をマッサージ | 反対側も同様にマッサージする。 | 両足を同じ方法でマッサージするのが大切です。片方だけを行うことは偏った負担をかける原因になります。 |
| 主な効果 | 足裏の筋肉をほぐし、アーチ部分の負担を軽減、シンスプリントの症状を改善します。 | マッサージ後は無理のない範囲で、足を軽くストレッチすると、筋肉がさらにリラックスしやすくなります。 |
足裏を親指や指の腹で優しく押し、足の前部からかかとに向かって円を描く形でマッサージします。マッサージを行う際は、無理のない範囲で行い、強く押しすぎないことが大切です。
足裏をマッサージを行うことで、筋肉をほぐれ、アーチ部分の負担を軽減できます。
スネの内側のマッサージ
| ステップ | 詳細 | 注意点 |
|---|---|---|
| 準備するもの | 手だけで行えますが、マッサージオイルなどを使用しても良いです。 | 圧力を加える前に手やオイルでスネ部分を軽く温めておくと、よりリラックスできます。 |
| マッサージ部位 | スネの内側、脛骨の周辺を指の腹でマッサージします。 | 強い力を加えすぎないように注意する。違和感を感じたら、すぐに中止しましょう。 |
| マッサージの方法 | 上から下に向けて円を描くように軽く押しながら、マッサージします。 | 1~2分間マッサージする。スネの筋肉がリラックスした感覚を覚えましょう。 |
| 反対側のマッサージ | 反対側のスネも同様にマッサージします。 | 両側をバランスよくマッサージする。片方だけに偏らないようにしましょう。 |
| 主な効果 | スネの内側の筋肉をほぐし、筋肉の緊張を和らげ、症状を軽減します。 | 強く押しすぎないように、リラックスした状態で行うと効果的です。 |
スネの内側のマッサージを反対側と合わせ、1〜2分間マッサージし、筋肉の緊張を和らげ、症状を軽減できます。(文献6)
シンスプリントの負担を軽減するストレッチの仕方
シンスプリントの負担を軽減するには、ストレッチが有効です。ストレッチを行うことで、マッサージ同様、筋肉の緊張を和らげ、症状の改善につながります。
以下ではシンスプリントの負担を軽減するストレッチの方法を解説します。
後脛骨筋(こうけいこつきん)ストレッチ
| ステップ | 手順 | ポイント |
|---|---|---|
| 1.準備 | 座った状態で、片足をもう一方の太ももに乗せる。 | リラックスして姿勢を安定させる。 |
| 2.足首を曲げる | 乗せた足のつま先を手で持ち、足首を内側にゆっくりと曲げる。 | 無理に力を入れず、心地良い伸びを感じる程度に調整する。 |
| 3.キープ | 足首の内側を曲げた状態を15~30秒間保持する。 | 深呼吸しながら、筋肉の伸びを意識する。 |
| 4.反対側も実施 | ゆっくり元の位置に戻し、反対側の足も同様に行う。 | 左右交互に2~3回繰り返す。 |
脛骨の内側から足首にかけて付着する後脛骨筋のストレッチを行い、柔らかくします。コツは反動をつけずにゆっくりと伸ばすことを意識します。
無理な力は後脛骨筋に負担をかけ、シンスプリントを悪化させる恐れがあるため注意しましょう。無理がない範囲で行うことが大切です。
腓腹筋(ひふくきん)ストレッチ
| ステップ | 方法 | ポイント |
|---|---|---|
| 1. 姿勢をとる | 壁の前に立ち、片足を一歩後ろに引く。 | 後ろ足のかかとを床につけたままにする。 |
| 2. 体を前に倒す | 壁に手をつき、前足の膝を軽く曲げながら体を前方に倒す。 | 背筋を伸ばし、無理に体を曲げすぎないようにする。 |
| 3. ストレッチを保持 | ふくらはぎが伸びるのを感じながら15~30秒キープ。 | 反動をつけず、ゆっくりと伸ばす。 |
| 4. 反対側も行う | 片側が終わったら反対の足も同様にストレッチする。 | 毎日継続して行うことで効果が期待できる。 |
腓腹筋を伸ばし、ふくらはぎの柔軟性を高めることで、シンスプリントの改善に役立ちます。反動をつけず、かかとを床につけたまま無理のない範囲で行いましょう。
ヒラメ筋ストレッチ
| ステップ | 方法 | ポイント |
|---|---|---|
| 1.姿勢をとる | 壁の前に立ち、片足を一歩後ろに引く。 | 後ろ足のかかとを床につけたままにする。 |
| 2.ひざを曲げる | 後ろ足のひざを軽く曲げ、ふくらはぎの下部(ヒラメ筋)を伸ばす。 | 背筋を伸ばし、ゆっくりと動作を行う。 |
| 3.ストレッチを保持 | ふくらはぎの下部に伸びを感じながら15~30秒キープ。 | 反動をつけず、無理のない範囲で行う。 |
| 4.反対側も行う | 片側が終わったら反対の足も同様にストレッチする。 | 呼吸を意識して、リラックスしながら行う。 |
ヒラメ筋ストレッチはシンスプリントの症状緩和に効果的です。ふくらはぎの柔軟性を高めることで、脛骨への負担が軽減されます。
無理はせず、ゆっくりとした動作でヒラメ筋ストレッチを行うことが大切です。適切に行うことで、症状の悪化を防ぎ、パフォーマンス向上に繋がります。
シンスプリントを予防|足裏やふくらはぎのトレーニング方法
シンスプリントの予防には、足裏やふくらはぎのトレーニングも大切です。正しいトレーニングを行い、筋力を鍛えることで、足部の衝撃吸収能力や安定性が向上し、発症を防止できます。
以下では、足裏やふくらはぎのトレーニング方法について解説します。
タオルギャザー
足裏の筋力を鍛えるトレーニングで、床にタオルを広げ、足でタオルを引き寄せる動作を繰り返します。このとき、かかとの位置は変えずに行うようにしましょう。
足底のアーチを意識しながら、タオルを引き寄せることで、足裏の筋力を強化できます。
両脚ヒールレイズ
ふくらはぎの後面に位置する、ヒラメ筋と腓腹筋を鍛えるトレーニングです。直立した状態で、両足を使ってかかとを上げ下げします。
このとき、できるだけかかとを高く上げ、膝をしっかり伸ばした状態で行います。また身体がふらつかないように注意しましょう。
チューブを使った筋力トレーニング
トレーニングチューブを使って、足やふくらはぎの筋肉を鍛えるトレーニングです。コツは低負荷から始め、徐々に負荷を上げていくようにします。
いきなり負荷をかけると筋肉が炎症を起こし、症状が悪化する恐れがあります。ゆっくりと無理のない範囲で行いましょう。
チューブを使った筋力トレーニングについては、以下の記事で詳しく解説しております。
走ると辛いシンスプリントは当院にご相談ください
シンスプリントは走りながら治すのは難しいですが、適切な対策とトレーニングで改善できます。
改善が進まない場合は、当院「リペアセルクリニック」にご相談ください。再生医療で組織の修復をサポートします。
走ると辛いシンスプリントでお悩みの方は「メール相談」もしくは「オンラインカウンセリング」にてお気軽にお問い合わせください。
走りながらシンスプリントを治したい方からよくあるQ &A
シンスプリントの主な原因は
シンスプリントの原因は、筋肉や被膜の異常によって引き起こされます。筋肉に負荷がかかると硬くなり、柔軟性が低下します。その結果、筋肉が脛骨を引っ張り、負荷が増加して炎症が起き、違和感が生じるのです。
以下の記事では、シンスプリントの原因と予防策を詳しく解説しています。
シンスプリントは走りながら治すのではなく病院行くべきですか?
シンスプリントは走りながら治すのではなく、病院に行くべきです。シンスプリントは筋肉や神経が炎症を起こしている状態であり、負荷をかけると症状が悪化する可能性があります。
症状を悪化させないためにも、病院で診察を受けることをおすすめします。
シンスプリントに湿布は効果的ですか?
シンスプリントに湿布は一時的な痛みを和らげる効果がありますが、根本的な治療にはならないことが多いです。湿布は主に炎症を抑え、血流を改善するために使用されます。
冷湿布は炎症や腫れを抑える効果があり、急性の炎症があるときに適しています。一方、温湿布は、患部を温めて血行を促進し、筋肉の緊張を和らげます。
慢性的な痛みに効果的ですが、炎症がひどい場合には逆効果になることもあるので、注意が必要です。
参考文献
Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA「シンスプリント」MSDマニュアル プロフェッショナル版,2021年10月
一般臨床整形外科学会日本臨床整形外科学会「アイシング」一般臨床整形外科学会日本臨床整形外科学会ホームページ
Laurent Malisoux, et al. (2020)Shoe Cushioning Influences the Running Injury Risk According to Body Mass: A Randomized Controlled Trial Involving 848 Recreational Runners – PubMed
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31877062/(Accessed: 2025-02-24)
Naoko Aminaka,et al.(2018),NO IMMEDIATE EFFECTS OF HIGHLY CUSHIONED SHOES ON BASIC RUNNING BIOMECHANICS,1-10
https://hrcak.srce.hr/file/283953(Accessed:2025-02-24)
Miloš Dakić, et al.(2023),The Effects of Massage Therapy on Sport and Exercise Performance: A Systematic Review – PMC
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10302181/(Accessed:2025-02-24)
(文献6) Robert D Herbert, et al.(2011),Stretching to prevent or reduce muscle soreness after exercise – PubMed
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21735398/(Accessed:2025-02-24)