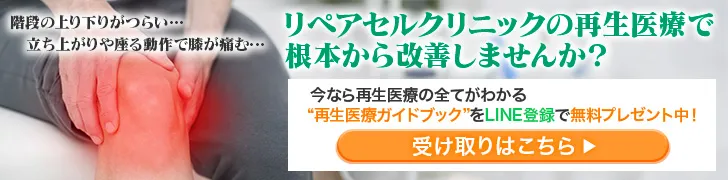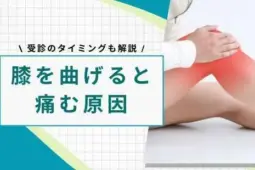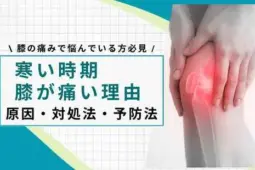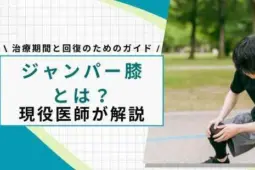- 下肢(足の障害)
- ひざ関節
- スポーツ外傷
- 膝部、その他疾患
ジャンパー膝における湿布の貼り方を医師が解説!冷やす・温める問題にも言及
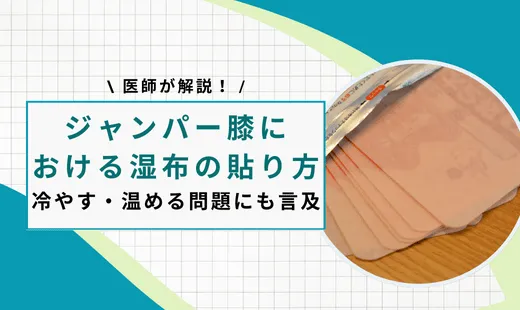
ジャンパー膝の正しい湿布の貼り方がわからない
ジャンパー膝は冷やすべきか温めるべきかわからない
ジャンパー膝の湿布の貼り方に悩んでいませんか?
湿布は、ジャンパー膝の症状を改善させるのに効果的なものです。しかし湿布の貼り方や、温める方法を間違えると、適切な効果を得られません。
- ジャンパー膝の湿布の貼り方
- ジャンパー膝の温めるべきケース・冷やすべきケース
- ジャンパー膝に対する「冷湿布」の効果
- ジャンパー膝に対する「温湿布」の効果
- ジャンパー膝における湿布以外のセルフケア
- ジャンパー膝と湿布の貼り方に関するよくある質問
本記事では、症状を悪化させない適切な貼り方や、冷やす・温めるべきケースをわかりやすく解説します。
最後には、ジャンパー膝と湿布の貼り方に関するよくある質問をまとめておりますので、ぜひ最後まで読み進めていただければと思います。
目次
ジャンパー膝の湿布の貼り方
| ステップ | 内容 | 目的 |
|---|---|---|
| 1.患部の洗浄と乾燥 | 膝周囲の皮膚を洗浄し、乾燥させる | 汗や汚れを取り除き、湿布の密着を高める |
| 2.湿布に切れ目を入れる | 湿布の中央に縦の切れ目を入れる | 膝の動きにフィットさせ、剥がれにくくする |
| 3.湿布の貼り付け | 違和感のある箇所(膝蓋骨の下部など)に貼る | 患部に薬剤を浸透させる |
| 4.固定 | テーピングやサポーターで固定する | 湿布の剥がれを防ぎ、効果を持続させる |
ジャンパー膝の湿布は、膝蓋腱の炎症を抑える目的で使用します。貼り方の手順は、患部の洗浄と乾燥→湿布の切れ目入れる→湿布の貼り付け→固定の流れで行います。
湿布を貼る前に、皮膚の汗を拭き取り、清潔にしておきましょう。また、膝は動きが多い部分なので、湿布が剥がれないように工夫する必要があります。
湿布で症状の改善がみられない場合は、医療機関の受診が必要です。
ジャンパー膝は冷やすべき?温めるべき?
ジャンパー膝の症状に対して冷やすべきか、症状の種類とその時点での膝の状態によって異なります。
冷やす・温めるタイミングを間違えると、症状が悪化する可能性があるため注意しましょう。
- 冷湿布などで冷やすべきケース
- 温湿布などで温めるべきケース
症状や状況別で、解説します。
冷湿布などで冷やすべきケース
| ケース | 理由 | 使用方法 |
|---|---|---|
| 急性期(発症0~6週) | 炎症が進行しやすいため、冷却し、症状の悪化を防ぐ | 20分間冷却し、30-40分間休憩を挟みながら繰り返す |
| 運動直後 | 運動による筋肉の微細損傷を抑え、炎症を最小限に抑える | 運動後すぐに冷湿布を適用し、腫れを予防する |
| 腫れや炎症がある場合 | 血管を収縮させることで、腫れや違和感を抑える | 腫れが引くまで定期的に冷やし、違和感が治まるか様子を見る |
| 急激な違和感がある場合 | 神経の感受性を低下させ、膝への違和感の伝達を遅らせ、症状を和らげる | 氷や冷湿布を布で包み、直接皮膚に触れないよう注意する |
(文献1)
冷湿布で冷やすべきケースは、違和感が顕著に現れて、炎症を起こした段階です。ジャンパー膝の直後は、冷湿布を使用し血管が収縮させることで、炎症の拡大を抑えます。
冷湿布の効果に関する研究では、急性期の違和感に対して冷却療法が推奨されています。(文献1)
違和感が現れた初期の段階では、冷湿布で冷やすようにしましょう。
温湿布などで温めるべきケース
| ケース | 理由 | 使用方法 |
|---|---|---|
| 慢性期(発症から12週間以上) | 血流を促進し、組織の回復を助けるため、慢性的なこわばりや不調に適している | 15~20分程度、温湿布や温めたタオルを使用し、血流を促す |
| 運動前のウォームアップ | 筋肉の柔軟性を高め、ケガの予防や動きのスムーズさを向上させる | 運動開始前に10~15分ほど温めて、筋肉の柔軟性を向上させる |
| 筋肉のこわばりや違和感がある場合 | 筋肉が硬くなり、動きが制限されるとパフォーマンスが低下するため、温めることで緊張を緩和する | 温めながら軽いストレッチを行い、筋肉をほぐすと効果的 |
| 冷やしても症状が改善しない場合 | 冷却しても症状が改善しない場合、血行を促進し、組織の修復を助ける | 冷湿布で改善が見られない場合、温湿布を試して様子を見る |
慢性期(発症から12週間)の場合は、血流を促進し、組織の回復力を助けるために、温湿布を使用します。
炎症が落ち着き、膝周囲の筋肉が硬くなっている段階では、冷やすよりも温めることで血流が促進され、柔軟性が向上し膝への負荷が軽減されます。
冷やしても症状が改善しない段階で、温湿布の使用を検討しましょう。
ジャンパー膝に対する「冷湿布」の効果
| 効果 | 解説 |
|---|---|
| 炎症による腫れや熱感を抑える | 冷却効果により、血管が収縮し、炎症物質の放出を抑制 |
| 違和感を和らげる | 冷たさにより神経の伝達速度が遅くなり、違和感を鈍らせる |
| 炎症の拡大を防ぐ | 血管収縮により、炎症が周囲に広がるのを防ぐ |
| 筋肉のこわばりを緩める | 冷却により筋肉の緊張が緩和され、柔軟性が向上する |
冷湿布は、主に急性期の炎症症状に対して有効です。冷湿布の効果について解説します。
炎症による腫れや熱感を抑える
| 作用 | メカニズム | 効果 |
|---|---|---|
| 冷却作用 | 水分蒸発による患部の冷却、血管収縮、血流抑制 | 腫れ、熱感の軽減 |
| 鎮痛作用 | メントールなどの成分による感覚神経刺激 | 違和感の緩和 |
冷湿布の冷却効果により、血管を収縮させることで、炎症を抑制させます。
冷湿布に含まれるメントールなどの成分は、皮膚の感覚神経を刺激し、鎮痛効果をもたらします。
違和感を和らげる
| 作用 | メカニズム | 効果 |
|---|---|---|
| 冷却作用による感覚麻痺 | メントールなどが皮膚の温度感覚を鈍らせる | 腫れなどの違和感を一時的に軽減 |
| 血管収縮による炎症抑制 | 患部の血管を収縮させ、炎症物質の放出を抑える | 炎症が鎮まり、腫れなどの違和感を軽減 |
冷湿布は、ジャンパー膝で起こる膝への違和感に対して有効です。
とくに冷湿布に含まれるメントールが皮膚の温度感覚を一時的に鈍らせることで、腫れや違和感を軽減します。
炎症の拡大を防ぐ
炎症が起こると、患部の血管が拡張し、血液中の炎症物質が組織内に漏れ出します。冷湿布は炎症物質の拡大を防ぐための手段として有効です。
ただし、冷湿布は初期段階での炎症を防ぐために使われるため、炎症が落ち着いた慢性期には、冷湿布よりも温湿布が適しています。
筋肉のこわばりを緩める
ジャンパー膝で起きた筋肉の強張りに対して、冷湿布の冷却は効果的です。患部を冷却すると、血管が収縮し、患部への血流が抑制されます。
また、冷却は神経の伝達速度を遅らせ、膝にかかる違和感を一時的に鈍らせるため、初期段階の対応として有効です。
冷却で筋肉の過剰な収縮を抑制できるものの、冷やしすぎると筋肉が逆にこわばる可能性があります。
冷湿布は、症状の変化を見ながら使用しましょう。
ジャンパー膝に対する「温湿布」の効果
| 効果 | 解説 |
|---|---|
| 血行を促進させる | 温熱効果により血管を拡張させ、血流を促進させる |
| 慢性的な違和感や筋肉のコリを和らげる | 温熱効果に柔軟性の向上、筋肉の緊張緩和を促す |
| リラックス効果 | 違和感の軽減や悪循環を抑える |
温湿布は主に慢性期の違和感や筋肉のこわばりを和らげるために使用されます。
ジャンパー膝に対して、温湿布が有効である理由を解説します。
血行を促進させる
| メカニズム | 効果 |
|---|---|
| 血管拡張 | 血流増加、酸素・栄養素の供給促進 |
| 血流速度増加 | 代謝活性化、疲労物質・発痛物質の排出促進 |
| 代謝活性化 | 違和感の軽減、筋肉の緊張緩和 |
温湿布を使用し、温まった部位が血管を広げ、血流が改善されます。
血流が改善されると、患部に栄養素や酸素が供給されやすくなり、症状の回復を促します。
ジャンパー膝の初期段階での血行促進は、炎症や違和感を悪化させる可能性があるため、温湿布は落ち着いた慢性期に使用しましょう。
慢性的な違和感や筋肉のコリを和らげる
| メカニズム | 効果 |
|---|---|
| 血行促進 | 筋肉の柔軟性向上、疲労物質の排出促進 |
| 神経の鎮静化 | 違和感の緩和 |
| 心理的リラックス | 筋肉の緊張緩和、違和感の軽減 |
温湿布は、慢性的な違和感や筋肉のコリを軽減します。注意点としては、低温やけどに注意し、長時間同じ場所に貼り付けないようにしましょう。特に寝る前に貼る場合は注意が必要です。
また、炎症がひどい状態では、症状を悪化させる可能性があるため、温湿布ではなく、冷湿布を使用しましょう。
リラックス効果
| メカニズム | 効果 |
|---|---|
| 筋肉の緊張緩和 | 違和感や悪循環を抑える |
| ストレス軽減 | 違和感を和らげる |
| 睡眠の質の向上 | 疲労回復を促進する |
(文献2)
温湿布には、ジャンパー膝に有効なリラックス効果があります。
温熱刺激は副交感神経に対してリラックス効果を与え、交感神経の活動を抑制します。
また、リラックス効果によるストレス軽減は、違和感に対してだけでなく、生活や睡眠の質を上げるためにも有効です。
ジャンパー膝における湿布を貼る際の注意点
| 項目 | 注意点 |
|---|---|
| 貼る前の準備 | 湿布を貼る前に、肌を清潔に、関節には目を切れさせて密着させる |
| 貼り方 | 湿布はフィルムを剥がした後、軽く伸ばし、必要に応じてテープやネット包帯で固定する |
| 剥がし方 | 湿布は体毛の流れに沿ってゆっくり剥がし、剥がした後は、肌を休めるために時間を空ける |
| 使用上の注意 | お風呂上りや汗で濡れている場合や、湿疹や発疹がある部位には使用しない |
| その他 | 膝への違和感が続く場合は、医療機関を受診する |
湿布を貼る際は、正しい使い方や、注意点を守ることが大切です。まず、炎症の状態に応じた湿布を選びます。
急性期には炎症を抑える冷湿布、慢性期には血行を促進する温湿布を選びましょう。
湿布を貼る際は、水や汗で皮膚が濡れていないことを確認し、必要に応じてテープやネットを使用します。湿布は、8~12時間を目安に交換しましょう。
湿布を貼り付けた場所にかゆみや発疹が出た際は、すぐに使用を中止します。かゆみや赤み、ジャンパー膝が続く場合は、医療機関を受診しましょう。
ジャンパー膝における湿布以外のセルフケア
| セルフケア | 重要な理由 |
|---|---|
| アイシング | 炎症を抑制し、違和感を軽減する |
| ストレッチ | 筋肉の柔軟性を高め、膝への負担を軽減する |
| サポーターの活用 | 膝を安定させ、負担を軽減する |
| 安静にする | 炎症の悪化を防ぎ、組織の修復を促す |
湿布はジャンパー膝の症状を一時的に緩和するのに役立ちますが、根本的な改善には、ストレッチや安静などのセルフケアが必要です。
ジャンパー膝におけるセルフケアについて解説します。
アイシング
| 手順 | 内容 |
|---|---|
| 準備 | 氷や保冷剤を薄いタオルで包む |
| 実施時間 | 患部に15 ~20分間程度(凍傷にならないよう注意する) |
| 調整 | 当てる時間を短くする、タオルの厚さを調整する |
| 冷やす頻度 | 1日に数回、とくに運動後や違和感がある時 |
(文献3)
ジャンパー膝は、膝蓋腱の炎症によって違和感が生じる疾患です。そのため、発症時は、炎症を拡大させないためにアイシングを行います。
アイシングを行う場合の注意点としては、凍傷を防止するために氷や保冷剤を薄いタオルで包み、患部に15〜20分程度冷やします。
冷やす時間はあくまで目安なので、冷たいと感じた場合は、無理をせずに調節しましょう。
ストレッチ
| ストレッチ | 方法 |
|---|---|
| 大腿四頭筋(前もも) | 立った状態や横向きに寝た状態で、かかとをお尻に近づけるように膝を曲げ、太もも前側を伸ばす |
| ハムストリングス(肉裏) | 立った状態や座った状態で、足を伸ばしてつま先を上げ、太ももの裏側を伸ばす |
| 腸腰筋(股関節付け根) | 足を前後に開いて立ち、後ろ足の付け根を伸ばす |
ストレッチは筋肉の柔軟性向上と負担軽減する手段として有効です。ストレッチは、無理のない範囲で行うことが重要です。
運動前後のウォームアップやクールダウンに取り入れることで、筋肉の緊張をほぐし、ジャンパー膝の防止にできます。
ストレッチは自己判断ではなく、医師の指導のもと行いましょう。
以下の記事では、ジャンパー膝に有効な効果的なストレッチ方法を解説しております。
サポーターの活用
| 効果 | 詳細 |
|---|---|
| 膝蓋腱の負担軽減 | サポーターが膝蓋腱周囲を圧迫し、負担を分散 |
| 膝の安定性向上 | 膝のぐらつきを抑え、関節の安定性を高める。衝撃を和らげ、悪化を防ぐ |
| 動きやすさのサポート | 膝のサポートにより、正しい動作を維持しやすくなる |
サポーターを活用し、膝蓋腱の周囲を適度に圧迫します。
また、サポーターには、関節の安定性を高める効果があり、膝への負担を軽減するために役立ちます。
サポーターを選ぶ際は、サイズ・種類・圧迫の強さを考慮し、自身の症状に合ったものを選ぶことが大切です。
サイズが合わない、圧迫が強すぎるまたは弱すぎるなど、自分に合わないサポーターを選んでしまうと、症状が悪化するリスクがあります。
違和感や不快感がある場合は、無理に使用せずに調整や交換を検討しましょう。
以下の記事では、サポーターの注意点を詳しく解説しております。
安静にする
ジャンパー膝は、膝蓋腱に何度も負荷がかかることで炎症や腫れを起こします。そのため、発症初期の段階では、安静が大切です。
しかし、一定期間が経過し、安静にしすぎると、筋力低下を引き起こします。その結果、膝蓋腱への負担が再び増加し、再発する可能性があります。
再発しないためにも、安静だけでなく、適度なリハビリやトレーニングで徐々に膝を慣らしていきましょう。
湿布で改善しないジャンパー膝は早めの受診を
ジャンパー膝に対する湿布は、膝にかかる違和感や炎症を一時的に抑える応急処置として有効ですが、根本を解決するものではありません。
ジャンパー膝の症状が湿布で改善しない場合は、早めに整形外科を受診しましょう。
ジャンパー膝の改善が湿布で見込めないと感じた方は当院「リペアセルクリニック」へお気軽にご相談ください。
再生医療を活用し、膝の違和感や炎症に対して、回復を促します。
湿布で改善しないジャンパー膝でお悩みの方は「メール相談」もしくは「オンラインカウンセリング」にてお気軽にお問い合わせください。
ジャンパー膝と湿布の貼り方に関するよくある質問
湿布は1日に何回張り替えれば良いですか?
湿布の貼り替え回数は、湿布の種類によって異なります。1日1回タイプであれば、8〜10時間程度効果が持続します。
1日2回タイプの湿布の場合の効果持続は、4〜6時間程度です。(文献3)
湿布を貼ったまま運動しても大丈夫ですか?
運動によって湿布がずれたり汚れたりする場合があるため、運動後は患部を確認して新しい湿布に貼り替えるようにしましょう。
湿布とサポーターは併用できますか?
湿布とサポーターは併用できます。併用する際は、皮膚に炎症や圧迫に気をつけ、違和感を感じたら使用を中止しましょう。
湿布は寝るときに貼っても良いですか?
注意するべき点はありますが、基本的に問題ありません。湿布を使用する前に、製品の取扱説明書をよく読み、皮膚のかぶれや湿疹に注意しましょう。
皮膚に異常が現れるようであれば、就寝時は湿布を剥がすなど、工夫する必要があります。
湿布を貼るのと飲み薬(鎮痛剤)ではどちらが効果的ですか?
どちらが効果的かは症状や状況によって異なります。症状が軽度であれば、湿布で十分な効果が得られる場合があります。
湿布で症状の改善が見込めない場合は、飲み薬(鎮痛剤)の服用を検討しましょう。
湿布や飲み薬を使用する際は、説明書をよく読み、用法・用量を守り、自己判断はせず、医師や薬剤師の指示に従いましょう。
参考文献
綾田 練ほか,「ジャンパー膝に対する運動後のアイシングの効果」『体力科学(2007)』pp.1-6, (2007)
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jspfsm/56/1/56_1_125/_pdf(最終アクセス:2025年3月15日)
2008年から2019年に発表された温罨法に関する国内文献の検討
武田七海ほか,「〈総説〉2008年から2019年に発表された温罨法に関する国内文献の検討」pp.1-9, 2008年
https://www.thcu.ac.jp/research/pdf/bulletin/bulletin17_09.pdf(最終アクセス:2025年3月15日)
宮川,羽毛田「薬の伝言版 湿布薬の使い方」, pp.1-2, 2024年
(最終アクセス:2025年3月15日)
関連する症例紹介
-

リペア幹細胞プラス【分化誘導】痛み10段階中10が4に!靴下が履ける日常を取り戻した!変形性股関節症 50代 女性
-

“リペア幹細胞” 痛み10段階中10が3に!高齢でも諦めなくてよかった!左変形性膝関節症 80代 女性
-

リペア幹細胞プラス【分化誘導】 痛み10段階中6が1に!テニス復帰も夢じゃない! 両変形性ひざ関節症 60代 女性
-

“リペア幹細胞” 右膝痛み4が0に完全消失!快適な歩行を取り戻した!両膝変形性関節症 70代 女性
-
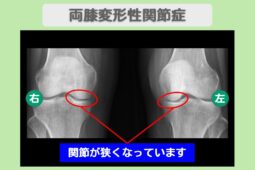
“リペア幹細胞” 10年悩んだ両膝の痛みから解放 両変形性膝関節症 60代女性
-

リペア幹細胞プラス【分化誘導】 両母指の痛みが消えて手術回避 両母指CM関節症 60代 女性