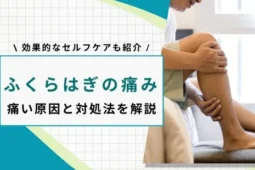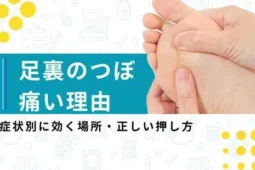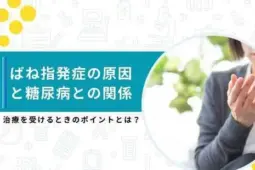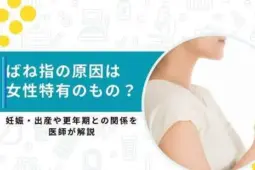- 足部、その他疾患
- 手部、その他疾患
- 手部
- 足部
- その他、整形外科疾患
末梢神経障害の症状を解説|しびれやストレスとの関係性もあわせて紹介
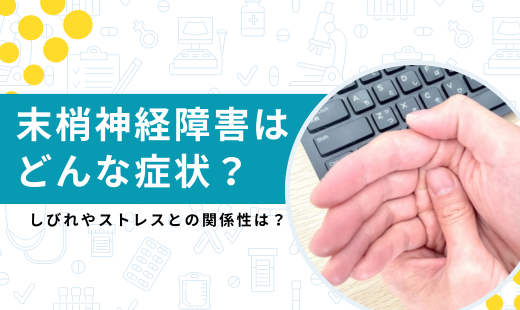
「足のしびれや自律神経の乱れを感じる」
「足にピリピリ感があり、日常生活に影響をきたしている」
最近、原因不明の足のしびれやピリピリ感はありませんか。日常生活や仕事にも影響が出始めると不安になりますよね。
とくに忙しい毎日を送っていると、足のしびれや自律神経の乱れがストレスによるものではないかと気になることでしょう。
それらの原因不明の症状は、末梢神経障害によるものかもしれません。
本記事では、末梢神経障害の症状とともに以下の内容について解説します。
末梢神経障害を放置すると筋肉の萎縮や痛みの慢性化につながりますので、症状と原因を正しく理解し、早めに医療機関を受診しましょう。
また、つらい末梢神経障害の治療には、再生医療も選択肢の一つです。
\末梢神経障害に対する再生医療とは/
再生医療は、患者さまの細胞や血液を用いて自然治癒力を向上させることで、痛みやしびれの原因となっている損傷した神経の改善を促す治療法です。
【こんな方は再生医療をご検討ください】
- 長年、手足のしびれや痛みに悩まされている
- 既存の治療では改善が見られない
具体的な治療法については、当院リペアセルクリニックで無料カウンセリングを行っておりますので、ぜひご相談ください。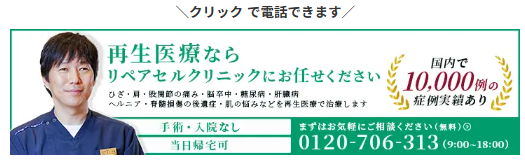
末梢神経障害とは
| 区分 | 主な症状 |
|---|---|
| 感覚神経の障害 | しびれ・冷感・灼熱感、感覚の低下、ピリピリ・チクチクする異常感覚 |
| 運動神経の障害 | 筋力低下、筋萎縮、歩行困難、運動機能の低下 |
| 自律神経の障害 | 発汗異常、立ちくらみ・めまい、便秘・下痢、排尿障害、動悸 |
| 症状の特徴 | 手足の先から始まる、左右対称に出る、徐々に進行する |
(文献1)
末梢神経障害とは、脳や脊髄から枝分かれした神経が傷つき、感覚や運動、自律神経の働きに異常が起きる状態のことを指します。
主に糖尿病やビタミン欠乏、ストレス、生活習慣の乱れなどが原因で引き起こされます。症状を放置すると徐々に進行し、重症化する恐れがあるため、早めに医療機関を受診しましょう。
以下の内容では、末梢神経障害に対してタリージェは効果があるのかを解説しております。
末梢神経障害の症状
末梢神経障害の症状は多岐に渡ります。主な症状は以下の4つです。
| 症状の種類 | 概要 |
|---|---|
| 足のしびれ・冷感・灼熱感 | 足先にしびれや冷たさ、焼けつくような感覚が現れる |
| 筋力低下 | 力が入りにくくなり、歩行時につまずきやすくなる |
| 感覚の異常 | 触れた感覚が鈍くなる、逆に過敏になる |
| 自律神経に異常をきたす | 発汗や血圧、消化・排尿などの機能に影響が出ることがある |
少しでも違和感を覚えた場合は、早めに医療機関を受診しましょう。
足のしびれ・冷感・灼熱感
| 症状 | 内容の概要 |
|---|---|
| 足のしびれ | 神経の障害で足の感覚が鈍くなり、しびれが起こる |
| 足の冷感 | 自律神経の障害により血流が悪化し、冷たく感じる |
| 足の灼熱感 | 足が焼けるように熱く感じられる |
感覚神経がダメージを受けると現れる代表的な症状です。足先や足裏にジンジン、ピリピリといったしびれを感じたり、正座の後のような感覚が続いたりします。
また、実際の温度とは関係なく、足が冷たく感じたり熱く感じたりする症状が現れることもあります。
症状の持続性には個人差がありますが、少しでも違和感を覚えた場合は、医療機関を受診しましょう。
筋力低下
| 症状 | 内容の概要 |
|---|---|
| 筋肉の萎縮 | 神経の損傷によって筋肉が細くなり、見た目にも痩せてくることがある |
| 歩行困難 | 足の筋力が低下し、ふらつきや転倒が起きやすくなる |
| 日常生活動作の困難 | 手の筋力が弱まり、物をつかむ・ボタンを留めるなど細かな作業がしにくくなる |
運動神経がダメージを受けると、筋肉を動かす指令がうまく伝わらなくなり、筋力が低下します。筋力が低下すると足の場合、スリッパが脱げやすくなったり、つま先が上がらずにつまずきやすくなります。
手の筋力であれば、物を落としやすくなり、私生活に支障をきたすでしょう。進行すると、歩行が不安になったり、物を持つことが困難になったりする可能性があります。
感覚の異常
| 症状 | 概要 |
|---|---|
| しびれ(感覚鈍麻) | 触れた感覚が鈍くなり、とくに手足の先に出やすい |
| 違和感 | 焼ける・刺す・電気が走るような違和感など、多様なタイプの症状が現れる |
| 異常感覚(錯感覚) | 触れていないのに触れたように感じる |
| 感覚過敏 | 軽い刺激でも強い不快感を覚える |
| 温度感覚の異常 | 冷たさ・熱さに対する感覚が鈍くなる、または過敏になる |
| 振動感覚の異常 | 携帯のバイブレーションなど、小さな振動を感じにくくなる |
| 位置感覚の異常 | ふらつきや物にぶつかりやすくなることも |
(文献4)
しびれや冷感・灼熱感以外にも、さまざまな感覚の異常が現れます。
触った感じが鈍くなる感覚鈍麻が起こると、やけどや怪我をしても気づきにくくなることがあります。逆に軽い刺激に対して過敏になるアロディニアと呼ばれる状態になることもあり、症状はさまざまです。
感覚の異常は、QOL(生活の質)を低下させる原因になるだけでなく、症状によっては後遺症が出る可能性があります。
自律神経に異常をきたす
自律神経は、血圧、体温、発汗、消化、排泄など、自分の意思とは関係なく体の機能を調整する神経のことを指します。
具体的な症状としては、起立性低血圧や発汗異常、消化器症状、排尿障害など、全体にさまざまな不調が現れるため、重症化する前に早期発見が必要です。
また、自律神経とストレスの因果関係に関して、現時点で明確なエビデンスがありません。
研究段階ではあるものの、ストレスが末梢神経障害を引き起こす原因であるといわれているため、生活習慣に気をつける必要があります。
末梢神経障害の原因
末梢神経障害の原因は、主に以下のような糖尿病や過度なアルコール摂取・喫煙など生活習慣から来るものや遺伝的なものといわれています。
これから紹介する内容が当てはまる方は、末梢神経障害を発症させないためにも生活習慣の見直しが必要です。
ストレス性によるもの
| 要因 | 概要 |
|---|---|
| 自律神経の乱れ | ストレスにより交感神経が過剰に働き、血管収縮や筋緊張が起こり、神経への血流が悪化する |
| 炎症反応の促進 | ストレスが炎症性物質の分泌を促進し、慢性的な炎症が神経を傷つける可能性がある |
| 違和感の感受性亢進 | 脳の違和感を汲み取る領域が影響を受け、症状を感じやすくなる |
| 生活習慣の乱れ | ストレスが睡眠・食事・運動に影響し、神経への負担や回復力低下を招くことがある |
過度な精神的ストレスが、直接的に末梢神経障害を引き起こすエビデンスはありません。
しかし、ストレスは血行不良や免疫機能の低下、睡眠不足などを招き、間接的に神経の健康に影響を与える可能性が指摘されています。
他に明らかな原因がなく、精神的な負荷を感じる時期に症状が悪化するような場合は、ストレスの関与が疑われるでしょう。
精神的な負荷が引き金になり、末梢神経障害を引き起こしている可能性を感じた場合は、ストレス環境から距離を取り、休息を取りましょう。
糖尿病(糖尿病性神経障害)
| 障害の種類 | 概要 |
|---|---|
| 感覚障害 | 足先のしびれ、ピリピリするような違和感など |
| 運動障害 | 足に力が入らない、筋力の低下など |
| 自律神経障害 | 立ちくらみ、便秘、発汗異常など |
(文献4)
糖尿病で長期間、血糖値が高い状態が続くと、細い血管がダメージを受けて血流の悪化や、糖代謝の異常によって神経細胞そのものが変性する神経障害が引き起こされます。
足先のしびれや感覚鈍麻から始まることが多く、進行すると筋力低下や自律神経症状も現れ、日常生活に大きな支障をきたします。
糖尿病を患っている方は、とくに足先のしびれや感覚鈍麻の症状に注意が必要です。
過度なアルコール摂取・喫煙
| 要因 | 概要 |
|---|---|
| アルコールの毒性 | 神経細胞に直接ダメージを与え、長期摂取で変性や破壊を引き起こす |
| ビタミンB群の欠乏 | 吸収阻害により神経の維持に必要な栄養素が不足し、障害リスクが高まる |
| 肝機能障害 | 栄養代謝が妨げられ、神経細胞に必要な成分の供給が不足する |
| 血管収縮・血流低下 | ニコチンが血管を収縮させ、神経への酸素・栄養供給が不足し機能が低下する |
| 酸化ストレス増加 | 神経細胞が酸化ダメージを受けやすくなり、障害のリスクが上がる |
長期間にわたる過度なアルコール摂取は、神経毒性やアルコール代謝に伴う栄養障害により、末梢神経障害を引き起こします。
また、喫煙もニコチンによる血管収縮作用や血行不良を引き起こし、神経への酸素や栄養の供給を妨げるため、末梢神経障害のリスクがあります。
普段からお酒を飲む習慣がある、タバコを普段から吸う方は、末梢神経障害の症状に注意が必要です。
ビタミンB12欠乏症
| 原因 | 概要 |
|---|---|
| 摂取不足 | 動物性食品を控えた食事や偏った食生活により、ビタミンB12が不足する |
| 吸収不良 | 胃や小腸の疾患により、ビタミンB12の吸収がうまくいかなくなる |
| 薬剤の影響 | 一部の薬(メトホルミン、PPIなど)がビタミンB12の吸収を妨げることがある |
(文献4)
ビタミンB12は、神経細胞の髄鞘を維持したり、神経伝達物質の合成を助けたりする役割があります。
偏った食生活でビタミンBの不足や、胃の切除手術後、特定の胃腸疾患などによってビタミンB12の吸収が妨げられると、欠乏症となり末梢神経障害を引き起こす恐れがあります。
普段から偏った食事や胃腸に疾患を持つ方は、ビタミンB12が不足しないよう工夫しましょう。
自己免疫疾患・遺伝性疾患・感染症
| 分類 | 代表疾患 | 特徴・メカニズム |
|---|---|---|
| 自己免疫性 | ギラン・バレー症候群 | 感染後に免疫が神経を攻撃すると、急に手足が動かしにくくなることがある |
| CIDP(慢性型) | 髄鞘を慢性的に攻撃し、筋力低下やしびれがゆっくり進行する | |
| 遺伝性 | CMT(シャルコー・マリー・トゥース病) | 遺伝子の異常で筋力や感覚に障害が出る、手足の変形を伴うこともある |
| 感染症 | 帯状疱疹 | ウイルスが神経にダメージを与えることで、神経痛が起こる |
| その他(HIV、ライム病など) | 神経を直接傷つけたり、免疫を介して障害を起こすことがある |
自己免疫疾患である、ギラン・バレー症候群やCIDPは、免疫が誤って末梢神経を攻撃し、障害を引き起こします。
遺伝子異常による家族性ニューロパチーや帯状疱疹後神経障害、ライム病、HIV感染などの感染症も原因となることがあります。
自己免疫疾患が疑われる場合は、専門の医療機関での検査が必要です。
末梢神経障害の治療法
| 治療法 | 概要 |
|---|---|
| 薬物療法 | 神経の過敏性を抑える薬(抗てんかん薬、抗うつ薬など)や、違和感の軽減を目的とした薬を使用 |
| 栄養療法 | ビタミンB群や必要な栄養素を補い、神経の修復や維持をサポート |
| 手術療法 | 神経の圧迫が原因の場合、圧迫部位を除去・緩和するための手術が行われる |
| 再生医療 |
幹細胞や再生因子を用いて、傷ついた神経の修復や機能回復をめざす治療法 |
末梢神経障害の改善には、複数の治療法を組み合わせた適切な治療が必要です。以下で詳しく解説します。
薬物療法
| 分類 | 主な薬剤 | 概要 |
|---|---|---|
| 糖尿病性神経障害 | 血糖コントロール薬(メトホルミンなど) | 血糖値を管理し、神経への負担を軽減 |
| メコバラミン(ビタミンB12製剤) | 神経の修復や維持に必要なビタミンB12を補う | |
| 自己免疫性神経障害 | 免疫グロブリン製剤、ステロイド薬 | 自己免疫による神経の炎症を抑える |
| 免疫抑制薬(アザチオプリンなど) | 免疫の過剰な働きを抑制し、神経への攻撃を防ぐ | |
| ビタミン欠乏性神経障害 | ビタミンB1、B12、葉酸など | 不足しているビタミンを補い、神経の機能回復を促す |
| 症状に対する治療薬 | プレガバリン、ガバペンチン、デュロキセチン | 神経の興奮を抑え、しびれや神経障害性疼痛を緩和 |
| 抗けいれん薬(カルバマゼピンなど) | 神経の過剰な信号を抑え、不快感を軽減 |
(文献8)
症状緩和を目的とし、しびれや不快な感覚を抑える薬が用いられます。
末梢神経障害の症状によって処方される薬剤が異なり、服用は医師の指示に従いながら服用し、自己判断で量を増減させたり中止したりしてはいけません。
薬剤の服用でも改善が見込めない場合や副作用が出た場合は、医師に相談しましょう。
栄養療法
| 栄養素 | 主な役割 | 多く含まれる食品例 |
|---|---|---|
| ビタミンB群 | 神経の修復・機能維持 | 豚肉、レバー、魚、卵、緑黄色野菜 |
| タンパク質 | 神経や筋肉の材料となる | 肉、魚、大豆製品、卵 |
| 食物繊維 | 血糖コントロールや便通の改善 | 野菜、果物、海藻、きのこ類 |
| 抗酸化物質 | 神経の酸化ストレスを軽減・保護 | 緑黄色野菜、果物、ナッツ類 |
| ビタミンB12 | 神経の構造維持・修復に関与 | レバー、貝類、魚、乳製品 |
| シスチン・テアニン | 疼痛の緩和に関与するとされるアミノ酸 | 肉類、魚介類、玉ねぎ、緑茶(※食品によって含有量に差) |
(文献9)
末梢神経障害では、ビタミンB群(B1、B6、B12など)の補給が大切です。医師や管理栄養士の指導のもと、個々の状態に合わせた栄養管理を行います。
栄養療法を行う場合は、医師の指導に従い、偏った栄養補充は行わないようにしましょう。
手術療法
| 項目 | 概要 |
|---|---|
| 目的 | 神経の圧迫除去、損傷した神経の修復 |
| 代表的手術 | 神経剥離術、神経縫合・移植術、脊椎手術、胸郭出口症候群手術 |
| メリット | 薬やリハビリで改善しない症状の改善、根本原因の除去が可能 |
| デメリット | 手術リスクあり(感染・出血など)、術後リハビリが必要な場合もある、手術が適応外の場合もある |
| 手術の適応例 | 圧迫や損傷が明確、重度の麻痺、薬剤療法などで症状が改善しない場合 |
症状が改善しない場合、その圧迫を取り除くための手術が選択肢に入ります。手術療法では、神経圧迫の除去や、神経の修復などが行われます。
手術が適応となるケースは限定的であり、術後もリハビリや後遺症が出る可能性もあるため、患者と医師の慎重な判断が必要です。
再生医療
損傷した神経細胞や組織の修復・再生を目指す再生医療は、末梢神経障害に対して、有効な治療法です。
再生医療では、骨髄や脂肪から採取した幹細胞を損傷した神経組織に移植し、症状の改善を目指します。
薬剤療法で起こりうる副作用や、手術を必要としないのが魅力です。
実際に、当院では40年来の糖尿病患者である方が、内科主治医から糖尿病性末梢神経障害と診断されており、10年以上続く両足のしびれ・既存の治療では改善が見られない状態になっていました。
【治療後の変化】
- 両足のしびれが大幅に軽減
- 日常生活の質の向上
- 健康増進への積極的な姿勢の芽生え
- 「運動療法と食事療法をさらに頑張っていきたい」という前向きな発言
当院(リペアセルクリニック)では、患者様一人ひとりの症状や体調に合わせた治療を行っております。
「長年しびれが改善しない」「薬を増やしたくない」「足の感覚が鈍くなって不安」という方は、ぜひ一度ご相談ください。
再生医療については、以下の記事で解説しております。
末梢神経障害を再発しないための注意点
| 注意点 | 概要 |
|---|---|
| 血糖のコントロール | 高血糖を防ぐことで、神経へのダメージを抑える |
| ビタミンB群と栄養バランス | 神経の修復・維持に必要な栄養素を不足なく摂取する |
| アルコール・喫煙を控える | 神経への直接的ダメージや血流悪化を防ぐ |
| 適度な運動 | 血流促進・筋力維持により神経の機能を保つ |
| ストレス管理・良質な睡眠 | 自律神経のバランスを整え、神経への負担を軽減する |
末梢神経障害の治療後や、症状を悪化させないためには、原因への対処を継続するとともに、神経に負担をかけない生活習慣を心がけることが重要です。
末梢神経障害が再発しないための注意点を解説します。
血糖のコントロールを徹底する
| 方法 | 内容の概要 |
|---|---|
| 食事療法 | バランスよく規則正しく食べる、食物繊維・低GI食品を積極的に摂取する |
| 運動療法 | 有酸素運動(例:ウォーキング、水泳)を無理なく継続する |
| 薬物療法 | 医師の指示で血糖降下薬を服用 |
| 定期検査 | 血糖値やHbA1c(ヘモグロビンエーワンシー)を定期的に測定 |
糖尿病性神経障害の予防・進行抑制において重要なのは、血糖値を良好な範囲に維持することです。
医師の指示に従い、食事療法、運動療法、必要であれば薬物療法を継続し、定期的に血糖値をチェックしましょう。
継続的な血糖コントロールは、末梢神経障害の再発予防だけでなく、糖尿病との合併症などへの予防にもつながります。
ビタミンB群の摂取と栄養バランスを整える
| ビタミン | 主な働き | 不足時のリスク |
|---|---|---|
| B1(チアミン) | 糖質をエネルギーに変換、神経細胞のエネルギー源を供給 | 神経の炎症など |
| B6(ピリドキシン) | 神経伝達物質の合成、神経の興奮を抑制 | しびれの発生など |
| B12(コバラミン) | 神経細胞の修復・再生をサポート | 神経の変性・破壊、重度な神経障害のリスク |
ビタミンB群(とくにB1、B6、B12)は神経の機能維持に重要な役割を果たします。これらのビタミンを多く含む食品(豚肉、レバー、魚介類、豆類、緑黄色野菜など)を意識的に摂取しましょう。
特定の栄養素に偏った食事ではなく、全体的な栄養バランスが取れた食事を心がけることが大切です。
アルコール摂取と喫煙を控える
アルコールは神経に直接的なダメージを与える可能性があります。喫煙は血行を悪化させ神経への栄養供給を妨げます。神経の健康を維持するためには、できる限りアルコール摂取を控え(節酒)、禁煙が大切です。
末梢神経障害の予防と症状改善のためにも、神経細胞を傷つける過度のアルコール摂取や、血管を収縮させるタバコは控えましょう。
適度な運動を日常に取り入れる
| 運動による効果 | 概要 |
|---|---|
| 血行促進 | 神経に酸素と栄養を届け、機能低下を防ぐ |
| 筋力維持 | 筋力低下を防ぎ、神経への負担を軽減 |
| 血糖コントロール | 血糖値を安定させ、神経へのダメージを軽減 |
| ストレス軽減・自律神経調整 | ストレスを和らげ、自律神経のバランスを整える |
| 神経再生の促進 | 神経成長因子(NGF)の産生を促し、神経の修復や再生を助ける |
ウォーキングや軽いジョギング、ストレッチなどの適度な運動は、血行を促進し、神経への酸素や栄養の供給を改善する効果が期待できます。
運動を行う場合は、怪我に注意し、無理のない範囲で行うことが大切です。運動の内容は、医師の指示に従うようにしましょう。
ストレス管理や睡眠の質を高める
| 項目 | 主な方法 |
|---|---|
| ストレス管理 | リラックス時間の確保(入浴・音楽など)、適度な運動、専門家への相談 |
| 睡眠の質向上 | 規則正しい生活リズム、寝る前のスマホ・カフェイン・アルコールを避ける |
過度なストレスや睡眠不足は、自律神経の乱れを招き、血行や免疫力を低下させ、神経症状を悪化させる原因になります。
趣味や入浴、瞑想など、自分に合った方法でリラックスし、ストレスをため込まないことが大切です。
規則正しい生活と十分な睡眠で、神経の修復を促しましょう。
末梢神経障害の症状がある方は早めに医療機関を受診しよう
足のしびれや感覚の異常、力の入りにくさなど、末梢神経障害を疑う症状がある場合は、自己判断せずに早めに医療機関を受診しましょう。
末梢神経障害は放置すると症状が進行し、悪化する恐れがあります。
少しでも末梢神経障害の疑いのある方は当院「リペアセルクリニック」にご相談ください。
当院では、患者さま自身の細胞や血液を活用し、自然治癒力を高める再生医療による治療を行っています。
損傷した神経の修復を促すことで、しびれ・痛み・脱力感などの改善を目指す治療法で、従来の対症療法とは異なるアプローチが期待できます。
末梢神経障害が疑われる症状でお困りの方は、一人で悩まず、ぜひ当院の無料カウンセリングをご利用ください。
参考記事
独立行政法人 医薬品医療機器総合機構「末梢神経障害」
https://www.pmda.go.jp/files/000145962.pdf(最終アクセス:2025年4月9日)
Michael C. Levin, et al.(2023)Weakness.MSD MANUAL Professional Version
https://www.msdmanuals.com/professional/neurologic-disorders/symptoms-of-neurologic-disorders/weakness (Accessed: 2024-04-09)
Michael Rubin, et al. (2022).Peripheral Neuropathy.MSD MANUAL Professional Version
https://www.msdmanuals.com/professional/neurologic-disorders/peripheral-nervous-system-and-motor-unit-disorders/peripheral-neuropathy (Accessed: 2024-04-09)
Larry E. Johnson, et al. (2024). Vitamin B12 Deficiency.MSD MANUAL Consumer Version
https://www.msdmanuals.com/home/disorders-of-nutrition/vitamins/vitamin-b12-deficiency (Accessed: 2024-04-09)
Michael Rubin, et al. (2024). Guillain-Barré Syndrome (GBS).MSD MANUAL Consumer Version
https://www.msdmanuals.com/home/brain-spinal-cord-and-nerve-disorders/peripheral-nerve-and-related-disorders/guillain-barr%C3%A9-syndrome-gbs(Accessed: 2024-04-09)
Michael Rubin,et al. (2022). Charcot-Marie-Tooth Disease.MSD MANUAL Consumer Version
https://www.msdmanuals.com/home/brain-spinal-cord-and-nerve-disorders/peripheral-nerve-and-related-disorders/charcot-marie-tooth-disease(Accessed: 2024-04-09)
Kenneth M. Kaye, et al. (2023). Shingles.MSD MANUAL Consumer Version
https://www.msdmanuals.com/home/infections/herpesvirus-infections/shingles(Accessed: 2024-04-09)
ガン科学療法を受ける患者さんへ末梢神経障害『東邦大学医療センター薬学部』, pp.1-2, 2020年
https://www.sakura.med.toho-u.ac.jp/sinryoka/yakuzai/ue7s91000000a3px-att/massyousinnkeisyougai.pdf(最終アクセス:2025年4月9日)
木田 耕太「神経疾患における栄養療法,その基礎知識」, pp.1-5, 2020年
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsnt/39/1/39_8/_pdf(最終アクセス:2025年4月9日)