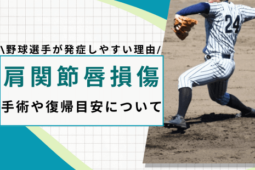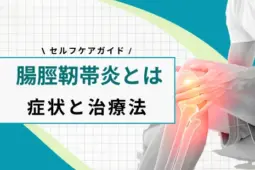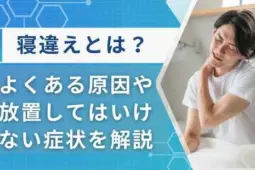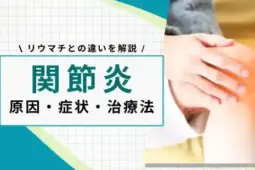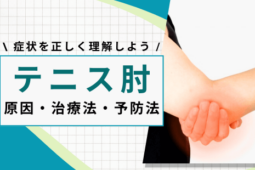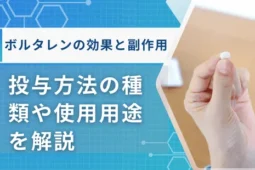- スポーツ外傷
- その他、整形外科疾患
胸郭出口症候群に効果的なストレッチとは?自宅でできるセルフケアを医師が紹介
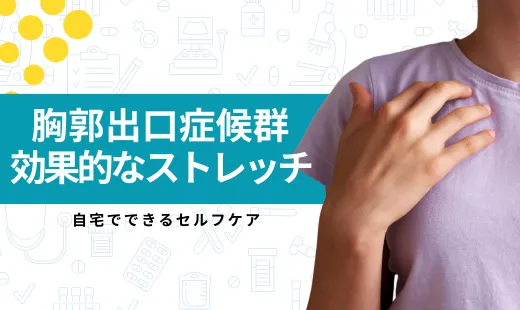
「胸郭出口症候群に効果的なストレッチとは?」「自宅でできるセルフケアも知りたい」
肩から腕にかけて痛みやしびれが生じる「胸郭出口症候群」に、日々悩まされる方は多いのではないでしょうか。
悪化すると日常生活に支障をきたすため、早めの対策が重要ですが、自宅で行うストレッチで症状を軽減できる場合があります。
この記事では、症状緩和に効果的なセルフケアとして、ストレッチやマッサージ、ツボ押しを詳しく紹介します。
痛みを軽減して快適な毎日を目指したい方は、ぜひ最後までご覧ください。
目次
胸郭出口症候群を和らげるセルフケアとストレッチ
胸郭出口症候群はセルフケアによって症状の軽減が期待できます。
ストレッチでは首や肩、鎖骨周囲の筋肉をほぐして神経や血管の圧迫を緩和するため、痛みやしびれが和らぐでしょう。
ここでは、初心者でもできる以下3つのストレッチやマッサージ方法をご紹介します。
- 胸鎖関節のマッサージ
- 鎖骨周囲筋のマッサージ
- 小胸筋のストレッチ
日常生活に取り入れて、症状の緩和を目指してみましょう。
胸鎖関節のマッサージで肩周りをほぐす
1. 「兪府(ゆふ)」というツボを押さえる(鎖骨の真下、胸骨の際から指一本分横の位置に取ります)
2. 手で胸骨と鎖骨のつな繋ぎ目のところをさするようにマッサージする
3. 慣れてきたら、同部位を押さえた状態で肩を回す
欠盆というツボをつかむ鎖骨周囲筋のマッサージ
1. 「欠盆(けつぼん)」というツボを挟むようにつかむ(鎖骨中央のすぐ上、大きくへこんでいる場所にあります)
2. 少し前屈みになり鎖骨を浮き出させたら、反対の手の親指を鎖骨の下に入れ、その上から人差し指で挟むようにつかむ
3. つかみながら周りの筋肉をほぐすようにマッサージする
首から鎖骨にかけての痛みは小胸筋ストレッチで解消
1. 「中府(ちゅうふ)」というツボの位置を押す(鎖骨の外側端から指一本分下の場所です)
2. 反対側の手で小胸筋(※)に対して垂直に押す
※鎖骨外側 1 / 3部から 3 ~ 4 横指下の部分をゆっくりと触診します
3. 押した状態で腕を 20 回ほど前後に振る
4. 少しずつ位置をずらしながら 5 セット程度行う
セルフケアは無理のない範囲で、様子を見ながら行いましょう。
胸郭出口症候群とは「神経や血管が胸郭出口で圧迫されて起こる疾患」
胸郭出口症候群とは、首から肩にかけての神経や血管が「胸郭出口」という部位で圧迫されて生じる症状の総称です。
一般的な症状として肩から手先にかけての「痛み・しびれ・肩こり」が挙げられます。
また、この疾患にはスポーツ選手から主婦まで、幅広い年代や分野の人が悩まされているのも特徴です。
ここでは、胸郭出口症候群の原因や特徴について詳しく解説します。
胸郭出口症候群の原因は「肩・腕に負担がかかるスポーツや生活習慣」
胸郭出口症候群の原因は、日常生活やスポーツによる肩や腕への負担が挙げられます。
たとえば「野球・テニス・剣道・水泳」など、肩を多用するスポーツは筋肉の緊張が強くなり、神経や血管を圧迫しやすくなります。
また、生活の中では以下のような肩に負担のかかる動作もリスクを高めます。
- つり革を持つ
- 洗濯物を高い位置に干す
- 姿勢不良
予防には、定期的に肩周りの筋肉をほぐすストレッチやマッサージが効果的です。
セルフケアによって症状の改善が期待できる
胸郭出口症候群は、セルフケアを取り入れることで症状の改善が期待できます。
筋肉をほぐし血行を良くすると、神経や血管の圧迫が緩和されるためです。
とくに症状が軽度なうちから対策しておくと、悪化や慢性化を防げます。
ただし、痛みがある場合は無理せず、改善が見られなければ専門医に相談しましょう。
胸郭出口症候群の症状や原因については以下の記事でも解説していますので、参考にしていただければ幸いです。
胸郭出口症候群になりやすい人の特徴3選
胸郭出口症候群になる人の多くは以下のような特徴がみられます。
- オーバーハンドスポーツをする人
- なで肩の人
- 猫背など姿勢が悪い人
自分に当てはまるものが一つでもあれば、注意が必要です。
オーバーハンドスポーツをする人
オーバーハンドスポーツとは、野球のピッチングやバレーボールのアタック、バドミントンのスマッシュなど、腕を上に挙げる動作を繰り返すスポーツを指します。
腕を上から振り下ろす動作は、肩の前方から前胸部の筋肉を使うことが多いため、それらの筋肉が発達し過ぎて、腕神経叢や鎖骨下動静脈を圧迫する可能性がでてきます。
オーバーワークの人も、カラダのコンディションがついていかず、発症する危険性も上がるため注意が必要です。
なで肩の人
胸郭出口症候群が起こりやすい姿勢の一つに「なで肩」があります。
なで肩だと鎖骨が低い位置にあるため、神経や血管が通る鎖骨と肋骨の隙間が狭くなり、圧迫が生じやすくなるのです。
猫背など姿勢が悪い人
猫背など背中が丸まった姿勢を長時間続けると、胸の前側にある小胸筋が縮みやすくなります。
そして小胸筋が硬くなると、腕の神経束や鎖骨下の血管を圧迫するリスクが高まるのです。
また、小胸筋が硬い状態で胸を張ると、脇の下で神経や血管が圧迫されて症状が悪化するケースもあります。
そのため、姿勢が崩れがちな方は、胸郭出口症候群のリスクが増えるため注意が必要です。
胸郭出口症候群の症状をチェックするやり方については以下の記事で紹介しています。セルフチェックをしたい人は参考にしていただければ嬉しく思います。
胸郭出口症候群でストレッチ以外の治療法3選
胸郭出口症候群の治療には、ストレッチやセルフケアの他にも医療による治療法が複数あります。
セルフケアで症状が改善しない場合は、医療機関での適切な治療も検討すべきでしょう。
ここでは代表的な治療法である以下3つについて解説します。
- 薬物療法
- リハビリ(理学療法)
- 手術
本章を参考に、自分に合った胸郭出口症候群の治療法を検討してみましょう。
薬物療法
薬物療法は、痛みや炎症を軽減するために行われる治療方法です。
胸郭出口症候群の症状緩和には、消炎鎮痛剤(ロキソニン・ボルタレンなど)や神経痛に対する薬(プレガバリン・ミロガバリン)の内服が一般的です。
また、痛みが強い場合には、神経周囲に薬を注射するブロック注射も用いられます。
ただし、薬物療法は一時的な痛みの軽減が目的であり、根本的な改善にはセルフケアやリハビリとの併用が効果的です。
リハビリ(理学療法)
リハビリテーションは、筋肉や神経にかかる負担を軽減するための治療法です。
整形外科に通いながら、専門の理学療法士による指導を受けて正しい姿勢や動作を学びます。
姿勢を整えたり筋肉を緩めたりすると、神経や血管への圧迫が軽減し痛みの緩和につながります。
また、筋力を強化しつつ再発防止も図るため、長期的な改善が期待できるでしょう。
手術
手術は薬物療法やリハビリで改善が見られない場合に検討される治療法です。
具体的には、胸郭出口症候群の原因となっている神経や血管の圧迫を物理的に取り除くために行われます。
ただし、手術にはリスクも伴いますので、専門医と十分に相談してリスクとメリットを納得してから判断しましょう。
胸郭出口症候群の治療法については以下の記事もご覧ください。
まとめ|胸郭出口症候群はストレッチだけでなく医療機関への相談も検討しよう
胸郭出口症候群のセルフケアとして行うストレッチやマッサージは、症状を和らげるだけでなく再発予防にも効果的です。
また、日常の姿勢や生活習慣に気を配ることで症状の悪化や予防対策にも役立ちます。
しかし、症状が長引く場合は早めに医療機関に相談してください。
薬物療法や理学療法にて健康を保ちながら改善を目指しましょう。
また、当院「リペアセルクリニック」では、胸郭出口症候群のようなスポーツ外傷の治療法として、再生医療を提供しています。
「メール」や「オンラインカウンセリング」でのご相談も受け付けておりますので、お気軽にお問合せください。
この記事が、胸郭出口症候群でお悩みの方の参考になれば嬉しく思います。
\無料オンライン診断実施中!/