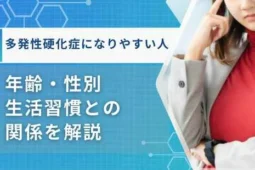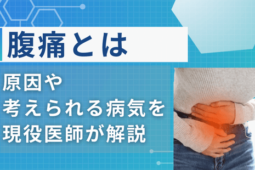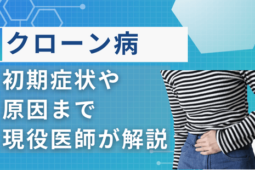- 内科疾患
- 内科疾患、その他
降圧剤(高血圧の薬)の種類と副作用を解説|生活習慣と併用して血圧を下げる方法【医師監修】
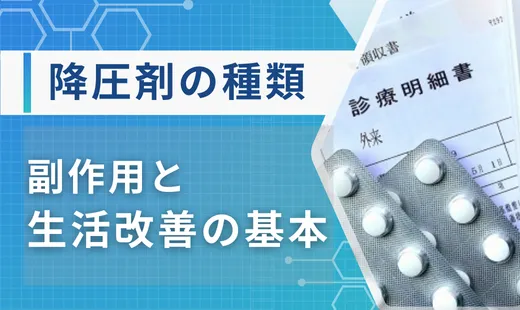
高血圧で医師から降圧剤をすすめられたものの、「薬の違いがわからない」「副作用が不安」と感じている方は少なくありません。
高血圧は放置すると、脳卒中や心筋梗塞など命に関わる病気のリスクが高まるため、適切な治療が必要です。
まずは食事の見直しや運動など生活習慣の改善が基本ですが、それだけでは十分に血圧が下がらない場合に、降圧剤が使用されます。
降圧剤には複数の種類があり、血圧を下げる仕組みが薬ごとに異なるため、体質に合う薬を選ぶことが大切です。
この記事では医師監修のもと、降圧剤の種類と特徴、副作用、そして薬と併用して血圧を下げる生活改善のポイントを解説します。
不安を取り除き、納得して治療を続けられるよう、ぜひ最後までご覧ください。
また、当院「リペアセルクリニック」の公式LINEでは、再生医療に関する情報提供や簡易オンライン診断を実施しています。
高血圧について気になる症状がある方は、ぜひ一度公式LINEにご登録ください。
目次
降圧剤(高血圧の薬)とは?
降圧剤とは、血圧を適切な範囲に保ち、高血圧による病気のリスクを抑えるために使われる薬です。
生活習慣の見直しだけでは血圧の改善が難しい場合に、治療の一環として用いられます。
ここでは、高血圧が起こる原因と、降圧剤が必要になる理由について解説します。
血圧が上がる原因と降圧剤が必要な理由
血圧が上がる原因には、次のような背景があります。
- 加齢による血管の硬化
- 塩分の多い食事
- 運動不足
- 肥満
- ストレスの蓄積
- 遺伝的な体質
上記の影響が重なると血管に負担がかかり、血圧が高い状態が続きやすくなります。
高血圧は自覚症状がほとんどないまま進行することが多く、「少し高いだけだから」と放置してしまう方も少なくありません。
血圧が高い状態をそのままにしておくと、体に負担が蓄積され、将来的な健康リスクが高まります。
そのため、必要に応じて降圧剤を用いた治療が重要になります。
降圧剤の役割は「合併症リスクの回避」
降圧剤の目的は「今ある症状を和らげること」よりも、「将来的に起こり得る病気を防ぐこと」にあります。
高血圧の状態が続くと、脳卒中や心筋梗塞、心不全、腎臓病などの合併症を引き起こすリスクが高まります。
こうした背景から、医師は血圧を適切にコントロールし、合併症を防ぐ目的で降圧剤の使用を提案します。
降圧剤は「血圧を下げるための薬」というよりも、「将来の重大な病気を予防するための治療の一部」と理解しておくと安心です。
降圧剤が必要になる血圧の基準値とは?
現在のガイドラインでは、最高血圧が120mmHg未満、最低血圧が80mmHg未満の状態を「正常血圧」としています。(文献1)
一方で、最高血圧が130〜139mmHg、または最低血圧が80〜89mmHgの場合は「高値血圧」とされ、将来的に高血圧へ進行する可能性が高い状態です。
さらに、最高血圧が140mmHg以上、または最低血圧が90mmHg以上になると、「高血圧症」と診断され、薬物治療を含めた対策が検討されます。
ただし、降圧剤を使うかどうかは血圧の数値だけで決まるわけではありません。
年齢や持病の有無、生活習慣などを総合的に考慮したうえで診断されるため、自己判断せず、医師と相談しながら治療方針を決めることが大切です。
降圧剤(高血圧の薬)の種類と副作用
降圧剤にはいくつかの種類があり、血圧を下げる仕組みや副作用の出やすさがそれぞれ異なります。
代表的な降圧剤は、以下表のとおりです。
【代表的な降圧剤の種類】
| 薬の種類 | 主な作用 |
|---|---|
| カルシウム拮抗薬 | 末梢の血管を拡張させて血圧を下げる作用の薬 |
| ARB(アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬) | 血管収縮を抑えて血圧を下げる作用の薬 |
| ACE阻害薬(アンジオテンシン変換酵素阻害薬) | アンジオテンシンⅡの産生を抑えて血圧を下げる薬 |
| 利尿薬 | 体内の水分と塩分を排出して血圧を下げる薬 |
| β(ベータ)遮断薬 | 心拍数や心臓の負担を抑えて血圧を下げる薬 |
| α(アルファ)遮断薬 | 交感神経の働きを抑えて血管を広げる薬 |
| MR拮抗薬 | ホルモンの作用を抑えて体液量を調整する薬 |
次に、それぞれの特徴と副作用について詳しく解説します。
カルシウム拮抗薬
カルシウム拮抗薬は、末梢の血管を拡張させることで血圧を下げる作用を持つ降圧剤です。
副作用が比較的少なく使いやすいため、現在の高血圧治療では最も多く処方されています。
また、高血圧の治療を始める際に、第一選択として選ばれることが多い薬でもあります。
一方で、血圧が下がりすぎた場合には、次のような症状が出る場合があります。
- めまい感
- 動悸
- 頭痛
- ほてり感
- 顔面紅潮
- むくみ
- 歯茎の肥厚(歯肉肥大) など
| 【主なカルシウム拮抗薬の商品名(後発品含む)】 |
|---|
|
ARB(アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬)
ARB(アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬)は、カルシウム拮抗薬に次いで多く使用されている降圧剤です。
血管に作用する「アンジオテンシンⅡ」という物質の働きを抑え、血管収縮を防ぐことで血圧を下げます。
副作用が少なく、治療の第一選択として使われることもあり、カルシウム拮抗薬だけでは十分な効果が得られない場合に、併用されるケースも少なくありません。
注意点として、副作用の一つに、服用中に血中カリウム値が上昇する可能性があります。
腎機能が低下している方が服用する場合、定期的に腎機能やカリウム濃度等をチェックする必要があります。
また、妊娠中や授乳中の方は服用できません。
| 【主なARBの商品名(後発品含む)】 |
|---|
|
ACE阻害薬(アンジオテンシン変換酵素阻害薬)
ACE阻害薬(アンジオテンシン変換酵素阻害薬)は、ARBと同じアンジオテンシン系に作用する降圧剤です。
アンジオテンシンⅡの産生そのものを抑えることで、血管収縮を防ぎ、血圧を下げます。
ACE阻害薬の副作用として知られているのが「空咳(からせき)」です。
これは体内物質であるブラジキニンの影響によるもので、日本人を含むアジア人に出やすい傾向があります。
妊娠中や授乳中の方は、ARBと同様に服用できません。
| 【主なACE阻害薬の商品名(後発品含む)】 |
|---|
|
利尿薬
利尿薬は、体内の余分な水分や塩分(ナトリウム)を尿として排出し、血液量を減らすことで血圧を下げる薬です。
とくに、塩分摂取量が多い日本人にとって、効果が期待できる薬の一つです。
また、利尿薬は高血圧だけでなく、むくみを伴う心不全がある場合や、他の降圧剤で効果が不十分な場合に併用されます。
副作用としては、電解質異常やトイレの回数増加などが起こる場合があります。
| 【主な利尿薬の商品名(後発品含む)】 |
|---|
|
β(ベータ)遮断薬
β遮断薬は、心臓の働きを抑えて心拍数や心臓の負担を軽くすることで血圧を下げる薬です。
高血圧治療の第一選択になることは多くありませんが、特定の病気を合併している場合に使用されます。
心筋梗塞後や脈が速いタイプの高血圧では、他の降圧剤と併用されることもあります。
喘息などの呼吸器疾患を持病に持ち、吸入を行っている方が使用する場合は、症状が悪化する可能性があるため注意が必要です。
| 【主なβ遮断薬の商品名(後発品含む)】 |
|---|
|
α(アルファ)遮断薬
α遮断薬は、交感神経の働きを抑えて血管を拡張し、血圧を下げる薬です。
交感神経が活性化しやすい早朝に血圧が上昇するタイプの方の場合、就寝前に服用することで効果が期待されます。
α遮断薬は自律神経に働きかける薬のため、交感神経の作用を抑えることで以下のような副作用が起こる可能性があります。
- 起立性低血圧(立ち上がったときに血圧が下がる状態)
- めまい
- 失神
α遮断薬を服用する場合は少量から開始し、副作用に注意しながら徐々に増やしましょう。
| 【主なα遮断薬の商品名(後発品含む)】 |
|---|
|
MR拮抗薬(ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬)
MR拮抗薬(ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬)は、アルドステロンというホルモンの働きを抑え、体内の水分量を調整することで血圧を下げる薬です。
心臓を保護する作用も期待でき、心不全を合併する高血圧で使用されることがあります。
一方で、MR拮抗薬は体液バランスを調節する薬のため、高カリウム血症などの電解質異常に注意が必要です。
とくに、腎機能障害がある方や糖尿病性腎症がある方では、使用できない場合があります。
| 【主なMR拮抗薬の商品名(後発品含む)】 |
|---|
|
\無料オンライン診断実施中!/
降圧剤(高血圧の薬)の配合剤とは?
高血圧の治療において、1種類の降圧剤では血圧が十分に下がらない場合、複数の降圧剤を1つにまとめた「配合剤」を服用するケースがあります。
降圧剤の配合剤は、異なる作用を持つ薬を組み合わせることで、より安定した血圧管理を目指す治療法です。
ここでは、配合剤の仕組みや特徴、代表的な配合パターンについて解説します。
複数の作用を一度に得られる治療薬
配合剤とは、血圧を下げる仕組みが異なる降圧剤を1錠にまとめた薬です。
たとえば、血管を広げる薬と、体内のホルモンの働きを抑える薬を組み合わせることで、それぞれの作用を補い合いながら血圧をコントロールできます。
高血圧の治療が進むにつれて薬の種類が増えると、「飲み忘れが心配」「管理が大変」と感じる方も少なくありません。
配合剤は、薬が増えることへの不安を軽減しやすい治療の選択肢として用いられています。
配合剤のメリットとデメリット
配合剤は、作用の異なる複数の降圧剤を1錠にまとめた薬で、服用する錠数を減らしながら血圧管理を行える点が特徴です。
薬の数が増えると飲み忘れが起こりやすくなりますが、配合剤を用いることで服薬管理がシンプルになり、治療を継続しやすくなる効果が期待できます。
一方で、配合剤には複数の成分が含まれているため、副作用が現れた場合に、どの成分が影響しているのかを判断しにくいという側面があります。
そのため、めまいや体調不良など、これまでと異なる症状を感じた際には、自己判断で服用を中止せず、医師に相談しながら調整を行うことが重要です。
降圧剤の主な配合パターンと代表的な薬剤
現在国内で処方可能な降圧薬の配合剤は、大きく分けて3種類です。
| 降圧薬の配合剤 | 詳細 |
|---|---|
| カルシウム拮抗薬+ARB | ザクラス アイミクス ミカムロ レザルタス エックスフォージなど |
| ARB+利尿薬 | イルトラ エカード プレミネント ミコンビなど |
| カルシウム拮抗薬+ARB+利尿薬 | ミカトリオ |
配合剤を使用する際は、それぞれの降圧薬の副作用に注意してください。
配合剤の場合、名前だけでどの薬が配合されているかがわかりにくいため、注意が必要です。
降圧剤(高血圧の薬)を安全に服用するための注意点
降圧剤は、飲み合わせや服用方法を誤ると、思わぬ副作用につながる場合があります。
ここでは、降圧剤を安全に服用するために知っておきたい注意点を解説します。
グレープフルーツなどの柑橘類を避ける
降圧剤を服用している場合、グレープフルーツを含む柑橘類の摂取は避けるようにしましょう。
グレープフルーツには「フラノクマリン類」と呼ばれる成分が含まれており、体内で薬を分解する酵素の働きを妨げます。
この酵素の働きが阻害されると、薬の成分が体内に通常より長く残り、作用が強く出すぎることで、かえって副作用のリスクを高める恐れがあります。
これは降圧剤に限らず、コレステロール低下薬や抗不安薬など、さまざまな薬で起こる可能性があります。
降圧剤を服用している間は、柑橘類の摂取にも意識し、少しでも気になる場合は医師や薬剤師に相談しましょう。
自己判断で降圧剤の服用をやめるのは危険
血圧が落ち着いてくると、「もう治ったのではないか」と感じ、自己判断で薬をやめてしまう方もいます。
しかし、血圧が下がった状態は、薬によってコントロールされている結果であり、高血圧そのものが治ったわけではありません。
途中で降圧剤の服用を中止すると、再び血圧が上昇し、高血圧の状態に戻ってしまう可能性があります。
そのため、薬の減量や中止を考える場合は、必ず医師と相談しながら進めることが重要です。
また、降圧剤を一生飲み続けなければならないのか不安に感じる方もいるでしょう。
血圧を下げるには薬の服用が重要ですが、中には生活習慣が改善したことで徐々に減量し、降圧薬をやめられた方もいます。
そのため、治療が順調であれば、薬を中止できる可能性は十分にあります。
降圧剤の飲み忘れに気づいたらどうする?
降圧剤を飲み忘れた場合の対応は、薬の種類や服用タイミングによって異なります。
そのため、自己判断で対応せず、あらかじめ医師や薬剤師から指示を受けておくことが大切です。
一般的には、飲み忘れに気づいた時点で時間をずらして服用する場合がありますが、1度に2回分をまとめて飲むことは避けましょう。
まとめて服用すると、血圧が下がりすぎたり、副作用が出やすくなる恐れがあります。
飲み忘れが続く場合や、対応に迷った場合は、早めに医師や薬剤師へ相談しましょう。
降圧剤(高血圧の薬)だけに頼らない!血圧を下げる生活習慣
降圧剤は血圧をコントロールするうえで重要な役割を果たしますが、生活習慣の見直しも同じくらい大切です。
毎日の食事や運動、過ごし方を少し見直すだけでも、血圧に良い影響を与える場合があります。
ここでは、血圧管理に役立つ生活習慣の改善方法について解説します。
食事の改善|食塩を減らす工夫
高血圧の改善には、食事内容の見直しが重要です。
なかでも塩分の摂りすぎは血圧を上げる大きな要因となるため、意識的に減塩を心がけましょう。
日本人は、もともと塩分摂取量が多い傾向にあり、高血圧の方では1日の食塩摂取量を6g未満に抑えることが推奨されています。(文献2)
家庭の食事だけでなく、外食や加工食品にも多くの塩分が含まれている点にも注意が必要です。
減塩を続けるためには、次のような工夫が役立ちます。
- 香味野菜や香辛料を活用して薄味でも満足感を高める
- 外食や加工食品の利用を控えめにする
- 食べすぎを防ぎ、適量を意識する
- 麺類はスープを残す
また、アルコールの飲みすぎも血圧を上げる原因になります。
1日の純アルコール摂取量の目安は約20g程度とされており、ビール中瓶1本(500ml)、日本酒1合(180ml)、ワイン1杯(120ml)程度に相当します。(文献3)
お酒を飲む習慣がある方は、量と頻度を意識することが大切です。
運動習慣の改善|有酸素運動・体重管理
食事とあわせて、運動習慣を見直すことも血圧管理に役立ちます。
高血圧の改善を目的とした運動では、ウォーキングやジョギングなどの有酸素運動がすすめられています。
運動の強さは、「ややきつい」と感じる程度で十分です。
激しい運動を行うと、かえって血圧が上がる場合があるため、無理のないペースを心がけましょう。
目安としては、1日20分以上、週200分程度の運動が推奨されています。(文献2)
ただし、急に長時間の運動を始めると体への負担が大きくなるため、まずは短時間から少しずつ習慣化することが大切です。
まとまった運動時間を確保しにくい場合は、次のような日常生活の中で体を動かす機会を増やす工夫も効果的です。
- エレベーターではなく階段を使う
- 近い距離は歩いたり自転車を利用したりする
- 長時間座り続けないよう、こまめに立ち上がる
こうした積み重ねが、体重管理や血圧の安定につながります。
ストレスケアと睡眠リズムの整備
ストレスや睡眠不足も、血圧に影響を与える要因のひとつです。
強いストレスが続くと自律神経のバランスが乱れ、血圧が上がりやすくなる場合があります。
自律神経の安定には、十分な睡眠の確保と就寝・起床のリズムを整えることが重要です。
また、趣味の時間を持つ、深呼吸や軽いストレッチを行うなど、自分なりのリラックス方法を見つけることも、血圧管理に役立ちます。(文献2)
降圧剤(高血圧の薬)に関するよくある質問
降圧剤を服用する中で「一生続くのか」「体に合わなかったらどうするのか」など、不安や疑問を感じる方も多いでしょう。
治療を続けるうえでは、正しい知識を持ち、必要に応じて医師と相談することが大切です。
ここでは、降圧剤に関してよく寄せられる質問をもとに解説します。
降圧剤は一生飲み続ける?
降圧剤は、必ずしも一生同じ薬を飲み続けなければならないものではありません。
血圧の状態や年齢、体質、生活習慣の改善状況によって、薬の量や種類が調整される場合があります。
また、治療が順調に進み、食事や運動などの生活習慣が整ってくると、医師の判断で減量や中止を検討できる場合もあります。
自己判断で薬をやめるのではなく、定期的な診察を受けながら医師と相談して進めることが大切です。
降圧剤で血圧が下がりすぎた際の対処法は?
降圧剤の影響で血圧が下がりすぎると、めまい、立ちくらみ、ふらつき、倦怠感などの症状が出る場合があります。
とくに立ち上がったときに症状が出やすい場合は、注意が必要です。
こうした症状が続く場合や、日常生活に支障を感じる場合は、早めに医師へ相談しましょう。
薬の量や種類を調整することで、症状が改善するケースも少なくありません。
サプリメントと併用しても大丈夫?
サプリメントの中には、降圧剤の作用に影響を与えるものがあります。
とくに、カリウムを多く含むサプリメントや健康食品は、薬との組み合わせによって体に負担がかかる可能性があります。
自己判断で併用するのではなく、サプリメントを使用している場合や新たに取り入れたい場合は、事前に医師や薬剤師へ相談すると安心です。
安全に治療を続けるためにも、服用しているものはすべて伝えるようにしましょう。
\無料オンライン診断実施中!/
まとめ|降圧剤(高血圧の薬)と生活習慣の両立で血圧を安定させる
降圧剤は、高血圧による脳卒中や心筋梗塞などの重大な病気を防ぐために、血圧を適切な範囲に保つ重要な治療方法です。
降圧剤にはさまざまな種類があり、それぞれ作用の仕組みや副作用が異なるため、自分の体質や状態に合ったものを選ぶことが大切になります。
一方で、高血圧の治療は薬だけで完結するものではありません。
食事の減塩や運動習慣の見直し、十分な睡眠やストレスケアといった生活習慣の改善を併せて行うことで、血圧の安定につながりやすくなります。
また、降圧剤の服用を続ける中で不安や疑問が生じた場合は、自己判断せず、医師や薬剤師に相談することが重要です。
降圧剤と生活習慣の両立を意識しながら、自分に合った血圧管理を続けていきましょう。
参考文献
(文献1)
高血圧治療ガイドライン・エッセンス|日本心臓財団
(文献2)
血圧を適切に保つための10のヒント|日本高血圧学会
(文献3)
アルコール|厚生労働省