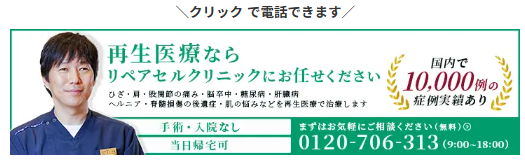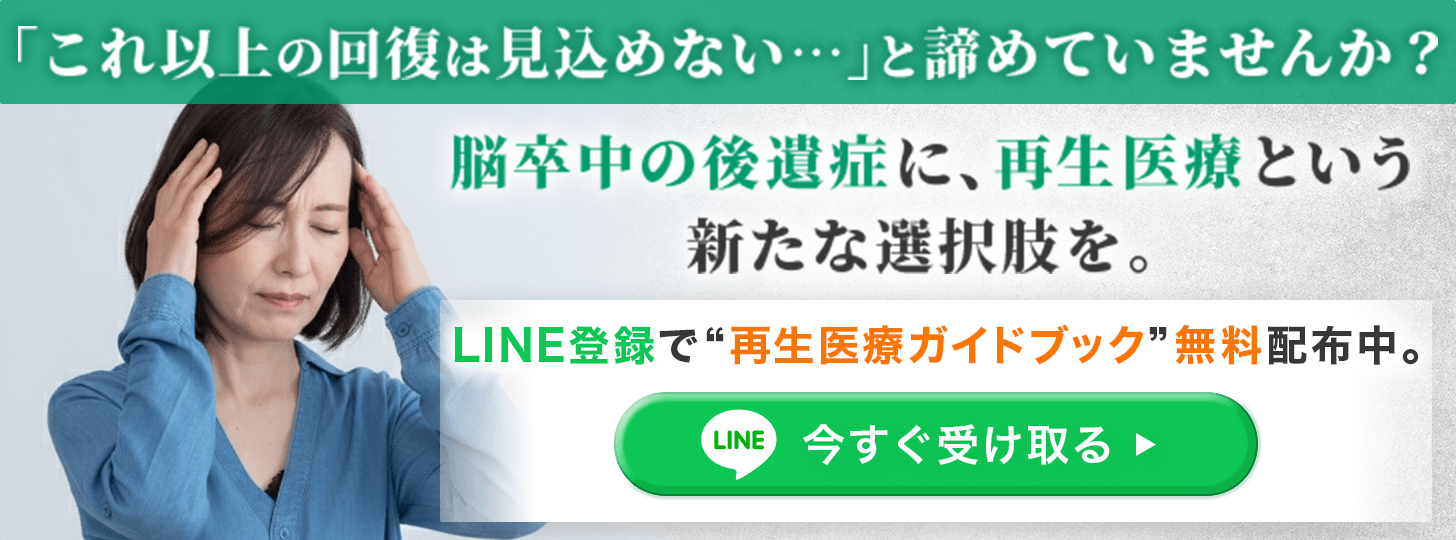- 脳卒中
- 頭部
【医師監修】高次脳機能障害の平均余命はどのくらい?基礎知識と再生医療の可能性を解説
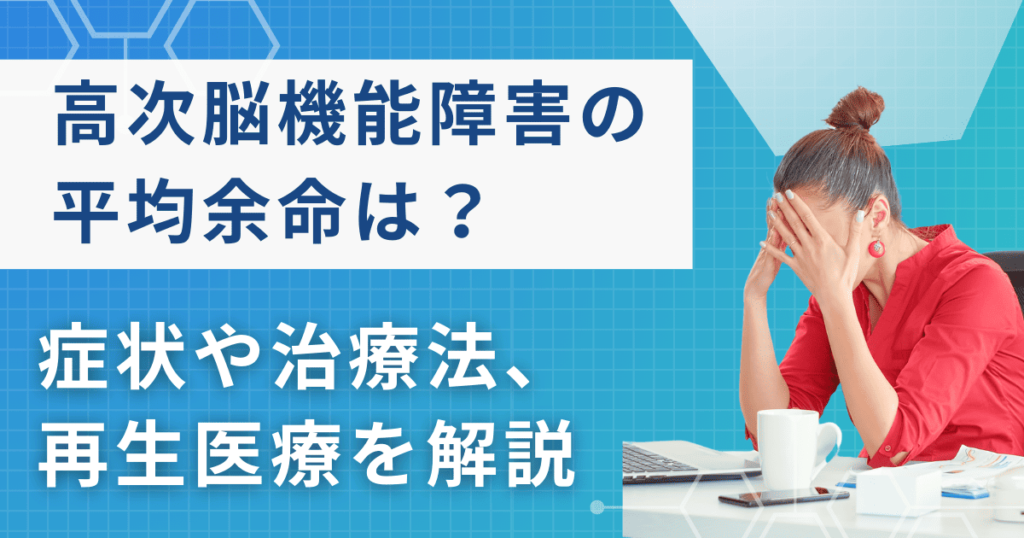
「高次脳機能障害になったら平均余命はどれくらい?」
「余命を伸ばすための治療法はない?」
上記のように、余命や治療法について疑問や不安を抱えている方もいるのではないでしょうか。
本記事では、高次脳機能障害を発症した方の平均余命や、治療法について詳しく解説します。
高次脳機能障害を根本的に治療できる可能性がある再生医療についても紹介しているので、ぜひ治療の参考にしてみてください。
\根本治療につながる再生医療とは/
再生医療とは、機能障害や機能不全になった脳細胞に対して、体が持つ再生能力を利用して損なわれた機能を再生させる医療技術のことです。
従来の治療では難しかった脳血管障害の後遺症治療にも注目されています。
【こんな方は再生医療をご検討ください】
- 高次脳機能障害は治らないと思っている
- 現在受けている治療やリハビリで期待した効果が得られていない
- 大きな手術や長期間の入院をせずに治療する方法を探している
再生医療では、損傷した脳細胞に対してアプローチできる治療法で、従来の治療では元に戻らないとされている脳細胞の改善が期待できます。
高次脳機能障害の治療やリハビリに疲れてしまった方、後遺症の回復を諦めてしまった方の新たな選択肢になる治療法です。
「高次脳機能障害を根本的に治したい」「治療法について詳しく知りたい」という方は、再生医療を専門とする当院リペアセルクリニックにお問い合わせください。
目次
高次脳機能障害の平均余命
高次脳機能障害の平均余命は、健常者の平均余命に比べて短い傾向です。ここでは、高次脳機能障害の平均余命を男女別に紹介します。
なお、高次脳機能障害の平均余命に関しては「脳出血」「脳梗塞」「くも膜下出血」の症状を平均としています。
男性の平均余命
東京福祉局と厚生労働省のデータをもとに比較したところ、高次脳機能障害の男性は健常な男性より平均余命が短くなっています。
高次脳機能障害の男性と健常な男性の平均余命は、以下の通りです。
|
年齢 ※高次脳機能障害の場合、発症年齢 |
高次脳機能障害の男性 |
健常な男性 |
平均余命の差 |
|---|---|---|---|
|
20歳 |
42.61年 |
61.45年 |
18.84年 |
|
30歳 |
35.59年 |
51.72年 |
16.13年 |
|
40歳 |
28.88年 |
42.06年 |
13.18年 |
|
50歳 |
20.16年 |
32.60年 |
12.44年 |
|
60歳 |
11.56年 |
23.68年 |
12.12年 |
|
70歳 |
5.62年 |
15.65年 |
10.03年 |
|
80歳 |
2.47年 |
8.98年 |
6.51年 |
高次脳機能障害の男性と健常な男性における平均余命は、約10年以上の差が生じています。
また、80歳で高次脳機能障害を発症した場合でも、約6年ほど異なります。
データを比べた結果、若いうちに高次脳機能障害を発症するほど平均余命は健常時と比較して短くなってしまう可能性が考えられます。
しかし、近年では高次脳機能障害を根本的に治療できる可能性がある治療法として、先端医療である再生医療が注目されています。
当院リペアセルクリニックでは、無料のカウンセリングも実施しており、再生医療の治療内容についてわかりやすくご説明いたします。
「高次脳機能障害を根本的に治したい」という方は、ぜひ当院までご相談ください。
▼無料相談はこちらから
>>(こちらをクリックして)今すぐ電話で相談してみる
女性の平均余命
東京福祉局と厚生労働省のデータをもとに比較したところ、男性同様、高次脳機能障害の女性は健常な女性より平均余命が短くなっています。
高次脳機能障害の女性と健常な女性の平均余命は、以下の通りです。
|
年齢 ※高次脳機能障害の場合、発症年齢 |
高次脳機能障害の女性 |
健常な女性 |
平均余命の差 |
|---|---|---|---|
|
20歳 |
50.21年 |
67.48年 |
17.27歳 |
|
30歳 |
42.58年 |
57.65年 |
15.07歳 |
|
40歳 |
35.18年 |
47.85年 |
12.67歳 |
|
50歳 |
26.30年 |
38.23年 |
11.93歳 |
|
60歳 |
15.84年 |
28.91年 |
13.07歳 |
|
70歳 |
7.22年 |
19.96年 |
12.74歳 |
|
80歳 |
3.35年 |
11.81年 |
8.46歳 |
高次脳機能障害の女性と健常な女性における平均余命は、約10年以上の差が生じています。また、80歳で高次脳機能障害を発症した場合でも、約8年ほど異なります。(文献1)
高次脳機能障害になった女性の平均余命は男性に比べて長いものの、健常な女性と比較すると短い傾向です。(文献2)
近年では、高次脳機能障害を根本的に治療できる可能性がある治療法として、先端医療である再生医療が注目されています。
当院リペアセルクリニックでは、無料のカウンセリングも実施しており、再生医療の治療内容についてわかりやすくご説明いたします。
「高次脳機能障害を根本的に治したい」という方は、ぜひ当院までご相談ください。
▼無料相談はこちらから
>>(こちらをクリックして)今すぐ電話で相談してみる
高次脳機能障害の主な症状
高次脳機能障害は、脳の損傷によって「考える」「記憶する」「行動する」といった人間の重要な機能に影響を及ぼします。
高次脳機能障害を発症すると、主に以下の症状が見られます。
- 新しいことを覚えられない・事実と異なる話をするなどの記憶障害
- ミスが多い・集中できないなどの注意障害
- 寝てばかり・暴力的などの社会的行動障害
- 自分で計画ができない・優先順位が決められないなどの遂行機能障害
- うまく話せないなどの症状
高次脳機能障害はさまざまな症状を引き起こすため、自立した生活が困難になります。また、外見だけでは症状がわかりにくいため、仕事や人付き合いなどの社会活動が困難と感じるケースも少なくありません。
一般的には高次脳機能障害の症状が理解されにくい点から、本人や家族が周囲との関係でストレスを感じる場合もあります。
高次脳機能障害の種類や原因など、包括的な解説を見たい方は「【医師監修】高次脳機能障害とは|種類・原因・治療法を解説」をご覧ください。
また、高次脳機能障害の症状について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
数年後に治った人はいる?高次脳機能障害の回復過程
高次脳機能障害が完治した事例は、2025年1月において確認されていません。高次脳機能障害は、脳の損傷による障害のため、完治するのは難しいとされています。
しかし、リハビリ専門医療機関や地域活動支援センターなどで適切な支援を受けると、症状が回復する可能性があります。また、症状が残っても、支援により日常生活や社会生活を送れるようになるケースが期待できます。
そのため、家族や職場など周囲の方が高次脳機能障害への理解を深め、適切な支援をすることが回復過程においては重要です。
高次脳機能障害は治るのか知りたい方は、あわせて以下の記事をご覧ください。
高次脳機能障害の治療法
高次脳機能障害の治療法は、薬物療法とリハビリの2つに分類されます。各治療法の特徴は、以下の通りです。
|
治療法 |
特徴 |
|---|---|
|
薬物療法 |
|
|
リハビリ |
|
また、高次脳機能障害のリハビリ方法は、症状や患者の状態に応じて異なります。例えば、注意障害がある場合は、集中しやすい環境を整えるリハビリを実施します。
体を動かしたり脳トレを実施したりと、自宅でできるリハビリもあるため、医師に相談の上、無理のない範囲で取り入れてみましょう。
高次脳機能障害の余命に悩む方への選択肢「再生医療」
近年、高次脳機能障害の新たな治療法として再生医療が注目されています。再生医療は人間が持っている再生力を用いた治療法で、失われた組織や機能の修復を行います。
再生医療で期待できる治療効果は、以下の通りです。
- 壊れた脳細胞を再生医療で修復し、身体の機能回復を目指す
- 後遺症に対するリハビリ効果を向上させる
- 傷ついた血管を修復し再発を予防する
高次脳機能障害の症状でお悩みの方は、治療の選択肢の一つとして再生医療を検討してみましょう。
【こんな方は再生医療をご検討ください】
- 高次脳機能障害は治らないと思っている
- 現在受けている治療やリハビリで期待した効果が得られていない
- 大きな手術や長期間の入院をせずに治療する方法を探している
再生医療では、損傷した脳細胞に対してアプローチできる治療法で、従来の治療では元に戻らないとされている脳細胞の改善が期待できます。
高次脳機能障害にお悩みの方は、ぜひ当院「リペアセルクリニック」へご相談ください。
まとめ・高次脳機能障害の平均余命を踏まえたうえで適切な治療を受けよう
高次脳機能障害の平均余命は、健常な方と比べて短い傾向です。特に、発症した年齢が若いほど健常な方と比較して、余命は短いと考えられます。
高次脳機能障害を発症すると、記憶障害や注意障害などさまざまな症状が見られます。完治した事例は確認されていませんが、適切な治療法により症状が改善する可能性はあります。
高次脳機能障害の治療法として、薬物療法やリハビリの他に再生医療という選択肢もあります。
再生医療は、人間の体が持つ能力を活かした最新の治療法となるため、高次脳機能障害の症状回復へ向けた一助となる場合があります。
高次脳機能障害に向き合い適切な治療を受け、症状の回復へ向けて行動しましょう。
\こちらを”クリック”して無料相談/
0120-706-313
(受付時間:9:00〜18:00)

脳卒中のお悩みに対する新しい治療法があります。
参考文献
(文献1)
東京都福祉保健局「高次脳機能障害者実態調査結果 第3章 高次脳機能障害者数の推計」https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/fukushi/houkoku4
(文献2)
厚生労働省「令和5年簡易生命表の概況」https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/life/life23/dl/life23-15.pdf