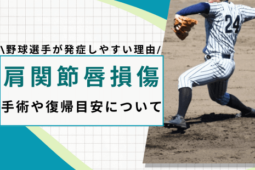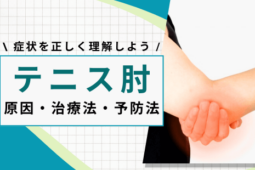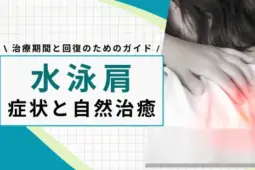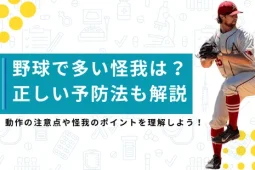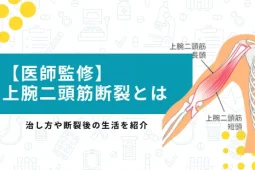- 野球肘
- 上肢(腕の障害)
- 肘関節
- スポーツ外傷
外側が痛む野球肘の原因や治し方を医師が解説
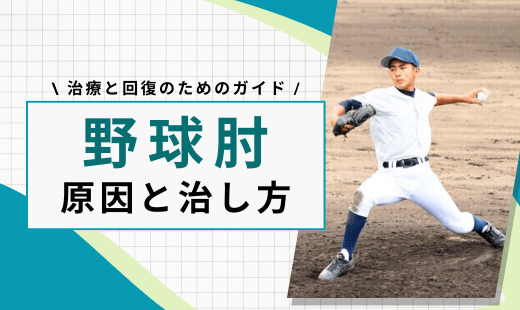
「練習後にいつも肘の外側が痛む」
「思い切りボールを投げられない」
日々野球に打ち込む中で、肘の外側に違和感はありませんか。その症状は、野球肘かもしれません。
野球肘とは、投球動作によって引き起こされます。野球肘の主な原因は、オーバーユースや投球フォームの乱れにあります。本記事では、外側が痛む野球肘について解説します。
- 外側が痛む野球肘の原因
- 外側が痛む野球肘の治し方
- 外側が痛む野球肘を治す方法
- 外側が痛む野球肘を再発させないための予防法
野球肘は適切な治療と予防策をしっかり守れば、改善する症状です。外側が痛む野球肘の症状でお悩みの方は、ぜひ最後までお読みください。
外側が痛む野球肘の原因
野球肘(外側)は、投球動作の繰り返しによって肘の外側にストレスがかかることで発症します。
とくに成長期の段階は、骨や軟骨が未発達なため、損傷を起こしやすいのも特徴です。野球肘で外側が痛む原因は以下の3つです。
- 不適切な投球フォーム
- オーバーユース(使いすぎ)
- 成長期の骨・関節の未成熟
野球肘(外側)の原因を解説します。
また、野球肘が野球以外のスポーツでも発症する可能性ついて解説した参考記事もあわせてご覧ください。
不適切な投球フォーム
| フォームの種類 | 動作の特徴 | 肘への影響 |
|---|---|---|
| 肘下がりのフォーム | 投球時に肘が肩よりも下がる | 肘の外側に過度な外反ストレスが加わる |
| 手投げのフォーム | 下半身や体幹を使わず腕だけで投げる | リリース時に肘関節へ瞬間的な高負荷 |
| 体の開きが早いフォーム | 上半身が先に開くことでリリースが不安定になる | 腕のしなりが失われ、肘が遅れて出てくる |
| ステップ不足のフォーム | ステップが小さい、動きが止まる、前足が早く着地する | 上半身主導になり肘が遅れて出る |
(文献1)
肘に過度な負担をかける投球フォームは、野球肘(外側)を引き起こす原因です。手投げになる、肘が下がるフォームなどは、肘の外側の小さな骨や軟骨に繰り返し牽引力や圧迫力を生じさせます。フォームの歪みが長年積み重なることで、損傷が蓄積し、肘の違和感として現れます。
予防には、指導者による適切なフォーム指導や、自身のフォームを見直すことが大切です。
オーバーユース(使いすぎ)
試合や練習での投球過多は、肘関節に繰り返しダメージを与え、野球肘を引き起こします。疲労が蓄積すると組織が回復しきれず、炎症や損傷の負担を増加させます。
とくに、投球数や練習時間の管理が不十分な場合、野球肘を引き起こしやすくなるため、注意が必要です。オーバーユースを防止するには、投球数の制限(1日70球程度など)や、ウォーミングアップ・クールダウンの時間を設けることが大切です。
成長期の骨・関節の未成熟
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 原因部位の特徴 | 成長期の骨には骨端線(成長軟骨)があり、ストレスに弱い構造をしている |
| 成長期のリスク | 骨端軟骨は未成熟で、機械的ストレスに対して脆弱 |
| 野球肘(外側)との関連 | 投球による圧迫で上腕骨小頭に微小骨折や血流障害が起き、離断性骨軟骨炎を発症しやすい |
成長期の段階では、骨や関節が完全にできあがっていないため、強い力が加わると損傷を起こしやすくなります。この時期に過度な負荷がかかると、骨端線と呼ばれる成長軟骨帯を損傷し、野球肘を発症する原因になります。
野球肘を引き起こさないためにも、年齢や発育に応じた投球管理が大切です。
外側が痛む野球肘の治療方法
| 治療法 | 内容 | 特徴・ポイント | 適応されるケース |
|---|---|---|---|
| 保存療法 | 安静、投球中止、装具の使用などで自然回復を目指す | 体への負担が少なく、多くの初期症状に対応できる | 軽症~中等症、骨に大きな損傷がない場合 |
| 薬剤療法 | 炎症や違和感を抑える薬(消炎鎮痛薬など)を使う | 違和感を和らげ、回復をサポートする補助的な治療 | 違和感が強いとき、保存療法と併用されることが多い |
| 手術療法 | 損傷した骨・軟骨を除去、骨片の固定、関節鏡手術など | 根本的な修復が必要な場合に有効だが、リハビリが必要 | 保存療法で改善しない中等度〜重症の場合 |
| 再生医療 | 自己由来の幹細胞やPRPを用いて組織の再生を促す治療 | 身体への負担が少なく、回復力を高める治療法 | 手術を避けたいケースや、早期復帰を目指す場合 |
野球肘(外側)は、症状に合わせた適切な治療が求められます。野球肘の症状が重度の場合、手術を行うケースもあります。
外側が痛む野球肘の治し方は以下の4つです。
- 保存療法
- 薬剤療法
- 手術療法
- 再生医療
野球肘(外側)の治療法について解説します。
以下の記事では肘のクリーニング手術について詳しく解説しています。
保存療法
| 治療の目的 | 治療方法 | 内容・ポイント |
|---|---|---|
| 炎症の抑制 | 安静 | 投球中止や日常生活での肘の使用制限。負担を避けることで炎症を抑える |
| アイシング | 1回15〜20分、1日数回の冷却で腫れ・違和感を軽減。投球後や違和感が強い時に有効 | |
| 薬剤療法 | NSAIDsなどの消炎鎮痛薬を医師の指示で服用する。炎症と違和感をコントロール | |
| 組織の修復 | 安静(継続) | 靭帯や軟骨の自然回復を促す。違和感が取れるまでは無理な動作を避ける |
| 機能回復 | リハビリテーション | 肘周囲の筋力・柔軟性を高め、再発予防。専門家の指導で段階的に進める |
| 装具療法 | サポーターやテーピングで肘を固定・安定化。運動中や回復期に使用する |
初期の野球肘(外側)に対しては、保存療法で症状の改善を目指します。野球肘(外側)の治療は、安静、アイシング、リハビリ(ストレッチ・筋トレ)、投球フォーム修正などを、違和感の程度や状態に合わせて組み合わせて行います。
リハビリは自己判断せず、違和感が再発した場合は、すぐにリハビリを中止し、医師に相談してください。
薬剤療法
| 項目 | 内容 | ポイント・補足 |
| 治療の目的 | 違和感の緩和 | 炎症や違和感を抑え、日常生活やリハビリをスムーズに進めるために使用 |
| 炎症の抑制 | 組織の回復を促進し、治癒までの時間を短縮する効果 | |
| 薬剤の種類 | NSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬) | 内服・塗り薬・湿布など(例:ロキソプロフェン、ジクロフェナク) |
| ステロイド注射 | 炎症が強い場合に使用。効果は高いが副作用リスクあり(関節内注射など) | |
| ヒアルロン酸注射など | 関節の滑らかさを保ち、痛みを和らげる補助的な治療法 | |
| 注意点 | 根本的な治療ではない | 薬だけでの完治は難しく、投球フォームの改善や休養が不可欠 |
| 副作用の可能性 | 胃腸障害やアレルギーなど。自己判断での使用は避ける | |
| 医師の指示が必須 | 症状に応じた薬の選択が重要。医療機関で診察を受けること |
違和感が強く出る場合には、炎症を抑えるための外用薬や内服薬が用いられることがあります。
しかし、薬剤療法はあくまで症状を緩和するためのものであり、根本的な治療ではありません。副作用が出る可能性もあるため、医師の指導のもと、薬を服用しましょう。
手術療法
| 項目 | 内容 | 補足・ポイント |
|---|---|---|
| 手術療法の位置づけ | 原則は保存療法が優先される | 症状が軽度~中等度なら、まずは安静・アイシング・リハビリで経過をみる |
| 保存療法で改善が見られない場合に手術を検討 | とくに骨軟骨が損傷している場合や関節内に遊離片がある場合 | |
| 手術が必要となる原因 | 離断性骨軟骨炎の進行 | 剥がれた骨軟骨が関節内で動き、引っかかりや痛みを引き起こす |
| 骨軟骨の損傷 | 投球による負荷で軟骨が損傷し、自然治癒が難しい状態になる | |
| 手術法 | 関節鏡手術 | 関節内を小さなカメラで確認しながら遊離片の除去や修復を行う。傷が小さく回復も早い |
| 骨軟骨移植術 | 広範囲の損傷に対して、自身の骨軟骨を別部位から移植して再建する方法 |
保存療法で症状が改善しない場合は、手術療法が検討されます。野球肘(外側)の手術では、剥離した骨片や軟骨片の摘出、損傷した靭帯の修復といった処置が行われます。
手術療法は、後遺症や感染症のリスクを伴う可能性があるため、治療を選択する際には医師との十分な相談が不可欠です。(文献2)
再生医療
患者自身の血液や骨髄由来の成分を患部に注入し、組織の修復を促進します。再生医療は、従来の治療法と比較して、薬の副作用が少ない、あるいは手術に伴うリスクを軽減できる利点があります。
現時点では、再生医療を提供できる医療機関は限られているため、再生医療を検討している方は、再生医療を取り扱っている医療機関での受診が必要です。
以下では再生医療について詳しく解説しています。
外側が痛む野球肘を早く治す方法
医師の指導に従いながら、適切に肘のケアを行うことは、治療効果を高める上で大切です。
野球肘(外側)を治す方法は以下の4つです。
- 安静期間を守る
- アイシングを行う
- 適度なリハビリを行う
- 投球フォームを見直す
野球肘を治す方法について解説します。
安静期間を守る
| 効果 | 内容 | 補足・ポイント |
|---|---|---|
| 炎症の悪化を防ぐ | 肘の使いすぎで生じた炎症を悪化させないために安静が必要 | 炎症を悪化させないためには安静が必要。違和感が軽減しても内部の炎症は残っていることが多く、早期復帰は再発リスクを高める |
| 組織の修復を促進 | 靭帯や軟骨、骨などの損傷した組織が自然に回復する時間を確保 | 動かし続けると修復が遅れ、治療期間が長引く可能性がある |
| 慢性化を防ぐ | 十分な休養を取ることで、症状の長期化や重症化を防げる | 放置すると慢性痛や可動域制限に進行し、手術が必要になるケースも |
違和感を無視して投げ続けると、炎症や損傷が悪化し回復が長引く可能性があります。安静期間を守ることで、炎症が悪化するのを防ぎ、組織の修復を促します。
違和感が治まるまでの間は、投球練習や肘に負担のかかる動作は避けるべきです。焦らず身体を休ませ、復帰時期は医師と相談し、指示に従うようにしましょう。
アイシングを行う
| アイシングの手順 | 内容 | ポイント・注意点 |
|---|---|---|
| 手順1.用意するもの | 氷または保冷剤、薄手のタオル、タイマー | 保冷材は凍結しすぎないものが望ましい(冷却ジェルなども可) |
| 手順2.氷を包む | 氷や保冷剤をタオルで包む | 凍傷を防ぐために直接肌に当てないようにする |
| 手順3.肘の外側にあてる | 違和感や腫れがある部分を中心に冷やす | 肘の外側(外側上顆〜関節周囲)を広く覆うようにあてる |
| 手順4.時間を計る | 1回15〜20分を目安に冷却 | 長時間の冷却は避ける。間隔を空けて1日数回行う |
| 手順5. 使用後のケア | 肌の状態を確認し、赤みや感覚異常があれば中止 | 湿布など他の冷却法との併用は医師の指示に従う |
患部の違和感や炎症を軽減するには、冷却処置であるアイシングが効果的です。練習後や入浴後など、肘に熱感があるときに行います。
冷やしすぎると凍傷の恐れがあるため、タオルを巻いた氷嚢などを使い、違和感のある部分を冷やします。
冷却は1回につき15〜20分を目安に行い、無理のない範囲で、やさしく冷やすことが大切です。
適度なリハビリを行う
| 効果の観点 | 内容 | ポイント・補足 |
|---|---|---|
| 機能回復と柔軟性向上 | 関節や筋肉の硬さを防ぎ、肘の動きをスムーズに保つ | 早期復帰を目指すために、安静だけでなく積極的な可動域訓練が必要 |
| 筋力低下の防止・再発予防 | 肘周りの筋力を維持・強化し、再発リスクを減らす | 長期間の安静後は、段階的な筋トレが再発防止に重要 |
| 違和感のコントロールと回復促進 | 軽い運動で血流を促し、組織の修復を助ける | ストレッチや軽負荷の運動で症状を悪化させずに進められる |
| 投球フォームの改善 | 誤ったフォームを修正し、肘への負担を減らす | 医師の指導のもと、再発防止につながる正しいフォームを習得 |
違和感がある程度改善した段階で、医師の指導のもと、段階的にリハビリを進めていきましょう。リハビリでは、肘周りの柔軟性を取り戻すストレッチや、違和感がでない範囲での軽い筋力トレーニングを実施します。
無理のない範囲で徐々に運動強度を上げていくことが大切です。リハビリは自己流ではなく、医師の指示に従いながら行いましょう。
投球フォームを見直す
| 期待できる効果 | 内容 | ポイント・補足 |
|---|---|---|
| 肘への負担軽減 | 誤ったフォーム(肘下がり・手投げ)は外側に過度な負荷をかける | 正しいフォームで全身の力を使うことで、肘の負担が大幅に軽くなる |
| 早期回復と再発予防 | 症状が治っても誤ったフォームでは再発リスクが残る | 原因そのものを見直すことで改善を目指す |
| 全身のバランス改善 | 肘だけでなく肩・体幹・下半身の連動が大切 | フォーム改善により全身の動きがスムーズになり、肘の負担を分散できる |
| 投球パフォーマンス向上 | 肘の負担を減らしながら球速やコントロールが向上 | 怪我を防ぎつつ、より良い投球フォームが身につく |
誤ったフォームでの投球は肘へ負荷をかけるだけでなく、症状を再発させる恐れがあります。フォームは自分だけでは改善しにくい部分が多く、医師や指導者のアドバイスが不可欠です。
正しいフォームを身につけることで、改善後の再発を防ぐだけでなく、投球パフォーマンスの向上が期待できます。
外側が痛む野球肘を再発させないための予防法
再発防止には、日頃の投球環境や身体の状態を整えることが欠かせません。野球肘(外側)の症状を再発させないための予防法は以下の7つです。
- 正しい投球フォームの習得
- 投球数の制限と適切な休息
- ウォーミングアップとクールダウンの徹底
- 筋力トレーニングとストレッチを怠らない
- 栄養と休養をしっかり取る
- 定期的なメディカルチェックを受ける
- 投球後のアイシングを怠らない
以下では、外側が痛む野球肘を再発させない方法をくわしく解説します。
正しい投球フォームの習得
| 項目 | 内容 | 期待できる効果 |
|---|---|---|
| 肘の位置が肩と同じ高さ以上 | 投球時、肘が肩より下がらないようにする | 肘下がりを防ぎ、外側へのストレスを軽減 |
| 体幹の回旋を使う | 腕だけで投げず、体幹をひねって投げる | 肘の負担を分散し、全身の力で投げられる |
| 下半身主導のフォーム | 踏み出し足で地面を蹴り、腰を先行させて投げる | 手投げを防ぎ、肘の過負荷を防止 |
| ステップの幅を確保 | ステップが小さすぎないようにする | 軸足のパワーを十分に使えて肘に負担がかかりにくい |
| リリース時の肩・肘・手の連動 | 肩→肘→手の順に、自然な連動意識が大切 | 肘に不自然なねじれが加わらず、損傷リスクを低減 |
| 柔軟性の確保 | 肩・股関節・胸郭の柔軟性を高める | スムーズなフォームの維持と筋肉疲労の予防 |
野球肘を再発させないためには、正しい投球フォームの習得が不可欠です。重要なのは、肘を肩より下げない、肘下がりの防止です。肘下がりは肘の外側に大きなストレスがかかり、再発リスクが高まります。
ステップの幅やリリース時の肩・肘・手のスムーズな連動も大切な要素であり、肩や股関節、胸郭の柔軟性を高めることでスムーズな動作ができるようになります。体の軸を意識し、下半身の力を十分に伝えるフォームを習得すれば、肘への負担を軽減できます。
投球数の制限と適切な休息
過度な投球は肘へのストレスを与える原因になります。肘へストレスを与えないためにも投球制限と適切な休息を取ることが大切です。
とくに成長期の連投や過度な練習は、未発達な肘に大きな負担をかけます。連日の投球は避け、身体のサインを見逃さないことも再発防止につながります。
ウォーミングアップとクールダウンの徹底
| 分類 | 目的 | 内容 | 期待できる効果 |
|---|---|---|---|
| ウォーミングアップ | 筋肉・関節の準備 | 軽い運動で身体を温め、関節の可動域を広げる | 肘や肩を動かしやすくし、怪我を防ぐ |
| 血流の促進 | 全身の血行をよくする | 酸素や栄養が筋肉・腱に行き渡り、負担を軽減 | |
| 神経系の活性化 | 動作の反応や協調性を高める | 投球フォームの安定につながり、再発予防になる | |
| クールダウン | 疲労物質の除去 | 軽い運動やストレッチで血流を促す | 疲労回復を早め、筋肉痛や炎症を防ぐ |
| 筋肉の柔軟性維持 | 運動後のストレッチ | 筋肉の硬化を防ぎ、次回の投球もスムーズに行える | |
| 炎症の抑制 | アイシングなどで局所を冷却 | 肘関節の炎症を抑え、損傷の進行を防ぐ |
練習前には、全身の筋肉を温め、関節の可動域を広げるウォーミングアップを丁寧に行いましょう。また、練習後には、クールダウンとしてストレッチや軽い運動を実施し、筋肉の疲労回復を促すことで、野球肘の防止につながります。
ウォーミングアップとクールダウンは、毎回忘れずに徹底しましょう。
筋力トレーニングとストレッチを怠らない
| 分類 | 目的 | 内容 | 期待できる効果 |
|---|---|---|---|
| 筋力トレーニング | 肘や肩周りの安定性強化 | チューブを使った肩のインナーマッスル強化(ローテーターカフ)前腕の回外・回内筋の筋トレ | 投球時に関節を安定させ、肘への過剰な負荷を防ぐ |
| 体幹の強化 | プランク、ヒップリフトなどの体幹トレーニング | 下半身~上半身の力の伝達をスムーズにし、手投げフォームの防止 | |
| 下半身の強化 | スクワット、ランジ、カーフレイズ | 投球のパワー源を腕に頼らず、下半身から生み出すことで肘の負担を軽減 | |
| ストレッチ | 柔軟性の向上 | 肩関節・胸郭・前腕・手首の静的ストレッチ | 可動域を広げ、無理のないスムーズな投球動作を促す |
| 疲労回復と再発予防 | 投球後のリカバリーストレッチ(上腕三頭筋、前腕伸筋群) | 投球による慢性負荷の蓄積を防ぐ |
(文献6)
肘周りだけでなく、肩や体幹の筋力強化は、投球動作の安定性を高め、肘への負担を軽減します。筋肉や腱の柔軟性が低下すると、投球時に肘にかかる負担が増大し、野球肘を引き起こす原因になります。
筋力低下を防ぐため、医師の指示に従い、筋トレやストレッチを継続的に行いましょう。
以下の記事では、野球肘におすすめのストレッチ方法を解説しております。
栄養と休養をしっかり取る
| 項目 | 内容 | 具体例・補足 |
|---|---|---|
| バランスの取れた食事 | 組織修復と体づくりに必要な栄養を摂る | タンパク質(鶏むね肉・卵)炭水化物(ごはん・バナナ、脂質(ナッツ・アボカド)ビタミン類(緑黄色野菜・牛乳) |
| 十分な睡眠 | 成長と回復を促すホルモンの分泌を助ける | 7〜8時間睡眠、就寝前のスマホは控える、入浴・ストレッチでリラックス |
| 水分補給 | 血流・代謝を保ち、炎症を防ぐ | 運動前後に水やスポーツドリンクをこまめに飲む、のどが渇く前に補給 |
バランスの取れた食事と十分な睡眠は、骨や筋肉の成長、疲労回復に不可欠です。偏った食事や睡眠不足は、身体の回復力を低下させるだけでなく、怪我のリスクを高める原因になります。
とくに成長期は骨や筋肉が発達する重要な時期であるため、たんぱく質やカルシウムなどの栄養素をしっかり摂り、睡眠時間の確保が大切です。
定期的なメディカルチェックを受ける
| メディカルチェックを受ける目的 | 期待できるメリット | 補足 |
|---|---|---|
| 早期発見・早期治療 | 自覚症状が出る前に、異常を見つけられる | 画像検査(レントゲン・エコー)や触診で、関節の異常や初期炎症を早期発見が可能 |
| 重症化を防ぎ、早期の競技復帰が期待できる | 状態に応じた保存療法・リハビリを早期に開始できる | |
| 再発リスクの軽減 | 肘の状態だけでなく、柔軟性・筋力・フォームの問題もチェックできる | 肘に負担がかかるフォームや体の使い方の改善指導が受けられる |
| 投球動作全体を見直す機会になり、再発を予防できる | フォーム改善はパフォーマンス向上にも直結する |
(文献6)
無症状でも関節や軟骨に損傷が起きていることがあります。また、野球肘と診断された後も定期的にメディカルチェックを受けることで、症状の悪化や再発リスクを軽減できます。
また、成長期の段階は、骨や軟骨が未発達なため、野球肘(外側)を発症しやすいため、メディカルチェックで適切な投球制限やトレーニング指導を受けることが大切です。
症状改善後も、メディカルチェックで肘、柔軟性、筋力、投球フォームを定期的に確認し、再発予防に努めましょう。
投球後のアイシングを怠らない
| アイシングの目的 | 期待できる効果 | 補足 |
|---|---|---|
| 炎症の抑制と違和感の軽減 | 血管を収縮させて炎症を抑え、違和感を軽減 | 投球による微細な損傷の広がりを防ぎ、回復を早める |
| 疲労回復の促進 | 筋肉や腱の緊張を緩和し、疲労をリセット | 肘の柔軟性を保ち、翌日の投球への負担を軽減 |
| 組織修復の促進 | 損傷した組織の修復を助ける | 回復力を高め、再発予防につながる |
アイシングは、血管を収縮させて炎症を抑え、違和感を抑え、回復を助けます。筋肉や腱の緊張を緩和し、疲労回復を促します。
投球後のアイシングは、野球肘の予防・治療において欠かせないケアです。アイシングを行う際は、凍傷に注意し、長時間の冷却や強い冷却は避けましょう。
外側が痛む野球肘は放置せずに専門医にご相談ください
投球時の肘の違和感は、野球肘(外側)の可能性があります。放置すれば、症状は進行し、プレーを続けるのが困難になるだけでなく、日常生活に支障をきたす恐れがあります。症状が悪化する前に早めに医療機関を受診しましょう。
当院「リペアセルクリニック」では、野球肘の症状に対して、幹細胞を活用した再生医療を提供しています。改善しない野球肘の症状でお悩みの方は「メール相談」もしくは「オンラインカウンセリング」にて、当院へお気軽にご相談ください。
参考文献
「野球肘」『手外科シリーズ』, pp.1-2
https://www.jssh.or.jp/ippan/sikkan/pdf/18yakyu.pdf(最終アクセス:2025年4月12日)
公益財団法人 日本整形外科学会「症状・病気をしらべる「術後感染症」」公益財団法人 日本整形外科学会
https://www.joa.or.jp/public/sick/condition/postoperative_infection.html(最終アクセス:2025年4月12日)
富田一誠,渡邊幹彦「成長期投球障害予防に関する日本野球協議会の取り組み」『第30回日本臨床スポーツ医学会学術集会』, pp.1-3,2020
https://www.rinspo.jp/journal/2020/files/28-3/420-422.pdf(最終アクセス:2025年4月12日)
荒井秀典ほか.「健康づくりのための身体活動・運動ガイド 2023(案)」『健康づくりのための身体活動基準・ 指針の改訂に関する検討会』, pp.1-46, 2023年
https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/001171393.pdf(最終アクセス:2025年4月12日)
「5章 部活動中における健康面での留意事項」, pp.1-19,
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/kyoiku/guideline_06(最終アクセス:2025年4月12日)
山根将弘ほか.「スポーツにおけるけがの予防野球肘検診の取り組み」『特集 輪・和・話』, pp.1-4, 2020年
https://www.town.tobetsu.hokkaido.jp/uploaded/attachment/14974.pdf(最終アクセス:2025年4月12日)