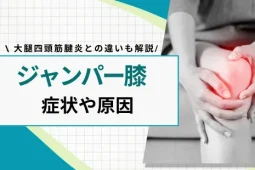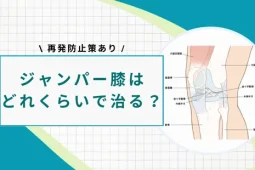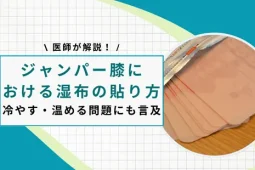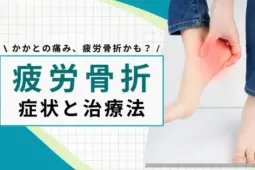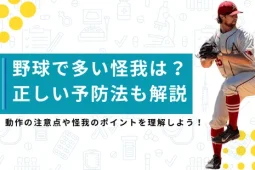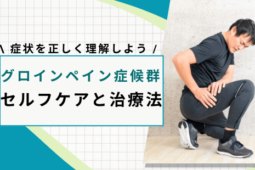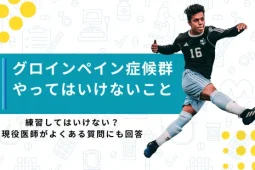- 下肢(足の障害)
- スポーツ外傷
【医師監修】ジャンパー膝とは|症状・原因・治療法までをわかりやすく解説
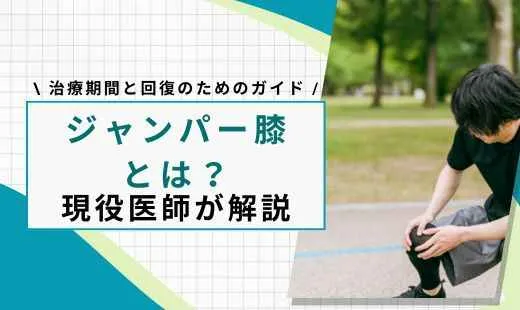
「スポーツ中に膝が痛むようになってきた」
「階段の昇り降りやしゃがむ動作で膝が痛む」
このような症状がある方の中には、「ジャンパー膝」と診断された方も少なくありません。
「ジャンパー膝とはどんなもの?」
「治るものなの?」
「またスポーツできるようになる?」
このような疑問や不安を感じる方も多いことでしょう。
本記事では、ジャンパー膝の概要や主な症状、治療法、セルフケアのポイントなどをわかりやすく解説していきます。
ジャンパー膝への正しい知識を得ることで、不安解消につながりますので、ぜひ最後までご覧ください。
当院「リペアセルクリニック」の公式LINEでは、再生医療の情報提供と簡易オンライン診断を実施しております。
ジャンパー膝について気になる症状がある方は、ぜひ一度公式LINEにご登録ください。
目次
ジャンパー膝とは
ジャンパー膝とは、膝に繰り返し負担がかかったために生じる損傷です。
バレーボールやバスケットボールといったスポーツで膝を使いすぎることが、ジャンパー膝の主な原因とされています。
ジャンパー膝に該当する主な疾患としては、膝蓋腱炎と大腿四頭筋腱付着部炎の2つがあります。
膝蓋腱炎
膝蓋腱炎とは、バレーボールやバスケットボール、ランニングなどで繰り返し膝を使ったりジャンプを続けたりした際に生じる膝の障害です。
特徴的な症状は、主に以下のとおりです。
- 膝関節が痛む
- 膝蓋骨下部を押すと痛む
- ジャンプや階段昇降時に痛む
痛みの原因は、膝蓋骨と脛骨(すねの骨)をつないでいる膝蓋腱に小規模な断裂や炎症が生じることです。
大腿四頭筋腱付着部炎
大腿四頭筋腱付着部炎は、膝蓋腱炎と同様、バレーボールやバスケットボール、ランニングなどで繰り返し膝を使ったりジャンプを続けたりしたことで生じる膝の障害です。
膝に強い負荷が繰り返しかかると、太もも前面にある4つの筋肉である「大腿四頭筋」の先端部の腱に炎症が起こります。
特徴的な症状は、主に以下のとおりです。
- 膝蓋骨の上部に痛みが生じる
- 階段昇降時に痛みが増す
- しゃがむ動作のときに強く痛む
大腿四頭筋腱付着部炎については、以下の記事でも詳しく解説しています。あわせてご覧ください。
ジャンパー膝の原因
ジャンパー膝の主な原因は、膝に繰り返し負担がかかること、いわゆるオーバーユースです。
ジャンプや着地のたびに、膝蓋腱が引っ張られ、小さな傷ができてしまいます。
傷を治そうとして増えるのが、新しい血管です。傷が治ると血管は消えますが、ジャンプや着地を何度も繰り返すと、小さな傷がどんどん増えてしまい、それに合わせて血管も増え続けます。
血管が増えると、神経繊維も一緒に増えるため、痛みを感じやすくなるのです。
オーバーユース以外の原因としては、運動時の間違ったフォームや筋力の低下などがあげられます。
サイズが合わない、クッション性が低いといった不適切なシューズも、膝蓋腱に負担をかけてしまうので、ジャンパー膝のリスクを高めます。
ジャンパー膝の重症度分類
ジャンパー膝の重症度分類としてあげられるのが、Blazina(ブラジナ)分類です。(文献1)
Blazina分類では、ステージ1から4の4段階で重症度が分類されています。
| ステージ | 状況 |
|---|---|
| ステージ1 | スポーツ活動中に痛みがある |
| ステージ2 | スポーツ開始時に痛み、ウォームアップで消えるが、疲労時に再び現れる |
| ステージ3 | 活動中および活動後にも痛みがあり、スポーツに参加できない |
| ステージ4 | 腱が完全に断裂している |
ジャンパー膝で感じる痛みと生活への影響
ジャンパー膝の初期は、運動時を中心に痛みや違和感があり、安静にしていると症状がおさまります。そのため日常生活への影響は少ないといえるでしょう。
しかし、進行すると安静時にも痛みが生じるようになり、日常生活にも支障をきたし始めます。
初期に感じやすい違和感
ジャンパー膝の初期には、ジャンプしたときや運動開始時、もしくは運動終了後に痛みや違和感を生じることが多いとされています。しかし、安静にしていると痛みが消えるため、運動を続ける方も少なくありません。
階段昇降時、とくに昇るときに膝に違和感を覚える場合もあります。
階段を昇るときは膝を大きく曲げることにより、膝蓋骨上部に負担がかかりやすいためです。
進行による日常生活の影響
ジャンパー膝が進行すると、スポーツだけにとどまらず、日常生活にも影響を及ぼします。
階段の昇り降りや椅子からの立ち上がり、しゃがみ姿勢からの立ち上がりで強く痛むことがあります。しゃがむ動作ができなくなるケースも少なくありません。
重症化すると、歩行が困難になったり安静時にも痛みが生じたりして、日常生活に支障をきたすようになります。
「ジャンパー膝は治るのか」について
ジャンパー膝は、適切な治療とリハビリにより、十分回復可能です。しかし、症状によって回復までの時間が異なります。
大事なことは、ジャンパー膝を放置せず早期に治療を受けることです。
治すためには早期対応が必要
ジャンパー膝が治る期間は症状によって異なりますが、いずれにしても、早い対応が必要です。膝に痛みが生じた時点で医療機関を受診しましょう。X線やMRI、エコーなどの検査を受けて、膝の状態を確認します。
安静や膝のアイシングで回復する場合もありますが、重症例では運動制限が加わったり、手術が必要になったりするケースも少なくありません。
ジャンパー膝の重症度を判別するためにも、早期に医療機関を受診しましょう。
下記の記事では、ジャンパー膝が治るまでの期間や、やってはいけないことについて解説しています。
あわせてご覧ください。
放置するとさまざまなリスクがある
ジャンパー膝を放置して運動を続けていると、痛みが悪化し、運動能力に影響を及ぼす可能性があります。
非常にまれですが、膝蓋腱が断裂する可能性もあります。膝蓋腱が断裂すると、立てなくなったり、あお向けや座った状態で足をまっすぐ伸ばせなくなったりするケースも少なくありません。
膝蓋骨がずれて、本来の位置から上または下に移動するケースもあります。これは、転位と呼ばれる現象です。
ジャンパー膝を放置すると、さまざまなリスクが発生すると知っておきましょう。
ジャンパー膝の治療法
ジャンパー膝の治療法としては、主に以下の4つがあげられます。
- 保存的治療
- 理学療法
- 手術療法
- 再生医療
保存的治療
保存的治療としてあげられるものは、主に以下のとおりです。
- 安静
- 膝のアイシング
- 物理療法
- 消炎鎮痛剤の活用
第一に、ジャンプやランニングなど、膝に負担をかけている動作を避けて安静にします。
安静を保つことと並行して、膝のアイシングおよび、電気治療や超音波治療といった物理療法で炎症を抑えます。
内服薬および塗り薬、湿布などの消炎鎮痛剤の役割は、痛みや炎症を抑えることです。
ステロイドの局所注射をするケースもありますが、腱を弱くする可能性があるため、慎重な対応が求められます。(文献2)
理学療法
ジャンパー膝の理学療法としてあげられるものは、主に以下のとおりです。
- ハムストリング(太もも裏側の筋肉)のストレッチ
- 大腿四頭筋のストレッチ
- 大腿四頭筋の筋力トレーニング
- スクワット
ジャンパー膝は、ハムストリングスや大腿四頭筋の柔軟性とも関係しているため、ストレッチが効果的とされています。
ジャンパー膝が長期化しているときのリハビリテーションでは、スクワットや階段昇降など「遠心性収縮訓練」も有効です。
遠心性収縮とは「筋肉が伸ばされながら力を発揮する動き」を意味します。
ジャンパー膝のストレッチについては、下記の記事でも詳しく解説しています。あわせてご覧ください。
手術療法
膝蓋腱が断裂した場合などの重症例では、手術療法が検討されます。
主な手術としては、関節鏡を用いた膝蓋腱切除や膝蓋腱修復などがあります。
膝蓋腱切除とは炎症により変性した部分を切り取る手術であり、膝蓋腱修復とは、断裂部分を修復する手術です。
再生医療
手術に抵抗がある場合の選択肢としてあげられるのが、再生医療です。再生医療とは、ヒトの体内にある幹細胞の修復力を活用した治療方法です。
腹部の脂肪から幹細胞を採取し、既定の量になるまで培養してから体内に戻します。これは、「自己脂肪由来幹細胞治療」と呼ばれる治療法です。
「PRP療法」と呼ばれる治療法もあります。PRPとは、血小板を多量に含む血漿のことです。血小板には成長物質が多く含まれており、組織修復や炎症抑制の働きがあります。
ジャンパー膝も、「自己脂肪由来幹細胞治療」および「PRP療法」の適応となる疾患です。
再生医療について詳しく知りたい方は、リペアセルクリニックへお気軽にお問い合わせください。
メール相談やオンラインカウンセリングにて、詳しくお話を伺います。
以下の記事では、スポーツ外傷に対する再生医療について詳しく解説しています。

スポーツ外傷は⼿術しなくても治療できる時代です。
ジャンパー膝のセルフケア
ジャンパー膝のセルフケアとしては、主に以下のようなものがあげられます。
- 膝関節の安静
- 膝関節のアイシング
- サポーターやテーピングによる膝の保護
- 湿布の活用
無理のない範囲でのストレッチも、柔軟性向上や膝蓋腱への負担軽減に役立ちます。運動前のウォーミングアップ、運動後のクールダウンとして取り入れてみましょう。
運動時のフォームやシューズの見直しも、セルフケアの一環として重要です。
以下の記事では、ジャンパー膝における湿布の貼り方について解説しています。あわせてご覧ください。
ジャンパー膝を理解して早期対応を心がけよう
ジャンパー膝は主に、膝蓋腱炎と大腿四頭筋腱付着部炎に分けられます。
当初は、運動後の違和感だけですが、進行するうちに運動中にも痛みを感じ、重症になると日常生活にも支障をきたします。そのため、ジャンパー膝は早期の対応が重要です。
重症度判別や早期回復のためにも、膝に痛みや違和感を覚えた時点で、医療機関を受診しましょう。
ジャンパー膝の治療法としては、保存療法や理学療法、手術療法などがあります。膝の痛みについては、再生医療も選択肢として考えられます。
ジャンパー膝による痛みでお悩みの方は、リペアセルクリニックまでお気軽にお問い合わせください。
メール相談やオンラインカウンセリングも行っております。
\無料オンライン診断実施中!/
ジャンパー膝に関するよくある質問
ジャンパー膝の際にやってはいけないことは何ですか?
ジャンパー膝の際にやってはいけないことは、主に以下のとおりです。
- 痛みを我慢し無理してスポーツを続ける
- 安静の指示を守らない
- 医師の指示なくストレッチやマッサージを行う
- 治療を中断する
これらの行動は、回復の遅れや重症化につながります。
スポーツだけにとどまらず、日常生活にも大きな支障をきたすリスクがあるため、行わないようにしましょう。
ジャンパー膝とオスグッド病の違いは何ですか?
オスグッド病は、脛骨粗面(けいこつそめん)と呼ばれる、膝蓋骨の下の骨に炎症や痛みが生じる疾患です。
両者の違いは、痛みが生じる部分です。
ジャンパー膝は、膝蓋腱や大腿四頭筋腱など「腱」に痛みを生じますが、オスグッド病は脛骨粗面と呼ばれる「骨」に痛みを生じます。
オスグッド病は、脛骨粗面が筋肉や腱で強く引っ張られてしまうことで、骨が出っ張ってしまう特徴があります。
ジャンパー膝とオスグッド病の違いは下記の記事でも詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
ジャンパー膝で身長伸びるって本当ですか?
ジャンパー膝で身長が伸びることはありません。
ジャンパー膝は、急激に身長が伸びる時期に多く見られます。
身長が急激に伸びる時期は、骨格も成長しており、大腿四頭筋の柔軟性向上が追いつかない状況です。その結果、相対的に筋肉の緊張が高まります。
筋緊張が高まった状態でジャンプを繰り返すと、膝蓋腱に負担がかかり、ジャンパー膝を発症すると考えられます。
ジャンパー膝と身長の関係については、下記の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
関連記事:ジャンパー膝は身長伸びる?成長期との関係性と原因について医師が解説
参考文献