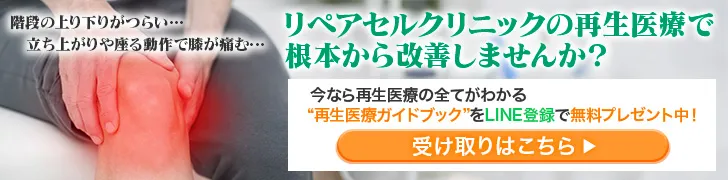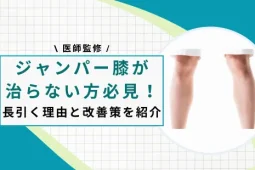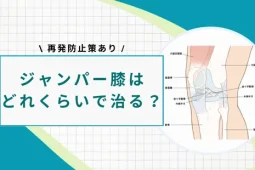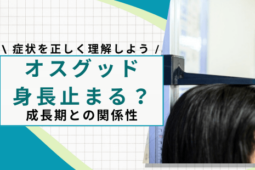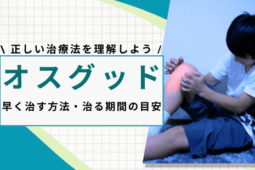- 下肢(足の障害)
- ひざ関節
- オスグッドシュラッター病
- スポーツ外傷
ジャンパー膝とオスグッド病の違いは?原因や症状、治療法を比較解説

「ジャンパー膝とオスグッド病の違いは何?」
「スポーツを続けるために必要な方法は?」
ジャンパー膝とオスグッド病は症状がよく似ていて、見分けがつかないケースも多いのではないでしょうか。
どちらもジャンプ競技で繰り返し膝を使うことで発症しますが、痛みが出る膝の部位が異なります。
この記事では、ジャンパー膝とオスグッド病の原因と症状の違いや、それぞれの治療法について解説していきます。
ジャンパー膝とオスグッド病の一般的な見分け方や対処法についても紹介するので、ぜひ最後までお読みください。
目次
ジャンパー膝とオスグッド病の違い【比較表】
ジャンパー膝とオスグッド病は、どちらもジャンプスポーツが原因で膝まわりの痛みが出るため似たような疾患に見えがちです。
しかし、発症する原因や影響を受ける膝の部位が異なります。それぞれの定義や原因、症状を比較表で整理しました。
| 項目 | ジャンパー膝 | オスグッド病 |
|---|---|---|
| 定義 | 膝蓋腱の炎症 | 脛骨粗面の剥離(はくり) |
| 原因 | ジャンプ動作や走行が多いスポーツ | ジャンプ動作や走行が多いスポーツ |
| 症状 | スポーツ時の膝蓋腱の痛み・腫れ | 脛骨粗面の突出、スポーツ時の脛骨粗面の痛み・腫れ |
| 影響を受ける部位 | 膝蓋腱(膝蓋骨の下の靭帯) | 脛骨粗面(膝蓋骨の下にある突出している骨) |
はじめに、それぞれの原因の違いについて説明していきます。
【関連記事】
ジャンパー膝(膝蓋腱炎)とは?症状チェックと効果的なストレッチ・テーピング技術
オスグッド・シュラッター病|成長期の少年の膝に発症するスポーツ障害
ジャンパー膝とオスグッド病の原因の違い
ジャンパー膝とオスグッド病は、いずれも膝への負荷が強いスポーツで起きやすい点が共通しています。
しかし、主に痛む場所は成長期特有の影響があるかどうかなど、発症の仕組みには違いがあります。それぞれ詳しく見ていきましょう。
ジャンパー膝の原因
ジャンパー膝(膝蓋腱炎)は膝蓋骨(膝のお皿の部分)のすぐ下にある膝蓋腱にストレスがかかり、炎症が起こる疾患です。
バレーボールやバスケットボール、サッカーなどのスポーツで多くみられ、繰り返し行うジャンプ動作が主な原因です。
ジャンプスポーツによる膝の使いすぎ(オーバーユース)が続くと、膝蓋腱に過度なストレスがかかり、組織に小さな損傷や炎症が起こって慢性的な痛みを発症させます。
オスグッド病の原因
オスグッド病(オスグッド・シュラッター病)は小学校高学年から中学生の成長期に、脛骨粗面(膝蓋骨の下にあるわずかに突出している骨の部分)の軟骨が剥がれる疾患です。
原因はジャンパー膝と同じで、ジャンプや走行、ボールを蹴る動作などで膝を頻回に使うことで生じます。
この時期は軟骨から骨に成長する時期なので、膝を伸ばす動作の繰り返しで脛骨粗面の軟骨が剥がれることにより痛みが増します。
ジャンパー膝とオスグッド病の症状の違い
ジャンパー膝とオスグッド病に見られる主な症状は、どちらもスポーツ中の膝まわりの痛みです。それぞれ詳しく見ていきましょう。
ジャンパー膝の症状
ジャンパー膝に見られる典型的な症状は、ジャンプや走る動作、階段の昇り降りのときに見られる膝蓋腱の痛みです。
膝蓋腱の痛みは程度により軽症と中等症、重症に分類されます。
| 重症度 | 痛みの程度 |
|---|---|
| 軽症 | スポーツの後や歩いた後に痛む |
| 中等症 | 活動開始期と終わった後に痛む |
| 重症 | 活動中や後の痛みで続行困難 |
重症化して膝蓋腱に断裂がある場合は、手術が必要になる可能性もあります。
軽症や中等症のうちは専門家と相談した上でスポーツの継続が可能ですが、症状を悪化させないためにも、毎日ケアを続けることが大切です。
オスグッド病の症状
オスグッド病に見られる症状は、脛骨粗面の痛みや腫れ、突出です。
痛みはスポーツ中に見られ、休んでいるときに軽快する点がジャンパー膝とよく似ています。
症状は脛骨粗面以外の部位には見られません。症状が悪化すると、剥がれた骨片を取り出す手術が必要になる可能性もあります。
ジャンパー膝とオスグッド病の発症部位の違い
ジャンパー膝とオスグッド病の発症部位はそれぞれ膝蓋腱と脛骨粗面です。どちらの疾患も、膝の曲げ伸ばしによる大腿四頭筋の作用が影響して発症します。
以下に詳しく解説していきます。
ジャンパー膝の発症部位
ジャンパー膝で影響を受ける膝の部位は、大腿四頭筋(太もも前面の筋肉)につながる膝蓋腱です。膝蓋腱は大腿四頭筋の伸び縮みに伴って脛骨(すねの骨)や膝蓋骨の動きをコントロールし、膝の曲げ伸ばしを可能としています。
スポーツをしている時のジャンプやダッシュ、ストップ、ターンなどの動作は、急激な膝の曲げ伸ばしを繰り返し行っているため、膝蓋腱の負担も大きいのです。
この状態が続くと膝蓋腱に過度なストレスがかかり、組織に小さな損傷や炎症が起こって慢性的な痛みを発症させます。
オスグッド病の発症部位
オスグッド病で影響を受ける膝の部位は、大腿四頭筋の下端が付着する脛骨粗面です。膝の曲げ伸ばしを繰り返すと、大腿四頭筋の伸び縮みによって脛骨粗面に刺激が加わります。
小学生から中学生にかけて骨が成長している時期は、この刺激により脛骨粗面の軟骨が急激に剥がれやすくなるのです。
軟骨が剥がれると、脛骨粗面まわりに炎症が起き、痛みや腫れを発症させます。
ジャンパー膝とオスグッド病の診断方法と治療方法の違い
ジャンパー膝やオスグッド病が疑われる場合は、整形外科で問診や触診、画像診断などの診断と鎮痛薬や外用薬の投与による治療を行います。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
ジャンパー膝の診断方法と治療方法
ジャンパー膝の診断では問診や触診、MRI、超音波検査などを行います。膝蓋腱をゆびで圧迫した時に痛みが強まることや、MRIや超音波による画像診断で筋肉や腱の変性が確認できることで確定診断となります。
ジャンパー膝の治療は、患部の安静や練習量を減らすこと、炎症を抑えるための鎮痛剤や外用薬を使用することです。膝蓋腱に負担のかかるジャンプやダッシュの練習を減らすだけでも、症状の改善に効果があります。
また、医薬品は市販ではなく医師に処方されたものを使用しましょう。症状によってはステロイド注射を行うこともあります。
オスグッド病の診断方法と治療方法
オスグッド病の診断は問診や触診、レントゲン検査で可能です。問診で実際の話を聞きながら、痛みが出るときの状況や、痛みが出る部位を確認します。
脛骨粗面の状態を触診やレントゲン検査で確認し、痛みや腫れ、突出、軟骨の剥離が認められると確定診断になります。
オスグッド病の症状を治すためには、スポーツを控えて安静にすることが大切です。軟骨から骨に成長する3〜6カ月間は痛みが出やすい時期なので、負担をかけないようにできるだけ休息をとりましょう。
痛みが強いようなら、医師から処方された飲み薬やぬり薬などを使用することもあります。
なお、膝の痛みの治療には「再生医療」の選択肢が挙げられます。再生医療は、損傷を起こしている骨や細胞に幹細胞を投与する治療法です。
再生医療について詳しく知りたいという方は、メール相談、オンラインカウンセリングも承っておりますので、ぜひご活用ください。
ジャンパー膝とオスグッド病の予防策の違い
ジャンパー膝やオスグッド病の予防策には、アイシングや大腿四頭筋のストレッチ、膝蓋腱バンドの装着などがあります。
痛みの症状に悩んでいる方は、専門医と相談しながらこれらの方法を行うようにしましょう。詳しく解説していきます。
ジャンパー膝の予防策
ジャンパー膝の予防には、大腿四頭筋のストレッチや筋力トレーニングが大切です。症状を管理しながらスポーツを続けていく場合は、スポーツ直後のアイシングや、スポーツ中の膝蓋腱バンドの装着も必要になります。
過去の論文ではジャンパー膝の予防策に、傾斜台上での片脚立ちスクワットが効果的であると報告されています。(文献1)
ジャンパー膝の予防に重要な、片脚立ちスクワットや大腿四頭筋のストレッチの方法について見ていきましょう。
|
【片脚立ちスクワット】 ①25度程度の傾斜台を準備し、降りの方向に顔を向けて立つ ②片脚立ちになり、股関節と膝関節を曲げながらお尻を床に近づける。膝の位置が足の位置より前方に出ないように注意する ③股関節と膝関節を伸ばして片脚立ちの姿勢に戻る。10回連続で行い、1日3セットほど行う。きつく感じるようであれば、必要に応じて手すりを持ちながら行う |
|
【大腿四頭筋のストレッチ(膝を曲げると痛む場合の方法)】 ①ストレッチをする側の膝を床につき、ストレッチをしない側の膝を立てて片膝立ちの姿勢になる ②上半身を起こしながら身体を前方に移動させ、太もも前面の筋肉を伸ばす ③20秒〜30秒ほど時間をかけて動きを行い、10秒ほど休んだ後にもう一度行う |
|
【大腿四頭筋のストレッチ(膝を曲げても痛みがでない場合の方法)】 ①床に両膝を伸ばして座った後、ストレッチをする側の膝を曲げて踵をお尻に近づける ②両手を床について身体を支えながら、上半身を後ろに倒して太もも前面の筋肉を伸ばす ③20秒〜30秒ほど時間をかけて動きを行い、10秒ほど休んだ後にもう一度行う |
オスグッド病の予防策
オスグッド病の予防策と管理方法は、アイシングや大腿四頭筋のストレッチ、ベルトの装着です。
オスグッド病は痛みが出なければスポーツが可能ですが、症状を悪化させないためにこれらを継続して行うことが大切です。
|
【アイシング】 練習直後にアイシングを15〜30分ほど行いましょう。激しい運動の後は脛骨粗面のまわりにより炎症が起こりやすく、熱感や腫れが強まります。 できるだけ早く患部を冷やし、炎症を抑えることで症状の悪化を防げるわけです。氷を入れた袋を患部に持続的に当てるか、弾性包帯で巻きつけて固定すると効果的です。 |
|
【バンドを装着する】 ジャンパー膝やオスグッド病の治療として、膝蓋腱の走行に横断して取り付けるバンド(サポーター)の装着が効果的です。 バンドによる膝蓋腱の圧迫は、腱の走行を変化させて負担を減らせることが明らかになっています。 スポーツ中の膝蓋腱や脛骨粗面に対する過剰なストレスが減り、痛みの緩和が期待できます。 |
まとめ|ジャンパー膝とオスグッド病の違いを把握して判断に役立てよう
ジャンパー膝とオスグッド病は、どちらもジャンプ競技で膝を伸ばす動作を繰り返すことで起こる症状です。
似ている疾患ですが、以下のように発症部位や診断方法、治療方法などに違いがあります。
| 疾患 | 発症部位 | 診断方法 | 治療方法 |
|---|---|---|---|
| ジャンパー膝 | 膝蓋腱(膝蓋骨の下の靭帯) |
|
|
| オスグッド病 | 脛骨粗面(膝蓋骨の下にある突出している骨) |
|
|
どちらの症状でも違和感を感じたら、早めに医療機関を受診しましょう。スポーツを継続するためには、早期発見・早期治療が大切です。
また、身体的な負担が少ない治療法として、再生医療も選択肢の1つです。
再生医療では、入院を必要としません。患者様自身から採取した脂肪や血液に加工を施し、患部に注射・点滴を行います。
再生医療について詳しくは、当院リペアセルクリニックにお気軽にお問い合わせください。
ジャンパー膝とオスグッド病の違いに関するよくある質問
ジャンパー膝とオスグッド病はどれくらいで治りますか?
ジャンパー膝の回復期間は、痛みの度合いや腱へのダメージ具合で異なります。
軽症なら1〜2カ月ほどで落ち着く例がある一方、炎症が強まると2〜3カ月を要するケースも珍しくありません。
オスグッド病は骨の成長段階が関連し、半年で改善する例から2年ほどかかる例まで幅広い経過を示します。成長期特有の個人差も影響し、同じような症状でも回復期間にばらつきが見られる点が特徴です。
いずれの場合も痛みが続くときは無理をせず、医師の指示に従いリハビリを続けてください。
ジャンパー膝とオスグッド病でやってはいけないことを教えてください
ジャンパー膝でやってはいけないことは、以下の通りです。
- 痛みを我慢しての練習や試合の継続
- 膝への負担が大きいジャンプ動作の繰り返し
- 適切な休息を取らずに連日のトレーニング
また、オスグッド病では以下の行為はやってはいけません。
- 成長期の過度な筋トレや運動の継続
- 素人判断での自己流マッサージや処置
どちらの症状も初期段階では適切な休息と負荷軽減で回復可能ですが、無視して運動を続けると骨の変形や痛みの慢性化を招くリスクがあります。
違和感や痛みを感じたら、すぐに運動強度を調整し、症状が続く場合は早めに専門医を受診しましょう。
参考文献
(文献1)
Visnes, H., Hoksrud, A., Cook, J., & Bahr, R. British Journal of Sports Medicine 39巻 11号 pp847~850 2005年
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16244196/(最終アクセス:2025年4月19日)