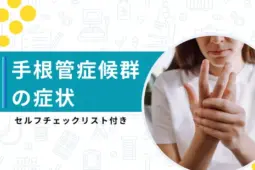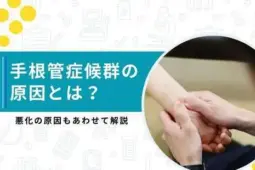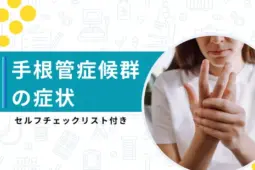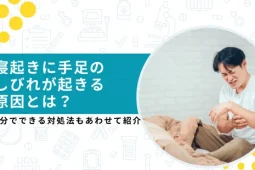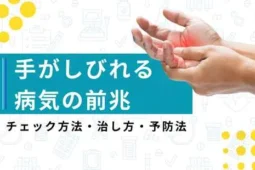- 手根管症候群
- 手部
手根管症候群のリハビリ方法3選|日常生活でやってはいけない事も現役医師が解説

「手根管症候群と診断され、リハビリをしているが効果はあるの?」
「自宅でもできるリハビリ方法を知りたい」
手根管症候群に対してリハビリを受けていても、効果があるのか不安に思う方もいるでしょう。軽度〜中程度の手根管症候群では、継続的にリハビリを行うと症状の緩和が期待できます。
本記事では、自宅でも取り組めるリハビリ方法や手術後に行うリハビリの流れについて解説します。日常生活で避けるべき習慣についても紹介するので、ぜひ参考にしてください。
当院リペアセルクリニックでは、公式LINEにてオンライン診断を実施しております。再生医療に関する情報提供もしておりますので、手根管症候群でお悩みの方はぜひご登録ください。
目次
手根管症候群におけるリハビリ方法3選
手根管症候群は、手首にある「手根管(しゅこんかん)」と呼ばれるトンネル状の構造内を通っている正中神経という神経が圧迫されて発症する神経障害です。症状には、親指・人差し指・中指などのしびれや痛み、筋力低下などが現れます。
手根管症候群によって生じるしびれや痛みなどの改善には、薬物療法や装具療法に加え、ご自身で行うリハビリテーションが欠かせません。リハビリは圧迫された正中神経への負担を物理的に軽減し、手根管内部の組織の柔軟性を取り戻して、本来の手の機能を取り戻すのが目的です。
自宅で実践できる3つのリハビリ方法を具体的に紹介するので、参考にしてください。
手根管症候群の症状については、こちらの記事に詳しくまとめていますので、ぜひご覧ください。
手首のストレッチ
手根管症候群の症状軽減には、手首の柔軟性を高めるストレッチが重要です。ストレッチ方法は、以下のとおりです。
- 腕を肩の高さに上げる
- 親指を内側に入れて握り、小指側に手首を曲げる
- 手首と指を曲げてカタカナの「コ」の字にし、反対側の手で手前に引く
- 手首を反らせて壁に固定し、反対側の手で上から押す
2〜4の動作は10秒ほど保持し、反対側も同様に行います。急に強く引っ張ると逆効果になるため、呼吸を止めずにゆっくりと行うのがポイントです。
ストレッチは1日数回ほど無理のない範囲で行い、痛みを感じた際はすぐに中止しましょう。
腱のグライディングエクササイズ
腱のグライディングエクササイズは手指の動きをスムーズにするのが目的で、複数の指の形を切り替えながら腱の動きを変える方法です。具体的な方法は、以下を参考にしてください。
- 手首と指をまっすぐに伸ばす
- 指を反らせる
- 親指は伸ばしたまま、他の指を曲げて拳をつくる
- 親指以外の第1・2関節は伸ばし、第3関節を曲げる
- 親指以外の第3関節を伸ばし、第1・2関節を曲げる
腱のグライディングエクササイズは指を段階的に動かし、それぞれ10秒ほど保持するのを3セットほど行います。
動作の途中で違和感がある場合は無理に続けず、痛みが出ない範囲で行うのが重要です。繰り返し行うと腱の動きが滑らかになり、手のしびれや痛みの軽減につながるケースも多くみられます。
手の筋力トレーニング
手根管症候群の症状が長期化すると、親指の付け根にある母指球筋という筋肉が痩せてしまい、物をつまんだり、瓶の蓋を開けたりする力が弱くなります。手の筋力トレーニングは、弱ってしまった筋肉を鍛え、日常生活に不可欠な手の機能を取り戻すのが目的です。
手の筋力トレーニングとして、以下が挙げられます。
- 洗濯ばさみを指でつまむ
- 柔らかいゴム製のボールやスポンジを握る
手根管症候群では、手指の筋力低下が進行すると握力や日常動作に支障が出るため、早期からの筋力維持が欠かせません。無理に力を加えるのではなく、軽い負荷で回数を多くする方が神経への負担が少なくトレーニングできます。
症状が安定してきた段階から取り入れ、少しずつ手の機能を取り戻していきましょう。
手根管症候群の術後に行われるリハビリ
軽度〜中程度の手根管症候群では、装具療法や薬物療法・リハビリなどの保存療法が行われますが、改善しない場合は手術が行われるケースもあります。
神経の圧迫を取り除く手根管症候群の手術後は、症状の改善が期待されますが、すぐに手の機能が完全に回復するわけではありません。術後には適切なリハビリを行い、可動域の確保や筋力の回復、神経の滑走性改善などを目指すのが重要です。
術後の回復には段階があり、術後すぐに始めるべきリハビリと、ある程度回復したあとに取り組むべきリハビリのように時期によって内容は異なります。ここでは「術後早期」と「術後回復期」に分けて、それぞれのリハビリ内容について詳しく解説します。
術後早期
術後早期のリハビリでは、手術による腫れやむくみを最小限に抑え、手首の傷に過度な負担をかけずに指関節が硬くなるのを防ぐのが目的です。具体的なリハビリ内容は、以下のとおりです。
- 関節可動域訓練(前腕と手指中心)
- マッサージ
関節可動域訓練とは、関節の動きを維持したり改善したりするのを目的とした訓練を指します。手術を行ってまもない段階では、前腕と手指を中心に関節可動域訓練を行います。
指を「グー」「パー」に動かしたり、手のひらを内側と外側にひねったりする運動を行いますが、痛みや腫れが出ない程度にしてください。マッサージも前腕と手指中心に行うと、血液循環の向上や維持に効果的です。
術後早期の段階では、まだ手首自体を意図的に曲げ伸ばしする運動は行いません。あくまで指を優しく動かして血行を促し、本格的な回復に向けた土台を作るのが重要になります。
術後回復期
術後数週間が経過した回復期は傷口の安定や炎症の軽減が進み、より積極的なリハビリが可能です。具体的には、以下のリハビリを行います。
- マッサージ
- 関節可動域訓練(手指と手首中心)
マッサージは、ギプス固定期間に低下した皮膚の柔軟性や手首の動きを良くする目的で、前腕や手指・傷口の周囲を中心に行います。
術後回復期の関節可動域訓練は、手のひらを手前に倒したり反らしたりして、手首を屈曲・伸展させましょう。ほかにも、手首の動きやつまみ動作の訓練をするために、手指と手首の運動を重心的に行うケースが多いです。
また、日常生活での動作を少しずつ再開し、手にかかる負荷を確認しながら使い方を調整するのも重要です。症状の程度や回復速度には個人差があるため、医師や作業療法士と連携しながら適切なペースでリハビリを継続するのが回復への近道となります。
手根管症候群になったらやってはいけない事
手根管症候群の症状を改善へ導くには、リハビリと並行して日常生活の見直しが欠かせません。とくに、神経への圧迫を助長するような動作や生活習慣を続けると、せっかくの治療効果が十分に得られない場合もあります。
手根管症候群を発症した際は、避けるべき行動を把握しておくと、症状の悪化や再発を防ぐのに役立ちます。以下に挙げる3つの行動は、見過ごされがちですが、神経への負担を大きくしやすいため注意が必要です。
ただし、症状が続く方は無理せず早めに整形外科を受診しましょう。当院では、LINEでの相談も可能ですので、お気軽にご相談ください。
\無料オンライン診断実施中!/
手根管症候群になったらやってはいけない事や対処法に関しては、以下の記事に詳しくまとめていますので、ご覧ください。
長時間パソコンやスマートフォンを操作する
長時間にわたるパソコンのキーボード入力やスマートフォンの操作は、手首を曲げた不自然な位置で指を動かし続けるため、手根管症候群の症状を進行させる代表的な原因です。とくに、手首を手のひら側に深く曲げた状態は、手根管の内圧を高めてしまい、神経の圧迫を強めます。
対策としては、以下の方法が挙げられます。
- 1時間に1度は作業を中断し、手首を優しく伸ばすストレッチをする
- パソコンの操作時はリストレストを置いて手首の角度を水平に保つ
- 自然な形で握れるマウスを選ぶ
- スマートフォンは両手で持ち、手首を曲げすぎないようにする
連続した作業時間を意識的に減らし、道具で手首の負担を軽減すると、症状緩和につながるでしょう。
家事で手を酷使する
洗濯や掃除・料理などの家事全般は、手首に強い負担をかける動作が多いため注意が必要です。とくに、以下の動作は手根管周囲の組織を強く緊張させ、神経の圧迫を助長しやすくなります。
- タオルや雑巾を絞る
- フライパンを振る
- 重い買い物袋を持つ
すべての家事を休むのは難しいですが、意識的に休憩を挟んだり、片手で重いものを持たずに両手で支えたりする工夫が大切です。ほかにも、以下の対処法も検討すると良いでしょう。
- 便利な調理器具を活用する
- 1度に行う作業量を減らす
- 手首の負担を軽減するサポーターやスプリントを使用する
日々の動作の中に潜む負担を見つけて軽減していく姿勢が、症状の改善につながります。手根管症候群の症状がある場合は、作業時間や方法を工夫するのが重要です。
痛みを我慢して使う・放置する
手根管症候群の初期段階では、軽いしびれや違和感を放置してしまう方が少なくありません。しかし、痛みやしびれを我慢して手を使い続けると、正中神経に持続的なダメージが加わり、症状が進行してしまう恐れがあります。
進行すると、感覚麻痺や筋力低下に至り、手術が必要になるケースもあります。症状を感じた際の対処方法は以下のとおりです。
- 痛みやしびれを感じたらすぐに作業を中止する
- 適切なリハビリや生活習慣の見直しを行う
また、違和感を感じた時点で、早めに医師へ相談するのが重要です。リハビリの一環としてストレッチを指導されるケースもありますが、無理に行うと悪化する可能性があるため、注意しましょう。
手根管症候群と診断されたらリハビリを取り入れて症状の改善を目指そう
手根管症候群は、手のしびれや痛みを引き起こす疾患ですが、適切なリハビリを取り入れると症状の緩和や再発防止が期待できます。
手首のストレッチや腱のグライディングエクササイズ、筋力トレーニングなどは、自宅でも継続しやすい運動です。術後には段階的なリハビリが必要であり、無理のない範囲で進めるのが大切です。
治療だけでなく、日常生活においても手の酷使や誤った使い方は避けた方が良いでしょう。正しいケアと早期対応が重要ですが、自己判断せず症状が改善しない場合はぜひご相談ください。
\無料相談受付中/
また、手根管症候群に関して詳しく知りたい方はこちらの記事もチェックしてください。
手根管症候群のリハビリに関するよくある質問
手根管症候群におけるリハビリを行う上で、よくある質問をまとめました。ここでは、リハビリ期間や手術後の開始時期などの質問について、解説します。
回復のペースには個人差があるため、あくまで一般的な目安として参考にしてください。
手根管症候群のリハビリ期間はどれくらいですか
手根管症候群のリハビリ期間は、軽症であれば数週間〜1カ月程度で症状が落ち着く場合がありますが、中等度以上では3カ月以上必要になるケースもみられます。
保存療法でも改善がみられないと、手術による治療を検討する症例も珍しくありません。
手根管症候群の手術後は、神経や筋肉の回復が緩やかに進むため、さらにリハビリ期間が長期にわたる場合もあります。
リハビリ期間は、症状の程度や発症からの経過、生活習慣によって個人差があります。自己判断でリハビリを途中でやめてしまうと再発や悪化のリスクが高まるため、医師やリハビリ担当者と相談しながら根気よく続けるのが大切です。
手根管症候群の術後はいつからリハビリを開始しますか?
手根管症候群の術後にリハビリを始める場合、開始時期は実施した手術方法によって、以下のように異なります。
|
手術方法 |
リハビリ開始時期 |
|---|---|
|
手根管開放術 |
術後1週間〜 |
|
母指対立再建術 |
術後1カ月〜 |
手根管開放術は手のひらを切開し、圧迫されている正中神経を解放するために行われる手術方法です。傷口の範囲が小さく、局所麻酔下で手術するため、術後は帰宅できます。
通常2〜4cmほどの範囲を切開しますが、内視鏡を使用するとさらに傷口は小さくなります。術後はギプスで固定しますが、傷口も小さいため1週間ほど固定し、回復していればリハビリが可能です。
母指対立再建術は手首や指の腱や筋肉を採取し、親指の付け根に移植する手術方法です。手術は全身麻酔下で行われるため1〜2週間ほどの入院が必要となり、術後は1カ月ほどの固定期間を経て、リハビリを開始します。
傷の回復に応じて、手首の動きや握力回復を目的としたリハビリも段階的に取り入れていきます。無理に進めると炎症や痛みを悪化させる可能性があるため、主治医の指示に従いリハビリを進められると、回復が期待できるでしょう。
術後の経過について詳しく知りたい方は、下記の記事もご覧ください。