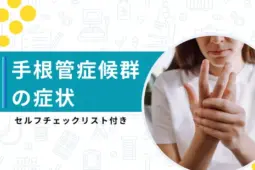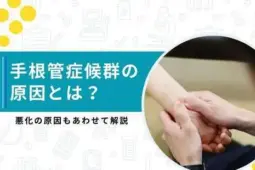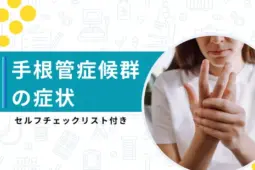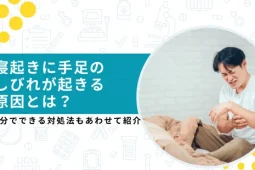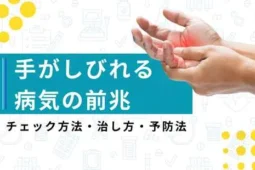- 手根管症候群
- 手部
手根管症候群とは|症状・原因・治療法からセルフチェックのやり方まで現役医師が解説

指のしびれや痛みが見られ、手根管症候群を疑う方もいるでしょう。手根管症候群は神経障害の1つで、親指や人差し指、中指にしびれや痛みが生じる場合があります。症状が進行すると物が上手くつまめないなど日常生活に支障をきたすため、早めの治療が必要です。
本記事では、手根管症候群とはどのような疾患か、症状や原因などを解説します。治療法やセルフチェック方法も紹介するので、指のしびれや痛みの回復が見込めずお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。
また、当院「リペアセルクリニック」の公式LINEでは、再生医療の情報提供と簡易オンライン診断を実施しております。
手根管症候群について気になる症状がある方は、ぜひ一度公式LINEにご登録ください。
目次
手根管症候群とは
手根管症候群(しゅこんかんしょうこうぐん)とは、指や手のひらにしびれや痛みが生じる疾患です。手指や手首の動きに関わる正中神経が、手根管と呼ばれる手首周辺に位置する狭い管の中で圧迫されることで症状を引き起こします。手根管症候群の好発年齢は50代以上で、女性に多い疾患です。
なお、類似症状として腱鞘炎がありますが、両者には次のような違いが見られます。
|
疾患名 |
特徴 |
|---|---|
|
手根管症候群 |
手根管が圧迫されることで起こる神経障害 |
|
腱鞘炎 |
腱鞘が炎症を起こして腱がスムーズに通過できなくなることで起こる炎症 |
手根管症候群と腱鞘炎には症状にも違いが見られるため、各疾患の特徴を理解しておきましょう。
【関連記事】
手足のしびれの原因となる病気の症状や予防法を解説!前兆も紹介
【医師監修】腱鞘炎とは|症状・原因・治療法から重症度のチェック方法まで解説
手根管症候群の症状
手根管症候群を発症すると、次のような症状が見られます。
- 親指や人差し指、中指にしびれや痛みが生じる
- 夜間や明け方に症状が強くなる
- 冷たい刺激に手の感覚が過敏になる
- 指がつまみづらいなど細かい作業がしにくくなる
- 手がむくんでいるような感じがする
とくに代表的な症状は、人差し指や中指を中心としたしびれや痛みです。なかには、手のひら全体に痛みを伴うケースもあります。
また、症状が進行するとボタンが上手くかけられなくなったり財布から硬貨を掴みにくくなったりと、日常生活へ影響を及ぼします。症状が見られた場合は、悪化しないためにも早めに受診しましょう。
手根管症候群の原因
手根管症候群は、正中神経と呼ばれる神経の圧迫が原因です。しかし、原因不明で発症するケースも多く見られます。
手根管症候群の発症要因として以下が考えられます。(文献1)
- 女性ホルモンの乱れによる滑膜の増加
- 家事や仕事による手の酷使
- 基礎疾患の影響
女性の場合、妊娠や出産、閉経によって症状が見られるケースも少なくありません。育児や家事などで手を酷使している場合や、パソコン・スマートフォンの使い過ぎは手根管症候群を引き起こす可能性が考えられます。
また、関節リウマチや人工透析、甲状腺機能低下症も手根管症候群との関連性があるといわれています。
【関連記事】
【医師監修】手根管症候群の原因とは?悪化を招く習慣を含めて解説
症状でみる手根管症候群のセルフチェック方法
手根管症候群は、セルフチェックも可能です。ここでは、手根管症候群のセルフチェック方法を4つ紹介します。
- 手根管圧迫テスト
- ティネル徴候
- ファーレン徴候
- つまようじテスト
症状の疑いがある方は参考の上、実践してみてください。
手根管圧迫テスト
手根管圧迫テストは、手根管部分を軽く圧迫する検査方法です。手根管は手首の中央部に位置し、骨と靭帯に囲まれたトンネル状の空間をいいます。
検査方法の順番は、以下の通りです。
- 手のひら側を上に向けた状態でテーブルに置く
- 検査者は手根管を指で軽く圧迫する
- 30秒ほど圧迫する
30秒ほど圧迫している間に、親指から薬指にかけてしびれや鈍痛などの症状が見られた場合は、手根管症候群の可能性が高いと考えられます。
ティネル徴候
ティネル徴候とは、指や診察用のハンマーを使用して手根管を刺激する検査方法です。検査は、次の手順で行います。
- リラックスした状態で手のひら側を上に向けたままテーブルに置く
- 片方の手を使って手首の真ん中あたりを軽く叩く
軽く叩いた際、親指から薬指の指先にかけてしびれを感じたら手根管症候群の可能性が考えられます。ティネル徴候は、手根管症候群だけでなく、肘部管症候群や腓骨神経麻痺などの疑いもあるため、検査で電気が走るようなしびれを感じた際は、専門機関を受診しましょう。
ファーレン徴候
ファーレン徴候とは、手首を曲げて行う検査方法です。検査は、次の手順で行います。
- 立位もしくは座位で行う
- 胸の前で手の甲同士を合わせる
- 手の甲を押しつけながら両手首を曲げ、1分ほどキープする
1分ほど両手首を曲げている間に親指から薬指にかけて、しびれや痛みが出る、もしくは症状が悪化する場合は手根管症候群の可能性が考えられます。ファーレン徴候を実施する際は、手首を直角に曲げるのがポイントです。
つまようじテスト
つまようじテストは、親指から薬指を刺すときにしびれや鈍痛があるか診断する方法です。検査は、次の手順で行います。
- 親指から薬指の先をつまようじで軽く刺す
- 小指の先をつまようじで軽く刺す
- 小指の先を刺すの感覚を比較する
親指から薬指の先と、小指の先を刺したときの感覚に違いがあれば、手根管症候群の可能性があります。
手根管症候群におけるやってはいけないこと
手根管症候群の可能性があるときにやってしまうと、症状を悪化させてしまう動作があります。悪化を招くリスクがあるため、手根管症候群の疑いがある場合は以下の動作を避けましょう。
- ねじったりパソコンのキーボードを打ったりと手に負担のかかる動作を行う
- ストレッチやマッサージで手首を無理に伸ばす
- 自己判断で市販の鎮痛剤や抗炎症薬を使用する
- 症状を放置する
知識がない状態でストレッチやマッサージを行うと、かえって手首や指に負担がかかり、症状を悪化させる可能性があるため注意が必要です。また、自然に治ると思って放置するのは避けてください。
手根管症候群が進行すると、日常生活に支障をきたすため、症状が続く場合は早めに診てもらいましょう。
手根管症候群の治療法
手根管症候群の治療法は、進行状況によって異なります。ここでは、主な治療法を3つ解説します。
- 薬物療法
- サポーターなどの装具治療
- 手術療法
手根管症候群の治療法が知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
薬物療法
手根管症候群の治療法には、内服薬もしくは手首へステロイド剤の注射が行われます。内服薬には、ビタミンB12を使用するケースが一般的です。
ビタミンB12には、末梢神経の保護・再生効果が期待できるため、手根管症候群の治療に効果的です。また、ステロイド注射では炎症を抑え、痛みやしびれの緩和が期待できます。ステロイド注射の持続期間は人によって異なるため、定期的な注射が必要になる場合もあります。
サポーターなどの装具治療
一般的に、手根管症候群は手の使い過ぎが原因と考えられるため、安静にすることが大切です。作業量の調整も治療法の1つですが、仕事や家事で手を使わなければいけない場合は、サポーターなどの装具治療が行われます。
サポーターなどの装具を利用すると手首の負担を軽減できるため、症状の緩和が期待できます。手首を固定すると正中神経への圧迫軽減の効果が期待できるので、夜間や明け方のしびれや痛みを緩和したい場合に効果的です。
手術療法
手根管症候群は、薬物療法やサポーターなどの装具治療で安静にするのが主な治療法です。しかし、症状の回復が見られない場合は、手術を行います。
手根管症候群の術式は、手根管開放術と母指対立再建術の2つが一般的です。各術式には、以下の違いが見られます。
|
術式 |
概要 |
|---|---|
|
手根管開放術 |
手のひらを切開し神経圧迫のもとになっている靭帯を切って、圧迫を解放する手術 |
|
母指対立再建術 |
手首や指にある腱や筋肉を採取して、親指の付け根に移植する手術 |
症状の進行状況によって手術は異なり、回復期間にも違いがあります。
手根管症候群の手術後におけるリハビリ内容
手根管症候群の手術後は、早期と回復期でリハビリ内容が異なります。治療後すぐは、関節可動域訓練を実施します。関節可動域訓練では前腕と手首を動かし、筋肉の伸張性低下を防ぐのが目的です。
回復期には、手の動きや指のつまみ動作を重点的に行います。洗濯や料理、食事などで必要となる動作となるため、早い段階で日常生活に戻れるようリハビリを実施します。症状の早期回復には、術後のタイミングにあわせて適切なリハビリの実施が重要です。
手根管症候群を自分で治すことはできる?放置するリスク
手根管症候群は自分で治すことは難しいですが、適切なセルフケアにより症状緩和が期待できます。有効なセルフケア方法は、以下の通りです。
- 手関節屈曲筋や手関節伸展筋を伸ばすストレッチをおこなう
- 手のひらの筋肉や手根管を通る腱の動きを滑らかにするエクササイズをする
- 横手根靭帯のマッサージをする
ストレッチ以外にも、安静に過ごしたりサポーターを使用したりするのもおすすめです。症状が軽減しないまま放置すると、感覚が鈍くなるなどのリスクが生じます。
また、ストレッチのやり方を間違えると症状を悪化させる可能性もあるため、手根管症候群の疑いがある場合は医療機関で適切な治療を行いましょう。
再生医療は手根管症候群の症状回復が見込めない場合の選択肢
手根管症候群の痛みやしびれを放置すると、日常生活に支障を及ぼします。損傷した指の神経治療には、再生医療も選択肢の1つです。
再生医療とは、患者自身の脂肪組織から幹細胞を分離・培養し、静脈内投与により組織修復や機能回復を目指す治療法です。幹細胞を採取する際は、おへその横からごくわずかな脂肪を取るため、身体の負担を最小限に抑えられます。
また、入院が不要な点も再生医療の特徴です。当院では、メール相談やオンラインカウンセリングも受け付けておりますので、手根管症候群の症状回復が見込めずお悩みの場合は、お気軽にお問い合わせください。
\無料オンライン診断実施中!/
手根管症候群の症状回復には早期治療が重要
手根管症候群は症状が進行すると、物が上手く掴みにくくなるなど日常生活にも支障をきたす疾患です。症状が悪化し手術を行う場合、入院が必要になる場合もあります。
手根管症候群の症状回復には早期治療が重要なため、セルフチェックを実施し、疑いが見られた場合は専門機関への受診を検討しましょう。
万が一症状の回復が見込めない場合は、改善策として再生医療を検討するのもおすすめです。手根管症候群の症状や原因を理解し、早期対策を図りましょう。

手術をしない新しい治療「再生医療」を提供しております。
手根管症候群に関するよくある質問
手根管症候群の手術後はすぐ日常生活に戻れますか?
手根管症候群の代表的な手術は、手根管開放術と母指対立再建術の2種類で、手術によって日常生活に戻れるタイミングが異なります。
手根管開放術はギブスが外れ、傷口の治癒や痛みの軽減が確認できれば日常生活に復帰可能です。母指対立再建術は手術後1カ月ほど手術部位を固定するため、日常動作ができるようになるまでには1カ月ほどかかります。
手根管症候群の手術を受ける場合の入院期間はどのくらいですか?
手根管症候群の手術は、症状によって入院期間が異なります。症状が軽い場合は、1泊もしくは日帰りが可能です。物を掴むのが難しいほど症状が悪化している場合は、1〜2週間ほど入院が必要な手術を行う場合があります。
手根管症候群は何科を受診すればいいですか?
手根管症候群は手のしびれや痛みを伴う疾患のため、整形外科を受診しましょう。近くに神経外科がない場合は、脳神経外科や形成外科で受診しても問題ありません。
ただし、整形外科は専門性がわかれているため、手外科専門医がいる整形外科で診てもらうのが適しています。
参考文献