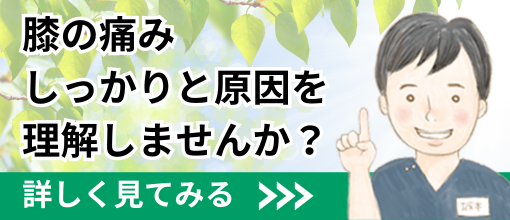-
- 大腿骨骨頭壊死
- 肩関節、その他疾患
- ひざ関節
- 股関節
- 膝部、その他疾患
「大腿骨頭壊死にはどんなステージ分類がある?」 股関節周辺に痛みを抱えている方の中には、上記のような疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。 結論、大腿骨頭壊死のステージ分類は、以下の通りです。 ステージ 目安となる状態 ステージ1 レントゲンで異常がなく、MRI検査などで壊死がわかる状態 ステージ2 レントゲンで異常があるものの、骨頭が潰れていない状態 ステージ3 骨頭が潰れているものの、関節軟骨があり関節の隙間が残っている状態 ステージ4 軟骨がすり減り、変形性股関節症となっている状態 大腿骨頭壊死のステージ分類の特徴は、大腿骨頭の壊死部分が進行し、軟骨がすり減っていくことです。 ステージ4になると関節同士の隙間がなくなってしまい、激しい痛みを伴います。 本記事では、壊死してしまった骨の根本治療にも期待できる再生医療の選択肢も紹介しているため、ぜひ参考にしてください。 \骨壊死の改善が期待できる再生医療とは/ 再生医療は、壊死・損傷した骨に対してアプローチできる治療法で、手術せずに大腿骨頭壊死の改善が期待できます。 以下の動画では、骨壊死に対する再生医療の治療について詳細を解説しています。 https://www.youtube.com/watch?v=ic_6QaEU5NU 【こんな方は再生医療をご検討ください】 進行している大腿骨頭壊死でも手術せずに治したい 大腿骨頭壊死による痛みを早く治したい 現在受けている治療やリハビリで期待した効果が得られていない 再生医療は、早く治療を受けるほど治療成績が良いですが、進行している大腿骨頭壊死も治療できるケースがあります。 具体的な治療法については、当院(リペアセルクリニック)で無料カウンセリングを行っておりますので、ぜひご相談ください。 ▼まずは骨壊死の治療について無料相談! >>(こちらをクリックして)今すぐ電話してみる 大腿骨頭壊死とは「骨頭壊死症」の一種 大腿骨頭壊死とは「骨頭壊死症」の一種です。 骨頭壊死症とは、骨に栄養を届けている血管が障害されて血液が供給されなくなり、骨の一部分が壊死する病気です。 ただし、原因は血液供給がなくなるだけでなく、以下のような原因も発症に関係していると考えられています。 怪我などの外傷による血管の障害 アルコール摂取 ステロイド使用者 また、骨壊死は全身のあらゆる骨に起こり得ます。 代表的な部位は、股関節の大腿骨頭に起きる「大腿骨頭壊死」、肩関節の上腕骨に起こる「上腕骨頭壊死」、「膝関節骨壊死」などがあります。 股関節と肩関節は、大腿骨頭・上腕骨頭と呼ばれる部位があるため、「骨頭壊死」と病名が付くのが特徴です。 一方で、膝関節は骨頭と呼ばれる部位がないため「骨壊死」が病名となります。 大腿骨頭壊死のステージ分類と原因 大腿骨頭壊死は、1〜4のステージに分類されます。ステージによって、進行度合いが異なり、ステージが上がる度に症状も顕著になっていくのが特徴です。 ここからは、大腿骨頭壊死のステージ分類と原因を詳しく解説していきます。 大腿骨頭壊死から進行・変形性股関節症へのステージの分類 大腿骨頭壊死のステージ分類は、以下の通りです。 ステージ 目安となる状態 ステージ1 レントゲンで異常がなく、MRI検査などで壊死がわかる状態 ステージ2 レントゲンで異常があるものの、骨頭が潰れていない状態 ステージ3 骨頭が潰れているものの、関節軟骨があり関節の隙間が残っている状態 ステージ4 軟骨がすり減り、変形性股関節症となっている状態 大腿骨頭壊死のステージ分類の特徴は、大腿骨頭の壊死部分が進行し、軟骨がすり減ると「変形性股関節症」を発症する可能性がある点です。 ステージ3までは関節軟骨があり、関節同士に隙間があるものの、さらに進行すると、関節同士の隙間がなくなってしまいます。 大腿骨頭壊死や症状が変形性股関節症まで進行した場合、従来の治療では根治が難しいため、ぜひ再生医療による治療をご検討ください。 \こんな方は再生医療をご検討ください/ 進行した大腿骨頭壊死の根治を目指したい 大腿骨頭壊死や変形性股関節症を早く治したい 現在受けている治療やリハビリで期待した効果が得られていない 具体的な治療法については、当院(リペアセルクリニック)で無料カウンセリングを行っておりますので、ぜひご相談ください。 ▼まずは骨壊死の治療について無料相談! >>今すぐ電話してみる 大腿骨頭壊死の重症度分類 原因不明である「特発性骨頭壊死」は、壊死の範囲によって重症度分類がありType A〜Cに分けられます。 重症になるほど、壊死範囲が大きくなり、大腿骨頭が潰れるリスクは高くなるのが特徴です。大腿骨頭壊死の重症度分類は以下のとおりです。 Type A:壊死範囲が体重のかかる領域の1/3未満 Type B:壊死範囲が体重のかかる領域の1/3〜2/3 Type C:壊死範囲が体重のかかる領域の2/3以上 Type C-1:壊死の範囲が骨盤の縁の「内側」にあるもの Type C-2:壊死の範囲が骨盤の縁の「外側」にあるもの Type Aが軽症でCになるとより重症となります。さらにTypeCは、より重症なC-1とC-2に分けられるのが特徴です。 大腿骨頭壊死の原因 大腿骨頭壊死の原因は、主に以下があげられます。 股関節を構成している大腿骨頭に流れている血管の障害 骨折や脱臼などの外傷 放射線治療 潜函病 股関節を形成している大腿骨頭に血液が供給されなくなると、大腿骨頭壊死を発症するケースが多い傾向にあります。 しかし、なかには、原因不明で突発的に大腿骨頭壊死を発症する可能性もあります。 上腕骨頭壊死のステージ分類と原因 上腕骨頭壊死とは、上腕部分にある「上腕骨頭」と呼ばれる部位が壊死してしまう病気です。大腿骨頭壊死のように、他の病気に進行するケースはありません。 ここからは、上腕骨頭壊死のステージ分類と原因を詳しく見ていきましょう。 上腕骨頭壊死の進行・ステージ分類 上腕骨頭壊死のステージ分類は、以下のとおりです。 ステージ1:レントゲンで異常がなく、CTやMRI検査で壊死がわかる状態 ステージ2:骨透亮像や骨硬化像、限局性の骨溶解像がみられる状態 ステージ3:軟骨下骨に骨折線を認める状態 ステージ4:上腕骨頭に加えて、肩甲骨の関節窩にも骨の変化を生じている状態 ステージが上がり末期になると、薬物療法や保存療法では治せない可能性が高まります。 末期ステージになると、骨切り術や人工関節を挿入する手術療法が行われるケースもあります。 ただし、治療方法はステージ分類だけでなく、症状や年齢などさまざまな要因によって決まるため、一概に治療方法は断言できません。 上腕骨頭壊死の原因 上腕骨頭壊死の原因は、主に以下があげられます。 肩関節を構成している上腕骨頭に流れている血管の障害 骨折や脱臼などの外傷 ステロイドの使用 アルコール 鎌状赤血球症・関節リウマチ・全身性エリテマトーデスなどの全身性疾患 骨折や脱臼などの原因は外傷性と呼ばれています。一方でステロイド使用や全身性疾患などは、非外傷性に分類されるのが特徴です。 膝関節骨壊死のステージ分類と原因 膝関節骨壊死は、名前の通り膝関節の骨が壊死してしまう病気です。 膝関節と呼ばれているものの、太ももの内側に壊死が起こる症例が多いため「大腿骨内顆骨壊死」と呼ばれるケースもあります。 また膝関節骨壊死は、60歳以上の女性に多く見られるのが特徴です。 ここからは、膝関節骨壊死のステージ分類と原因を紹介します。 膝関節骨壊死の進行|ステージ分類 膝関節骨壊死のステージ分類は、以下のとおりです。 ステージ1:レントゲンで異常がみられない状態 ステージ2:レントゲンで骨内に壊死領域がみられる状態 ステージ3:レントゲンで軟骨の下に骨折線があり、関節面が凹んでいる状態 ステージ4:関節の隙間が狭くなってしまっている状態 ステージが進むと、膝関節骨同士の隙間が狭くなるのが特徴です。膝関節同士が狭くなる病気として、膝関節骨壊死の他に、変形性膝関節症があげられます。 両病気とも、初期ステージの症状だけで判別するのは難しい傾向にあります。 レントゲン検査で、膝関節骨壊死か変形性膝関節症かを判別できるため、膝に痛みを抱いている方は、速やかに医療機関を受診するのがおすすめです。 膝関節骨壊死の原因 膝関節骨壊死の原因は、主に以下があげられます。 肩関節を構成している上腕骨頭に流れている血管の障害 軽微な骨折 肥満ステロイド薬の使用 大腿骨頭壊死や上腕骨頭壊死と同様に、明確な原因は判明していませんが、上記のような要因によって膝関節骨壊死が起こると考えられています。 肥満体型によって、膝関節に負担がかかるのも、膝関節骨壊死を発症させるリスクがあります。 肥満は、変形性膝関節症のリスクも高めるため、食事管理や運動習慣を身に着け、減量を目指しましょう。 大腿骨頭壊死のステージ分類の診断方法 大腿骨頭壊死のステージ分類の診断は、主にレントゲン検査やMRI検査で行われます。 基本的レントゲン検査だけで大腿骨頭壊死の患部は確認できますが、早期の骨壊死を確認するには、MRI検査が必要になります。 レントゲン検査やMRI検査では、骨が潰れていたり、壊死が進行していたりするかを確認可能です。変形性股関節症や変形性膝関節症の判断もできます。 また、血液凝固疾患をはじめとした基礎疾患を確認するために、血液検査を行うケースもあります。 大腿骨頭壊死の予防方法 大腿骨頭壊死の予防方法は、以下があげられます。 ステロイド薬の使用に注意する 過度な飲酒や喫煙は控える 股関節への負担を軽減する ステロイド薬を長期的に使用していると、大腿骨頭壊死のリスクが高まると考えられています。 ステロイド薬を使用する際は、自己判断で使用したり、量を調整したりするのは控えましょう。 他にも飲酒や喫煙も大腿骨頭壊死の発症にかかわっているとされているため、できるだけ避けてください。 また、肥満体型の方は、股関節への負担を軽減するため、体重減量を目指しましょう。 長時間の立ち仕事や、重い荷物を持つ仕事も、股関節の負担となるため、注意が必要です。 大腿骨頭壊死(骨壊死)治療法・保存療法 大腿骨頭壊死の治療は、保存療法や手術療法があげられます。 治療方法は、進行ステージやライフスタイル、年齢などを考慮して決められます。 ここからは、大腿骨頭壊死の治療法を4つ見ていきましょう。 保存療法 保存療法とは、リハビリテーションや薬物療法が代表的です。リハビリテーションでは、股関節にかかる負荷を抑えるため、体重管理が行われるケースもあります。 股関節の可動域を維持し、筋力を強化するために、ストレッチや筋力トレーニングも行われます。リハビリテーションの期間は一般的に、医療保険で対応できる150日が目安です。 なお、保存療法は、あくまでも症状を和らげる手段であり、骨壊死を治癒させるのは不可能である点に留意しておきましょう。 骨切り術 骨切り術は、大腿骨頭の壊死した部分へかかる負荷を抑えるため、骨の一部を切って角度を変える手術を指します。 病気の進行を遅らせ、股関節の機能を温存するのが目的であり、比較的若い方や病気の進行が初期から中期の方に適用されます。 ただし、骨切り術は難しい手術方法であり、医師の高いスキルや医療機関の充実した設備が必要です。 術後は、最長6カ月間松葉杖を使用したり、長期間リハビリテーションをしたりしなくてはならない点に留意しておきましょう。 人工関節 人工関節置換術は、壊死した大腿骨頭を人工関節に置き換える手術です。骨壊死により関節の多くが潰れてしまっているケースに適用されます。 人工関節置換術は、痛みを大幅に軽減し、股関節の機能の改善を期待できます。 リハビリテーションは必要ですが、入院期間は10日ほどと短いのが特徴です。ただし耐用年数の問題で、若い方に行うのは避けるべきとされている点に留意が必要です。 人工関節は脱臼リスクもあるため、メリットだけでなくリスクも理解して検討しましょう。 再生医療 大腿骨頭壊死を手術せずに根治を目指したい方は、再生医療も選択肢の一つです。 再生医療は、患者さま自身の細胞を採取・培養し、患部に投与することで損傷した組織の再生・修復を促す医療技術です。 患者さま自身の幹細胞や血液を用いるため、拒絶反応やアレルギー反応などの副作用リスクが少ないのが特徴です。 \こんな方は再生医療をご検討ください/ 大腿骨頭壊死でも手術せずに治したい 副作用リスクの少ない治療で根治を目指したい 現在受けている治療で期待した効果が得られていない 再生医療は、早く治療を受けるほど治療成績が良いですが、進行している大腿骨頭壊死も治療できるケースがあります。 当院(リペアセルクリニック)では、患者さま一人ひとりの症状やお悩みに合わせてご案内しておりますので、ぜひ無料カウンセリングにてご相談ください。 ▼まずは骨壊死の治療について無料相談! >>今すぐ電話してみる 大腿骨頭壊死でお悩みの方は、再生医療を視野に入れてみてはいかがでしょうか。 まとめ|大腿骨頭壊死のステージ分類とは?治療方法やよくある質問も紹介 大腿骨頭壊死では、1〜4のステージに分類され、それぞれ以下のような状態が目安となります。 ステージ 目安となる状態 ステージ1 レントゲンで異常がなく、MRI検査などで壊死がわかる状態 ステージ2 レントゲンで異常があるものの、骨頭が潰れていない状態 ステージ3 骨頭が潰れているものの、関節軟骨があり関節の隙間が残っている状態 ステージ4 軟骨がすり減り、変形性股関節症となっている状態 ステージが上がると関節軟骨がすり減ってしまう「変形性股関節症」や「変形性膝関節症」につながるため、早期治療が重要です。 悪化を防ぐためにも、痛みや違和感を抱いている方は、早めに医療機関を受診しましょう。 近年の治療では、従来の保存療法や手術療法に加え、患者様の細胞を用いて手術をせずに根治を目指す再生医療も選択肢の一つです。 \こんな方は再生医療をご検討ください/ 進行している大腿骨頭壊死でも手術せずに治したい 大腿骨頭壊死による痛みを早く治したい 現在受けている治療やリハビリで期待した効果が得られていない 再生医療は、早く治療を受けるほど治療成績が良いですが、進行している大腿骨頭壊死も治療できるケースがあります。 具体的な治療法については、患者様一人ひとりの症状やお悩みに合わせてご案内しておりますので、当院(リペアセルクリニック)の無料カウンセリングにて、ぜひご相談ください。 ▼まずは骨壊死の治療について無料相談! >>今すぐ電話してみる 大腿骨頭壊死に関するよくある質問 骨壊死にならないか心配ですが、気を付けることはありますか。 現代医学でも骨壊死の正確な原因はわかっていません。危険因子としてわかっているのは外傷、ステロイドの使用、アルコール多飲です。 ステロイドは、関節リウマチや全身性エリテマトーデスなど全身性疾患の治療に必要なため、飲まないことはおすすめしませんが、外傷やアルコールはご自分で気を付けられます。無理な運動は行わず、規則正しい生活習慣を送るのが予防に必要と言えるでしょう。 レントゲンで問題ないと言われましたが、大丈夫でしょうか。 骨壊死は初期の段階ではレントゲンで異常がわからないケースがほとんどです。壊死した領域がレントゲンでわかるまでは時間がかかりますが、MRI検査では早期に病気を見つけられます。 痛みが強く心配な場合は、MRI検査や精密検査について担当の医師と相談するのがおすすめです。 大腿骨頭壊死と診断されたらスポーツはできませんか? 大腿骨頭壊死を発症後、スポーツができるかは、進行度合いによって異なります。 壊死の範囲が小さく、悪化リスクが低ければ、問題なくスポーツができるケースもあります。 しかし、壊死の範囲が広いと、股関節にかかる負担が大きくなるため、スポーツが制限される可能性がある点に注意が必要です。 体への負荷が少ないスポーツは許可されやすいですが、ジャンプをしたり、走ったりするスポーツは制限されやすい傾向にあります。 大腿骨頭壊死は医療費補助の対象になりますか? 明らかな原因がない「特発性大腿骨頭壊死」は、医療費補助の対象となります。特発性大腿骨頭壊死は、指定難病に分類されているためです。 特発性大腿骨頭壊死と診断された場合は、医療機関に医療費補助の手続き方法を相談しましょう。
2023.10.02 -
- 関節リウマチ
- ひざ関節
- 膝部、その他疾患
関節リウマチは全身の関節に炎症が起こり、痛みや腫れを起こす病気です。 進行すると関節の変形や機能の障害を残してしまいます。 関節リウマチでは膝の痛み、膝の腫れも多い症状です。 膝が痛いとき、変形性膝関節症と考え「年のせいでは?」と悩んでいる方もいるでしょう。 もし関節リウマチだった場合に放置していると、悪化してしまう可能性もあります。 この記事では関節リウマチによる膝関節炎の症状や治療法について解説していきます。 膝の痛みでお困りの方はぜひ参考にしてみてください。 膝の関節炎とリウマチの違い 関節炎とリウマチの違いは、大きく分けると以下の通りです。 関節炎 さまざまな原因で関節に起こる炎症の総称 リウマチ 関節炎を起こしている症状の1つ たとえば関節リウマチでは、自分の体を細菌やウイルスから守る免疫の異常によって関節の滑膜に炎症が起こります。 関節リウマチが起こると痛みや腫れを感じるでしょう。 関節リウマチは無治療のままで放置してしまうと、関節が変形など機能的な障害をきたすので注意しましょう。 以下の記事では関節炎の1つ「化膿性関節炎」について解説しています。 治療法や再発予防もまとめたので、具体的な症状なども把握しておきたい方は、ぜひご覧ください。 リウマチが発症する主な原因や症状 関節炎とリウマチの違いが理解できても「気づかないうちに痛みを感じるようになった」方もいるでしょう。 ここからは、リウマチになる主な原因と症状を順番に解説していきます。 関節リウマチの主な原因 関節リウマチの多くは40〜60歳代頃の中高年女性に発症します。 正確な原因はまだ明らかになっていませんが、自己免疫疾患とも言えるでしょう。 自分の組織に対して攻撃する抗体が作られてしまい、関節内の滑膜にリンパ系の細胞が集まって炎症性の物質が作られるのが原因とも考えられています。 【リウマチの発症が疑われるサイン】 起床時に関節部分がこわばっているように感じる 関節が腫れている 関節が熱っぽい 力が入りにくい 日常生活の作業が上手くいかない 家族にリウマチの患者がいる など 上記の症状が感じられる方はリウマチになっている可能性があるので、しっかり検査しておきましょう。 発症には遺伝的な要因や喫煙、歯周病などが関連しているとわかっています。 発症すると関節炎によって痛みや腫れを起こし、進行すると関節の変形を生じてしまうため、早期の発見と治療が大切です。 リウマチによる膝関節炎の症状 関節リウマチで多い症状は手や足の指の腫れ、痛み、朝のこわばりなどです。 膝関節で滑膜が増殖して炎症を起こすと膝関節炎をきたしてしまいます。 膝関節炎の主な症状は以下の通りです。 膝が腫れる 膝に水が溜まる 歩くときや階段での痛みを感じる 膝が曲がらない など 膝の痛みは膝裏に起こるケースが多く、曲げ伸ばしのときに音が生じた経験もあるでしょう。 炎症が強い場合には安静にしていても歩けないくらいの激痛が生じる場合もあるので注意してください。 なお、リウマチはあくまで関節炎の1つなので、以下の表で似ている症状をまとめました。 病名 主な症状 膠原病(こうげんびょう) 関節に痛みを感じたり血管症などの症状がある 線維筋痛症 手足の関節だけでなく筋肉に激痛を感じるケースがある 比較的女性が発症しやすい 関節炎とリウマチの違いについてだけでなく、細かい症状の違いや治療法などが気になる方は、以下の記事で詳しく解説していきます。 膝関節炎を放置するリスク 膝の関節炎を放置しておくと、関節の軟骨がなくなってしまうだけでなく、徐々に関節の変形が進んでいきます。 日常生活を送る上で「多少の痛みだから」と放置しすぎてしまうと、膝の曲げ伸ばしが難しくなるので注意してください。 骨同士のぶつかりだけで痛みを感じる可能性もあるので、症状が悪化してしまいます。 関節の変形を生じさせないためにも、早期の発見と治療が大切です。 リウマチによる膝関節炎の診断方法 リウマチの診断は問診、身体診察と血液検査、画像検査などを組み合わせて総合的に行います。関節が腫れて、痛む病気は複数あり、検査だけで関節リウマチと診断できない場合があるからです。 関節リウマチの診断基準を使用して診断を行うので、専門家である医師の診断が必須となります。 現在では2010年に米国、欧州リウマチ学会が合同で発表した分類基準を使用するケースが大半です。(文献1) 以下の4項目についてそれぞれ点数をつけ、合計して6点以上であれば関節リウマチと診断します。 診断基準 症状がある関節の数 症状が続いている期間 血液検査での炎症反応の数値 血液検査でのリウマトイド因子や抗CCP抗体の数値 血液検査では、リウマトイド因子や抗CCP抗体が重要で、多くの関節リウマチで陽性になります。 しかし、両方とも陰性でも関節リウマチと診断されたり、陽性でも関節リウマチではなかったりもします。 炎症反応は活動性を反映する指標ですが、リウマチ以外でも上昇する可能性もあるので診断結果は要チェックです。 画像検査は診断基準には含まれませんが、単純レントゲン写真では「骨びらん」と呼ばれる骨の異常な透過性がみられる場合があります。 関節エコーやMRI検査も滑膜炎の範囲、程度を評価するのに有用です。 リウマチによる膝関節の治療法 リウマチによる膝関節の治療法は、日常生活で応急処置をする方法はもちろん、専門医からお薬を処方してもらう方法などがあります。 ここからは、自宅でできる応急処置から薬物治療などの治療法を解説していきます。 体や関節を保温する 膝の関節炎だけでなく、体の関節が動かしにくいと感じた場合、患部を保温すると効果が期待できます。 冬場はもちろん、夏場の冷房があたるのも避け、長袖や長ズボンを着用しておくのがおすすめです。 患部を保温しておくと関節部分の血液がよく流れ、こわばりなどの症状を軽減する効果が期待できるのです。 関節が腫れている場合は炎症が起きている可能性があるので、保温以外の治療法を選択する必要があります。 以下の記事では、関節リウマチの初期症状や治療を詳しくまとめているので、あわせてご覧ください。 食事や姿勢などの私生活を見直す 関節リウマチの患者様は、食生活だけでなく姿勢改善などを普段から実施してもらうのがおすすめです。 症状を悪化させないためにも、以下のポイントには要注意です。 砂糖や加工食品を摂取しすぎない 激しい運動を控える 首に負担をかけない 同じ姿勢を長時間とる 重いものを持つ 正座をする 喫煙をする ストレスを溜める など 詳しい改善項目は、以下の記事でまとめているので、ぜひ参考にしてください。 専門医から抗リウマチ薬を処方してもらう リウマチの治療法は基本的に薬物治療です。 リウマチと診断した早期から、抗リウマチ薬を開始し、痛みの程度に応じて炎症を抑えるステロイドや、鎮痛薬を併用します。 薬物治療を開始しても膝関節炎の症状が続く場合にはサポーターを使用したり、膝関節に注射をしたりする方法があります。 日本リウマチ学会による2020年のガイドラインから代表的なお薬を以下の一覧でまとめました。(文献2) 抗リウマチ薬 メトトレキサート(第一段階) 生物学的製剤やJAK阻害薬(第二段階) 関節リウマチはこれまで治療が難しく、関節の変形が進行してしまう患者様も多かったのですが、現在では薬剤の種類も多くなっています。 効果が高いお薬もあるため、適切に治療すれば症状を抑えられます。 しかし、膝の関節炎が治まらず、関節の変形や破壊が進行した場合、人工関節置換術などの手術治療が行われるので不安に感じている方もいるでしょう。 膝の痛みは現在、⼿術をしなくても治療できる時代になっているので、気になる方は気軽にお問い合わせください。 まとめ・関節炎とリウマチの違いを把握して適切な治療を行おう! 関節リウマチによる膝関節炎は、日常生活に大きな影響を与える深刻な疾患です。 膝の痛みや腫れを放置すると、関節の変形や機能障害が進行し、歩行困難や日常生活の質の低下を招く恐れがあります。 しかし、早期発見と適切な治療を行えば、症状の進行を抑え生活の質を維持できます。 関節リウマチの診断には、問診や身体診察、血液検査、画像検査が用いられるので、専門医による診断が必須です。 リウマトイド因子や抗CCP抗体の検査結果が重要な診断指標となり、診断基準に基づいて総合的に判断されます。 自己判断で治療を中断したり放置したりせず、定期的な診察と検査を受けるよう心がけましょう。 日常生活では関節に負担をかけないように注意し、適度な運動やストレッチを取り入れるのも大切です。 関節リウマチの早期発見と適切な治療を通じて、健康的で快適な生活を維持しましょう。
2023.09.10 -
- ひざ関節
- お皿付近に違和感
- 膝部、その他疾患
「膝を捻挫して歩けるけど痛い」という方の中には、病院に行くべきか悩んでいる方もいるのではないでしょうか。 結論、膝の捻挫後に歩けるけど痛い場合は、靭帯断裂など重症な可能性があります。 軽症な場合は適切な応急処置とセルフケアで早期に回復するケースもありますが、治療を受けずに放置してしまうと重症化するリスクがあります。 捻挫を放置することで、後遺症がでる場合や靭帯が完全に断裂して手術が必要になる可能性も少なくありません。 当院リペアセルクリニックでは、捻挫による痛みだけでなく「少し違和感がある」など些細なことでも無料でご相談を承っています。 「捻挫の痛みを早く治したい」「後遺症や手術は避けたい」という方は、ご自身の症状に適した治療法についてご相談ください。 ▼捻挫の早期回復に再生医療が注目 (こちらをクリックして)無料で相談しよう \お問い合わせはこちらから/ 0120-706-313 (受付時間:9:00〜18:00) 膝を捻挫して歩けるけど痛いときに考えられる原因 膝を捻挫して歩けるけど痛いときに考えられる原因として、捻挫ではなく靭帯断裂などの重症な可能性があります。 捻挫とは、膝の曲げ伸ばしを行うための「関節包」や「靭帯」が損傷してしまう外傷のことです。 しかし、捻挫と診断されるのは軽症の場合に限り、損傷度合いが強く、靭帯が完全に切れている場合「靭帯断裂」という診断になります。 捻挫だと思って痛みを我慢して放置していたら靭帯断裂だったというケースも少なくありません。 受傷後に歩行できる場合でも、適切な治療を受けなければ関節が不安定になったり、再発しやすくなる(クセがつく)可能性があります。 近年の治療では、捻挫や靭帯断裂の早期回復が目指せる治療法として、再生医療による治療が注目されています。 「膝の痛みを早く治したい」「再発のクセがつく前に治したい」という方は、ぜひお問い合わせください。 \無料相談・お問い合わせはこちら/ 0120-706-313 (受付時間:9:00〜18:00) 膝を捻挫して歩けるけど痛いときの症状 膝を捻挫すると主に以下のような症状が現れます。 受傷直後の強い痛み 内出血とむくみの発生 膝全体の腫れ 受傷直後は痛みが強いですが、機能は比較的保たれている事が多く、その後も痛みを我慢して普通に生活できる方もいます。 ですが、徐々に内出血とむくみが出てきて、膝全体が腫れてきます。 膝全体が腫れると、膝を動かす際に痛みが生じます。また、左右を比較すると動かせる範囲が狭くなる「可動域制限」がでてきます。 ひどい場合は痛みで足が地面につかないケースも。 ただし、「捻挫」であれば一時的な症状なので、数日で改善するケースが多いです。 いつまでたっても痛みが引かない、腫れがひどくなってきたという場合は「靭帯損傷」のレベルまで症状が悪化している可能性があります。注意しましょう。 以下の記事では、靭帯損傷の原因や治療法について解説しています。ぜひ参考にしてください。 「歩けるけど痛い」「膝がぐらぐらして不安定」は要注意! 「ただひねっただけだと思って様子を見ていたら、実は靭帯損傷だった。」という事例は意外に多いです。 膝には主に4つの重要な靭帯があります。 前後方向の安定性を保つ前十字靭帯・後十字靭帯、左右方向の安定性を保つ内側側副靭帯・外側側副靭帯です。これらはバスケットボールやサッカーなどのスポーツはもちろん、転倒などでも痛めるケースがあります。 「歩けるけれども痛みが続く」や「膝がぐらぐらして不安定」と感じるときは、これらの靭帯を痛めている可能性があります。 また、靭帯を痛めていると関節の中に血が溜まることが多いです。 「もしかしたら当てはまるかも」と思った場合は、自己判断せずに病院を受診しましょう。 歩けるけど痛い 膝がぐらぐらして不安定 「靭帯」や「半月板」を損傷している恐れがあります。自己判断はせず、病院を受診しましょう! また、膝のクッションや安定性を保つ役割をしている組織に半月板が存在します。半月板は左右に1つずつありますが、こちらも膝をひねって痛めた際に損傷してしまうことがあります。 年を取ると徐々にすり減って切れやすくなります。特に、高齢の方はバスの乗り降りなど少しの段差を下りただけでも半月板が切れてしまう恐れも。「ブチッ」という感覚を伴うのが特徴的です。半月板損傷は検査しないと判明せず、病院でMRIなどを撮影しなければなりません。 一口に「捻挫」と言っても、紹介したような損傷が隠れている可能性もあります。ちょっとでも違和感があるなら、病院に受診するようにしてみてください。 膝を捻挫して歩けるけど痛いときの対処法 膝をひねってしまった受傷直後は、RICE処置を行いましょう。 Rest:安静 Ice:冷やす Compression:圧迫 Elevation:挙上 スポーツはすぐに中止し、歩行もできればしない方が望ましいです。氷や保冷材などを使って膝を冷やしながら、包帯などがあれば圧迫してください。 また、寝ているときは心臓より高い位置に足をあげておくと、膝が腫れてくるのを予防できます。 しかし、自己判断での応急処置は症状を悪化させてしまうリスクもあるため、症状に適した応急処置について確認することが重要です。 当院リペアセルクリニックでも捻挫の症状に適した対処法や治療法についてご説明いたしますので、お気軽にお問い合わせください。 膝を捻挫して歩けるけど痛いときに受けるべき診断方法は? 問診と身体診察で、どのような怪我が疑わしいのか予想がつく場合もあります。 基本的には、まずレントゲンで骨折がないかどうか確認します。レントゲンだけではわからない場合は、骨をより詳しく見るためにCT検査を行うこともあります。その後、靭帯損傷や半月板損傷が疑われる場合にはMRI撮影を実施します。 レントゲン撮影 CT検査 MRI撮影 検査の結果、手術が必要な靭帯損傷などの疑いがなければ保存療法になります。 損傷した関節包や靱帯が修復する期間は、通常3週間前後です。この期間は激しい運動や重労働などはせず、安静にしていましょう。安静を保つ目的で、一定期間添木や松葉杖・サポーターなどの使用を指定するケースもあります。 痛みが強い場合は、飲み薬や湿布を処方する場合もあります。ただし、鎮痛薬は痛みを止めるだけで治ったわけではないので、一番大事なのは膝の安静です。 そのまま通常の生活に戻れる場合は、晴れて治療終了です。しかしながら、安静にしていた影響で筋力が低下したり、動きが悪くなることがあります。 その際はリハビリテーションを実施して膝関節の機能を戻すとともに、次の怪我の予防も同時に行うことが大切です。 膝を捻挫して歩けるけど痛いときによくある質問 膝を捻挫して歩けるけど痛いときによくある質問をQ&A形式で紹介します。 膝関節を含む捻挫の予防法や対処法はありますか? 運動をされる場合は、適切なストレッチやウォーミングアップが大切です。筋肉の柔軟性を保ち、温めてしっかりと動かせる状態にしてから運動を始めることで、関節に負担がかかりにくくなります。 また、普段から下肢の筋力が衰えないように意識してトレーニングをしておくことも重要です。さらに、自分の足に合った靴を選ぶことも転倒の予防になります。 膝関節捻挫を引き起こしてからスポーツに復帰できる目安は? スポーツ復帰には、痛みがなくなっていることが大前提です。痛みがあるまま再開すると、膝をさらに痛めたり、かばって別の部位の怪我を引き起こしかねません。 一般的に、通常の捻挫であれば2〜3週間で痛みが落ち着くので、軽い運動から再開するように指導します。 膝に過度な負担をかけないよう、サポーターなどの補助具を使用することも勧められます。 膝関節捻挫は何科を受診すればよいですか? 膝関節捻挫は外傷により発症します。よって、整形外科を受診しましょう。 とはいえ、受傷した時間が深夜や早朝だと、最寄りの整形外科医が受診の時間外の場合もあるでしょう。このような場合は、整形外科のある最寄りの大きな病院に問い合わせるか、厚生労働省が推奨している「♯7119」に電話で相談してみてください。 あきらかに緊急性がない場合は当院へご相談ください。国内で10,000以上ある実績を元に、親身に対応いたします。 膝を捻挫して歩けるけど痛いときは重症の可能性あり!早めに医療機関を受診しよう この記事では、膝関節捻挫について解説しました。 膝関節捻挫は直接的・間接的な原因から発症し、受傷直後に強い痛みを伴います。病院を受診せずに痛みを我慢しその後も様子をみてしまう方も多いのが現状です。しかし、裏側に潜む靭帯や半月板の損傷も考えられます。 自己判断で無理せず、最寄りの医療機関を受診するよう心がけましょう。 従来の治療では、症状に応じて約4〜8週間の固定期間が必要ですが、先端医療である再生医療による治療で痛み症状の早期改善が期待できます。 捻挫の痛みを早く治したい方は、この機会に再生医療がどのような治療をするのかお問い合わせください。 ▼捻挫の早期回復に再生医療が注目 (こちらをクリックして)無料で相談しよう \お問い合わせはこちらから/ 0120-706-313 (受付時間:9:00〜18:00)
2023.08.28 -
- ひざ関節
- 膝部、その他疾患
「離断性骨軟骨炎ってどんな病気?」 「具体的な原因や症状を知りたい」 離断性骨軟骨炎(りだんせいこつなんこつえん)とは、スポーツ動作などにより関節内の軟骨が傷んでしまい、進行すると一部が剥がれてしまう病気です。初期は軽い痛みですが、進行すると変形性関節症(関節の骨が変形する病気)に移行するリスクがあるため放置してはいけません。 本記事では、離断性骨軟骨炎の概要をはじめとして以下を解説します。 好発部位別の原因 ステージ分類 進行度別の症状 診断方法 治療方法 予防方法 離断性骨軟骨炎は、成長痛と勘違いされ放置されることがあります。見逃さないためにも、本記事で具体的な原因や症状の理解を深めてください。 なお、当院「リペアセルクリニック」の公式LINEでは、再生医療の情報提供と簡易オンライン診断を実施しております。膝や足首、肘の痛みや違和感でお悩みの方は、ぜひ一度公式LINEにご登録ください。 離断性骨軟骨炎とは関節の中に軟骨が剥がれ落ちる障害 離断性骨軟骨炎とは、肘や膝などの関節の軟骨が傷んで、進行すると一部が剥がれてしまう病気です。肘の場合は野球肘とも呼ばれています。成長期の小中学生に多く見られる病気で、10代の男児に好発します。 主な原因は、スポーツ動作により繰り返される負荷です。基本的には運動を中止し、保存療法で経過を観察します。軟骨が剥がれてしまった場合や保存療法で治癒しない場合は、手術を検討しなければなりません。 離断性骨軟骨炎の好発部位別の原因 離断性骨軟骨炎の好発部位別の主な原因は以下の通りです。 好発部位 主な原因 膝・足首 繰り返す過剰な負荷 肘 不適切な投球フォーム それぞれの好発部位の原因について詳しく解説します。 膝・足首|繰り返す過剰な負荷 膝・足首の離断性骨軟骨炎は、繰り返される膝・足首への負荷により発症します。とくに膝関節では急激な動きや衝撃が影響します。 例えば、サッカーやバスケットボール、バレーボールにおける以下のような動作です。 繰り返されるジャンプ 急激な方向転換 これらの繰り返しの衝撃の積み重ねが発症の原因です。先天的な膝関節の不安定性が原因になることもあります。 肘|不適切な投球フォーム 肘の離断性骨軟骨炎は、繰り返される肘への負荷により発症します。野球の投球動作やバッティング動作の中で、繰り返される過度な負荷が主な原因と考えられます。 投球においてはオーバーユース(使い過ぎ)だけではありません。 以下のような要因から起きる不適切な投球フォームが発症の原因になります。 体幹や関節の筋力不足 肩や前腕、股関節、下肢の柔軟性の不足 体幹の回旋不足 ボールの握り方の問題 以上を改善または修正して、正しい投球フォームを取得することは、再発を予防するためにも重要です。 【関連記事】 野球で多い怪我と予防方法を解説【医師監修】 野球肘(軟骨剥離)とは?子どもの肘が痛む原因や症状、治療法を解説 離断性骨軟骨炎のステージ分類 離断性骨軟骨炎をステージ分類すると以下のように分けられます。 分類 詳細 グレード1 軟骨が軟らかくなっているが軟骨表面に損傷はない グレード2 損傷部位は安定しているが軟骨表面の一部に亀裂が現れている グレード3 損傷部位が不安定で軟骨が剥がれかかっている グレード4 軟骨の一部が剥がれてしまい軟骨が欠けた状態になっている 離断性骨軟骨炎の進行度別の症状 離断性骨軟骨炎の進行度別の症状を大別すると以下の通りです。 進行度 症状 初期 運動後に鈍い痛みや不快感が現れる 進行時 強い痛みや関節の違和感が現れる 以下では症状について詳しく解説します。 初期症状|運動後に鈍い痛みや不快感が現れる 初期症状は、運動後の鈍い痛みや不快感です。そのほかに特別な症状は現れません。発症後初期は軟骨に損傷がないためです。関節軟骨の表面に亀裂や変性が起き始めると痛みが強くなっていきます。 初期は軽い痛みであるため運動も可能です。この段階で放置して運動を続けると、亀裂が悪化して軟骨の一部が剥がれてしまいます。疑われる症状が現れている場合は医療機関の受診をしてください。 進行時の症状|強い痛みや関節の違和感が現れる 進行時の症状は強い痛みで、スポーツ動作にも影響をきたします。関節軟骨の亀裂や変性が起きているためです。 さらに進行すると肘や膝の曲げ伸ばしの際に、引っかかる感覚やズレた感覚が現れます。軟骨の一部が関節の中に剥がれてしまったためです。 軟骨の一部が関節に挟まると、ロッキングと呼ばれる「関節が急に動かなくなる症状」が現れます。ロッキングが起きた際は、無理に動かさず速やかに医療機関を受診してください。 また、これらの症状が長期に及ぶと変形性関節症に移行するおそれがあります。軽い痛みの段階から治療を受けましょう。 離断性骨軟骨炎の診断方法 離断性骨軟骨炎の診断方法は、関節の痛みや動きの診察のほか、以下のような画像検査を行って判断します。 検査 詳細 レントゲン検査 進行状態を確認できる 超音波検査 初期段階を早期発見するのに有用である CT検査 剥がれた軟骨の大きさや位置を確認できる MRI検査 初期段階のわずかな変化を診断できる MRI検査は超音波検査で代用できます。そのため、MRI検査は進行後に手術の必要性を判断する際に利用します。 離断性骨軟骨炎の治療方法 離断性骨軟骨炎の治療方法には、以下のようなものがあります。 保存療法 手術療法 リハビリ療法 再生医療 それぞれの治療方法について詳しく解説します。 保存療法 ステージ分類のグレード2までは保存療法が適用されます。運動制限や安静を保ちながら自然治癒を促します。 投球やバッティングなどのスポーツ動作だけでなく、腕立て伏せなどの関節に負荷がかかる運動は禁止です。ギプスを巻くと治癒が促されるとの報告があり、必要に応じてギプス固定を行うこともあります。 保存療法を行いながら、定期的に画像検査を行い復帰の目安を判断します。多くの場合完全に治癒するまでに1年ほどは必要です。(文献1)本人の努力だけでなく、周囲にサポートをしてもらいながら治療を進めることが大切です。 手術療法 進行した場合や保存療法が効果を示さない場合には、手術療法が選択されます。手術にはいくつかの種類がありますが、軟骨の一部が剥がれていない場合と剥がれた場合で大別すると以下のように分けられます。 軟骨の状態 行われる手術内容 剥がれていない場合 ・内視鏡(細い管の先端に小型カメラが付いた医療器具)を用いて、損傷部位に1mmほどの穴をいくつか開ける ・意図的に出血を起こして治癒を促進させる 剥がれた場合 ・剥がれた軟骨の状態が良い場合は、吸収性ピン(体に吸収されるピン)で元の位置に固定して再接合させる ・剥がれた軟骨の状態が悪いまたは大きい場合は、大腿骨などから採取した自分の軟骨を移植する スポーツ復帰の目安は手術により異なります。骨軟骨移植術の場合は、復帰まで3カ月以上の期間が必要です。 リハビリ療法 離断性骨軟骨炎におけるリハビリ療法は、保存療法の一環として行う場合と、術後に実施するものがあります。例えば、術後であれば関節の動く範囲の改善や筋力強化のリハビリを行います。 術後の投球のリハビリプログラムの一例を挙げると以下の通りです。 シャドーピッチング ネットスロー 塁間半分の投球 塁間の投球 1〜3塁間対角線に投球 このように段階的にリハビリの強度を高めていきます。 再生医療 手術を必要としない再生医療も選択肢の1つです。再生医療とは、自己の細胞を損傷部位に注入して、身体が持つ自然治癒力を活かす治療方法です。 再生医療の種類には以下のようなものがあります。 再生医療の種類 詳細 幹細胞治療 (かんさいぼうちりょう) 組織の修復に関わる働きを持つ「幹細胞」を患部に投与する治療方法 PRP療法 血液中の血小板に含まれる成長因子などが持つ、炎症を抑える働きや組織修復に関与する働きを利用した治療方法 離断性骨軟骨炎などのスポーツ外傷の再生医療に関して、詳しく知りたい方は以下を参考にしてください。 離断性骨軟骨炎の予防法 離断性骨軟骨炎の予防にはストレッチが有効です。 肘の離断性骨軟骨炎の予防を目的とした、ストレッチの一例を挙げると以下のようなものがあります。 片腕の手のひらを上にして伸ばし前に出す もう片方の手で伸ばした腕の指先を持ち手前に引っ張り伸ばす 投球だけでなくあらゆるスポーツ動作は、肩や肘、股関節、体幹などの連動が大切です。いずれかの部位の柔軟性が悪いと、なんらかの損傷のリスクが高まります。日頃から体全体のストレッチを取り入れるように心がけましょう。 まとめ|スムーズなスポーツ復帰のために適切な診断と治療を受けよう 離断性骨軟骨炎は、スポーツをしている小中学生に多く見られる病気です。軟骨が剥がれてしまうと、手術が必要になってしまうおそれがあるため早期発見が重要です。また、治療せずに放置すると、変形性関節症に移行するリスクが高まるため注意してください。 運動後に膝や足首、肘のいずれかに鈍い痛みや違和感がある場合は、成長痛と決めつけずに離断性骨軟骨炎を疑いましょう。膝や足首、肘に引っかかる感覚やズレた感覚がある場合は、軟骨が剥がれてしまったおそれがあるため、速やかに医療機関を受診してください。 当院「リペアセルクリニック」では、離断性骨軟骨炎などのスポーツ外傷に対しても再生医療を行っています。相談だけでもお気軽にご連絡ください。 離断性骨軟骨炎に関するよくある質問 離断性骨軟骨炎が完治するまでの期間は? 離断性骨軟骨炎が完治するまでの期間は、損傷の状態や治療方法などによって異なります。例えば、肘の離断性骨軟骨炎で保存療法の場合は、半年から1年ほどは必要と考えられます。(文献1) 適切な治療を受けずに放置するとどうなる? 放置すると慢性的な痛みが続き、スポーツ復帰だけなく日常生活にも支障をきたすおそれがあります。変形性関節症に進行するリスクも高くなるため、適切な治療を受けてください。 スポーツ復帰はいつごろになる? スポーツ復帰の時期は、治療の進行状況や個々の症状によります。例えば、手術療法を受けた場合は、術後3〜10カ月と手術の種類によって差があります。(文献2) 大人も発症する? 離断性骨軟骨炎は、成長中の軟骨に見られるため大人が発症するのはまれです。軟骨が成長しきった大人の場合は、剥がれかけの軟骨であっても自然治癒が望めません。 参考文献 (文献1) 野球肘:離断性骨軟骨炎(上腕骨小頭OCD)|江戸川病院 (文献2) 外側型野球肘(肘離断性骨軟骨炎)|芦屋中央病院
2023.08.24 -
- 下肢(足の障害)
- ひざ関節
- 肘関節
- 動作時の痛み
- スポーツ外傷
- 膝部、その他疾患
離断性骨軟骨炎は、主にスポーツを行っている人が発症しやすい病気です。発症した際、完治期間はどのくらいの期間を要し、運動はいつから再開できるのか疑問に感じる方もいるのではないでしょうか。 離断性骨軟骨炎は安静にしていると次第に痛みが軽減されるものの、完治したと思って無理に動くと再発する可能性があるため注意が必要です。 本記事では、離断性骨軟骨炎における完治期間の目安を解説します。再発予防法も紹介するので、離断性骨軟骨炎の症状回復へ向けた治療が知りたい方は参考にしてください。 離断性骨軟骨炎の完治期間 離断性骨軟骨炎は、治療法によって完治期間の目安が異なりますが、一般的に完治するまで6カ月以上かかる可能性があります。 そのため、完治期間の目安を把握したうえで、復帰スケジュールを組むのが大切です。ここでは、保存療法と手術療法の完治期間の目安を解説するので参考にしてください。 保存療法における完治期間の目安 保存療法における完治期間は、6カ月以上~1年ほどが目安になります。離断性骨軟骨炎は10代~20代くらいに多く発症するため、低年齢の場合は保存療法を優先するケースが一般的です。 保存療法では、離断性骨軟骨炎の要因となるスポーツ活動を禁止して安静に過ごしながら、レントゲンやMRIなどで修復状態を定期的に確認します。 症状を見ながら段階的にスポーツ活動への復帰を進めていきますが、発症前の運動レベルまで戻す場合は数カ月~1年くらいはかかる可能性があります。また、保存療法で症状回復が得られない場合は、手術を行うのが一般的です。 手術療法における入院期間と完治期間の目安 手術療法における完治期間の目安は、術式によって異なりますが6カ月~10カ月ほどでスポーツ活動に復帰できる可能性があります。入院期間も術式でさまざまで、おおむね5日~7日程度です。 退院後はリハビリを行い、修復状態を確認しながら軽い運動から復帰を開始します。本格的な復帰は6カ月ほどが多いため、6カ月ほどは無理のない範囲でリハビリを進めていくのが重要です。 スポーツ復帰を目指す場合は、適切な手術を受けて完治期間までは医師の指示に沿ったリハビリを受けましょう。 離断性骨軟骨炎の主な治し方 離断性骨軟骨炎の主な治し方は、以下の通りです。 治療法の種類 特徴 安静 運動をせず安静に療養する リハビリテーション 患部への負担軽減を目的にリハビリ訓練を実施する 薬物療法 鎮痛薬や関節内注射を行う マイクロフラクチャー法 膝関節鏡を関節内に入れて、患部の数カ所に小さい穴を開けて出血させて治癒を促進 整復内固定術 骨釘や生体吸収性ピンなどを使用して固定 骨軟骨移植術 円柱状の軟骨片を採取して、損傷した部分に移植 離断性骨軟骨炎は、問診や触診、レントゲン検査などを行ったうえで診断します。ただし、初期の場合はレントゲンでは写りにくいため、MRI検査で確定診断をするのが一般的です。 また、手術療法の術式は、遊離した軟骨片の大きさや状態などから総合的に判断して決めます。 無理に運動を継続すると手術が必要になるだけでなく、競技生活を続けられなくなる可能性があります。離断性骨軟骨炎は、早期発見・早期治療が重要なため、肘や膝に違和感があった際は、ただちに医療機関を受診し、医師の指示に従いましょう。 離断性骨軟骨炎は再発するためリハビリが重要 離断性骨軟骨炎は、症状が治まっても再発するリスクが生じます。 再発する理由は、関節軟骨は血流が乏しく自然治癒力が限られているためです。離断性骨軟骨炎の症状は安静にしていると落ち着いてくる場合があるため、完治したと勘違いする人も少なくありません。 しかし、完治していない状態で運動を再開すると、まだ安定していない軟骨に負荷をかけてしまい結果として再発につながります。 痛みや引っかかりがなくなったとしても、自己判断で運動を再開するのは危険です。離断性骨軟骨炎は完治までに6カ月以上かかるケースが一般的なため、再発を防ぐためにもリハビリが重要です。運動を再開する際は自己判断せず、医師の診察を受けましょう。 離断性骨軟骨炎のリハビリ治療と期間 離断性骨軟骨炎は、症状が軽い場合はリハビリと安静中心の保存療法で治療が行われます。リハビリ期間は、患者さんの年齢や症状の進行具合によって変わってきます。 離断性骨軟骨炎は、一般的に約1〜2カ月で痛みがやわらぎますが、3か月ほどの安静が必要です。 リハビリは、可動域訓練や筋力トレーニングを中心に行います。理学療法士の指導やアドバイスをもとに、肘や膝に負荷のかからない動作を身につけるのがリハビリの目的です。 3カ月以上保存療法を行っていても症状の回復が見込めない、もしくはすでに症状が進行しており軟骨の状態が良くない場合は、リハビリより手術を先に行います。 手術は関節鏡を使ったものが多いですが、症状によっては軟骨の移植など大がかりな方法になる場合があります。 関節鏡下の手術の場合は傷口が小さく回復が早く、早期にリハビリを開始可能です。ただし、軟骨の修復は普通の骨と比べて時間がかかるため、無理に動かさないよう注意しましょう。 離断性骨軟骨炎の再発予防法 離断性骨軟骨炎は、再発する可能性のある病気です。痛みが軽減されたかといって、本格的な復帰をしないよう注意しましょう。ここでは、離断性骨軟骨炎の再発予防法を解説します。 完治してから復帰する 離断性骨軟骨炎の再発予防には、完治してから復帰するのが重要です。痛みがなくなると運動を再開しても問題ないと判断してしまいがちですが、完治していない場合、軟骨は不安定な状態です。 離断性骨軟骨炎の発症前と同じレベルで体を動かすのは、再発につながるリスクが生じるため注意しなければなりません。再発しないためにも運動の時期は勝手に決めず、治療期間中は医師の指示に従い、段階を踏んで本格的な復帰を目指すようにしましょう。 オーバーワークになりすぎないようにする 離断性骨軟骨炎の再発予防には、オーバーワークになりすぎないよう練習量を調整するのが大切です。痛みがなくなると、発症前と同じ運動量で練習に参加してしまう可能性があります。 特にスポーツをしている場合はまわりに遅れをとりたくないと思って、無理をしてしまいがちです。完治していない状態でオーバーワークになりすぎると、再発により長期離脱につながりかねません。医師から完治と言われない限りは、練習量を抑えるのが重要です。 サポーターを着用する 離断性骨軟骨炎の再発予防には、サポーターの着用が効果的です。軟骨と骨をつなぎとめる部分の血流障害を引き起こすと軟骨が剝がれやすくなり、離断性骨軟骨炎を再発する要因になります。 離断性骨軟骨炎の場合は、サポーターを使用すると体の重心バランスが整い、患部の負担軽減につながります。サポーターはギブスと異なり関節の動きを固定しないため、自然な動きが可能です。 なお、離断性骨軟骨炎向けのサポーターには大腿四頭筋を補強するタイプや固定力の高いタイプなど、さまざまな種類があります。再発防止策には、目的や症状に合ったサポーターを選ぶのが大切です。 定期的に検診を受ける 定期的に検診を受けるのが、離断性骨軟骨炎の再発予防策です。スポーツでは継続的な負荷がかかるため、定期的な検診により症状が悪化していないか確認できます。 離断性骨軟骨炎は治療が早ければ、保存療法で症状回復が期待できる病気です。完治したからといって無理をしてしまうと、再発する可能性が考えられます。再び長期離脱につながらないよう定期的に受診し、再発を予防するのが大切です。 離断性骨軟骨炎における治療法の1つ再生医療の可能性 再生医療とは、損傷した組織や臓器の機能を回復させるために、細胞や組織、臓器を人工的に作製したり、自己修復能力を促進したりする医療技術の総称です。 当院「リペアセルクリニック」では、患者様自身の幹細胞を接種、培養しているため、副作用のリスクが低く抑えられます。 また、採取する脂肪量は米粒2~3粒程度のため、体への負担は大きくありません。再生医療では、手術不要で治療が受けられます。 メール相談やオンラインカウンセリングを受け付けておりますので、離断性骨軟骨炎の治療に関する悩みがある方は、お気軽にお問い合わせください。 まとめ・離断性骨軟骨炎の再発予防には完治期間を守ることが大切 離断性骨軟骨炎の完治期間は、6カ月以上が目安となります。一般的に安静にしていれば症状軽減が期待できますが、完治したと思って発症前と同様の生活をすると再発しやすくなるため注意が必要です。 離断性骨軟骨炎はリハビリを正しく行うと症状緩和につながり、再発を予防できます 治療後はいきなり発症前と同じ練習量やトレーニングをするのではなく、段階を踏んで運動を再開するのが大切です。 離断性骨軟骨炎の完治期間を踏まえたうえで、症状回復へ向けた適切な治療を受けましょう。
2023.05.26 -
- ひざ関節
- 膝部、その他疾患
膝の痛みにお困りの方は、痛みの原因を知って「早く治したい」という方がほとんどでしょう。 リンパの詰まりによる膝の痛みは「筋肉の働きの低下」や「食生活」が影響しているため、運動習慣や食生活の改善が重要です。 しかし、セルフケアで症状が改善しない場合は、医療機関に相談して適切な治療を受ける必要があります。 「セルフケアで治らない」「膝の痛みが長引いて不安」という方に向けて、「再生医療によって膝の痛み症状の改善が見られた症例」を公式LINEで大公開! LINE登録をしていただいた方限定で「再生医療の基礎がわかるガイドブック」が無料でお受け取りいただけます。 ▼公式LINEでは再生医療に関する情報や症例を公開中! 膝の裏側(内側)を押すと痛む症状はリンパの詰まりが原因の一つ 膝の裏側に痛みや腫れがある場合や膝から下がむくむ症状は、「リンパの詰まり」が原因の一つであることが考えられます。 特に、長時間の立ち仕事や座りっぱなし、飛行機やバスで足を下げたままの姿勢では、リンパの流れが悪くなることが多いです。 リンパが詰まることにより、リンパ液の流れが滞り、体内の老廃物がたまりやすくなります。 その結果、膝の裏を押すと痛みがあるほか、腫れやだるさ、重さ、冷えなどの症状が生じることがあるのです。 これらの症状はリンパの流れを改善することで軽減されるため、日常的にリンパマッサージやストレッチを取り入れることが効果的です。 適切なケアや治療を実施すれば、症状が緩和される可能性が高まります。 膝裏でリンパが詰まる原因 膝の裏には「膝窩リンパ節(しっかリンパせつ)」というリンパ節が存在します。 リンパ管は体内で老廃物や細菌を運ぶ役割を担い、リンパ節はそのリンパ管を通る異物を取り除く場所です。 しかし、リンパの流れが悪くなると、リンパ液がリンパ節でスムーズに循環できず、詰まりが起こることがあります。 特に、筋肉の働きが低下したり、偏った食生活をしていると、膝の裏でリンパが詰まりやすくなるのです。 これらの原因がリンパの流れを悪くし、むくみや不快感を引き起こします。 ここでは、それぞれの原因について詳しく見ていきましょう。 筋肉の働きが低下している リンパの流れは筋肉の動きによって支えられていますが、筋肉が十分に働かないと、リンパの流れが滞りやすくなります。 特に運動不足やデスクワークなどで長時間座ったままでいると、膝の裏側の筋肉が使われず、リンパ液が溜まりやすくなるのです。 また、加齢やケガにより筋肉の柔軟性や強度が低下すると、リンパ液の循環が阻害されることもあります。 筋肉の働きが弱まると、リンパ管が圧迫されて流れが悪くなることが原因です。 そのため、筋肉を適度に動かし、柔軟性を維持することが大切です。 例えば、軽いストレッチやウォーキングなどの運動を日常生活に取り入れることで、筋肉を活性化させ、リンパの流れをスムーズにすることができます。 偏った食生活になっている 偏った食生活は、体内の水分バランスや代謝機能に悪影響を与え、リンパの流れを悪くすることがあります。 特に塩分が多い食事や脂っこい食べ物を頻繁に摂ると、体内に余計な水分が溜まり、リンパ液の流れが滞りやすくなるので注意が必要です。 また、ビタミンやミネラル、マグネシウムが不足していると、リンパの循環がスムーズに進まなくなります。だからこそ、バランスの良い食事を心がけることが大切です。 野菜や果物を多く摂り、適切な水分補給を行い、加工食品や高塩分の食事を控えることで、リンパ液の流れを正常に保つことができます。 膝の裏側(内側)にリンパが詰まっている時の対処法 膝裏のリンパが詰まっている場合は、先ほど説明したリンパの流れが悪くなる原因を考慮した対応が必要です。 その際の具体的な解消方法を3つ紹介しましょう。 適度な運動をする 筋肉を動かして血液やリンパの流れを促すことを「筋ポンプ作用」と言います。 この筋ポンプ作用を働かせるには、適度な運動が必要です。 運動不足は筋肉量や代謝の低下を引き起こしますが、適度な運動を行うことで、筋肉量や代謝が向上し、血液やリンパ液の循環も良くなります。 特におすすめなのは、膝や足首の屈伸運動です。 たとえば、つま先を上げ下げする足首の運動は「第二の心臓」と呼ばれるふくらはぎの筋肉を刺激し、血液やリンパの流れを促進する効果があります。 運動は「テレビを見ながら」や「トイレで座りながら」など、日常の合間にこまめに行うのが良いでしょう。 ただし、筋肉痛になるほどの激しい運動は疲労を蓄積させるため、無理をしないように注意が必要です。 マッサージを行う リンパの流れを良くするためのマッサージを行いましょう。 膝裏やふくらはぎを軽くさする、推すなどの程度から始めて、徐々にほぐすようにしていきましょう。 足裏からふくらはぎに向かって優しくマッサージすることで、血管やリンパ管の収縮力を高め、血液やリンパ液の排出を助けます。 押すなどして圧迫した場合に、痛みや違和感を感じる場合はリンパの流れが悪いだけではなく、他の病気が潜んでいる可能性があるので無理に行わないで中止しましょう。 専門家によるマッサージではなく、自分で行う場合は、あくまで気持ちいい程度の加減で行うことが大切です。 ▼先端医療である再生医療も選択肢の一つ >>【無料プレゼント】再生医療ガイドブックを今すぐ受け取る 生活習慣を見直す リンパの流れを妨げる肥満を防ぎ、改善するためには、バランスの取れた食事や運動を続けるなど、規則正しい生活習慣が大切です。 また、長時間椅子に座って膝を圧迫したり、足を下げたままにすると、膝の後ろにあるリンパ節に負担をかける原因になります。 時々立ち上がって歩いたり、しゃがんでみたり、足を伸ばしたりすることで体を動かしましょう。運動やマッサージも効果的です。 自宅にいるときは、足を心臓より高い位置にして休むのも良い方法です。 こうすることで、重力に逆らわずに血液やリンパ液を戻しやすくなります。 さらに、食事や水分摂取にも注意が必要です。塩分やカフェインを摂り過ぎると水分代謝が悪くなるため、控えるようにしましょう。 また、水分不足もむくみの原因になるので、適度に水分補給を心がけてください。 膝の内側を押すと痛む場合に自宅でできるリンパをほぐすマッサージのやり方 膝の内側の痛みには、以下のでリンパをほぐすマッサージを実践してみましょう。 マッサージをしても膝の内側や膝裏が痛みが長引いている方は、治療しないと治らない疾患の可能性が考えられます。 長引く膝裏の痛みにお困りの方は、症状が悪化する前に医療機関の受診、早期に治療を開始しましょう。 また、近年の治療では手術せずに治療する方法として「再生医療」が注目されています。 膝の痛みが悪化して日常生活に影響が出る前に、先端医療の再生医療ではどのような治療を行うのか知っておきましょう! \公式LINEでは再生医療に関する情報や症例を公開中!/ リンパ以外の原因もある?膝裏を押すと痛い場合に注意すべき症状 膝の裏が腫れている場合に、リンパ節のむくみだけではなく、他の病気が潜んでいる可能性もあります。 以下のポイントを参考にして、気になる場合は自己判断で治療したり、放置したりせずに整形外科や循環器内科などを受診しましょう。 全身にむくみがある|内科系の疾患によるむくみの可能性 全身にむくみがある場合は、心臓や腎臓など内科系の疾患によるむくみの可能性があります。 膝裏のむくみに気づいた場合には、他の部位にもむくみがないかどうかをチェックしましょう。 膝周辺に痛みや熱がある|関節の炎症や怪我の可能性 膝裏のむくみだけでなく、痛みや熱がある場合は、膝関節の炎症や怪我などの可能性があります。 また、リンパ節に細菌が入って感染症を起こしてしまうこともあります。 このような症状の場合は、早めの医療機関で適切な治療を受けることが大切ですので注意しましょう。 だんだん浮腫がひどくなる|病気が潜んでいる可能性 時間とともにむくみが悪化する場合、何かしらの病気が原因になっている可能性があります。 その中でも特に考えられるのが「ベイカー嚢腫(のうしゅ)」です。 この病気は、膝の裏側にある袋状の部分が大きくなってしまうもので、特に50歳以上の女性に多く見られます。 また、膝の変形が進むと、膝関節に炎症が起こり、水が溜まってしまうこともあります。 このような症状が現れた場合は、放置せずに早めに医師の診断を受けることが大切です。 適切な治療を受けることで、症状の悪化を防げます。 まとめ・膝の裏側の腫れや痛み、膝下のむくみはリンパの詰まりが原因か?! 膝の裏側(内側)の痛みや腫れ、膝下のむくみはリンパの詰まりが原因の一つです。 しかし、リンパの問題だけでなく、他の健康問題が影響している場合もあります。 リンパの詰まりが疑われる場合は、まずは早めに対処法を試してみましょう。 もし症状が改善しなかったり、悪化したりするようであれば、医師の診断を受けることが大切です。 膝の痛みやむくみは日常生活に大きな支障をきたすことがあるため、軽視せず、早めの対策を心がける必要があります。 適切な運動やマッサージを行ったり、生活習慣を見直したりすることで、リンパの流れを改善し、健康な体を保てるでしょう。 ▼LINE限定のガイドブックを無料でプレゼント >>【公式LINE限定】再生医療に関する情報を見てみる ▼以下もご参考ください 膝が痛い|朝寝起きや、歩きはじめの膝に痛みや違和感を感じたときの治療法
2022.11.25 -
- ひざ関節
- 脊柱管狭窄症
- 膝部、その他疾患
「膝から下が痛くて重い」「膝下がジンジン・ズキズキする」 上記のような膝下の痛みやだるさの原因を知って「早く治したい」という方も多いのではないでしょうか。 本記事では「膝から下が痛い・重い・だるい」ときに考えられる4つの疾患と原因を医師が解説します。 多くの症例実績がある「リペアセルクリニック」だからこそお伝えできる、膝から下が痛いときに取るべき行動もお伝えします。 また、当院の公式LINEでは、手術以外の選択肢として注目を集める「再生医療」に関する症例を公開中です。 再生医療に関する無料のガイドブックも配信していますので、膝の痛みの根本的な治療が期待できる医療技術に興味がある方は是非ご参考ください。 \公式LINEでは再生医療に関する情報や症例を公開中!/ ▼LINEでしか見られない情報をこちらから! 膝から下が痛いときに考えられる4つの疾患と原因 膝から下が痛いときに考えられる疾患と原因は、以下の4つが挙げられます。 閉塞性動脈硬化症 深部静脈血栓症 脊柱管狭窄症 下肢静脈瘤 普段聞きなれない言葉が並んでおり、不安になる方もいるかもしれません。これらの各疾患について、症状や原因を記しながら、できるだけ簡単に説明してまいります。 なお、膝の内側・外側のように痛む場所から考えられる疾患もあるので、ある程度「痛みの場所が特定」できている方は、以下の記事もご覧ください。 ①閉塞性動脈硬化症(へいそくせいどうみゃくこうかしょう) 閉塞性動脈硬化症とは、以下のように足の血管の動脈硬化が進んでしまい、血液が流れづらくなったり、つまったりする病気です。 足の血流が悪くなるので、歩くときに足の痛みや痺れ、冷たさを感じることがあります。進行すると、安静にしていても同様の症状が出てきますので、注意が必要です。 「動脈硬化」は全身に起こりやすいものなので、足だけでなく手にも同様の症状が出てくる可能性もあります。安静時の足の痛みや足の潰瘍、壊死はだいぶ進行している状態です。下表に閉塞性動脈硬化症の症状や原因をまとめたので、ぜひ参考にしてみてください。 閉塞性動脈硬化症の症状 足の痺れや冷感(しびれ・冷える) 歩行の時の足の痛み 間欠性跛行(しばらく歩行していると、足の痛みが強くなり歩行困難となる症状) 安静時の足の痛み 足の潰瘍・壊死 閉塞性動脈硬化症の原因 肥満 高血圧 喫煙 糖尿病 このように、動脈硬化の主な原因として生活習慣の乱れによるものが大きいことがわかります。 治療には早めの対処が必要となりますので「足の痺れ」「痛み」「冷たい感覚」などの症状を感じたら医療機関を受診し、早めにご相談されることをお勧めします。 ▼膝の疾患に関する症例を限定公開! >>【公式LINE限定】再生医療に関する情報を見てみる ②深部静脈血栓症(しんぶじょうみゃくけっせんしょう) 深部静脈血栓症とは、以下のように足の奥深くに通る静脈血管のなかに、血の塊(血栓)ができてしまう病気です。 この血栓が心臓や肺に流され詰まってしまうと、心筋梗塞や肺塞栓症などの命に関わる重大な疾患を引き起こす危険性があります。 特に足の整形外科の手術後や長時間のフライトなどで多くみられ、別名「エコノミークラス症候群」と呼ばれることもあります。下表に深部静脈血栓症の症状や原因をまとめたので、ぜひ参考にしてみてください。 深部静脈血栓症の症状 片足が大きく腫れ上がる 赤黒く変色する ジンジンとした痛みが伴う 肺塞栓症へ移行した場合、呼吸が荒くなり、胸が痛くなる 深部静脈血栓症の原因 手術や怪我による静脈血管の損傷 長期の臥床(寝たきり)など、足を動かしていない期間が長い 喫煙 脱水 その他血流の低下が起こりうる場合 手術やケガによって「血液が固まりやすい・静脈内血液の流れが悪い・静脈が傷ついている」という3つの状態が満たされる場合に深部静脈血栓症が起こりやすくなります。 このように、不動に伴う血液循環が滞りやすい期間が長くなってしまった場合によく起こります。 放置しておくと、重篤な肺塞栓症へと進行してしまう可能性もあるため、おかしいと思ったらただちに専門の医療機関へ行きましょう。 ③脊柱管狭窄症(せきちゅうかんきょうさくしょう) 脊柱管狭窄症とは、脊髄や抹消神経が通るトンネル(脊柱管)が何らかの影響を受けて狭くなってしまい、発症する疾患です。 中高年で腰痛を伴う代表的なもので、長時間歩くことができなくなる間欠性跛行(かんけつせいはこう)がみられます。 脊柱管狭窄症で悩む中高年の患者さんは数多くいます。それゆえ、見過ごされやすいのも事実です。脊柱管狭窄症を見過ごさないためにも、下表を参考に当てはまる症状がないかチェックしてみてください。 脊柱管狭窄症の症状 お尻から足にかけて痛みや痺れがある 長く歩いたり、立ったままになるのが辛い 足に力が入りにくい 体を反らす動きがしづらい 体を前屈みにすることで症状が楽になる 尿漏れなどの排尿・排便障害がある 脊柱管狭窄症の原因 加齢による背骨の変形や、ヘルニア 先天的なもの 猫背などの偏った姿勢 反り腰 仕事などで腰に負担のかかる動作の繰り返し ひどいものでは「足に力が入らない」「オムツが必要となる排尿障害」が起こるなど、日常生活に大きく影響してくる場合もあります。 気になる症状が出たら、できるだけ早く専門医に受診しましょう。 ④下肢静脈瘤(かしじょうみゃくりゅう) 下肢静脈瘤とは、足の血管(静脈)に異常が起こる病気です。血管がコブ(瘤)のように膨れ上がり、以下のように体表からはボコボコしたように見えます。 静脈の中には、血液の逆流を防ぐための弁がついており、ふくらはぎの筋肉などの力で下から上に血液を戻してくれます。 しかし、その弁が壊れて正常に働かない場合は、血液が滞ってしまい、下の方に溜まってしまうのです。その血液が溜まった状態を下肢静脈瘤と言います。 下肢静脈瘤の症状や原因は、さまざまあります。見た目的にも分かりやすいため、自分で気づきやすい病気です。下表に下肢静脈瘤の症状や原因をまとめたので、ぜひ参考にしてみてください。 下肢静脈瘤の症状 ふくらはぎのだるさ、重さ 湿疹や皮膚の変症、皮膚炎 足がむくむ 足がつる(こむら返り) 血管が目立つ(ボコボコなる) 下肢静脈瘤の原因 加齢による筋肉や血管機能の低下 立ち仕事 妊娠や出産 遺伝的な要素 激しいスポーツ このように下肢静脈瘤は加齢による血管のしなやかさがなくなったり、立ちっぱなしの仕事を続けたりなど、誰にでも起こりうる病気です。上記の症状に当てはまる場合は、医療機関に相談しましょう。 膝から下が痛いときは何科を受診すべきか【疾患別に解説】 「膝から下が痛い」と感じた時に、考えられる疾患について4例説明しましたが、似ている症状も数多くあります。 そのため、疾患の見分け方は専門医でなければ難しいことが多々あります。 早めの対処が必要な疾患もありますので気になる症状がみられましたら、下記を参考に専門医へご相談ください。 症状 受診科目 下肢静脈瘤 血管外科※ 心臓血管外科 皮膚科 形成外科 循環器内科 閉塞性動脈硬化症 血管外科※ 循環器内科 深部静脈血栓症 血管外科※ 循環器内科 整形外科 脊柱管狭窄症 整形外科 自分の症状がどれに該当するのかわからない方は、当院(リペアセルクリニック)へお電話ください! 当院ではどんな些細なことでも無料でご相談いただけます。 >>今すぐ電話してみる また、当院の公式LINEでは、再生医療に関するガイドブックや無料診断が受けられます。 「電話をかけるのはちょっと...」という方は、まず無料診断からご利用ください! ▼膝の疾患に関する症例を限定公開! >>【公式LINE限定】再生医療に関する情報を見てみる まとめ|膝から下が痛いと重大な疾患も考えられるので早めに受診を! 今回は、膝の病気で「膝から下が痛い・重い・だるい」という症状で、考えられる疾患についてお話しました。 本記事で挙げた疾患の中には命に関わる重大な疾患も含まれている為、気になる症状がありましたらできるだけ早めに専門医へ相談してください。 難しい言葉が並び、読むのも嫌になるかもしれませんが、これらの疾患は誰にでも起こりうるものです。例えば「深部静脈血栓症」から「肺塞栓症」へ移行してしまうと、一刻も争う状態になります。 「あの時、もっと早く相談しておけば良かった……」そんな声が1人でも少なくなるよう、本記事を読んでいただけると幸いです。 当院「リペアセルクリニック」では、膝の痛みなどに関する再生医療や幹細胞治療をおこなっています。万が一、重い症状だとしても再生医療を実施すれば、身体に負担のかかる手術をしなくてもよくなる可能性があります。 膝の痛みで少しでも気になる症状がありましたら、当院へご相談ください。 ▼膝の疾患に関する症例を限定公開! >>【公式LINE限定】再生医療に関する情報を見てみる 膝から下が痛いのよくある質問 Q.膝がズキズキ痛む原因はなんですか? A.膝がズキズキ痛む原因として、以下が考えられます。 肉離れ、打撲などのスポーツ外傷や膝の使いすぎによって膝がズキズキ痛む場合があります。 しかし、痛みが続いている場合は「半月板や軟骨の損傷」や「筋肉や腱の断裂」が原因となっているケースもあり早期に治療が必要なことも。 少しでも膝の痛みにお困りの方は、放置せずに当院(リペアセルクリニック)にお気軽にご相談ください。 また、当院の公式LINEでは、半月板や軟骨の損傷など膝の痛みを手術しないで治療できる再生医療について情報を配信しています。 「手術しないで膝を治療したい」「膝の痛みを早く治したい」という方は、ぜひご参考ください。 ▼膝の疾患を手術しないで治すなら再生医療 >>【公式LINE限定】再生医療に関する情報はこちら Q.膝が痛くて夜寝れない原因と対処法はありますか? A.膝が痛くて寝れない場合の原因は様々ありますが、「変形性膝関節症」の可能性が考えられます。主な原因としては、加齢や膝への負担により軟骨が摩耗するためです。 進行すると痛みで膝を伸ばせず寝ていても痛みを感じるケースも珍しくありません。少しでも痛みを軽減する対処法としては、以下が挙げられます。 腓腹筋のストレッチ ハムストリングのストレッチ 寝るときの姿勢は仰向け これらの具体的な方法については、以下の記事をご覧ください。 なお、膝が痛くて夜に寝れない場合、他の疾患の可能性も考えられるので、早めに医療機関に相談しましょう。
2022.11.14 -
- 変形性膝関節症
- ひざ関節
- 膝部、その他疾患
「O脚って見た目だけの問題?」「自分で治せる?」「放っておくとどうなるの…?」 O脚は見た目のコンプレックスだけでなく、放置すると将来的に膝の痛みや変形性膝関節症につながる可能性も。 すぐに改善される訳でもないため、日頃から予防を積み重ねていくことが、将来の健康につながってきます。 この記事では、O脚を自分で治すための方法に加え、セルフケアで改善しない場合や、痛みが強い場合の治療法についてご紹介。 さらに、「セルフケアだけでは不安…」「もっと根本的に改善したい」という方のために、 近年注目されている「再生医療」という選択肢についても解説します。 公式LINEの方でもO脚を始めとした関節のお役立ち情報を配信しているので、ぜひ日頃の予防知識をストックしてください。 ▼LINE登録で「無料で再生医療の基礎がわかるガイド」をプレゼント! O脚に有効な治し方・改善方法3選 O脚に有効な治し方・改善方法を3点紹介します。 筋力トレーニング ストレッチ 姿勢の改善 どれもすぐに試せる方法なので、無理のない範囲で実践してみてください。 1.筋力トレーニング 膝にかかる負担を減らすために、筋肉を鍛えて膝の関節を守るトレーニングが必要です。 とくに膝を伸ばす筋肉や内もも、お尻の横の筋肉を鍛えれば、膝が左右にブレにくくなるため、O脚の改善につながります。 おすすめの運動はボールやクッションといった厚みのある柔らかいものを両膝で挟みながらのスクワットです。内ももの筋肉を働かせながら、膝を伸ばす筋肉も同時に鍛えられます。 ただし、スクワットは以下の注意点を守らなければ、膝に負担がかかるので注意しましょう。 【スクワットの注意点】 膝を深く曲げすぎない 曲げた膝がつま先より前に出ないようにする 膝を内側にひねらないようにする(内股にならないようにする) 勢いをつけてやらないようにする また、横を向いて寝た状態で、上になっている脚を斜め後ろ方向に持ち上げる運動もお尻の筋肉を鍛え、O脚改善の効果が期待できます。 2.ストレッチ 太ももの裏にあるのはハムストリングスと呼ばれる筋肉です。この筋肉は膝を曲げるときに働くため硬くなると膝が伸びにくくなってしまい、O脚につながります。 今回は床や椅子に座って簡単にできるハムストリングスのストレッチを紹介します。 【床でできるハムストリングスのストレッチ】 1.ストレッチする方の脚をまっすぐ伸ばして、つま先を上に向ける 2.ゆっくり体を倒しながら片手でつま先を触る 3.伸びているのを感じた状態で60〜90秒ほどキープする 体を倒す場合に背中が丸くならないように気をつけましょう。 【椅子でできるハムストリングスのストレッチ】 1.椅子に浅く腰掛けてストレッチする方の脚をまっすぐ伸ばす 2.かかとを床につけてつま先を上に向ける 3.ゆっくり体を前に倒して太ももの裏が伸びているのを感じながら15秒ほどキープする 背中を丸くするのではなく足の付け根から曲げるように体を倒すのがポイントです。 3.姿勢の改善 猫背といった悪い姿勢を改善するのもO脚を改善する方法です。 猫背が強まり骨盤は後ろに倒れてしまうと、重心が後ろに偏ってしまいます。そのままでは後ろにバランスを崩してしまうので、重心を前に保つために膝が曲がってガニ股のような姿勢になってしまい、O脚の傾向が強まりやすくなります。 猫背を改善するには、座った状態で猫背にして骨盤が後ろに倒れた状態から、軽く下腹を凹ますように力を入れるのがポイントです。実際にやってみると、背筋が伸びて骨盤が立ってくる感覚が得られるはずです。 O脚は、見た目だけでなく、将来的な膝の痛みや変形性膝関節症のリスクを高める可能性があります。 当院の公式LINEではO脚をはじめとした膝の症状改善に役立つ情報だけでなく、膝の健康を守るための内容や、手術を必要としない最先端の医療技術である「再生医療」に関する情報も配信しています。 無料のガイドブックも贈呈しておりますので、深刻化してしまった際の医療技術としてご活用ください。 ▼LINE限定のガイドブックを無料でプレゼント >>再生医療の情報をLINEにて配信中! O脚(内反膝)とは?脚が外側にカーブした状態 O脚とは別名「内反膝(ないはんひざ)」と呼ばれ、脚が外側にカーブしてしまい、膝から下が内側に曲がった姿勢になります。両脚を合わせたときに太ももから膝、そしてすねで作られる形が英語の「O」になることから「O脚」と呼ばれています。 左右の「くるぶし」をくっつけて立ったときに、膝の内側に目立った隙間ができてしまうのが特徴です。 O脚のデメリット O脚は単に見た目の問題だけでなく、膝関節への負担が増加し、変形性膝関節症のリスクを高めてしまうことが最大のデメリットです。 O脚の場合、体重が膝の内側に偏ってかかるため内側の軟骨がすり減りやすくなり、将来的に膝の痛みや変形を引き起こす可能性が高まります。 その他にも、特に見た目に関しては以下のようなデメリットが考えられます。 脚のラインが崩れる 服装の選択肢が狭まる コンプレックスになる 気になる症状がある場合や将来的なリスクを減らしたい場合は、専門医に相談することをおすすめします。 O脚の原因 O脚は子どもの頃にみられる場合と、大人になってからみられる場合があります。それぞれ原因について紹介します。 子どもの頃にみられるO脚の原因 乳幼児から2歳までの子どもはO脚になるのが普通で、この時期のO脚を「生理的O脚」と呼びます。2歳以降はO脚の反対で膝から下が外側に曲がって、両足を揃えたときに「X」になる「X脚」という状態に変化するのです。 そして、成長するにつれてX脚の程度が弱まっていき、成人になるとわずかに膝から下が外側に曲がった状態で止まります。 しかし、生まれながら骨に異常があったり、成長の過程で骨に関する病気になったりすると異常なO脚になる場合があります。また、怪我や関節を支える靱帯の異常によりO脚がみられるケースも少なくありません。 成人以降でみられるO脚の原因 成人以降では加齢や肥満などにより関節の変形が進む「変形性膝関節症(へんけいせいひざかんせつしょう)」や関節の炎症が続く「関節リウマチ」などの病気がO脚の原因になります。 また、姿勢が影響してO脚になるケースも珍しくありません。具体的には「猫背」になって、体の各関節が連動して変化して結果的にO脚につながります。 当院(リペアセルクリニック)では分化誘導と呼ばれる最新の再生医療として、「変形性膝関節症」や「関節リウマチ」の疾患に対しても改善が期待できる治療を提供しています。 O脚の原因となる変形性膝関節症や関節リウマチは放置すると症状が悪化し、日常生活に支障をきたすこともあります。 当院の公式LINEでは、これらの疾患に関する情報や、新しい治療の選択肢である再生医療について詳しく解説していますので、将来の対策として備えとしてご活用ください。 ▼ガイドブックを無料でプレゼント中! >>公式LINE限定で再生医療の情報を確認する まとめ|O脚の治し方を覚えて自分にあう方法を試してみよう O脚の治し方に有効なのは「筋力トレーニング」「ストレッチ」「姿勢改善」です。本記事では、それぞれの方法における具体的な実践方法も紹介しました。 どの方法も、今日から実行できる簡単なものです。O脚に悩んでいる方は、無理のない程度に実践してみてください。 ただしO脚の改善には継続的な取り組みが必要です。セルフケアで改善が見られない場合や、痛みが強い場合は、専門医に相談しましょう。 リペアセルクリニックでは、O脚や変形性膝関節症に対する再生医療を提供しています。 リペアセルクリニックが提供する再生医療の特長 患者様ご自身の細胞を使用するため、拒絶反応や副作用のリスクが低い 変形性膝関節症をはじめとする、様々な関節の疾患の治療への豊富な実績 「O脚を根本から改善したい」「膝の痛みを何とかしたい」「手術は避けたい」、 そのようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度、リペアセルクリニックの無料相談をご利用ください。 O脚に関するよくある質問 O脚に関するよくある質問と回答をまとめました。 男性がO脚の場合、治し方のポイントはありますか? 男性がO脚になる原因は、筋肉のバランスの乱れや、ガニ股・内股にあるといわれています。 そのため、本記事で紹介した筋トレトレーニングの実践はO脚改善に効果があります。ガニ股・内股の改善に有効なのは、正しい歩き方を習慣化することです。正しい歩き方のポイントは、この後に紹介します。 寝ながらO脚を治す方法はありますか? 寝ながらできるストレッチでおすすめなのは「ブリッジ」です。 ブリッジは、お尻と背筋を鍛え、姿勢改善の効果があります。正しい姿勢は、O脚改善にもつながります。 ブリッジのやり方は以下のとおりです。 仰向けに寝る 両膝を立てる ゆっくりお尻を上げる 秒間キープする ゆっくりお尻を戻す これを10回ほど繰り返しましょう。 O脚を治すための歩き方が知りたい O脚を矯正する正しい歩き方は以下のとおりです。 背筋を伸ばす かかとから地面に足をつける つま先で蹴るようにして歩く 歩幅を広めにとる 日頃から正しい歩き方を意識すれば、O脚が少しずつ改善されていくでしょう。 O脚を治すための立ち方が知りたい O脚を治すための正しい立ち方は以下のとおりです。 背筋を伸ばす 重心を少し前に置く 小指・親指・かかとにバランス良く体重をかける O脚は脚の外側に体重がかかりやすい傾向にあります。バランス良く体重を乗せた立ち方を意識すれば、O脚改善の効果が期待できます。 O脚を治すための座り方が知りたい 以下は、O脚改善に効果が期待できる座り方です。 椅子に深く腰かけ背筋を伸ばす お尻を引き締める かかとをしっかりと床につける 両膝をくっつける 良い姿勢で座ると骨盤が正しい位置に戻ります。後傾気味だった骨盤が適正な位置に戻ると、膝が内側に向きやすくなるため、O脚の改善につながります。 >>公式LINE限定で再生医療のさらに詳しい情報を配信中!
2022.10.10 -
- ひざ関節
- 膝に赤みや腫れ
- 膝部、その他疾患
棚障害に悩んでいるが治し方がわからない。 棚障害を起こした場合、どのくらいで復帰できるの? 上記のようなお悩みをお持ちではないでしょうか? 本記事では、棚障害の治し方・治療法を中心に、原因や症状について詳しく解説していきます。 初期段階では症状が軽いからと放置してしまうと症状が悪化したり、手術が必要になって回復が難しくなったりする可能性があります。 「棚障害をできるだけ早く治したい」「手術はしたくない」という方は、再生医療による治療をご検討ください。 \棚障害の早期改善を目指す「再生医療」とは/ 再生医療は、患者さまの細胞や血液を用いて自然治癒力を向上させることで、損傷した組織の再生・修復を促す治療法です。 【こんな方は再生医療をご検討ください】 棚障害による痛みや膝の違和感を早く治したい 根本的に治療したいが、手術はできるだけ避けたい 膝の曲げ伸ばしで「パキッ」とした音が鳴る >>再生医療専門の「リペアセルクリニック」に無料相談する 当院リペアセルクリニックでは、棚障害に対する再生医療について無料カウンセリングを実施中のため、お気軽にご相談ください。 まずは棚障害の治療について無料相談! 膝棚障害(タナ障害)とは 棚障害(膝滑膜ひだ障害)は、膝の傷害で運動中に膝くずれを引き起こす病気で、膝の内側にある滑膜ひだに炎症を起こすことで発症します。 「症状が軽いから」と放置してしまう方もいるようですが、治療が手遅れになると重症になってしまい、痛みが強くなり、手術が必要な状態になってしまう病気です。 膝の病気、棚障害とはどんな病気なのか、原因と症状、その治療法について紹介していきます。 膝棚障害(タナ障害)の特徴 棚障害とは、『滑膜ひだ』という膝関節の内側にある『ひだ』に炎症が起きてしまう病気です。 滑膜とは、膝の動きを滑らかにする滑液という液体を作っている薄い膜です。滑膜に炎症が起きてしまうと、膝を滑らかに動かすことができなくなったり、膝を動かすと痛みを感じたりします。 最初の症状としては、膝のお皿と言われている部分である膝蓋骨の内側や下側に痛みを感じるのが特徴です。 徐々に『膝がぐらぐらする』といった、動かしにくさを自覚するようになり、痛みが出現し始めると動ける範囲内が制限されるようになるでしょう。 悪化すると数分歩行するだけで痛みが出現するようになり、歩行中や運動中、突然、膝くずれを起こしてしまうことも考えられます。 膝棚障害(タナ障害)の原因とは? 棚障害は、膝の曲げ伸ばしや、捻る動作の繰り返しによって「滑膜ひだ」が狭くなり、炎症を起こしてしまうことが原因で起こります。 大きな外傷がなくても、膝の曲げ伸ばしや、捻る動作を繰り返すことで、徐々に痛みが増すこともあります。 『棚障害』は、野球や、バレーボール、バスケットボール、ハンドボールなど膝の曲げ伸ばしを頻繁に繰り返し行う運動選手によくみられますが、運動習慣のある人は誰しも起こり得る病気です。 一般的な中高生の部活動で発症することも多くみられます。 膝棚障害(タナ障害)の治し方 棚障害(タナ障害)は軽症か重症かによって、治療法が異なります。 保存療法 手術療法 症状に合わせた治療やリハビリテーションを行い、再発を防ぎましょう。 保存療法 初期の棚障害(タナ障害)では、手術せずに症状改善・緩和を目指す保存療法による治療が中心です。 主に以下のような保存療法があります。 安静 物理療法 薬物療法 関節内注射 リハビリテーション 安静 棚障害の治療で一番大事なことは、運動を休み、膝の安静を保つことです。 多少の動かしにくさや痛みがありながらも「症状は一時的なものだ」「このくらいなら大丈夫だろう」と考えてしまうこともあるかもしれません。 しかし棚障害であるにもかかわらず運動を継続した結果、重症化してしまうケースもゼロではないため注意が必要です。 症状が重症化したあと稀ではありますが、手術も選択肢となり治療期間も長引くことになるため、違和感等を感じた際は、早めに医療機関や整形外科等を受診して専門家の判断を仰ぐべきです。 物理療法 物理療法:電気、超音波、レーザー、温熱を用いる 装具の使用:膝の装具を使用し動きを矯正する 非手術的療法で膝の筋力を増加させたり、膝の使い方を見直したりすることで、棚障害の治療を行います。 薬物療法 棚障害の症状が軽いときには、湿布を貼ったり、炎症を抑える薬を内服したりといった薬物療法を行うケースもあります。 棚障害は、運動をやめる又は、減らして安静を保ちつつ、ストレッチや湿布等での冷却をはかり、大腿四頭筋の筋力維持訓練など、膝への負担を減らせば症状は落ち着きはじめます。 現在現れている症状を、医師に十分に説明しましょう。 関節内注射 膝の関節内にヒアルロン酸を注射して関節の動きを良くしたり、ステロイド剤を注射して滑膜の炎症を抑えたりすることで痛みが引くこともあります。 関節内注射の効果は永続的ではないため、他の治療法と組み合わせて用いられます。 リハビリテーション 痛みや炎症を抑えたあとには、リハビリテーションを行い筋力をつけたり、バランスを整えたりすることで再発を防げます。 棚障害のリハビリテーションでは、運動療法やストレッチ、バランス訓練を行い、筋肉の増強や柔軟性の向上を目指します。 主には大腿四頭筋やハムストリングスを強くする筋力トレーニングや、片足立ち、スクワットなどを医師、理学療法士の指示に基づき行います。 棚障害が重症化した場合は運動を休止し、湿布や内服、注射などの治療を開始しても痛みがひかないことが多いです。また、痛みが一時的にひいても、運動を再開したときにすぐに痛みが再発してしまう可能性もあります。 手術療法 手術による治療が必要になった場合は、関節鏡手術という関節の内視鏡を用いる手術で「ひだ」の切除を行います。 入院期間は2日から1週間程度で行われることが多いですが、手術後の経過によって前後します。 また、手術が成功すればすぐに運動に復帰できるわけではなく、およそ2週間から数カ月のリハビリを覚悟しなければなりません。 さらには、リハビリを行った後でも、元々のパフォーマンスがすぐに発揮できるまでは、さらに時間を要することが多いです。 「棚障害をできるだけ早く治したい」「手術を避けて治療したい」という方は、近年注目されている「再生医療」による治療をご検討ください。 再生医療は、患者さまの細胞や血液を用いて、損傷した組織の再生・修復を促すことで早期改善を目指せる治療法です。 当院リペアセルクリニックでは、棚障害に対する再生医療について無料カウンセリングを実施中のため、お気軽にご相談ください。 >>再生医療専門の「リペアセルクリニック」に無料相談する 膝棚障害(タナ障害)についてよくある質問 棚障害(タナ障害)についてよくある質問と回答を紹介します。 棚障害と半月板損傷の違いは何ですか? 棚障害は冷やした方が症状が和らぎますか? 棚障害(タナ障害)の検査方法は? 棚障害(タナ障害)の予防やセルフケア方法は? 棚障害と半月板損傷の違いは何ですか? 棚障害と半月板損傷は、いずれも膝の痛みが起こる疾患ですが、原因となる部位が異なります。 棚障害は膝の内側にある「滑膜ひだ」と呼ばれる部位の炎症ですが、半月板損傷は、膝関節の内側と外側に一枚ずつある「半月板」と呼ばれる部位が炎症を起こすことで起こります。 棚障害は冷やした方が症状が和らぎますか? 棚障害には、冷却を含む「RICE処置」が効果的です。 RICE処置とは、応急処置のやり方の1つで、以下の頭文字をとったものです。 Rest(安静):なるべく動かさない Ice(冷却):痛みや熱を持っている部位を冷やす Compression(圧迫):適度に圧迫する Elevation(挙上):患部を心臓よりも高い位置に置く 強い痛みがあったり患部が熱を持っていたりする場合は、上記を試してみてください。 棚障害の検査方法は? 診察では、棚テストと呼ばれる検査が行われます。 この検査は、膝蓋骨内側の下の方を医師が親指で押さえた状態で、膝を曲げるものです。 このときに痛みを自覚するときや、医師が『ひっかかり』を感じるときに『棚障害』が疑われます。 さらに、レントゲン検査や、超音波検査、M R I検査といった画像検査を行い、滑膜の状態を評価して総合的に診断が行われます。 また、棚障害の簡易的な診断は自分でも可能です。 膝の曲げ伸ばしをすると、お皿の周りで引っ掛かりがみられ「ポキッ、ポキッ」といったクリックしたような音が聞こえたり、膝に手を当てると感じる場合は可能性が高いと思われます。 棚障害の予防やセルフケア方法 棚障害の予防には、膝に負担をかけすぎないことが大切です。 ウォーミングアップを行い、膝周辺の筋肉を温めてから運動をしましょう。 また日頃から膝関節付近の筋肉増強に努めたり、柔軟性を向上させたりするのも効果的です。とくに大腿筋を鍛えることで、バランスが安定し、棚障害が起こりにくくなります。 また、棚障害があっても試合や練習に参加しなければいけない場合には、テーピングで膝への負担を和らげるようにしましょう。 そして、動いたあとにはアイシングを行い、膝関節を休ませる必要もあります。 日頃から棚障害を起こさないよう気をつけること、また適切なセルフケアで重症化を防ぎましょう。 膝棚障害(タナ障害)を治すには症状に合わせて適切な治療を受けよう 「棚障害(滑膜ひだ障害)」は、運動選手によく起こる病気の一つで、滑膜の炎症が原因で起こります。 軽症であれば安静・薬物療法などの治療を行いますが、症状を我慢して運動を続けると、重症化して手術が必要になることもあります。 手術後は、リハビリを行う必要があり、すぐ運動に復帰することはできません。 膝の痛みや違和感を無視して運動を続けようとせず、早期に医療機関を受診して、適切な治療を受けることが重要です。 「棚障害をできるだけ早く治したい」「手術はしたくない」という方は、再生医療による治療を検討してみましょう。 \棚障害の早期改善を目指す「再生医療」とは/ 再生医療は、患者さまの細胞や血液を用いて自然治癒力を向上させることで、損傷した組織の再生・修復を促す治療法です。 【こんな方は再生医療をご検討ください】 棚障害による痛みや膝の違和感を早く治したい 根本的に治療したいが、手術はできるだけ避けたい 膝の曲げ伸ばしで「パキッ」とした音が鳴る >>再生医療専門の「リペアセルクリニック」に無料相談する 当院リペアセルクリニックでは、棚障害に対する再生医療について無料カウンセリングを実施中のため、お気軽にご相談ください。 まずは棚障害の治療について無料相談! また、スポーツによって膝の痛みを起こす慢性障害については、以下の記事もご覧ください。
2022.07.08 -
- ひざ関節
- 膝部、その他疾患
この記事にたどり着いたあなたは「特発性膝骨壊死は治るの?」「骨が壊死するなんて怖い」と不安になっているのではないでしょうか。 特発性膝骨壊死(とくはつせいひざこつえし)は、原因不明の膝の疾患です。動かしているときだけでなく、じっとしているときや夜間の急激な膝の痛みが特徴です。 軽度であれば完治する可能性もありますが、重症化すると手術が必要になるケースもあります。早期発見・早期治療が重要です。 本記事では特発性膝骨壊死の特徴や治療法について詳しく解説します。特発性膝骨壊死と診断された方や今後の経過が気になる人はぜひ最後までチェックしてください。 特発性膝骨壊死とは|起こるとどうなる? 特発性膝骨壊死とは「大腿骨内顆骨壊死(だいたいこつないかこつえし)」と呼ばれ、太ももの骨に起こる骨壊死です。60歳以降の中高年女性に多く、歩行時痛や階段の昇り降りなどでの痛みを生じます。 特発性膝骨壊死の特徴は、動かしていないときや夜間にも激痛を感じることです。座っているだけで激痛に襲われたり、夜間の痛みで寝れなくなったりなど日常生活に支障をきたす可能性があります。 また、骨壊死部分は骨が脆くなっているため、体重をかけるなどの負担によって骨が変形していく可能性があります。放置すると変形性膝関節症を合併する危険があり、注意が必要です。 特発性膝関節壊死は、軽度であれば完治する可能性があります。変形が進むと手術の必要性が高まるため、変形が進む前の治療が大切です。 軽度なら自然治癒する可能性がある 特発性膝骨壊死は、軽度であれば自然治癒する可能性があります。特発性膝骨壊死には「ステージ1(発生期)」「ステージ2(吸収期)」「ステージ3(完成期)」「ステージ4(変性期)」と4つの分類があります。過去の研究結果では、ステージ1の患者に対しては保存療法によって骨壊死が消失する結果が得られました。(文献1) このように軽度であれば壊死部が治癒することがありますが、ステージ4になると軟骨が削れて関節の隙間も狭く変形します。重度の変形では自然治癒しないため、変形性膝関節症と同様に手術の検討が必要です。(文献2) なお、骨壊死については以下の記事でも詳しく解説しています。特発性膝骨壊死への理解も深まる内容なので、気になる人はぜひこちらもチェックしてみてください。 特発性膝骨壊死と変形性膝関節症は症状が似ている 特発性膝骨壊死と変形性膝関節症はどちらも膝の痛みを感じ、進行すると膝の変形が進むという点で似ている病気です。 変形性膝関節症が「動かしたときの痛みや動き出しなどで鈍い痛み」を感じるのに対して、特発性膝骨壊死は「動いていないときや夜間の鋭い痛み」を感じるのが特徴です。 どちらもレントゲン画像で診断できますが、初期ではほとんど判別がつきにくい傾向があります。そのため、特発性膝骨壊死が疑われる場合にはMRI検査を行うことも多いです。 とくに特発性膝骨壊死を放置して骨壊死しているところに負担がかかり続けると、急速に変形性膝関節症に移行するといわれています。(文献2) じっとしているときや夜間の激痛がある場合には、できるだけ整形外科を受診するようにして対処しましょう。 突発性膝骨壊死の原因は明らかになっていない 特発性膝骨壊死を発症する明確な原因はわかっていませんが、以下のような説が考えられています。 高用量のステロイドの長期間服用 腎移植 過度の飲酒 血液凝固障害 度重なる放射線治療 膝のクッションである半月板の損傷(文献3) 過去の小さな骨折(文献4) しかし、はっきりとした原因はわかっていないのが実情です。 特発性膝骨壊死の治療法 特発性膝骨壊死の治療は、変形性膝関節症と同様「保存療法」「手術療法」といった治療を行うのが一般的です。 保存療法 ステージが初期のころは消炎鎮痛剤(痛み止め)やヒアルロン酸注射などの保存療法が主流です。 これらの治療で痛みをコントロールしつつ、運動療法を中心としたリハビリで筋肉を鍛えて骨壊死部への負担軽減を目指します。 また、膝への負担を軽減する方法として装具の利用も重要です。 外反装具(膝を外に曲げる装具)や足底装具(インソール)、T字杖や松葉づえを用いることで、膝の負担軽減を図る場合もあります。 手術療法 保存療法で痛みの軽減が得られない場合、手術療法を検討します。 主な術式は、壊死部を関節鏡で除去したうえでプレート固定する「高位脛骨骨切り術」と、膝関節を人工物に取り替える「人工関節置換術」です。 軟骨や靭帯の損傷が限局的で、膝関節の他の部分が比較的健全に保たれている場合は、関節機能を温存できる「高位脛骨骨切り術」を検討します。 75歳以上の高齢者に「高位脛骨骨切り術」を実施した結果、術後の痛みは軽減され変形も進みにくいなど良い結果が多く得られたという研究もあります。(文献5) 一方、特発性膝骨壊死が進行し、関節の変形が大きい場合には「人工関節置換術」を行うのが一般的です。 人工関節については以下の記事でも解説しています。気になる方は合わせてご覧ください。 再生医療という選択肢もある 保存療法を試しているが改善しない、手術には抵抗があるといった方は、再生医療という選択肢も検討してみましょう。 再生医療は人工関節に変わる治療方法として選択肢となる治療法の一つです。 膝関節に幹細胞を注入することで、膝の痛みの軽減が期待されています。当院リペアセルクリニックでも、再生医療を実施しています。 もし特発性膝骨壊死の治療で再生医療に興味があれば、メール相談もしくはオンラインカウンセリングからお気軽にご相談ください。 なお、当院で実施している再生医療については以下の記事で詳しく解説しています。再生医療についての知識が深まる内容なので、ぜひこちらもご覧ください。 特発性膝骨壊死を悪化させないためのポイント 特発性膝骨壊死の進行を抑えるために重要なポイントは以下の3つです。 適切な日常生活を心がける 膝に負担をかけすぎない 早めに受診して診断を受ける 特発性膝骨壊死と診断された人は、日常生活で本章の内容を意識してみましょう。 適切な日常生活を心がける 特発性膝骨壊死の進行を抑えるには、過度な飲酒や喫煙を避け、規則正しい生活を心がけることが大切です。 喫煙者や肥満者は、特発性膝骨壊死に悪影響を及ぼすと報告されています。(文献4) 膝の痛みに悩んでいる方は可能であれば禁煙し、栄養バランスの整った食生活や適度な運動を心がけましょう。 膝に負担をかけすぎない 肥満や激しい運動は膝へ大きな負担がかかり、特発性膝骨壊死を悪化させる原因になる可能性があります。 また、太ももの前にある大腿四頭筋(だいたいしとうきん)は体重を乗せたときなどに衝撃を受け止めるクッションの役割をしています。 膝の負担を軽減させるためには、痛みのない範囲での筋トレを行い、大腿四頭筋を鍛えるのもおすすめです。 早めに受診して診断を受ける 特発性膝骨壊死は進行性の病気です。膝の痛みが長引く場合は、可能な限り早く受診することが大切です。 痛みや症状が変形性膝関節症と似ており、自己判断は難しいでしょう。整形外科での診察や検査を受けることで、早期に適切な治療を開始できます。 安静時や夜間の急激な鋭い痛みを感じるなど特発性膝骨壊死が疑われる特徴的な症状がある場合、早めに整形外科に相談しましょう。 まとめ|特発性膝骨壊死は激しい痛みが特徴!悪化させないためにも早めの受診がおすすめ 特発性膝骨壊死は安静時や夜間の激しい痛みが特徴の病気です。放置しておくと症状が進行し、変形性膝関節症に移行してしまう可能性があります。 悪化を防ぐためにも、早めに受診の上、適切な治療を受けましょう。 なお、当院リペアセルクリニックでおこなっている再生医療は、特発性膝骨壊死に対する治療選択肢の一つとして再生医療を提供しています。 膝の痛みにお悩みの方や、手術以外の治療法を検討している方は、お気軽にメール相談もしくはオンラインカウンセリングからご相談ください。 特発性膝骨壊死についてよくある質問 特発性膝骨壊死は自然治癒しますか? 軽度なら自然治癒する可能性があります。 特発性膝骨壊死が軽度の状態であれば骨の壊死範囲も小さいため、改善する可能性があります。しかし軽度の状態ではレントゲンでは映らないため、MRI検査を受けないとわかりません。特発性膝骨壊死が疑われたらできるだけ早くMRIがある整形外科を受診してください。 特発性膝骨壊死を悪化させないためにはどうすれば良いですか? 規則正しい生活習慣を心がけましょう。 特発性膝骨壊死は喫煙や肥満によって悪化する可能性があるため、生活習慣を整えることが大切です。また、適度な運動によって太ももの筋肉を鍛えれば、膝にかかる負担を軽減でき症状の悪化予防につながるでしょう。 参考文献 (文献1) 安原良典「保存療法による早期膝関節特発性骨壊死の検討|日関病誌(33巻,1号)」 https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsjd/33/1/33_13/_pdf/-char/ja (文献2) 牛島貴宏「特発性膝骨壊死に対する高位脛骨骨切り術後のX線学的評価と関節軟骨変化|整形外科と災害外科(59巻,4号)」 https://www.jstage.jst.go.jp/article/nishiseisai/59/4/59_4_675/_pdf/-char/ja (文献3) Yamamoto Takuaki ほか「Spontaneous Osteonecrosis of the Knee: The Result of Subchondral Insufficiency Fracture|The Journal of Bone & Joint Surgery 82 (6)」 https://journals.lww.com/jbjsjournal/Abstract/2000/06000/Spontaneous_Osteonecrosis_of_the_Knee__The_Result.13.aspx (文献4) Santiago Pache ほか「Meniscal Root Tears: Current Concepts Review|Arch Bone Jt Surg」 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30175171/ (文献5) 小無田航 ほか「75歳以上の特発性膝骨壊死に対する高位脛骨骨切り術後の関節鏡評価と臨床成績|整形外科と災害外科(72巻,3号)」 https://www.jstage.jst.go.jp/article/nishiseisai/72/3/72_368/_pdf/-char/ja
2022.07.07 -
- ひざ関節
- 膝部、その他疾患
膝の傷病であるベーカー嚢腫は世間的にあまり周知されていない疾病です。しかし、ベーカー嚢腫は誰でも起こる可能性があり、治療が遅れると重症になりえます。 日常生活の中で『膝に違和感を感じる』といった経験をされたことはありませんか?膝の違和感と一口に言っても症状はさまざまですが、もしかするとベーカー嚢腫かもしれません。 そこで本記事では、ベーカー嚢腫について当クリニック医師が詳しく解説します。症状を理解し、早期発見・治療を心がけましょう。 ベーカー嚢腫とは?原因はなに? ベーカー嚢腫は、膝の関節の隙間の裏側に袋ができて、その中に滑液と呼ばれる膝の動きを滑らかにしている液体が溜ることで起こります。 症状が起きる原因は、激しい運動などで膝を使いすぎたり、関節リウマチや変形性関節症といった病気が誘引となって滑液が大量に作られ溜ることでベーカー嚢腫を発症します。 ベーカー嚢腫の症状 ベーカー嚢腫は、発症初期に痛みがないといった特徴をもっています。 最初は膝の裏が腫れたり曲げたときに、なんとなく違和感や不快感を感じる程度であることが大半です。この初期段階で腫れが小さくなり、自然治癒するケースも少なくありません。 しかし、痛みがないからといって自己判断の放置には注意が必要です。 膝の裏の腫れがニワトリの卵くらい大きくなると、膝を曲げるときや、正座をしようとしたときに引っかかるような感じがして姿勢を保てなくなります。 さらに悪化すると滑液を包んでいる袋が破裂し、滑液が漏れ出てきて周りの組織が炎症を起こしてしまいます。すると、膝の腫れがさらにひどくなり、腫れに対して熱や痛みを発します。 ベーカー嚢腫の好発年齢 ベーカー嚢腫は、関節リウマチや変形性関節症が起こりやすい50代~70代に多い疾病です。だからといって、若い方が発症しないと安心できるものではありません。 年齢関係なく誰でも起こりうる疾病とされ、ときには4歳~7歳くらいの子どもでも発症します。 ベーカー嚢腫の検査方法 診察では、変形性関節症や関節リウマチなどの病気が合併していないか調べることが重要です。 医師による触診や超音波検査・MRI検査などの精密な画像検査を行い、大きさや正確な発症位置を特定します。 【治し方】ベーカー嚢腫の治療 ベーカー嚢腫の治療方法は、合併している疾患の有無や重症度によって大きく変わってきます。 関節リウマチや変形性関節症などが合併している疾患があるときは、合併疾患に対して治療を行うことがベーカー嚢腫の改善にもつながります。合併している病気の治療が進まないとベーカー嚢腫を含め再発を繰り返してしまいます。 合併している病気の症状が落ち着いているときや、合併疾患がないときは、手術を伴わない治療で完結するケースが大半です。 保存療法 手術を行わない際の治療としては、湿布を貼ったり炎症を抑える薬を内服します。 また、袋の中に滑液がたくさんたまっているときは、注射器により滑液の吸引を行います。吸引を繰り返してもベーカー嚢腫が頻回してしまう際や、周囲の組織に炎症を伴うときはステロイド剤の注射を行うケースがあります。 手術療法 手術を行う場合は、膝の裏を2cm程度切り開いて行います。ベーカー嚢腫の元となる袋を取り出したり、関節から嚢腫へ滑液が漏れ出している穴を塞いだりと療法はさまざまですが、いずれの手術も全身麻酔で行われます。 術後の感染や麻酔によるアレルギー症状など、副作用の確認を行うため入院による治療となります。1~2週間の入院期間を設けることが多いですが、合併症の有無など、術後の経過によって前後します。 膝の裏には神経や血管がたくさんあり、すべての袋の除去が難しいことから、術後再びベーカー嚢腫ができてしまうケースも少なくありません。 ベーカー嚢腫に関するQ &A この項目では、ベーカー嚢腫に関するよくある質問に対しての答えを提示しています。 ベーカー嚢腫にお悩みの方は問題解決の参考にしてください。 ベーカー嚢腫は何科を受診すればいいの? ベーカー嚢腫の疑いがある場合は、整形外科を受診しましょう。お住まいの地域に整形外科院がない場合は、総合病院の受診をおすすめします。 また、当クリニックでも足の疾病に関する悩み相談は可能です。手術をしない再生医療に興味がある方は、お気軽にお問い合わせください。 ベーカー嚢腫に効くストレッチは? ベーカー嚢腫には、膝周りの筋肉を伸ばすストレッチが効果的です。 ストレッチの種類は多岐にわたりますが、この項目では代表的なふくらはぎのストレッチを紹介します。 仰向けになり片方の足を上げます 上げた足にタオルをかけます 両手でタオルの端を持ちながら、足を伸ばした状態で45度程度まで下に引きます 呼吸を止めずに10秒程キープします 反対側の足も同様にストレッチします ベーカー嚢腫とがんの見分け方は? ベーカー嚢腫とがんを見分けるためにも、まずはお互いの特徴を把握しておきましょう。 ベーカー嚢腫 悪性腫瘍(軟部肉腫/骨腫) 膝をの裏側が腫れる 普段から膝を使っている 次第に腫れが大きくなる 初期は痛みを感じないが、悪化すると痛みや熱を発する 膝の怪我・負担をかけていなくても発症する 長期にわたる腫れの継続 しびれや麻痺を伴う 痛みを伴わないことも多い 初期の段階では、いずれも痛みを感じることなく発症するケースが大半です。しかし、ベーカー嚢腫の場合は関節の隙間にできた袋から滑液が漏れ出し、炎症をきたし痛みや熱を発します。 対して悪性腫瘍(軟部肉腫)の場合はしびれや麻痺症状を伴うことを覚えておきましょう。 いずれにせよ、一般的に区別がつきづらい症状であることから、膝の不安感を覚えたら最寄りの医療機関を受診するよう心がけましょう。 まとめ|ベーカー嚢腫(膝裏の腫れ)の放置は禁物! 発症初期のベーカー嚢腫は、痛みを伴わず自然に小さくなる傾向にあるため放置してしまいがちな病気です。しかし、悪化すると、手術が必要になることもあります。 手術には入院が伴うため誰しもが望まない治療だと思います。最近では感染対策で入院中での面会が制限され、家族や友人に会えずに寂しく辛い経験をされる方も非常に多いです。 治療が手遅れになる前に、膝の裏に違和感を感じたら自分で判断したり、放置せずに医療機関に受診し、専門家に診てもらいましょう。
2022.07.06 -
- ひざ関節
- 膝部、その他疾患
ちょっと立ったり座ったりするにも不自由する膝の痛み、嫌なものですね。膝の痛みに悩む方の中には、膝に水が溜まっている方も多くいらっしゃいます。 「水を抜く治療を勧められたけれど、抜いて大丈夫?」 「抜いたらどんな注意が必要なの?」 「水を抜かない治療方法はないの?」 と気になる方もいるのではないでしょうか。 この記事では、膝に溜まった水を抜いたあとの注意点について医師が解説します。 また、水を抜かない治療法についてもお伝えするので参考にしてください。 なお、本記事では一般的な注意点について解説しています。個別の事象については各自で判断せず、医療機関に相談するようにしましょう。 膝の水を抜いた後の注意点 膝の痛みで医療機関を受診した際に膝の水を抜くことがあります。この診療行為を、医療用語で「関節穿刺」といいます。関節穿刺により、膝の痛みや突っ張り感の改善が期待できます。 一方で、関節穿刺を行っても水が溜まる原因はなくなりません。関節穿刺は根本的な治療にはならないことは、知っておきたい注意点の一つです。 また、関節穿刺によって別の症状や病気、つまり合併症が起きる可能性もあります。関節穿刺後の注意点について解説します。 膝の痛みの根本的な治療にはならない 膝が痛み、水が溜まるのにはなんらかの原因があります。 たとえば変形性膝関節症では、関節の軟骨がすり減ることで痛みが起きたり、炎症が起きて水が溜まったりします。水を抜くだけでは原因が残ったままのため、再度溜まってしまうかもしれません。根本的に解決するには、筋力をつけて膝を安定させたり、重度なら手術を検討したりといった対策が必要です。 他の病気でも同様に、原因が残っていれば痛みが消えない場合や、再び水が溜まる場合もあります。 感染症のリスクが上がる 通常、関節内は無菌状態が維持されています。しかし、関節穿刺によって体の表面にいた細菌が関節内に入ってしまうことがあります。細菌が関節内に移行し感染を起こすと、膝が赤く腫れたり、熱を持ったり、痛みを伴うことがあります。 通常、関節穿刺の後数時間は穿刺による痛みが生じることがありますが、痛みが長引く場合は感染の可能性があります。一般的な目安としては48時間以上持続する症状、48時間以内でも悪化を伴う症状を認めた場合には感染などの可能性を考慮し、可能な限り処置を行った医療機関に相談することをお勧めします。 出血する可能性がある 関節穿刺の際に関節周囲の血管を傷つけてしまい出血を起こすことがあります。多くの場合は細い血管の損傷にとどまるため、自然に止まることがほとんどです。仮に穿刺後に貼付していたテープなどを剥がした際に出血が起きても、綺麗なガーゼなどでしばらく圧迫すれば止血されることが多いです。 しかし、他の持病などで血液をサラサラにする薬を飲まれている方やもともと血が固まりにくい病気の方、あるいは太い血管を損傷してしまった場合などは自然に止血されないこともあります。圧迫しても止まらない出血の際には速やかに処置を行った医療機関に相談することをお勧めします。 薬剤の影響でアレルギー反応が見られる 関節内に薬剤を注射した場合などには、薬剤による合併症が起きる場合もあります。たとえば、アレルギー反応は通常原因となる薬剤などの物質を投与されてから数時間以内に、発疹・呼吸困難感・腹痛などの多彩な症状を生じる合併症です。 多くの場合は投与後すぐに発症するため医療機関で発見される場合がほとんどですが、まれに帰宅後に発症することもあります。帰宅後に症状が現れた場合は、速やかに処置を行った医療機関へ相談してください。 まれに神経や靭帯を傷つける 血管以外の神経、靭帯、腱などの損傷もまれな合併症の例です。穿刺のみでこれらの組織に重大な損傷をきたすことはまれですが、薬剤注入などを伴うと症状をきたす可能性があります。 神経が損傷すると、強い痛みやしびれ、電気が走るような痛みなどを伴います。靭帯や腱が損傷すると、関節が不安定になったり、痛みが持続したりする可能性があります。異常を感じたときは、処置を行った医療機関に相談することをお勧めします。 膝の水を抜いた後の安静期間 膝の水を抜いた後の安静期間は明確な決まりはありませんが、膝の痛みが消えるまでは安静にすることが大切です。 膝の痛みがない場合は通常の生活を送って問題なく、積極的な運動療法も可能です。 膝の水を抜くことで関節が動きやすくなり、運動もしやすくなると期待できます。 安静にしすぎると、かえって膝が動きにくくなることもあるため、無理のない範囲で動かしましょう。 そもそも膝の水がたまる原因とは? 膝の関節の中には、関節がスムーズに動くための潤滑油のような役割を果たす「関節液」が存在します。この関節液は健常者においても常に作られながら吸収され、一定の量になるように調整されています。 ところが疾患やケガが原因となって、関節液が作られるスピードが吸収されるスピードを超えてしまうことがあります。すると「膝に水が溜まる」という症状が起きるのです。 変形性膝関節症 変形性膝関節症では、膝の軟骨がすり減ることで痛みが出て、水が溜まってしまいます。関節軟骨の老化によって起きることが多く、性別では女性に多い病気です。膝の外傷や感染症の後に発症することもあります。 変形性膝関節症の初期症状は、膝がこわばる、曲げ伸ばしの際に引っ掛かりを感じる、歩き始めに痛みがあるといったものです。早い段階で発見できれば、後述する運動療法などで悪化を防げる可能性があります。 半月板損傷・靭帯の損傷 スポーツや交通事故などで膝に強い衝撃が加わると、半月板や靭帯を損傷することがあります。これにより膝の内部で炎症が起きると、関節液の分泌が増加して水が溜まります。関節内で出血が起きれば血液が溜まることもあります。 増加した関節液は、損傷部位を守ったり、修復に必要な栄養素を運んだりといった役目を持つと考えられるため、悪いものとは言い切れません。しかし多すぎたり長期化したりすると、慢性的な痛みや関節の機能低下といった問題を引き起こします。 関節リウマチ・痛風 関節リウマチは、関節内部に慢性の炎症が起きる病気です。症状は手や足の指に出やすいですが、膝関節にも現れることがあり、水が溜まると動かしにくくなります。30〜40代の女性に多く発症し、原因は免疫システムの異常と考えられています。 痛風で炎症が起きる原因は、血液中の尿酸値が上昇し、関節内に尿酸炎の結晶ができることです。親指の付け根が痛む発作がよく知られていますが、膝関節でも発作が起きたり、水が溜まったりすることがあります。生活習慣が原因となるほか、腎機能や薬剤が原因のケースもあります。 抜いた水の色で予測される病気 正常な関節液はやや黄色がかった透明で、わずかな粘り気があります。しかし病気やけがになると、以下のように特徴的な色の変化が見られます。 水の色 予測される病気 濃いめの黄色 変形性膝関節症 赤色・褐色 半月板損傷、靭帯の損傷など 白濁 関節リウマチ、痛風など 変形性膝関節症の場合は、関節液の色がやや濃く、粘り気は少なくなります。赤や褐色の関節液は、けがによる内出血が原因のケースが多いです。混濁が見られる場合は、関節リウマチや痛風のほか、感染症の可能性もあります。 このように、関節液の色から病気を推測することで、適切な治療につながります。 膝の水を抜かない治療法 症状が軽度なら、関節穿刺以外の治療も選択肢です。ここでは運動療法と温熱療法を紹介します。どちらも膝の状態を評価した上で、適切な方法で行うのが大切です。 運動療法 運動療法では、膝周りの筋肉の強化や関節可動域の改善、鎮痛効果などが期待できます。体重のコントロールや全身の健康状態を維持する効果も期待でき、とくに変形性膝関節症では積極的に勧められる方法です。 運動の種類は、筋力トレーニングやエアロビクス、太極拳、ヨガ、水中での運動など多岐にわたります。継続すれば徐々に筋力がつき、膝が安定するでしょう。 膝に負担がかかりすぎないように、運動の種類や量、時間について医師や理学療法士と相談しながら行ってください。 物理療法(温熱) 変形性膝関節症や関節リウマチでは、温熱療法も効果的です。膝を温めることで、筋肉の緊張が和らいで動きやすくなったり、血流が増えて代謝が促進されたりといった効果が期待できます。冷えていると痛みを感じやすいため、温めることで鎮痛効果も期待できます。 温める方法としては、超音波を照射して関節の内側から温める超音波療法や、ホットパックを当てて表面から温める方法など、いくつかの方法があります。適切な温度に設定することで、軟骨成分の合成が促進されるとも考えられています。 まとめ|膝の水を抜いた後の注意点を正しく理解しよう 今回の記事では膝に溜まった水を抜いたあとの注意点について解説しました。 水を抜いた後には、感染症や出血をはじめとする合併症が起きる可能性があります。一般的には、関節穿刺により生じた痛みなどの症状は、数時間から1日程度で消失します。これ以上持続する場合や、処置から時間が経っていなくてもどんどん悪化する場合は、速やかに処置を行った医療機関に相談しましょう。時間外などで相談できない場合は夜間救急などの受診を検討しましょう。 また、水を抜くだけでは根本的な治療にはならず、再び痛みが出たり水が溜まったりすることがある点にも注意が必要です。当院では膝の軟骨を再生させる幹細胞治療を行っており、痛みの原因に対する治療が可能です。膝の痛みでお悩みの方は、ぜひ当院にご相談ください。
2022.06.10