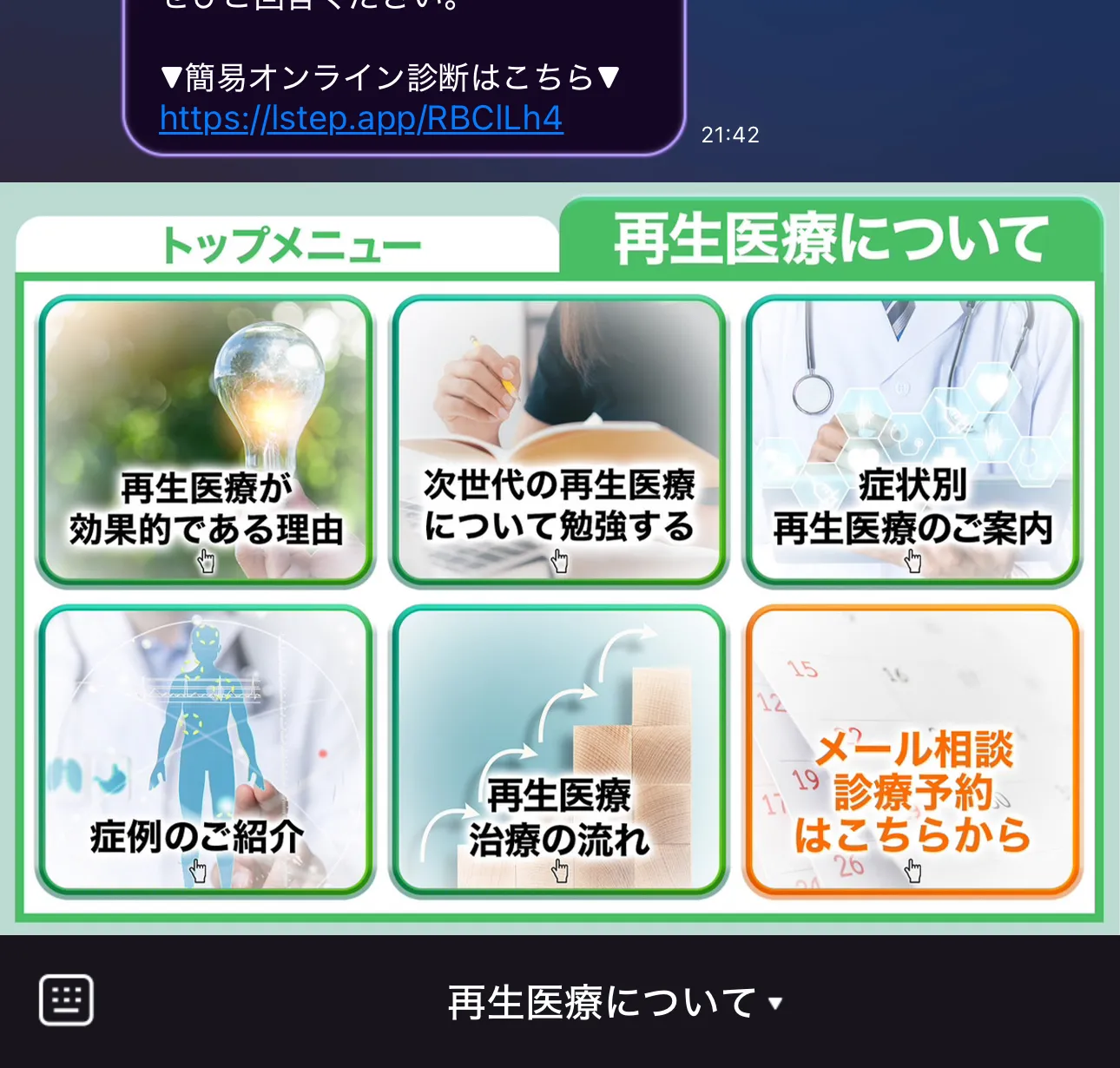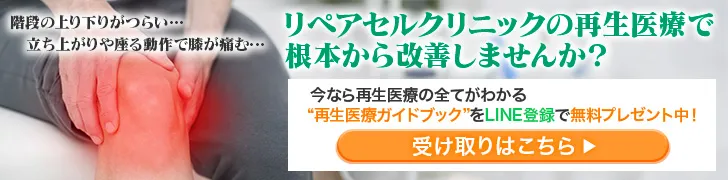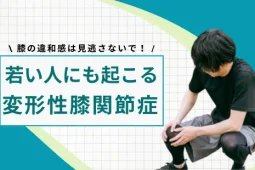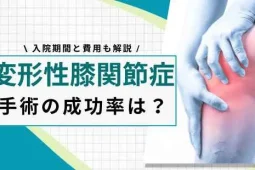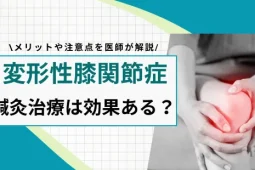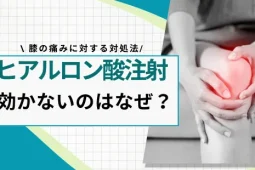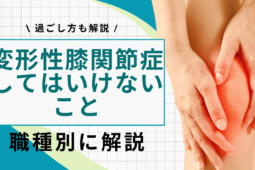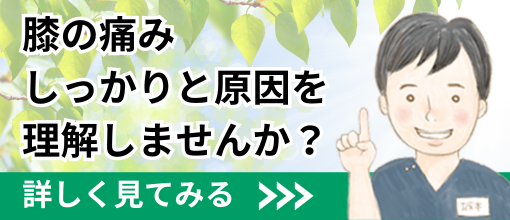- 変形性膝関節症
- 幹細胞治療
- 再生治療
- ひざ関節
変形性膝関節症の最新治療|ヒアルロン酸、ステロイドでは不可能な軟骨を再生させる治療方法とは

目次
変形性膝関節症でヒアルロン酸、ステロイドでは不可能な軟骨を再生させる再生医療をご紹介
「変形性膝関節症」の治療でヒアルロン酸を注射をしているけど「思ったような結果が得られず困っている・・・」、「ステロイド注射は副作用が怖いと聞いたが・・・」こんなお悩みはありませんか?
変形性膝関節症の炎症や痛みに対する治療と言えば、ヒアルロン酸や、ステロイドを関節内に注射することが多々ありますが、実のところ、これらの注射は一時しのぎで根本的な治療にはなりません。
これらヒアルロン酸や、ステロイドなどの注射による治療では症状を改善させたり、症状の進行を止めることが難しく、最終的に人工関節などの手術に頼ることになりかねません。つまり、これらの治療では根本的な治療にはならないということです。
なぜなら、ヒアルロン酸注射やステロイドは、一時的に痛みを緩和することはできるのですが、痛みの根本原因となっている傷んだ軟骨を再生させる力は無いからです。
しかし、医療の発展で「再生医療」という新たな選択肢が現れました。
再生医療は、手術はもちろん、入院までもが不要という、これまでの常識を覆した最新の治療法として厚生労働省が許認可し、中でも「幹細胞治療」は、変形性膝関節症で軟骨を再生する可能性を持った治療法として非常に期待が持てます。
|
そこで今回は、再生医療の中でも「幹細胞」を培養して注射で投与でき、軟骨を再生させる!「変形性膝関節症の最新治療法」をご紹介します。
まずは、これまで変形性膝関節症の治療に使われてきた、「ヒアルロン酸注射」、「ステロイド注射」をについてご説明し、最新の再生医療での治療法である再生医療、中でも「PRP療法」「自己脂肪由来・幹細胞治療」をご紹介してまいりましょう。合わせて以下の動画もご参照ください
従来の治療法①|膝関節へのヒアルロン酸注射について
さて、膝関節へのヒアルロン酸や、ステロイドの注射は、関節の潤滑性を高めたり、炎症や痛みを抑える目的で使われるものです。関節内にある関節液は、関節軟骨を保護し、膝の動きを滑らかにサポートする潤滑油の役割を果たしています。
そんな関節液の潤滑成分としてヒアルロン酸が含まれていることから、変形性関節症で枯渇したサラサラの関節液に対して、ヒアルロン酸を関節内へ注射することで潤滑性を高めることで膝の動きをサポートさせます。
今、まさに治療を行われている方なら、お分かりかもしれませんが慣れてくると注射後2〜3日、中には1日ほどで、また痛みに悩まされることも少なくないのです。
ヒアルロン酸注射の頻度・回数は、ヒアルロン酸に含まれる分子量により異なります。この分子量が高いほど関節内で長時間留まるとされています。ただ、実際に痛みを回避するには週に1回から、いずれは3回~注射することになりかねません。
| ご注意)ヒアルロン酸を注射で痛みの原因である「軟骨が再生されることはありません」 |
膝に水が溜る!とは
膝に炎症が起こり、水が溜まることがあります。これを「関節水腫」といい、膝に水が溜っていたらヒアルロン酸注射の前にこの水を抜いてやる必要があります。
なぜなら膝に水が溜まった状態でヒアルロン酸注射をしたところで、溜った水によってヒアルロン酸の濃度が薄められ、効果が半減されてしまうからです。更に、溜まった関節液には、炎症を悪化させてしまうサイトカインという物質も含まれています。
また稀にヒアルロン酸にアレルギー反応を起こす場合もあるため、万人が受けられるわけでもありません。
膝への「ヒアルロン酸注射」 |
||
| 効果 | 問題 | 注意事項 |
|
|
・水が溜る「関節水腫」になる危険性 |
従来の治療法②|「ステロイド注射」痛みは消えるが注意が必要
痛みや炎症が強い時は、ステロイド薬を関節内へ注射します。ステロイド注射はヒアルロン酸注射と比べ、痛みを抑えるのに非常に高い効果を発揮するとの報告が多くあります。
ただし、注意しておきたいのは、ステロイド注射を多用すると副作用があること。それは骨や、軟骨の新陳代謝をステロイドが阻害したことによって起こる可能性のある「骨壊死」、関節が破壊される「ステロイド関節症」というもので注意が必要です。
注意)ステロイド注射の多用による副作用に注意
▼「骨壊死」「ステロイド関節症」を防ぐために
- 最低でも6週間置いての注射とする。
- できれば3ヶ月ほどは、間隔を空けるべきであること。
- 短期での連続した注射や長期間に及ぶ使用は避けるべき。
- 知識として知っていて欲しい。
繰り返しになりますがステロイド注射による痛みの改善は一過性であり、変形性膝関節症の痛みの起因となる、すり減った軟骨が元に戻るわけではありません。痛いからと、使い方を誤ると副作用という大きな危険性があります。
ここまでヒアルロン酸や、ステロイドとしった痛みを抑える目的で使われる注射を紹介しました。
次に自分の血液や細胞を使うことで「アレルギー反応が起こりにくい」「軟骨の再生を期待できる」最新の注射による治療方法を紹介します。
膝への「ステロイド注射」 |
||
| 効果 | 副作用 | 副作用を抑えるための注意事項 |
|
|
|
|
膝の痛みを消すだけ、変形性膝関節症の痛みの起因となる、すり減った軟骨が元に戻るわけではない |
||
最新|変形性膝関節症の再生医療
再生医療
- PRP治療
- 幹細胞治療
1)PRP治療(Platelet-Rich Plasma=多血小板血漿)
PRP療法とは、患者様の血液を採取し、血液中に含まれる血小板の多い血漿だけを抽出し、膝へ注射する治療法です。多血小板血漿には、組織や細胞の成長を促す成長因子が多く含まれています。
そのため、高い治癒効果が期待できる方法といえます。またヒアルロン酸と違い、自分の血液を使用することでアレルギー反応が出にくいのも特徴です。PRP療法は、近年耳にする機会が増えた「再生医療」に分類される治療法です。
まだ日本では保険が適応されない自由診療となるため、ヒアルロン酸注射やステロイド注射のように気軽に打てる金額ではない点がデメリットになります。
また再生医療を扱うには「再生医療等の安全性確保等に関する法律」に基づき、厚生労働省に届出し、受理された医療機関、専門医にしかできない治療法になっているため、近所の整形外科で簡単にできるわけではありません。
ただ、そのため、安全性が確保されている治療法とも申せます。
2)幹細胞治療
「軟骨の再生」を期待!自己脂肪由来
主に皮下脂肪にある幹細胞組織を使い、軟骨をはじめとして、さまざまな組織に再生させる機能を持つ、可能性に満ちた治療法です。
幹細胞は、軟骨や皮膚、骨などに分化(複雑なものに発展していくこと)する機能があります。体から採取した幹細胞を培養(増やす)して膝の関節内へ注射することで、傷んだ軟骨の再生を期待することができ、これまでになかった治療法になります。
幹細胞は骨髄からも採取することはできますが、より侵襲が少ない皮下脂肪から採取されるのが一般的です。それでは同じ再生医療の分野であるPRP治療と幹細胞治療とは何が、どう違うのでしょうか?
PRP治療は、傷んだ組織に対して組織や、細胞の成長を促す栄養素が含まれている「多血小板血漿」を注射します。もともと血小板の役割に成長因子の分泌がありますが、「多血小板血漿」には通常の血小板と比べて3〜5倍もの成長因子があることが特徴です。
これにより、ヒアルロン酸注射にはできなかった慢性化した患部の修復や、治癒を高めることができます。その一方でPRPには幹細胞が含まれていないため、軟骨を再生することはできません。
幹細胞治療では、さまざまな組織に分化(変化)する働きをもつ幹細胞を、何千〜何百万倍にも培養し、膝に注射します。この幹細胞が集中的にすり減った軟骨に働きかけることで、これまで不可能とされてきた「軟骨を再生」させます。
そのため、注射する幹細胞の数にも注目すべきです。海外の臨床データによると幹細胞の数が多いほど治療成績が良いことがわかっているからです。
なぜなら培養せず注射する治療法をADRC(脂肪組織由来再生幹細胞治療)セルーションと言うのですが、培養を行わないため幹細胞の数自体が少ないことになるからです。
その意味で治療を受ける際は、受診するクリニックが幹細胞を培養しているか確認することは大切なことになります。PRP治療は注射で実施できることから、傷口は小さくてすみます。
自脂肪由来幹細胞治療も米粒2〜3粒ほどの脂肪を摂取するために、下腹部周辺を5ミリほど切開しますが、投与自体はPRPと同じく直接膝に注射することため、大きな傷口を作ることはありません。
日帰りで受けられるこれまでには無かった治療法です。なお自己脂肪由来幹細胞治療もPRP治療ともに自由診療で、厚生労働省によって認可された医療機関でしか行えません。
再生医療の比較 |
PRP治療 |
幹細胞治療 |
| 軟骨 | 再生できない | 再生する |
| アレルギー | ⇒ | 出にくい |
| 治療 | ⇒ | 専門医、専門院に限る |
| 種類 | 再生医療 | |
まとめ・変形性膝関節症の最新治療|ヒアルロン酸、ステロイドでは不可能な軟骨を再生させる再生医療という治療方法
いかがでしたか?変形性膝関節症に対する従来の注射「ヒアルロン酸注射」と「ステロイド注射」、最新治療の注射「PRP治療」「自己脂肪由来幹細胞治療」の役割を紹介しました。
これまで変形性膝関節症に対する注射は、痛みを抑え、少しでも悪化を遅らせる目的で使用されてきたものですが、再生医療であるPRP治療・自己脂肪由来幹細胞治療により、治癒そのものを促進させ、失われた軟骨を再生させることで回復を目指す!といった今までには無かった前向きな治療法です。
変形性膝関節症の痛みで悩み、薬や注射をしたけれど「期待していた効果を感じられなかった」「できるだけ手術はしたくない」という思いがある方は、薬や注射といった薬物療法と手術の中間に位置する再生医療での治療を検討してみてはいかがでしょうか。
以上、変形性膝関節症の最新治療と題し、従来のヒアルロン酸やステロイド注射では不可能な軟骨の再生を期待できる新たな選択肢である再生医療による治療について解説させていただきました。
ご参考にしていただければ幸いです。
変形性膝関節症は、再生医療により手術せずに症状を改善することができます
▼以下もご参考にされませんか
変形性膝関節症の治療「薬物療法の種類と悪化を防ぐ」ポイントとは